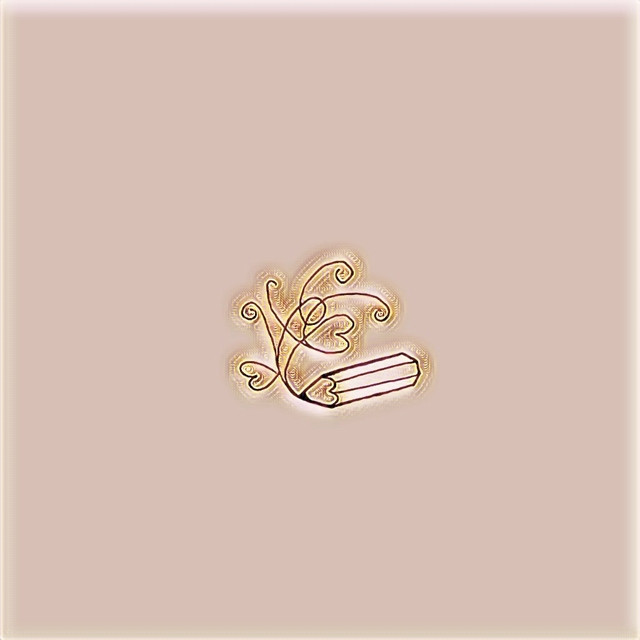8-1
文字数 1,298文字
わたしたちはむかし、三階建ての細長いおうちに住んでいた。
一階はご飯を食べる部屋と、テレビを見る部屋と、お風呂とトイレがあって、二階にはわたしと涼也くんの部屋があって、三階にはママの部屋と、あともうひとつ、部屋があった。
ちいさいころ、ママはわたしに言った。
二階までしか行っちゃだめよ。
上は危ないから。
わたしは三階に続く階段の下で、このさきにはなにがあるんだろうと思いながら、よく上を見上げていた。気になって階段をのぼろうとすると、決まってママに見つかって、上はまだだめと止められて、抱っこされた。
まだ、ということは、いつか、いいよという日がくるということ。
そこに考えがたどり着かないくらい、わたしは、とてもこどもだった。
わたしたちは3人で暮らしていた。ママと、おにいちゃんと、わたし。
おにいちゃんは、涼也くん。
おにいちゃんはわたしのいちばんだいすきなひと。
ものごころついてから今までそれはずっと変わらない。
ママは涼也くんをおにいちゃんと呼ぶことに良い顔をしなかった。
おにいちゃんは名前じゃないでしょう。
ちゃんと名前を呼びましょうね。
それがママのいいぶんだった。
だからわたしはママのいないところでだけ、涼也くんをおにいちゃんと呼んだ。
ママはこの家の、支配者であり、女だった。
つまり、絶対ということ。
そういえば、わたしには幼稚園生のころの記憶があまりない。階段をのぼろうとして抱っこされたこといがいは、ぼんやりと全部にかすみがかっている。たぶんそれは、覚えておく必要がないということなんだろう。
いっぽう、小学生になってからの記憶はとてもはっきりしていて、入学式の日にはじめてせおったランドセルの重さとか、ママの香水の甘い香りとか、入学おめでとうのお花の針がママの指を刺しかけたこととか、ママに丁寧に教えられたキッズケータイの使い方とか、もっとささいなことまで全部しっかり覚えている。
キッズケータイはわたしの首輪だった。
ママから帰ってきなさいとれんらくが来たら、なにをしていても――たとえ授業中であっても――帰らなければならなかったし、帰ってきてはだめと言われればよいと言われるまで帰れなかった。
そんなわたしにおとなたちは顔をしかめたけど、そのことを気にすることもなかった。
いま思えば、おとなが顔をしかめていたのはわたしにではなくて、ママに対してだったんだろう。ママはだれになにを言われたって素知らぬ顔で、いつだってほほ笑んでいたけれど。
小学校に入ってはじめてのお友達は、ゆいなちゃんと、すみれちゃんだった。席が前とうしろで、給食の班も同じで、それで仲良くなった。ママに話したら一度会ってみたいわ、と言った。おうちに連れて行ったら、ママは笑顔でふたりを迎えてくれた。ママが買ってきてくれたショートケーキを食べて、ママと、ゆいなちゃんと、すみれちゃんと、わたしでいっぱいお話をした。ママもふたりを好きになってくれたんだと思ってうれしかった。
でも、ふたりが帰ったあと、ママには言った。
「ママはあの子たち好きじゃないわ。日捺子はああいう子が好きなの?」
一階はご飯を食べる部屋と、テレビを見る部屋と、お風呂とトイレがあって、二階にはわたしと涼也くんの部屋があって、三階にはママの部屋と、あともうひとつ、部屋があった。
ちいさいころ、ママはわたしに言った。
二階までしか行っちゃだめよ。
上は危ないから。
わたしは三階に続く階段の下で、このさきにはなにがあるんだろうと思いながら、よく上を見上げていた。気になって階段をのぼろうとすると、決まってママに見つかって、上はまだだめと止められて、抱っこされた。
まだ、ということは、いつか、いいよという日がくるということ。
そこに考えがたどり着かないくらい、わたしは、とてもこどもだった。
わたしたちは3人で暮らしていた。ママと、おにいちゃんと、わたし。
おにいちゃんは、涼也くん。
おにいちゃんはわたしのいちばんだいすきなひと。
ものごころついてから今までそれはずっと変わらない。
ママは涼也くんをおにいちゃんと呼ぶことに良い顔をしなかった。
おにいちゃんは名前じゃないでしょう。
ちゃんと名前を呼びましょうね。
それがママのいいぶんだった。
だからわたしはママのいないところでだけ、涼也くんをおにいちゃんと呼んだ。
ママはこの家の、支配者であり、女だった。
つまり、絶対ということ。
そういえば、わたしには幼稚園生のころの記憶があまりない。階段をのぼろうとして抱っこされたこといがいは、ぼんやりと全部にかすみがかっている。たぶんそれは、覚えておく必要がないということなんだろう。
いっぽう、小学生になってからの記憶はとてもはっきりしていて、入学式の日にはじめてせおったランドセルの重さとか、ママの香水の甘い香りとか、入学おめでとうのお花の針がママの指を刺しかけたこととか、ママに丁寧に教えられたキッズケータイの使い方とか、もっとささいなことまで全部しっかり覚えている。
キッズケータイはわたしの首輪だった。
ママから帰ってきなさいとれんらくが来たら、なにをしていても――たとえ授業中であっても――帰らなければならなかったし、帰ってきてはだめと言われればよいと言われるまで帰れなかった。
そんなわたしにおとなたちは顔をしかめたけど、そのことを気にすることもなかった。
いま思えば、おとなが顔をしかめていたのはわたしにではなくて、ママに対してだったんだろう。ママはだれになにを言われたって素知らぬ顔で、いつだってほほ笑んでいたけれど。
小学校に入ってはじめてのお友達は、ゆいなちゃんと、すみれちゃんだった。席が前とうしろで、給食の班も同じで、それで仲良くなった。ママに話したら一度会ってみたいわ、と言った。おうちに連れて行ったら、ママは笑顔でふたりを迎えてくれた。ママが買ってきてくれたショートケーキを食べて、ママと、ゆいなちゃんと、すみれちゃんと、わたしでいっぱいお話をした。ママもふたりを好きになってくれたんだと思ってうれしかった。
でも、ふたりが帰ったあと、ママには言った。
「ママはあの子たち好きじゃないわ。日捺子はああいう子が好きなの?」