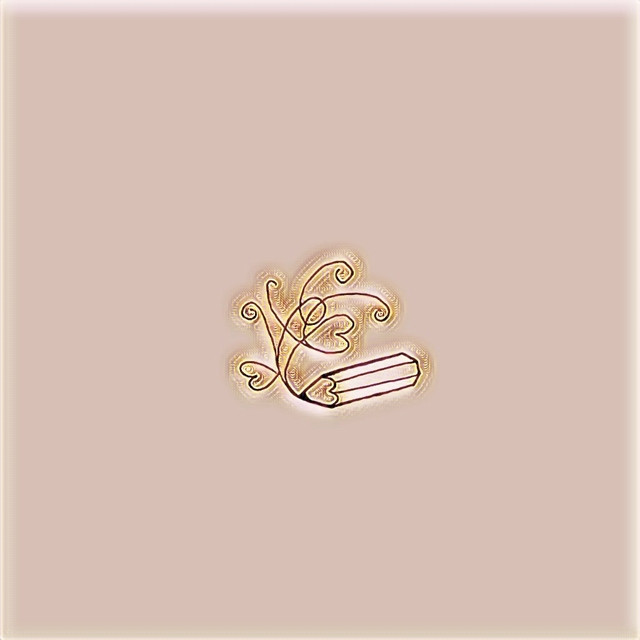5-4
文字数 1,247文字
「腹、へりましたね」
早坂晟が続ける。今、俺の腹鳴ったの聞こえました? 日捺子には聞こえなかった。ううんと首を振った視線の先、グエンとは違う店員がこちらに向かってくる。
「おまたせしました」
料理が運ばれてきた。いっぺんに。小エビのサラダ、辛味チキン、ほうれん草のソテー、ラージライス、イタリアンハンバーグ。どんどんテーブルの上に並べられていく。コップが邪魔そうだったので端にずらした。早坂晟のもついでに一緒に。ご注文は以上でよろしいですか。ごゆっくりどうぞ。お決まりの挨拶をして店員が去る。日捺子と早坂晟はそれぞれ自分が頼んだものを、手元に引き寄せた。
「里中さん、少なくないですか?」
「そう?夜はいつも、こんな感じだけど」
日捺子の前には小エビのサラダとほうれん草のソテーが並んでいる。
「草ばっか。肉も食いましょうね。あと、米も」
早坂晟がハンバーグの3分の1と少量のライスを日捺子のソテーの皿の隅に乗せた。
「そんなにいらないんだけど」
「肉と米、食べないと元気になりませんよ」
なんだか、お母さんみたい。日捺子はふふっと笑った。そう、お母さん。抱擁力とか母性とか肝っ玉とか、そういうもののあるひと。
私の母はお母さんではなかった。あれは、ママという固有の生き物だった。女の煮こごりみたいな。
「早坂くんは、野菜が足りないね」
日捺子は小エビのサラダのレタスと人参を早坂晟のライスの皿の空いたところに置いた。
そういえば母は“野菜は大事”とちいさなころから野菜を多く日捺子に食べさせた。料理が得意ではなかった母が出すのは生野菜ばかりだった。いつもサラダボウルいっぱいの細切りにされただけの野菜が食卓にはあった。私と母の前には必ずひとつ。兄の前にもあったかどうかは、覚えていない。ドレッシングのかかってない青臭く味気のない野菜を子どもの日捺子はがんばって飲み込んでいた。残すことは許されなかった。
幼い日捺子にとって食事は、ちょっとした苦行だった。
その反動か、母から離れてすぐは、ハンバーグだとか、カレーだとか、唐揚げだとか、健康的とは言い難いものばかりを好んで作っていたような気がする。なのに今の私は、どうだろう。いつの間にか野菜を好んで食べるようになっているから不思議だ。幼いころから体に慣れ親しんでしまったもの。結局はそういうものを、ひとは欲するのかもしれない。
「チキンも食べますか?」
「辛いの……刺激物あんまり得意じゃないから、いい」
「へえ。でもカフェインって刺激物じゃないんですか?」
「どういう、意味?」
「ほら、会社でいつもブラックコーヒーばっかり飲んでるじゃないですか?あれって刺激物に入らないんですか?」
「よく、見てますね」
日捺子の眉間にしわがよる。早坂晟が慌てた様子で付け加えた。
「別に里中さんばっかり見てるわけじゃないですよ。藤田さんとかコーヒーにすごい砂糖入れんなぁとか、思うし」
「へぇ、花ちゃん甘いの好きなんですね」
「知らなかったんですか? 結構話してますよね、藤田さんと」
早坂晟が続ける。今、俺の腹鳴ったの聞こえました? 日捺子には聞こえなかった。ううんと首を振った視線の先、グエンとは違う店員がこちらに向かってくる。
「おまたせしました」
料理が運ばれてきた。いっぺんに。小エビのサラダ、辛味チキン、ほうれん草のソテー、ラージライス、イタリアンハンバーグ。どんどんテーブルの上に並べられていく。コップが邪魔そうだったので端にずらした。早坂晟のもついでに一緒に。ご注文は以上でよろしいですか。ごゆっくりどうぞ。お決まりの挨拶をして店員が去る。日捺子と早坂晟はそれぞれ自分が頼んだものを、手元に引き寄せた。
「里中さん、少なくないですか?」
「そう?夜はいつも、こんな感じだけど」
日捺子の前には小エビのサラダとほうれん草のソテーが並んでいる。
「草ばっか。肉も食いましょうね。あと、米も」
早坂晟がハンバーグの3分の1と少量のライスを日捺子のソテーの皿の隅に乗せた。
「そんなにいらないんだけど」
「肉と米、食べないと元気になりませんよ」
なんだか、お母さんみたい。日捺子はふふっと笑った。そう、お母さん。抱擁力とか母性とか肝っ玉とか、そういうもののあるひと。
私の母はお母さんではなかった。あれは、ママという固有の生き物だった。女の煮こごりみたいな。
「早坂くんは、野菜が足りないね」
日捺子は小エビのサラダのレタスと人参を早坂晟のライスの皿の空いたところに置いた。
そういえば母は“野菜は大事”とちいさなころから野菜を多く日捺子に食べさせた。料理が得意ではなかった母が出すのは生野菜ばかりだった。いつもサラダボウルいっぱいの細切りにされただけの野菜が食卓にはあった。私と母の前には必ずひとつ。兄の前にもあったかどうかは、覚えていない。ドレッシングのかかってない青臭く味気のない野菜を子どもの日捺子はがんばって飲み込んでいた。残すことは許されなかった。
幼い日捺子にとって食事は、ちょっとした苦行だった。
その反動か、母から離れてすぐは、ハンバーグだとか、カレーだとか、唐揚げだとか、健康的とは言い難いものばかりを好んで作っていたような気がする。なのに今の私は、どうだろう。いつの間にか野菜を好んで食べるようになっているから不思議だ。幼いころから体に慣れ親しんでしまったもの。結局はそういうものを、ひとは欲するのかもしれない。
「チキンも食べますか?」
「辛いの……刺激物あんまり得意じゃないから、いい」
「へえ。でもカフェインって刺激物じゃないんですか?」
「どういう、意味?」
「ほら、会社でいつもブラックコーヒーばっかり飲んでるじゃないですか?あれって刺激物に入らないんですか?」
「よく、見てますね」
日捺子の眉間にしわがよる。早坂晟が慌てた様子で付け加えた。
「別に里中さんばっかり見てるわけじゃないですよ。藤田さんとかコーヒーにすごい砂糖入れんなぁとか、思うし」
「へぇ、花ちゃん甘いの好きなんですね」
「知らなかったんですか? 結構話してますよね、藤田さんと」