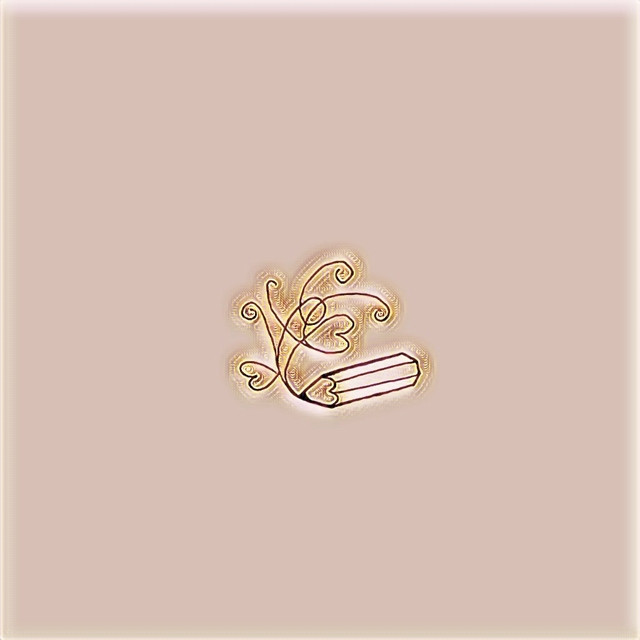1-2
文字数 1,240文字
そのあとの食事は砂を噛むようなものだった。いつもどおり味気なく、しずかに終わっていく。
お肉は半分。付け合わせの野菜のソテーはなくなってる。ごはんは三分の一。少なめによそったのに。お味噌汁は半分。ほうれん草のおひたしは手付かず。
日捺子は残飯ををごみ箱に捨てていく。前はタッパーにいれて残していたけど、結局誰も食べずに腐らせるだけだから、やめた。銀色のトラッシュ缶の中にきれいに焼けた柔らかいステーキ肉を落とす。
こんなに食べなかったらいつか涼也くんは消えてなくなっちゃうんじゃないかな。そんなことありえない。お昼にマックを食べられるくらい、涼也くんは健康なのだ。問題なんてない。考えすぎ。なのにずっと不安でしかたない。
「涼也くん。デザート、えっと、プリン、買ってくるね」
日捺子は明るく涼也に声をかけ、財布とスマホだけを持って玄関に向かう。サンダルをシューズボックスから出しているとき涼也がなにかを言っているような気がしたけれど、日捺子は振り向くとなく部屋を出た。
外で大きく息を吐く。ゆっくりと、吸う。それから日捺子は浅くため息をついた。
今日も間違えちゃった。
わたしはいつも、そう。ずっと、そう。
子どものころから、ずっと。だから『日捺子は涼也くんの言うとおりにしておきなさい』って、『日捺子は、なんにも考えなくていいんだよ』って、ママとか涼也くんに言われ続けてきた。
涼也くんのしあわせを一番に考えること。
それはわたしに沁みついた生き方のはず。
ちいさなときから涼也くんとママの言うことだけを聞いて、そうやって生きてきたのに、今日みたいに間違うことが増えた。涼也くんの望まないことをしてしまう。むかしはもっと上手にできてた気がするのに。間違いを重ねれば重ねるほど、涼也くんの正解がもっと分からなってしまう。
「あ。また、間違えた」
日捺子はスーパーに行くのとは違う道に居た。まあいいや。少し遠回りにはなったとしても、歩いていればいつか着くのだから。日捺子は進む。戻ることを、日捺子は選ばない。
いつもと違う道には発見があると、日捺子は思う。新しいコンビニができていたり、間違えた道の方が近道だったり、あったはずのなにかがなくなっていたり。なくなっているとき、日捺子はあったものを思い出すことを試みてみる。家だったのか、ビルだったのか、駐車場だったのか。でも、それはいつもかたちになることなく、もやもやのまま霧散して、記憶の扉が開かれることはない。日捺子は思い出すということがいっとう苦手だった。
今日の道には公園があった。
桜が満開の桃色の公園。そこは花見をするには小さすぎるのか、宴会をする集団は見当たらなかった。日捺子は舞い散る桃色の花びらに誘われるように中へと入っていった。桜の木を見上げて、桃色の視界のなか、ただただ歩く。手をぶらぶらさせて。のんびりと。きれいだな。桜はきれいで、かわいい。ピンク色なのがいい。だってやわらかくて、大好きな色だから。
「あっ……」
お肉は半分。付け合わせの野菜のソテーはなくなってる。ごはんは三分の一。少なめによそったのに。お味噌汁は半分。ほうれん草のおひたしは手付かず。
日捺子は残飯ををごみ箱に捨てていく。前はタッパーにいれて残していたけど、結局誰も食べずに腐らせるだけだから、やめた。銀色のトラッシュ缶の中にきれいに焼けた柔らかいステーキ肉を落とす。
こんなに食べなかったらいつか涼也くんは消えてなくなっちゃうんじゃないかな。そんなことありえない。お昼にマックを食べられるくらい、涼也くんは健康なのだ。問題なんてない。考えすぎ。なのにずっと不安でしかたない。
「涼也くん。デザート、えっと、プリン、買ってくるね」
日捺子は明るく涼也に声をかけ、財布とスマホだけを持って玄関に向かう。サンダルをシューズボックスから出しているとき涼也がなにかを言っているような気がしたけれど、日捺子は振り向くとなく部屋を出た。
外で大きく息を吐く。ゆっくりと、吸う。それから日捺子は浅くため息をついた。
今日も間違えちゃった。
わたしはいつも、そう。ずっと、そう。
子どものころから、ずっと。だから『日捺子は涼也くんの言うとおりにしておきなさい』って、『日捺子は、なんにも考えなくていいんだよ』って、ママとか涼也くんに言われ続けてきた。
涼也くんのしあわせを一番に考えること。
それはわたしに沁みついた生き方のはず。
ちいさなときから涼也くんとママの言うことだけを聞いて、そうやって生きてきたのに、今日みたいに間違うことが増えた。涼也くんの望まないことをしてしまう。むかしはもっと上手にできてた気がするのに。間違いを重ねれば重ねるほど、涼也くんの正解がもっと分からなってしまう。
「あ。また、間違えた」
日捺子はスーパーに行くのとは違う道に居た。まあいいや。少し遠回りにはなったとしても、歩いていればいつか着くのだから。日捺子は進む。戻ることを、日捺子は選ばない。
いつもと違う道には発見があると、日捺子は思う。新しいコンビニができていたり、間違えた道の方が近道だったり、あったはずのなにかがなくなっていたり。なくなっているとき、日捺子はあったものを思い出すことを試みてみる。家だったのか、ビルだったのか、駐車場だったのか。でも、それはいつもかたちになることなく、もやもやのまま霧散して、記憶の扉が開かれることはない。日捺子は思い出すということがいっとう苦手だった。
今日の道には公園があった。
桜が満開の桃色の公園。そこは花見をするには小さすぎるのか、宴会をする集団は見当たらなかった。日捺子は舞い散る桃色の花びらに誘われるように中へと入っていった。桜の木を見上げて、桃色の視界のなか、ただただ歩く。手をぶらぶらさせて。のんびりと。きれいだな。桜はきれいで、かわいい。ピンク色なのがいい。だってやわらかくて、大好きな色だから。
「あっ……」