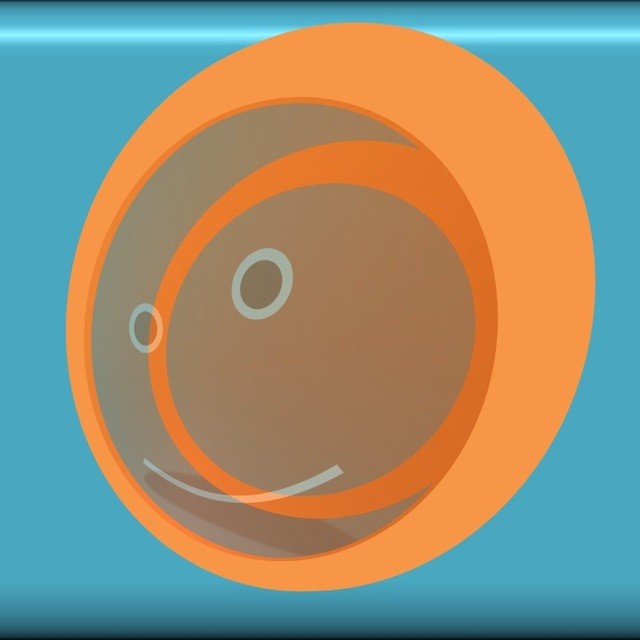第2話:赤髪の男。
文字数 7,297文字
「――あのう、実は、アイサさん、体調が悪いみたいで冒険には参加出来ない様です。ぼくは、只の通りすがりの者ですが、言伝を頼まれたので……」と、少年はありのままを、冒険者一団のひとりに伝えた。
レオンは、アイサと別れた場所からコーリング街道を南に走って一団の最後尾へと追いついたわけだ。
全体で三十名程度。重装備の戦士から軽装の魔導師まで様々な冒険者の集まりだった。
どの人物が指揮官か見分けが付かなかったため、取り敢えず適当に声を掛けていた。
「んん?え、ちょっと待って、アイサって……ああ、後方支援で雇った魔導士か。確かバルバトスの生き残り……。あれ、さっきまで後ろを歩いていると思ったけど。いない、か。いや、それは不味いな。今回は彼女の腕を見込んで支援職の人数を少なくしてるんだよ。キミ、アイサの知り合い?ちょっとさ、呼び戻して来てもらえるかな?体調悪いだけなら、魔法か薬でなんとか出来ると思うから……」
偶然声を掛けた男性の冒険者は至って冷静にまともな返答をしてくれた。
その出で立ちから戦闘職で経験も豊富そうに見える。
もしかしたらあまり関係の無い自分が怒られてしまうかもしれないと思っていたため、レオン的には取り敢えずの一安心を手にしていた。
「ごめんなさい、ぼく、あの人の事よく知らないんです。この冒険者の一団を見て格好がいいから後ろに着いて歩いていたら、突然声を掛けられてしまって、それで急に伝言も頼まれて、兎に角走って追いかけて来ましたが、現状もよく飲み込めて無い状態なんです」
いや、実際少年はある程度状況は飲み込めていて、アイサは全く縁も所縁も無い訳では無い。
けれど、流石にこの場で自分と彼女の関係を正直に説明するのは面倒臭く、無駄に勘繰られるのも馬鹿馬鹿しいと思っていたのだ。
アイサが本当に体調を崩してしまっていたなら、或いは正直に打ち明けていた可能性もあるが、彼女の言葉を聞く限りでは恐らく彼女に正義は無いだろうから、それに巻き込まれる気にはならなかった。
「ふうむ、そうか、では大至急冒険者ギルドで代わりの支援職を見付けなくてはならないな。少年よ、変な事に巻き込んで済まなかったな。帰りにこれで何か買って食べなさい。では、私は先を急ぐので……」
冒険者はレオンに銀貨一枚を渡すと、颯爽とその場から立ち去ってしまった。
とても誠実でまともな人物だった。
少なからず嘘をついてしまった自分を呪いたくなるくらいにいい人だと、少年の胸中は残念な思いで一杯になってしまう。
少年は貰った銀貨を握り締め、やはりここは、アイサについて知っている事を全部伝えた方が良いのだろうか?と思ったが、しかし今更伝えた所でたいして何も現状は変わらないだろう。
レオンは「ふうううう」と長い溜息をひとつついた。
朝の散歩がてらアンヌヴンの塔の近くまで行ってみようとしていただけなのに、いきなり何だかよく分からない事に巻き込まれてしまったのだ。
「やっぱり、ローラが起きるまで大人しく店で待っていた方がいいかもしれないなあ。チャックさんは仕事中だろうし、フレイザーさんのお店までは辿り着ける自信が無いし」
少年はそう言うと、握り締めていた銀貨をポケットに仕舞った。
善良な冒険者から何か買って食べなさいと言われたが、まだ朝食を取ってから幾許も過ぎて無い。
取り敢えず、まず来た道を引き返すことにした。
寄ってみたい店や入ってみたい路地は沢山あるが、そう言う事はもう少しこの街に慣れてからにすればいいと思う事にしたのだ。
しかし、大人しく帰るにしては、少年の存在は余りにも目立ってしまう。
この地方の人間は大抵黒色か茶色の髪が多く、ホビットやエルフは特徴的な髪色の者が少なく無いが、銀色の髪と言うのはまずお目には掛かれない。
その上まるで雪の様に色白の肌で、限りなく中性的で美しさと可愛らしさを併せ持つレオンが朝日に照らされると、さながら絵画に描かれた神の使いの様にも見えてしまう訳で、街人の中には老若男女問わず足を止めて少年に見惚れる者たちも現れ出していた。
その数多の視線に、少年自身も気が付いていたのだ。
もっとも彼の場合、好意的な目で見られているとは思っておらず、どちらかと言えば田舎者を好奇の目で見ているのだろうと思っていた。
そう言う心持で、少年は人通りの多いコーリング大通りを、伏目がちに、かなりの速足で北上していた。
兎に角今は一刻も早く酔いどれ小路へと入って、酒房ルロイに戻りたい、とその一心で。
だが、しかし、少年の細やかで可愛らしい陰謀は意図も容易く打ち砕かれてしまう。
今から正に酔いどれ小路へと入る所で、声を掛けられてしまった。
「――おい、ちょっと待て、そこの銀髪のガキ」
鋭い、男の声だった。
真後ろから声を掛けられたため、さっきの冒険者の仲間が追いかけて来たのかもしれないと思い、足を止めた。
「なぁ?オマエさ?白銀のせがれだろう?ははは、マジで瓜二つじゃねえかよ。笑っちまうぜ。余りにも似てっからオレの頭がおかしくなっちまったかと思ったし、はははは」
男は大きな声でそう言い放ち、高らかに笑っていた。
少年は恐る恐ると振り返った。その視線の先には、人間にしてはかなり背の高い男が立っていた。
ぼさぼさで燃えるような赤色の髪と、瞳は髪と同じ様に赤い。
明らかにこの地方の人間でないのだろう。
そして何より、その笑みは胸の奥がざわつくくらい不敵で禍々しく感じられる。
「えーっと、貴方は、父のことを知っているんですか?」
「知ってるも何も、オレは元ベリアルだからよ、オマエの父ちゃんとは一緒に冒険し捲ってた仲だっての。いや、しかし、マジで同じ顔してんな。声とか歩き方までそっくりだってイライザが言ってたけどよ、ここまで似てるとは思わなかったぜ」
恐らく、話からしてこの赤髪の男は冒険者なのだろうと思ったが、その恰好は街人の様で、先ほどの正義の冒険者とは似ても似つかない様相だった。
「元ベリアル……って事は、母の事も知ってますか?」
「鬼女アンナだろう?知ってるも何も、オレはあの女に恋い焦がれてベリアルに入った様なモンだからよ。まぁ、ベリアルに参加してからアンナが白銀の女だって知って、それからはことある毎にアンナを賭けて白銀にタイマン吹っ掛けてたんだよなぁ、あの頃はよう。まぁ、結果は百回やってオレの百敗だわ。あと一回やってればぜってぇオレが勝ってたけど、その前に白銀は死んじまいやがったから……」
そう言うと、赤髪の男は大きな手で少年の頭をぐしゃぐしゃと撫でた。
「なぁ?オマエの母ちゃん、アンナよう、死んじまったんだろう?」
「はい、先月、流行り病で……」
「はあああ、マジでさ、オレが好きなヤツはさ、皆、すぐ死んじまいやがるんだわ。皆イイヤツばっかなのになあ。って、あのよ?オマエ、名前なんてんだっけ?昨日イライザから聞いたけど、忘れちまったわ」
「レオンです」
「ああ、そうか。そうだったな。いやいや、そう言えば、今思い出したわ。白銀のヤロウ、男が生れたらレオンって名付けるって言ってたな、確か。女の時は忘れたけどよ。今までずーっと忘れてたのに。はははは、多分レオンが白銀に似すぎてっから、思い出しちまったんだろうなぁ。懐かしいよなぁ、もう十三年も前だぜ?オレなんてもう、白銀が死んだ時の歳をゆうに超えちまってんだもんよ。ははは、マジで、ヤベぇよな、マジでよ……」
この上無く粗雑な喋り口調だが、この男からは、イライザやフレイザーよりも熱く白銀の獅子に対する想いが伝わって来るように、少年は感じていた。
「あの、タイマンって、一対一で殴り合うって事ですよね?白銀の獅子は、父は、強かったですか?」
一見、赤い髪の男は長身で痩身に見えるが、腕の筋肉は隆々としており引き締まった身体をしている。
大人のドワーフと比べると、体格的には見劣りしてしまうが、少年はこの男から今まで感じたことが無い様な、強い圧を感じていた。
「そんなの強ぇにきまってんだろ?死んでから十三年も経ってんのに、この街では未だに最強の冒険者って扱いなんだぜ?白銀はマジで半端ねぇんだよ。初めてヤリ合った時なんて、オレ、デコピン一発でヤラれちまったんだからよ」
「でも、あと一回やってれば勝てたんですよね?」
「ああ、まあな。けどよ、そのあと一回は永遠に来ないからな。結局は白銀の勝ち逃げってワケよ」
「あの?」
「ああん?」
「もしかして、父の事も、好きだったんですか?」
「くくく……それは流石に愚問だわ。嫌いなワケねえだろ?あの時、全滅に瀕してたベリアル全員をその命で救った男のことを嫌いになれるはずがねえ。まぁルロイのヤロウだけは、そんな白銀を救おうとして一緒に死んじまったけどよ。散々タイマンでボコられたからケツの穴舐めれるくらい大好き!って感じじゃあねえけどな!へへへへ、なあ、レオン?オレ、腹減ってっから、今からメシに付き合えよ?こんなとこウロついてるくらいだから、どうせ暇してんだろ?ちょっと、着いて来い」
そう言うと赤髪の男は、黒いズボンのポケットに両手を突っ込み大通りへと出て行く。
大股で、人の流れなど気にすることなくずけずけと。
仕方なく少年は赤髪の男の後について行くことにした。
出来るだけ目立たない様に酒房ルロイへと帰ろうと思っていたのに、結局は自分より派手で目立つ男と行動を共にする羽目となってしまった。
「あの、すみません、貴方の名前教えてくれますか?」と、少年は赤髪に追いつきそう尋ねた。
この街の人は名前を聞いてくるけれど、名乗ってくれない人が多いな、と思いつつ。
「あん?ああ、名乗って無かったっけ?オレはヴィルってんだ」
「ヴィルさん」
「ヴィルでいい」
「じゃあ、ヴィルは元ベリアルで、今は何処かのユニオンに所属してるんですか?」
「あー?まぁな。オレ、これでも一応ユニオンマスターだからよ。バルバトスってんだけど。最近はあんまり活動してねえんだよな、これがさ……。と、そうだな、今日はこの店にするか、久しぶりに……」
――北の鯨亭。
そこはコーリング通り沿いにある食事処だった。
大勢の客で賑わっているが、店舗が広いため幾つか空いているテーブルはある。
ヴィルは大通り同じノリで店内へと入り、一番奥にあるテーブル席を陣取った。
そして、雑踏の中でも良く響く声で「おおーい、そこの店員よう?この席に大盛りのメシ二人前持って来てくれ」と言っていた。
少年は周囲の客の邪魔にならない様奥のテーブルにまで辿り着き、赤髪の対面へと腰掛けた。
「あのヴィル?ぼく、もう朝御飯食べましたよ?ローラが用意してくれてたので」
「あ、マジで?でも、まだ食えんだろ?ここのメシ美味いから、遠慮しないで食っとけよ。奢ってやっから」
「じゃぁ、はい、いただきます」遠慮なんて全然してないけど、と少年は思いつつ言う。
それとバルバトスやヴィルという名は、何処かで耳にした記憶があるとも思っていた。
「えーっと、バルバトスは何故活動してないんですか?」
「ははは、流石は白銀のせがれだな!そう言う事、普通は聞きにくいから遠まわしに言うだろ?」
「あ、ごめんなさい、聞いては不味い事でしたか?」
「いやいや、全然マズかねえよ。半年前にアンヌヴンの昇りでな、オレの判断ミスで、仲間を半分くらい死なせちまったんだわ。怪我が酷くて冒険者から足を洗っちまったヤツもいたからよ。今は冒険に出れる戦力が整ってねえから、活動できねえんだ。それまでは結構毎日冒険三昧だったから、半年間もダラダラと生活するのは冒険稼業になってからは初めてだな。まぁ最初の三ヵ月くらいは、おれも怪我が酷くて身動き取れなかったんだけどよ。あ、メシ来たぜ。がっつり食えよ?足りなかったらお代わりもしていいからな」
赤髪が頼んだメシとは、鶏肉のスープに穀物を粉末状にして捏ねた団子と芋や野菜を一緒に煮込んだ物だった。
空腹でなくともそそられる良い匂い。二人分で銀貨一枚は物価が高いとされるアンヌヴンではお手頃価格と言えるだろう。
が、しかし問題なのはその量だった。どう見ても一人で食べ切れる分量では無い。少年の頭がすっぽりと隠れてしまいそうな大きな器に、具材が山盛りになっているのだ。
目の前のヴィルは、食事と一緒に運ばれて来たフォークをスプーンを巧みに使いこなしガツガツと食べ進めている。取り敢えず少年は見様見真似て、その山盛りへと挑戦する事にした。
勿論、こう言う場合でも食前の祈りは欠かす事が無い。
「――どうだ?美味いだろう?」
ヴィルは少年の様子を見つつ、そう言った。
「はい、美味しいです。すごい量ですけど……」
「この店は昔からあってよ、よく白銀と一緒にメシ食いに来たんだわ。オレは久しぶりに来たんだけど、昔と全然味は変わってねえ。冒険に出る前とか、タイマン張った後とかよ。へへへ、懐かしいよなぁ。あれから十三年後に、まさかこうして白銀のせがれと一緒にメシ食う事になるとは……。半年前、あの時、オレが死ななかったのは、レオン、お前とこうしてメシ食う為だったのかもしれねえ。神とか運命とか、信じてねえオレが言っても何の有難味もねえけどな」
ヴィルは話ながらも器用に食事を進めていく。
上品さの欠片も無いため、彼の食器の周りは家畜が餌を貪っているかの様に汚れてしまっていた。
「父も、この店に来てたんですね?」
「ああ、最初は白銀に連れて来られたんだけどよ、それ以来、この店のメシは美味いし、量が多いし、何より安いからな、駆け出しの冒険者で貧乏だった頃はほぼ毎日メシ食いに来てたぜ。多分、一年間くらい冒険で来れない時以外は毎日来てたんじゃねえかな?あの頃の、ここの親父はもう死んじまったけど、今はその息子が切り盛りしてんだよな。何処もかしこも世代交代の波が押し寄せてくるって事か。オレも年取るワケだぜ。へへへへ……」
少年の器にはまだ半分以上残っていたが、ヴィルはこの時点で殆ど平らげてしまっていた。
「あの、ヴィル?」
「ん、どーした?」
「いや、この料理すごく美味しいんですけど、全部食べ切れそうに無いです、ごめんなさい」
「ははは、そうか、そう言えばもう朝メシ食ったって言ってたっけか?じゃぁ、残りはオレが食ってやるよ」
そう言うと赤髪は長い腕を伸ばし、少年の器を自分の前まで引き寄せ、変わらぬ勢いで食事を再開してしまった。
行儀もへったくれも無いが、観てるだけで楽しくなってしまう様な食べ方だった。
そして、あっと言う間にレオンが残した分も平らげてしまう。凄まじい食いっぷりに、少年は思わず手を叩き「すごい、すごい!」と賛辞を贈っていた。
「へっ、ガキにメシの食いぷり褒められても全然嬉しかねえんだよ。おーい、ちょっと、ここ片付けてくんねえか?」
ヴィルの大声が店内へと響き渡る。
すると、少年と同い年くらいの少女がいそいそと食器を片付け、喰い散らかしてあったテーブルを綺麗に拭いてくれた。
「――なぁ、レオン?」
「はい?」
「腹も一杯になった事だし。ちょっと、ここで一発、力比べしてみねえか?」
「力比べ……ですか?ここで?」
「おう、ここで。腕相撲ってやった事あるだろう?」
「あ、はい。村で、ドワーフの子供たちとやってました」
「ほう、ドワーフとかい。それじゃぁ本場仕込みってヤツだな。腕相撲は元々酔ったドワーフ共の遊びから生まれたって聞いた事があるし」
赤髪はそう言うと立ち上がり右腕の袖を捲りあげた。
室内で立ち上がると頭が天井に届いてしまいそうで、外で見るよりも大きく見える。
少年と比べたら頭二つ分は大きいだろう。それこそ、背丈はドワーフに見劣りしないくらいだ。
そして、腕の筋肉はかなり発達していた。太い血管が幾筋もあった。
そんな大人の冒険者を目の前にしたら、如何に腕相撲だとは言え子供なら怯んで当然だが、少年の心は沸々と燃えていた。
昔からそう言う性分なのだ。
遊びでも勝負事となると、人が変わったかのように熱くなってしまう。
「へへへ、女みてえなガキのくせに、白銀と同じ目ぇしてやがる」
ヴィルは不敵な笑みを浮かべつつ、腰を落とし、テーブルの上に右肘を付けた。
レオンは、その姿を見てごくりと息を飲み、赤髪の大きな手を握り締め、右肘をテーブルへとつける。
「おーい、そこの、店員よう?ちょっとこっち来て、合図出してくれ」
余所のテーブルを片付けていた少女は面倒な事に巻き込まれたく無さそうだったが、ヴィルの声の大きさと勢いに負けて二人のテーブルへと駆け寄ってくる。
「あ、合図って、どうすれば、いいんですか?」と、少女は声を震わせそう言った。
「あん?そんなもん何でもいいんだよ。オレらの手の上にオメェの手を重ねてな、始め!って声掛けて離れればいい。後はオレらが勝手にやるから」
早口でそう説明され、少女はおどおどとしつつも、ヴィルとレオンががっちりと組んでいる手の上に、震える右手を乗せた。
その間、レオンはそんな少女は全く眼中に無いと言った感じで、ヴィルの事を燃えるような眼差しで見ていた。
「はははは、ヤベぇなこのガキ。そんな目で見られたら本気出したくなっちまうぜ」
ヴィルは、ヘラヘラとしつつもレオンの手を握り潰すくらいの勢いで力を込めた。
それに対し、少年は臆する事無く、力を込め握り返した。
大人と子供の遊びの腕相撲という雰囲気では無い。
それを察した他の客たちが、次第に二人の周りを囲みだす。
その中、野次馬たちの雑踏に紛れ、か細い少女の声が「ハジメっ!」と、響いた。
レオンは、アイサと別れた場所からコーリング街道を南に走って一団の最後尾へと追いついたわけだ。
全体で三十名程度。重装備の戦士から軽装の魔導師まで様々な冒険者の集まりだった。
どの人物が指揮官か見分けが付かなかったため、取り敢えず適当に声を掛けていた。
「んん?え、ちょっと待って、アイサって……ああ、後方支援で雇った魔導士か。確かバルバトスの生き残り……。あれ、さっきまで後ろを歩いていると思ったけど。いない、か。いや、それは不味いな。今回は彼女の腕を見込んで支援職の人数を少なくしてるんだよ。キミ、アイサの知り合い?ちょっとさ、呼び戻して来てもらえるかな?体調悪いだけなら、魔法か薬でなんとか出来ると思うから……」
偶然声を掛けた男性の冒険者は至って冷静にまともな返答をしてくれた。
その出で立ちから戦闘職で経験も豊富そうに見える。
もしかしたらあまり関係の無い自分が怒られてしまうかもしれないと思っていたため、レオン的には取り敢えずの一安心を手にしていた。
「ごめんなさい、ぼく、あの人の事よく知らないんです。この冒険者の一団を見て格好がいいから後ろに着いて歩いていたら、突然声を掛けられてしまって、それで急に伝言も頼まれて、兎に角走って追いかけて来ましたが、現状もよく飲み込めて無い状態なんです」
いや、実際少年はある程度状況は飲み込めていて、アイサは全く縁も所縁も無い訳では無い。
けれど、流石にこの場で自分と彼女の関係を正直に説明するのは面倒臭く、無駄に勘繰られるのも馬鹿馬鹿しいと思っていたのだ。
アイサが本当に体調を崩してしまっていたなら、或いは正直に打ち明けていた可能性もあるが、彼女の言葉を聞く限りでは恐らく彼女に正義は無いだろうから、それに巻き込まれる気にはならなかった。
「ふうむ、そうか、では大至急冒険者ギルドで代わりの支援職を見付けなくてはならないな。少年よ、変な事に巻き込んで済まなかったな。帰りにこれで何か買って食べなさい。では、私は先を急ぐので……」
冒険者はレオンに銀貨一枚を渡すと、颯爽とその場から立ち去ってしまった。
とても誠実でまともな人物だった。
少なからず嘘をついてしまった自分を呪いたくなるくらいにいい人だと、少年の胸中は残念な思いで一杯になってしまう。
少年は貰った銀貨を握り締め、やはりここは、アイサについて知っている事を全部伝えた方が良いのだろうか?と思ったが、しかし今更伝えた所でたいして何も現状は変わらないだろう。
レオンは「ふうううう」と長い溜息をひとつついた。
朝の散歩がてらアンヌヴンの塔の近くまで行ってみようとしていただけなのに、いきなり何だかよく分からない事に巻き込まれてしまったのだ。
「やっぱり、ローラが起きるまで大人しく店で待っていた方がいいかもしれないなあ。チャックさんは仕事中だろうし、フレイザーさんのお店までは辿り着ける自信が無いし」
少年はそう言うと、握り締めていた銀貨をポケットに仕舞った。
善良な冒険者から何か買って食べなさいと言われたが、まだ朝食を取ってから幾許も過ぎて無い。
取り敢えず、まず来た道を引き返すことにした。
寄ってみたい店や入ってみたい路地は沢山あるが、そう言う事はもう少しこの街に慣れてからにすればいいと思う事にしたのだ。
しかし、大人しく帰るにしては、少年の存在は余りにも目立ってしまう。
この地方の人間は大抵黒色か茶色の髪が多く、ホビットやエルフは特徴的な髪色の者が少なく無いが、銀色の髪と言うのはまずお目には掛かれない。
その上まるで雪の様に色白の肌で、限りなく中性的で美しさと可愛らしさを併せ持つレオンが朝日に照らされると、さながら絵画に描かれた神の使いの様にも見えてしまう訳で、街人の中には老若男女問わず足を止めて少年に見惚れる者たちも現れ出していた。
その数多の視線に、少年自身も気が付いていたのだ。
もっとも彼の場合、好意的な目で見られているとは思っておらず、どちらかと言えば田舎者を好奇の目で見ているのだろうと思っていた。
そう言う心持で、少年は人通りの多いコーリング大通りを、伏目がちに、かなりの速足で北上していた。
兎に角今は一刻も早く酔いどれ小路へと入って、酒房ルロイに戻りたい、とその一心で。
だが、しかし、少年の細やかで可愛らしい陰謀は意図も容易く打ち砕かれてしまう。
今から正に酔いどれ小路へと入る所で、声を掛けられてしまった。
「――おい、ちょっと待て、そこの銀髪のガキ」
鋭い、男の声だった。
真後ろから声を掛けられたため、さっきの冒険者の仲間が追いかけて来たのかもしれないと思い、足を止めた。
「なぁ?オマエさ?白銀のせがれだろう?ははは、マジで瓜二つじゃねえかよ。笑っちまうぜ。余りにも似てっからオレの頭がおかしくなっちまったかと思ったし、はははは」
男は大きな声でそう言い放ち、高らかに笑っていた。
少年は恐る恐ると振り返った。その視線の先には、人間にしてはかなり背の高い男が立っていた。
ぼさぼさで燃えるような赤色の髪と、瞳は髪と同じ様に赤い。
明らかにこの地方の人間でないのだろう。
そして何より、その笑みは胸の奥がざわつくくらい不敵で禍々しく感じられる。
「えーっと、貴方は、父のことを知っているんですか?」
「知ってるも何も、オレは元ベリアルだからよ、オマエの父ちゃんとは一緒に冒険し捲ってた仲だっての。いや、しかし、マジで同じ顔してんな。声とか歩き方までそっくりだってイライザが言ってたけどよ、ここまで似てるとは思わなかったぜ」
恐らく、話からしてこの赤髪の男は冒険者なのだろうと思ったが、その恰好は街人の様で、先ほどの正義の冒険者とは似ても似つかない様相だった。
「元ベリアル……って事は、母の事も知ってますか?」
「鬼女アンナだろう?知ってるも何も、オレはあの女に恋い焦がれてベリアルに入った様なモンだからよ。まぁ、ベリアルに参加してからアンナが白銀の女だって知って、それからはことある毎にアンナを賭けて白銀にタイマン吹っ掛けてたんだよなぁ、あの頃はよう。まぁ、結果は百回やってオレの百敗だわ。あと一回やってればぜってぇオレが勝ってたけど、その前に白銀は死んじまいやがったから……」
そう言うと、赤髪の男は大きな手で少年の頭をぐしゃぐしゃと撫でた。
「なぁ?オマエの母ちゃん、アンナよう、死んじまったんだろう?」
「はい、先月、流行り病で……」
「はあああ、マジでさ、オレが好きなヤツはさ、皆、すぐ死んじまいやがるんだわ。皆イイヤツばっかなのになあ。って、あのよ?オマエ、名前なんてんだっけ?昨日イライザから聞いたけど、忘れちまったわ」
「レオンです」
「ああ、そうか。そうだったな。いやいや、そう言えば、今思い出したわ。白銀のヤロウ、男が生れたらレオンって名付けるって言ってたな、確か。女の時は忘れたけどよ。今までずーっと忘れてたのに。はははは、多分レオンが白銀に似すぎてっから、思い出しちまったんだろうなぁ。懐かしいよなぁ、もう十三年も前だぜ?オレなんてもう、白銀が死んだ時の歳をゆうに超えちまってんだもんよ。ははは、マジで、ヤベぇよな、マジでよ……」
この上無く粗雑な喋り口調だが、この男からは、イライザやフレイザーよりも熱く白銀の獅子に対する想いが伝わって来るように、少年は感じていた。
「あの、タイマンって、一対一で殴り合うって事ですよね?白銀の獅子は、父は、強かったですか?」
一見、赤い髪の男は長身で痩身に見えるが、腕の筋肉は隆々としており引き締まった身体をしている。
大人のドワーフと比べると、体格的には見劣りしてしまうが、少年はこの男から今まで感じたことが無い様な、強い圧を感じていた。
「そんなの強ぇにきまってんだろ?死んでから十三年も経ってんのに、この街では未だに最強の冒険者って扱いなんだぜ?白銀はマジで半端ねぇんだよ。初めてヤリ合った時なんて、オレ、デコピン一発でヤラれちまったんだからよ」
「でも、あと一回やってれば勝てたんですよね?」
「ああ、まあな。けどよ、そのあと一回は永遠に来ないからな。結局は白銀の勝ち逃げってワケよ」
「あの?」
「ああん?」
「もしかして、父の事も、好きだったんですか?」
「くくく……それは流石に愚問だわ。嫌いなワケねえだろ?あの時、全滅に瀕してたベリアル全員をその命で救った男のことを嫌いになれるはずがねえ。まぁルロイのヤロウだけは、そんな白銀を救おうとして一緒に死んじまったけどよ。散々タイマンでボコられたからケツの穴舐めれるくらい大好き!って感じじゃあねえけどな!へへへへ、なあ、レオン?オレ、腹減ってっから、今からメシに付き合えよ?こんなとこウロついてるくらいだから、どうせ暇してんだろ?ちょっと、着いて来い」
そう言うと赤髪の男は、黒いズボンのポケットに両手を突っ込み大通りへと出て行く。
大股で、人の流れなど気にすることなくずけずけと。
仕方なく少年は赤髪の男の後について行くことにした。
出来るだけ目立たない様に酒房ルロイへと帰ろうと思っていたのに、結局は自分より派手で目立つ男と行動を共にする羽目となってしまった。
「あの、すみません、貴方の名前教えてくれますか?」と、少年は赤髪に追いつきそう尋ねた。
この街の人は名前を聞いてくるけれど、名乗ってくれない人が多いな、と思いつつ。
「あん?ああ、名乗って無かったっけ?オレはヴィルってんだ」
「ヴィルさん」
「ヴィルでいい」
「じゃあ、ヴィルは元ベリアルで、今は何処かのユニオンに所属してるんですか?」
「あー?まぁな。オレ、これでも一応ユニオンマスターだからよ。バルバトスってんだけど。最近はあんまり活動してねえんだよな、これがさ……。と、そうだな、今日はこの店にするか、久しぶりに……」
――北の鯨亭。
そこはコーリング通り沿いにある食事処だった。
大勢の客で賑わっているが、店舗が広いため幾つか空いているテーブルはある。
ヴィルは大通り同じノリで店内へと入り、一番奥にあるテーブル席を陣取った。
そして、雑踏の中でも良く響く声で「おおーい、そこの店員よう?この席に大盛りのメシ二人前持って来てくれ」と言っていた。
少年は周囲の客の邪魔にならない様奥のテーブルにまで辿り着き、赤髪の対面へと腰掛けた。
「あのヴィル?ぼく、もう朝御飯食べましたよ?ローラが用意してくれてたので」
「あ、マジで?でも、まだ食えんだろ?ここのメシ美味いから、遠慮しないで食っとけよ。奢ってやっから」
「じゃぁ、はい、いただきます」遠慮なんて全然してないけど、と少年は思いつつ言う。
それとバルバトスやヴィルという名は、何処かで耳にした記憶があるとも思っていた。
「えーっと、バルバトスは何故活動してないんですか?」
「ははは、流石は白銀のせがれだな!そう言う事、普通は聞きにくいから遠まわしに言うだろ?」
「あ、ごめんなさい、聞いては不味い事でしたか?」
「いやいや、全然マズかねえよ。半年前にアンヌヴンの昇りでな、オレの判断ミスで、仲間を半分くらい死なせちまったんだわ。怪我が酷くて冒険者から足を洗っちまったヤツもいたからよ。今は冒険に出れる戦力が整ってねえから、活動できねえんだ。それまでは結構毎日冒険三昧だったから、半年間もダラダラと生活するのは冒険稼業になってからは初めてだな。まぁ最初の三ヵ月くらいは、おれも怪我が酷くて身動き取れなかったんだけどよ。あ、メシ来たぜ。がっつり食えよ?足りなかったらお代わりもしていいからな」
赤髪が頼んだメシとは、鶏肉のスープに穀物を粉末状にして捏ねた団子と芋や野菜を一緒に煮込んだ物だった。
空腹でなくともそそられる良い匂い。二人分で銀貨一枚は物価が高いとされるアンヌヴンではお手頃価格と言えるだろう。
が、しかし問題なのはその量だった。どう見ても一人で食べ切れる分量では無い。少年の頭がすっぽりと隠れてしまいそうな大きな器に、具材が山盛りになっているのだ。
目の前のヴィルは、食事と一緒に運ばれて来たフォークをスプーンを巧みに使いこなしガツガツと食べ進めている。取り敢えず少年は見様見真似て、その山盛りへと挑戦する事にした。
勿論、こう言う場合でも食前の祈りは欠かす事が無い。
「――どうだ?美味いだろう?」
ヴィルは少年の様子を見つつ、そう言った。
「はい、美味しいです。すごい量ですけど……」
「この店は昔からあってよ、よく白銀と一緒にメシ食いに来たんだわ。オレは久しぶりに来たんだけど、昔と全然味は変わってねえ。冒険に出る前とか、タイマン張った後とかよ。へへへ、懐かしいよなぁ。あれから十三年後に、まさかこうして白銀のせがれと一緒にメシ食う事になるとは……。半年前、あの時、オレが死ななかったのは、レオン、お前とこうしてメシ食う為だったのかもしれねえ。神とか運命とか、信じてねえオレが言っても何の有難味もねえけどな」
ヴィルは話ながらも器用に食事を進めていく。
上品さの欠片も無いため、彼の食器の周りは家畜が餌を貪っているかの様に汚れてしまっていた。
「父も、この店に来てたんですね?」
「ああ、最初は白銀に連れて来られたんだけどよ、それ以来、この店のメシは美味いし、量が多いし、何より安いからな、駆け出しの冒険者で貧乏だった頃はほぼ毎日メシ食いに来てたぜ。多分、一年間くらい冒険で来れない時以外は毎日来てたんじゃねえかな?あの頃の、ここの親父はもう死んじまったけど、今はその息子が切り盛りしてんだよな。何処もかしこも世代交代の波が押し寄せてくるって事か。オレも年取るワケだぜ。へへへへ……」
少年の器にはまだ半分以上残っていたが、ヴィルはこの時点で殆ど平らげてしまっていた。
「あの、ヴィル?」
「ん、どーした?」
「いや、この料理すごく美味しいんですけど、全部食べ切れそうに無いです、ごめんなさい」
「ははは、そうか、そう言えばもう朝メシ食ったって言ってたっけか?じゃぁ、残りはオレが食ってやるよ」
そう言うと赤髪は長い腕を伸ばし、少年の器を自分の前まで引き寄せ、変わらぬ勢いで食事を再開してしまった。
行儀もへったくれも無いが、観てるだけで楽しくなってしまう様な食べ方だった。
そして、あっと言う間にレオンが残した分も平らげてしまう。凄まじい食いっぷりに、少年は思わず手を叩き「すごい、すごい!」と賛辞を贈っていた。
「へっ、ガキにメシの食いぷり褒められても全然嬉しかねえんだよ。おーい、ちょっと、ここ片付けてくんねえか?」
ヴィルの大声が店内へと響き渡る。
すると、少年と同い年くらいの少女がいそいそと食器を片付け、喰い散らかしてあったテーブルを綺麗に拭いてくれた。
「――なぁ、レオン?」
「はい?」
「腹も一杯になった事だし。ちょっと、ここで一発、力比べしてみねえか?」
「力比べ……ですか?ここで?」
「おう、ここで。腕相撲ってやった事あるだろう?」
「あ、はい。村で、ドワーフの子供たちとやってました」
「ほう、ドワーフとかい。それじゃぁ本場仕込みってヤツだな。腕相撲は元々酔ったドワーフ共の遊びから生まれたって聞いた事があるし」
赤髪はそう言うと立ち上がり右腕の袖を捲りあげた。
室内で立ち上がると頭が天井に届いてしまいそうで、外で見るよりも大きく見える。
少年と比べたら頭二つ分は大きいだろう。それこそ、背丈はドワーフに見劣りしないくらいだ。
そして、腕の筋肉はかなり発達していた。太い血管が幾筋もあった。
そんな大人の冒険者を目の前にしたら、如何に腕相撲だとは言え子供なら怯んで当然だが、少年の心は沸々と燃えていた。
昔からそう言う性分なのだ。
遊びでも勝負事となると、人が変わったかのように熱くなってしまう。
「へへへ、女みてえなガキのくせに、白銀と同じ目ぇしてやがる」
ヴィルは不敵な笑みを浮かべつつ、腰を落とし、テーブルの上に右肘を付けた。
レオンは、その姿を見てごくりと息を飲み、赤髪の大きな手を握り締め、右肘をテーブルへとつける。
「おーい、そこの、店員よう?ちょっとこっち来て、合図出してくれ」
余所のテーブルを片付けていた少女は面倒な事に巻き込まれたく無さそうだったが、ヴィルの声の大きさと勢いに負けて二人のテーブルへと駆け寄ってくる。
「あ、合図って、どうすれば、いいんですか?」と、少女は声を震わせそう言った。
「あん?そんなもん何でもいいんだよ。オレらの手の上にオメェの手を重ねてな、始め!って声掛けて離れればいい。後はオレらが勝手にやるから」
早口でそう説明され、少女はおどおどとしつつも、ヴィルとレオンががっちりと組んでいる手の上に、震える右手を乗せた。
その間、レオンはそんな少女は全く眼中に無いと言った感じで、ヴィルの事を燃えるような眼差しで見ていた。
「はははは、ヤベぇなこのガキ。そんな目で見られたら本気出したくなっちまうぜ」
ヴィルは、ヘラヘラとしつつもレオンの手を握り潰すくらいの勢いで力を込めた。
それに対し、少年は臆する事無く、力を込め握り返した。
大人と子供の遊びの腕相撲という雰囲気では無い。
それを察した他の客たちが、次第に二人の周りを囲みだす。
その中、野次馬たちの雑踏に紛れ、か細い少女の声が「ハジメっ!」と、響いた。