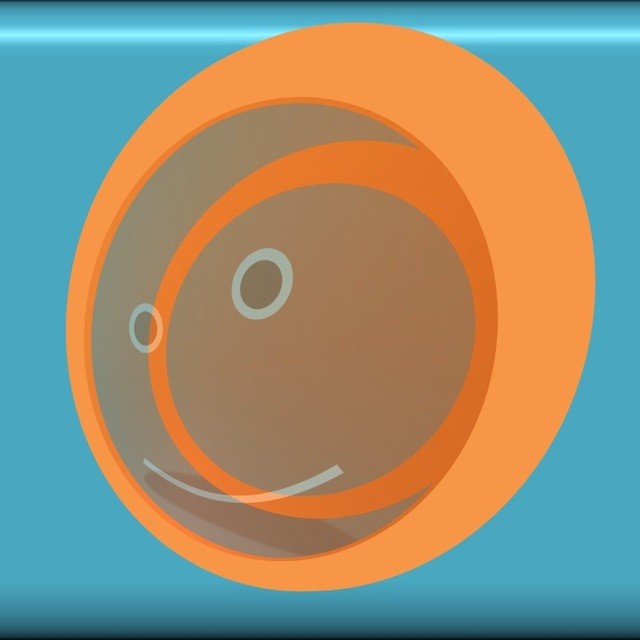第3話:酒場ルロイ
文字数 6,899文字
レオンはカウンターの椅子に腰掛け足をぷらぷらとして、大人しくしていた。
店内をぐるりと見渡す。
奥のテーブルの三人は、なにやら密談をしている様な雰囲気だった。
何となく声は聞こえるが、その内容までは分からない。しかし、その体格や声の質から言って三人とも大人の男だろう、と見当はつく。
イライザは上機嫌に鼻歌を鳴らしながら、レオンの食事の用意をしてくれていた。
街に着いて、これほど早くに出逢えるとは思っておらず、自分を簡単に受け入れてはくれないかもしれないとも思っていたため、今の状況は少年にしてみれば最高としか言いようが無かった。
「――はいよ、ルロイ名物の豚の香草焼きと、鶏肉と芋をこってりと煮込んだグリュエルだよ!たぁんっとお食べ。お代わりも好きなだけしていいからね」
テーブルには一人ではとても食べきれそうに無い量が並べられていた。
「凄いご馳走!ぼく、豚肉とか食べた事無いです。あ、猪はありますけど……似た様なものですかね?」
レオンはそう言うと手を握り合わせ目を閉じた。
そして「女神タリヴィアよ、わたくしたちを祝福し、御身によって、今いただくこの食事を祝福ください」とヴァース教徒らしく食前の祈りを捧げる。
イライザは、その可愛らしい甥の姿を慈しみを湛えた瞳で見詰めていた。
祈りの間にスプーンと木製のコップに水も入れてやり、少年の祈りが終わるのをじっと待っている。
他人が祈っている最中に声を掛けたり邪魔をするのは御法度とされているのだが、今のイライザの場合は、単にこの愛くるしい甥っ子を唯々眺めていたいと言う思いもあったのだ。
祈りを終え、目を開けるとレオンは用意されてあったスプーンを手に、まずはグリュエルから口にする事にした。
「味付けはどうだい?口に合うといいんだけどねぇ。酒飲み相手の料理だから、ちょいと濃いかもしれないけど……」
と、心配げなイライザを余所にレオンはスプーンが止まらないと言った風で、がつがつとグリュエルを口に運んでいた。
「味付けが、母さんのグリュエルと似てます。凄く美味しいです」
「あはは、そうかい、そうかい。良かった、良かった。まあ、あたしの料理も姉さんの料理も所詮は母さんの真似っこだからね、そんなに違う味になる訳は無いんだけどさあ。それでも、美味しいって言われてこんなに嬉しいのは、ほんと、何年振りだろうねえ」
「この豚の香草焼きも凄く美味しいです。猪よりも肉が柔らかくて。アンヌヴンの人って毎日こう言う美味しい料理を食べてるんですか?」
少年は故郷で食べて来た食事と比べてそう言っていた。
まず肉や芋の分量が随分と違っていた。味は似ていても食べ応えで言うと断然今の食事の方が凄いとしか言いようが無かったのだ。
「ああ、うーん、食事は人それぞれだからねえ。でも、それぐらいの質と量の食事を毎日摂れるのは、この街じゃあ一割未満かな。いや、もっと少ないかなあ」
「じゃぁ、やっぱり凄いご馳走なんですね」
「うん、普通だったらご馳走なんだけど、ここはさ、ほら売る程あるから、これからは毎日食べれるよ。アンタ、ここに住むんだしさ」
イライザは会話をしつつ、愛用のコップにエールを汲みゴクゴクと喉を鳴らしていた。
それから煙管に火を点けて、ふわりと煙を吐き出した。
「ここって……、お店に住むんですか?」
そう言うとレオンは辺りを見回す。広さ的には申し分無いが、ゆっくりと寛いだり寝たり出来る場所は無い様に見えた。
「とんでもない!こんな飲んだくれの集まる店なんかで寝させたら、姉さんが怒って蘇えっちまうよ!ここのね、二階が住居になってんのさ。三階は物置に使ってる。あたしと娘と、旦那の父親が住んでんの。義父さんは、殆ど留守にしてるけどね。あと、ヴィルって馬鹿が空いてる部屋に転がり込んでんだけどね……。とにかく、そこに今晩からはアンタも仲間入りってワケ」
「あー、なるほどー。じゃぁ、酔いどれ小路にある他の酒場も大体そう言う造りって事ですか?一階がお店で二階三階が住居、みたいな」
「酔いどれ小路がって言うか、この街にある商店は大抵そう言う造りになってんだよ。街壁の内側の土地には制限があるからね。そこから溢れ出たのは外側の貧民街に一杯住んじゃってんだから。ねー、レオン?アンタ今幾つだっけ?」
「春の四の月に十三になりました」
少年は口の中にある豚肉をもぐもぐと頬張りつつ言った。
「そうだよね。ブレイズとルロイが死んでから十三年だもん。そうか十三年かぁ。早いなあ。そっかそっか……」
「ルロイって、お店の名前ですよね?」
「うん、お店の名前。あと、あたしの旦那の名前でもあるけど」
「もしかして、父と同じ時に亡くなったんですか?その、ルロイさんは……」
イライザはコップにあったエールを一気に飲み干し、それから煙管を口に咥えた。
目を閉じて深く長く呼吸を繰り返し、紫煙を吐き散らしながらまたエールを汲んで飲みだした。
「――ブレイズはね、ベリアルの仲間全員を守ろうとして死んだ。ルロイはそんなブレイズを守ろうとして死んだ……らしいよ。その時はもう、あたし冒険者引退してたから。娘が生まれたばかりでね。ブレイズとルロイの最期の話は仲間から聞いた話でしか知らない。それからさ、姉さんはアンタを身籠った身体でアンヌヴンから出て行っちまったんだよ。誰よりもブレイズの事を愛してたからね、この街に残る事が出来なかったんだろうって思う」とイライザはいい、口を噤んだ。
想い出すのも、話すのも辛いと言った様相だった。しかし、繰り返し煙管を吹かし再び口を開く。
「――まあ、それはあたしだって同じだったんだけど、もう娘が生れててさ、意地でも育てなきゃなんなかったから。それでも、いつかは戻って来てくれると思ってたんだよなあ。そんでさ、姉妹でこの店切り盛りして、皆でわいわい面白おかしく生きて行くのも悪くないって……あはは、ごめんごめん、湿っぽくなっちゃったね、グリュエル、お代わりするかい?」
少年はもう、かなり満たされていたが、悲しい笑みを浮かべる叔母の誘いを断る事が出来ずに、皿を差し出していた。
父の事も冒険やこの街の事も、まだ分からない事ばかりだが、その悲痛な想いだけは十分に伝わって来る。
イライザは少年から皿を受け取りカウンターの奥へと行った。
それと時を同じくして、酒房ルロイに来店する者があった。
静かに扉を開けて、声も無く入店しカウンターの真ん中に腰掛けているレオンの左手に、ふわりと腰掛けた。
濃紫色のローブを目深に被っているので、人相も性別も分からない。しかし、鼻先を擽る様な軽やかな良い匂いを漂わせていた。
その人物は席に着くなり、カウンターの上に白く輝く綺麗な石を置き、そして濃紫色のローブから頭をするりと出した。
知らない人をあまりじろじろと見ては失礼だと、思いつつもレオンはその人物の所作から目を離す事が出来なかった。
「おやおや、こんな野蛮な店に可愛らしいお客さんだ……」
その人物は、そう会釈をしてから暫くレオンの顔をじいっと見詰めていた。か細く神経質そうな声だが、不思議と耳心地が良い。
鼻が高く、緑色の目は切れ長でとても整った顔立ち。
そして何より目を惹くのが長く尖った耳だ。
レオンはその人物を恐らく男性だと思ってはいたが、とても綺麗で美しい人だとも思っていた。
「あれ、おかしい、少しハーブをキメ過ぎた様だ。幻覚が見えてしまう。いや、それとも忌まわしい悪魔教ギヴオンの輩からまたぞろ妙な手管の魔術を仕掛けられているのだろうか?」
そう言いつつ、美しい男はレオンの銀髪に指先で触れ、はらはらと撫でる様に感触を確かめていた。
「ふむ、この感触は幻覚の類では無いな。しかし、それにしてもこれは白銀の獅子そのものでは無いか。少し幼い様に見えるが。と、なるともしかしたら私の記憶から彼の者姿を抽出して実体化させたのだろうか?それ程高位の錬金かそれに準ずる術を使える者がこんな辺境の街に現れる筈も無いとは思うが……いやしかし、目の前のコレは実に……」
男の細く長い指は少年の髪から耳、頬、唇にまで伸びていた。まるで小動物を弄るかの様に。
そこにイライザの鋭い声が響き渡る。
「やい、この馬鹿エルフ!いい加減にしなー。ほら、レオンが困ってるじゃ無いか。似てるけど、その子はブレイズじゃ無いよ。幻術とか怪しい術の類でも無いから」
「やあ、イライザ、御機嫌よう。では、この白銀の獅子と瓜二つの生物は一体何物なのだろう?スライムの様な軟体生物から成型したのか?ほら、この頬の部分は実に柔らかく触り心地が良いぞ?何処で売っているのだ?まだ売っているのなら私もひとつ買ってみるから……」
イライザは溜息混じりに、カウンターから躍り出て馬鹿エルフと呼んだ男からレオンを引き剥がした。
「ったく、犬猫を触るみたいに触れんなっての。この子はねあたしの甥っ子だよ。レオンっての。ブレイズとアンナ姉さんの息子なの。まぁ、本当にブレイズと瓜二つだから見間違うのは分かるけどね。レオン?コイツはね、フレイザーってエルフの魔導士。元ベリアルだから、アンタの父さんと母さんとは顔馴染みなんだよ」
犬猫みたいに触るなと言い放った彼女が、レオンの事を子犬の様に抱き締めている事について、フレイザーは一言物申そうと思ったが、面倒臭くなるのは目に見えたので止めることにした。
イライザから抱き締められつつ、レオンは美しいエルフの魔導士に見惚れていた。
その所作は男性的だが、容姿は限りなく中性的で、何より優美で所作や振る舞いが軽やかだ。
少年の住んでいた村には人間とドワーフしかいなかった為、エルフを見たのがこれが初めての事だった。
「――はじめまして、フレイザーさん。レオンと言います。今日から、この店でお世話になる事になりました」
「そうか、なるほどな。では、やはり鬼女殿は逝かれてしまっていたか……」
「は?ちょっと、フレイザー?何?アンタ、姉さんが死んだこと知ってたワケ?」
イライザはレオンをぎゅっと抱き締めたまま声を荒げていた。
それに対しフレイザーは飄々とした態度で受け応えている。
「そうだね、先月、アンナに結びつけていた紐がぷつりと切れてしまったから。私の紐付けを切るとなると、私より高位のエルフの魔導士の手によるものか、対象人物の死以外には考えられない。それで、現実的に山岳の村のドワーフ臭い村に住んでいる以上、前者はありえないから、必然として後者になると、踏んではいたのだけれど」
「あーあーあーあー、違う違う!そうじゃ無くて!そんな理屈っぽい事じゃ無くてさ!何で姉さんが死んじゃった事教えてくれなかったんだよ?って言いたいの、あたしは!どうせ、アンタぐらいの力があったら、姉さんが流行り病に罹っていた事とかも分かってたんでしょう?」
「いや、流石にそこまでは分かり兼ねた。白銀の獅子が無くなって以来、彼女はかなり長い間心を閉ざし外との繋がりを拒んでたからね。鬼女殿であれば私と紐で繋がっている事を察してしまう可能性があったから、一応切った体にした訳。実際は、紐を極限にまで細くして何とか繋げていたのだけれど、戦闘職にしては勘の鋭い鬼女殿に気が付かれぬ様に、細く細く、ね」
美しいエルフは自信ありげな表情を浮かべ、親指を人差し指を擦り合わせて細さを表現していた。そして、更に続ける。
「――お陰様で私の紐付けの能力は他のエルフの魔導士と比べても群を抜いてしまっていると言うか、正直この地方のエルフの中では最高級の紐付けと言える。故に本来の私の紐付けであれば対象者の健康状態程度の把握は容易いが、対鬼女殿の紐付けは、残念ながら切れたかどうか程度の事しか分からなかったと言うのが、事の真実になるということだよ。至極簡素に説明してあげれば」
フレイザーは飄々とした態度のまま、そう言葉を切った。
「いや、だから、そうじゃ無くて。ああ、もういいわ。はあああああ……」とイライザの長い溜息が響く。
このエルフに人情とか感情論を幾らぶつけても無駄な事は重々承知しているが、彼女にしてみればやり切れない思いが胸中に宿ってしまうのだろう。
「レオン?これで、このエルフがどんなヤツかは何となく分かったでしょ?」
イライザはレオンの頭を撫でてから、彼を解放してカウンターの中へと戻った。
そして、濃い緑色の瓶と同じ色のグラスを持ってフレイザーへと差し出す。
すると彼は、懐から小さな白く輝く石を取り出しグラスの中へと入れ、そこへ瓶から液体を注いだ。
瓶から出たばかりの液体は緑色に見えるが、グラスの中に納まると薄い紫色の様に見える。
不思議な飲み物だった。
「――ふふふふ、色が変わって面白いだろう?」
美しいエルフはそう言って、その液体を一口含み、ごくりと喉を鳴らした。
「はい、すごく綺麗ですね……それは、お酒ですか?グラスに入ったら色が変わった様に見えました」
「お酒だよ。リキュールと言って、エルフが作るエルフの為のお酒。これは私のお手製でね、緑色から紫色に変化させれるまでに二十年もの月日を要したんだよ。ちなみに、これを人間が飲んだら、三日間くらい性欲が収まらなくなってしまうみたいだから、キミはまだ手を出さない方がいいろうね。それに、あの小五月蠅い毒使いにこっぴどく怒られてしまうだろうしさ、ふふふふふ」
「その白く輝いてる石は、何ですか?」レオンはグラスを指さしそう訊ねていた。
「おお、流石は白銀の獅子の子だね、目の付け所が実に素晴らしい。これは……光の魔魂の結晶を、私が高圧の魔力で圧縮した物。カウンターの上に転がしてあるのも同じ。これらでね、身の回りを常に浄化しなければ、エルフは人間の住む地帯には住めないんだ。移動する時はこの浄化ローブを常に纏っている。人間やら他の種族やら亜人の住むところは空気が穢れているからね。浄化無しで生活していると、エルフは、あっと言う間に闇堕ちしてしまって、所謂、邪悪な存在になってしまうから、常にこうして浄化できる装備と道具を持ち歩いているワケ。まあ、他の種族と比べたら圧倒的に優雅で高貴な種族だから、それくらいの罰は甘んじて受け入れて当然とも言えるのだけれどね。高貴な種族に生れてしまったが故の宿命ってやつだ」
フレイザーは左手にグラスを持ち、右手の指を軽やかに動かしながら語っていた。
初めて相対するエルフの言葉を丸っと信じ込んでいるレオンと、それを呆れ顔で見詰めているイライザ。彼女はテキパキと店の開店準備をしつつ、エルフの言葉が切れるのを待っていた。
「はんっ!何が高貴な種族だよ。そんな穢れた人間とか他の種族と、冒険するのが楽しくて楽しくて止めれなくってこの街を離れられなくなったのは何処のどのエルフ様だい?レオン、覚えときなよ?普通の大森林の奥とかで暮らしてるエルフはね、人間嫌いで有名なんだよ。基本的に他種族とは交流をしない種族なの。フレイザーみたいにね、人間の街に住んでるエルフなんてさ、只の変人なんだから」
それに対して、フレイザーは依然、飄々と切り返してくる。
「街エルフを変人と揶揄するのは構わないけれど、その変人たちの血の滲む様な努力と研究のお陰で、今や森のエルフたちも外の世界へと自由に行き来出来る様になったのだ。今でこそまだ他種族との交流を拒んでいる者たちも多いが、何れはその垣根も無くなってしまうだろう。その、そう遠くは無い未来、今変人と罵られている我々街のエルフたちは、歴史を動かした偉人として語り継がれている事だろうね。いや、偉人どころか神として崇められているかもしれないね、ふふふふ」
「はぁ?何が神だよ!このハーブ狂いのイカレエルフが!!」
「イライザ?ハーブ狂いはまだしも、イカレエルフは許せない。直ちに訂正なさい、このアバズレヤリマン女」
「ああん!?てめー誰がアバズレヤリマンだと?このクソキチガイイカレエルフが、上等だよ!掛かってきな!今日という今日は、ぶっころしてやる!!」と、こんな感じでイライザとフレイザーの激しい罵り合いは延々と続いてゆく。
二人ともレオンの存在を完全に忘れてしまっている様だった。
少年は、罵詈雑言を適当に流し聞きしつつ、出された食事を全部食べ切ってしまったので、食器を洗う事にした。
一応、イライザに水場を使う断りを入れ様としたが、エルフとの舌戦が激しさを増していたため、諦めて使用した食器を持ちカウンターの奥へと入る。
取り敢えず、理解出来た事はこの叔母とエルフが犬猿の仲だと言う事。これは間違いない。
恐らく、二人ともいい人なんだろうけど、と少年は思いつつ使った食器を水場へと置いた。
店内をぐるりと見渡す。
奥のテーブルの三人は、なにやら密談をしている様な雰囲気だった。
何となく声は聞こえるが、その内容までは分からない。しかし、その体格や声の質から言って三人とも大人の男だろう、と見当はつく。
イライザは上機嫌に鼻歌を鳴らしながら、レオンの食事の用意をしてくれていた。
街に着いて、これほど早くに出逢えるとは思っておらず、自分を簡単に受け入れてはくれないかもしれないとも思っていたため、今の状況は少年にしてみれば最高としか言いようが無かった。
「――はいよ、ルロイ名物の豚の香草焼きと、鶏肉と芋をこってりと煮込んだグリュエルだよ!たぁんっとお食べ。お代わりも好きなだけしていいからね」
テーブルには一人ではとても食べきれそうに無い量が並べられていた。
「凄いご馳走!ぼく、豚肉とか食べた事無いです。あ、猪はありますけど……似た様なものですかね?」
レオンはそう言うと手を握り合わせ目を閉じた。
そして「女神タリヴィアよ、わたくしたちを祝福し、御身によって、今いただくこの食事を祝福ください」とヴァース教徒らしく食前の祈りを捧げる。
イライザは、その可愛らしい甥の姿を慈しみを湛えた瞳で見詰めていた。
祈りの間にスプーンと木製のコップに水も入れてやり、少年の祈りが終わるのをじっと待っている。
他人が祈っている最中に声を掛けたり邪魔をするのは御法度とされているのだが、今のイライザの場合は、単にこの愛くるしい甥っ子を唯々眺めていたいと言う思いもあったのだ。
祈りを終え、目を開けるとレオンは用意されてあったスプーンを手に、まずはグリュエルから口にする事にした。
「味付けはどうだい?口に合うといいんだけどねぇ。酒飲み相手の料理だから、ちょいと濃いかもしれないけど……」
と、心配げなイライザを余所にレオンはスプーンが止まらないと言った風で、がつがつとグリュエルを口に運んでいた。
「味付けが、母さんのグリュエルと似てます。凄く美味しいです」
「あはは、そうかい、そうかい。良かった、良かった。まあ、あたしの料理も姉さんの料理も所詮は母さんの真似っこだからね、そんなに違う味になる訳は無いんだけどさあ。それでも、美味しいって言われてこんなに嬉しいのは、ほんと、何年振りだろうねえ」
「この豚の香草焼きも凄く美味しいです。猪よりも肉が柔らかくて。アンヌヴンの人って毎日こう言う美味しい料理を食べてるんですか?」
少年は故郷で食べて来た食事と比べてそう言っていた。
まず肉や芋の分量が随分と違っていた。味は似ていても食べ応えで言うと断然今の食事の方が凄いとしか言いようが無かったのだ。
「ああ、うーん、食事は人それぞれだからねえ。でも、それぐらいの質と量の食事を毎日摂れるのは、この街じゃあ一割未満かな。いや、もっと少ないかなあ」
「じゃぁ、やっぱり凄いご馳走なんですね」
「うん、普通だったらご馳走なんだけど、ここはさ、ほら売る程あるから、これからは毎日食べれるよ。アンタ、ここに住むんだしさ」
イライザは会話をしつつ、愛用のコップにエールを汲みゴクゴクと喉を鳴らしていた。
それから煙管に火を点けて、ふわりと煙を吐き出した。
「ここって……、お店に住むんですか?」
そう言うとレオンは辺りを見回す。広さ的には申し分無いが、ゆっくりと寛いだり寝たり出来る場所は無い様に見えた。
「とんでもない!こんな飲んだくれの集まる店なんかで寝させたら、姉さんが怒って蘇えっちまうよ!ここのね、二階が住居になってんのさ。三階は物置に使ってる。あたしと娘と、旦那の父親が住んでんの。義父さんは、殆ど留守にしてるけどね。あと、ヴィルって馬鹿が空いてる部屋に転がり込んでんだけどね……。とにかく、そこに今晩からはアンタも仲間入りってワケ」
「あー、なるほどー。じゃぁ、酔いどれ小路にある他の酒場も大体そう言う造りって事ですか?一階がお店で二階三階が住居、みたいな」
「酔いどれ小路がって言うか、この街にある商店は大抵そう言う造りになってんだよ。街壁の内側の土地には制限があるからね。そこから溢れ出たのは外側の貧民街に一杯住んじゃってんだから。ねー、レオン?アンタ今幾つだっけ?」
「春の四の月に十三になりました」
少年は口の中にある豚肉をもぐもぐと頬張りつつ言った。
「そうだよね。ブレイズとルロイが死んでから十三年だもん。そうか十三年かぁ。早いなあ。そっかそっか……」
「ルロイって、お店の名前ですよね?」
「うん、お店の名前。あと、あたしの旦那の名前でもあるけど」
「もしかして、父と同じ時に亡くなったんですか?その、ルロイさんは……」
イライザはコップにあったエールを一気に飲み干し、それから煙管を口に咥えた。
目を閉じて深く長く呼吸を繰り返し、紫煙を吐き散らしながらまたエールを汲んで飲みだした。
「――ブレイズはね、ベリアルの仲間全員を守ろうとして死んだ。ルロイはそんなブレイズを守ろうとして死んだ……らしいよ。その時はもう、あたし冒険者引退してたから。娘が生まれたばかりでね。ブレイズとルロイの最期の話は仲間から聞いた話でしか知らない。それからさ、姉さんはアンタを身籠った身体でアンヌヴンから出て行っちまったんだよ。誰よりもブレイズの事を愛してたからね、この街に残る事が出来なかったんだろうって思う」とイライザはいい、口を噤んだ。
想い出すのも、話すのも辛いと言った様相だった。しかし、繰り返し煙管を吹かし再び口を開く。
「――まあ、それはあたしだって同じだったんだけど、もう娘が生れててさ、意地でも育てなきゃなんなかったから。それでも、いつかは戻って来てくれると思ってたんだよなあ。そんでさ、姉妹でこの店切り盛りして、皆でわいわい面白おかしく生きて行くのも悪くないって……あはは、ごめんごめん、湿っぽくなっちゃったね、グリュエル、お代わりするかい?」
少年はもう、かなり満たされていたが、悲しい笑みを浮かべる叔母の誘いを断る事が出来ずに、皿を差し出していた。
父の事も冒険やこの街の事も、まだ分からない事ばかりだが、その悲痛な想いだけは十分に伝わって来る。
イライザは少年から皿を受け取りカウンターの奥へと行った。
それと時を同じくして、酒房ルロイに来店する者があった。
静かに扉を開けて、声も無く入店しカウンターの真ん中に腰掛けているレオンの左手に、ふわりと腰掛けた。
濃紫色のローブを目深に被っているので、人相も性別も分からない。しかし、鼻先を擽る様な軽やかな良い匂いを漂わせていた。
その人物は席に着くなり、カウンターの上に白く輝く綺麗な石を置き、そして濃紫色のローブから頭をするりと出した。
知らない人をあまりじろじろと見ては失礼だと、思いつつもレオンはその人物の所作から目を離す事が出来なかった。
「おやおや、こんな野蛮な店に可愛らしいお客さんだ……」
その人物は、そう会釈をしてから暫くレオンの顔をじいっと見詰めていた。か細く神経質そうな声だが、不思議と耳心地が良い。
鼻が高く、緑色の目は切れ長でとても整った顔立ち。
そして何より目を惹くのが長く尖った耳だ。
レオンはその人物を恐らく男性だと思ってはいたが、とても綺麗で美しい人だとも思っていた。
「あれ、おかしい、少しハーブをキメ過ぎた様だ。幻覚が見えてしまう。いや、それとも忌まわしい悪魔教ギヴオンの輩からまたぞろ妙な手管の魔術を仕掛けられているのだろうか?」
そう言いつつ、美しい男はレオンの銀髪に指先で触れ、はらはらと撫でる様に感触を確かめていた。
「ふむ、この感触は幻覚の類では無いな。しかし、それにしてもこれは白銀の獅子そのものでは無いか。少し幼い様に見えるが。と、なるともしかしたら私の記憶から彼の者姿を抽出して実体化させたのだろうか?それ程高位の錬金かそれに準ずる術を使える者がこんな辺境の街に現れる筈も無いとは思うが……いやしかし、目の前のコレは実に……」
男の細く長い指は少年の髪から耳、頬、唇にまで伸びていた。まるで小動物を弄るかの様に。
そこにイライザの鋭い声が響き渡る。
「やい、この馬鹿エルフ!いい加減にしなー。ほら、レオンが困ってるじゃ無いか。似てるけど、その子はブレイズじゃ無いよ。幻術とか怪しい術の類でも無いから」
「やあ、イライザ、御機嫌よう。では、この白銀の獅子と瓜二つの生物は一体何物なのだろう?スライムの様な軟体生物から成型したのか?ほら、この頬の部分は実に柔らかく触り心地が良いぞ?何処で売っているのだ?まだ売っているのなら私もひとつ買ってみるから……」
イライザは溜息混じりに、カウンターから躍り出て馬鹿エルフと呼んだ男からレオンを引き剥がした。
「ったく、犬猫を触るみたいに触れんなっての。この子はねあたしの甥っ子だよ。レオンっての。ブレイズとアンナ姉さんの息子なの。まぁ、本当にブレイズと瓜二つだから見間違うのは分かるけどね。レオン?コイツはね、フレイザーってエルフの魔導士。元ベリアルだから、アンタの父さんと母さんとは顔馴染みなんだよ」
犬猫みたいに触るなと言い放った彼女が、レオンの事を子犬の様に抱き締めている事について、フレイザーは一言物申そうと思ったが、面倒臭くなるのは目に見えたので止めることにした。
イライザから抱き締められつつ、レオンは美しいエルフの魔導士に見惚れていた。
その所作は男性的だが、容姿は限りなく中性的で、何より優美で所作や振る舞いが軽やかだ。
少年の住んでいた村には人間とドワーフしかいなかった為、エルフを見たのがこれが初めての事だった。
「――はじめまして、フレイザーさん。レオンと言います。今日から、この店でお世話になる事になりました」
「そうか、なるほどな。では、やはり鬼女殿は逝かれてしまっていたか……」
「は?ちょっと、フレイザー?何?アンタ、姉さんが死んだこと知ってたワケ?」
イライザはレオンをぎゅっと抱き締めたまま声を荒げていた。
それに対しフレイザーは飄々とした態度で受け応えている。
「そうだね、先月、アンナに結びつけていた紐がぷつりと切れてしまったから。私の紐付けを切るとなると、私より高位のエルフの魔導士の手によるものか、対象人物の死以外には考えられない。それで、現実的に山岳の村のドワーフ臭い村に住んでいる以上、前者はありえないから、必然として後者になると、踏んではいたのだけれど」
「あーあーあーあー、違う違う!そうじゃ無くて!そんな理屈っぽい事じゃ無くてさ!何で姉さんが死んじゃった事教えてくれなかったんだよ?って言いたいの、あたしは!どうせ、アンタぐらいの力があったら、姉さんが流行り病に罹っていた事とかも分かってたんでしょう?」
「いや、流石にそこまでは分かり兼ねた。白銀の獅子が無くなって以来、彼女はかなり長い間心を閉ざし外との繋がりを拒んでたからね。鬼女殿であれば私と紐で繋がっている事を察してしまう可能性があったから、一応切った体にした訳。実際は、紐を極限にまで細くして何とか繋げていたのだけれど、戦闘職にしては勘の鋭い鬼女殿に気が付かれぬ様に、細く細く、ね」
美しいエルフは自信ありげな表情を浮かべ、親指を人差し指を擦り合わせて細さを表現していた。そして、更に続ける。
「――お陰様で私の紐付けの能力は他のエルフの魔導士と比べても群を抜いてしまっていると言うか、正直この地方のエルフの中では最高級の紐付けと言える。故に本来の私の紐付けであれば対象者の健康状態程度の把握は容易いが、対鬼女殿の紐付けは、残念ながら切れたかどうか程度の事しか分からなかったと言うのが、事の真実になるということだよ。至極簡素に説明してあげれば」
フレイザーは飄々とした態度のまま、そう言葉を切った。
「いや、だから、そうじゃ無くて。ああ、もういいわ。はあああああ……」とイライザの長い溜息が響く。
このエルフに人情とか感情論を幾らぶつけても無駄な事は重々承知しているが、彼女にしてみればやり切れない思いが胸中に宿ってしまうのだろう。
「レオン?これで、このエルフがどんなヤツかは何となく分かったでしょ?」
イライザはレオンの頭を撫でてから、彼を解放してカウンターの中へと戻った。
そして、濃い緑色の瓶と同じ色のグラスを持ってフレイザーへと差し出す。
すると彼は、懐から小さな白く輝く石を取り出しグラスの中へと入れ、そこへ瓶から液体を注いだ。
瓶から出たばかりの液体は緑色に見えるが、グラスの中に納まると薄い紫色の様に見える。
不思議な飲み物だった。
「――ふふふふ、色が変わって面白いだろう?」
美しいエルフはそう言って、その液体を一口含み、ごくりと喉を鳴らした。
「はい、すごく綺麗ですね……それは、お酒ですか?グラスに入ったら色が変わった様に見えました」
「お酒だよ。リキュールと言って、エルフが作るエルフの為のお酒。これは私のお手製でね、緑色から紫色に変化させれるまでに二十年もの月日を要したんだよ。ちなみに、これを人間が飲んだら、三日間くらい性欲が収まらなくなってしまうみたいだから、キミはまだ手を出さない方がいいろうね。それに、あの小五月蠅い毒使いにこっぴどく怒られてしまうだろうしさ、ふふふふふ」
「その白く輝いてる石は、何ですか?」レオンはグラスを指さしそう訊ねていた。
「おお、流石は白銀の獅子の子だね、目の付け所が実に素晴らしい。これは……光の魔魂の結晶を、私が高圧の魔力で圧縮した物。カウンターの上に転がしてあるのも同じ。これらでね、身の回りを常に浄化しなければ、エルフは人間の住む地帯には住めないんだ。移動する時はこの浄化ローブを常に纏っている。人間やら他の種族やら亜人の住むところは空気が穢れているからね。浄化無しで生活していると、エルフは、あっと言う間に闇堕ちしてしまって、所謂、邪悪な存在になってしまうから、常にこうして浄化できる装備と道具を持ち歩いているワケ。まあ、他の種族と比べたら圧倒的に優雅で高貴な種族だから、それくらいの罰は甘んじて受け入れて当然とも言えるのだけれどね。高貴な種族に生れてしまったが故の宿命ってやつだ」
フレイザーは左手にグラスを持ち、右手の指を軽やかに動かしながら語っていた。
初めて相対するエルフの言葉を丸っと信じ込んでいるレオンと、それを呆れ顔で見詰めているイライザ。彼女はテキパキと店の開店準備をしつつ、エルフの言葉が切れるのを待っていた。
「はんっ!何が高貴な種族だよ。そんな穢れた人間とか他の種族と、冒険するのが楽しくて楽しくて止めれなくってこの街を離れられなくなったのは何処のどのエルフ様だい?レオン、覚えときなよ?普通の大森林の奥とかで暮らしてるエルフはね、人間嫌いで有名なんだよ。基本的に他種族とは交流をしない種族なの。フレイザーみたいにね、人間の街に住んでるエルフなんてさ、只の変人なんだから」
それに対して、フレイザーは依然、飄々と切り返してくる。
「街エルフを変人と揶揄するのは構わないけれど、その変人たちの血の滲む様な努力と研究のお陰で、今や森のエルフたちも外の世界へと自由に行き来出来る様になったのだ。今でこそまだ他種族との交流を拒んでいる者たちも多いが、何れはその垣根も無くなってしまうだろう。その、そう遠くは無い未来、今変人と罵られている我々街のエルフたちは、歴史を動かした偉人として語り継がれている事だろうね。いや、偉人どころか神として崇められているかもしれないね、ふふふふ」
「はぁ?何が神だよ!このハーブ狂いのイカレエルフが!!」
「イライザ?ハーブ狂いはまだしも、イカレエルフは許せない。直ちに訂正なさい、このアバズレヤリマン女」
「ああん!?てめー誰がアバズレヤリマンだと?このクソキチガイイカレエルフが、上等だよ!掛かってきな!今日という今日は、ぶっころしてやる!!」と、こんな感じでイライザとフレイザーの激しい罵り合いは延々と続いてゆく。
二人ともレオンの存在を完全に忘れてしまっている様だった。
少年は、罵詈雑言を適当に流し聞きしつつ、出された食事を全部食べ切ってしまったので、食器を洗う事にした。
一応、イライザに水場を使う断りを入れ様としたが、エルフとの舌戦が激しさを増していたため、諦めて使用した食器を持ちカウンターの奥へと入る。
取り敢えず、理解出来た事はこの叔母とエルフが犬猿の仲だと言う事。これは間違いない。
恐らく、二人ともいい人なんだろうけど、と少年は思いつつ使った食器を水場へと置いた。