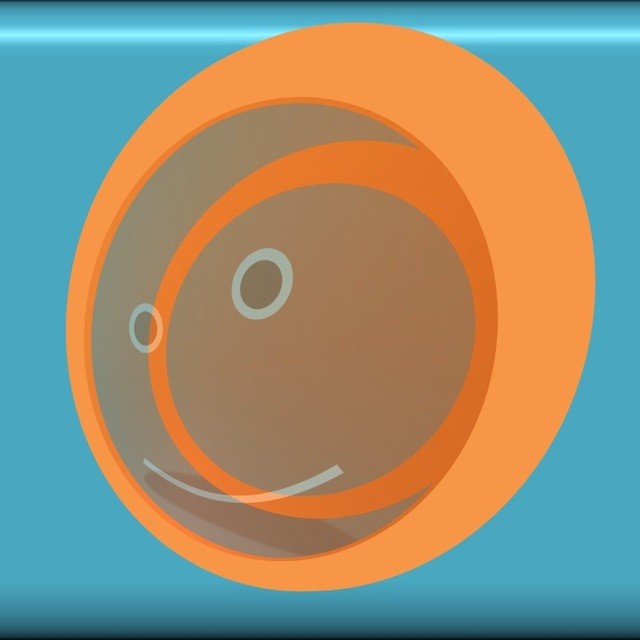第2話:昔の仲間の娘。
文字数 5,354文字
アンヌヴンの街の西側には、雄大なイリス川が流れており街の対岸には森林が広がっている。
そこはラートの森と呼ばれ、大昔はドールズ大森林と同等の規模を誇っていたが、アンヌヴンの街が栄え人口が増えると共に、森は縮小の一途を辿っていた。
数十年前までは幻獣やオークが多く棲みついており、年に数回討伐隊が組まれていたが、近年ではそれらの目撃例も減っている。
現在ではその規模こそ縮小しつつあるも、鹿や猪などが多く住む穏やかで豊かな森へと変様していた。
ラートの森の近隣には幾つか集落があり、アンヌヴン近郊の大きな集落は森の名を冠されラート集落と呼ばれていた。
その集落に赤髪のヴィルの姿があった。
エイプリルの娼婦館を出てから、北門経由で貧民街を通り渡り船でイリス川を越え集落まで来たのだ。
太陽は西側へと傾き始めていた。
「――五年振りくらいか。確か、ラートの森の奥の方で珍しい幻獣が目撃されたとかで、それを狩りに来た以来だな、たしか……」
赤髪はそう言って過去を振り返り、舌打ちをして地面にツバを吐いた。
五年前に何か嫌な事があった訳では無く、只単に、その歳月の間に起こってしまった事に対する、悪態と言ったところか。
ラート集落は、頑丈な木製の柵で周囲を覆われていた。
今となっては外敵は殆ど無いが、まだオークが森をうろついていた頃の名残として今でも、集落の人々が定期的に整備している。
柵の外には掘っ建て小屋が幾つも並んでいた。
「ん?ボロい家多いな。前来た時より、確実に増えてるよな……いずれ、この辺りも貧民街みたいになるのか?」
そう言うと赤髪は辺りを見回しつつ、集落の中へと足を踏み入れた。
アンヌヴンの街壁沿いの貧民街と呼ばれる地域も年々広がっているのだ。
闇市や禁止薬物の取引などが横行してる為、年に数回は辺境伯や地方行政区の取り締まりが入ってはいるが一向に治安が良くなる兆しは見えないのが現状だった。
ラート集落の柵の外の掘っ建て小屋に住んでいるのは木こりの見習いや、貧民街にすらも居場所を見つける事が出来なかった弱者ばかりなので、今のところ行政は軽視していると言って過言無いだろう。
「――おい、そこのヤツ、赤髪のヴィルじゃあないかい?」
若い女の声が響いた。凛とした声だった。赤髪はその声の主へと振り返る。
ふと、知った顔だと思ったが、名前も素性も思い出す事は出来なかった。
ただ、いい女だとは感じていた。
「あ?えーっと、オマエ、誰だっけ?そのナリからすると、ドワーフか?いや、ドワーフの女にしちゃぁちいとばかし背が低いか」
目を細め、女の全身を舐める様に見ていた。
癖の強い真っ黒な髪を無理やり一つに束ねている。凛々しい眉毛と意思の強い瞳が印象的だった。
そして、明らかに人間では無いが抱き応えの有りそうな身体だと、赤髪の口許はいやらしく緩んでしまっている。
「あら、残念ね、覚えて無いかしら?ローゼマリーよ。ヴォルフ・ユルゲンの娘。五年前に会ったじゃない。と、言ってもあの頃は見向きもされなかったけれどね」
彼女からそう告げられて、赤髪は漸く途切れていた記憶が繋がる。
「ん?あ!おー!おー!そう言えば、ガキがいたよなぁ。ヴォルフを冒険に誘ったら、ガキに腕噛み付かれたから蹴っ飛ばしてやったんだよ。そしたらピーピー泣きやがって……アレお前かよ。あん時、オレはヴォルフに強烈な拳骨喰らったんだ。超痛ぇやつな!」
「そんなの、子供だった私を本気で蹴っ飛ばしたアンタが悪いんでしょう?それに、あの頃は母が亡くなったばかりで、アンタたちみたいな冒険者に父を取られたくないって思いが強かったのよ」
ローゼマリーはそう言うと、赤髪へと歩み寄り、右手を差し出した。
それを見てヴィルは、いつもの不敵な笑みを口許に湛えつつその手を握り締めた。かなり力を込めて。
普通の女の手なら握り潰されていただろうが、ローゼマリーは平然と涼し気な表情で握り返していた。
「ちっ、親父譲りの馬鹿力だな!お前の親父は、おれの知る限りじゃ三本の指に入る戦士だから、冒険があるなら誘うに決まってんだろうが?こんな集落で木こりとか……同じ斧振るうならユニオンの最前衛でバケモン相手に振りやがれってんだ」
「そんなのもう十年以上も昔の話だろう?今更、また父を引っ張り出して冒険に連れてこうってのかい?」
「へへへ、だったらどうする?またオレの腕に噛み付くかよ?」
赤髪は更に力を込めて、ローゼマリーの手を握り締めた。
腕が小刻みに震えている。顔には出して無いが朝、レオンと腕相撲した時よりも本気で力を入れているがローゼマリーは依然涼し気な表情で握り返してくる。
「あははは、そんな汚らわしい腕に誰が噛み付くものか。それに……連れて行きたければどうぞご勝手に」
「いいんだな?今度は本気で連れてくぜ?」
「うふふふ、そう、本気なのか。じゃぁ、案内してあげるよ」
「けっ、案内なんていらねえってんだよ!こんな小せぇ集落で迷わねえっての」
「あら、そう?でも、アンタが向かおうとしてるところに、もう父は住んで無いわよ?」
そういうと、彼女はどこか寂し気な笑みを浮かべていた。
「あぁん?なんだ、ヴォルフのヤロー家越したのか?って、まさかアンヌヴンの街に住んでんのか?だとしたら、イリス川まで越えて飛んだ無駄足……ん?いや、街に住むって柄じゃねえからなぁ。って、おい、まさかヴォルフのヤロー……」
「父は、先月他界したの。家や家財道具は全部売り払ったわ。それが父の遺言だったから。今日、私は残りの金貨を引き取りに来ただけ。お墓は森の奥の、大きな杉の木の下に。だから、父を連れて行きたいなら、そこまで案内してあげる」
ローゼマリーの話途中で、赤髪は手と腕から力を抜いた。
それを感じ彼女も脱力していた。
「まじか。まじかよ……。ヴォルフ、死にやがったのか。なんだよ、アンナといい、ヴォルフといい、昔の仲間がどんどん死んじまいやがる。くそっ、なんでだよ、くそっ……」
「アンタとか白銀とかベリアルの話をしてる時の父はいつも楽しそうだった。お酒を飲んで酔っ払っている時は、いつも大抵その頃の冒険譚を語ってくれてた。で、どうする?お墓まで案内しようか?」
目に見えて気を落としている赤髪を覗き込む様に、彼女はそう言った。
身長はヴィルよりも少し低い。普通のドワーフなら女でも人間の男より背が高いのだが。
「あ?馬鹿言うんじゃねえ。冒険者は墓参りはしちゃいけねえんだ。あの世に魂が引っ張られっからな。だから、墓参りには行かねえ」
「へえ、そんな決まり事があるんだ?じゃぁ、私もこれからはお墓参り行っちゃダメって事だね。では、私はそろそろ行くから……さようなら、赤髪のヴィル」
ローゼマリーは、そう言うときびきびとした足取りで歩き出した。
彼女の言葉を聞いた赤髪は、ばっと身を翻す。
「ん?お、おい、ちょっと待て。お前、もしかして、冒険者になったのか?」
その声は少し上擦っている様に響いた。
ローゼマリーはピタリと足を止めて、振り返る。軽快な身のこなしだった。
「ええ、ついさっき、冒険者ギルドで登録して来たわ」
「ついさっきって、まじかよ。そんで、もうユニオンは決めてんのか?」
「ユニオンはまだ決めて無いよ。私、冒険者の知り合いいないし、ユニオンの評判とかもよく分からないから」と、彼女はまた平然とした顔でそう言った。
無知ゆえの自信なのか、生来胆が据わっているのか。
そして、また赤髪を置いて歩き始める。
きびきびとした足取り。迷い無く己の道を歩いて行く、この感じ。
その凛々しい後ろ姿を見て、赤髪は「感じってゆーか、雰囲気ってゆーか、何となく、若い頃の神槍に似てるんだよな」と呟く。
それから大きな声で彼女の名を呼んだ。
「おーい、ローゼマリー?」
彼女はまたぴたりと足を止めて、赤髪へと振り返った。
「何?まだ用件があるの?」
十歩ほどの距離。彼女は腕を組み、赤髪の様子を伺っていた。
「いや、まぁ、用件ってゆーか、お前よう?住むトコとかあんのか?」
「それは、まぁ、一応。そう広くは無いけれど、街壁の中に部屋を借りているわ」
「そうか。まぁヴォルフの家とか家財道具とか一切合切売り払ったなら、それなりに金は持ってるってことか……」
嫌われているのは重々承知していた。しかし、彼はそれで引き下がる様な軟な男ではない。冒険だろうが家だろうが、なんでもいいから兎に角、会話を弾ませる切っ掛けを探っていた。
「ねえ?もう行っていいかしら?私、これから街に帰って会いたい人がいるの。アンタといつまでもダラダラと生産性の無い会話をしてる暇は無いのだけれど」
「あ、いやいや、ちょっと待てって。ちなみにその会いたいヤツって誰だよ?」
「はぁ?なんでそんな事アンタに教えなければなんないのよ?」
「まぁまぁ、そんなにツンケンすんなって」
そう言うと赤髪は、小走りでローゼマリーとの距離を詰めた。
「お前、この集落とか森で育ったから、冒険者の事は疎か街の事もあんまり知らねえんだろう?その会いたいヤツってよ、恐らく、ヴォルフの顔馴染みなんじゃねえか?」
「うん、まぁ、そうね。流石に、このまま冒険者として生きていくには、私は余りにも無知なので、父の知り合いから助言を頂けたらと思って」
「おいおい、そしたら、誰よりも先にまずオレんとこに来るだろうよ、普通は?一応、これでもユニオンのマスターやってんだぜ?お前の親父とはいつも前線で獲物を取り合ってた仲なんだからよ!」
漸く本来の調子を取り戻しつつある赤髪の姿を見て、ローゼマリーは溜息を吐いた。
「あのね?私は平気で子供を蹴っ飛ばす様な下品で粗暴で獣の様な冒険者に教えを乞うつもりは、これっぽちも無いの。私が憧れてるのは、神槍カレン・トワイニングだから。彼女の様になりたし、彼女の様に強く生きてみたい。それで、ここ数日、街で神槍とどうしたら出逢えるか色々と聞き込みをして、酔いどれ小路の酒房ルロイの女将なら会わせてくれるかもしれないと聞いて……ああ、私ったら、どうして馬鹿正直に答えてしまってるんだろう?兎に角、私はもう行くから」
そう言うと、ローゼマリーはきゅっと踵を返して歩き出した。
赤髪をその後をぴたりと張り付く様に着いていく。
「ちょっと、着いて来ないで貰える?それとも、今から私が手にする金貨を狙っている、とか?」
「ああ、いやいや、金はどうでもいいんだわ。まぁ、要するに、向かう先は同じだからよ、折角の縁だし、一緒に行こうぜーってことだ」
「はぁ?なんで私がアンタと……」
ローゼマリーの言動を、赤髪は両手を前に出して制止させた。
しかし、彼女はその制止を振り切りどんどんと歩いてゆく。
赤髪は悪態をつきつつも、すぐにその後えお追い、大声で語りだした。
「あのな?まあ、歩きながらでいいから、聞いてくれよ。お前、酔いどれ小路の酒房ルロイに行くんだろう?オレな、今、そこの二階に住んでんだよ。そんで、その女将ってのはイライザってんだ。神槍もイライザも元ベリアルだからな。確かに、イライザならお前を神槍に引き合わせてくれるかもしれねえ。お前の聞き込みの成果も強ち的外れではねえって事だ。けどよ、神槍に会ったところでなぁんにも変わんねぇし、相手にもされねえと思うぜ?アイツは、基本的に群れるのが嫌いだし、弟子とかもいねえ。たまに高難度な冒険の時だけ、昔の顔馴染みとつるんでるみたいだけどなぁ。けど、そうやってつるむにしても冒険者として相当な経験と知識と実力が必要ってことだ。要するに、今のお前が何等かの形で神槍と会ったところで、だから何?って突き放されるだけだろうな。いや、声すら掛けて貰えないかもしれねえなぁ」
赤髪はローゼマリーの様子を伺いつつ、彼なりに選んだ言葉を投げかけていた。
彼女は、その言葉を聞きつつ何度か足を止めそうになっていたが、止まることも振り向く事も無く、今はもう手放してしまった生家の前にまで辿り着く。
そして、漸く赤髪の方へと顔を向けた。
「ふうう。ああ、もう。分かったわ。取り敢えず、今日は、アンタに酒房ルロイまで案内してもらう事にする。神槍の事や、冒険の事に関してはその道すがら聞かせてもらうわ。けど、取り敢えず今はここで待っていてもらえる?アンタみたいなのをお金の受け渡しの場に連れて行ったら、無駄に警戒されるだけ、だから」
そう言うと、ローゼマリーは右の拳で赤髪の胸をぐっと押し込んでから、家の中へと入って行った。
それを見て、赤髪は不敵な笑みを浮かべる。
彼女に父親譲りの戦士としての素養があれば、何とか口説き落としてバルバトスに加入させるし、素養が無ければ、取り敢えず一回抱いてみるか、と下卑た想いを募らせていたのだ。
彼は冒険者として熱い想いを秘めつつも、死ななければ治らない下品な病気を患っていた。
そこはラートの森と呼ばれ、大昔はドールズ大森林と同等の規模を誇っていたが、アンヌヴンの街が栄え人口が増えると共に、森は縮小の一途を辿っていた。
数十年前までは幻獣やオークが多く棲みついており、年に数回討伐隊が組まれていたが、近年ではそれらの目撃例も減っている。
現在ではその規模こそ縮小しつつあるも、鹿や猪などが多く住む穏やかで豊かな森へと変様していた。
ラートの森の近隣には幾つか集落があり、アンヌヴン近郊の大きな集落は森の名を冠されラート集落と呼ばれていた。
その集落に赤髪のヴィルの姿があった。
エイプリルの娼婦館を出てから、北門経由で貧民街を通り渡り船でイリス川を越え集落まで来たのだ。
太陽は西側へと傾き始めていた。
「――五年振りくらいか。確か、ラートの森の奥の方で珍しい幻獣が目撃されたとかで、それを狩りに来た以来だな、たしか……」
赤髪はそう言って過去を振り返り、舌打ちをして地面にツバを吐いた。
五年前に何か嫌な事があった訳では無く、只単に、その歳月の間に起こってしまった事に対する、悪態と言ったところか。
ラート集落は、頑丈な木製の柵で周囲を覆われていた。
今となっては外敵は殆ど無いが、まだオークが森をうろついていた頃の名残として今でも、集落の人々が定期的に整備している。
柵の外には掘っ建て小屋が幾つも並んでいた。
「ん?ボロい家多いな。前来た時より、確実に増えてるよな……いずれ、この辺りも貧民街みたいになるのか?」
そう言うと赤髪は辺りを見回しつつ、集落の中へと足を踏み入れた。
アンヌヴンの街壁沿いの貧民街と呼ばれる地域も年々広がっているのだ。
闇市や禁止薬物の取引などが横行してる為、年に数回は辺境伯や地方行政区の取り締まりが入ってはいるが一向に治安が良くなる兆しは見えないのが現状だった。
ラート集落の柵の外の掘っ建て小屋に住んでいるのは木こりの見習いや、貧民街にすらも居場所を見つける事が出来なかった弱者ばかりなので、今のところ行政は軽視していると言って過言無いだろう。
「――おい、そこのヤツ、赤髪のヴィルじゃあないかい?」
若い女の声が響いた。凛とした声だった。赤髪はその声の主へと振り返る。
ふと、知った顔だと思ったが、名前も素性も思い出す事は出来なかった。
ただ、いい女だとは感じていた。
「あ?えーっと、オマエ、誰だっけ?そのナリからすると、ドワーフか?いや、ドワーフの女にしちゃぁちいとばかし背が低いか」
目を細め、女の全身を舐める様に見ていた。
癖の強い真っ黒な髪を無理やり一つに束ねている。凛々しい眉毛と意思の強い瞳が印象的だった。
そして、明らかに人間では無いが抱き応えの有りそうな身体だと、赤髪の口許はいやらしく緩んでしまっている。
「あら、残念ね、覚えて無いかしら?ローゼマリーよ。ヴォルフ・ユルゲンの娘。五年前に会ったじゃない。と、言ってもあの頃は見向きもされなかったけれどね」
彼女からそう告げられて、赤髪は漸く途切れていた記憶が繋がる。
「ん?あ!おー!おー!そう言えば、ガキがいたよなぁ。ヴォルフを冒険に誘ったら、ガキに腕噛み付かれたから蹴っ飛ばしてやったんだよ。そしたらピーピー泣きやがって……アレお前かよ。あん時、オレはヴォルフに強烈な拳骨喰らったんだ。超痛ぇやつな!」
「そんなの、子供だった私を本気で蹴っ飛ばしたアンタが悪いんでしょう?それに、あの頃は母が亡くなったばかりで、アンタたちみたいな冒険者に父を取られたくないって思いが強かったのよ」
ローゼマリーはそう言うと、赤髪へと歩み寄り、右手を差し出した。
それを見てヴィルは、いつもの不敵な笑みを口許に湛えつつその手を握り締めた。かなり力を込めて。
普通の女の手なら握り潰されていただろうが、ローゼマリーは平然と涼し気な表情で握り返していた。
「ちっ、親父譲りの馬鹿力だな!お前の親父は、おれの知る限りじゃ三本の指に入る戦士だから、冒険があるなら誘うに決まってんだろうが?こんな集落で木こりとか……同じ斧振るうならユニオンの最前衛でバケモン相手に振りやがれってんだ」
「そんなのもう十年以上も昔の話だろう?今更、また父を引っ張り出して冒険に連れてこうってのかい?」
「へへへ、だったらどうする?またオレの腕に噛み付くかよ?」
赤髪は更に力を込めて、ローゼマリーの手を握り締めた。
腕が小刻みに震えている。顔には出して無いが朝、レオンと腕相撲した時よりも本気で力を入れているがローゼマリーは依然涼し気な表情で握り返してくる。
「あははは、そんな汚らわしい腕に誰が噛み付くものか。それに……連れて行きたければどうぞご勝手に」
「いいんだな?今度は本気で連れてくぜ?」
「うふふふ、そう、本気なのか。じゃぁ、案内してあげるよ」
「けっ、案内なんていらねえってんだよ!こんな小せぇ集落で迷わねえっての」
「あら、そう?でも、アンタが向かおうとしてるところに、もう父は住んで無いわよ?」
そういうと、彼女はどこか寂し気な笑みを浮かべていた。
「あぁん?なんだ、ヴォルフのヤロー家越したのか?って、まさかアンヌヴンの街に住んでんのか?だとしたら、イリス川まで越えて飛んだ無駄足……ん?いや、街に住むって柄じゃねえからなぁ。って、おい、まさかヴォルフのヤロー……」
「父は、先月他界したの。家や家財道具は全部売り払ったわ。それが父の遺言だったから。今日、私は残りの金貨を引き取りに来ただけ。お墓は森の奥の、大きな杉の木の下に。だから、父を連れて行きたいなら、そこまで案内してあげる」
ローゼマリーの話途中で、赤髪は手と腕から力を抜いた。
それを感じ彼女も脱力していた。
「まじか。まじかよ……。ヴォルフ、死にやがったのか。なんだよ、アンナといい、ヴォルフといい、昔の仲間がどんどん死んじまいやがる。くそっ、なんでだよ、くそっ……」
「アンタとか白銀とかベリアルの話をしてる時の父はいつも楽しそうだった。お酒を飲んで酔っ払っている時は、いつも大抵その頃の冒険譚を語ってくれてた。で、どうする?お墓まで案内しようか?」
目に見えて気を落としている赤髪を覗き込む様に、彼女はそう言った。
身長はヴィルよりも少し低い。普通のドワーフなら女でも人間の男より背が高いのだが。
「あ?馬鹿言うんじゃねえ。冒険者は墓参りはしちゃいけねえんだ。あの世に魂が引っ張られっからな。だから、墓参りには行かねえ」
「へえ、そんな決まり事があるんだ?じゃぁ、私もこれからはお墓参り行っちゃダメって事だね。では、私はそろそろ行くから……さようなら、赤髪のヴィル」
ローゼマリーは、そう言うときびきびとした足取りで歩き出した。
彼女の言葉を聞いた赤髪は、ばっと身を翻す。
「ん?お、おい、ちょっと待て。お前、もしかして、冒険者になったのか?」
その声は少し上擦っている様に響いた。
ローゼマリーはピタリと足を止めて、振り返る。軽快な身のこなしだった。
「ええ、ついさっき、冒険者ギルドで登録して来たわ」
「ついさっきって、まじかよ。そんで、もうユニオンは決めてんのか?」
「ユニオンはまだ決めて無いよ。私、冒険者の知り合いいないし、ユニオンの評判とかもよく分からないから」と、彼女はまた平然とした顔でそう言った。
無知ゆえの自信なのか、生来胆が据わっているのか。
そして、また赤髪を置いて歩き始める。
きびきびとした足取り。迷い無く己の道を歩いて行く、この感じ。
その凛々しい後ろ姿を見て、赤髪は「感じってゆーか、雰囲気ってゆーか、何となく、若い頃の神槍に似てるんだよな」と呟く。
それから大きな声で彼女の名を呼んだ。
「おーい、ローゼマリー?」
彼女はまたぴたりと足を止めて、赤髪へと振り返った。
「何?まだ用件があるの?」
十歩ほどの距離。彼女は腕を組み、赤髪の様子を伺っていた。
「いや、まぁ、用件ってゆーか、お前よう?住むトコとかあんのか?」
「それは、まぁ、一応。そう広くは無いけれど、街壁の中に部屋を借りているわ」
「そうか。まぁヴォルフの家とか家財道具とか一切合切売り払ったなら、それなりに金は持ってるってことか……」
嫌われているのは重々承知していた。しかし、彼はそれで引き下がる様な軟な男ではない。冒険だろうが家だろうが、なんでもいいから兎に角、会話を弾ませる切っ掛けを探っていた。
「ねえ?もう行っていいかしら?私、これから街に帰って会いたい人がいるの。アンタといつまでもダラダラと生産性の無い会話をしてる暇は無いのだけれど」
「あ、いやいや、ちょっと待てって。ちなみにその会いたいヤツって誰だよ?」
「はぁ?なんでそんな事アンタに教えなければなんないのよ?」
「まぁまぁ、そんなにツンケンすんなって」
そう言うと赤髪は、小走りでローゼマリーとの距離を詰めた。
「お前、この集落とか森で育ったから、冒険者の事は疎か街の事もあんまり知らねえんだろう?その会いたいヤツってよ、恐らく、ヴォルフの顔馴染みなんじゃねえか?」
「うん、まぁ、そうね。流石に、このまま冒険者として生きていくには、私は余りにも無知なので、父の知り合いから助言を頂けたらと思って」
「おいおい、そしたら、誰よりも先にまずオレんとこに来るだろうよ、普通は?一応、これでもユニオンのマスターやってんだぜ?お前の親父とはいつも前線で獲物を取り合ってた仲なんだからよ!」
漸く本来の調子を取り戻しつつある赤髪の姿を見て、ローゼマリーは溜息を吐いた。
「あのね?私は平気で子供を蹴っ飛ばす様な下品で粗暴で獣の様な冒険者に教えを乞うつもりは、これっぽちも無いの。私が憧れてるのは、神槍カレン・トワイニングだから。彼女の様になりたし、彼女の様に強く生きてみたい。それで、ここ数日、街で神槍とどうしたら出逢えるか色々と聞き込みをして、酔いどれ小路の酒房ルロイの女将なら会わせてくれるかもしれないと聞いて……ああ、私ったら、どうして馬鹿正直に答えてしまってるんだろう?兎に角、私はもう行くから」
そう言うと、ローゼマリーはきゅっと踵を返して歩き出した。
赤髪をその後をぴたりと張り付く様に着いていく。
「ちょっと、着いて来ないで貰える?それとも、今から私が手にする金貨を狙っている、とか?」
「ああ、いやいや、金はどうでもいいんだわ。まぁ、要するに、向かう先は同じだからよ、折角の縁だし、一緒に行こうぜーってことだ」
「はぁ?なんで私がアンタと……」
ローゼマリーの言動を、赤髪は両手を前に出して制止させた。
しかし、彼女はその制止を振り切りどんどんと歩いてゆく。
赤髪は悪態をつきつつも、すぐにその後えお追い、大声で語りだした。
「あのな?まあ、歩きながらでいいから、聞いてくれよ。お前、酔いどれ小路の酒房ルロイに行くんだろう?オレな、今、そこの二階に住んでんだよ。そんで、その女将ってのはイライザってんだ。神槍もイライザも元ベリアルだからな。確かに、イライザならお前を神槍に引き合わせてくれるかもしれねえ。お前の聞き込みの成果も強ち的外れではねえって事だ。けどよ、神槍に会ったところでなぁんにも変わんねぇし、相手にもされねえと思うぜ?アイツは、基本的に群れるのが嫌いだし、弟子とかもいねえ。たまに高難度な冒険の時だけ、昔の顔馴染みとつるんでるみたいだけどなぁ。けど、そうやってつるむにしても冒険者として相当な経験と知識と実力が必要ってことだ。要するに、今のお前が何等かの形で神槍と会ったところで、だから何?って突き放されるだけだろうな。いや、声すら掛けて貰えないかもしれねえなぁ」
赤髪はローゼマリーの様子を伺いつつ、彼なりに選んだ言葉を投げかけていた。
彼女は、その言葉を聞きつつ何度か足を止めそうになっていたが、止まることも振り向く事も無く、今はもう手放してしまった生家の前にまで辿り着く。
そして、漸く赤髪の方へと顔を向けた。
「ふうう。ああ、もう。分かったわ。取り敢えず、今日は、アンタに酒房ルロイまで案内してもらう事にする。神槍の事や、冒険の事に関してはその道すがら聞かせてもらうわ。けど、取り敢えず今はここで待っていてもらえる?アンタみたいなのをお金の受け渡しの場に連れて行ったら、無駄に警戒されるだけ、だから」
そう言うと、ローゼマリーは右の拳で赤髪の胸をぐっと押し込んでから、家の中へと入って行った。
それを見て、赤髪は不敵な笑みを浮かべる。
彼女に父親譲りの戦士としての素養があれば、何とか口説き落としてバルバトスに加入させるし、素養が無ければ、取り敢えず一回抱いてみるか、と下卑た想いを募らせていたのだ。
彼は冒険者として熱い想いを秘めつつも、死ななければ治らない下品な病気を患っていた。