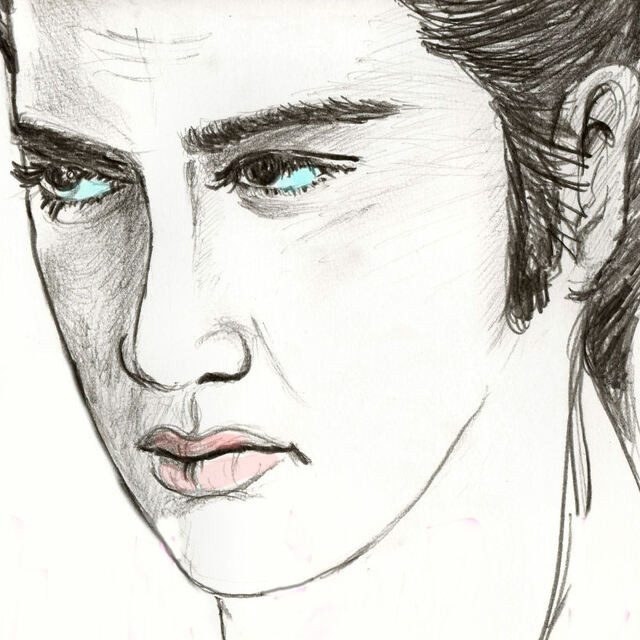第22話 揺れ動く母の気持ち
文字数 1,472文字
それが現場の厳しい現実だった。愛菜は歯を食いしばってその屈辱に耐えていた。いつ辞めようかと、そのことばかり思いながら。
或る日、愛菜は前の上司の課長に聞いてみたことがある。しかし、いつも埒 の明かない同じような返事だった。
「あの、課長、何で私が倉庫課に行かなければいけなかったのでしょうか?」
普段は大人しい愛菜が珍しく課長の中村に詰め寄っていた。痩せた神経質そうな中村は、しどろもどろになっていた。
「いや、私にもわからんよ。人事課にでも聞いてみたらどうかね」
愛菜にとって職場の配置転換は苦痛だった。何の対応もしてくれない会社に嫌気がさし、数ヶ月して愛菜は会社を辞めた。
それから、始めは慣れないアルバイトにも少し慣れてきたときに、真一郎から愛菜の携帯電話にかかってきたのである。しかもこの携帯電話の番号は、ある特定の人間以外には教えていないはずなのに。
「あの、この電話番号はどこでお知りになったのですか?」
「いや、君の家に電話したら、お母さんが出て、事情を話したら教えてくれたんですよ」
「はあ、母がですか。わかりました。男性には誰も教えていませんので、失礼しました」
「いえいえ、この間の件では貴女に辛い思いをさせてしまったようで、申し訳ありません。それで、いちどお会いして、きちんとした格好でお詫びしたいのです。お時間をいただけませんか?」
愛菜は真一郎の真摯な言葉に胸を打たれた。そして今まで胸の中につかえていた重荷が軽くなったような気がした。
「はい。お気持ちはありがたいのですが、でももうすんだことですから」
「そうですか。わかりました。もう新しいお仕事は見つかりましたか?」
「いえ。なんとかアルバイトをして……」
「それは大変ですね。今は不況ですからなかなか良い仕事先も見つからないでしょう。もし貴女さえ良ければ元の職場にと思いまして」
「ありがとうございます。でもいまさら」
「そうですか。もし私の力が必要になったときにはいつでも言って下さい。電話を待っていますよ」
「はい。わざわざありがとうございます。その時にはこの電話番号でよろしいのですか?」
「ええ。これは自分用の携帯電話ですから。もし繋がらないときには留守電でも入れておいて下さい」
「わかりました。もしその時には……」
「了解しました。では」
愛菜が聞いたその声はハキハキとして、男らしくて気持ちがよかった。彼女は心が救われたような気がして嬉しかった。そしてあの精悍でしかも優しい顔の真一郎の顔を思い浮かべていた。愛菜は真一郎には、あのように言ったものの、心の中では迷っていた。
きちんとした会計事務の専門学校を出て資格も持っている愛菜にとっては、今のアルバイトは不満だった。愛菜は家に帰ってから母親に聞いてみた。
「お母さん。今日前の会社の事業部長さんから電話があったでしょう?」
「えっ。ああ、あったわよ」
母の顔に少し動揺した気配があったのだが、愛菜には気が付かなかった。
「それで私の電話番号を教えたのね?」
「そうよ。是非ということだからね。教えてはいけなかったかしら?」
「ううん。そんなことないけれど」
「じゃあ、よかったのね。それで電話が愛菜にかかってきたの?」
「うん。お詫びがしたいんだって」
「そう。それでどうするの?」
「うーん。まだ決めていないわ」
「そう」
母はそれきり何も言わなかったが、どこか気にしているようだった。そのとき愛菜は、母と浦島真一郎との間で、かつて思いがけないことがあったなどとは想像もしていなかった。
或る日、愛菜は前の上司の課長に聞いてみたことがある。しかし、いつも
「あの、課長、何で私が倉庫課に行かなければいけなかったのでしょうか?」
普段は大人しい愛菜が珍しく課長の中村に詰め寄っていた。痩せた神経質そうな中村は、しどろもどろになっていた。
「いや、私にもわからんよ。人事課にでも聞いてみたらどうかね」
愛菜にとって職場の配置転換は苦痛だった。何の対応もしてくれない会社に嫌気がさし、数ヶ月して愛菜は会社を辞めた。
それから、始めは慣れないアルバイトにも少し慣れてきたときに、真一郎から愛菜の携帯電話にかかってきたのである。しかもこの携帯電話の番号は、ある特定の人間以外には教えていないはずなのに。
「あの、この電話番号はどこでお知りになったのですか?」
「いや、君の家に電話したら、お母さんが出て、事情を話したら教えてくれたんですよ」
「はあ、母がですか。わかりました。男性には誰も教えていませんので、失礼しました」
「いえいえ、この間の件では貴女に辛い思いをさせてしまったようで、申し訳ありません。それで、いちどお会いして、きちんとした格好でお詫びしたいのです。お時間をいただけませんか?」
愛菜は真一郎の真摯な言葉に胸を打たれた。そして今まで胸の中につかえていた重荷が軽くなったような気がした。
「はい。お気持ちはありがたいのですが、でももうすんだことですから」
「そうですか。わかりました。もう新しいお仕事は見つかりましたか?」
「いえ。なんとかアルバイトをして……」
「それは大変ですね。今は不況ですからなかなか良い仕事先も見つからないでしょう。もし貴女さえ良ければ元の職場にと思いまして」
「ありがとうございます。でもいまさら」
「そうですか。もし私の力が必要になったときにはいつでも言って下さい。電話を待っていますよ」
「はい。わざわざありがとうございます。その時にはこの電話番号でよろしいのですか?」
「ええ。これは自分用の携帯電話ですから。もし繋がらないときには留守電でも入れておいて下さい」
「わかりました。もしその時には……」
「了解しました。では」
愛菜が聞いたその声はハキハキとして、男らしくて気持ちがよかった。彼女は心が救われたような気がして嬉しかった。そしてあの精悍でしかも優しい顔の真一郎の顔を思い浮かべていた。愛菜は真一郎には、あのように言ったものの、心の中では迷っていた。
きちんとした会計事務の専門学校を出て資格も持っている愛菜にとっては、今のアルバイトは不満だった。愛菜は家に帰ってから母親に聞いてみた。
「お母さん。今日前の会社の事業部長さんから電話があったでしょう?」
「えっ。ああ、あったわよ」
母の顔に少し動揺した気配があったのだが、愛菜には気が付かなかった。
「それで私の電話番号を教えたのね?」
「そうよ。是非ということだからね。教えてはいけなかったかしら?」
「ううん。そんなことないけれど」
「じゃあ、よかったのね。それで電話が愛菜にかかってきたの?」
「うん。お詫びがしたいんだって」
「そう。それでどうするの?」
「うーん。まだ決めていないわ」
「そう」
母はそれきり何も言わなかったが、どこか気にしているようだった。そのとき愛菜は、母と浦島真一郎との間で、かつて思いがけないことがあったなどとは想像もしていなかった。