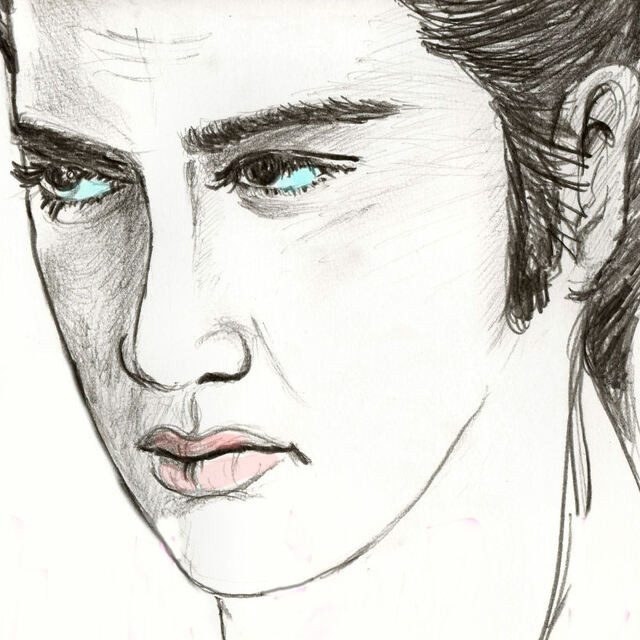第62話 つらい真実を告げて
文字数 2,285文字
真一郎は昼間、駅前の喫茶店に珍しく愛菜に呼ばれてやってきた。
彼は忙しい中を時間を割いてやってきたのだ。
「すみません。真一郎さん」
「いや、大丈夫だよ。この間、以来だね。沙也香と一緒の時で……」
「はい。あれから沙也香さんのマンションから家に帰りました」
「そう」
相変わらず真一郎は精悍な顔をしてダンディーである。この人が自分の父親だと思うと不思議な気がした。もしあのことがなければ、若い自分は彼の女になるはずだった。
好奇心が旺盛な愛菜は、そういう関係も悪くないな、と思っていた。
だから彼の愛人になることを決めたのである。親子ほど歳が離れてはいたが……実際はそうなったのだが。
しかし、もうそれはできない。目の前の彼は、まだそれを知らない。自分の娘をすでに愛人と思っているのだろう。愛菜は彼がそんな目で自分を見ているのがよくわかる。
胸を見たり、脚を見たりしている目は、まさに男だった。今までの愛菜なら、むしろそれを期待していたかもしれない。しかし、今から彼は、事実を知ることになる。彼は驚くだろう。
そう思うと不思議な気がした。
もう愛菜の中では、真一郎はセックスの対象者にはなっていない。
真実を知った以上、自分と血のつながった父親という事実は変えられない。そして、今日を最後にして、彼に事実を告げて合わないつもりでいる。その方がお互いのためになると思うからだ。ただ、小さいころに亡くなったと思っていた父に会えたこと。本当の父に会えたのは嬉しかった。
その父とこういう関係でなく、ちゃんとして対面出来たのなら別れることもなかったに違いない。そう思うと悲しくなる。
でも、素敵な父で良かった。優しそうで、女性にもてそうで、素敵な父……。
そんな夢を与えてくれただけでも、幸せと思わなければいけない。
我が子を、本当の娘として慈しみ、愛されはしなかった。自分をセックスの対象として見ていた父。それも運命の悪戯……それも今日で終わり。
親子の対面をしたその日が、別れの日だという悲しい皮肉。彼には彼の家族もいる。
それも運命。
愛菜は自分に心の中で言い聞かせた。
(最後の会話をして、それでさよならを……)
「真一郎さんは血の繋がりをどう思いますか?」
「いきなりだね。そうだね、つまり血の繋がりとは、親や兄弟、姉妹、親戚などで、切っても切れない大切なものだと思っている」
「では、その血の繋がった関係で、もし許されない関係になった場合に、その人達をどう思いますか?」
「うむ、難しい問題だな。それは肉体関係とかを言っているのかな?」
「そうですね」
「例えば母親と息子、父親と娘或いは兄妹等の関係でセックスをした場合には、倫理的な問題があるし、好ましい関係では無いと思う。しかし世の中にはそれを承知の上での関係を維持している人もいるとは聞いているので、一概には否定はできない。法律上ではそれは禁止していないしね」
「そうですよね。例えばもし真一郎さんが、当事者だとした場合にはどうですか?」
「えっ、私が?」
「はい」
「まあ、もし自分の場合には、これは仮定の話しだけど、してはいけないと思うし、そう言う関係にはならないと思う」
「そうですか」
しばらく、愛菜は考えていた。その日の愛菜はいつもと違っていた。まるで別人のようである。なんで彼女がそのような話題を振ってきたのかわからなかったが、真一郎は何か不吉な予感を感じていた。
彼女の母親と肉体関係を持っていたが、その時点では愛菜を自分の娘だとは夢にも思っていない。
「私、母から聞きました」
「なにをかな?」
「驚かないでくださいね」
「おやおや。怖いな。どんな話だろうか?」
「真一郎さんとわたしはそう言う関係だったのです。母から聞きました」
「えっ?」
真一郎は始め、愛菜が言っている意味がよくわからなかった。
「私も初めは信じられませんでした。お母さんが真一郎さんと付き合っていた特に、お母さんのお腹の中に赤ちゃんがいたそうです」
「そんな……」
「つまり、お母さんは妊娠していたのです。真一郎さんと付き合っていたとき……」
「……」
「お母さんが真一郎さんから別れた原因も聞きました」
「わたしもそれをずっと知りたいと思っていたんだ、教えてくれないか、それを、前から気になっていたんだ」
真一郎は体を前に乗り出して、じっと愛菜を見つめた。今迄、愛人として接してきた少女が、自分の娘だということを……彼はまだそれを知らない。
「実は、浦島慶次という人から言われたそうです。母と別れてくれって」
「ほ、本当かい」
「はい。母は泣く泣く自分から身を退いたのです。お腹の赤ちゃんを宿しながら、その時の赤ちゃんがわたしです」
「えっ? で、では、君は私の娘!?」
「はい」
「真一郎さんは、わたしのお父さんです」
淡々と話しながらも、愛菜は目に涙をいっぱい溜めて、それがこぼれそうになっていた。真一郎は繁々として、今迄に存在すら思ったことのない自分の娘を見つめた。
(そんな我が娘を、自分は性の対象として抱いていたのか……)
「だから、だからもうあなたとは会いません。これ以上、母を苦しめるだけですから」
「ま、待ってくれ!」
「沙也香さんも知っています。このことは、ではさようなら」
愛菜はそう言って椅子から立ち上がり、涙の顔で店から逃げるようにして出て行った。真一郎は彼女が去っていった後ろ姿をじっと見つめていた。あまりの急な展開に、珍しく彼は頭が混乱していた。
「あの娘が、自分の娘……」
そう言えば、顔も自分に似ていると前から思っていたが、その理由がようやく理解できた。
彼は忙しい中を時間を割いてやってきたのだ。
「すみません。真一郎さん」
「いや、大丈夫だよ。この間、以来だね。沙也香と一緒の時で……」
「はい。あれから沙也香さんのマンションから家に帰りました」
「そう」
相変わらず真一郎は精悍な顔をしてダンディーである。この人が自分の父親だと思うと不思議な気がした。もしあのことがなければ、若い自分は彼の女になるはずだった。
好奇心が旺盛な愛菜は、そういう関係も悪くないな、と思っていた。
だから彼の愛人になることを決めたのである。親子ほど歳が離れてはいたが……実際はそうなったのだが。
しかし、もうそれはできない。目の前の彼は、まだそれを知らない。自分の娘をすでに愛人と思っているのだろう。愛菜は彼がそんな目で自分を見ているのがよくわかる。
胸を見たり、脚を見たりしている目は、まさに男だった。今までの愛菜なら、むしろそれを期待していたかもしれない。しかし、今から彼は、事実を知ることになる。彼は驚くだろう。
そう思うと不思議な気がした。
もう愛菜の中では、真一郎はセックスの対象者にはなっていない。
真実を知った以上、自分と血のつながった父親という事実は変えられない。そして、今日を最後にして、彼に事実を告げて合わないつもりでいる。その方がお互いのためになると思うからだ。ただ、小さいころに亡くなったと思っていた父に会えたこと。本当の父に会えたのは嬉しかった。
その父とこういう関係でなく、ちゃんとして対面出来たのなら別れることもなかったに違いない。そう思うと悲しくなる。
でも、素敵な父で良かった。優しそうで、女性にもてそうで、素敵な父……。
そんな夢を与えてくれただけでも、幸せと思わなければいけない。
我が子を、本当の娘として慈しみ、愛されはしなかった。自分をセックスの対象として見ていた父。それも運命の悪戯……それも今日で終わり。
親子の対面をしたその日が、別れの日だという悲しい皮肉。彼には彼の家族もいる。
それも運命。
愛菜は自分に心の中で言い聞かせた。
(最後の会話をして、それでさよならを……)
「真一郎さんは血の繋がりをどう思いますか?」
「いきなりだね。そうだね、つまり血の繋がりとは、親や兄弟、姉妹、親戚などで、切っても切れない大切なものだと思っている」
「では、その血の繋がった関係で、もし許されない関係になった場合に、その人達をどう思いますか?」
「うむ、難しい問題だな。それは肉体関係とかを言っているのかな?」
「そうですね」
「例えば母親と息子、父親と娘或いは兄妹等の関係でセックスをした場合には、倫理的な問題があるし、好ましい関係では無いと思う。しかし世の中にはそれを承知の上での関係を維持している人もいるとは聞いているので、一概には否定はできない。法律上ではそれは禁止していないしね」
「そうですよね。例えばもし真一郎さんが、当事者だとした場合にはどうですか?」
「えっ、私が?」
「はい」
「まあ、もし自分の場合には、これは仮定の話しだけど、してはいけないと思うし、そう言う関係にはならないと思う」
「そうですか」
しばらく、愛菜は考えていた。その日の愛菜はいつもと違っていた。まるで別人のようである。なんで彼女がそのような話題を振ってきたのかわからなかったが、真一郎は何か不吉な予感を感じていた。
彼女の母親と肉体関係を持っていたが、その時点では愛菜を自分の娘だとは夢にも思っていない。
「私、母から聞きました」
「なにをかな?」
「驚かないでくださいね」
「おやおや。怖いな。どんな話だろうか?」
「真一郎さんとわたしはそう言う関係だったのです。母から聞きました」
「えっ?」
真一郎は始め、愛菜が言っている意味がよくわからなかった。
「私も初めは信じられませんでした。お母さんが真一郎さんと付き合っていた特に、お母さんのお腹の中に赤ちゃんがいたそうです」
「そんな……」
「つまり、お母さんは妊娠していたのです。真一郎さんと付き合っていたとき……」
「……」
「お母さんが真一郎さんから別れた原因も聞きました」
「わたしもそれをずっと知りたいと思っていたんだ、教えてくれないか、それを、前から気になっていたんだ」
真一郎は体を前に乗り出して、じっと愛菜を見つめた。今迄、愛人として接してきた少女が、自分の娘だということを……彼はまだそれを知らない。
「実は、浦島慶次という人から言われたそうです。母と別れてくれって」
「ほ、本当かい」
「はい。母は泣く泣く自分から身を退いたのです。お腹の赤ちゃんを宿しながら、その時の赤ちゃんがわたしです」
「えっ? で、では、君は私の娘!?」
「はい」
「真一郎さんは、わたしのお父さんです」
淡々と話しながらも、愛菜は目に涙をいっぱい溜めて、それがこぼれそうになっていた。真一郎は繁々として、今迄に存在すら思ったことのない自分の娘を見つめた。
(そんな我が娘を、自分は性の対象として抱いていたのか……)
「だから、だからもうあなたとは会いません。これ以上、母を苦しめるだけですから」
「ま、待ってくれ!」
「沙也香さんも知っています。このことは、ではさようなら」
愛菜はそう言って椅子から立ち上がり、涙の顔で店から逃げるようにして出て行った。真一郎は彼女が去っていった後ろ姿をじっと見つめていた。あまりの急な展開に、珍しく彼は頭が混乱していた。
「あの娘が、自分の娘……」
そう言えば、顔も自分に似ていると前から思っていたが、その理由がようやく理解できた。