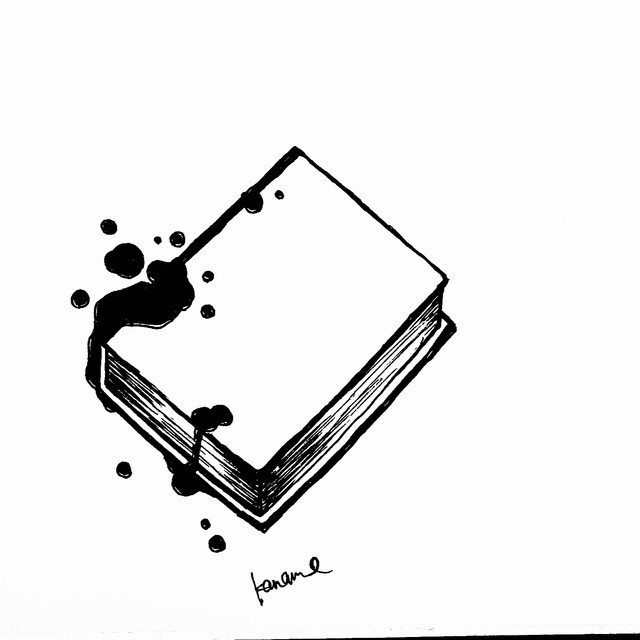第七十五話 過去と傷跡
文字数 2,665文字
──…………。
立ち上がることも、顔を上げることも出来ない。
呼吸は浅く乱れ、額や首に汗が滲む。
──……こわい……。
力なく項垂れ、座り込んだまま動けなくなった恭介の脳裏には、記憶の片隅にこびり付いたまま離れない幼少時代に恐怖対象となった母親が蘇っていた。
過去と重なる母親の姿。
思い出したくない記憶が掘り起こされたことに耐え切れず、強く瞼を伏せた。
恭介の両親は、母親──愛璃が大学一年の頃に合コンで知り合った、当時二十歳だった父親──
愛璃も勢いに任せ、自ら望んで身体を重ねた。
その三ヶ月後、妊娠が発覚。
子を孕んだから仕方ないと、酔いが覚めればさして好きでもない相手同士での結婚、書類上夫婦となった。
そんな二人が、都合良く好き合える筈がない。
恭介が産まれたことで周りにチヤホヤされるのは嬉しかったものの、育てるとなれば自由はまるでなくなる。
その頃から既にファッションデザイナーとして花を咲かせたかった愛璃にとって、片時も目を離せない恭介が邪魔な存在になるまでに時間は掛からなかった。
授乳期間中は、泣きはするものの抱っこやおんぶをすれば大人しい恭介に手は掛からず、周りからのチヤホヤや気遣いもあり気分は良かった。
しかし、恭介が一人遊びをし始める二歳頃から、成長と共に駄々を捏ねたり我儘な態度をとるようになり、次第に邪魔な存在となっていった。
『お前は私の言うことを聞いていれば良いのよ!』
幼い頃、母親が口癖のように恭介に向かって怒鳴っていた言葉だった。
『嫌だ』と首を横に振ろうものなら、頬を引っ叩かれた。
それ以上の虐待はなかったが、幼い恭介にとって、母の怒鳴り声と叩かれる痛みは恐怖でしかなかった。
怒鳴られたくない。
叩かれたくない。
だから、黙って言うことを聞くようになった。
反論もせず、『何故そうしなければならないのか』という理由も聞かなくなった。
父親は、いつもパソコンの画面に向かったまま、助けてくれることはなかった。
食事を与えられ、風呂に入れられ、布団を用意され、生かされる。
恭介はただ母親の言うことに従っていた。
抱き締めて貰ったことも、頭を撫でて貰ったこともない。
そんな恭介が初めて結羽と出会ったのは、保育園へ通うようになってからのことだった。
手が空いたと勘違いした母親がデザイナーの仕事をし始めたことで、朝早くから夜遅くまで帰ってこないことが増え、恭介は結羽と共に保育園へ向かい、結羽と共に園原家に帰ることが日常になった。
そして、夜になって父親が迎えに来ていた。
いつも俯いていた恭介は、父親の顔を殆ど覚えていない。
やがて、恭介が小学校へ通うようになると、母親はデザイナーとしての地位を確立し、収入が増えていった。
そのお陰で裕福な家庭として周りから見られるようになり、恭介の身に付ける衣服も次第に値の張るものへ変わった。
しかし、それは恭介のためではない。
『素敵な家庭』を演じるために、母親が利用したに過ぎなかった。
恭介はそれからも母親に言われるがまま、従って生きてきた。
──『ちゃんと言うこと聞いたら、僕のこと、見てくれるかな?』
決して口には出せないが、いつもいつも、心の中にそんな希望を抱いていた。
何度その希望が打ちのめされても、例え褒めて貰えなくても、いつかは母親の目に自分を映して貰えるように。
──『ちゃんと、言うこと聞かなきゃ』
しかし、そんな希望は高校生の頃に消えさった。
高校一年の夏休み直前、学校から部活を終えて帰宅した恭介が目にしたのは、自分の荷物だけが纏められただけの空っぽな自宅だった。
物が無いだけではない。
両親の気配すら感じられなくなっていた。
纏められた荷物の上に、一枚のメモ。
そこには、『渡米したこと』『アパートを借りたこと』『アパートの住所』『毎月通帳にお金を振り込むこと』が記載されていた。
恭介はその日を境にして、突然過ぎる一人暮らしを余儀なくされたのだった。
あまりに唐突な出来事に、何も考えられなかった。
自宅だった家からアパートまで歩いた記憶もないくらいに茫然自失となっていたことだけは覚えている。
──『……捨てられたのか、俺……』
虚しい気持ちにはなったが、不思議と悲しみは感じなかった。
どちらかと言えば、解放された感覚に近いかも知れない。
『親の顔色を伺うことなく自分の意思で生きていける』という気持ちが大きかった。
そして、そんな恭介が一人暮らしをして居られたのも、結羽とその家族の支えがあったから。
結羽は毎朝恭介を迎えに行って一緒に登校し、毎晩のように電話をしては恭介の様子に変わりがないか確かめ、頻繁にアパートへ出入りするようになった。
そして、休みの日には恭介を自宅に招いて家族と共に過ごさせるようにしていた。
『恭介が寂しくないように』と想いながら。
普段から決して弱音を口にしない恭介だが、結羽には何となく伝わり始めていた。
だから、何も言わず手を差し伸べる。
それまで共に過ごした時間が長くて深く、結羽にとって恭介という存在がとても大切で愛しいものになっていった。
恭介が結羽に支えられていただけではない。
高校に入る頃にはめっきり捻くれ者となっていた結羽もまた、全てを受け止めてくれる恭介に支えられていた。
互いが支え合い、必要とし、一緒に居ることで不思議と安心する。
何時しか、恭介と結羽は深い絆で結ばれていた。
初めての感覚に戸惑いながらも、二人は幸せを掴もうとしていた。
……否、既に掴んでいたはずだった。
恭介は、伏せていた瞼をゆっくりと開く。
抱き締めるように肩を支えてくれる優しい手のひらが、とても暖かい。
少し視線を動かせば、共に幸せを掴んだ相手が母親を睨み付けていた。
──……結羽。
静かに深呼吸をして、恐る恐る視線を上げる。
「……っ」
冷たく睨む視線は、幼少の頃を思い出させるばかりで恐怖に襲われた。
それでも、立ち向かわなければならない。
──……結羽を置いて、逃げるな。
自分は、一人ではない。
一緒なら大丈夫。
改めて気持ちを伝えようと、顔を上げた。
しかし──。
「……お前が産まれてこなければ楽だったのに」
「! …………」
怒鳴られたわけでもなく、叩かれたわけでもない。
ただ、溜め息混じりに洩れた無感情な声色。
それだけなのに。
まるで存在自体を否定するその言葉は、恭介の心を深く抉るには十分過ぎるほどに残酷だった。