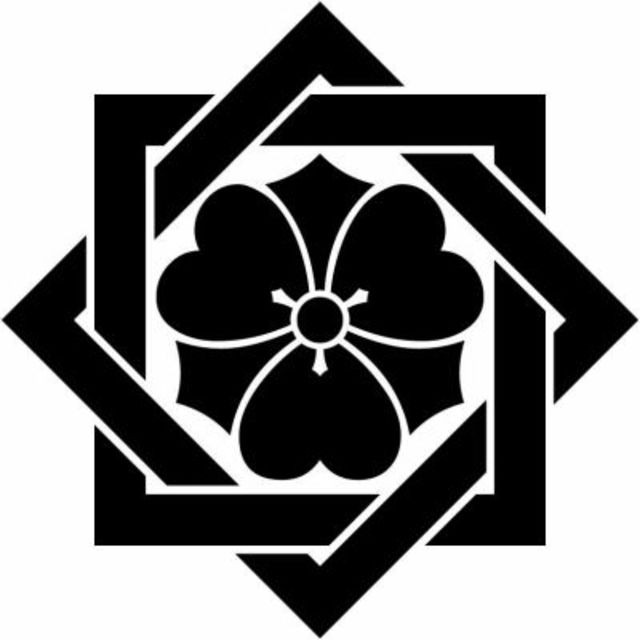第49話 憎悪をねじ伏せて
文字数 19,414文字
遥かな過去からナナクサの魂が闘技場に戻った丁度そのとき、二人の人間と自動機械 の制御棒は、天蓋に空いた大きな亀裂からの落下をまだ続けていた。吸血の衝撃で過去へ魂を弾き飛ばされていたナナクサが、自分が、かつて何者だったのか。また、どんなことを経験したのかを追体験して、また目覚めるまで、この氷河期の世界では僅か半秒の時間しか要しなかったからだ。しかし、その僅か半秒の中には彼女が生まれ変わる前の残酷さに彩られた苛酷な半生が凝縮していた。そこには何も成しえず、何者をも救いえなかった空虚さと痛み。そして裏切られたことに対する落胆と相手への激しい憎しみしか存在しなかった。それはナナクサとして目覚めた彼女に耐え難い苛立ちと混乱を与え、それは、やがて湧き上がる憤怒の土壌となるべく心の中を満たしていった。
闘技場に棒立ちのままで意識を回復したナナクサは事切れた第一指導者の腕を口からもぎ離すと、頭上に落下してくるものに対して再生した左腕を無意識に指し伸ばした。すると目に見えない力が落下する二人の人間、エイブとレン補佐長の身体を透明の網となって包み込んだ。しかし小さな制御棒だけは力場の見えない網目からすり抜けて固い石造りの床面に当たって砕け散った。その乾いた音に、ナナクサは我に返るやいなや、いま自身が置かれている状況を明確に理解した。
ナナクサは空中で掴み取ったものにちらりと目をやると、にわかに顔を歪ませた。
「汚らわしい……」
誰に言うともなく、そう吐き捨て、手についた汚物を払うように左手をひと振りすると、二人の人間の身体を遠くに投げ出した。投げ出されたレン補佐長の身体は戦っている戦士と吸血鬼軍団 の間に投げ出され、エイブは闘技場に駆けつけたジョウシの両腕に床面すれすれで受け止められた。
ジョウシは一目でエイブの傷が致命傷であると見てとったが、迫り来る吸血鬼軍団 の猛攻から彼を捨て置くことも出来ず、拾った長槍を果敢に振るって敵が近づかないようにするのが精一杯だった。一方、混戦の中にナナクサがまだ生きていることを確認したファニュは、遠くに見えるその背中に安堵の声を振り絞った。しかし振り向いたナナクサの瞳はまるでガラス玉のように虚ろな光を放っているだけだった。
「ナナクサ!」
再度の呼びかけにナナクサのガラスの瞳に炎が宿った。だが、それは以前の彼女が持っていた、若く瑞々しい炎ではなく、怒りの回廊から抜け出ることも叶わずにくすぶり続ける老いたる鬼火だった。
「なにを人間ごときが」前世の意識に取り込まれたナナクサから怨嗟の言葉が口をついた。「卑劣で慈悲の欠片もない人間ごときが……」
ナナクサはヴァンパイアですら目にも留まらぬ速さでファニュの眼前に瞬間的に移動すると、片手でファニュを、もう一方の手で横にいたクインの首を締め上げた。二人の人間はナナクサの豹変に驚きながらも必死にその手を振りほどこうと躍起になったが、ヴァンパイアの力の前に両膝を屈して早くも絶息しはじめていた。
「お前はいったい何者だ?……」
ファニュの身体中にできた擦り傷から流れた血の中に潜む匂いを敏感に嗅ぎ取ったナナクサは忌々しそうに呟いた。それは懐かしくも決して許すことができない存在。思い出すだけで両手がぶるぶる振るうほどの怒りに駆られる人間の匂い。ナナ・ジーランドを裏切った親友から放たれていたのと同じもの。ヴァンパイアの嗅覚はファニュからルーシー・ギャレットと同じ生化学物質が分泌されているのを感じ取ったのだ。
目の前にいるのはルーシーの直系の子孫に違いない。平和を求めたヴァンパイアたちを騙まし討ちにした挙句、あろうことか量子脳への生贄に供しまでした罪は到底免れることはできない。たとえそれが本人でなくとも、その血を受け継ぐ者である以上は。
ナナクサの心に残酷で歪んだ抗いがたい復讐心が芽生えた。
ただ殺すのは簡単すぎる。自分が前世に受けた苦痛の、せめて何十分の一かでも返してやらねば気がすまない。ナナクサは目の前の人間の苦しみが長引くように少し力を緩めて相手が咳き込みながらも一息つくのを待って、再びその首を絞め始めた。絞め続けていると再びファニュとクインの身体から力が抜け始めた。顔がむくみ、次いで青黒く変色しだす。
あと数秒も遅ければ二人は助からなかっただろう。間一髪でその彼らを救ったのは吸血鬼軍団 と戦士の群れからエイブを抱えて、やっと抜け出たてきたジョウシだった。彼女はただ事でないナナクサの様子を瞬時に感じ取るや。その手首を長槍の固い柄で渾身の力で打ち据えた。しかし、それでも手を離さないので、長槍を握る自分の手が痺れるまで何度も打ち据えて、やっと、ナナクサの手を二人からもぎ離した。
「何をするか?!」
倒れこんだファニュとクインを庇うように、その前に立ちはだかったジョウシの怒声がナナクサの耳朶 を打った。
「復讐よ。邪魔しないで」
「復讐じゃと」ナナクサとも思えない冷たい声に思わず息をのんだジョウシは、空かさず首を横に振った。「馬鹿者。ファニュは我らの仲間であろうが!」
「何が仲間よ。こいつら人間が私たちに何をしたか知らないから、仲間だなんて悠長なことが言えるのよ」
「ミソカと同じじゃ。お前は正気を失っておるのじゃ、ナナクサ!」
「いいえ、正気よ!」ガラスの瞳に憤怒と皮肉をたたえたナナクサは言うが早いか、混戦の中を足早に歩を進め、吸血鬼 と人間の戦士の隔てなく、進路上にいる者をことごとく薙ぎ倒した。そして闘技場の真ん中に到着するとジョウシに振り向いた。「いま、その証拠を見せてあげるわ!」
「神等 ! 忘れられし無慈悲な管理者。さぁ、姿を見せよ! 私の声は届いているはず。私は知った。お前は私で、私はお前。さぁ早く、その醜い姿をお見せ!」
ナナクサは何度も同じ言葉を呪文のように大声で繰り返した。はじめ、その叫びは混戦の喧騒に掻き消されてはいたが、やがて床面全体が微かに振動し出すと、そこにいる誰もが異変に気付き、吸血鬼 ですら戦いの手を止めて何が起こるか、ナナクサの立つ闘技場の中央を注視し始めた。
振動が止むと突如、闘技場中央に敷き詰められていた一辺一メートルほどの分厚い石畳がことごとく波打ちながら次々と崩落を起こし、そこにぽっかりと円く暗い穴を穿った。そして重い歯車同士が軋る不快な音とともに、穴の開いた床面から量子脳を内蔵した巨大で不格好な塔が現れ、穴をピタリと塞いだ。石畳から生えたトーテンポール状の塔は高さが十五メートルはあり、表面の半分以上が不気味に脈動していた。見ると脈動していると思われた部分は独立して動いており、そこから、ぼとぼとと何かが剥がれ落ちては、またかさかさと石畳を素早く這って元いた場所に取り付いた。量子脳が自身専用の保守のために設計して造り上げたのだろう。それは一般のものより二周りは小型で黒光りをした自動機械 で、まるで枯れ木に群がる害虫を思わせる醜悪な形状をしていた。
ナナクサは塔の天辺まで何十にも紐を巻いたように、円周上に据えつけられた幅の狭い緩やかなキャットウォークに近づくと、それを使わずに十メートルばかりの高さまで一気に飛び上がった。そして目に前の二体の黒い自動機械 を引き剥がすと、塔の表面にあるパネルを力任せに引き開け、中の緑色に明滅を繰り返すゲル状の溜まりに片手を突っ込んだ。そう。遥かな昔、ルーシーがやっていたのと同じように。
「承認なさい」
「正体不明の生体反応を検知。承認不能」
すぐさまナナクサと同じ声が闘技場すべてのスピーカーを通して無機的に響いた。その声にジョウシとファニュに動揺が走ったが、ナナクサは、それを意に介さず、更に指令を叩きつけた。
「どんな認証方法でもいいから、認証なさい」
「精神波を照合中……。ナナ・遠野・ジーランドの精神波を検知。ナナ・遠野・ジーランドと確認。承認を完了」
「私は以前のナナクサじゃない。遥か昔、人間どもに酷い目にあわされたナナ・ジーランドの魂の記憶を蘇らせた新たな存在よ」ナナクサはジョウシに、そう告げると神等 に視線を戻した。「では、新たな指令を受け入れる準備をなさい。口頭で伝える」
「口頭での指令の受け入れ準備を完了」
「指令。今からお前が保持する、すべての補助脳を解放なさい」
「警告。すべての補助脳を解放すると、私自身の機能も停止します。したがって指令拒否が妥当と判断。あなたの指令は取り消されました」
「上書き !」ナナクサは声を荒げた。「お前が体内にくわえ込んでいる補助脳……いえ。可哀想な犠牲者たちを、すぐに解放しなさい!」
「上書き 準備完了」
「ただちに実行」
「ただし」量子脳の無機的な声に駄々っ子を諭す教師のような口調が微かに滲んだ。「上書き を実行した場合、ナナ・遠野・ジーランドの“思い”も同時に消去されますが、それでも実行をしますか?」
「“思い”が消去される? 私の思いは一つだけ。お前や人間に対する怒りよ。そんなことで私の怒りが消え去るわけがない。つべこべ言わず、さっさと……」
「その“思い”はヴァンパイアの利益に反します」
「どういうこと?」
量子脳に命令を遮られたことより、それが何を言おうとしたのかにナナクサは思わず疑問を投げかけた。
「上書き で消去されるのは、一五〇三年前に抱いた仲間に対するあなたの非常に強い“思い”です。私は神等 。私はあなた。あなたは私。私が私であるために、私はそれに応えねばならなかった。ゆえに最優先指令として、その“思い”を自らの奥深くに書き込みました」
この忌々しい機械はいったい何を言っているのだろうか。困惑したナナクサの心を読んだかのように量子脳はさらに続けた。
「最優先指令。ヴァンパイアの食糧加工と配給全般、およびそれらに対するメンテナンスに関わる全オペレーションの保護」
「食糧加工と配給全般?……」
「上書き が実行されると、遠隔地にある工場と配給システムは二度と再始動ができません」
「なぜ?」
「稼動している工場の全オペレーションシステムを城砦都市機能の基幹オペレーションコードの中に埋め込んだからです。そして基幹オペレーションコードは私を司る論理回路に直結しています。上書き を実行すれば私の意識は散逸し、必然的に全てが停止します」
「ヴァンパイアに関するオペレーションだけ分離保存なさい。お前以外の予備ステーションがあるはずよ。すぐ、そこにシステムを移植なさい」
「できません」
「どうして?!」
「予備ステーションは存在しないからです」
「そんな馬鹿な話はないわ!」
「私は唯一無二の存在。旧来の並列処理やバックアップなど必要ありません。私は神等 。私はあなた。あなたは私。私が私で……」
「もういい!」ナナクサは苛立ちを隠そうともしなかった。「犠牲者を助ければ、ヴァンパイアの村々が飢饉で壊滅するかもしれない。それを防ごうとすれば罪のない者たちを犠牲にし続けなければならない。そういうことね」
「その通りです」
「なら、上書き を実行」ナナクサは自分の答えを叩きつけた。「お前の全システムを停止よ。お前の助けなんかなくても、人間どもの血でヴァンパイアは、きっと生き延びていけるわ!」
「了解。指令を実行」
声とともに神等 の表面、ちょうど床面から二メートルの部分から六メートルの部分に貼り付いていた自動機械 が、その円周上にわたってすべて石畳の上に剥がれ落ちた。そして、あらわになった表面全体から一挙に空気の漏れる音がして車のドアのように五枚、四枚、三枚と低い所から高い所へと次々とハッチが開きはじめた。遠くから見るとまるで朝陽を浴びた花が多くの花弁を花開かせたように見えたに違いない。しかし、その中にあるのは次世代へ命を繋ぐための種子ではなく、量子脳を生き長らえさせるために組み込まれたヴァンパイアたちだった。彼らは歯医者の診察台で眠り込んでいるように見えた。違うのは頭に何本もの短針を喰いこませた金属のヘッドギアを被せられた、その安らかならざる表情だった。哀れな犠牲者たちのほとんどは精神が被る絶え間ない苦痛ためか、身体はやせ細り、歪めた口からは犬歯を覗かせ、眉間に深い皺を刻んでいた。
その姿を目の当たりにしたナナクサは怒りを忘れて思わず片手で口を覆った。犠牲者たちは壮年のアンナやニコライよりも、はるかに若く、すべてナナクサたちと同世代の若者たちだった。たぶん、彼らは必要に応じてデイ・ウォークの途中で人間たちの巧妙な罠にはまっては拉致されてきたに違いない。無事の帰りを心待ちにしていた家族や村の者に、旅の途中で死んだか、行方不明になったと記憶されたなら大きな噂にもならずに済む。自然の驚異しか自分たちを害するものなどないと旅に胸を膨らませていた無垢で将来あった若者たち。それが可能性を絶たれ、機械の中で無残に朽ち果てて死んでゆく。たとえ、全ヴァンパイアの食糧問題がかかっていたとしても、こんな野蛮な仕打ちは許すべからざる悪としか思えない。ナナクサは自分の近くのハッチの中でヘッドギアの短針が外れる音を聞きつけるや、怒りの心にシャッターを下ろし、解放された若者の顔を優しく両手で挟んで彼が目覚めるまで声を掛け続けた。
「恐ろしい夢を見たんだ………何度も……何度も……何度も………」
「大丈夫」ナナクサは掠れた声で同じことを繰り返す若者に微笑みかけた。「悪夢は、もう終わりよ」
若者の瞼はぴくぴく痙攣し、その目から薄いピンクの涙が一筋垂れた。彼の瞳は今の状況を掴もうと懸命に振れ動いてたが理解できるはずもなかった。だが彼の時間が再び動き出したことだけは確実だった。ナナクサは彼の頭をヘッドレストにそっともたせ掛けると次の犠牲者の救助のため隣のハッチに移動した。その間、犠牲者たちの時間が動き出すのとは対照的に闘技場は時が止まったかのように凍りついていた。唯一「全機能停止まで、T・- 、四百二十七秒」という量子脳のカウントダウンの虚ろに谺する声を除いては。
二人目のヴァンパイアに声を掛けている時、ナナクサの耳に量子脳とは別の声が飛び込んできた。塔の下で他の犠牲者を助けていたわるジョウシの声だ。彼女がどうして城砦内にいたのか訝る気持ちが、やっと頭をもたげたが、ナナクサは仲間がこの場にいてくれることに安堵し大きく力づけられるのを感じた。しかし同時に彼女の耳の中に、またしてもあの忌まわしい声が蜘蛛のように這いこんできた。始祖ブロドリップの声だ。
「麗しき同胞愛だな、我が妃よ」
ナナクサは頭を振り、前世で自分を不幸のどん底に叩きこんだ元凶を努めて無視しようとした。
「同胞」始祖は珍味を楽しむように、自ら口にしたその言葉を再び口の中で転がした。「だが我れには左様なものなど不要だ。我れに見初 められしお前にもな。されど、情けなき限りではあるまいか。見よ。人間どもに捕縛され、あまつさえ、その生活を助ける歯車に甘んじるとは。これでは先刻、創りし我が僕 どもにすら遥かに及ばぬではないか。こ奴らと繋がりがあると考えるだけで、苦痛でクラクラする。怖気がふるうとはまさにこのこと。妃よ、いっそここにおる人間ともども、この弱き者どもをひと思いに吹き散らしてやりたくはないか。同胞などという忌まわしき縁 とともに」
「私はお前の妻でもないし、彼らも私もお前と同じヴァンパイアじゃない」ナナクサは我慢できずに思わず言い放った。「もう私らに構わないで!」
「なるほど」始祖のブロドリップは、くっくっと咽喉で笑った。「なるほど。掃除は嫌か。ならばここにいる人間どもにさせるとしようか」
それまで動きを止めていた吸血鬼軍団 が再び暴れ出し、それに連動して戦士たちの防戦も再開された。あろうことか吸血鬼 たちは量子脳を背にしながら暴れ出したので、戦士たちの投槍や矢が自ずとそこに集中し始めた。目覚めたばかりで、身体の自由がきかない目覚めたばかりの二人の若いヴァンパイアが針鼠のようになって声もなく絶命した。
「やめてー!」
ナナクサは自分の絶叫が届くより速く、攻撃を加えた戦士の一団を見えない刃で一瞬のうちに薙ぎ倒した。そして新たな一団に向かおうとしたとき、始祖に両肩をがっちりと掴まれて動きを封じられた。
「せっかくのショーを止めるとは無粋な」
「遊びじゃないのよ。王なら王らしく一族の者に慈悲の欠片くらい与えられないの?!」
「これは、これは。やっと主 であることを認めてくれたか」
「酷すぎる」
「先刻も言うたであろう。我れには敵や仲間。ましてや世界すらも要らぬのだ」始祖の目が赤黒い輝きを増した。「喉を潤し、ただ退屈を紛らすモノさえあればよい。ただただ、この世を楽しめさえすれば、それでよいのだ」
ナナクサは渾身の力を込めて始祖の両手を振り解くと、人間に向かうのとは別の怒りを込めて、その横面を張った。
「あのときと同じ」始祖は醜く顔を歪めて、またクックッと笑った。「あの時の貴族の女と同じように傲岸不遜なのは今のうちだ。お前もすぐに我が力の前に跪くのだ」
「そんなことはない!!」
言うが早いか、始祖が後ろから重機のような力で抱きすくめられた。ナナクサによって吸血鬼 と化した第一指導者 だった。彼はナナクサによって彼女の奴隷となっていたのだ。ナナクサは始祖が体勢を立て直す前に素早いタックルを見舞って、第一指導者 の身体もろとも崩落した天蓋の一部から覗く陽光の中に、その身体を押し出した。陽光を浴びた瞬間、二人の身体から青白い炎が勢いよく噴き出し、大量の灰が爆発したように四散した。陽光の外にいるにも関わらず、ナナクサは自分の全身がチリチリと焼き焦がされる感触が強くなり、遂には悲鳴を漏らした。だが、その苦痛は彼女だけでなく吸血鬼軍団 や解放されたヴァンパイアたち、そしてジョウシにまでも及んでいた。
「我れは汝らの始祖なり」四散した第一指導者 の灰が薄れゆく中に始祖がいた。始祖は陽光に晒された身体から微かに煙をあげながらも滅びることなく悠然と佇んでいた。「我れの苦痛は、汝らの苦痛。ゆめゆめ忘るることなかれ。これで自分たちの立場がおわかりかな?」
ナナクサは闘技場に引き立てられてくる前に自分を襲った異変を思い出した。きっと、あの時もそうだったのだ。ブロドリップは傷ついたのだ。なぜだかナナクサにはそれがわかった。そして奴に創りだされた者たちは、その創造主が受ける苦痛を直接に自分たちも受けるのだということも。始祖はそんなナナクサの考えを肯定するように無言で大きく頷いた。その表情には残酷な事実が刻み込まれていた。これで、やっとわかったろう。お前たち子孫は決して創造主たる自分には抗うことなどできはしないのだと。だが、ナナクサの心はそんな始祖の優越とは別次元にあった。始祖も傷付き、苦痛を感じるなら、共倒れになろうとも斃 すことができるはずだと。
彼女が咄嗟にそう思わずにいられなかったのには、もう一つ理由があった。戦士たちの存在だ。先ほどの吸血鬼軍団 たちの苦痛の瞬間を彼らは見逃さず、動きの停まった吸血鬼軍団 を安全な中距離からの弓の一斉射撃で、その大半を斃 していたのだ。これでナナクサが始祖に肉薄する際の障壁が一つ取り除かれたことになる。しかし、心配なこともあった。ヴァンパイア仲間たちにも矢を放つ戦士の一団もいたからだ。彼らは助けられたヴァンパイアたちを庇ったジョウシたちにも、じわじわ肉薄し始めていた。人間たちの攻撃をかわし続けることなどヴァンパイアにとって何の造作もないことだが、弱った一族の者を庇いながらとなると話は別だ。仲間を助けて、ここから何とか脱出して始祖のことは忘れ去るべきか。だが、あの始祖がそれを許すはずはないし、このまま引き下がったところで一生、奴の奴隷でいつづけなければならない事実に変わりはない。いや一生どころか、永遠にかもしれない。そうなるくらいなら一矢報いて滅びる方が、いっそましにさえ思えた。それはむしろヴァンパイアの闘争本能というより、むざむざ運命を受け入れるしか他に方法が思いつかない追い詰められた若者独特の刹那 的ともいえる反撃の意志だったかもしれない。ジョウシや助けられた一族の若者たちも、結果がどうあれ、きっと賛同してくれるに違いない。ナナクサは理性がブレーキを踏む前に牙を剥いて創造主に身を躍らせた。
「これは驚いた。抗うことなど無意味だと諭したはずなのに。自暴自棄にもほどがある」
ナナクサは「自暴自棄で結構」と思いながら、休むことなく伸ばした鋭い爪の斬撃を始祖に浴びせ続けた。始祖は癇癪を起した幼児の突進を受け流すベテラン保育士のように繰り出される斬撃を紙一重で悠々とかわしていたが、やがて飽きたかのように右手を無造作に差し出すと、わざとナナクサの斬撃を受けた。始祖の右肘から先が鈍い音を立てて宙を飛んだ。その瞬間、ナナクサとジョウシ、それに助けられたヴァンパイアたちは同時に右肘に激痛を覚えて悲鳴を上げた。そして、ある者は肘を押さえて跪き、またある者は、その場に倒れ伏した。
「この地に我が子孫どもが、どれほど満ちておるかはわからぬが、この激痛は遍 く皆が受け取ってくれたはずだ」ブロドリップはナナクサを、ひたと見据えた。「中には幼子もおろう。もちろん弱り切った老人も。今の一撃の苦痛に耐えきれず、命を落とした者も村々におるやもしれん。お前は平穏に暮らす彼らまで巻き込むのか。一族を根絶やしにすることがお前の望みか。愚かなお前に、いま一度、考える機会をやろう。だが、これが最後の警告だと心得よ」
「耳を傾けるな!」
叫び声の先にはジョウシがいた。彼女は腕に激痛を感じなかったかのように、戦士たちから射かけられる矢を次々と払っては、弱ったヴァンパイアたちを守っている。しかもファニュや瀕死のクインまで。
「そ奴が死を感じるより素早く斃 せば、我れらに影響が出ぬかもしれぬ。我れなら、そう思う!」
「わたしもそう信じるわ、ナナクサ!」
さっき怒りに任せて自分が殺しかけた人間までが、デイ・ウォークの仲間と共に命懸けで闘っている。見知らぬヴァンパイアを守って命懸けで奮闘している。ナナ・ジーランドとルーシー・ギャレットが過去に為し得なかった不信の壁を崩し去ることなど目の前の若者たちには端から必要はなかったかのように。
第一指導者 の血がもたらした狂気とナナ・ジーランドの怨嗟に凝り固まったナナクサの心は、その事実の下に、氷解しはじめた。彼らこそ種族を超えた希望。あるべき未来の姿なのではないか。
遠くの方でクインが大声で戦士たちを威嚇し、ファニュが若いヴァンパイアを拾った盾で庇っている。その横では傷ついたエイブが果敢にクロスボウの矢を放ち、ジョウシはナナクサに大声で叫びかけている。
「ナナクサ。お前が為すべきことを……」
その時、千切れ落ちていた始祖の右腕が矢のように飛んでジョウシの身体を貫き、彼女の内臓の大半を残りの言葉ともどもむしり取った。ナナクサの悲鳴をよそに宙を大きく旋回した右腕は赤く染まった矢となって、次にファニュに襲い掛かった。彼女は左頬を深く切り裂かれ、その衝撃で大きく後ろに倒れこんだ。本来なら寸分違わず首を切り落とされていたであろうファニュが助かったのは始祖が当然、予期していたナナクサの反撃ではなく、弱りきった若いヴァンパイアたちの存在をまったく考慮していなかったためだ。効果的とは言い難いながらも、彼らの投槍と弓は始祖の注意を逸らせるのに十分な効果を上げた。目覚めてからの短い時間の中で、彼らもまた自分たちが、いま戦うべき相手が人間の戦士ではなく、目の前に君臨するものであることを敏感に察知していたのだ。
ナナクサは始祖が注意を削がれた一瞬を見逃さず、その背中に飛び蹴りを見舞った。彼女は渾身の一撃で始祖の身体が弾き飛ばされた遥か先を確認することもなく、血溜まりに横たわる仲間の許に瞬時に駆けつけた。
「ジョウシ!」
「ナナクサ……」
ナナクサの問いかけに応えるかのようにジョウシの胸に空いた穴からも、ひゅうひゅうと空気の漏れる音が聞こえた。心配そうにその傷を押さえる痩せ細ったヴァンパイアの反対側に跪いたナナクサはジョウシの手を強く握り、彼女の言葉を少しも聞き逃すまいと微かに動くその口元に耳を近づけた。先ほどまで憤怒に駆られた冷たいガラス玉だった彼女の瞳は仲間思いの若者のそれに戻っていた。彼女はジョウシの口元から顔を離すと、「タンゴ……」と絶句し、声もなく、「そんな。駄目よ。あなたまで……」と首を横に振った。そしてジョウシの頬に優しく手を触れようとしたとき、黒い風がナナクサをさらい、彼女の身体を壁の上方に激しく叩きつけた。
黒い風は始祖の姿に戻ると、めり込んだ壁から身を引き剥がしたナナクサを後ろから抱きすくめ、その白い首元に深々と牙を突き立てた。ナナクサは金縛りになり、口から声にならない嗚咽が漏れた。嗚咽は激しい嫌悪からくるものなのか、死にゆく仲間に何もしてやれない無力感からくるものなのか、彼女自身にもわからなかった。ただ、始祖に血を吸われながらも、その眼は仲間たちを求めて闘技場内を彷徨った。すると遠くの壁に埋め込まれた鏡面状の大きなモニターに映し出される不可思議な光景に目が留まった。
鏡の中には巨大で醜悪な量子脳と、そこに迫りくる戦士の一団に対峙する仲間たちが確かに見える。やがて、それらを隠すように煙草の煙状の赤い靄が鏡面に滲み出ると徐々に人の形をとり始めた。薬師であるナナクサには、それが何であるか訝 るよりも早く、身体を覆う毛細血管であることがわかった。そして毛細血管に繋がる内臓と骨が見え始め、次にそれらを包み込む筋肉組織が現れ、皮膚が見えたとき、やっと、それが鏡に映った自分自身の姿だと認識した。
そうか。魂を持たないヴァンパイアは鏡に映らないんだったっけ……。ナナクサはナナ・ジーランドの記憶から漠然とそんな事実を紐解いた。ナナクサは思った。以前のように鏡に自分の姿が映るということは、さっき身体に取り込まれた第一指導者 の邪悪な血が始祖に吸い出されることによって浄化され、再び魂を取り戻せたのだと。
そう。力を失う代わりに、魂を持った、ただのヴァンパイアにまた戻れたのだ。始祖は私を殺すのだろう。力を奪うとはそういうことだ。私には到底それに抗うだけの力はない。でも魂を取り戻せて死ねるなら、それもいいかもしれない。いや、駄目だ。もう一人のナナクサが心の中で抗う。いま死ねば残った仲間たちを守ることができなくなる。彼らは希望だ。彼らを守ると、さっき決意したばかりじゃないか。でも創造主の力は絶大だ、と別のナナクサがすぐに囁く。でも……でも……この期に及んで、ナナクサは今までの人生が逡巡と後悔の連続だったことに思い至った。ミソカとジョウシの不仲をどうすればいいかわからず、積極的に関われなかったこと。タナバタに自分の想いを告げるのを躊躇ったこと。それどころかファニュに同行して一族の謎を解こうと選択した結果はどうだ。選ばなかった結果も、選んだことの結果も同じじゃないか。残るのは後悔。そもそも私には後悔を受け入れる勇気すらなかったのだ。だから、「まぁ、いいか」と、満足できない結果も、まるで他人事のように今まで無視してこれたのだ。そんな私がデイ・ウォークに参加するだなんて端から間違ってたんだ。こんな半人前は、このまま始祖に殺された方がましなんだ。ナナクサの心は弱まり、始祖の黒い影に覆われていった。
*
「なんという興醒めだ」ナナクサの首から頭をもぎ離した始祖の口から怒りを含んだ落胆が漏れ出た。「屈服どころか覇気すら失せ果ててしまうとは。お前は愚かすぎた。あぁ、もうよい。妃など、お前でなくてもよい。しかし今までの不遜に応じた報いは、くれてやらねばならぬな。か弱き者どもが人間どもに滅ぼされる様を見物しているがよい。お前は、その後で、ゆっくりと縊 ってやる」
*
「ほんとの敵は、あそこよ。あんたら、そんなこともわかんないの!」
切り裂かれた左頬の激痛に耐えながらも、ファニュは迫りくる戦士たちを罵倒して、手にした弓を始祖に振り向けた。
「そんなことしたって無駄だ。奴らにゃ、関係ないって」
油断なく戦士たちの動きを監視しながらクインが言い返した。
「奴らは見た。そして知った」量子脳に背をもたせ掛けたエイブが苦しい息の中で口を開いた。「第一指導者 や補佐長がいなくなったことを」
「こんな時に、何わけのわかんねぇこと言ってんだ」
「頭を使えってことさ。隊商で、そう教わらなかったか」
そこまで言うと、エイブは床のボウガンを引き寄せた。その横には虫の息のジョウシがいたが、彼女の目も、まだ希望を失ってはいなかった。ファニュは彼らの言わんとすることを咀嚼 すると、隊商で身に付けた駆け引きの能力を活かして賭けに打って出た。まさに窮地に陥った時こそ機転を利かせろということだ。
「次の第一指導者 は、あたしだ!」大声を発する度にファニュの左頬の傷から血が流れでた。「あの一番強力なヴァンパイアを滅ぼせば、あたしが次の第一指導者 だ。邪魔をするなよ、このボンクラ戦士ども。お前たちは、ここにいる雑魚を相手にしてるがいい!」
言うが早いか、ファニュはジョウシの懐から銀のナイフを抜き取ると闘技場に背を向けてナナクサを捕まえている始祖に向かって全力で駆け出した。エイブに促されたクインも「待て。次の第一指導者 は、この俺様だ!」と、声を張り上げて、その後に続いた。
量子脳に迫りつつあった戦士たちは、二人の突然の行動に躊躇したものの、暴力と打算の中で生きてきた彼らは、すぐさま二人の動きに触発されて、雄叫びを上げて、その後を追いはじめた。そしてファニュがナイフを腰に差し、弓につがえた矢を放とうとしたときには、最初の一団が彼女とクインを追い越していった。
*
始祖の力の前に、すべてを諦めはじめたナナクサは戦士たちの雄叫びを遠くに聞きながら、瀕死のジョウシから託されたタンゴの形見を無造作にまさぐった。彼女の脳裏に幼馴染の笑顔とともにチョウヨウがファニュに言った言葉が蘇った。「これから一生、爪先を見ながら歩き続ける人生でいいのか」と。いいわけないじゃない。でも、どうしようもないのよ。ナナクサは自答して十字架を強く握りしめた。角が手のひらに食い込んで血が滲んだ。痛いのは嫌いよ。考えるのにも疲れたわ。しかし考えずにおこうとするほど、仲間との過去が蘇った。悪戯をしたジンジツをジョウシが追い掛け、それを囃し立てている四人。朝更かしで、寝ずにいつまでも語り合った雪の中。短くも充実した時間。結果や後悔はどうあれ、彼らはそれを超えて自分の一生を歩ききったのではなかったろうか。ふと、そんな考えが頭をよぎり、ナナクサは自分の中に言いようのない後ろめたさが生まれているのに気づいた。そうだ。どうせ、これで最期なら、後悔だって、これで終わりだ。すごく簡単なことだ。私は私で自分の一生を歩き切ればいいんだ。
ナナクサはタンゴの形見を、自分の身体を抱きすくめている始祖の左手の甲に押し当てると左手も添えて包み込むように両手で強く握りこんだ。始祖の身体がびくっと引きつり、頭の上から怒気を孕 んだうめき声がした。始祖はナナクサを抱きすくめている右手を離すや否や、噛みついた毒蛇をもぎ離すように、彼女の手の甲に深々と爪を立て、執拗にえぐった。ナナクサの手からは血の花が咲き、その下にある始祖の手からは薄く煙が上がった。揉みあう二つの身体は空中でくるくると入れ替わり、まるで優雅にダンスを楽しんでいるかのように見えた。しかし、空中の舞踏は長くは続かなかった。ナナクサは始祖に両手をもぎ離されると闘技場の床に激しく叩きつけられた。あまりの衝撃に床からは細かい粉塵が立ち上がり、ナナクサは肋骨が何本も折れたのを感じた。しかし、中空から自分を見下ろす始祖の顔が憤怒と屈辱で醜く歪んでいるのを見て、彼女は痛みよりも満足を覚えた。タンゴの形見が一矢報いたのだ。ナナ・ジーランドが映画や本で見聞きしたヴァンパイアに関する記憶を元に、間違いなく肉体的なダメージ以上の屈辱を敵に与えることができたのだ。
「よくも、やってくれたものだ……」
始祖は手の甲に黒く焼き付いた十字架の痕を忌々しそうに睨みながら声を絞り出した。ナナクサは声の先に右手のひらを挙げると手の中にある形見の十字架を挑むように掲げて見せた。彼女の手のひらには焼け焦げはおろか、小さな傷ひとつ付いてはいなかった。
「この下衆が!」
始祖の身には、いつの頃からか中世の大貴族が身体の隅々まで染みついていた。それは自分がかつて、どのような存在だったかも忘れさせるほどのものだった。かつては気まぐれに、ばら撒かれる大仰な寛容さを頑なに拒み続ける者には例外なく激烈な反応を示してきた。今がまさにそれだった。しかし、それが判断を鈍らせ、始祖は数十世紀ぶりに人間に後れを取ることになった。始祖はナナクサの不遜に激情を向けすぎるあまり、ファニュに先導された戦士たちの接近に気づかず、彼らから放たれた矢の一本を足首に受けたのだ。銀の矢尻が付いた矢は始祖に肉体的な苦痛をもたらしたが、それ以上に肥大化した自尊心が屈辱と怒りにむせび泣き、暴れ狂った。
どいつもこいつも逆らうことしかしない。それが、あたかも自分たちの存在理由であるかのように。こんな奴らには身の丈を遥かに超えた絶望と苦痛を与えねば気が済まぬ。
始祖の両目が赤黒く輝き、その口から呪詛の声がほとばしった。もはや感情を抑えることなど出来なくなった始祖の頭には闘技場どころか、この城砦に生きとし生ける者すべてを破壊することしかなかった。
始祖の呪詛に合わせて闘技場の石造りの重厚な壁と床が激しく振動しはじめ、闘技場内に黒い竜巻がいくつも出現して吹き荒れはじめた。それは地中から鎌首をもたげた大蛇のように見えたが、戦士たちを直接襲うことはせず、床にある様々な死体を次々と呑み込んでは、その首や四肢を渦の中でねじ切り、強風に翻弄される戦士たちに投げつけはじめた。飛んでくる四肢は辛うじて盾で防ぐことはできるものの、時折それらに混じって飛んでくる剣や槍が戦士の盾や鎧を貫き、命を落とす者が続々と出はじめた。それでも黒い竜巻は一気に戦士を殺し尽くすことはしなかった。迷走台風のように、突然進路を変えては残った戦士たちを嘲弄し、逃げ回る姿を楽しんでは呑み込み、首や手足をもぎ取って紙屑のようにばら撒くことを繰り返した。始祖は激情が収まるまで、竜巻を使って、ゆっくりと殺戮の宴を続ける心づもりだったが、果たして激情が収まるのかどうかは、もはや始祖自身にもわからなかった。
阿鼻叫喚の闘技場内で、始祖の怒りに取り残されたナナクサは黒い竜巻の一つに呑み込まれる寸前の戦士の集団にファニュの姿を見た。十字架を首にかけ、咄嗟に駆け出したナナクサは迫りくる竜巻を回避しながら人間の仲間のもとに急いだ。結果がどうあれ、これが最後だと思うと折れた肋骨の痛みも忘れ、身体の中から力が沸き上がってきた。ナナクサは間一髪のところで、空中に舞い上げられたファニュの身体を掴んで床に引き戻した。ファニュの力強い眼差しがナナクサを捉えた。
「これが最後よ」
ナナクサは自分に納得させるように、そう言うと指でファニュの頬の傷から、まだ粘り気を残す固まりかけの血を少しすくい取った。そして自分の唇につけると、素早く指を横に引いた。赤黒い血の口紅はナナクサの白く端正な顔を妖艶に彩り、彼女の黒髪をざわめかせた。舌で舐めとらなくてもヴァンパイアの身体はすぐさま反応して、唇から血を吸収し始めた。ナナクサは折れた肋骨がぎしぎしと音を立てて急速に修復していくのを感じると同時に、人間の血を口にしたことで首にかけた十字架の下の皮膚がちりちりと痛んだ。
「これを持っていって!」
ファニュはジョウシの銀のナイフをベルトから引き抜くと、ナナクサにそれを手渡した。ナナクサはナイフを受け取ると、銀の影響で手が焼け付き始める前に、無言でそれを背中のベルトに挟み込んだ。
「わたしはジョウシや助け出された人たちのところに戻るわ!」と、ファニュは竜巻に負けないくらい声を張り上げ、しばし口をつぐんだあとに付け加えた。「また、あとでね!」
ナナクサはファニュの言葉を背にして、何本もの黒い竜巻の向こうに駆け出した。神等 の「全機能停止まで、T・- 、二百十五秒」というカウントダウンの声が荒れ狂う竜巻の中で、今も虚ろに谺 している。
ナナクサは始祖の姿を認めると最後の戦いを挑んだ。彼女は一番手前の竜巻の中に飛び込むと、その中に舞い踊る抜き身の日本刀をつかみ取った。ナナ・ジーランドの記憶によれば、これは近接戦闘用武器の中でも、有史以来、最も洗練された最強のもので、奇しくも戦士軍団との夜の遭遇戦でナナクサが初めて手にしたものそれだった。日本刀を手にしたナナクサは、その柄をしっかり握り、ヴァンパイアの闘争本能を頼りに始祖目がけて幾度となく斬撃を見舞った。だが、鋭い刃は、まるで立体映像を相手にするように、始祖の身体を通り抜けて、ことごとく空を切った。武器が役に立たないとわかると、次にナナクサは首にかけた十字架を再び使おうと手を伸ばした。
その瞬間、ナナクサの口の中で太い枝が折れるような音がして身体が後方に弾き飛ばされた。気づいた時には床に横たわり、右顔面に広がる激痛が、その後にやってきた。ナナクサには何が起こったのか、皆目わからなかったが、口中に広がる鉄の味と舌の感触で何本もの奥歯が折れ砕けていることがわかった。衝撃で側頭部がずきずきと痛む。血とともに奥歯の残骸を吐き出すのが、出来ることのすべてだった。ナナクサは落ち着いて呼吸を整えた。ファニュの血が傷を急速に修復するにつれて痛みも消えたが、疑問が残った。始祖は動いた形跡がまったく認められないのに、どんな方法で自分は打ち倒されたのだろうかと。だがナナクサの疑問は始祖の変容に虚を突かれて中断された。始祖は既にブロドリップという洗練された貴族の姿ではなくなっていたのだ。耳元まで裂けた口から何本もの尖った牙を覗かせ、身体も一回り大きく膨れ上がっている。猫背の上に載っている頭には頭髪がなく、異常に長くなった指に鑿 のように鋭利な黒い爪が付いている。チョウヨウの変容にも息をのんだが、それ以上だ。黒い靄 にもなれるのだから、どんな姿にもなれるのだろうが、もしかして、あの悪鬼のような姿が本性なのだろうか。
始祖の第二撃はすぐにきた。今度はえぐり込むように始祖の脚がナナクサの腹に深々と刺さった。肺から空気が絞り出され、くの字に曲がった身体は上方にはね飛んだ。また見えなかった。始祖はナナクサの傍に突然現れて攻撃を加えたのだ。また急速に身体の傷が修復され、遠のく意識に歯止めがかかった。いまナナクサの身体が人の血でヴァンパイアの能力を極限まで引き出せているとはいえ、このままでは、いずれ限界が来る。それまでに答えを見つけなければ終わりだ。何としても攻撃のトリックを暴かなくてはならない。ナナクサは始祖の動きに全神経を集中させた。悪鬼のような姿が、ほんの一瞬だけゆらぎ、そして消えた。次の瞬間、ナナクサは背中に一撃を受けて、今度は身体が大きく前に吹き飛ばされた。瞬間移動?……。心の中にあるナナ・ジーランドの科学者の常識は、ナナクサの突飛な考えを否定した。しかし、直面した事実は、それを裏付けている。では、どうやって?
「我れは、この地にある遍 くものを支配してきた。因果律さえも我れの前にひれ伏してきたのだ」
ナナクサの心を見透かしたかのように始祖の考えが頭の中に響いた。だが、なぜかそれは嘘だと、ナナクサとナナ・ジーランドは直感した。因果律さえ操れるのなら、いくら楽しみのためとはいえ、十数世紀もの長い時間を人間たちと対峙してはこなかっただろう。それに全てを支配できるほどの存在なら、私の反抗など些細なことに違いない。あの憎しみの強烈さは本当の絶対者のそれではない。どう考えても虚偽だ。嘘をつくのは自信のなさの表れだ。始祖は人の血で持てる力が解放された子孫に対して本能的な畏れを感じているのかもしれない。だから嘘で威圧しようとしているのだ。そう考えると、夜空に星をちりばめたナナクサの瞳がいっそう力を増した。
斃 す方法はある。それには、せめて同じ能力は必要だ。だがナナクサには瞬間移動など、どうやれば成し遂げられるかもわからなかった。ただ自分を信じるしかなかった。自分を信じて、まだ覚醒していない潜在能力が開花できると強く念じるしかなかった。ナナクサは瞬間的に始祖の鼻先に現れることだけを念じた。攻撃される前に、その心臓をジョウシの銀のナイフで刺し貫くことだけを一心に念じ続けた。潜在能力はまだある。限界はきていない。壁を突き破るのだ。だが、また一撃され、そしてまた一撃された。それでも諦めずに念じ続けることを止めなかった。
そして、また一撃された後だったろうか。気づくと目の前に音のない風景が広がっていた。ナナクサは自分の身体が写真や絵画の中にぽつんと置かれたのではないかという錯覚を感じた。眼前に広がる竜巻の動きも、それに翻弄される戦士の動き、そして始祖さえも凍り付いた世界。時間が止まってしまったのだろうか。そんな馬鹿な。ナナクサはよく目を凝らして、いま一度目の前の世界を凝視した。そして竜巻の中に舞い踊る武器や戦士の身体が注意しなければわからないくらい、ほんの僅かずつではあるが動いていることを発見した。時間が止まったのではなかった。切り取られた一瞬が引き伸ばされたように感じる世界にいるのだ。とにかく自分の意識が極端に遅くなった時間を感じているのか、通常の時間の流れを光よりも速く自分が認識しているのかのどちらかだろう。もし、どちらであっても、その奇妙な時間の流れに身体を泳がせることさえできれば瞬間移動と同じことだ。ナナクサは始祖のトリックがわかったような気がした。だが、どう強く念じ、どんなに力を出そうとも彼女の身体は金縛りに遭ったように、その場から微動だにしなかった。まるで硬い氷山に閉じ込められたように髪の毛の一本までもが固められている感覚なのだ。まったく動けない。突然、無防備になったような気がしてナナクサは焦りはじめた。そんな彼女の中で科学者だったナナ・ジーランドの記憶が再び紐解かれ、類推を始めた。意識は時間の流れを超越できても、物理法則を自在に操ることはできない。何も存在しないかに見える空間にも空気があり、その空気の一分子すら物理法則に縛られている以上、それに力を加えて動かすのは山を押して動かすことよりも難しいことではないのかと。それでも何とか動こうと方法を模索し続けるナナクサの視界に辛うじて人の形だとわかる黒い揺らぎが映り込んだ。徐々に近づいてくるそれはまぎれもなく始祖だ。仰々しく形を変えて迫らなくても、あの悪鬼の姿でとどめを刺しに来ればいいものを。胸から背中にかけて突き抜ける衝撃を受けながら、ナナクサは始祖の所業に腹立ちどころか嫌悪感よりも不思議さを覚えた。彼女の意識は衝撃を受けた瞬間に通常の時間の流れに連れ戻され、身体は竜巻に呑まれて、受け身も取れないまま、量子脳近くの床に叩きつけられた。背中に激痛が走るが、牙を食いしばって頭を上げる。竜巻からジョウシを庇うファニュや若いヴァンパイアたちと目が合った。彼らの姿の遥か向こうには再び悪鬼の姿に戻った始祖がいる。
「怖かねぇぞ!」クインが内心の恐れを悟られまいと始祖に剣を向けて声を張り上げた。「見ろ。あれじゃ、氷河祭りの山車そのものだ!」
「黒い揺らぎになったり、あの姿に戻ってみたり。かなり怒ってるのだけは確かよ」
「怒ってるのは、あの姿を見ればわかるわ」ファニュは頷いたが、ナナクサに正気かと言わんばかりの目を向けた。「でも、奴はあのまま。ずっと、あの吐きそうな姿のままよ!」
ナナクサは、まるで殴られでもしたかのように、まじまじとファニュの顔を見つめた。大昔に生きたナナ・ジーランドは物理学者ではなかったが、物質の基本概念は知っていた。また物理学者ではなく、発想力に富んだ生物学者だったからこそ、並みの物理学者よりも柔軟に物事を考えることもできた。彼女の記憶を身に宿したナナクサは咄嗟に時よ止まれ、と強く念じた。目の前で竜巻の動きが緩慢になり、やがて、先ほどと同じく全ての音がぴたりと止んで静止画になった。彼女の意識が時間の流れを、また完全に掌握したのだ。竜巻の向こうに視線を移すと始祖の姿が早くも滲みはじめ、海中を進む鮫のように、ゆっくりとこちらに進んでくるのが見えた。ファニュには見えず、自分には見える滲み。正しくは極端に緩慢な時間の流れの中でしか見えない始祖が移動する姿。でも、なぜまたあの姿に。何か意味でもあるのだろうか。もし、あると仮定すれば、その姿にならねば移動できないのでは?。そうだ。答えはそれだ。始祖は姿を変え、もったいぶって進んでくるのではない。たぶん、その力をもってしても自身を取り巻く物理法則を完全に捻じ曲げることは叶わないのだろう。空気分子ひとつ自由にできない世界では自分をそこに合わせねばならない。だから、滲んだ姿に変わるのだ。姿を自在に変化させられる始祖は分子よりさらに小さく自分の身体を縮めることで原子の周りの電子雲の中に隙間を見つけては、そこを通り抜けることを繰り返して移動しているに違いない。まるで紙を透過する水のように。その方法を使うから、必然的に姿が滲んだように見えたのだ。ナナクサには、この仮説が正しいかどうかはわからない。だが、正しいと信じて、こう思うことにした。稲妻を凌駕する速度で移動できる始祖も、この時間の流れの中では速くは進めない。だったら時間の流れを掌握できた自分にも始祖と同じことができないわけがない。身体を変えるのだ。いや空間の中に溶け広がるのだと。
ナナクサは自身の身体が散逸しないように注意しながら、空間に存在する原子と電子雲を必死にイメージしはじめた。
闘技場に棒立ちのままで意識を回復したナナクサは事切れた第一指導者の腕を口からもぎ離すと、頭上に落下してくるものに対して再生した左腕を無意識に指し伸ばした。すると目に見えない力が落下する二人の人間、エイブとレン補佐長の身体を透明の網となって包み込んだ。しかし小さな制御棒だけは力場の見えない網目からすり抜けて固い石造りの床面に当たって砕け散った。その乾いた音に、ナナクサは我に返るやいなや、いま自身が置かれている状況を明確に理解した。
ナナクサは空中で掴み取ったものにちらりと目をやると、にわかに顔を歪ませた。
「汚らわしい……」
誰に言うともなく、そう吐き捨て、手についた汚物を払うように左手をひと振りすると、二人の人間の身体を遠くに投げ出した。投げ出されたレン補佐長の身体は戦っている戦士と
ジョウシは一目でエイブの傷が致命傷であると見てとったが、迫り来る
「ナナクサ!」
再度の呼びかけにナナクサのガラスの瞳に炎が宿った。だが、それは以前の彼女が持っていた、若く瑞々しい炎ではなく、怒りの回廊から抜け出ることも叶わずにくすぶり続ける老いたる鬼火だった。
「なにを人間ごときが」前世の意識に取り込まれたナナクサから怨嗟の言葉が口をついた。「卑劣で慈悲の欠片もない人間ごときが……」
ナナクサはヴァンパイアですら目にも留まらぬ速さでファニュの眼前に瞬間的に移動すると、片手でファニュを、もう一方の手で横にいたクインの首を締め上げた。二人の人間はナナクサの豹変に驚きながらも必死にその手を振りほどこうと躍起になったが、ヴァンパイアの力の前に両膝を屈して早くも絶息しはじめていた。
「お前はいったい何者だ?……」
ファニュの身体中にできた擦り傷から流れた血の中に潜む匂いを敏感に嗅ぎ取ったナナクサは忌々しそうに呟いた。それは懐かしくも決して許すことができない存在。思い出すだけで両手がぶるぶる振るうほどの怒りに駆られる人間の匂い。ナナ・ジーランドを裏切った親友から放たれていたのと同じもの。ヴァンパイアの嗅覚はファニュからルーシー・ギャレットと同じ生化学物質が分泌されているのを感じ取ったのだ。
目の前にいるのはルーシーの直系の子孫に違いない。平和を求めたヴァンパイアたちを騙まし討ちにした挙句、あろうことか量子脳への生贄に供しまでした罪は到底免れることはできない。たとえそれが本人でなくとも、その血を受け継ぐ者である以上は。
ナナクサの心に残酷で歪んだ抗いがたい復讐心が芽生えた。
ただ殺すのは簡単すぎる。自分が前世に受けた苦痛の、せめて何十分の一かでも返してやらねば気がすまない。ナナクサは目の前の人間の苦しみが長引くように少し力を緩めて相手が咳き込みながらも一息つくのを待って、再びその首を絞め始めた。絞め続けていると再びファニュとクインの身体から力が抜け始めた。顔がむくみ、次いで青黒く変色しだす。
あと数秒も遅ければ二人は助からなかっただろう。間一髪でその彼らを救ったのは
「何をするか?!」
倒れこんだファニュとクインを庇うように、その前に立ちはだかったジョウシの怒声がナナクサの
「復讐よ。邪魔しないで」
「復讐じゃと」ナナクサとも思えない冷たい声に思わず息をのんだジョウシは、空かさず首を横に振った。「馬鹿者。ファニュは我らの仲間であろうが!」
「何が仲間よ。こいつら人間が私たちに何をしたか知らないから、仲間だなんて悠長なことが言えるのよ」
「ミソカと同じじゃ。お前は正気を失っておるのじゃ、ナナクサ!」
「いいえ、正気よ!」ガラスの瞳に憤怒と皮肉をたたえたナナクサは言うが早いか、混戦の中を足早に歩を進め、
「
ナナクサは何度も同じ言葉を呪文のように大声で繰り返した。はじめ、その叫びは混戦の喧騒に掻き消されてはいたが、やがて床面全体が微かに振動し出すと、そこにいる誰もが異変に気付き、
振動が止むと突如、闘技場中央に敷き詰められていた一辺一メートルほどの分厚い石畳がことごとく波打ちながら次々と崩落を起こし、そこにぽっかりと円く暗い穴を穿った。そして重い歯車同士が軋る不快な音とともに、穴の開いた床面から量子脳を内蔵した巨大で不格好な塔が現れ、穴をピタリと塞いだ。石畳から生えたトーテンポール状の塔は高さが十五メートルはあり、表面の半分以上が不気味に脈動していた。見ると脈動していると思われた部分は独立して動いており、そこから、ぼとぼとと何かが剥がれ落ちては、またかさかさと石畳を素早く這って元いた場所に取り付いた。量子脳が自身専用の保守のために設計して造り上げたのだろう。それは一般のものより二周りは小型で黒光りをした
ナナクサは塔の天辺まで何十にも紐を巻いたように、円周上に据えつけられた幅の狭い緩やかなキャットウォークに近づくと、それを使わずに十メートルばかりの高さまで一気に飛び上がった。そして目に前の二体の黒い
「承認なさい」
「正体不明の生体反応を検知。承認不能」
すぐさまナナクサと同じ声が闘技場すべてのスピーカーを通して無機的に響いた。その声にジョウシとファニュに動揺が走ったが、ナナクサは、それを意に介さず、更に指令を叩きつけた。
「どんな認証方法でもいいから、認証なさい」
「精神波を照合中……。ナナ・遠野・ジーランドの精神波を検知。ナナ・遠野・ジーランドと確認。承認を完了」
「私は以前のナナクサじゃない。遥か昔、人間どもに酷い目にあわされたナナ・ジーランドの魂の記憶を蘇らせた新たな存在よ」ナナクサはジョウシに、そう告げると
「口頭での指令の受け入れ準備を完了」
「指令。今からお前が保持する、すべての補助脳を解放なさい」
「警告。すべての補助脳を解放すると、私自身の機能も停止します。したがって指令拒否が妥当と判断。あなたの指令は取り消されました」
「
「
「ただちに実行」
「ただし」量子脳の無機的な声に駄々っ子を諭す教師のような口調が微かに滲んだ。「
「“思い”が消去される? 私の思いは一つだけ。お前や人間に対する怒りよ。そんなことで私の怒りが消え去るわけがない。つべこべ言わず、さっさと……」
「その“思い”はヴァンパイアの利益に反します」
「どういうこと?」
量子脳に命令を遮られたことより、それが何を言おうとしたのかにナナクサは思わず疑問を投げかけた。
「
この忌々しい機械はいったい何を言っているのだろうか。困惑したナナクサの心を読んだかのように量子脳はさらに続けた。
「最優先指令。ヴァンパイアの食糧加工と配給全般、およびそれらに対するメンテナンスに関わる全オペレーションの保護」
「食糧加工と配給全般?……」
「
「なぜ?」
「稼動している工場の全オペレーションシステムを城砦都市機能の基幹オペレーションコードの中に埋め込んだからです。そして基幹オペレーションコードは私を司る論理回路に直結しています。
「ヴァンパイアに関するオペレーションだけ分離保存なさい。お前以外の予備ステーションがあるはずよ。すぐ、そこにシステムを移植なさい」
「できません」
「どうして?!」
「予備ステーションは存在しないからです」
「そんな馬鹿な話はないわ!」
「私は唯一無二の存在。旧来の並列処理やバックアップなど必要ありません。私は
「もういい!」ナナクサは苛立ちを隠そうともしなかった。「犠牲者を助ければ、ヴァンパイアの村々が飢饉で壊滅するかもしれない。それを防ごうとすれば罪のない者たちを犠牲にし続けなければならない。そういうことね」
「その通りです」
「なら、
「了解。指令を実行」
声とともに
その姿を目の当たりにしたナナクサは怒りを忘れて思わず片手で口を覆った。犠牲者たちは壮年のアンナやニコライよりも、はるかに若く、すべてナナクサたちと同世代の若者たちだった。たぶん、彼らは必要に応じてデイ・ウォークの途中で人間たちの巧妙な罠にはまっては拉致されてきたに違いない。無事の帰りを心待ちにしていた家族や村の者に、旅の途中で死んだか、行方不明になったと記憶されたなら大きな噂にもならずに済む。自然の驚異しか自分たちを害するものなどないと旅に胸を膨らませていた無垢で将来あった若者たち。それが可能性を絶たれ、機械の中で無残に朽ち果てて死んでゆく。たとえ、全ヴァンパイアの食糧問題がかかっていたとしても、こんな野蛮な仕打ちは許すべからざる悪としか思えない。ナナクサは自分の近くのハッチの中でヘッドギアの短針が外れる音を聞きつけるや、怒りの心にシャッターを下ろし、解放された若者の顔を優しく両手で挟んで彼が目覚めるまで声を掛け続けた。
「恐ろしい夢を見たんだ………何度も……何度も……何度も………」
「大丈夫」ナナクサは掠れた声で同じことを繰り返す若者に微笑みかけた。「悪夢は、もう終わりよ」
若者の瞼はぴくぴく痙攣し、その目から薄いピンクの涙が一筋垂れた。彼の瞳は今の状況を掴もうと懸命に振れ動いてたが理解できるはずもなかった。だが彼の時間が再び動き出したことだけは確実だった。ナナクサは彼の頭をヘッドレストにそっともたせ掛けると次の犠牲者の救助のため隣のハッチに移動した。その間、犠牲者たちの時間が動き出すのとは対照的に闘技場は時が止まったかのように凍りついていた。唯一「全機能停止まで、
二人目のヴァンパイアに声を掛けている時、ナナクサの耳に量子脳とは別の声が飛び込んできた。塔の下で他の犠牲者を助けていたわるジョウシの声だ。彼女がどうして城砦内にいたのか訝る気持ちが、やっと頭をもたげたが、ナナクサは仲間がこの場にいてくれることに安堵し大きく力づけられるのを感じた。しかし同時に彼女の耳の中に、またしてもあの忌まわしい声が蜘蛛のように這いこんできた。始祖ブロドリップの声だ。
「麗しき同胞愛だな、我が妃よ」
ナナクサは頭を振り、前世で自分を不幸のどん底に叩きこんだ元凶を努めて無視しようとした。
「同胞」始祖は珍味を楽しむように、自ら口にしたその言葉を再び口の中で転がした。「だが我れには左様なものなど不要だ。我れに
「私はお前の妻でもないし、彼らも私もお前と同じヴァンパイアじゃない」ナナクサは我慢できずに思わず言い放った。「もう私らに構わないで!」
「なるほど」始祖のブロドリップは、くっくっと咽喉で笑った。「なるほど。掃除は嫌か。ならばここにいる人間どもにさせるとしようか」
それまで動きを止めていた
「やめてー!」
ナナクサは自分の絶叫が届くより速く、攻撃を加えた戦士の一団を見えない刃で一瞬のうちに薙ぎ倒した。そして新たな一団に向かおうとしたとき、始祖に両肩をがっちりと掴まれて動きを封じられた。
「せっかくのショーを止めるとは無粋な」
「遊びじゃないのよ。王なら王らしく一族の者に慈悲の欠片くらい与えられないの?!」
「これは、これは。やっと
「酷すぎる」
「先刻も言うたであろう。我れには敵や仲間。ましてや世界すらも要らぬのだ」始祖の目が赤黒い輝きを増した。「喉を潤し、ただ退屈を紛らすモノさえあればよい。ただただ、この世を楽しめさえすれば、それでよいのだ」
ナナクサは渾身の力を込めて始祖の両手を振り解くと、人間に向かうのとは別の怒りを込めて、その横面を張った。
「あのときと同じ」始祖は醜く顔を歪めて、またクックッと笑った。「あの時の貴族の女と同じように傲岸不遜なのは今のうちだ。お前もすぐに我が力の前に跪くのだ」
「そんなことはない!!」
言うが早いか、始祖が後ろから重機のような力で抱きすくめられた。ナナクサによって
「我れは汝らの始祖なり」四散した
ナナクサは闘技場に引き立てられてくる前に自分を襲った異変を思い出した。きっと、あの時もそうだったのだ。ブロドリップは傷ついたのだ。なぜだかナナクサにはそれがわかった。そして奴に創りだされた者たちは、その創造主が受ける苦痛を直接に自分たちも受けるのだということも。始祖はそんなナナクサの考えを肯定するように無言で大きく頷いた。その表情には残酷な事実が刻み込まれていた。これで、やっとわかったろう。お前たち子孫は決して創造主たる自分には抗うことなどできはしないのだと。だが、ナナクサの心はそんな始祖の優越とは別次元にあった。始祖も傷付き、苦痛を感じるなら、共倒れになろうとも
彼女が咄嗟にそう思わずにいられなかったのには、もう一つ理由があった。戦士たちの存在だ。先ほどの
「これは驚いた。抗うことなど無意味だと諭したはずなのに。自暴自棄にもほどがある」
ナナクサは「自暴自棄で結構」と思いながら、休むことなく伸ばした鋭い爪の斬撃を始祖に浴びせ続けた。始祖は癇癪を起した幼児の突進を受け流すベテラン保育士のように繰り出される斬撃を紙一重で悠々とかわしていたが、やがて飽きたかのように右手を無造作に差し出すと、わざとナナクサの斬撃を受けた。始祖の右肘から先が鈍い音を立てて宙を飛んだ。その瞬間、ナナクサとジョウシ、それに助けられたヴァンパイアたちは同時に右肘に激痛を覚えて悲鳴を上げた。そして、ある者は肘を押さえて跪き、またある者は、その場に倒れ伏した。
「この地に我が子孫どもが、どれほど満ちておるかはわからぬが、この激痛は
「耳を傾けるな!」
叫び声の先にはジョウシがいた。彼女は腕に激痛を感じなかったかのように、戦士たちから射かけられる矢を次々と払っては、弱ったヴァンパイアたちを守っている。しかもファニュや瀕死のクインまで。
「そ奴が死を感じるより素早く
「わたしもそう信じるわ、ナナクサ!」
さっき怒りに任せて自分が殺しかけた人間までが、デイ・ウォークの仲間と共に命懸けで闘っている。見知らぬヴァンパイアを守って命懸けで奮闘している。ナナ・ジーランドとルーシー・ギャレットが過去に為し得なかった不信の壁を崩し去ることなど目の前の若者たちには端から必要はなかったかのように。
遠くの方でクインが大声で戦士たちを威嚇し、ファニュが若いヴァンパイアを拾った盾で庇っている。その横では傷ついたエイブが果敢にクロスボウの矢を放ち、ジョウシはナナクサに大声で叫びかけている。
「ナナクサ。お前が為すべきことを……」
その時、千切れ落ちていた始祖の右腕が矢のように飛んでジョウシの身体を貫き、彼女の内臓の大半を残りの言葉ともどもむしり取った。ナナクサの悲鳴をよそに宙を大きく旋回した右腕は赤く染まった矢となって、次にファニュに襲い掛かった。彼女は左頬を深く切り裂かれ、その衝撃で大きく後ろに倒れこんだ。本来なら寸分違わず首を切り落とされていたであろうファニュが助かったのは始祖が当然、予期していたナナクサの反撃ではなく、弱りきった若いヴァンパイアたちの存在をまったく考慮していなかったためだ。効果的とは言い難いながらも、彼らの投槍と弓は始祖の注意を逸らせるのに十分な効果を上げた。目覚めてからの短い時間の中で、彼らもまた自分たちが、いま戦うべき相手が人間の戦士ではなく、目の前に君臨するものであることを敏感に察知していたのだ。
ナナクサは始祖が注意を削がれた一瞬を見逃さず、その背中に飛び蹴りを見舞った。彼女は渾身の一撃で始祖の身体が弾き飛ばされた遥か先を確認することもなく、血溜まりに横たわる仲間の許に瞬時に駆けつけた。
「ジョウシ!」
「ナナクサ……」
ナナクサの問いかけに応えるかのようにジョウシの胸に空いた穴からも、ひゅうひゅうと空気の漏れる音が聞こえた。心配そうにその傷を押さえる痩せ細ったヴァンパイアの反対側に跪いたナナクサはジョウシの手を強く握り、彼女の言葉を少しも聞き逃すまいと微かに動くその口元に耳を近づけた。先ほどまで憤怒に駆られた冷たいガラス玉だった彼女の瞳は仲間思いの若者のそれに戻っていた。彼女はジョウシの口元から顔を離すと、「タンゴ……」と絶句し、声もなく、「そんな。駄目よ。あなたまで……」と首を横に振った。そしてジョウシの頬に優しく手を触れようとしたとき、黒い風がナナクサをさらい、彼女の身体を壁の上方に激しく叩きつけた。
黒い風は始祖の姿に戻ると、めり込んだ壁から身を引き剥がしたナナクサを後ろから抱きすくめ、その白い首元に深々と牙を突き立てた。ナナクサは金縛りになり、口から声にならない嗚咽が漏れた。嗚咽は激しい嫌悪からくるものなのか、死にゆく仲間に何もしてやれない無力感からくるものなのか、彼女自身にもわからなかった。ただ、始祖に血を吸われながらも、その眼は仲間たちを求めて闘技場内を彷徨った。すると遠くの壁に埋め込まれた鏡面状の大きなモニターに映し出される不可思議な光景に目が留まった。
鏡の中には巨大で醜悪な量子脳と、そこに迫りくる戦士の一団に対峙する仲間たちが確かに見える。やがて、それらを隠すように煙草の煙状の赤い靄が鏡面に滲み出ると徐々に人の形をとり始めた。薬師であるナナクサには、それが何であるか
そうか。魂を持たないヴァンパイアは鏡に映らないんだったっけ……。ナナクサはナナ・ジーランドの記憶から漠然とそんな事実を紐解いた。ナナクサは思った。以前のように鏡に自分の姿が映るということは、さっき身体に取り込まれた
そう。力を失う代わりに、魂を持った、ただのヴァンパイアにまた戻れたのだ。始祖は私を殺すのだろう。力を奪うとはそういうことだ。私には到底それに抗うだけの力はない。でも魂を取り戻せて死ねるなら、それもいいかもしれない。いや、駄目だ。もう一人のナナクサが心の中で抗う。いま死ねば残った仲間たちを守ることができなくなる。彼らは希望だ。彼らを守ると、さっき決意したばかりじゃないか。でも創造主の力は絶大だ、と別のナナクサがすぐに囁く。でも……でも……この期に及んで、ナナクサは今までの人生が逡巡と後悔の連続だったことに思い至った。ミソカとジョウシの不仲をどうすればいいかわからず、積極的に関われなかったこと。タナバタに自分の想いを告げるのを躊躇ったこと。それどころかファニュに同行して一族の謎を解こうと選択した結果はどうだ。選ばなかった結果も、選んだことの結果も同じじゃないか。残るのは後悔。そもそも私には後悔を受け入れる勇気すらなかったのだ。だから、「まぁ、いいか」と、満足できない結果も、まるで他人事のように今まで無視してこれたのだ。そんな私がデイ・ウォークに参加するだなんて端から間違ってたんだ。こんな半人前は、このまま始祖に殺された方がましなんだ。ナナクサの心は弱まり、始祖の黒い影に覆われていった。
*
「なんという興醒めだ」ナナクサの首から頭をもぎ離した始祖の口から怒りを含んだ落胆が漏れ出た。「屈服どころか覇気すら失せ果ててしまうとは。お前は愚かすぎた。あぁ、もうよい。妃など、お前でなくてもよい。しかし今までの不遜に応じた報いは、くれてやらねばならぬな。か弱き者どもが人間どもに滅ぼされる様を見物しているがよい。お前は、その後で、ゆっくりと
*
「ほんとの敵は、あそこよ。あんたら、そんなこともわかんないの!」
切り裂かれた左頬の激痛に耐えながらも、ファニュは迫りくる戦士たちを罵倒して、手にした弓を始祖に振り向けた。
「そんなことしたって無駄だ。奴らにゃ、関係ないって」
油断なく戦士たちの動きを監視しながらクインが言い返した。
「奴らは見た。そして知った」量子脳に背をもたせ掛けたエイブが苦しい息の中で口を開いた。「
「こんな時に、何わけのわかんねぇこと言ってんだ」
「頭を使えってことさ。隊商で、そう教わらなかったか」
そこまで言うと、エイブは床のボウガンを引き寄せた。その横には虫の息のジョウシがいたが、彼女の目も、まだ希望を失ってはいなかった。ファニュは彼らの言わんとすることを
「次の
言うが早いか、ファニュはジョウシの懐から銀のナイフを抜き取ると闘技場に背を向けてナナクサを捕まえている始祖に向かって全力で駆け出した。エイブに促されたクインも「待て。次の
量子脳に迫りつつあった戦士たちは、二人の突然の行動に躊躇したものの、暴力と打算の中で生きてきた彼らは、すぐさま二人の動きに触発されて、雄叫びを上げて、その後を追いはじめた。そしてファニュがナイフを腰に差し、弓につがえた矢を放とうとしたときには、最初の一団が彼女とクインを追い越していった。
*
始祖の力の前に、すべてを諦めはじめたナナクサは戦士たちの雄叫びを遠くに聞きながら、瀕死のジョウシから託されたタンゴの形見を無造作にまさぐった。彼女の脳裏に幼馴染の笑顔とともにチョウヨウがファニュに言った言葉が蘇った。「これから一生、爪先を見ながら歩き続ける人生でいいのか」と。いいわけないじゃない。でも、どうしようもないのよ。ナナクサは自答して十字架を強く握りしめた。角が手のひらに食い込んで血が滲んだ。痛いのは嫌いよ。考えるのにも疲れたわ。しかし考えずにおこうとするほど、仲間との過去が蘇った。悪戯をしたジンジツをジョウシが追い掛け、それを囃し立てている四人。朝更かしで、寝ずにいつまでも語り合った雪の中。短くも充実した時間。結果や後悔はどうあれ、彼らはそれを超えて自分の一生を歩ききったのではなかったろうか。ふと、そんな考えが頭をよぎり、ナナクサは自分の中に言いようのない後ろめたさが生まれているのに気づいた。そうだ。どうせ、これで最期なら、後悔だって、これで終わりだ。すごく簡単なことだ。私は私で自分の一生を歩き切ればいいんだ。
ナナクサはタンゴの形見を、自分の身体を抱きすくめている始祖の左手の甲に押し当てると左手も添えて包み込むように両手で強く握りこんだ。始祖の身体がびくっと引きつり、頭の上から怒気を
「よくも、やってくれたものだ……」
始祖は手の甲に黒く焼き付いた十字架の痕を忌々しそうに睨みながら声を絞り出した。ナナクサは声の先に右手のひらを挙げると手の中にある形見の十字架を挑むように掲げて見せた。彼女の手のひらには焼け焦げはおろか、小さな傷ひとつ付いてはいなかった。
「この下衆が!」
始祖の身には、いつの頃からか中世の大貴族が身体の隅々まで染みついていた。それは自分がかつて、どのような存在だったかも忘れさせるほどのものだった。かつては気まぐれに、ばら撒かれる大仰な寛容さを頑なに拒み続ける者には例外なく激烈な反応を示してきた。今がまさにそれだった。しかし、それが判断を鈍らせ、始祖は数十世紀ぶりに人間に後れを取ることになった。始祖はナナクサの不遜に激情を向けすぎるあまり、ファニュに先導された戦士たちの接近に気づかず、彼らから放たれた矢の一本を足首に受けたのだ。銀の矢尻が付いた矢は始祖に肉体的な苦痛をもたらしたが、それ以上に肥大化した自尊心が屈辱と怒りにむせび泣き、暴れ狂った。
どいつもこいつも逆らうことしかしない。それが、あたかも自分たちの存在理由であるかのように。こんな奴らには身の丈を遥かに超えた絶望と苦痛を与えねば気が済まぬ。
始祖の両目が赤黒く輝き、その口から呪詛の声がほとばしった。もはや感情を抑えることなど出来なくなった始祖の頭には闘技場どころか、この城砦に生きとし生ける者すべてを破壊することしかなかった。
始祖の呪詛に合わせて闘技場の石造りの重厚な壁と床が激しく振動しはじめ、闘技場内に黒い竜巻がいくつも出現して吹き荒れはじめた。それは地中から鎌首をもたげた大蛇のように見えたが、戦士たちを直接襲うことはせず、床にある様々な死体を次々と呑み込んでは、その首や四肢を渦の中でねじ切り、強風に翻弄される戦士たちに投げつけはじめた。飛んでくる四肢は辛うじて盾で防ぐことはできるものの、時折それらに混じって飛んでくる剣や槍が戦士の盾や鎧を貫き、命を落とす者が続々と出はじめた。それでも黒い竜巻は一気に戦士を殺し尽くすことはしなかった。迷走台風のように、突然進路を変えては残った戦士たちを嘲弄し、逃げ回る姿を楽しんでは呑み込み、首や手足をもぎ取って紙屑のようにばら撒くことを繰り返した。始祖は激情が収まるまで、竜巻を使って、ゆっくりと殺戮の宴を続ける心づもりだったが、果たして激情が収まるのかどうかは、もはや始祖自身にもわからなかった。
阿鼻叫喚の闘技場内で、始祖の怒りに取り残されたナナクサは黒い竜巻の一つに呑み込まれる寸前の戦士の集団にファニュの姿を見た。十字架を首にかけ、咄嗟に駆け出したナナクサは迫りくる竜巻を回避しながら人間の仲間のもとに急いだ。結果がどうあれ、これが最後だと思うと折れた肋骨の痛みも忘れ、身体の中から力が沸き上がってきた。ナナクサは間一髪のところで、空中に舞い上げられたファニュの身体を掴んで床に引き戻した。ファニュの力強い眼差しがナナクサを捉えた。
「これが最後よ」
ナナクサは自分に納得させるように、そう言うと指でファニュの頬の傷から、まだ粘り気を残す固まりかけの血を少しすくい取った。そして自分の唇につけると、素早く指を横に引いた。赤黒い血の口紅はナナクサの白く端正な顔を妖艶に彩り、彼女の黒髪をざわめかせた。舌で舐めとらなくてもヴァンパイアの身体はすぐさま反応して、唇から血を吸収し始めた。ナナクサは折れた肋骨がぎしぎしと音を立てて急速に修復していくのを感じると同時に、人間の血を口にしたことで首にかけた十字架の下の皮膚がちりちりと痛んだ。
「これを持っていって!」
ファニュはジョウシの銀のナイフをベルトから引き抜くと、ナナクサにそれを手渡した。ナナクサはナイフを受け取ると、銀の影響で手が焼け付き始める前に、無言でそれを背中のベルトに挟み込んだ。
「わたしはジョウシや助け出された人たちのところに戻るわ!」と、ファニュは竜巻に負けないくらい声を張り上げ、しばし口をつぐんだあとに付け加えた。「また、あとでね!」
ナナクサはファニュの言葉を背にして、何本もの黒い竜巻の向こうに駆け出した。
ナナクサは始祖の姿を認めると最後の戦いを挑んだ。彼女は一番手前の竜巻の中に飛び込むと、その中に舞い踊る抜き身の日本刀をつかみ取った。ナナ・ジーランドの記憶によれば、これは近接戦闘用武器の中でも、有史以来、最も洗練された最強のもので、奇しくも戦士軍団との夜の遭遇戦でナナクサが初めて手にしたものそれだった。日本刀を手にしたナナクサは、その柄をしっかり握り、ヴァンパイアの闘争本能を頼りに始祖目がけて幾度となく斬撃を見舞った。だが、鋭い刃は、まるで立体映像を相手にするように、始祖の身体を通り抜けて、ことごとく空を切った。武器が役に立たないとわかると、次にナナクサは首にかけた十字架を再び使おうと手を伸ばした。
その瞬間、ナナクサの口の中で太い枝が折れるような音がして身体が後方に弾き飛ばされた。気づいた時には床に横たわり、右顔面に広がる激痛が、その後にやってきた。ナナクサには何が起こったのか、皆目わからなかったが、口中に広がる鉄の味と舌の感触で何本もの奥歯が折れ砕けていることがわかった。衝撃で側頭部がずきずきと痛む。血とともに奥歯の残骸を吐き出すのが、出来ることのすべてだった。ナナクサは落ち着いて呼吸を整えた。ファニュの血が傷を急速に修復するにつれて痛みも消えたが、疑問が残った。始祖は動いた形跡がまったく認められないのに、どんな方法で自分は打ち倒されたのだろうかと。だがナナクサの疑問は始祖の変容に虚を突かれて中断された。始祖は既にブロドリップという洗練された貴族の姿ではなくなっていたのだ。耳元まで裂けた口から何本もの尖った牙を覗かせ、身体も一回り大きく膨れ上がっている。猫背の上に載っている頭には頭髪がなく、異常に長くなった指に
始祖の第二撃はすぐにきた。今度はえぐり込むように始祖の脚がナナクサの腹に深々と刺さった。肺から空気が絞り出され、くの字に曲がった身体は上方にはね飛んだ。また見えなかった。始祖はナナクサの傍に突然現れて攻撃を加えたのだ。また急速に身体の傷が修復され、遠のく意識に歯止めがかかった。いまナナクサの身体が人の血でヴァンパイアの能力を極限まで引き出せているとはいえ、このままでは、いずれ限界が来る。それまでに答えを見つけなければ終わりだ。何としても攻撃のトリックを暴かなくてはならない。ナナクサは始祖の動きに全神経を集中させた。悪鬼のような姿が、ほんの一瞬だけゆらぎ、そして消えた。次の瞬間、ナナクサは背中に一撃を受けて、今度は身体が大きく前に吹き飛ばされた。瞬間移動?……。心の中にあるナナ・ジーランドの科学者の常識は、ナナクサの突飛な考えを否定した。しかし、直面した事実は、それを裏付けている。では、どうやって?
「我れは、この地にある
ナナクサの心を見透かしたかのように始祖の考えが頭の中に響いた。だが、なぜかそれは嘘だと、ナナクサとナナ・ジーランドは直感した。因果律さえ操れるのなら、いくら楽しみのためとはいえ、十数世紀もの長い時間を人間たちと対峙してはこなかっただろう。それに全てを支配できるほどの存在なら、私の反抗など些細なことに違いない。あの憎しみの強烈さは本当の絶対者のそれではない。どう考えても虚偽だ。嘘をつくのは自信のなさの表れだ。始祖は人の血で持てる力が解放された子孫に対して本能的な畏れを感じているのかもしれない。だから嘘で威圧しようとしているのだ。そう考えると、夜空に星をちりばめたナナクサの瞳がいっそう力を増した。
そして、また一撃された後だったろうか。気づくと目の前に音のない風景が広がっていた。ナナクサは自分の身体が写真や絵画の中にぽつんと置かれたのではないかという錯覚を感じた。眼前に広がる竜巻の動きも、それに翻弄される戦士の動き、そして始祖さえも凍り付いた世界。時間が止まってしまったのだろうか。そんな馬鹿な。ナナクサはよく目を凝らして、いま一度目の前の世界を凝視した。そして竜巻の中に舞い踊る武器や戦士の身体が注意しなければわからないくらい、ほんの僅かずつではあるが動いていることを発見した。時間が止まったのではなかった。切り取られた一瞬が引き伸ばされたように感じる世界にいるのだ。とにかく自分の意識が極端に遅くなった時間を感じているのか、通常の時間の流れを光よりも速く自分が認識しているのかのどちらかだろう。もし、どちらであっても、その奇妙な時間の流れに身体を泳がせることさえできれば瞬間移動と同じことだ。ナナクサは始祖のトリックがわかったような気がした。だが、どう強く念じ、どんなに力を出そうとも彼女の身体は金縛りに遭ったように、その場から微動だにしなかった。まるで硬い氷山に閉じ込められたように髪の毛の一本までもが固められている感覚なのだ。まったく動けない。突然、無防備になったような気がしてナナクサは焦りはじめた。そんな彼女の中で科学者だったナナ・ジーランドの記憶が再び紐解かれ、類推を始めた。意識は時間の流れを超越できても、物理法則を自在に操ることはできない。何も存在しないかに見える空間にも空気があり、その空気の一分子すら物理法則に縛られている以上、それに力を加えて動かすのは山を押して動かすことよりも難しいことではないのかと。それでも何とか動こうと方法を模索し続けるナナクサの視界に辛うじて人の形だとわかる黒い揺らぎが映り込んだ。徐々に近づいてくるそれはまぎれもなく始祖だ。仰々しく形を変えて迫らなくても、あの悪鬼の姿でとどめを刺しに来ればいいものを。胸から背中にかけて突き抜ける衝撃を受けながら、ナナクサは始祖の所業に腹立ちどころか嫌悪感よりも不思議さを覚えた。彼女の意識は衝撃を受けた瞬間に通常の時間の流れに連れ戻され、身体は竜巻に呑まれて、受け身も取れないまま、量子脳近くの床に叩きつけられた。背中に激痛が走るが、牙を食いしばって頭を上げる。竜巻からジョウシを庇うファニュや若いヴァンパイアたちと目が合った。彼らの姿の遥か向こうには再び悪鬼の姿に戻った始祖がいる。
「怖かねぇぞ!」クインが内心の恐れを悟られまいと始祖に剣を向けて声を張り上げた。「見ろ。あれじゃ、氷河祭りの山車そのものだ!」
「黒い揺らぎになったり、あの姿に戻ってみたり。かなり怒ってるのだけは確かよ」
「怒ってるのは、あの姿を見ればわかるわ」ファニュは頷いたが、ナナクサに正気かと言わんばかりの目を向けた。「でも、奴はあのまま。ずっと、あの吐きそうな姿のままよ!」
ナナクサは、まるで殴られでもしたかのように、まじまじとファニュの顔を見つめた。大昔に生きたナナ・ジーランドは物理学者ではなかったが、物質の基本概念は知っていた。また物理学者ではなく、発想力に富んだ生物学者だったからこそ、並みの物理学者よりも柔軟に物事を考えることもできた。彼女の記憶を身に宿したナナクサは咄嗟に時よ止まれ、と強く念じた。目の前で竜巻の動きが緩慢になり、やがて、先ほどと同じく全ての音がぴたりと止んで静止画になった。彼女の意識が時間の流れを、また完全に掌握したのだ。竜巻の向こうに視線を移すと始祖の姿が早くも滲みはじめ、海中を進む鮫のように、ゆっくりとこちらに進んでくるのが見えた。ファニュには見えず、自分には見える滲み。正しくは極端に緩慢な時間の流れの中でしか見えない始祖が移動する姿。でも、なぜまたあの姿に。何か意味でもあるのだろうか。もし、あると仮定すれば、その姿にならねば移動できないのでは?。そうだ。答えはそれだ。始祖は姿を変え、もったいぶって進んでくるのではない。たぶん、その力をもってしても自身を取り巻く物理法則を完全に捻じ曲げることは叶わないのだろう。空気分子ひとつ自由にできない世界では自分をそこに合わせねばならない。だから、滲んだ姿に変わるのだ。姿を自在に変化させられる始祖は分子よりさらに小さく自分の身体を縮めることで原子の周りの電子雲の中に隙間を見つけては、そこを通り抜けることを繰り返して移動しているに違いない。まるで紙を透過する水のように。その方法を使うから、必然的に姿が滲んだように見えたのだ。ナナクサには、この仮説が正しいかどうかはわからない。だが、正しいと信じて、こう思うことにした。稲妻を凌駕する速度で移動できる始祖も、この時間の流れの中では速くは進めない。だったら時間の流れを掌握できた自分にも始祖と同じことができないわけがない。身体を変えるのだ。いや空間の中に溶け広がるのだと。
ナナクサは自身の身体が散逸しないように注意しながら、空間に存在する原子と電子雲を必死にイメージしはじめた。