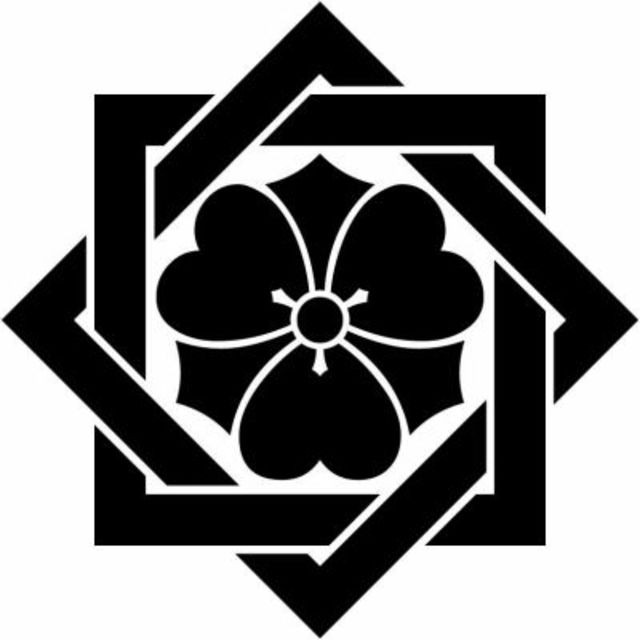第13話 逃亡
文字数 8,631文字
ファニュは逃げ出した。
ファニュはまんじりともせず、その後の長い夜をやり過ごすと、予想通り彼らは夜明けとともに、入り口を雪で塞いでみな眠りはじめた。
足音を忍ばせ、眠り込んだ彼らの枕元をそっと抜け、モグラのように氷穴を掘って外に出てみると、幸いにも雪嵐 は止んで燦々と太陽が照っていた。陽の光を見て安心した少女は出てきた穴を慎重に雪で埋め戻すと、後ろを振り返りもせず歩み始めた。行く宛はなかった。隊商を探そうにも自分が今どこにいるかがわからなかったからだ。しかし一刻も早くここを離れるに越したことはない。どこでもいいから、とにかく離れるのだ。
夜明けとともに石のように眠るなんて、人の形はしているが、彼らは話に聞いていたあの化け物に違いない。その中にあって、よく無事でいられたと少女は自分の運の強さに呆れると同時にその悪運に感謝した。少女は昨夜のことや隊商のことなど色々なことを考えながら左右の足を前に出し続けた。だが深い雪に足を取られて遅々として進む速度は上がらない。それでも彼女は一所懸命に移動し続けた。
夜明けから数時間移動したところで少女は激しい疲労から睡魔に襲われた。昨夜、徹夜したツケが回ってきたのだ。振り返ると一夜を過ごした氷塊が地平線の彼方に、まだ微かな姿を留めている。『まだ、頑張らなくちゃ』と自分を鼓舞するが、もう一歩も歩けそうにない。ここで休息を取ってから、また移動するか、それとも倒れるまで歩き続けるか。どちらも良い案ではないように思えた。
その時、氷塊とは反対方向に雪煙をあげる小さな動きが見えた。疲れで幻覚が見えているのかとファニュは頭を振り、目を擦ってみたが、その雪煙は視界から一向に去らなかった。見覚えのある雪煙。でもそんな奇跡はあるはずがない。世話役が持っていた双眼鏡 があれば確かめられるのに。少女は突然、呼子 を持っていることを思い出した。化け物に盗られてなければ、まだカバンの中にあるはずだ。彼女はカバンの中身を雪上にぶちまけるようにして呼子 を探した。それはすぐに見つかった。大きく息を吸い込むと一気に息を吹き込んだ。空気を送り込まれた呼子 は鋭い音を二度、三度と発して、何もない広い雪原の空気を震わせた。少女は、それでも足りないとばかりに何度も呼子 を吹き続けた。やがて呼子 から放たれた音を捉えた雪煙は、それを頼りにどんどん近づいてきた。ファニュは体中にアドレナリンがみなぎり、眠気が吹き飛ばされるのを感じた。
雪煙は少女の目の前まで来ると一声、いなないて大人しくなった。大人しくなると大きな胴をブルブル震わせ、白い体表にネオンのような青い光の波を明滅させた。雪の上を走ってきた十本の逞しい触腕の両横に付いている大きな二つの目も安心したのか、とろんとリラックスしている。雪走り烏賊 だ。しかも野生ではなく、胴体に手綱が縫い付けてあるところをみると、明らかに人に飼い慣らされていた一頭だ。
少女は雪走り烏賊 の明滅する胴を愛おしく撫でた。烏賊は雪に埋もれた口吻から雪を跳ね上げて、嬉しそうにまた一声、いなないた。胴を撫でている少女の手が焼印の所で、はたと止まった。まさかと思った。少女は目を凝らしてよく見てみたが間違いはなかった。
「どこかの隊商の先遣 からはぐれたのかと思ったのに、お前は……」
少女の口から自然と声が漏れた。その焼印は十三才のファニュ本人が所属する隊商のものだった。
「なぜ、お前が馭者もなく一頭だけでいたのかわからないわ」不安と焦りから、ファニュは堰を切ったように烏賊に話しかけた。「でも賢いお前なら隊商の所まで、きっと、あたしを戻してくれるでしょ。休むのは、その後よ。さぁ出発しましょ」
*
「どこに行ったんだろ?」
タンゴの苛々した声がチョウヨウの怒りに火をつけた。彼女は『あんな不気味な小娘にうつつを抜かす暇があったら、目的地まで先を急いだらどうなの』と、今にもタンゴに食つかんばかりに両方の拳を腰に当てて、その巨漢の背中を睨みつけた。しかし月明かりの雪原に少女の姿を探すタンゴから少し離れた所で、頭を寄せ合うタナバタとミソカの姿を認めて怒りの言葉を飲み込んだ。死を賭した苛酷さゆえにデイ・ウォークで親密になる男女はいるのだろう。現に自分も失踪した娘に嫉妬するくらいなのだ。でも、あの二人とは。
*
「あの時みたいに皆より早く見つければいいのよ」と、優しげにミソカがタナバタの耳元で囁く。
「いいや、駄目だよ。そんなこと」
「今さら何言ってんの」
「やっぱり、駄目だ」
「もう決めたでしょ、私たち。さぁ元気を出して」
チョウヨウには二人が何について話しているかなどわからなかった。大人びたタナバタが、か弱いミソカに元気づけられているなど、それだけで見物だ。それに年ごろの娘として二人の秘め事に少なからぬ興味もある。だが、それに嬉々として首を突っ込む悪趣味も彼女は持ち合わせてはいなかった。女子だけで、また秘密の雪語りをした時にでもミソカから二人の関係は話してくれるだろう。その時には興味津々で根掘り葉掘り聞いてやろう。
でも、よりによってタナバタとミソカとは意外だ。以前はナナクサの方がタナバタと親密に話をしていた姿を見掛けていただけにチョウヨウの心は複雑だった。
*
ナナクサは心を侵食する寂しさの陰で、幼馴染みの小さな手のひらが頭一つ分は高い薬師 見習いの仲間の頬に添えられるのを見た。彼らは二人とも自分にとって大切な存在だ。でも心の中では抑えがたい感情も疼いてはいる。
体の強くないミソカを小さな頃から姉のように見守ってきただけに彼女に想い人ができたのなら、それはそれで嬉しい。でも、博識で礼儀正しいタナバタの大人びた所に自分が惹かれていたのも確かだ。旅を続ける中で言葉に出さなくともタナバタもその気持ちは察してくれていたのではないか。彼との関係は薬師 見習い同士の単なる職業的なものだったのか。いえ、そもそも彼を想う気持ちがそんなに強かったのだろうか。ナナクサは自分でもはっきりとしない自身の心の中にそう問いかけ続けた。
ジョウシにはジンジツが。チョウヨウにはタンゴ。そして、ミソカにはタナバタ。でも私には……。一体この気持ちをどう理解すればいいのだろう。嫉妬。羨ましさ。それとも……。取り残され感。そうだ。自分の心を支配しているのは、きっとその気持ちなのだろう。そうならないように必死に生きてきた自分が、今そうなっただけなのだ。でも、そう考えると何もかもが味気なく、無性に煩わしく思えてくる。取り残された疎外感が寂しさと敗北感に変わってくる。それが理解できただけに、一層、落ち込んでもくる。それでも表面的には何事もないように演じ続けてしまう自分が堪らなく嫌だった。自分自身を嫌いになってしまいそうで、どうしようもなかった。まったく最悪な気分だ。
「ナナクサ、話があるんだ」
感情の負の連鎖を断ち切る突然の呼び掛けにナナクサは飛び上がりそうなほど驚いた。
「タ、タナバタ」
ナナクサは声の主を確認すると、思わず周りに視線を走らせた。
「大事な話なんだ」
タナバタはそう言うとナナクサの二の腕をしっかりと掴んで自分に引き寄せ、人気のない氷塊の裏まで彼女を引っ張って行った。ナナクサはタナバタに引っ張られながら、彼の手の感触を楽しんでいるもう一人の自分がいるのを感じていた。
「で、話って?」ナナクサは氷塊の裏まで来ると、素っ気なさを装おって口を開いた。
「手伝ってほしいんだ。君にしか頼めない」タナバタはナナクサの返事を待たずに言葉を継いだ。「あの少女を。ファニュを誰よりも早く見つけなきゃならない。いや、本当は見つけない方がいいのかもしれない。僕が間違ってたんだ、あぁ、そうだ。今ならそれがわかる。本当に馬鹿だったよ……」
「あなた何を言ってるの?」
まるで自問自答するようなタナバタに、ナナクサは戸惑いを感じた。
「お願いだ。君にしか頼めない」
空いているタナバタの手が伸ばされ、ナナクサの頬に触れた。ナナクサは体の芯がカッと火照り、戸惑いから生じかけた疑問の言葉を飲み込んだ。
「その時が来たら、驚くかもしれない。でも……でも僕を信じて助けてくれ、いいね」
冷静さが売りのタナバタの目が熱を帯びているのに気押されたナナクサは思わず頷いた。それを見たタナバタは寂しそうに微笑むと他の仲間の所へそそくさと戻って行った。
ナナクサは呆然とその後ろ姿を見送った。
*
ファニュの捜索は最大で三日と決められた。タンゴは異議を唱えたが、デイ・ウォークの旅程をこれ以上、逸脱できないことはタンゴもわかっていたので、これがパーティ全員の了解事項となった。捜索はデイ・ウォークの目的地に向け、雪嵐 のように半径二十キロ程の円を描くように進められた。
一日目は何も発見できなかった。二日目も同じだった。タナバタとミソカは夜明け前の数時間、二人で仲間の前から姿を消すことがあったが、みな何も言わなかった。そして三日目の夜も過ぎようとしていた。
この日の当番で棺桶穴 に入る準備を一人でしていたナナクサは、月明かりを遮る影に気付いて顔を上げた。そこには真っ青な夜空にシルエットを浮かび上がらせたタナバタが立っていた。
「早かったわね」自分の心とは裏腹にナナクサは、素っ気なく声を掛けた。「皆はまだ帰ってないわ」
「来てくれ、ナナクサ」
逆光となって表情はわからないながらも、その声は緊迫していた。
「『来てくれ』って、どこへ?」
「少し北東へ行く」
わけもわからず立ち上がったナナクサは今まで目の前にいたタナバタがいつの間にか自分の背後に回っているのに驚いた。振り向いて声を掛けようとしたとき、タナバタの両腕がナナクサを背後からしっかりと抱きしめた。細いながらも引き締まったタナバタの胸と腕の感触を感じながらナナクサは嬉しさと羞恥で頭の中が真っ白になった。
しかし次の瞬間、体がふわりと浮きあがり、思わず声をあげそうになった。
「大丈夫だ、しっかり掴まえてるから」
頭の後ろから聞こえるタナバタの緊迫した声は、決して安心と言えるものではなかった。質問をしたかったが、質問すればするほどパニックを起こしそうな自分がいることに気付き、ナナクサは口をつぐんで成り行きに身を任せた。
青く透き通った星空へ駆け上がり、その中を矢のように滑空するナナクサとタナバタの影が、遥か下に流れる雪原のスクリーンに映し出される。ありえない状況に戸惑いながらも、そのシルエットに見惚れていたナナクサは村の風車小屋の羽のような影がタナバタの身体の左右に大小二枚ずつ見えるのに気付いた。高度が低くなると時折、わさっとそれらが羽ばたき再び高く舞い上がる。
そう。これは翼なのだ。幼い頃に長 の老女 が子供たちに話してくれた古代の大絶滅 前に生きていた多種多様な生き物の中で、確か鳥とかいう動物が空を渡る時に使うものだ。それをタナバタが持っている。伝え聞いていた始祖 さまも持っていたのだ。それをタナバタが持っている。凄い。正直なところ、そうとしか言えない。
「今まで嘘をついていた」と、風を切る音に混じってタナバタの声が耳元に聞こえ、ナナクサの注意をひいた。「あの飛行船 の墜落現場で、僕は自分自身に御力水 を使ってしまった」
首を振り向けたナナクサは背中から真っ黒な翼を生やしたタナバタが痛々しい表情なのに気付いた。彼はナナクサの背後で懺悔し続けた。
「あれは僕たちが使っちゃいけないモノだ。瀕死の者の他は使っちゃいけないモノだったんだ。でも僕は誘惑に勝てなかった。もし健康な者が使ったら、どうなるか試したくって堪らなかったんだ。そのチャンスが目の前に転がってたんだ。でも間違いだった。あれは死にかけた者を呼び戻す強烈な力を持っている。ただ、それだけに普通の者が使うと始祖 の力を身体に呼び覚ましてしまう」
「力を呼び覚ます?」
「そう。今のぼくみたいに。でも……」
そこまで言うと急に押し黙ったタナバタに業を煮やしたナナクサは、思わず彼の緩んだ腕の中でするりと体の向きを変えるや、互いに向き合う姿勢を取った。今度はタナバタが驚いて失速しかけた。ナナクサは落ちないようにタナバタにぎゅっとしがみついた。彼が慌てて体勢を立て直すと、ナナクサは無言で答えを促した。
二人は抱き合ったまま暫く空を滑空し続けていた。月明かりで逆光になったタナバタのシルエットが口を開いた。
「副作用があったんだ」
「えっ、いったいどんな?」
「とても悪い副作用さ。凄く悪い。あれは不幸な力を呼び覚ます。だから、だから、早くあの少女を探さなきゃ」
「悪い副作用があったのはわかったわ。でも、なぜファニュを探すことと副作用が関係あるの?」
「それは………」
「ファニュが解毒剤を持ってでもいるの?」ナナクサはタナバタの首が力なく横に振られるのを見て、なおも捲 したてた。じゃぁ、解毒剤に関する知識を持ってるの。まさか、あのニンニクの実が?」
「どれも違うよ。解毒剤なんて無いさ。ただ、それをある程度抑える方法を考えついたんだ」
「抑えられるのね?」
「たぶん、ある程度ね」
「『ある程度』……」と、ナナクサはオウム返しにその言葉の重みを噛みしめた。
「劇薬を制するには劇薬を使う。そのためには品質の良い、穢れのない純粋なものでなければならないと思うんだ。だから、あの娘が鍵さ」
「いったい何を言ってるの?」
「僕だって薬師 の端くれだ。信じてくれ」
話を切り上げると、タナバタはナナクサを抱いたまま空を大きくバンクすると、ふわりと雪原に降り立った。
地上に着いた二人は抱き合っていた互いの腕をぎこちなくほどいた。ナナクサが見つめる中、タナバタの背中の黒くて大きな翼は塵が吹き飛ばされるようにサッと掻き消えた。タナバタは黙って自分を見つめ続けるナナクサの目を見つめた。青い夜空に星を散りばめたような綺麗な瞳だった。だがその瞳の中には、さっきの話の続きをしようと呼びかける無言の問い掛けがあった。タナバタはそれには答えず、視線を外した。
「この辺りに、あの少女の気配がする。さぁ、探そう」
*
ナナクサは行方知れずの少女の名前を叫んで何もない雪原を歩き回った。始祖 さまの力を発現したタナバタが言うのだ。ファニュはこの近くにいるのだろう。でもどこに。しかも肝心のタナバタは降り立ったあと、その場所で両手を握りしめたまま俯いて突っ立っているだけだ。
ナナクサは再び少女の名を叫んで歩き出した。歩いていると前方で雪が円形に盛り上がったところが、もぞもぞと動いたように見えた。彼女はその場に立ち止ると、しばらくその動きを注視した。気のせいかとも思ったが、確かにその円形の小山は一度動いたのだ。周りが平坦で動きがないだけにかえって、それはナナクサの注意を引き続けた。彼女は思い切って、その小山まで行くと、その端をブーツの先で突いてみた。雪とは違ったブヨブヨとした弾力がある。いや、正確には雪の中にその弾力がある。次に靴底全体で強く踏んでみた。今度は抗うように押し返す感触があり、ナナクサは思わず後ろへ飛び退って身構えた。小山は薄っすらと青白い光を明滅させたかと思うと、茹で卵が殻を脱ぎ去るように雪と氷をその表面から振るい落として白い身体を覗かせた。タンゴより大きい雪走り烏賊 だった。烏賊は全部で四頭。一頭が顔を覗かせると、次々とその白い胴体を雪の中から揺り起こした。話には聞いたことがあったが、初めて見る雪走り烏賊 はジンジツの命を奪った肉食の大海獣 とは違い、体を青白く明滅させて大人しくしている。この分では害はなさそうだ。
雪走り烏賊 の一頭が一声いななき、ナナクサの目の前でぶるっと体を震わした。そして丸めた胴体と、その下に折り畳まれた触腕をほどき始めた。ほどかれた触腕の下には怯えた表情のファニュがいた。
「ファニュ!」
緊張から自然に高まったナナクサの声は雪走り烏賊 のかまくら で休んでいた娘をすくみ上らせた。ナナクサは知らず知らず止めていた息を吐き出すと、努めて優しい声を少女に投げかけた。だがファニュを怯えさせた原因が自分でないことを、娘が凝視する先に視線を転じたナナクサはすぐに理解した。
「タ、タナバタ?……」
驚きで、つぶやきしか出なかった。しばらくして、やっと気を取り直したナナクサはタナバタの名を再び呼んでみた。それでも返事がないので、今度は大声で叫んだ。突っ立ったまま、両手で赤いシャーベットを貪っていたタナバタが反応して振り向いた。ナナクサはその赤黒く光る視線を捉えた瞬間、背中に冷たいものが走るのを感じた。直感的にタナバタが正気ではないと悟ったのだ。その顔は理知的であったことが嘘のように醜く歪み、大きく裂けた口からは喧嘩の時のように犬歯が鋭く伸びている。やがてタナバタは憑かれたように、一歩、また一歩と二人の方へ近づき始めた。
「タナバタ、どうしたの?!」
これが副作用か。そう直感したところでナナクサには何もできなかった。だからといって手をこまねいていることなどできない。ナナクサはタナバタに走り寄ると、彼を正気に返らせようとその二の腕を掴んで激しく揺すぶってみた。
「タナバタ。しっかりしてよ、タナバタ!」
それでもタナバタの前進は止まらない。彼の目は既にナナクサを見てはいなかった。彼女を通り越して雪走り烏賊 の触腕にくるまれた少女を凝視していた。なおも、すがり付くナナクサが数メートルも突き飛ばされた。遂にファニュの口から月夜を切り裂く悲鳴が上がった。ナナクサは立ち上がりながら、ファニュに近づくタナバタの姿を見て、さっき彼がファニュのことをしきりに言っていたのを思い出した。あれだけ固執していたのはファニュに何かをする気だったからだ。
ナナクサはタナバタの前へ出ると彼の頬を力一杯、平手で叩いた。それでも正気に返らないタナバタを後ずさりながらも叩きつづけた。気持ちを抑えきれず、つい伸ばしてしまった爪が、タナバタの頬を切り裂いても彼女は叩くのを止めなかった。ナナクサはまた突き飛ばされた。それでも諦めずに今度は彼の後ろから腰に両手を巻き付け、渾身の力で引き戻そうと試みた。しかし、雪の中を引きずられるだけで歩みは止まらない。ナナクサを引きずったまま、タナバタは逃げようとしたファニュに躍り掛かかった。彼は激しく抗う娘を容易に押さえつけると、長く鋭い犬歯で娘の首を貫こうと顔を近づけた。咄嗟に腰に回した腕をほどいたナナクサは、今度は後ろからタナバタの薄茶の髪の毛を両手で掴んで力一杯後ろに引きはじめた。彼の髪の毛が何十本も頭皮ごとメリメリ引きはがされる嫌な感触が両手に伝わる。牙の進撃が鈍ったが、ほんの少しだ。もう駄目だ。ナナクサがそう思った瞬間、電撃に貫かれたように半身を起こしたタナバタが悲鳴を上げてナナクサを振り払った。そして両手で顔を覆い、ファニュから離れると、くぐもった苦痛の叫びをあげながら雪の上に倒れ込んで、のた打ち回りはじめた。
雪の上に投げ出されたナナクサには何が起こったのかわからなかった。ただ考えられるのはファニュが何か対抗策を講じたのだろうということだけだ。でも何をやったのだろうか。それほどタナバタの苦しみ方は尋常ではなかった。ナナクサは凍てついた大気中を微かに漂う甘ったるい匂いの微粒子を感じ取ると、反射的に息を止めてその場から飛び退いた。何てことだ。あろうことか、ファニュはタナバタに猛毒を使ったのだ。薬師 の見習いとして毒物の知識がなければ、自分も不用意にそれを肺一杯に吸い込んで重体に陥るか、下手をすれば死んでいたところだ。
雪の中にうずくまり、肩で息をするファニュの傍らまで行くと、ナナクサは娘からまだ毒物の微粒子が微かに漂っているのに顔をしかめた。
「何てことするの、ファニュ。ニンニクを使うなんて、タナバタが死んだらどうするの?!」
ナナクサは怒りに任せてそう吐き捨てると、立ち上がれないでいるタナバタに目をやった。そして彼が生きていることに少し安堵した。
だが次の瞬間、安堵は強い驚きに吹き飛ばされた。
「タナバタも存外、情けないわね」
それはナナクサの幼馴染みの声。ミソカだった。
ファニュはまんじりともせず、その後の長い夜をやり過ごすと、予想通り彼らは夜明けとともに、入り口を雪で塞いでみな眠りはじめた。
足音を忍ばせ、眠り込んだ彼らの枕元をそっと抜け、モグラのように氷穴を掘って外に出てみると、幸いにも
夜明けとともに石のように眠るなんて、人の形はしているが、彼らは話に聞いていたあの化け物に違いない。その中にあって、よく無事でいられたと少女は自分の運の強さに呆れると同時にその悪運に感謝した。少女は昨夜のことや隊商のことなど色々なことを考えながら左右の足を前に出し続けた。だが深い雪に足を取られて遅々として進む速度は上がらない。それでも彼女は一所懸命に移動し続けた。
夜明けから数時間移動したところで少女は激しい疲労から睡魔に襲われた。昨夜、徹夜したツケが回ってきたのだ。振り返ると一夜を過ごした氷塊が地平線の彼方に、まだ微かな姿を留めている。『まだ、頑張らなくちゃ』と自分を鼓舞するが、もう一歩も歩けそうにない。ここで休息を取ってから、また移動するか、それとも倒れるまで歩き続けるか。どちらも良い案ではないように思えた。
その時、氷塊とは反対方向に雪煙をあげる小さな動きが見えた。疲れで幻覚が見えているのかとファニュは頭を振り、目を擦ってみたが、その雪煙は視界から一向に去らなかった。見覚えのある雪煙。でもそんな奇跡はあるはずがない。世話役が持っていた
雪煙は少女の目の前まで来ると一声、いなないて大人しくなった。大人しくなると大きな胴をブルブル震わせ、白い体表にネオンのような青い光の波を明滅させた。雪の上を走ってきた十本の逞しい触腕の両横に付いている大きな二つの目も安心したのか、とろんとリラックスしている。
少女は
「どこかの隊商の
少女の口から自然と声が漏れた。その焼印は十三才のファニュ本人が所属する隊商のものだった。
「なぜ、お前が馭者もなく一頭だけでいたのかわからないわ」不安と焦りから、ファニュは堰を切ったように烏賊に話しかけた。「でも賢いお前なら隊商の所まで、きっと、あたしを戻してくれるでしょ。休むのは、その後よ。さぁ出発しましょ」
*
「どこに行ったんだろ?」
タンゴの苛々した声がチョウヨウの怒りに火をつけた。彼女は『あんな不気味な小娘にうつつを抜かす暇があったら、目的地まで先を急いだらどうなの』と、今にもタンゴに食つかんばかりに両方の拳を腰に当てて、その巨漢の背中を睨みつけた。しかし月明かりの雪原に少女の姿を探すタンゴから少し離れた所で、頭を寄せ合うタナバタとミソカの姿を認めて怒りの言葉を飲み込んだ。死を賭した苛酷さゆえにデイ・ウォークで親密になる男女はいるのだろう。現に自分も失踪した娘に嫉妬するくらいなのだ。でも、あの二人とは。
*
「あの時みたいに皆より早く見つければいいのよ」と、優しげにミソカがタナバタの耳元で囁く。
「いいや、駄目だよ。そんなこと」
「今さら何言ってんの」
「やっぱり、駄目だ」
「もう決めたでしょ、私たち。さぁ元気を出して」
チョウヨウには二人が何について話しているかなどわからなかった。大人びたタナバタが、か弱いミソカに元気づけられているなど、それだけで見物だ。それに年ごろの娘として二人の秘め事に少なからぬ興味もある。だが、それに嬉々として首を突っ込む悪趣味も彼女は持ち合わせてはいなかった。女子だけで、また秘密の雪語りをした時にでもミソカから二人の関係は話してくれるだろう。その時には興味津々で根掘り葉掘り聞いてやろう。
でも、よりによってタナバタとミソカとは意外だ。以前はナナクサの方がタナバタと親密に話をしていた姿を見掛けていただけにチョウヨウの心は複雑だった。
*
ナナクサは心を侵食する寂しさの陰で、幼馴染みの小さな手のひらが頭一つ分は高い
体の強くないミソカを小さな頃から姉のように見守ってきただけに彼女に想い人ができたのなら、それはそれで嬉しい。でも、博識で礼儀正しいタナバタの大人びた所に自分が惹かれていたのも確かだ。旅を続ける中で言葉に出さなくともタナバタもその気持ちは察してくれていたのではないか。彼との関係は
ジョウシにはジンジツが。チョウヨウにはタンゴ。そして、ミソカにはタナバタ。でも私には……。一体この気持ちをどう理解すればいいのだろう。嫉妬。羨ましさ。それとも……。取り残され感。そうだ。自分の心を支配しているのは、きっとその気持ちなのだろう。そうならないように必死に生きてきた自分が、今そうなっただけなのだ。でも、そう考えると何もかもが味気なく、無性に煩わしく思えてくる。取り残された疎外感が寂しさと敗北感に変わってくる。それが理解できただけに、一層、落ち込んでもくる。それでも表面的には何事もないように演じ続けてしまう自分が堪らなく嫌だった。自分自身を嫌いになってしまいそうで、どうしようもなかった。まったく最悪な気分だ。
「ナナクサ、話があるんだ」
感情の負の連鎖を断ち切る突然の呼び掛けにナナクサは飛び上がりそうなほど驚いた。
「タ、タナバタ」
ナナクサは声の主を確認すると、思わず周りに視線を走らせた。
「大事な話なんだ」
タナバタはそう言うとナナクサの二の腕をしっかりと掴んで自分に引き寄せ、人気のない氷塊の裏まで彼女を引っ張って行った。ナナクサはタナバタに引っ張られながら、彼の手の感触を楽しんでいるもう一人の自分がいるのを感じていた。
「で、話って?」ナナクサは氷塊の裏まで来ると、素っ気なさを装おって口を開いた。
「手伝ってほしいんだ。君にしか頼めない」タナバタはナナクサの返事を待たずに言葉を継いだ。「あの少女を。ファニュを誰よりも早く見つけなきゃならない。いや、本当は見つけない方がいいのかもしれない。僕が間違ってたんだ、あぁ、そうだ。今ならそれがわかる。本当に馬鹿だったよ……」
「あなた何を言ってるの?」
まるで自問自答するようなタナバタに、ナナクサは戸惑いを感じた。
「お願いだ。君にしか頼めない」
空いているタナバタの手が伸ばされ、ナナクサの頬に触れた。ナナクサは体の芯がカッと火照り、戸惑いから生じかけた疑問の言葉を飲み込んだ。
「その時が来たら、驚くかもしれない。でも……でも僕を信じて助けてくれ、いいね」
冷静さが売りのタナバタの目が熱を帯びているのに気押されたナナクサは思わず頷いた。それを見たタナバタは寂しそうに微笑むと他の仲間の所へそそくさと戻って行った。
ナナクサは呆然とその後ろ姿を見送った。
*
ファニュの捜索は最大で三日と決められた。タンゴは異議を唱えたが、デイ・ウォークの旅程をこれ以上、逸脱できないことはタンゴもわかっていたので、これがパーティ全員の了解事項となった。捜索はデイ・ウォークの目的地に向け、
一日目は何も発見できなかった。二日目も同じだった。タナバタとミソカは夜明け前の数時間、二人で仲間の前から姿を消すことがあったが、みな何も言わなかった。そして三日目の夜も過ぎようとしていた。
この日の当番で
「早かったわね」自分の心とは裏腹にナナクサは、素っ気なく声を掛けた。「皆はまだ帰ってないわ」
「来てくれ、ナナクサ」
逆光となって表情はわからないながらも、その声は緊迫していた。
「『来てくれ』って、どこへ?」
「少し北東へ行く」
わけもわからず立ち上がったナナクサは今まで目の前にいたタナバタがいつの間にか自分の背後に回っているのに驚いた。振り向いて声を掛けようとしたとき、タナバタの両腕がナナクサを背後からしっかりと抱きしめた。細いながらも引き締まったタナバタの胸と腕の感触を感じながらナナクサは嬉しさと羞恥で頭の中が真っ白になった。
しかし次の瞬間、体がふわりと浮きあがり、思わず声をあげそうになった。
「大丈夫だ、しっかり掴まえてるから」
頭の後ろから聞こえるタナバタの緊迫した声は、決して安心と言えるものではなかった。質問をしたかったが、質問すればするほどパニックを起こしそうな自分がいることに気付き、ナナクサは口をつぐんで成り行きに身を任せた。
青く透き通った星空へ駆け上がり、その中を矢のように滑空するナナクサとタナバタの影が、遥か下に流れる雪原のスクリーンに映し出される。ありえない状況に戸惑いながらも、そのシルエットに見惚れていたナナクサは村の風車小屋の羽のような影がタナバタの身体の左右に大小二枚ずつ見えるのに気付いた。高度が低くなると時折、わさっとそれらが羽ばたき再び高く舞い上がる。
そう。これは翼なのだ。幼い頃に
「今まで嘘をついていた」と、風を切る音に混じってタナバタの声が耳元に聞こえ、ナナクサの注意をひいた。「あの
首を振り向けたナナクサは背中から真っ黒な翼を生やしたタナバタが痛々しい表情なのに気付いた。彼はナナクサの背後で懺悔し続けた。
「あれは僕たちが使っちゃいけないモノだ。瀕死の者の他は使っちゃいけないモノだったんだ。でも僕は誘惑に勝てなかった。もし健康な者が使ったら、どうなるか試したくって堪らなかったんだ。そのチャンスが目の前に転がってたんだ。でも間違いだった。あれは死にかけた者を呼び戻す強烈な力を持っている。ただ、それだけに普通の者が使うと
「力を呼び覚ます?」
「そう。今のぼくみたいに。でも……」
そこまで言うと急に押し黙ったタナバタに業を煮やしたナナクサは、思わず彼の緩んだ腕の中でするりと体の向きを変えるや、互いに向き合う姿勢を取った。今度はタナバタが驚いて失速しかけた。ナナクサは落ちないようにタナバタにぎゅっとしがみついた。彼が慌てて体勢を立て直すと、ナナクサは無言で答えを促した。
二人は抱き合ったまま暫く空を滑空し続けていた。月明かりで逆光になったタナバタのシルエットが口を開いた。
「副作用があったんだ」
「えっ、いったいどんな?」
「とても悪い副作用さ。凄く悪い。あれは不幸な力を呼び覚ます。だから、だから、早くあの少女を探さなきゃ」
「悪い副作用があったのはわかったわ。でも、なぜファニュを探すことと副作用が関係あるの?」
「それは………」
「ファニュが解毒剤を持ってでもいるの?」ナナクサはタナバタの首が力なく横に振られるのを見て、なおも
「どれも違うよ。解毒剤なんて無いさ。ただ、それをある程度抑える方法を考えついたんだ」
「抑えられるのね?」
「たぶん、ある程度ね」
「『ある程度』……」と、ナナクサはオウム返しにその言葉の重みを噛みしめた。
「劇薬を制するには劇薬を使う。そのためには品質の良い、穢れのない純粋なものでなければならないと思うんだ。だから、あの娘が鍵さ」
「いったい何を言ってるの?」
「僕だって
話を切り上げると、タナバタはナナクサを抱いたまま空を大きくバンクすると、ふわりと雪原に降り立った。
地上に着いた二人は抱き合っていた互いの腕をぎこちなくほどいた。ナナクサが見つめる中、タナバタの背中の黒くて大きな翼は塵が吹き飛ばされるようにサッと掻き消えた。タナバタは黙って自分を見つめ続けるナナクサの目を見つめた。青い夜空に星を散りばめたような綺麗な瞳だった。だがその瞳の中には、さっきの話の続きをしようと呼びかける無言の問い掛けがあった。タナバタはそれには答えず、視線を外した。
「この辺りに、あの少女の気配がする。さぁ、探そう」
*
ナナクサは行方知れずの少女の名前を叫んで何もない雪原を歩き回った。
ナナクサは再び少女の名を叫んで歩き出した。歩いていると前方で雪が円形に盛り上がったところが、もぞもぞと動いたように見えた。彼女はその場に立ち止ると、しばらくその動きを注視した。気のせいかとも思ったが、確かにその円形の小山は一度動いたのだ。周りが平坦で動きがないだけにかえって、それはナナクサの注意を引き続けた。彼女は思い切って、その小山まで行くと、その端をブーツの先で突いてみた。雪とは違ったブヨブヨとした弾力がある。いや、正確には雪の中にその弾力がある。次に靴底全体で強く踏んでみた。今度は抗うように押し返す感触があり、ナナクサは思わず後ろへ飛び退って身構えた。小山は薄っすらと青白い光を明滅させたかと思うと、茹で卵が殻を脱ぎ去るように雪と氷をその表面から振るい落として白い身体を覗かせた。タンゴより大きい
「ファニュ!」
緊張から自然に高まったナナクサの声は
「タ、タナバタ?……」
驚きで、つぶやきしか出なかった。しばらくして、やっと気を取り直したナナクサはタナバタの名を再び呼んでみた。それでも返事がないので、今度は大声で叫んだ。突っ立ったまま、両手で赤いシャーベットを貪っていたタナバタが反応して振り向いた。ナナクサはその赤黒く光る視線を捉えた瞬間、背中に冷たいものが走るのを感じた。直感的にタナバタが正気ではないと悟ったのだ。その顔は理知的であったことが嘘のように醜く歪み、大きく裂けた口からは喧嘩の時のように犬歯が鋭く伸びている。やがてタナバタは憑かれたように、一歩、また一歩と二人の方へ近づき始めた。
「タナバタ、どうしたの?!」
これが副作用か。そう直感したところでナナクサには何もできなかった。だからといって手をこまねいていることなどできない。ナナクサはタナバタに走り寄ると、彼を正気に返らせようとその二の腕を掴んで激しく揺すぶってみた。
「タナバタ。しっかりしてよ、タナバタ!」
それでもタナバタの前進は止まらない。彼の目は既にナナクサを見てはいなかった。彼女を通り越して
ナナクサはタナバタの前へ出ると彼の頬を力一杯、平手で叩いた。それでも正気に返らないタナバタを後ずさりながらも叩きつづけた。気持ちを抑えきれず、つい伸ばしてしまった爪が、タナバタの頬を切り裂いても彼女は叩くのを止めなかった。ナナクサはまた突き飛ばされた。それでも諦めずに今度は彼の後ろから腰に両手を巻き付け、渾身の力で引き戻そうと試みた。しかし、雪の中を引きずられるだけで歩みは止まらない。ナナクサを引きずったまま、タナバタは逃げようとしたファニュに躍り掛かかった。彼は激しく抗う娘を容易に押さえつけると、長く鋭い犬歯で娘の首を貫こうと顔を近づけた。咄嗟に腰に回した腕をほどいたナナクサは、今度は後ろからタナバタの薄茶の髪の毛を両手で掴んで力一杯後ろに引きはじめた。彼の髪の毛が何十本も頭皮ごとメリメリ引きはがされる嫌な感触が両手に伝わる。牙の進撃が鈍ったが、ほんの少しだ。もう駄目だ。ナナクサがそう思った瞬間、電撃に貫かれたように半身を起こしたタナバタが悲鳴を上げてナナクサを振り払った。そして両手で顔を覆い、ファニュから離れると、くぐもった苦痛の叫びをあげながら雪の上に倒れ込んで、のた打ち回りはじめた。
雪の上に投げ出されたナナクサには何が起こったのかわからなかった。ただ考えられるのはファニュが何か対抗策を講じたのだろうということだけだ。でも何をやったのだろうか。それほどタナバタの苦しみ方は尋常ではなかった。ナナクサは凍てついた大気中を微かに漂う甘ったるい匂いの微粒子を感じ取ると、反射的に息を止めてその場から飛び退いた。何てことだ。あろうことか、ファニュはタナバタに猛毒を使ったのだ。
雪の中にうずくまり、肩で息をするファニュの傍らまで行くと、ナナクサは娘からまだ毒物の微粒子が微かに漂っているのに顔をしかめた。
「何てことするの、ファニュ。ニンニクを使うなんて、タナバタが死んだらどうするの?!」
ナナクサは怒りに任せてそう吐き捨てると、立ち上がれないでいるタナバタに目をやった。そして彼が生きていることに少し安堵した。
だが次の瞬間、安堵は強い驚きに吹き飛ばされた。
「タナバタも存外、情けないわね」
それはナナクサの幼馴染みの声。ミソカだった。