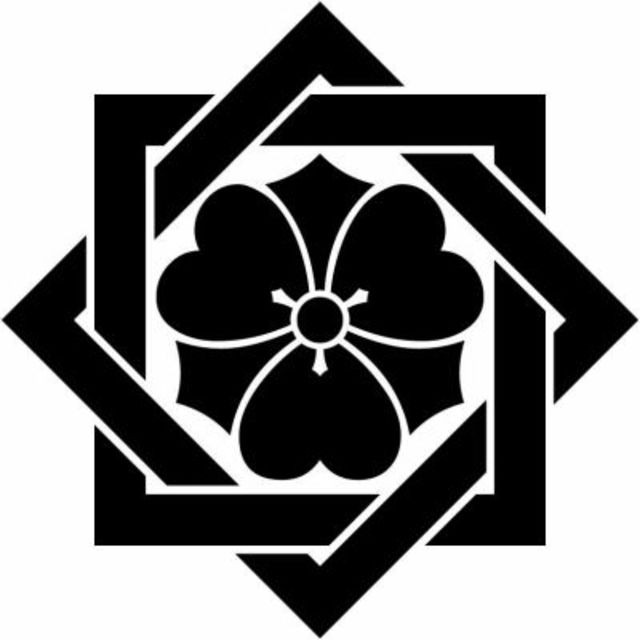第48話 生贄
文字数 7,015文字
八日かかってナナたちが帰り着いた城砦都市は出発した時となんら変わらぬ威容を誇っていた。ヴァンパイアの少年少女たちは初めて目にする巨大な防壁の禍々しさを前に、旅の疲れを忘れて、ただただ息を呑むばかりだった。
ヴァンパイアに転生した事実を隠し、あまつさえ無断で城砦を抜け出した一行は人目を憚ることを考えて、まず少人数で探りを入れることにした。月明かりが厚い雲に遮られる時を狙って、マリクとアンナ、そしてコルテスが一気に壁をよじ登って城砦内に入った。
護衛役として少年少女たちと残されたナナは正直彼らに対する微かな戸惑いを隠せなかった。まだ世界が比較的平和で、母国にいたころ、赤ん坊だった甥や姪の面倒をみたこともあったが、研究室詰めになってからというもの思春期の少年少女と接する機会など絶えてなかったからだ。事実、少年少女たちは一行の中でもナナには、道中どこかよそよそしかった。そんなナナと共に城壁前に残ったニコライは「年頃の子どもは自分たちと他人をきちんと線引きして接する術を既にもっている。ただ線引きが難しいと感じる者には余計に警戒心が働くだけだ。別に良いとか悪いの問題じゃないんだ。だから今は焦らず誠実に接してやるだけでいい。正しいやり方なんてない」と耳打ちしてくれた。実際に彼の言う通りなのだろう。彼らと過ごす時間はこれから十分にある。骨が折れることだろうが、彼らを知り、そして導くのはそれからだ。ナナは溜め息をつくと、好奇心と不安の中で落ち着かない様子の少年少女たちを見やった。
その時、ふと自分も大切な何かの目的のために見渡す限りの雪原を仲間たちと踏破したのだという既視感 めいたものを感じた。しかし中学 から大学の研究室に入るまでサマーキャンプと名の付くものに参加した経験すらなかったのに、そんなことがあるはずがない。もしかしたら、また脳腫瘍が再発して、ありもしない擬似記憶が形作られたのだろうか。詳細がぼやけてはいても、ナナはそんな事実が自分にあったのだという明確な思いを拭い去ることが出来なかった。いったいこれは何だろう。再びありもしなかったはずの記憶を探ろうと意識を集中した矢先、ナナの目の前で、突然内蔵された巨大な滑車の動きに連動して分厚く巨大な城門が地響きを立てて左右に開き始めた。
*
「私は執政委員のルーシー・ギャレットです。お待たせしました。歓迎しますわ、皆さん」
その歓迎の言葉とは裏腹に両手を背中の後ろで組んだルーシーの顔は緊張で半ば引き攣り、二十名近くの武装した警備も決して友好的とはいえない物々しさを醸し出していた。彼女は再び口を開いた。
「あなたたちのことは、さっきマリクから聞きました。これは最低限の予防措置だと思ってください。なにせ、あなたたちは、その……」
「ヴァンパイアですから」
相手が言いにくい言葉を引き取ったシンに少年少女から引き攣った微かな笑いが起こっただけだった。夜にヴァンパイアの一団と対峙するのだから、人間側の対応も無理からぬことだが、同時に目の前の親友に対して言いようのない違和感が湧き上がってくるのをナナは抑えることができなかった。
「では、これを」
シンがスイッチカバーを開けた状態の起爆装置を差し出した。少し躊躇ったのち、城門の外まで足を運んだルーシーはそれを受け取ると赤いライトの明滅するスイッチをしげしげと見やった。緊張の一瞬。その気になれば、ほんの一動作で、彼女はここに集ったヴァンパイアを一掃できる。
「お預かりしましょう」そう言うと、ルーシーはスイッチカバーを閉めた。「さぁ、ここの執政委員会のお歴々がお待ちかねです。もちろん、マリクたちも。早く中に入って雪上車に乗ってください。ナナ、あなたもよ」
どうやら使節団は歓迎されたようだった。記念すべき第一歩を城砦内に記したジェロン島のヴァンパイアたちは、雪上車が引くコンテナほどもある天蓋のない荷台に人間たちの一団と共に乗り込んで城塞都市の奥深くに進んでいった。しかし、道中、ヴァンパイアも人間も荷台の中で互いに距離を置いて座り、口をきく者はいなかった。そして誰もが値踏みをするように相手の集団を油断なく見張っているように見えた。歓迎と言ってもルーシーは歓迎してくれた者の代弁者にすぎないのだろう。だが、凄惨な殺し合いを演じた集団としては、これはこれで上等な方だ。
ぎこちない沈黙を乗せた荷台は、やがてナナが見慣れた建物に近づいていった。新型H5N1インフルエンザ患者とその死体を収容した巨大施設だ。施設に着いた一行は雪上車から降りると周りを武装した護衛に固められてエントランスに入り、そこから延々と続く長大な螺旋回廊を奥へと進んでいった。
「ルー」ナナの声が回廊に吸い込まれた。「中は感染した人たちの……」
「もう、誰もいないわ」ルーシーの答えは素っ気なかった。「亡くなった人たちの遺体は適切に処理したし、生き残った者は自分の宿舎に帰った」
「そう……」
「ところで」螺旋回廊を進むルーシーの口調が突然、以前のように打ち解けたものに変わった。「ここは都市の中心に位置してるから象徴的な意味合いも込めて委員会そのものも中に移したんだけど、どう思う?」
「『どう思う』って?」
「例えば力を感じるだとか、威厳がみなぎってるだとかよ」
「この場所には……」釈然としないものを感じながらナナは言いよどんだ。「その、あまり良い思い出がないから……」
「それは残念ね」
それだけ言うとルーシーは施設内部に到着するまで、今度はシンや少年少女たちに色々と話しかけ、ときに笑い声さえ立てた。その姿は査察に入った衛生局の役人に纏わりつく格式ばったレストラン・オーナーのようにも見えた。しかしナナはそんなルーシーの態度から一番重要なものを嗅ぎ分けられなかったことを後々まで後悔することになった。
「それで、ミスター・シン」ルーシーは立ち止まると手渡された設計図入れから目を上げた。「あなた方が私たちに提供できるのは、黒鉛炉に替わる、この新型リアクター。それに夜間限定のセキュリティとのことでしたが、それはブロドリップに対しても有効ですか?」
「奴自身が我々との関係を切りました。関係が切られた以上、再び操られることはないと信じていますが。確信するまでには至りません。ですから、受け入れてもらえた者には全て、あなたにお渡ししたのと同様の起爆装置を義務づけようと思います」
「ヴァンパイアの生殺与奪を私たち人間の手にということですか?」
「それで、あなたたち人間が安心してくれるなら」
「それは素晴らしい」
一行はジェロン島へ向かう前には入場を禁止されていた地下へ向かい、エアロックを思わせる区画に入った。急ごしらえで設置されたのだろうか、内面はどこもかしこもピカピカと真新しい金属の壁に覆われていた。やがて後方の分厚い扉が閉じられた。
「疑うわけではないのですが、あんなことがあった後です。洗浄のため、ここで少し待ちます。検疫みたいなものと思ってください」
ファンを回すモーター音がして、すぐに空気中にアーモンドのような甘ったるい匂いが漂い始めた。見る間に少年少女たちが喉を掻き毟りながら倒れていった。喉に激痛を覚えながらナナは身体から力が抜けてゆく感覚を味わった。青酸ガスでも撒かれたのかと薄れゆく意識の中で考えたが、ヴァンパイアに青酸性毒物が効かないのはナナ自身が人体実験で実証済みだ。それにルーシーたちは撹拌される空気の中で髪をなびかせて平然と佇んでいる。ルーシーたち人間は何事もない。ただ床に倒れ伏しているのはヴァンパイアだけ……まさか………。罠かもしれないと思った途端、ナナの意識はブラックアウトした。
*
ナナは撃たれたことを瞬時に感じ取った。胸の防弾プレートを難なく突き抜けた二発の高速ライフル弾が肺を抉り、そこからの大量出血で呼吸ができなくなった。その苦しみに身悶えながら口からゴボゴボと血反吐を吐いた。ぎらつく砂漠の太陽の下で仰向けに倒れているナナは自分の血で溺れ死ぬのだと誰に教わるでもなく自然に理解した。そして自分に覆い被さって何か叫んでいる兵士の声が遠のくと再びブラックアウトした。
*
ナナは遥か下のアスファルトの地面に向けて落下していた。来たるべき苦痛よりも恐怖と後悔で両目に涙が溢れたが、もうどうにもならなかった。会社に損益を被らせたからといって、そんなことぐらいで死ぬことはないのだ。そうだ。無一文になっても、またやり直せばいいだけことなんだ。小粋に着こなしたブランド物の高級スーツの裾が風に煽られるバタバタという音を遠くに聞きながら、ふと、ここでの自殺者は自分で何人目だろうと別の思いが頭をよぎった。しかし、その刹那 、もの凄い衝撃音がして頭と上半身に凄まじい激痛が走り、ナナの意識はそこでプッツリ途切れてブラックアウトした。
*
ナナは静かな死の床にいた。窓の外に広がる清々しい緑とは打って変わって病室の壁は冷たいリノリューム材の壁に覆われ、それより無機的に見える無数のチューブと医療器械が身体中に繋がっていた。痛み止めのモルヒネの効果も既になく、次から次と襲いくる末期癌の痛みに顔を歪ませ続けた。「お願いよ……もう終わらせて……」何十回、何百回と声にならない懇願を呟き続けるうち、ナナの意識はまたブラックアウトを迎えた。
何千回、何万回……ナナは様々な死の度ごとに、どれほど助けを求めてきただろう。いつしか彼女は次に来る死のステージの予感だけで、激しい恐怖と苦痛、強い悲しみに苛まれた。しかしいくら願ってみても慈悲深い助けの手が差し伸べられることはなかった。終末を迎えるごとにリセットされては繰り返される新たな破滅の人生。永遠の地獄。その責め苦に耐えかねて、とっくに精神が破綻していても不思議ではなかったし、いっその事そうなってほしいとさえ、数限りなく祈ってきた。だが、なぜか何者かがそれを頑なに阻止しているように思え、遂に正気を失うことはなかった。ゆっくり休みたい。二分……いや、それが無理なら十秒だってかまわない。この絶え間のない煉獄を退けることが無理でも、僅かばかりでも遠のけられたら、どんなに心が休まるだろうか。でも、それは儚い夢にすぎない。また次のステージが始まる仄かな予感が意識に浮かび上がってきた。また始まる……新たな破滅の人生が………。
*
不思議なことに目覚めると苦痛も恐怖もなかった。いつものように絶望の筋書きが自然と意識に受け入れられ、操り人形のように、その人生を演じさせられるのだという感覚もなかった。どうして?……深い安堵の中に疑問が頭をもたげた。目に視力が戻り始め、やがて焦点を結ぶと、髪が白く顔に深いしわが何本も刻まれた老齢の女がこちらに顔を向けていた。その女は両脇に自然生まれとは到底思えない巨大な体躯の人間を従えながらナナに近づくと、しげしげと彼女を観察しはじめた。そして、やおらフロアの下方にいるであろう誰かに大声を張り上げた。
「彼女は目覚めているの?!」
「オフラインにはなっておらんよ、指導者閣下。意識は戻ってないはずだがね」と、下方にいる車椅子の老人が人を見下したような声色で不平を漏らした。
「でも、そうは思えないわ!」と、ナナ睨みつけながら、また女が叫んだ。どこかで聞いたことのある声だった。「とにかく、解凍した補助デバイスを用済みのものと早く入れ替えなさい。そしてもう一つ。私の周りで陸ガメどもをうろちょろさせないで!」
「ルー?……」
その声に女の顔が引き攣って絶句した。
「やはり意識が。イースト博士。やはり目覚めてるわ。陸ガメはいいから、その車椅子をサッサと動かして、こっちに来てすぐに調べてちょうだい!」
「しかし……」
「すぐやりなさい!」
加齢で少し低くはなっていたものの怒った時の口調や自動機械 を陸ガメと揶揄したことから間違いはない。目の前の老女はルーシーだ。
「ルー……」ナナは声を絞り出した。声は声帯にヤスリを掛けられたようにざらついている上、指一本動かせなかった。「助けて……私に何が起こったの?……ずっと悪夢の中にいるの、助けて………」
「それは当然ね」だいぶ経ってから年老いたルーシーは応えた。その声は低く威厳に満ち、そして冷たかった。「お前は神等 に繋がれてるから、夢を見るのよ」
「神等 ?……」記憶を取り戻す鍵でもあるかのように、ナナはその言葉を反芻した。
「人恋しい変態量子脳よ、忘れたの。人間を繋ぐより遥かに良心的だから、あなたたちに協力してもらってるのよ。補助デバイスとしては人間より耐性もあって長持ちだから礼を言うべきかしらね」
「あなたたち?……」DVDの早戻しのように量子脳に見せられ続けた悪夢を一足飛びにしたナナは自分たちに対して行われたであろう仕打ちを、やっと理解した。しかし口をついて出た言葉は恨みや怒りではなかった。「子供たち……マリクは?……」
「お黙り!」ルーシーの平手打ちが頬を襲ったようだが、ナナは何も感じなかった。「あの人までヴァンパイアにするなんて親友が聞いて呆れるわ。ヴァンパイアになったお前を信じた私が馬鹿だった。これじゃぁ、四十年前の殺人ウィルスの方がまだましね!」
「違うの……」ルーシーの言葉から、既に四十年の歳月が欠落したという事実より、ナナには親友に誤解されたままの方がショックだった。「私はマリクたちに頼まれて彼らを……」
「違わないわ。お前は、あの時の殺人ウイルスと同じ。ここでヴァンパイアを増やし、新たなヴァンパイアまで連れ戻ってきた。でもここは人類最後の砦。お前たちを神等 に繋いでからも、お仲間が、たびたびやってきたけど、そのつど捕まえてやったわ、すべてね」ルーシーの顔に残酷な微笑が広がった。「ほら、用済みになった補助デバイスの交換よ。新しいのを入れたから、あれは用済みね」
ルーシーの肩越しに自動機械 の引くカーゴに折り重ねて乗せられたものが目に入った。干からびてミイラのようになっているが、それは間違いなく五人の人間の身体だった。その中の三つは大人にしては比較的小さかった。そして残りの一つには白髪交じりの立派な口髭が、もう一つにはボブに切りそろえた赤毛の頭髪が。中の二体はニコライとアンナだった。
「酷い……」
「さて」ルーシーは顔を近づけた。呼気からは微かなニンニク臭がした。用心のためか嫌がらせかはわからなかったが、おそらく両方だろう。ナナは顔を背けようとしたが無理だった。「今日、目覚めてもらったのは、この四十年間に二百体以上の陸ガメをどこにやったかよ。半数はジェロン島に送り出したことは突き止めたわ。残りの半数はどこに遣ったの?」
「なんの話かわからない」
応えながら、ナナの心にルーシーへの憎悪が止めどなく湧き上がってきた。いや、彼女へというだけでなく、ヴァンパイアというだけで善良な者たちを子供であっても容赦なく道具のように使い捨てて生き続ける、この砦にいる人間たちに対して。
「わからないわけはない!」再び平手が頬に飛び、ナナの冷たい憎悪が身体中に染みだした。それは枯れ枝のように細くなった腕をルーシーの喉元に伸ばす力を彼女に与えた。しかし死にかけた腕で出来るのはそこまでだった。驚きながらも腕の届かないところまで後ずさったルーシーはなおも叫び続けた。「この量子脳はあんたの脳をモデルにしてるのよ。あんたが量子脳を操って陸カメどもを、どこかにやったんでしょ。何を笑ってるの?!」
ナナには量子脳がやったことかどうかもわからなかったし、仮に量子脳に何かの目的があったとしても皆目わからなかった。所詮、人間に近づけたモノなら気まぐれを起こすことだってあり得るし、目的があったところで今の彼女にはどうでもよかった。ただ、わからないことに苛立つ人間がいることが無性に可笑しくてたまらなかった。ナナは自分に向かって口汚くののしり続ける、かつての親友と、その隣で途方に暮れる車椅子の老人に目を止めた。笑いが収まると、また先程の憎悪で心が満たされてゆくのを感じた。それに突き動かされるようにナナは何かを叫んだようだが、叫んだ当の本人にも、それが何だったか皆目わからなかった。ただ目の前の老女が巨躯の二人に何かを命じ、命じられた二人は何の躊躇もなくナナに歩み寄ってくるのだけが見えた。二人の手には巨大な刃物が握られていた。ヴァンパイアの彼女には光の反射具合から、それが銀製なのが見て取れた。自分は間もなく死ぬだろう。しかし恐怖はなかった。かといって永遠に続く煉獄から解放されるであろう安堵感があるわけでもなかった。あるのは不思議なくらいに研ぎ澄まされた純粋な憎悪だけだった。
死ぬ寸前、憎悪がすべてを包み込み、ナナの意識は再びブラックアウトした。
ヴァンパイアに転生した事実を隠し、あまつさえ無断で城砦を抜け出した一行は人目を憚ることを考えて、まず少人数で探りを入れることにした。月明かりが厚い雲に遮られる時を狙って、マリクとアンナ、そしてコルテスが一気に壁をよじ登って城砦内に入った。
護衛役として少年少女たちと残されたナナは正直彼らに対する微かな戸惑いを隠せなかった。まだ世界が比較的平和で、母国にいたころ、赤ん坊だった甥や姪の面倒をみたこともあったが、研究室詰めになってからというもの思春期の少年少女と接する機会など絶えてなかったからだ。事実、少年少女たちは一行の中でもナナには、道中どこかよそよそしかった。そんなナナと共に城壁前に残ったニコライは「年頃の子どもは自分たちと他人をきちんと線引きして接する術を既にもっている。ただ線引きが難しいと感じる者には余計に警戒心が働くだけだ。別に良いとか悪いの問題じゃないんだ。だから今は焦らず誠実に接してやるだけでいい。正しいやり方なんてない」と耳打ちしてくれた。実際に彼の言う通りなのだろう。彼らと過ごす時間はこれから十分にある。骨が折れることだろうが、彼らを知り、そして導くのはそれからだ。ナナは溜め息をつくと、好奇心と不安の中で落ち着かない様子の少年少女たちを見やった。
その時、ふと自分も大切な何かの目的のために見渡す限りの雪原を仲間たちと踏破したのだという
*
「私は執政委員のルーシー・ギャレットです。お待たせしました。歓迎しますわ、皆さん」
その歓迎の言葉とは裏腹に両手を背中の後ろで組んだルーシーの顔は緊張で半ば引き攣り、二十名近くの武装した警備も決して友好的とはいえない物々しさを醸し出していた。彼女は再び口を開いた。
「あなたたちのことは、さっきマリクから聞きました。これは最低限の予防措置だと思ってください。なにせ、あなたたちは、その……」
「ヴァンパイアですから」
相手が言いにくい言葉を引き取ったシンに少年少女から引き攣った微かな笑いが起こっただけだった。夜にヴァンパイアの一団と対峙するのだから、人間側の対応も無理からぬことだが、同時に目の前の親友に対して言いようのない違和感が湧き上がってくるのをナナは抑えることができなかった。
「では、これを」
シンがスイッチカバーを開けた状態の起爆装置を差し出した。少し躊躇ったのち、城門の外まで足を運んだルーシーはそれを受け取ると赤いライトの明滅するスイッチをしげしげと見やった。緊張の一瞬。その気になれば、ほんの一動作で、彼女はここに集ったヴァンパイアを一掃できる。
「お預かりしましょう」そう言うと、ルーシーはスイッチカバーを閉めた。「さぁ、ここの執政委員会のお歴々がお待ちかねです。もちろん、マリクたちも。早く中に入って雪上車に乗ってください。ナナ、あなたもよ」
どうやら使節団は歓迎されたようだった。記念すべき第一歩を城砦内に記したジェロン島のヴァンパイアたちは、雪上車が引くコンテナほどもある天蓋のない荷台に人間たちの一団と共に乗り込んで城塞都市の奥深くに進んでいった。しかし、道中、ヴァンパイアも人間も荷台の中で互いに距離を置いて座り、口をきく者はいなかった。そして誰もが値踏みをするように相手の集団を油断なく見張っているように見えた。歓迎と言ってもルーシーは歓迎してくれた者の代弁者にすぎないのだろう。だが、凄惨な殺し合いを演じた集団としては、これはこれで上等な方だ。
ぎこちない沈黙を乗せた荷台は、やがてナナが見慣れた建物に近づいていった。新型H5N1インフルエンザ患者とその死体を収容した巨大施設だ。施設に着いた一行は雪上車から降りると周りを武装した護衛に固められてエントランスに入り、そこから延々と続く長大な螺旋回廊を奥へと進んでいった。
「ルー」ナナの声が回廊に吸い込まれた。「中は感染した人たちの……」
「もう、誰もいないわ」ルーシーの答えは素っ気なかった。「亡くなった人たちの遺体は適切に処理したし、生き残った者は自分の宿舎に帰った」
「そう……」
「ところで」螺旋回廊を進むルーシーの口調が突然、以前のように打ち解けたものに変わった。「ここは都市の中心に位置してるから象徴的な意味合いも込めて委員会そのものも中に移したんだけど、どう思う?」
「『どう思う』って?」
「例えば力を感じるだとか、威厳がみなぎってるだとかよ」
「この場所には……」釈然としないものを感じながらナナは言いよどんだ。「その、あまり良い思い出がないから……」
「それは残念ね」
それだけ言うとルーシーは施設内部に到着するまで、今度はシンや少年少女たちに色々と話しかけ、ときに笑い声さえ立てた。その姿は査察に入った衛生局の役人に纏わりつく格式ばったレストラン・オーナーのようにも見えた。しかしナナはそんなルーシーの態度から一番重要なものを嗅ぎ分けられなかったことを後々まで後悔することになった。
「それで、ミスター・シン」ルーシーは立ち止まると手渡された設計図入れから目を上げた。「あなた方が私たちに提供できるのは、黒鉛炉に替わる、この新型リアクター。それに夜間限定のセキュリティとのことでしたが、それはブロドリップに対しても有効ですか?」
「奴自身が我々との関係を切りました。関係が切られた以上、再び操られることはないと信じていますが。確信するまでには至りません。ですから、受け入れてもらえた者には全て、あなたにお渡ししたのと同様の起爆装置を義務づけようと思います」
「ヴァンパイアの生殺与奪を私たち人間の手にということですか?」
「それで、あなたたち人間が安心してくれるなら」
「それは素晴らしい」
一行はジェロン島へ向かう前には入場を禁止されていた地下へ向かい、エアロックを思わせる区画に入った。急ごしらえで設置されたのだろうか、内面はどこもかしこもピカピカと真新しい金属の壁に覆われていた。やがて後方の分厚い扉が閉じられた。
「疑うわけではないのですが、あんなことがあった後です。洗浄のため、ここで少し待ちます。検疫みたいなものと思ってください」
ファンを回すモーター音がして、すぐに空気中にアーモンドのような甘ったるい匂いが漂い始めた。見る間に少年少女たちが喉を掻き毟りながら倒れていった。喉に激痛を覚えながらナナは身体から力が抜けてゆく感覚を味わった。青酸ガスでも撒かれたのかと薄れゆく意識の中で考えたが、ヴァンパイアに青酸性毒物が効かないのはナナ自身が人体実験で実証済みだ。それにルーシーたちは撹拌される空気の中で髪をなびかせて平然と佇んでいる。ルーシーたち人間は何事もない。ただ床に倒れ伏しているのはヴァンパイアだけ……まさか………。罠かもしれないと思った途端、ナナの意識はブラックアウトした。
*
ナナは撃たれたことを瞬時に感じ取った。胸の防弾プレートを難なく突き抜けた二発の高速ライフル弾が肺を抉り、そこからの大量出血で呼吸ができなくなった。その苦しみに身悶えながら口からゴボゴボと血反吐を吐いた。ぎらつく砂漠の太陽の下で仰向けに倒れているナナは自分の血で溺れ死ぬのだと誰に教わるでもなく自然に理解した。そして自分に覆い被さって何か叫んでいる兵士の声が遠のくと再びブラックアウトした。
*
ナナは遥か下のアスファルトの地面に向けて落下していた。来たるべき苦痛よりも恐怖と後悔で両目に涙が溢れたが、もうどうにもならなかった。会社に損益を被らせたからといって、そんなことぐらいで死ぬことはないのだ。そうだ。無一文になっても、またやり直せばいいだけことなんだ。小粋に着こなしたブランド物の高級スーツの裾が風に煽られるバタバタという音を遠くに聞きながら、ふと、ここでの自殺者は自分で何人目だろうと別の思いが頭をよぎった。しかし、その
*
ナナは静かな死の床にいた。窓の外に広がる清々しい緑とは打って変わって病室の壁は冷たいリノリューム材の壁に覆われ、それより無機的に見える無数のチューブと医療器械が身体中に繋がっていた。痛み止めのモルヒネの効果も既になく、次から次と襲いくる末期癌の痛みに顔を歪ませ続けた。「お願いよ……もう終わらせて……」何十回、何百回と声にならない懇願を呟き続けるうち、ナナの意識はまたブラックアウトを迎えた。
何千回、何万回……ナナは様々な死の度ごとに、どれほど助けを求めてきただろう。いつしか彼女は次に来る死のステージの予感だけで、激しい恐怖と苦痛、強い悲しみに苛まれた。しかしいくら願ってみても慈悲深い助けの手が差し伸べられることはなかった。終末を迎えるごとにリセットされては繰り返される新たな破滅の人生。永遠の地獄。その責め苦に耐えかねて、とっくに精神が破綻していても不思議ではなかったし、いっその事そうなってほしいとさえ、数限りなく祈ってきた。だが、なぜか何者かがそれを頑なに阻止しているように思え、遂に正気を失うことはなかった。ゆっくり休みたい。二分……いや、それが無理なら十秒だってかまわない。この絶え間のない煉獄を退けることが無理でも、僅かばかりでも遠のけられたら、どんなに心が休まるだろうか。でも、それは儚い夢にすぎない。また次のステージが始まる仄かな予感が意識に浮かび上がってきた。また始まる……新たな破滅の人生が………。
*
不思議なことに目覚めると苦痛も恐怖もなかった。いつものように絶望の筋書きが自然と意識に受け入れられ、操り人形のように、その人生を演じさせられるのだという感覚もなかった。どうして?……深い安堵の中に疑問が頭をもたげた。目に視力が戻り始め、やがて焦点を結ぶと、髪が白く顔に深いしわが何本も刻まれた老齢の女がこちらに顔を向けていた。その女は両脇に自然生まれとは到底思えない巨大な体躯の人間を従えながらナナに近づくと、しげしげと彼女を観察しはじめた。そして、やおらフロアの下方にいるであろう誰かに大声を張り上げた。
「彼女は目覚めているの?!」
「オフラインにはなっておらんよ、指導者閣下。意識は戻ってないはずだがね」と、下方にいる車椅子の老人が人を見下したような声色で不平を漏らした。
「でも、そうは思えないわ!」と、ナナ睨みつけながら、また女が叫んだ。どこかで聞いたことのある声だった。「とにかく、解凍した補助デバイスを用済みのものと早く入れ替えなさい。そしてもう一つ。私の周りで陸ガメどもをうろちょろさせないで!」
「ルー?……」
その声に女の顔が引き攣って絶句した。
「やはり意識が。イースト博士。やはり目覚めてるわ。陸ガメはいいから、その車椅子をサッサと動かして、こっちに来てすぐに調べてちょうだい!」
「しかし……」
「すぐやりなさい!」
加齢で少し低くはなっていたものの怒った時の口調や
「ルー……」ナナは声を絞り出した。声は声帯にヤスリを掛けられたようにざらついている上、指一本動かせなかった。「助けて……私に何が起こったの?……ずっと悪夢の中にいるの、助けて………」
「それは当然ね」だいぶ経ってから年老いたルーシーは応えた。その声は低く威厳に満ち、そして冷たかった。「お前は
「
「人恋しい変態量子脳よ、忘れたの。人間を繋ぐより遥かに良心的だから、あなたたちに協力してもらってるのよ。補助デバイスとしては人間より耐性もあって長持ちだから礼を言うべきかしらね」
「あなたたち?……」DVDの早戻しのように量子脳に見せられ続けた悪夢を一足飛びにしたナナは自分たちに対して行われたであろう仕打ちを、やっと理解した。しかし口をついて出た言葉は恨みや怒りではなかった。「子供たち……マリクは?……」
「お黙り!」ルーシーの平手打ちが頬を襲ったようだが、ナナは何も感じなかった。「あの人までヴァンパイアにするなんて親友が聞いて呆れるわ。ヴァンパイアになったお前を信じた私が馬鹿だった。これじゃぁ、四十年前の殺人ウィルスの方がまだましね!」
「違うの……」ルーシーの言葉から、既に四十年の歳月が欠落したという事実より、ナナには親友に誤解されたままの方がショックだった。「私はマリクたちに頼まれて彼らを……」
「違わないわ。お前は、あの時の殺人ウイルスと同じ。ここでヴァンパイアを増やし、新たなヴァンパイアまで連れ戻ってきた。でもここは人類最後の砦。お前たちを
ルーシーの肩越しに
「酷い……」
「さて」ルーシーは顔を近づけた。呼気からは微かなニンニク臭がした。用心のためか嫌がらせかはわからなかったが、おそらく両方だろう。ナナは顔を背けようとしたが無理だった。「今日、目覚めてもらったのは、この四十年間に二百体以上の陸ガメをどこにやったかよ。半数はジェロン島に送り出したことは突き止めたわ。残りの半数はどこに遣ったの?」
「なんの話かわからない」
応えながら、ナナの心にルーシーへの憎悪が止めどなく湧き上がってきた。いや、彼女へというだけでなく、ヴァンパイアというだけで善良な者たちを子供であっても容赦なく道具のように使い捨てて生き続ける、この砦にいる人間たちに対して。
「わからないわけはない!」再び平手が頬に飛び、ナナの冷たい憎悪が身体中に染みだした。それは枯れ枝のように細くなった腕をルーシーの喉元に伸ばす力を彼女に与えた。しかし死にかけた腕で出来るのはそこまでだった。驚きながらも腕の届かないところまで後ずさったルーシーはなおも叫び続けた。「この量子脳はあんたの脳をモデルにしてるのよ。あんたが量子脳を操って陸カメどもを、どこかにやったんでしょ。何を笑ってるの?!」
ナナには量子脳がやったことかどうかもわからなかったし、仮に量子脳に何かの目的があったとしても皆目わからなかった。所詮、人間に近づけたモノなら気まぐれを起こすことだってあり得るし、目的があったところで今の彼女にはどうでもよかった。ただ、わからないことに苛立つ人間がいることが無性に可笑しくてたまらなかった。ナナは自分に向かって口汚くののしり続ける、かつての親友と、その隣で途方に暮れる車椅子の老人に目を止めた。笑いが収まると、また先程の憎悪で心が満たされてゆくのを感じた。それに突き動かされるようにナナは何かを叫んだようだが、叫んだ当の本人にも、それが何だったか皆目わからなかった。ただ目の前の老女が巨躯の二人に何かを命じ、命じられた二人は何の躊躇もなくナナに歩み寄ってくるのだけが見えた。二人の手には巨大な刃物が握られていた。ヴァンパイアの彼女には光の反射具合から、それが銀製なのが見て取れた。自分は間もなく死ぬだろう。しかし恐怖はなかった。かといって永遠に続く煉獄から解放されるであろう安堵感があるわけでもなかった。あるのは不思議なくらいに研ぎ澄まされた純粋な憎悪だけだった。
死ぬ寸前、憎悪がすべてを包み込み、ナナの意識は再びブラックアウトした。