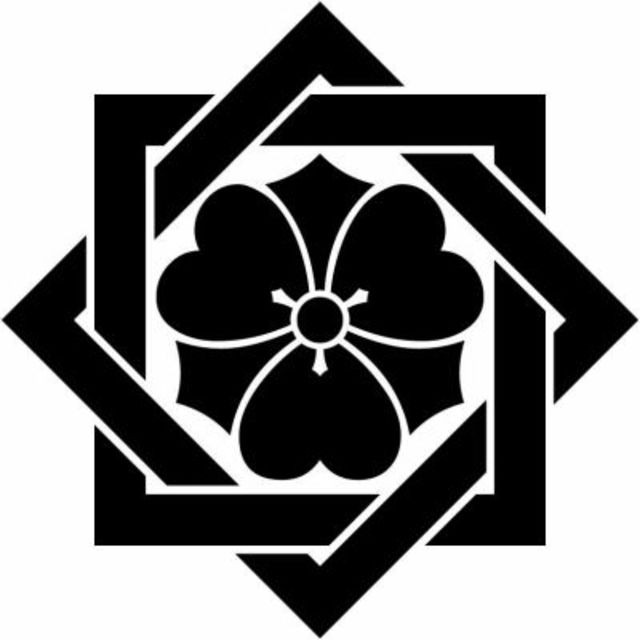第43話 転生
文字数 16,255文字
防寒ジャケットに身を固めたナナとルーシーは本島から研究施設のあるジュロン島に渡るため、双方を結ぶ一本しかない道路の入口に設置された大掛かりな対テロ用検問ゲートまで徒歩で移動した。ジュロン島はシンガポール南西部にある人工島で、沖合いの島々を埋め立てて一つの島にした面積約三十二平方キロメートルの同国最大の産業のみに特化した島だった。検問ゲートで静脈認証と眼紋チェックを済ませた二人はここから二・三キロメートルの距離を専用バスで移動するのだが、バスを待つ技術者たちの多くは、今ではジェロン島の大部分を占めていた石油プラント関連施設の職員から土木建築関係のスタッフにすっかり入れ変わっていた。しかし、これは二〇二五年から本格的に始まった『ブラム氷期』の到来がもたらした余波に他ならなかった。だがシンガポールのように資源はないが、技術を持つ比較的小さな国は小回りが利く分、世界の国々と比較するとまだましだった。世界では大国や小国、先進国や途上国の別なく寒冷化による農作物の大幅な減産。億単位を優に超える餓死者と凍死者を出すなど、既に圧倒的大多数の人類には餓死か凍死、もしくは生き残りを賭けた国同士の紛争で命を落とすかの三者択一の道しか残されてはいなかったからだ。しかし、各国がそんな危機的情勢にあって、ジェロン島が、なぜ土木技術スタッフの大幅増員をし続けるのかに対する答えを持つ者はいなかった。だから今なお生き残っているネット上では、多国籍企業群がジェロン島の地下に建設した原油備蓄用の巨大洞窟を人類最後の楽園 に改造して、自分たちのために秘密裏に運用しはじめているという噂まで、まことしやかに囁かれる遠因にもなっていた。だが、そうはいっても検問ゲートでバスを待つ一団にそんなことは、さして重要なことではなかった。いま彼らが重要と考えるのは、一刻も早く暖かい空調の利いた研究室やプラントに入り、そこで熱い紅茶かコーヒーで暖をとるという一点のみだった。
寒さを紛らわせるため、ナナが足踏みをし始めたとき大型のシャトルバスが降りしきる雪の中から現れた。ナナはルーシーと一緒に技術者たちに混じってバスに乗ると、後方の二人掛け用の席に腰を下ろした。雪は激しさを増して車窓から外の景色すらまともに見えなくなってきた。二人は最後の技術者が乗り終わるまで車内に吹き込む身を切る冷気に耐えねばならなかった。
「東欧の内乱が西に拡大……」発車までの時間潰しに携帯パッドを開いたルーシーが溜息をついた。「嫌なニュースばっかりだね。先週はインドと中国の衝突で二千万の人間が死んだとこなのに。これじゃ、もうどこの国が先に核を使うかだね」
「不謹慎よ、ルー」
「どこが?」
「極端すぎるわ」
「私が極端すぎるって。なに甘いこと言ってんの。物の取り合いになったら人間なんて、すぐに見境なんかなくなっちゃうんだから。理性なんて、所詮は夢想家のたわごとにすぎないってこと。そんなことより、マリクのメールをやっと拾えたわ」
「元気にやってるの、彼。タリサは元気かしら」
「えぇっと」ルーシーは携帯パッドの画面に目を走らせた。「ご丁寧に添付動画まであるわよ。『特別休暇を利用して、凍った海面を犬橇でピオンビーノからバスティアまでタリサと一緒に踏破したよ』ですって」
「バスティアって、コルシカ島の?」
「イタリア本島から片道九十キロはあるわね。なにをやってるんだか。相変わらず研究以外じゃ、馬鹿なことしかしないわね、あの男は。それにしてもなにもそんな無謀なことにタリサも付き合わなくてもいいのに」
「でも、特別休暇が貰えてるんなら、彼らの対極寒因子発現の研究が一段落したんじゃない?」
「えぇ、そうね。でなきゃ、研究所から放り出されたかだね、あの我がまま勝手な性格だもの」
ナナはイタリアにいる同窓生の数々の奇行を思い出して笑い声を上げた。ルーシーは次のファイルを開いて目を丸くした。
「たいへん。嘘。まさか今日じゃないの。これ」
「どうしたの?」
「マリクとタリサの研究の出資者がここに来るわよ。私たちの研究にも興味があるんだって。しかも今日よ!」
「嘘でしょ。いまどき自由に世界中飛びまわれる人間なんているの。私たちだって本国に帰るときだけよ、飛行機が許されるのは。それに一度帰れば、今はもう出国自体を規制されちゃうし」
「超がつくほどの大金持ちは別なのよ、ナナ。世界が氷で閉ざされようが、世の中の本質は変わらない。力のある者がすべてを動かす。それより、あんた嬉しくないの。研究費が増えるかもしれないんだよ」
「そりゃ嬉しいわよ。でも、大金持ちだからって緊急備蓄燃料を勝手に使うことなんてできっこないわよ」
「だから、そんなもの、どうにでもなるのよ」ルーシーは、なおも反論しようとするナナを無邪気に制した。「しかも、この出資者は貴族様よ。腐るほどお金を持ってるのは間違いないんだから、なんとかしてそれを引き出さなきゃ。いいわね」
ナナとルーシーはバスがターミナルに着くや否や、雪の吹きすさぶ中を一目散に研究棟に駆け込んだ。そして、暖をとる時間も惜しんで実験の成果を披露すべく、資料を整理して、自分たちが陸棲転化に成功した軟体生物のお披露目の準備に取り掛かった。
*
結局、多くの研究員たちの中で、出資者と直接対話が出来たのは数多くのグループの中で三グループの五名だけで、所長や上席研究員ですら、彼の興味が向かなければ挨拶はおろか、その顔を見ることすら叶わなかった。そんな中、ナナとルーシーは自分たちの研究成果が認められたことを誇らしく思う反面、ともに選ばれたグループの中にシンガポール科学技術研究庁で自身の研究のためなら殺人すら厭わないと噂されるほど傲慢で偏屈な奇人、ハーバート・イースト準教授が入っていたので、手放しで喜ぶ気にはなれなかった。特にルーシーなどは、相互協力の名の下に準教授と行わざるを得なかった度重なる実験がナナの脳腫瘍の原因の一つになったと信じて疑わなかった。とはいえ、どんな状況にあっても、今回のように無尽蔵と思えるくらいの資金を有する出資者に研究の重要性を直接アピールできるのは何物にも代えがたいチャンスであることに違いはなかった。ナナとルーシーは、出資者が量子脳工学の権威である奇人医師との面談を終えて自分たちの研究室に足を運んでくれるのを今か今かと待ち構えていた。
しかし研究室の壁に掛けられた時計の短針が面談予定の真上から右側に大きく傾くにしたがって、喜びと期待から姿を変えた不安と苛立ちが失望へと変わり始めてきた。ナナが淹 れた四杯目のハーブティにルーシーは引き出しの奥から取り出した秘蔵のバーボンを溜め息混じりに注ぎいれた。そして勧められた酒瓶をナナが手にした丁度そのとき、研究室のチャイムが心地よい電子音を響かせた。二人は顔を見合わせると居間のスツールから跳ねるように飛び降りた。慌ててバーボンの瓶を元の引き出しに放り込んだルーシーは、既にドアの前まで迎えに出たナナに追いつくと、緊張しながらもにっこり笑うと共同研究者に頷いた。頷き返したナナは自分の掌紋と眼紋をセキュリティに認識させると、深呼吸を一つしておもむろに部屋と廊下を隔てる隔離ドアを開いた。
二人の若い研究者の前に黒ずくめのスーツを隙なく着こなした青白い肌の長身の壮年紳士が立っていた。
「これは、これは」
それが紳士の第一声だった。
皮膚からじわりと染み通るような、そのバリトンにナナは言い知れぬ不安を覚えた。彼女はそれを一介の研究者が、住む世界の異なる上流階級の人間を前にしたときの畏れからくる武者震いのようなものだと理解しようとしたが、心の片隅では、もっと根源的なところからくる警鐘に近い感覚にも思われて少なからず動揺した。そんなナナの脇腹を、業を煮やしたルーシーが肘でさり気なく小突いた。
「失礼しました」我に返ったナナは慌てて口を開いた。「お待ちしておりました、ブロドリップ卿」
「こちらこそ、ずいぶんお待たせして申し訳ない」ブロドリップ卿と呼ばれた紳士はそこで言葉を切ると、二人の頭越しに視線をちらりと室内に走らせた。「さて、差し支えなければ早速お話をうかがいたいのですが、構いませんかな、お嬢さん方?」
「それはもう。どうそ、中にお入りください」
「えぇ、歓迎いたします」とルーシーに続いてナナ。
「ありがとう。それでは遠慮なく」
ブロドリップ卿と呼ばれるこの長身痩躯の壮年貴族が経済界に俄 かに登場してきたのは、つい最近のことである。新興国の財政にも匹敵する資産の持ち主が今まで脚光を浴びるどころか、社交界ですら少しも認知されていなかったのは誠に不思議なことであり、それは彼についての様々な憶測を呼ぶことにもなった。事実、マスコミだけでなく、各国の信用調査機関や財務機関、果ては諜報組織に至るまでが彼自身と彼の資産の出所を徹底的に調べ上げたが、結局わかったのは、未だに彼は謎多き人物であり、彼の資産も、過去の多数の大金持ちたちが彼の一族に残した信託財産を相続したものだという事実のみだった。もちろん、これを放蕩 三昧に浪費でもしてくれれば充分なゴシップにはなったのだろうが、彼は、その資産を慈善と研究開発の矢として、当時、混迷し始めた世界に遍く放ち続けることによって、一躍時代の寵児となり、人前に滅多に姿を現そうとしない謙虚さも相まって、自身に向けられる敵意と嫉妬の目を、尊敬と羨望のそれに見事に転化させたのだった。
「少し狭いですが」ルーシーがブロドリップを部屋の奥へ促した。
研究室に隣接した居間に第一歩を記したブロドリップは清潔に保たれた空間をしげしげと見回した。
「管理が行き届いて整然としていますね。大きな成果はこんな繊細な環境からもたらされると私は信じています」
「ありがとうごいざいます。ところで私たちの研究成果を見ていただく前に、お茶はいかがですか、丁度いま炒れたところですので」
「ええ、いただきましょう」と、緊張の面持ちのルーシーに返答すると、ブロドリップはナナに視線を向けた。ナナの背筋に微かな悪寒が走った。しかし彼女はそれを無視して彼を居間の奥の研究室へ案内した。
「早速ですが、私たちの研究の重要性についてなのですが……」
「ナナ。まだお茶も召し上がってないわ」
「いえ」ブロドリップは右手の人差し指を軽く掲げて彼らに追いついたルーシーを優雅に制した。「今の緊迫した世界情勢から鑑みるに、お二方の研究が重要かつ緊急を要するものと考えればこそ、こうして直にお話を伺いたく思って足を運んだのです」
ブロドリップはルーシーから湯気の立つ茶碗を受け取ると口もつけずに言葉を続けた。
「なんでも、お二方は海棲生物の陸棲化に成功なさったとか」
「えぇ、そうです」とルーシーが即答した。「正確には海棲軟体動物。頭足類である烏賊 の陸棲化です。陸上の動植物が絶滅の危機に瀕した今、寒さに強い彼らは人類の希望になるはずですわ」
「これですか?」
「えぇ、そうです」
三人は室内の三分の二以上を占める幾つかの水槽のうち一番奥のひときわ大きな水槽を覗き込んだ。水槽の中は、その半分の高さまで雪と氷が敷き詰められていた。
「これが今の地球表面の六〇パーセントの状況です。来年には最低でも七二パーセントが雪と氷に覆われます」
「スノーボール・アース……スーパー氷河期ですね」
「えぇ、そうです。そして凍った海では漁も思うように出来ません。もちろん大量の魚類が残っていればですが」
ルーシーが水槽横のラップトップを開いて操作すると水槽上部の照明が徐々に明るさを増していった。
「人工太陽灯です」ナナは、その言葉を聞いたブロドリップが、一瞬忌々しそうに顔を歪めたことには気付かなかった。「氷河期でも、まったく陽の光が望めないことはありません。私たちは、そこに着目しました。この烏賊たちは雪の中に混じりこんだ少量の不純物やシャーベット状の海水からエネルギーを取り込むだけで生育できるだけでなく、光合成も行えるんです」
「さぁ、ご覧ください。やや左側の雪の中です」
ルーシーの声が合図であったかのように雪の下から六匹の二十センチほどの陸棲烏賊が、もぞもぞと雪と氷をかき分けて灰色の胴体を現すと、個々にその表面を電飾のように青く光らせ始めた。
「彼ら、喜んでます」とナナが画面に見入りながら嬉しそうに口を開いた。
「海棲生物の気持ちがわかるんですか、ミス・ジーランド?」
「いえ」ナナは質問者の貴族に肩をすくめた。「たぶん、そうではないかと考えているだけです。こんな色素胞の変化は、私たちも見たことがありませんでした。恐らく遺伝子の組み合わせ過程で今まで眠っていた何らかのスイッチが入ったか、働きが未解明だった遺伝子にこのような反応をするものがあったかだと思います。何れにしても太陽灯が点くと、こうして気持ち良さそうに日向ぼっこです」
「可愛らしいですね」
「えぇ。軟体動物にこんな感情を抱くなんて思いもしませんでした」
「いえ。彼らがではなく、あなたがということです」
久し振りに掛けられた異性からの好意的な言葉に、ナナは思わずブロドリックを見つめ返した。不安を掻き立てられる雰囲気が減じたわけではないが、なかなか魅力的な男だ。
「ところで」ルーシーは咳払いをすると次の説明に移った。いよいよ本題だ。「わたしたちはこの烏賊 の再生能力の高さにも着目しています」
「再生能力……傷を治すということですか。私はこの生き物がどれ程の時間で傷を治すのかすら、わかりませんが」
「えぇ。ですが時間だけではありません」と、ルーシーはラップトップ上で別の動画画面を呼び出した。「これをご覧ください。画面上にいるのは、この烏賊 たちです。私たちは、それぞれ5本、6本、8本と彼らの足を切断してみました」
「というと」
「元通りになるかどうかの実験です」ルーシーはそう告げると、動画を再生した。「もちろん成功しました。一体残らず、足の再生実験に成功したのです。しかも九六時間で欠損箇所を完全再生します」
早送りされた動画の中で、高速度撮影された植物の発芽のように六体の中の四体の烏賊の足が完全に再生された。
「これを雪の中で飼えば、特定の餌もいりません。定期的に足を刈り取ればいいのです、まるで、その……」
「羊毛のように」ナナが助け舟を出した。
「羊毛ですか」
「えぇ」とルーシーは頷いた。「羊毛は食べれませんが、彼らの足は食糧になります。この氷河期に手に入る唯一無限の食糧資源です」
「なるほど。そして、これを量産すると言うことでしたね、ミス・ギャレット?」
「えぇ。正直に申し上げて、遺伝子操作で繁殖力こそ落ちてしまいましたが、私たちは、その問題を必ず解決できると考えています」
「しかし」ブロドリップは僅かに視線を落とした。明らかに納得に至ってはいないサインだ。「世界の人々には食べ慣れたものではないですね、この烏賊 という魚は。宗教によっては、かつては悪の存在に分類したものもあるのでは?」
「まず、烏賊 は厳密には魚ではなく、貝類に分類されます」貴族の考えを推し量ったナナも陸棲烏賊の可能性に慌てて援護を開始した。「それに一概に食べなれないものでもありません。例えば、祖母の国では寿司にして生で食べたりもします。もっとも牡蠣のような人気は出ないでしょうが、加工すれば誰もが抵抗なく食べれるようになると思います」
「申し訳ありません」ルーシーも口を開いた「もし、ご気分を害されたのでしたら謝ります。しかし、わたしたちは」
ブロドリップは再び人差し指を上げて、ルーシーを制した。「いえ、お二方は氷河期に突入した世界で人類を助けようと奮闘なさっておられるのです。賛辞がありこそすれ、それを貶すなどもっての外だ。それを忘れた私が悪かったのです。思慮が足りませんでした。どうか、今以上の援助に免じて、私の無礼をお許し願いたい」
「『今以上の援助』?」ナナは身を乗り出した。「それでは、私たちの研究は……」
「もちろん、大いに続けてくださって結構です。これからは金銭面だけでなく、その他、各国の許認可などもご心配なく」
「ありがとうございます。なんと御礼を申し上げればいいか!」
「いえ、礼には及びませんよ。お二方の研究の片鱗をイースト準教授からもうかがっていたのにも関わらず、失礼なことを申し上げたのは私の方ですから」
「そうでしたか」ルーシーから笑顔が消えた。
「えぇ、先ほどお会いしたときにお聞きしました。どうかしましたか、ミス・ギャレット?」
「いえ」
イースト準教授の試作型量子脳コンピューターのバージョンアップのための度重なる脳トレースが、ナナの脳腫瘍の原因だと信じて疑わないルーシーにとって、彼の名前は浮き立った心を穏やかならざるものにするのに十分な呪詛の言葉だった。もちろん“電脳の心を培う”だかの変人の実験を二人して好き好んで手伝ったりしたかったわけではなかった。しかし陸棲烏賊を造りだす過程で必要な生物間の遺伝子の組み合わせ演算とその予測、その他、膨大な理論上の処理をイーストに依頼する見返りに、親友をMRIの化物のような不快極まりない人工知能の犠牲にしてしまったという忸怩たる想いをルーシー自身は未だに持ち続けていた。
「実験は持ちつ持たれつということですわ、ブロドリップ卿」ナナは自責の念に駆られているであろう親友を気遣って代わりに口を開いた。「特にそれが繊細であればあるほど。それで互いの研究に得るものがあれば、私たち科学者には他に何も言うことはありません。前に進み続けるだけです。ちなみに準教授からは、他にどのようなことをお聞きですか?」
「同僚の評価が気になりますか?」
「えぇ、少し」本当は凄く。しかしナナは何とかその思いが表情に出るのを抑えた。
「では正直に。『研究の着眼点は素晴らしいが、実用段階までには改良の余地が多々残されている』と評価されていました」
評価は評価でも、これでは完成には程遠い欠陥品との酷評と同じではないか。傲慢で偏屈なイーストらしいといえばそれまでだが。ナナとルーシーは、その評価に揃って鼻白んだ。ブロドリップがいなければ、やり場のない、あまりの怒りに二人とも朝食を床に吐いてしまうところだった。
「ですが、私の見る限り、準教授の研究も、まだまだ改良の余地はありそうでしたね」
「『まだまだ』ですか?」とナナは、目の前の貴族の言葉を繰り返した。
「そう。まだまだです。だから、お二方を含めて皆さんには今後も私の援助が必要だということです」ナナの気持ちを知ってか知らずか、ブロドリップは微笑んだ。「特に有望な研究にはですよ。さて、お忙しいのに長居をしてしまいました。次には、より完成に近づいた成果を見せていただくことにしましょう」
失敗とは言えないまでもスポンサーの興味を失わさせずに済んだようだ。それどころか今以上の援助を取り付けることができた。
こうして、魅力的だが、どこか言い知れぬ不安に駆り立ててくれるスポンサーは去っていった。しかし彼が去っていった日からナナは奇妙な夢を毎日見るようになった。
*
見渡す限りの緑の大地を遙か眼下に望み、自由に大空を滑空する夢。妙に鮮明なその夢の中で、ナナは大空に漂う真っ赤な風船を懸命に追いかけては、それを掴もうと必死に手を伸ばす。突風に翻弄される風船は彼女の手をすり抜けてゆくときもあれば、運よく掴むことができることもある。しかし、やっと掴むことができても、その瞬間に風船はシャボン玉のようにぱっと弾けてしまう。だが一瞬でも掴むことができた日は一日中気分よく過ごすことができた。いや、気分よくというより、末期の脳腫瘍患者であることを忘れてしまいそうなくらい心と身体に力がみなぎって、すこぶる調子がいいのだ。そんなことが、もうひと月は続いていた。ブロドリップとの面談の後、ナナとルーシーは研究室に毎日泊まりこんで陸棲烏賊の更なるデータ収集と生態観察に明け暮れた。その間、ルーシーがアパートに戻っても、自分にはもう時間が残されてないのだと言い張って、ナナは戻るのを拒否して研究室に籠りつづけた。そして今日は着替えを取りがてら、久しく帰っていないアパートに戻っていた。
アパートの中は氷点下だというのに、どこも黴の匂いがした。ナナは洗濯物を洗濯機に詰め込むだけ詰め込むとスイッチを入れた。有難いことに、ここでは電気と水道だけはまだ生きていた。次に彼女は台所で冷蔵庫を開けてみた。さして中身はなかったが、帰宅してから喉の渇きを覚えていたのでトマトジュースのボトルを引っ張り出してコップに注いで飲み干した。さして旨くはなかったがお代わりを注いだ。そこではじめてラップトップの呼び出し音が鳴っているのに気が付いた。ルーシーは二週間前から南スマトラ沿岸から少し内陸に入った新たな研究施設で陸棲烏賊の放牧実験に出かけていた。ナナは実験の過程を知りたかったので、いつでもルーシーと話せるようにしておいたのだ。
ナナはコップを持って居間から狭い自室に戻ると、ベッドの上のラップトップに顔を近づけた。通信事情の悪化のため画像の乱がしばらく続いたが、すぐに目の前にやつれ切ったルーシーの顔が現れた。そして親友の横には同じようにやつれ切った友人のマルクの顔も見えた。彼は婚約者のタリサとイタリアで対極寒因子発現血清の最終試験中のはずだが。
「ハイ、ルー。ハイ、マリク」
「そんな……ナナ……」
画面から戸惑いと怯えを滲ませたルーシーの声が漏れ、ナナは思わず聞き返した。
「どうしたの、ルー?」
マリクがルーシーの耳元で何か囁いたがナナには聞こえなかった。だが彼の顔は引きつって蒼白だった。
「ねぇ、いったい何?」
「いえ。何でもないわ……」
「嘘よ。何もないわけないわ。どうしたの?」
ナナの問い掛けは沈黙で返された。
「ねぇ。ふざけてるんなら怒るわよ」ナナは唾を飲み込んで沈黙の理由をあれこれと類推してみたが、行き着くところは一つだった。「実験ね。そうでしょ……。正直に話してちょうだい。実験で烏賊たちに何かあったのね?」
「何もないって言ってるだろ!」
業を煮やしたマリクが画面に割って入った。冗談好きで温厚な彼とは思えない言動と表情に、ナナは、ますます疑念を募らせた。
「何もないわけないじゃない!」ナナも声を荒げた。「第一、あなたはタリサとイタリアで、まだ実験中のはずでしょ?!」
タリサの名前を耳にした途端、マリクは「くそ」と呟いて画面からフレームアウトした。残されたルーシーの目に涙が浮かんだ。
「いったい、どうしたっていうの、ルーシー?」
「本当にわからないの、ナナ?」
「えぇ。わからないわ。説明して」
フレームの外から「無駄だ」というマリクの吐き捨てる声が聞こえた。ルーシーは声の方をチラリと見やると意を決して口を開いた。
「烏賊たちの放牧実験は順調に進んでるわ。それだけは確かよ、だから安心して」
「本当に?」
「えぇ、本当よ……でもね……」
「だから、いったい何なのよ?!」
ルーシーは踏ん切りがつかないらしく、しきりに唇を舐めては、ちらちらと画面の中を覗き見ていた。
「お願い。話して」
「タリサが死んだの」それだけ言うとルーシーは目を伏せたが、大きく息を吸うと再び画面に向き直った。「いえ、死んだんじゃなく、私たちが滅ぼしたの。そうせざるを得なかったから」
ナナの沈黙は長かった。やがて彼女は怒りに顔を強張らせた。「なんの話、ルーシー。冗談でも酷すぎるんじゃない?」
「冗談でこんなこと言えるわけないでしょ。彼女はね………タリサはヴァンパイアだったの。多くの人が彼女の犠牲になったわ。こんなご時世だもの、仲間の研究者に犠牲が出始めるまで、マリクも気付かなかったのよ。もしかしたらタリサ自身も自分が何をしてるか、わかってなかったかも……」
「いったい何の話をしてるの。せっかく繋がった通信なのに唐突に下らないお伽話なんて、いくらなんでも付きあってられないわよ!」
「まだわからないの、ナナ。ブロドリップよ。奴はヴァンパイアだったの。タリサを仲間に引き入れて」そこまで言うと画面の奥でルーシーは涙をぬぐった。「タリサはスマトラまでマリクを追いかけてきた。そして私たちに滅ぼされて枯葉みたいに燃えて灰になったわ、弱々しい薄暮の下でね。そんな死に方ってあると思う。冗談なんかじゃないのよ」
「そんな話、信じられないわ」
「あなたの周りでも行方不明者が出始めてるんじゃないの、ナナ?」
「ずっと研究室から出てないから、わからないわ……」
「ネット・ニュースは、まだあるでしょ?」
「最近のアクセスの酷さは知ってるでしょ。どんどん悪くなってるのよ。それに研究ばかりだったから」
ルーシーは再び大きく息を継ぐと、自分を納得させるかのように何度か頷いてみせた。
「あなたが、いつからそうなったかはわからない。でも、少なくとも私は……私はそうなってない。もし、あなたに人間らしい心がまだ残ってるのなら……あぁ、親友にこんなことを言うなんて、でも……お願い。自分自身が大事なら。まだ、あなたがあなたなら自殺して。手遅れにならないうちに」
「もう切るわ。付き合ってられ……」
「ナナ」ルーシーはナナを遮った。「たぶん、あなたは手にコップは持ってるはずよね。それは私にも見えるわ。でも、それだけ。宙に浮いたジュース入りのコップだけよ、私に見えるのは。声は聞こえるけど、あなたの姿が見えない。画面に姿が映らないのよ、あなたはもう魂を持たないヴァンパイアだから。……さよなら、私の親友。大好きだったわ……」
ルーシーは泣いていた。そしてナナは一方的に切れた通信画面を暫く見つめていたが、ラップトップを畳むとベッドから降りてバスルームに向かった。そして洗面台に据えつけられてる鏡の曇りを手で拭うと食い入るように覗き込んだ
彼女の喉からクックックッと声が漏れた。それが笑い声なのか嗚咽なのか、ナナ自身にもわからなかった。研究棟では毎朝顔も洗っていたのに鏡さえ、まともに見なかったのは、なぜなのかもわからなかった。ナナは叫び声を上げると自分の背後のバスルームの壁しか映し出さない鏡を素手で叩き割った。血が飛び散るほど何度も鏡に向かって手の平を打ちつけた。ガラスで切れて血が流れ出たが、すぐに傷が塞がって元通りになった。その不思議な光景に心を奪われている彼女の頭の中に声が響いた。声はしきりに部屋へ招き入れるように要請していたが、ナナはそれを無視した。声は要請が聞き入れられないことに心底驚いているようだった。しかし、諦めず執拗に命令してくる。
ルーシーの言うようにブロドリップがヴァンパイアで、自分を仲間に引き入れたのだとしたら、これほど腹立たしいことはない。いや。そもそもこんな馬鹿らしいことが現実であるわけがない。きっと脳腫瘍がもたらす白日夢の中にいるのだ。だが自分にそう言い聞かせようとするナナの頭の中では「部屋に入れろ」と執拗に命令する強圧的な声が響いている。頭の中に響く声がどこからするのか不思議とナナにはわかった。彼女は声の主に怒りをぶつけようと急いで居間に戻ると道路に面した窓を勢いよく押し開けた。雪が深々と降り続く中にブロドリップが佇んでいた。
やはりそうか。ここまできてナナにも、やっと得心がいった。人間なら三階の窓の外の空中に立てるわけがないのだから。
「そなたのような娘は初めてだ」
ナナは古風な言い回しをするヴァンパイアのブロドリップを無言で激しく睨みつけた。
「さぁ、そろそろ部屋へ招き入れてはくれまいか。でないと、この寒空で凍えてしまいそうだ」
自分の言ったことが面白くて堪らないというように寒さを感じないヴァンパイアは笑い声を漏らした。それでもナナは彼を無視して、ただただ憎悪を込めて睨み続けた。
「私はお前が何を怒っているのかわからぬ。だが、それ以上に、お前が我が命に、なぜ背けるのかが謎なのだ」初めて会った時の謙虚さは、もう欠片も残っていなかった。ヴァンパイアはなにか閃いたかのように自分のこめかみを指先でトンと突いた。「死の病がそうさせるのか。いやいや、そうではあるまい。以前、お前と同じ病の者も、ほんのひと噛みで我が傘下に馳せ参じたのだ。ではなぜだ?……」
「あんたが嫌いだから。憎いからよ」
すぐさまヴァンパイアは人差し指をたててナナを制した。
「そなたの気持ちなど関係ない。多くの下僕 同様、お前は既に身も心も我がものだ。だが、事実は違う。それを、そなたが理解しようとせぬのが、もどかしい。既に、そなたは人ではない。招待の言葉など端から無意味なのだ。しかし我が心が部屋に入れぬと警鐘を鳴らしておる。なぜだ。一族の部屋になぜ始祖たる我れが入れぬ。人の部屋のようになぜ結界がある……」ヴァンパイアはニヤリと笑って鋭い犬歯を覗かせた。「だが、さればこそ面白い。お前を下僕 とせず、伴侶として迎え入れ、その謎を解いていくとしよう。これは長い時の中でも最良の暇つぶしの一つになるはずだ」
ナナはヴァンパイアが言い終わらないうちに怒りに任せて窓外の彼に飛び掛かっていた。しかし、その人間離れした体当たりも難なくかわされ、遥か下の凍ったアスファルトの路面に激しく叩きつけられた。身体の中で骨の砕ける音と内臓が押し潰される音がした。ナナは全身を貫く激痛に咳き込むと雪の上に大量に吐血をした。
「なぜ我に牙を向けられる。なぜ己 の運命に抗える?」
ナナの耳元でブロドリップの声がした。
「あんたは友人を殺した!」
ナナから流れ込んだタリサのイメージにブロドリップがすぐさま反論した。
「あれを滅ぼしたのは人間だ。お前のかつての友人たちではないか」
「じゃぁ、やっぱり事実なのね。ヴァンパイアにされなきゃ、彼女は死なずに済んだ!」
「人間のままなら、いずれはこの氷河に押し潰され、すり潰されて死ぬのだ」
「人間はそんなに弱くないわ!」
「買い被るな。弱いからこそ、他人を押し退けてまで食糧に群がり、自分だけ暖をとろうとするのだ。氷河期が訪れ、どれほどの人間が死んだことか。どれほどの国が反目し合って滅ぼしあっておることか」
「許せない」
「何が許せぬ……友が滅んだことか。それとも人の文明が滅ぶことか。まさか我が一族にお前を迎えたことではあるまい。ヴァンパイアになろうと、お前はナナ・遠野・ジーランドのままだ。変わったのは、お前の周りだ。なぜなら今もお前は残された人間のために研究を続けようとしているではないか。翻って、親友たちはどうだ。友人を滅ぼし、あまつさえ、お前を見捨てた。違うか?」
「ルーシーが私と関係を絶ったのは、ヴァンパイアが人間を襲うからよ。私がその化け物になったからよ!」
「左様。されど我れらが殺 めるのは悪人のみ」
「嘘よ!」
むろん、嘘だった。
しかしナナの目の前のヴァンパイアが古来より悪人の方を多く餌食にしていたのは紛れもない真実だった。なぜなら悪人の血は、より強い力を授けてくれるだけでなく、善人より遥かに刺激的で美味だったからだ。それゆえに彼は長い休息から目覚める度に世界のどこかしこに内紛の芽を見つけては、それを育てたり、疫病を流行らせては、人心を荒ませ、悪心の量産と高濃縮化に腐心してきたのだった。
「人間の本質は悪だ。異質というだけで残酷な仕打ちを何の呵責もなくやってのけられる。先ずはお前もその事実を味あわねばならぬようだ。そして我が命に従わぬ愚かさを悔い改めた方が良いぞ、我が妃よ」
ヴァンパイアの姿が風雪の中に掻き消えた。
暫くしてアパートの角を曲がって派手に警告灯を点滅させた警察車両が通りに何台もなだれ込んできた。車両はどれもナナの前で急停車するや否や重武装の警官を次々と吐き出すと血まみれのナナに眩しいライトと銃を向けた。
「さぁ、どうする? あの者たちはお前を害しようとしているぞ。だが、そうさせなくするのは簡単なはずだ。ほら、夜ごと風船を掴むように」
ナナの頭の中にヴァンパイアの声が響いた。途端に、毎晩、自分が見ていた夢が意味するものを彼女は直感的に理解した。空に漂う風船は、風船ではなかった。逃げ惑う人間であったということに。
ナナの目は涙と後悔で曇りはじめた。彼女は銃を向ける警官たちに両手を上げて敵意がないことを示しながらも、自分が犯した罪の大きさに恐れおののき、激しく震えはじめた。
「怪我をしてるぞ」一人の若い警官が小声で横の同僚に囁いた。
「黙ってろ、シン」若い同僚を制した年かさの警官はナナから目を離さず、防弾ベストに装備された無線機に向かって報告した。「通報通り、臨海居住区裏で容疑者を発見。複数の目撃情報と完全に一致している」
「怪我をしてるのか。手当ては必要か?」
シンと呼ばれた若い警官がナナに再び呼びかけ、ナナは黙って首を横に振った。既に痛みは消えていた。ヴァンパイアの治癒力は短い時間の間に三階から転落した彼女の身体を完全に修復していたからだ。
「貿易商及び警官殺害の容疑で逮捕する。両手を頭の上で組み、路面に膝をつけ!」
年かさの警官の言葉に、その傍にいる女性警官も「言われた通りになさい!」と追随した。
「容疑者は普通の状態じゃないです」若い警官のシンは慎重にナナに近づいた。「怪我の程度を見ないと、後で何かあったら訴えられますよ」
「やめろ。距離をとれ!」
「大丈夫。危険な兆候は見えません」
しかしナナにあと一歩の所でシンの喉がぱっくり開いて鮮血がほとばしった。ブロドリップの仕業だった。しかしナナは喉を押さえたシンを助けるでもなく、彼が路上に倒れ伏すまで顔にふりかかる血を無意識に手の平に受けて喉を鳴らして呑んでいた。遠くの方で悲鳴や叫びを聞いた気がしたが、気にならなかった。頭や体を何度も小突かれる感触を味わったが、湧き上がる陶酔感に我を忘れた。これでは駄目だとナナが意識を強く持って自分を取り戻したときには恐怖に引き攣った警官たちの銃撃を一身に浴びている最中だった。
警官たちにとって、頭と言わず胴体と言わず拳銃やショットガンの弾を無数に浴びても倒れないナナは不死身の化物そのものだった。ナナは悲鳴を上げると、その場から逃げだした。人間には到底追いつけないスピードで逃げ去ったナナのあとを彼女の悲鳴だけが不気味に追いかけた。ブロドリップの高笑いがその悲鳴に微かに混じっていたのを聞けたのは、悲鳴を上げた本人だけだった。
数時間後、パニックから解放されたナナは研究棟まで戻ってみたが、エントランス前で緊急配備された警官や警備員たちの激しい銃撃を受けて早々に退散した。予想されたこととはいえ、人々の反応にナナは途方に暮れるしかなかった。しかもヴァンパイアになってしまったとはいえ、体力が無限に続くとも思えない。明け方近くにナナは激しさを増した吹雪に紛れて再びジェロン島に舞い戻ることに成功した。そして人気のない工場群の屋外に雪の吹き溜まりを見つけると、寒さを全く感じなくなった身体をそこへ横たえた。疲れ切った身体に雪が降り積もってゆく。無事に目覚めることができればルーシーのいる南へ出発しよう。自分が以前のナナと変わりないことを信じてもらい、そこでこの身体を元に戻す努力を一緒にしてみるつもりだ。だが、もし親友の所にたどり着く途中で息絶えるなら、それはそれでいい。突然ヴァンパイアにされてしまったという事実は、そこまで彼女の心を投げやりにさせてしまっていた。
やがて眠りに落ちたナナは、この日だけは夢を見なかった。
*
シンガポールからスマトラ半島にかけての海は水深が浅く、そのほとんどが固い氷に覆われていた。ナナは凍った海面を吹き渡る風よりも速く夜の闇を駆け抜けた。ヴァンパイアに転生したいま、息切れもしなければ疲れや寒さを感じることもなかった。途中の洋上で打ち捨てられた大型の豪華クルーザーを見つけて、そこで幾晩か過ごした。船内に入った時、喉の渇きを覚えたが遺棄されていた凍った船客たちの遺体から血を飲もうとは考えなかった。このとき頭にあったのは親友と再会して誤解を解くことと残された研究の事だけだった。だから凍りついた空の船室で眠っている時に赤い風船の夢を見ても完全にそれを無視することができた。それでも我慢できなくなると船内に残された食べ物を試してみた。固形物は見ただけで胃がむかついた。酒は呑んでみたが酔いもしなければ味もせず、渇きを癒すことすらできなかった。味覚だけでなく代謝も人間とは変わってしまっていたのだ。しかし倉庫にあったトマトジュースだけは少しずつ噛むように飲み込むと、アパートで過ごした最後のひと時と同様に咽喉を潤すことができた。その色が血を連想させて偽薬効果 でももたらすのだろうか。ナナには、なぜこれだけは飲めるのかその原理は皆目わからなかったが、人を襲って血を糧にするヴァンパイアが菜食で命を繋ぐことができるかもしれない皮肉な発見に思わず笑い出しそうになった。
四夜目。
クルーザーの船長室で目的地である南スマトラの詳細な地図を物色する間も、ナナは科学者として今の自分にできる簡単な実験に明け暮れた。
そう人体実験だ。
ナナは医務室に入ると、そこに残された数少ない薬品でパッチテストを行ったり、身体修復能力を試すため、体内に致死量の劇薬を注入してみたりした。自分の他にヴァンパイアにされた者が、どうしてもその状態を受け入れられない場合、自決の手を差し伸べる方策を得ることができるかもしれないという思いからだ。しかし予想通り医薬品類はおろか、劇物も毒薬もナナにはほとんど無害か役に立たなかった。再び空腹を覚えたナナは、次にクルーザー内を調べて凍った死体の血液以外に摂取できるものが残されていないか試すことにした。試す食料が底をつくと洗剤から船の燃料まで口に含んでみたが、口にした途端に咽 て吐き出してしまった。ヴァンパイアになったとはいえ口にできないものは、やはり口にできないのだ。人間と同じその反応に少し気をよくした彼女は、次に船の外で固い氷を深く掘ってシャーベット状の海水も口にしてみた。“海水は血液の代わりになりうる”という二十世紀初頭のルネ・カントンの『海水療法』を思い出したからだ。さして期待はしてなかったが、口にしてみると海水は塩辛さは全くなく、それどころか微かな甘味すらしてトマトジュースと同様に喉の渇きを少しは癒す効果があることが分かった。
「塩分やミネラルに期待してたわけじゃないけど、無限の海水で生きれれば、私もあの子たちと同じね」
ナナは研究していた陸棲烏賊のことを思い出すと、居ても立ってもいられなくなり、自身の人体実験レポートを船内で見つけたデイパックに突っ込むと、六夜を過ごした難破クルーザーを後にした。
そして翌日には南スマトラに上陸を果たし、その山中を飛ぶように頂上へ向けて駆け上っていった。
山頂から見ると、遥か前方の凍った湖を臨む山間部一帯に目指す研究施設が見えた。いや研究施設というより、それは四方を高い城壁に囲まれた城塞都市だった。以前、ルーシーが送ってくれた動画で見た研究施設とは似ても似つかないその禍々しさに、ナナはただただ目を見張るしかなかった。
寒さを紛らわせるため、ナナが足踏みをし始めたとき大型のシャトルバスが降りしきる雪の中から現れた。ナナはルーシーと一緒に技術者たちに混じってバスに乗ると、後方の二人掛け用の席に腰を下ろした。雪は激しさを増して車窓から外の景色すらまともに見えなくなってきた。二人は最後の技術者が乗り終わるまで車内に吹き込む身を切る冷気に耐えねばならなかった。
「東欧の内乱が西に拡大……」発車までの時間潰しに携帯パッドを開いたルーシーが溜息をついた。「嫌なニュースばっかりだね。先週はインドと中国の衝突で二千万の人間が死んだとこなのに。これじゃ、もうどこの国が先に核を使うかだね」
「不謹慎よ、ルー」
「どこが?」
「極端すぎるわ」
「私が極端すぎるって。なに甘いこと言ってんの。物の取り合いになったら人間なんて、すぐに見境なんかなくなっちゃうんだから。理性なんて、所詮は夢想家のたわごとにすぎないってこと。そんなことより、マリクのメールをやっと拾えたわ」
「元気にやってるの、彼。タリサは元気かしら」
「えぇっと」ルーシーは携帯パッドの画面に目を走らせた。「ご丁寧に添付動画まであるわよ。『特別休暇を利用して、凍った海面を犬橇でピオンビーノからバスティアまでタリサと一緒に踏破したよ』ですって」
「バスティアって、コルシカ島の?」
「イタリア本島から片道九十キロはあるわね。なにをやってるんだか。相変わらず研究以外じゃ、馬鹿なことしかしないわね、あの男は。それにしてもなにもそんな無謀なことにタリサも付き合わなくてもいいのに」
「でも、特別休暇が貰えてるんなら、彼らの対極寒因子発現の研究が一段落したんじゃない?」
「えぇ、そうね。でなきゃ、研究所から放り出されたかだね、あの我がまま勝手な性格だもの」
ナナはイタリアにいる同窓生の数々の奇行を思い出して笑い声を上げた。ルーシーは次のファイルを開いて目を丸くした。
「たいへん。嘘。まさか今日じゃないの。これ」
「どうしたの?」
「マリクとタリサの研究の出資者がここに来るわよ。私たちの研究にも興味があるんだって。しかも今日よ!」
「嘘でしょ。いまどき自由に世界中飛びまわれる人間なんているの。私たちだって本国に帰るときだけよ、飛行機が許されるのは。それに一度帰れば、今はもう出国自体を規制されちゃうし」
「超がつくほどの大金持ちは別なのよ、ナナ。世界が氷で閉ざされようが、世の中の本質は変わらない。力のある者がすべてを動かす。それより、あんた嬉しくないの。研究費が増えるかもしれないんだよ」
「そりゃ嬉しいわよ。でも、大金持ちだからって緊急備蓄燃料を勝手に使うことなんてできっこないわよ」
「だから、そんなもの、どうにでもなるのよ」ルーシーは、なおも反論しようとするナナを無邪気に制した。「しかも、この出資者は貴族様よ。腐るほどお金を持ってるのは間違いないんだから、なんとかしてそれを引き出さなきゃ。いいわね」
ナナとルーシーはバスがターミナルに着くや否や、雪の吹きすさぶ中を一目散に研究棟に駆け込んだ。そして、暖をとる時間も惜しんで実験の成果を披露すべく、資料を整理して、自分たちが陸棲転化に成功した軟体生物のお披露目の準備に取り掛かった。
*
結局、多くの研究員たちの中で、出資者と直接対話が出来たのは数多くのグループの中で三グループの五名だけで、所長や上席研究員ですら、彼の興味が向かなければ挨拶はおろか、その顔を見ることすら叶わなかった。そんな中、ナナとルーシーは自分たちの研究成果が認められたことを誇らしく思う反面、ともに選ばれたグループの中にシンガポール科学技術研究庁で自身の研究のためなら殺人すら厭わないと噂されるほど傲慢で偏屈な奇人、ハーバート・イースト準教授が入っていたので、手放しで喜ぶ気にはなれなかった。特にルーシーなどは、相互協力の名の下に準教授と行わざるを得なかった度重なる実験がナナの脳腫瘍の原因の一つになったと信じて疑わなかった。とはいえ、どんな状況にあっても、今回のように無尽蔵と思えるくらいの資金を有する出資者に研究の重要性を直接アピールできるのは何物にも代えがたいチャンスであることに違いはなかった。ナナとルーシーは、出資者が量子脳工学の権威である奇人医師との面談を終えて自分たちの研究室に足を運んでくれるのを今か今かと待ち構えていた。
しかし研究室の壁に掛けられた時計の短針が面談予定の真上から右側に大きく傾くにしたがって、喜びと期待から姿を変えた不安と苛立ちが失望へと変わり始めてきた。ナナが
二人の若い研究者の前に黒ずくめのスーツを隙なく着こなした青白い肌の長身の壮年紳士が立っていた。
「これは、これは」
それが紳士の第一声だった。
皮膚からじわりと染み通るような、そのバリトンにナナは言い知れぬ不安を覚えた。彼女はそれを一介の研究者が、住む世界の異なる上流階級の人間を前にしたときの畏れからくる武者震いのようなものだと理解しようとしたが、心の片隅では、もっと根源的なところからくる警鐘に近い感覚にも思われて少なからず動揺した。そんなナナの脇腹を、業を煮やしたルーシーが肘でさり気なく小突いた。
「失礼しました」我に返ったナナは慌てて口を開いた。「お待ちしておりました、ブロドリップ卿」
「こちらこそ、ずいぶんお待たせして申し訳ない」ブロドリップ卿と呼ばれた紳士はそこで言葉を切ると、二人の頭越しに視線をちらりと室内に走らせた。「さて、差し支えなければ早速お話をうかがいたいのですが、構いませんかな、お嬢さん方?」
「それはもう。どうそ、中にお入りください」
「えぇ、歓迎いたします」とルーシーに続いてナナ。
「ありがとう。それでは遠慮なく」
ブロドリップ卿と呼ばれるこの長身痩躯の壮年貴族が経済界に
「少し狭いですが」ルーシーがブロドリップを部屋の奥へ促した。
研究室に隣接した居間に第一歩を記したブロドリップは清潔に保たれた空間をしげしげと見回した。
「管理が行き届いて整然としていますね。大きな成果はこんな繊細な環境からもたらされると私は信じています」
「ありがとうごいざいます。ところで私たちの研究成果を見ていただく前に、お茶はいかがですか、丁度いま炒れたところですので」
「ええ、いただきましょう」と、緊張の面持ちのルーシーに返答すると、ブロドリップはナナに視線を向けた。ナナの背筋に微かな悪寒が走った。しかし彼女はそれを無視して彼を居間の奥の研究室へ案内した。
「早速ですが、私たちの研究の重要性についてなのですが……」
「ナナ。まだお茶も召し上がってないわ」
「いえ」ブロドリップは右手の人差し指を軽く掲げて彼らに追いついたルーシーを優雅に制した。「今の緊迫した世界情勢から鑑みるに、お二方の研究が重要かつ緊急を要するものと考えればこそ、こうして直にお話を伺いたく思って足を運んだのです」
ブロドリップはルーシーから湯気の立つ茶碗を受け取ると口もつけずに言葉を続けた。
「なんでも、お二方は海棲生物の陸棲化に成功なさったとか」
「えぇ、そうです」とルーシーが即答した。「正確には海棲軟体動物。頭足類である
「これですか?」
「えぇ、そうです」
三人は室内の三分の二以上を占める幾つかの水槽のうち一番奥のひときわ大きな水槽を覗き込んだ。水槽の中は、その半分の高さまで雪と氷が敷き詰められていた。
「これが今の地球表面の六〇パーセントの状況です。来年には最低でも七二パーセントが雪と氷に覆われます」
「スノーボール・アース……スーパー氷河期ですね」
「えぇ、そうです。そして凍った海では漁も思うように出来ません。もちろん大量の魚類が残っていればですが」
ルーシーが水槽横のラップトップを開いて操作すると水槽上部の照明が徐々に明るさを増していった。
「人工太陽灯です」ナナは、その言葉を聞いたブロドリップが、一瞬忌々しそうに顔を歪めたことには気付かなかった。「氷河期でも、まったく陽の光が望めないことはありません。私たちは、そこに着目しました。この烏賊たちは雪の中に混じりこんだ少量の不純物やシャーベット状の海水からエネルギーを取り込むだけで生育できるだけでなく、光合成も行えるんです」
「さぁ、ご覧ください。やや左側の雪の中です」
ルーシーの声が合図であったかのように雪の下から六匹の二十センチほどの陸棲烏賊が、もぞもぞと雪と氷をかき分けて灰色の胴体を現すと、個々にその表面を電飾のように青く光らせ始めた。
「彼ら、喜んでます」とナナが画面に見入りながら嬉しそうに口を開いた。
「海棲生物の気持ちがわかるんですか、ミス・ジーランド?」
「いえ」ナナは質問者の貴族に肩をすくめた。「たぶん、そうではないかと考えているだけです。こんな色素胞の変化は、私たちも見たことがありませんでした。恐らく遺伝子の組み合わせ過程で今まで眠っていた何らかのスイッチが入ったか、働きが未解明だった遺伝子にこのような反応をするものがあったかだと思います。何れにしても太陽灯が点くと、こうして気持ち良さそうに日向ぼっこです」
「可愛らしいですね」
「えぇ。軟体動物にこんな感情を抱くなんて思いもしませんでした」
「いえ。彼らがではなく、あなたがということです」
久し振りに掛けられた異性からの好意的な言葉に、ナナは思わずブロドリックを見つめ返した。不安を掻き立てられる雰囲気が減じたわけではないが、なかなか魅力的な男だ。
「ところで」ルーシーは咳払いをすると次の説明に移った。いよいよ本題だ。「わたしたちはこの
「再生能力……傷を治すということですか。私はこの生き物がどれ程の時間で傷を治すのかすら、わかりませんが」
「えぇ。ですが時間だけではありません」と、ルーシーはラップトップ上で別の動画画面を呼び出した。「これをご覧ください。画面上にいるのは、この
「というと」
「元通りになるかどうかの実験です」ルーシーはそう告げると、動画を再生した。「もちろん成功しました。一体残らず、足の再生実験に成功したのです。しかも九六時間で欠損箇所を完全再生します」
早送りされた動画の中で、高速度撮影された植物の発芽のように六体の中の四体の烏賊の足が完全に再生された。
「これを雪の中で飼えば、特定の餌もいりません。定期的に足を刈り取ればいいのです、まるで、その……」
「羊毛のように」ナナが助け舟を出した。
「羊毛ですか」
「えぇ」とルーシーは頷いた。「羊毛は食べれませんが、彼らの足は食糧になります。この氷河期に手に入る唯一無限の食糧資源です」
「なるほど。そして、これを量産すると言うことでしたね、ミス・ギャレット?」
「えぇ。正直に申し上げて、遺伝子操作で繁殖力こそ落ちてしまいましたが、私たちは、その問題を必ず解決できると考えています」
「しかし」ブロドリップは僅かに視線を落とした。明らかに納得に至ってはいないサインだ。「世界の人々には食べ慣れたものではないですね、この
「まず、
「申し訳ありません」ルーシーも口を開いた「もし、ご気分を害されたのでしたら謝ります。しかし、わたしたちは」
ブロドリップは再び人差し指を上げて、ルーシーを制した。「いえ、お二方は氷河期に突入した世界で人類を助けようと奮闘なさっておられるのです。賛辞がありこそすれ、それを貶すなどもっての外だ。それを忘れた私が悪かったのです。思慮が足りませんでした。どうか、今以上の援助に免じて、私の無礼をお許し願いたい」
「『今以上の援助』?」ナナは身を乗り出した。「それでは、私たちの研究は……」
「もちろん、大いに続けてくださって結構です。これからは金銭面だけでなく、その他、各国の許認可などもご心配なく」
「ありがとうございます。なんと御礼を申し上げればいいか!」
「いえ、礼には及びませんよ。お二方の研究の片鱗をイースト準教授からもうかがっていたのにも関わらず、失礼なことを申し上げたのは私の方ですから」
「そうでしたか」ルーシーから笑顔が消えた。
「えぇ、先ほどお会いしたときにお聞きしました。どうかしましたか、ミス・ギャレット?」
「いえ」
イースト準教授の試作型量子脳コンピューターのバージョンアップのための度重なる脳トレースが、ナナの脳腫瘍の原因だと信じて疑わないルーシーにとって、彼の名前は浮き立った心を穏やかならざるものにするのに十分な呪詛の言葉だった。もちろん“電脳の心を培う”だかの変人の実験を二人して好き好んで手伝ったりしたかったわけではなかった。しかし陸棲烏賊を造りだす過程で必要な生物間の遺伝子の組み合わせ演算とその予測、その他、膨大な理論上の処理をイーストに依頼する見返りに、親友をMRIの化物のような不快極まりない人工知能の犠牲にしてしまったという忸怩たる想いをルーシー自身は未だに持ち続けていた。
「実験は持ちつ持たれつということですわ、ブロドリップ卿」ナナは自責の念に駆られているであろう親友を気遣って代わりに口を開いた。「特にそれが繊細であればあるほど。それで互いの研究に得るものがあれば、私たち科学者には他に何も言うことはありません。前に進み続けるだけです。ちなみに準教授からは、他にどのようなことをお聞きですか?」
「同僚の評価が気になりますか?」
「えぇ、少し」本当は凄く。しかしナナは何とかその思いが表情に出るのを抑えた。
「では正直に。『研究の着眼点は素晴らしいが、実用段階までには改良の余地が多々残されている』と評価されていました」
評価は評価でも、これでは完成には程遠い欠陥品との酷評と同じではないか。傲慢で偏屈なイーストらしいといえばそれまでだが。ナナとルーシーは、その評価に揃って鼻白んだ。ブロドリップがいなければ、やり場のない、あまりの怒りに二人とも朝食を床に吐いてしまうところだった。
「ですが、私の見る限り、準教授の研究も、まだまだ改良の余地はありそうでしたね」
「『まだまだ』ですか?」とナナは、目の前の貴族の言葉を繰り返した。
「そう。まだまだです。だから、お二方を含めて皆さんには今後も私の援助が必要だということです」ナナの気持ちを知ってか知らずか、ブロドリップは微笑んだ。「特に有望な研究にはですよ。さて、お忙しいのに長居をしてしまいました。次には、より完成に近づいた成果を見せていただくことにしましょう」
失敗とは言えないまでもスポンサーの興味を失わさせずに済んだようだ。それどころか今以上の援助を取り付けることができた。
こうして、魅力的だが、どこか言い知れぬ不安に駆り立ててくれるスポンサーは去っていった。しかし彼が去っていった日からナナは奇妙な夢を毎日見るようになった。
*
見渡す限りの緑の大地を遙か眼下に望み、自由に大空を滑空する夢。妙に鮮明なその夢の中で、ナナは大空に漂う真っ赤な風船を懸命に追いかけては、それを掴もうと必死に手を伸ばす。突風に翻弄される風船は彼女の手をすり抜けてゆくときもあれば、運よく掴むことができることもある。しかし、やっと掴むことができても、その瞬間に風船はシャボン玉のようにぱっと弾けてしまう。だが一瞬でも掴むことができた日は一日中気分よく過ごすことができた。いや、気分よくというより、末期の脳腫瘍患者であることを忘れてしまいそうなくらい心と身体に力がみなぎって、すこぶる調子がいいのだ。そんなことが、もうひと月は続いていた。ブロドリップとの面談の後、ナナとルーシーは研究室に毎日泊まりこんで陸棲烏賊の更なるデータ収集と生態観察に明け暮れた。その間、ルーシーがアパートに戻っても、自分にはもう時間が残されてないのだと言い張って、ナナは戻るのを拒否して研究室に籠りつづけた。そして今日は着替えを取りがてら、久しく帰っていないアパートに戻っていた。
アパートの中は氷点下だというのに、どこも黴の匂いがした。ナナは洗濯物を洗濯機に詰め込むだけ詰め込むとスイッチを入れた。有難いことに、ここでは電気と水道だけはまだ生きていた。次に彼女は台所で冷蔵庫を開けてみた。さして中身はなかったが、帰宅してから喉の渇きを覚えていたのでトマトジュースのボトルを引っ張り出してコップに注いで飲み干した。さして旨くはなかったがお代わりを注いだ。そこではじめてラップトップの呼び出し音が鳴っているのに気が付いた。ルーシーは二週間前から南スマトラ沿岸から少し内陸に入った新たな研究施設で陸棲烏賊の放牧実験に出かけていた。ナナは実験の過程を知りたかったので、いつでもルーシーと話せるようにしておいたのだ。
ナナはコップを持って居間から狭い自室に戻ると、ベッドの上のラップトップに顔を近づけた。通信事情の悪化のため画像の乱がしばらく続いたが、すぐに目の前にやつれ切ったルーシーの顔が現れた。そして親友の横には同じようにやつれ切った友人のマルクの顔も見えた。彼は婚約者のタリサとイタリアで対極寒因子発現血清の最終試験中のはずだが。
「ハイ、ルー。ハイ、マリク」
「そんな……ナナ……」
画面から戸惑いと怯えを滲ませたルーシーの声が漏れ、ナナは思わず聞き返した。
「どうしたの、ルー?」
マリクがルーシーの耳元で何か囁いたがナナには聞こえなかった。だが彼の顔は引きつって蒼白だった。
「ねぇ、いったい何?」
「いえ。何でもないわ……」
「嘘よ。何もないわけないわ。どうしたの?」
ナナの問い掛けは沈黙で返された。
「ねぇ。ふざけてるんなら怒るわよ」ナナは唾を飲み込んで沈黙の理由をあれこれと類推してみたが、行き着くところは一つだった。「実験ね。そうでしょ……。正直に話してちょうだい。実験で烏賊たちに何かあったのね?」
「何もないって言ってるだろ!」
業を煮やしたマリクが画面に割って入った。冗談好きで温厚な彼とは思えない言動と表情に、ナナは、ますます疑念を募らせた。
「何もないわけないじゃない!」ナナも声を荒げた。「第一、あなたはタリサとイタリアで、まだ実験中のはずでしょ?!」
タリサの名前を耳にした途端、マリクは「くそ」と呟いて画面からフレームアウトした。残されたルーシーの目に涙が浮かんだ。
「いったい、どうしたっていうの、ルーシー?」
「本当にわからないの、ナナ?」
「えぇ。わからないわ。説明して」
フレームの外から「無駄だ」というマリクの吐き捨てる声が聞こえた。ルーシーは声の方をチラリと見やると意を決して口を開いた。
「烏賊たちの放牧実験は順調に進んでるわ。それだけは確かよ、だから安心して」
「本当に?」
「えぇ、本当よ……でもね……」
「だから、いったい何なのよ?!」
ルーシーは踏ん切りがつかないらしく、しきりに唇を舐めては、ちらちらと画面の中を覗き見ていた。
「お願い。話して」
「タリサが死んだの」それだけ言うとルーシーは目を伏せたが、大きく息を吸うと再び画面に向き直った。「いえ、死んだんじゃなく、私たちが滅ぼしたの。そうせざるを得なかったから」
ナナの沈黙は長かった。やがて彼女は怒りに顔を強張らせた。「なんの話、ルーシー。冗談でも酷すぎるんじゃない?」
「冗談でこんなこと言えるわけないでしょ。彼女はね………タリサはヴァンパイアだったの。多くの人が彼女の犠牲になったわ。こんなご時世だもの、仲間の研究者に犠牲が出始めるまで、マリクも気付かなかったのよ。もしかしたらタリサ自身も自分が何をしてるか、わかってなかったかも……」
「いったい何の話をしてるの。せっかく繋がった通信なのに唐突に下らないお伽話なんて、いくらなんでも付きあってられないわよ!」
「まだわからないの、ナナ。ブロドリップよ。奴はヴァンパイアだったの。タリサを仲間に引き入れて」そこまで言うと画面の奥でルーシーは涙をぬぐった。「タリサはスマトラまでマリクを追いかけてきた。そして私たちに滅ぼされて枯葉みたいに燃えて灰になったわ、弱々しい薄暮の下でね。そんな死に方ってあると思う。冗談なんかじゃないのよ」
「そんな話、信じられないわ」
「あなたの周りでも行方不明者が出始めてるんじゃないの、ナナ?」
「ずっと研究室から出てないから、わからないわ……」
「ネット・ニュースは、まだあるでしょ?」
「最近のアクセスの酷さは知ってるでしょ。どんどん悪くなってるのよ。それに研究ばかりだったから」
ルーシーは再び大きく息を継ぐと、自分を納得させるかのように何度か頷いてみせた。
「あなたが、いつからそうなったかはわからない。でも、少なくとも私は……私はそうなってない。もし、あなたに人間らしい心がまだ残ってるのなら……あぁ、親友にこんなことを言うなんて、でも……お願い。自分自身が大事なら。まだ、あなたがあなたなら自殺して。手遅れにならないうちに」
「もう切るわ。付き合ってられ……」
「ナナ」ルーシーはナナを遮った。「たぶん、あなたは手にコップは持ってるはずよね。それは私にも見えるわ。でも、それだけ。宙に浮いたジュース入りのコップだけよ、私に見えるのは。声は聞こえるけど、あなたの姿が見えない。画面に姿が映らないのよ、あなたはもう魂を持たないヴァンパイアだから。……さよなら、私の親友。大好きだったわ……」
ルーシーは泣いていた。そしてナナは一方的に切れた通信画面を暫く見つめていたが、ラップトップを畳むとベッドから降りてバスルームに向かった。そして洗面台に据えつけられてる鏡の曇りを手で拭うと食い入るように覗き込んだ
彼女の喉からクックックッと声が漏れた。それが笑い声なのか嗚咽なのか、ナナ自身にもわからなかった。研究棟では毎朝顔も洗っていたのに鏡さえ、まともに見なかったのは、なぜなのかもわからなかった。ナナは叫び声を上げると自分の背後のバスルームの壁しか映し出さない鏡を素手で叩き割った。血が飛び散るほど何度も鏡に向かって手の平を打ちつけた。ガラスで切れて血が流れ出たが、すぐに傷が塞がって元通りになった。その不思議な光景に心を奪われている彼女の頭の中に声が響いた。声はしきりに部屋へ招き入れるように要請していたが、ナナはそれを無視した。声は要請が聞き入れられないことに心底驚いているようだった。しかし、諦めず執拗に命令してくる。
ルーシーの言うようにブロドリップがヴァンパイアで、自分を仲間に引き入れたのだとしたら、これほど腹立たしいことはない。いや。そもそもこんな馬鹿らしいことが現実であるわけがない。きっと脳腫瘍がもたらす白日夢の中にいるのだ。だが自分にそう言い聞かせようとするナナの頭の中では「部屋に入れろ」と執拗に命令する強圧的な声が響いている。頭の中に響く声がどこからするのか不思議とナナにはわかった。彼女は声の主に怒りをぶつけようと急いで居間に戻ると道路に面した窓を勢いよく押し開けた。雪が深々と降り続く中にブロドリップが佇んでいた。
やはりそうか。ここまできてナナにも、やっと得心がいった。人間なら三階の窓の外の空中に立てるわけがないのだから。
「そなたのような娘は初めてだ」
ナナは古風な言い回しをするヴァンパイアのブロドリップを無言で激しく睨みつけた。
「さぁ、そろそろ部屋へ招き入れてはくれまいか。でないと、この寒空で凍えてしまいそうだ」
自分の言ったことが面白くて堪らないというように寒さを感じないヴァンパイアは笑い声を漏らした。それでもナナは彼を無視して、ただただ憎悪を込めて睨み続けた。
「私はお前が何を怒っているのかわからぬ。だが、それ以上に、お前が我が命に、なぜ背けるのかが謎なのだ」初めて会った時の謙虚さは、もう欠片も残っていなかった。ヴァンパイアはなにか閃いたかのように自分のこめかみを指先でトンと突いた。「死の病がそうさせるのか。いやいや、そうではあるまい。以前、お前と同じ病の者も、ほんのひと噛みで我が傘下に馳せ参じたのだ。ではなぜだ?……」
「あんたが嫌いだから。憎いからよ」
すぐさまヴァンパイアは人差し指をたててナナを制した。
「そなたの気持ちなど関係ない。多くの
ナナはヴァンパイアが言い終わらないうちに怒りに任せて窓外の彼に飛び掛かっていた。しかし、その人間離れした体当たりも難なくかわされ、遥か下の凍ったアスファルトの路面に激しく叩きつけられた。身体の中で骨の砕ける音と内臓が押し潰される音がした。ナナは全身を貫く激痛に咳き込むと雪の上に大量に吐血をした。
「なぜ我に牙を向けられる。なぜ
ナナの耳元でブロドリップの声がした。
「あんたは友人を殺した!」
ナナから流れ込んだタリサのイメージにブロドリップがすぐさま反論した。
「あれを滅ぼしたのは人間だ。お前のかつての友人たちではないか」
「じゃぁ、やっぱり事実なのね。ヴァンパイアにされなきゃ、彼女は死なずに済んだ!」
「人間のままなら、いずれはこの氷河に押し潰され、すり潰されて死ぬのだ」
「人間はそんなに弱くないわ!」
「買い被るな。弱いからこそ、他人を押し退けてまで食糧に群がり、自分だけ暖をとろうとするのだ。氷河期が訪れ、どれほどの人間が死んだことか。どれほどの国が反目し合って滅ぼしあっておることか」
「許せない」
「何が許せぬ……友が滅んだことか。それとも人の文明が滅ぶことか。まさか我が一族にお前を迎えたことではあるまい。ヴァンパイアになろうと、お前はナナ・遠野・ジーランドのままだ。変わったのは、お前の周りだ。なぜなら今もお前は残された人間のために研究を続けようとしているではないか。翻って、親友たちはどうだ。友人を滅ぼし、あまつさえ、お前を見捨てた。違うか?」
「ルーシーが私と関係を絶ったのは、ヴァンパイアが人間を襲うからよ。私がその化け物になったからよ!」
「左様。されど我れらが
「嘘よ!」
むろん、嘘だった。
しかしナナの目の前のヴァンパイアが古来より悪人の方を多く餌食にしていたのは紛れもない真実だった。なぜなら悪人の血は、より強い力を授けてくれるだけでなく、善人より遥かに刺激的で美味だったからだ。それゆえに彼は長い休息から目覚める度に世界のどこかしこに内紛の芽を見つけては、それを育てたり、疫病を流行らせては、人心を荒ませ、悪心の量産と高濃縮化に腐心してきたのだった。
「人間の本質は悪だ。異質というだけで残酷な仕打ちを何の呵責もなくやってのけられる。先ずはお前もその事実を味あわねばならぬようだ。そして我が命に従わぬ愚かさを悔い改めた方が良いぞ、我が妃よ」
ヴァンパイアの姿が風雪の中に掻き消えた。
暫くしてアパートの角を曲がって派手に警告灯を点滅させた警察車両が通りに何台もなだれ込んできた。車両はどれもナナの前で急停車するや否や重武装の警官を次々と吐き出すと血まみれのナナに眩しいライトと銃を向けた。
「さぁ、どうする? あの者たちはお前を害しようとしているぞ。だが、そうさせなくするのは簡単なはずだ。ほら、夜ごと風船を掴むように」
ナナの頭の中にヴァンパイアの声が響いた。途端に、毎晩、自分が見ていた夢が意味するものを彼女は直感的に理解した。空に漂う風船は、風船ではなかった。逃げ惑う人間であったということに。
ナナの目は涙と後悔で曇りはじめた。彼女は銃を向ける警官たちに両手を上げて敵意がないことを示しながらも、自分が犯した罪の大きさに恐れおののき、激しく震えはじめた。
「怪我をしてるぞ」一人の若い警官が小声で横の同僚に囁いた。
「黙ってろ、シン」若い同僚を制した年かさの警官はナナから目を離さず、防弾ベストに装備された無線機に向かって報告した。「通報通り、臨海居住区裏で容疑者を発見。複数の目撃情報と完全に一致している」
「怪我をしてるのか。手当ては必要か?」
シンと呼ばれた若い警官がナナに再び呼びかけ、ナナは黙って首を横に振った。既に痛みは消えていた。ヴァンパイアの治癒力は短い時間の間に三階から転落した彼女の身体を完全に修復していたからだ。
「貿易商及び警官殺害の容疑で逮捕する。両手を頭の上で組み、路面に膝をつけ!」
年かさの警官の言葉に、その傍にいる女性警官も「言われた通りになさい!」と追随した。
「容疑者は普通の状態じゃないです」若い警官のシンは慎重にナナに近づいた。「怪我の程度を見ないと、後で何かあったら訴えられますよ」
「やめろ。距離をとれ!」
「大丈夫。危険な兆候は見えません」
しかしナナにあと一歩の所でシンの喉がぱっくり開いて鮮血がほとばしった。ブロドリップの仕業だった。しかしナナは喉を押さえたシンを助けるでもなく、彼が路上に倒れ伏すまで顔にふりかかる血を無意識に手の平に受けて喉を鳴らして呑んでいた。遠くの方で悲鳴や叫びを聞いた気がしたが、気にならなかった。頭や体を何度も小突かれる感触を味わったが、湧き上がる陶酔感に我を忘れた。これでは駄目だとナナが意識を強く持って自分を取り戻したときには恐怖に引き攣った警官たちの銃撃を一身に浴びている最中だった。
警官たちにとって、頭と言わず胴体と言わず拳銃やショットガンの弾を無数に浴びても倒れないナナは不死身の化物そのものだった。ナナは悲鳴を上げると、その場から逃げだした。人間には到底追いつけないスピードで逃げ去ったナナのあとを彼女の悲鳴だけが不気味に追いかけた。ブロドリップの高笑いがその悲鳴に微かに混じっていたのを聞けたのは、悲鳴を上げた本人だけだった。
数時間後、パニックから解放されたナナは研究棟まで戻ってみたが、エントランス前で緊急配備された警官や警備員たちの激しい銃撃を受けて早々に退散した。予想されたこととはいえ、人々の反応にナナは途方に暮れるしかなかった。しかもヴァンパイアになってしまったとはいえ、体力が無限に続くとも思えない。明け方近くにナナは激しさを増した吹雪に紛れて再びジェロン島に舞い戻ることに成功した。そして人気のない工場群の屋外に雪の吹き溜まりを見つけると、寒さを全く感じなくなった身体をそこへ横たえた。疲れ切った身体に雪が降り積もってゆく。無事に目覚めることができればルーシーのいる南へ出発しよう。自分が以前のナナと変わりないことを信じてもらい、そこでこの身体を元に戻す努力を一緒にしてみるつもりだ。だが、もし親友の所にたどり着く途中で息絶えるなら、それはそれでいい。突然ヴァンパイアにされてしまったという事実は、そこまで彼女の心を投げやりにさせてしまっていた。
やがて眠りに落ちたナナは、この日だけは夢を見なかった。
*
シンガポールからスマトラ半島にかけての海は水深が浅く、そのほとんどが固い氷に覆われていた。ナナは凍った海面を吹き渡る風よりも速く夜の闇を駆け抜けた。ヴァンパイアに転生したいま、息切れもしなければ疲れや寒さを感じることもなかった。途中の洋上で打ち捨てられた大型の豪華クルーザーを見つけて、そこで幾晩か過ごした。船内に入った時、喉の渇きを覚えたが遺棄されていた凍った船客たちの遺体から血を飲もうとは考えなかった。このとき頭にあったのは親友と再会して誤解を解くことと残された研究の事だけだった。だから凍りついた空の船室で眠っている時に赤い風船の夢を見ても完全にそれを無視することができた。それでも我慢できなくなると船内に残された食べ物を試してみた。固形物は見ただけで胃がむかついた。酒は呑んでみたが酔いもしなければ味もせず、渇きを癒すことすらできなかった。味覚だけでなく代謝も人間とは変わってしまっていたのだ。しかし倉庫にあったトマトジュースだけは少しずつ噛むように飲み込むと、アパートで過ごした最後のひと時と同様に咽喉を潤すことができた。その色が血を連想させて
四夜目。
クルーザーの船長室で目的地である南スマトラの詳細な地図を物色する間も、ナナは科学者として今の自分にできる簡単な実験に明け暮れた。
そう人体実験だ。
ナナは医務室に入ると、そこに残された数少ない薬品でパッチテストを行ったり、身体修復能力を試すため、体内に致死量の劇薬を注入してみたりした。自分の他にヴァンパイアにされた者が、どうしてもその状態を受け入れられない場合、自決の手を差し伸べる方策を得ることができるかもしれないという思いからだ。しかし予想通り医薬品類はおろか、劇物も毒薬もナナにはほとんど無害か役に立たなかった。再び空腹を覚えたナナは、次にクルーザー内を調べて凍った死体の血液以外に摂取できるものが残されていないか試すことにした。試す食料が底をつくと洗剤から船の燃料まで口に含んでみたが、口にした途端に
「塩分やミネラルに期待してたわけじゃないけど、無限の海水で生きれれば、私もあの子たちと同じね」
ナナは研究していた陸棲烏賊のことを思い出すと、居ても立ってもいられなくなり、自身の人体実験レポートを船内で見つけたデイパックに突っ込むと、六夜を過ごした難破クルーザーを後にした。
そして翌日には南スマトラに上陸を果たし、その山中を飛ぶように頂上へ向けて駆け上っていった。
山頂から見ると、遥か前方の凍った湖を臨む山間部一帯に目指す研究施設が見えた。いや研究施設というより、それは四方を高い城壁に囲まれた城塞都市だった。以前、ルーシーが送ってくれた動画で見た研究施設とは似ても似つかないその禍々しさに、ナナはただただ目を見張るしかなかった。