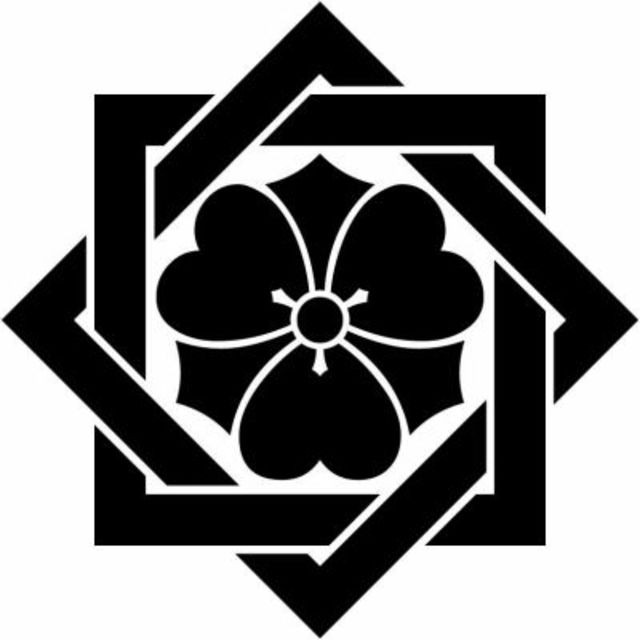第28話 歓喜と探索と
文字数 5,306文字
子孫の骸 に潜んでいた、その存在は待ち望んでいた一言を耳にして喜びに身をうち震わせた。生きた人間の口から発せられた嘘偽りのない招待の言葉。魂のない身に染み渡った、気の遠くなるほど待ち望んだ一言。その存在は大声で叫び出したくなるくらい狂喜した。そして興奮冷めやらぬままに人間からの招待を快く受け取るや、巨大な結界に開いた小さな穴を素早く潜り抜けると、招待者の人間に礼を失せぬように感謝の一撃を見舞った。一撃をまともに受けた招待者は甲冑を半ば断ち割られ、それに守られていたはずの背中は切り裂かれた。彼の背中一面は雪の上に倒れ込む時には真っ赤に染まっていた。それは世界の全てが、余すところなく、その存在に開かれたことを高らかに謳いあげる血で書かれた宣言文であり、今まで手出しが叶わなかった一握りの高慢な人間どもの終焉の始まりを示す、鮮やかな真紅の戦旗でもあった。
「さて、さて。最初の出し物が始める前に何をしようか?……」
子孫の身体を支配しているその存在は、今では黒く汚らわしい蠅の大群のような渦巻状に広がる外観を人間の目から隠そうともしなかった。それは幼子が絨毯の上で遊ぶように、ブンブン唸りながら広大な城塞都市 の中空を楽しげに転げまわった。そして建物の間を意志を持った矢のように縫いながら飛び回ると、爆撃機が腹の中の爆弾を投下するかのように、必要のなくなった骸 を地上目がけて捨て去った。数瞬後、子孫の骸は雪煙を巻き上げて街区にある大通りの真ん中に深々とクレーターを穿った。骸 の中では地上への落着と同時に時限装置を思わせる新たな脈動がゆっくりと、しかも着実に刻まれはじめていた。都市では、またいつもの一日が始まる。しかし、それは今までの一日とは全く異なったものになるはずだ。その脈動は、まるでそう告げるかのように周りの雪を震わせはじめた。
身軽になった黒い渦巻は曇った中空のキャンバスに、ゆったりと浮遊していた。自身が一番望んでいたこと。恐怖の果ての無残な死を、またそこからもたらされる避け難い絶望と苦痛を、ここにいる人間たちから広く収穫するにはどうすればいいのかは、もう既に知っていたので、風の流れに身を委ねて漂っていた。今までの運命を憤る必要はもうない。あとはわくわくしてお楽しみを待つだけなのだ、ただただ新たな一日の始まりを。
広大な城砦内に横たわる様々な形状の建築群。強化セラミックとローマ式コンクリートで形作られた文明の残滓 。住居棟とそれに隣接する食糧の自動生産施設。その片隅で一部が細々と稼動している工場。壊れた医療施設。空っぽの学校。そして自然公園になるはずだった手付かずの広大な更地。二十万人を越える人間が自給自足の生活ができるように設計されたこの城塞都市 は、今となっては当初の計画の十五パーセントに満たない人口しか養ってはいなかった。その文明の残滓 を黒い渦巻きは観光旅行者がするように無遠慮に、しかも興味深げに見聞しはじめた。もしガイドがいれば、その説明にいちいち頷いたり、首を振って感嘆することもあったろう。だが、城砦内の四分の一も観終わらないうちに街区の一角に最初の変化が現れた。
「これは、これは……もうはじまってしまったか」
その声ならぬ声は観光を中断された残念さよりも、膨らむ期待を抑えるかのように、うち震えていた。
*
目覚めた都市が動き出す頃、建物群の一角にある大きな十字路の一つから、苦痛に満ちた断末魔の合唱が途切れることなく流れはじめた。
*
不安は恐怖を産み、その恐怖は容易に恐慌 を育て上げる、しかも自分の手には負えないほどに。しかし、ジョウシは幼い頃からそうであったように、それらが自分の手に負えなくなる前に根元からごっそりと、それを刈り取ってやろうと決意していた。そのために必要なのは不安と恐怖とは反対の方向へ向かう論理の力だ。だが、その力を呼び起こすには強い自制心しかない。落ち着くのだ。考えろ。今の理解しがたい状況から分析されたものを素直に受け止め、それを充分に咀嚼 して対処法を探す。幼い頃に村のイジメっ子どもを何度も出し抜いたようにすればいいのだ。ジョウシは自分に、そう言い聞かせると目の前の荷台に横たわる傷ついた人間の戦士に静かに語りかけた。
「お前は自分を襲ったモノを見たか?」
「いや、見てない」苦痛にエイブの顔が歪んだ。
「以前は、どうじゃ。突然、お前のように瞬時に深手を負わされた者を見たことは?」
「いいや。それもない」
「聞いたこともないか?」
「あぁ、ないな」
「左様か……」
「何か答えを知ってそうな口調だな」エイブは痛みに堪えながら、疑いの眼差しを質問者に向けた。「この期に及んで、まだ何か隠し事をしようってのか?」
「あの時のことね」ファニュが心配そうにジョウシの顔をうかがった。
「そうじゃ……」
ファニュに応えるジョウシの顔は、負傷したエイブとは違った苦痛を耐え忍んでいるようだった。
「だから、それはなんだって聞いてんだ」
「隠し事などではないが」ジョウシは観念したように口を開いた。「ただ似たような力の発現に我れらは遭遇したことがある」
ジョウシは、ヴァンパイアの力を覚醒させた仲間のミソカが見せた超能力をかいつまんでエイブに説明した。
「やっぱりか。俺はヴァンパイアにやられたってことなんだな」
「おそらくは……」
「何が『おそらくは』だ!」エイブは痛みも忘れてジョウシにくってかかった。「お前らは危険だった。お前らを信じた俺が馬鹿だったんだ」
「エイブ、落ち着いて。何もヴァンパイアが犯人だなんて決まってないわよ」
「これが黙っていられるか、ファニュ。今の話を聞いて、こいつらヴァンパイア以外に犯人は考えられねぇだろ。くそ。しかも俺はこいつらを都市内に呼び込んじまったんだぞ」
「そうじゃな……ヴァンパイアの他に犯人はおるまいな。しかし、それだけでは正鵠 を射てはおらぬ。問題は、お主がヴァンパイアの“誰”を呼び込んだのかということじゃ」
「お前らの他にもいるってことか?……」
エイブはジョウシを、次に橇を走らせている馭者台のタンゴの背中に視線を走らせたが、沈黙に報いられただけだった。次に彼は問うような眼差しをファニュに向けた。しかし、そのファニュも既に沈黙の仲間になっていた。
「いったい、どういうことだ?……」
答えを得られないままのエイブは、大きな溜め息をつくと視線を橇の床に落とした。視線の先には自分の血で新たに赤黒くペイントされたキャンバスが敷かれていた。彼の目は、それに釘付けになった。ほんの少し前まで何かが包まれていたはずのキャンバス。その時、彼は自分を襲ったモノが何だったのかをにわかに悟った。
「いま気づいたんだが。もしかして、ここに乗っていた奴が……もしかして、お前たちが番を頼んだ死体が……」
「違うよ!」
振り向きもせずに即座にタンゴが否定した
「されど、それしか納得のゆく答えはあるまい」
「チョウヨウは、そんなことはしない。君だって、それくらい知ってるだろ」
「そうよ」ファニュもタンゴの反論に賛同した。「あのチョウヨウが理由もなく、人を傷つけるわけない。それにタンゴだって一度死んで蘇ったことがあったんでしょ。あなたたちが話してくれたことが本当ならタンゴだって、おかしくなってるはずじゃない。でも、その後も優しくて良い人のままなのよね」
「確かにそうじゃな」ジョウシの声は冷たかった。「ならば聞くが、なぜ荷台に無いのじゃ、チョウヨウの遺体が?」
橇を重苦しい沈黙が支配した。聞こえてくるのは雪走り烏賊 が雪を蹴立てる音だけだった。
ジョウシが再び口を開いた。口調は穏やかではあったが、それは残酷な現実を彼女なりに分析しようとするものだった。
「蘇ったとすれば、タンゴの例があっただけに合点がいく。間違いなく、チョウヨウは還 ってきたのじゃ」自分の言葉が皆の心に浸透するのをジョウシは待った。「じゃが、あ奴が突然の乱心に及んだことだけは合点がゆかぬ」
「タンゴと比べて蘇りまで時間がかかったのなら。それが問題かも」
事実を受け入れたファニュが暫くして、そんな推測を口にした。
「そうかもしれぬし、違うておるやもしれぬ。まさかとは思うが、御力水 そのものが原因だったやもしれんしのぅ。分量の問題であったか……それともタンゴに使ったものとチョウヨウのとでは成分が違うておったのか……されど、タナバタもミソカも正気を失うた……」
「きっと成分よ。だってタナバタさんは正気を取り戻して、あたしとナナクサを助けてくれたわ。あなたも知ってるでしょ」
ジョウシは微かに天を仰いだ。
「左様であったな。されど、ミソカは最後まで狂うたままじゃった……」
「それは、わからないわ」ファニュは諦めずにまくしたてた。「でも、あの時の戦士たち、凄く残酷で凶暴だったから……あんな性質の悪い連中の血だもの。チョウヨウだっておかしくなるわ。それにミソカの時のだって、戦士の死体があったわ。彼女は、きっとそれを飲んだのよ」
「少し飛躍しすぎではあるまいか」
チョウヨウに対するファニュの思い入れを知っているだけに、ジョウシの口調は柔らかかった。
「ううん、ぜんぜん飛躍なんかしてないよ。だって、あんなに優しくて意志の強かったチョウヨウが理由もなく人間を襲うなんて考えられない。ねっ、そうでしょう。もしかしたら蘇ったショックで混乱してるだけかもしれないし。どう考えたって、やっぱり原因は、奴らのあの残忍な血よ」
「おい。一体全体、お前らは何の話をしてるんだ?」
エイブの質問は二人から完全に無視された。そしてジョウシは戦士たちの凶暴さを思い出すと床に目を落とし、悔しそうに唇を噛んだ。
「確かにのぅ。ただでさえ劇薬であったものを……いや。じゃが、真相は、やはりわからぬ。えぇい。かような折に薬師 のナナクサが居 ってくれれば、他に知恵も働こうに……」
「忘れるな、みんな」今まで黙って聞いていたタンゴが業を煮やして言い放った。「僕らは、そのナナクサを助けに来たんだ。そして行方不明のチョウヨウも必ず探し出す。絶対だ。もし君らが嫌だって言うんなら、構わない。その時は僕だけでもチョウヨウを……」
「嫌と言うわけがなかろう」
「もちろんよ、二人とも必ず助ける」ジョウシに続いて、ファニュも空かさず返事を返した。
「だから無視すんなよ」苛立ったエイブは再び口を開いた。「いったい何なんだ『残虐な血』って。一番の被害者には秘密かよ」
橇が街路の十字路にさしかかった丁度そのとき、エイブの質問は壊れた人形のように人間の身体が放物線を描いて橇の進路に飛び込んできたことで中断された。それは重武装した女戦士の身体だった。
タンゴは急制動を掛けたが、橇は女戦士の身体を車体の下に巻き込んで、その身体に、もろに乗り上げると、彼女の骨と内臓を修復不能なまでに粉砕して停まった。二人のヴァンパイアと二人の人間が事態を充分に理解する間もなく、今度は戦士の身体に混じって、労働者の身体が大きな放物線を描いて投げつけられ、それを皮切りに次々と人体が橇が停止した十字路に降り注ぎはじめた。
まるで乱射される矢を思わせるその光景は、橇の若者たちをたじろがせはしたが、身体に染み付いた生存本能までたじろがせはしなかった。タンゴとジョウシは反射的にエイブを両側から抱きかかえると、既に行動を起こしたファニュに続いて橇から雪上に素早く飛び退いた。ヴァンパイアと人間の二組は車体の陰に身を潜めた。それが伝染したのか、雪走り烏賊 も雪の中に潜り込んで早くも身を硬く縮こまらせた。一瞬後、人体と橇の車体が太鼓を乱打するかのような不協和音を奏ではじめた。人体豪雨の中、彼らが十字路の奥。戦士の身体や労働者のそれが飛んできた方向を眺めると、今まさに人の集団を薙ぎ払おうとする一人のシルエットが目に留まった。折り重なった戦士の身体の上に仁王立ちしているその姿。必ずしも大きいとはいえないが、無駄なところが一片もない引き締まった体躯は遠目からでも十分にそれと確認することができた。
「チョウヨウ!」
タンゴの喜びと混乱が入り混じった叫びは、引き絞られた弩弓 のように力を溜めたシルエットの動きをピタリと止めた。それは人体の丘の上でおもむろに振り向くと、禍々しさの中にも純朴さを秘めた笑顔を四人に向けた。
「みんなやっと来たね。遅いよ。ねぇ、タンゴも早くおいで。スカッとして本当に面白いんだから!」
チョウヨウは、そう叫び返すと真っ赤に染まった目を細めた。
「さて、さて。最初の出し物が始める前に何をしようか?……」
子孫の身体を支配しているその存在は、今では黒く汚らわしい蠅の大群のような渦巻状に広がる外観を人間の目から隠そうともしなかった。それは幼子が絨毯の上で遊ぶように、ブンブン唸りながら広大な
身軽になった黒い渦巻は曇った中空のキャンバスに、ゆったりと浮遊していた。自身が一番望んでいたこと。恐怖の果ての無残な死を、またそこからもたらされる避け難い絶望と苦痛を、ここにいる人間たちから広く収穫するにはどうすればいいのかは、もう既に知っていたので、風の流れに身を委ねて漂っていた。今までの運命を憤る必要はもうない。あとはわくわくしてお楽しみを待つだけなのだ、ただただ新たな一日の始まりを。
広大な城砦内に横たわる様々な形状の建築群。強化セラミックとローマ式コンクリートで形作られた文明の
「これは、これは……もうはじまってしまったか」
その声ならぬ声は観光を中断された残念さよりも、膨らむ期待を抑えるかのように、うち震えていた。
*
目覚めた都市が動き出す頃、建物群の一角にある大きな十字路の一つから、苦痛に満ちた断末魔の合唱が途切れることなく流れはじめた。
*
不安は恐怖を産み、その恐怖は容易に
「お前は自分を襲ったモノを見たか?」
「いや、見てない」苦痛にエイブの顔が歪んだ。
「以前は、どうじゃ。突然、お前のように瞬時に深手を負わされた者を見たことは?」
「いいや。それもない」
「聞いたこともないか?」
「あぁ、ないな」
「左様か……」
「何か答えを知ってそうな口調だな」エイブは痛みに堪えながら、疑いの眼差しを質問者に向けた。「この期に及んで、まだ何か隠し事をしようってのか?」
「あの時のことね」ファニュが心配そうにジョウシの顔をうかがった。
「そうじゃ……」
ファニュに応えるジョウシの顔は、負傷したエイブとは違った苦痛を耐え忍んでいるようだった。
「だから、それはなんだって聞いてんだ」
「隠し事などではないが」ジョウシは観念したように口を開いた。「ただ似たような力の発現に我れらは遭遇したことがある」
ジョウシは、ヴァンパイアの力を覚醒させた仲間のミソカが見せた超能力をかいつまんでエイブに説明した。
「やっぱりか。俺はヴァンパイアにやられたってことなんだな」
「おそらくは……」
「何が『おそらくは』だ!」エイブは痛みも忘れてジョウシにくってかかった。「お前らは危険だった。お前らを信じた俺が馬鹿だったんだ」
「エイブ、落ち着いて。何もヴァンパイアが犯人だなんて決まってないわよ」
「これが黙っていられるか、ファニュ。今の話を聞いて、こいつらヴァンパイア以外に犯人は考えられねぇだろ。くそ。しかも俺はこいつらを都市内に呼び込んじまったんだぞ」
「そうじゃな……ヴァンパイアの他に犯人はおるまいな。しかし、それだけでは
「お前らの他にもいるってことか?……」
エイブはジョウシを、次に橇を走らせている馭者台のタンゴの背中に視線を走らせたが、沈黙に報いられただけだった。次に彼は問うような眼差しをファニュに向けた。しかし、そのファニュも既に沈黙の仲間になっていた。
「いったい、どういうことだ?……」
答えを得られないままのエイブは、大きな溜め息をつくと視線を橇の床に落とした。視線の先には自分の血で新たに赤黒くペイントされたキャンバスが敷かれていた。彼の目は、それに釘付けになった。ほんの少し前まで何かが包まれていたはずのキャンバス。その時、彼は自分を襲ったモノが何だったのかをにわかに悟った。
「いま気づいたんだが。もしかして、ここに乗っていた奴が……もしかして、お前たちが番を頼んだ死体が……」
「違うよ!」
振り向きもせずに即座にタンゴが否定した
「されど、それしか納得のゆく答えはあるまい」
「チョウヨウは、そんなことはしない。君だって、それくらい知ってるだろ」
「そうよ」ファニュもタンゴの反論に賛同した。「あのチョウヨウが理由もなく、人を傷つけるわけない。それにタンゴだって一度死んで蘇ったことがあったんでしょ。あなたたちが話してくれたことが本当ならタンゴだって、おかしくなってるはずじゃない。でも、その後も優しくて良い人のままなのよね」
「確かにそうじゃな」ジョウシの声は冷たかった。「ならば聞くが、なぜ荷台に無いのじゃ、チョウヨウの遺体が?」
橇を重苦しい沈黙が支配した。聞こえてくるのは
ジョウシが再び口を開いた。口調は穏やかではあったが、それは残酷な現実を彼女なりに分析しようとするものだった。
「蘇ったとすれば、タンゴの例があっただけに合点がいく。間違いなく、チョウヨウは
「タンゴと比べて蘇りまで時間がかかったのなら。それが問題かも」
事実を受け入れたファニュが暫くして、そんな推測を口にした。
「そうかもしれぬし、違うておるやもしれぬ。まさかとは思うが、
「きっと成分よ。だってタナバタさんは正気を取り戻して、あたしとナナクサを助けてくれたわ。あなたも知ってるでしょ」
ジョウシは微かに天を仰いだ。
「左様であったな。されど、ミソカは最後まで狂うたままじゃった……」
「それは、わからないわ」ファニュは諦めずにまくしたてた。「でも、あの時の戦士たち、凄く残酷で凶暴だったから……あんな性質の悪い連中の血だもの。チョウヨウだっておかしくなるわ。それにミソカの時のだって、戦士の死体があったわ。彼女は、きっとそれを飲んだのよ」
「少し飛躍しすぎではあるまいか」
チョウヨウに対するファニュの思い入れを知っているだけに、ジョウシの口調は柔らかかった。
「ううん、ぜんぜん飛躍なんかしてないよ。だって、あんなに優しくて意志の強かったチョウヨウが理由もなく人間を襲うなんて考えられない。ねっ、そうでしょう。もしかしたら蘇ったショックで混乱してるだけかもしれないし。どう考えたって、やっぱり原因は、奴らのあの残忍な血よ」
「おい。一体全体、お前らは何の話をしてるんだ?」
エイブの質問は二人から完全に無視された。そしてジョウシは戦士たちの凶暴さを思い出すと床に目を落とし、悔しそうに唇を噛んだ。
「確かにのぅ。ただでさえ劇薬であったものを……いや。じゃが、真相は、やはりわからぬ。えぇい。かような折に
「忘れるな、みんな」今まで黙って聞いていたタンゴが業を煮やして言い放った。「僕らは、そのナナクサを助けに来たんだ。そして行方不明のチョウヨウも必ず探し出す。絶対だ。もし君らが嫌だって言うんなら、構わない。その時は僕だけでもチョウヨウを……」
「嫌と言うわけがなかろう」
「もちろんよ、二人とも必ず助ける」ジョウシに続いて、ファニュも空かさず返事を返した。
「だから無視すんなよ」苛立ったエイブは再び口を開いた。「いったい何なんだ『残虐な血』って。一番の被害者には秘密かよ」
橇が街路の十字路にさしかかった丁度そのとき、エイブの質問は壊れた人形のように人間の身体が放物線を描いて橇の進路に飛び込んできたことで中断された。それは重武装した女戦士の身体だった。
タンゴは急制動を掛けたが、橇は女戦士の身体を車体の下に巻き込んで、その身体に、もろに乗り上げると、彼女の骨と内臓を修復不能なまでに粉砕して停まった。二人のヴァンパイアと二人の人間が事態を充分に理解する間もなく、今度は戦士の身体に混じって、労働者の身体が大きな放物線を描いて投げつけられ、それを皮切りに次々と人体が橇が停止した十字路に降り注ぎはじめた。
まるで乱射される矢を思わせるその光景は、橇の若者たちをたじろがせはしたが、身体に染み付いた生存本能までたじろがせはしなかった。タンゴとジョウシは反射的にエイブを両側から抱きかかえると、既に行動を起こしたファニュに続いて橇から雪上に素早く飛び退いた。ヴァンパイアと人間の二組は車体の陰に身を潜めた。それが伝染したのか、
「チョウヨウ!」
タンゴの喜びと混乱が入り混じった叫びは、引き絞られた
「みんなやっと来たね。遅いよ。ねぇ、タンゴも早くおいで。スカッとして本当に面白いんだから!」
チョウヨウは、そう叫び返すと真っ赤に染まった目を細めた。