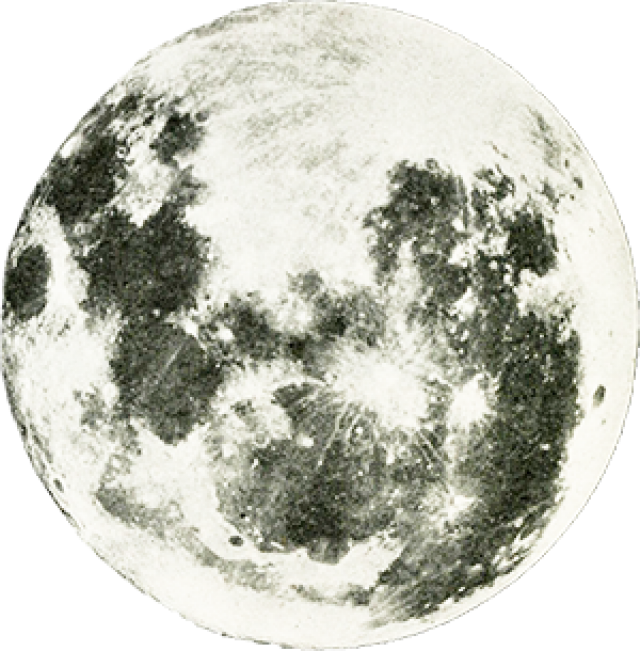-11-焦糖
文字数 1,329文字
ほんの少しだけ開いたカーテンの隙間から差し込んだ光が、ほんの一瞬部屋の中を照らした。
あの日のような満月の光ではない。土砂降りの空を裂くような雷の光が僕の睡眠を妨げてからかれこれ1時間は経とうとしていた。
本州も梅雨入りしてから早1週間。
真夏のような雷雨の夜が、それだけ続いている。
広すぎるベッドで寝るのは未だに慣れない。
右頬を埋めた枕からは、微かなジャスミンの香りがした。
また近くで、大きな雷が落ちた。
(………みず)
すっかり覚めてしまった眠気から手を離して、僕はゆっくりと身体を起こした。
廊下に出ると、部屋には無かったじめっとした空気が身体に纏わりついてくる。
「…………ん?」
台所へ行く途中のエントランスに、濡れた足跡を見つけて僕は足を止めた。
玄関から来たその足跡は、階段の上へと続いている。
大きさからいってマホロのものではない。
十影は、濡れた靴を拭かないまま屋敷内に入ってきたりはしない。
(誰、だ………)
足跡は階段を昇ったきり、戻ってきてはいない。
つまりまだ、2階にいるということだ。
自然と階段へ向いた自分の足が、可笑しいくらいに震えていることに気付いた。
まだ戻れる、と誰かが囁く。
部屋に戻って布団を被って眠ってしまえ、と誰かが腕を引く。
一度は昇りかけた足を、下ろしかけた、その時―――
「…………!………、…………!!」
「っ!」
人の話し声が―――マホロの声がした気がして、気付けば僕は階段を昇っていた。
心臓が飛び出しそうだった。
暗闇の中、自分の心臓の音だけが鼓膜を占領している。
熟した桃のような、微かな匂いがした。
やがてそれが焦げたカラメルのような匂いと混ざり合って廊下に漂いはじめる。
マホロの部屋の扉は、開いていた。
囁くように聞こえていたその声が、押し殺すような悲鳴だということに、僕はそこでやっと気が付いた。
暗闇の中。ベッドの上のシルエット。
雷が一瞬だけ、部屋の中を照らす。
「―――ッ!」
思わず叫びそうになって、僕は自分の指の背を噛んだ。
痛みは、感じなかった。
「いっ………ぁ……ッ……………」
マホロに馬乗りになる男の腕が、容赦なくマホロの太ももを掴んで上へと引き上げる。
砂糖の溶けるような甘い匂いが、途端に濃くなった。
氷水でも浴びたような寒気が、僕の身体に纏わりついていた熱とすり替わった。
男の吐き出す息の音がして、込み上げた胃液が咽喉の奥を焼く。
男は花酔いではない。
それは見ただけで分かった。この焦げたような匂いでも。
「――――……ッ!」
マホロの体が大きく仰け反る。
抱えている大きな枕にずっと隠されていた真っ白な咽喉が、引き攣った。
途端に、あの桃の匂いがカラメルの匂いに重なる。
男のシルエットが動く。
真っ白なベッドのシーツに、無数の花弁が散っていた。
そこからどうやって部屋に戻ったのか、よく覚えていない。
鼻の奥にこびりついた匂いと、目の奥に焼き付いた光景を思い出して何度か吐いた。
身体中を、頭中を侵すこの感情の名前と意味が分からなくて僕は、その日初めて一人で泣いた。
あの日のような満月の光ではない。土砂降りの空を裂くような雷の光が僕の睡眠を妨げてからかれこれ1時間は経とうとしていた。
本州も梅雨入りしてから早1週間。
真夏のような雷雨の夜が、それだけ続いている。
広すぎるベッドで寝るのは未だに慣れない。
右頬を埋めた枕からは、微かなジャスミンの香りがした。
また近くで、大きな雷が落ちた。
(………みず)
すっかり覚めてしまった眠気から手を離して、僕はゆっくりと身体を起こした。
廊下に出ると、部屋には無かったじめっとした空気が身体に纏わりついてくる。
「…………ん?」
台所へ行く途中のエントランスに、濡れた足跡を見つけて僕は足を止めた。
玄関から来たその足跡は、階段の上へと続いている。
大きさからいってマホロのものではない。
十影は、濡れた靴を拭かないまま屋敷内に入ってきたりはしない。
(誰、だ………)
足跡は階段を昇ったきり、戻ってきてはいない。
つまりまだ、2階にいるということだ。
自然と階段へ向いた自分の足が、可笑しいくらいに震えていることに気付いた。
まだ戻れる、と誰かが囁く。
部屋に戻って布団を被って眠ってしまえ、と誰かが腕を引く。
一度は昇りかけた足を、下ろしかけた、その時―――
「…………!………、…………!!」
「っ!」
人の話し声が―――マホロの声がした気がして、気付けば僕は階段を昇っていた。
心臓が飛び出しそうだった。
暗闇の中、自分の心臓の音だけが鼓膜を占領している。
熟した桃のような、微かな匂いがした。
やがてそれが焦げたカラメルのような匂いと混ざり合って廊下に漂いはじめる。
マホロの部屋の扉は、開いていた。
囁くように聞こえていたその声が、押し殺すような悲鳴だということに、僕はそこでやっと気が付いた。
暗闇の中。ベッドの上のシルエット。
雷が一瞬だけ、部屋の中を照らす。
「―――ッ!」
思わず叫びそうになって、僕は自分の指の背を噛んだ。
痛みは、感じなかった。
「いっ………ぁ……ッ……………」
マホロに馬乗りになる男の腕が、容赦なくマホロの太ももを掴んで上へと引き上げる。
砂糖の溶けるような甘い匂いが、途端に濃くなった。
氷水でも浴びたような寒気が、僕の身体に纏わりついていた熱とすり替わった。
男の吐き出す息の音がして、込み上げた胃液が咽喉の奥を焼く。
男は花酔いではない。
それは見ただけで分かった。この焦げたような匂いでも。
「――――……ッ!」
マホロの体が大きく仰け反る。
抱えている大きな枕にずっと隠されていた真っ白な咽喉が、引き攣った。
途端に、あの桃の匂いがカラメルの匂いに重なる。
男のシルエットが動く。
真っ白なベッドのシーツに、無数の花弁が散っていた。
そこからどうやって部屋に戻ったのか、よく覚えていない。
鼻の奥にこびりついた匂いと、目の奥に焼き付いた光景を思い出して何度か吐いた。
身体中を、頭中を侵すこの感情の名前と意味が分からなくて僕は、その日初めて一人で泣いた。