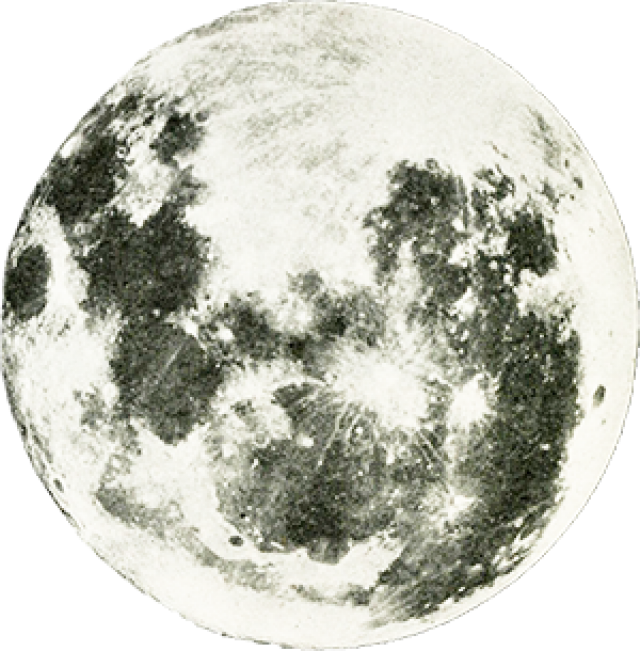-最終話-これから
文字数 4,521文字
ほーけきょう。
と、下手糞な鶯の泣き声が遠くに聞こえた。
うっすらと目を開けた先に、金色に光る空気に舞う埃。
開け放した窓からぶわりと風が吹いてレースのカーテンが膨らんだ。
鼻先に、微かに残る桜の香りがした。
開いたばかりの瞼が勝手に落ちていく。
眠ってしまえ、と脳が---
「先生!」
「…っう!?は、はい!はいっ!?」
勢いよく起き上がった拍子に、腹に載せていた本が床に落ちた。
それを拾い上げようと伸ばした手は、顔を覗き込んできた鬼の形相にびくりと止まる。
童顔の頬を膨らませて、ふんと彼女は鼻から息を吐いた。
「またここで寝てたんですね?っていうかまた泊まったんですね?まったくもう、身体壊したらどうするんですか!あぁ!またこんなに散らかして……!夕凪さんに見られたらお説教じゃ済みませんよ!?この間だって、ろくに食事もしていないのがバレて大変だったじゃないですか!いつになったら先生は、自分で自分の管理ができるようになるんですか!」
「はい……ごめんなさい」
「反省するなら反復しないでください」
「はい……すいません」
ソファの上で正座をして謝る僕を一瞥して、彼女は床に散らばる本を拾い上げ始めた。
それでもその小さな口から溢れるお小言は止まらない。
「まったく……もう少しご自身の立場を弁えてください。あの!斉藤 縁日大先生が!本当はこんな人だなんて知ったらみんな卒倒しますよ」
「その大先生ってやめてってば……それに、医者なんてみんなこんなものだよ」
「自分の悪癖を医者というカテゴリーで正当化しないでください」
「はい、すいません」
「先生のほうが身体壊してたら笑えませんからね」
「はは……」
「笑い事じゃありません!」
いつのまにか両腕に山積みになった本をどん、とテーブルの上に置いて彼女はまた僕を見下ろした。
「先生が発表した論文があるからこそ、花酔いの寿命は飛躍的に伸びたんですよ。いまや花酔いは御伽話の中の奇病ではなくなりました。先生が花酔いを救ったんです」
「救えたらいいんだけどね、本当に」
いつ淹れたか分からない珈琲に手を伸ばすと、咎めるようにその手を叩かれた。
「……まだ完治できるわけじゃない。花酔いが健常者とまったく同じ生活が遅れるわけじゃないし、症状の重さによっては昔の花酔いとなんら変わらない人もいる。まだまだだよ」
「だから!先生には長生きしてもらわないと困るんです」
「はいはい」
さっき僕が飲もうとした珈琲を片付けながら、彼女は呆れたように溜息を吐いた。
「まったく、本当に分かってるんですか?ちゃんとしないと小児科の子供たちに言いつけちゃいますからね」
「---もう知ってるよ」
部屋中の光が、一斉にその声に集まった。
昔より僅かに色味を増した髪、それでも光に透ける肌。
「縁日先生はいっつもナツお姉ちゃんに怒られてるんだーって、みんな俺に報告してくれるからね」
にやりと笑った、その頬に微かな桃色。
「眞秀!」
「おはよう縁日。おつかれさま」
「山谷さん!待っていてくださいと言ったのに!中庭は暑かったでしょう?」
「日陰を歩いてきたからね、大丈夫だよ。それにどうせお説教中だろうなぁ、とも思ったし?」
そう言いながら、眞秀は手に持っていたコーヒーショップのカップを僕に手渡した。
「山谷さんからも何か言ってください!先生ってばどうせ今日も徹夜してたんですよ?」
「十影が言っても治らないのに、俺が言って治るわけないじゃない」
そう言って肩を竦めると、眞秀は手に持っていた紙袋の中から一冊の本を取り出した。
「これ、届いてたよ。見本だって」
「あぁ、ありがとう」
「うわぁっ!とうとう出来上がったんですね!先生の本!」
「本っていうか、ただの論文だけど」
「ただの論文じゃないです!本当にすごいことなんですから!ねぇ?山谷さん」
そう話をふられた眞秀は、少し呆れたような、困ったような顔をして小さく笑った。
「まぁ、自覚ないのが縁日のいいとこだから」
「そうですけどぉ」
ぷう、と頬を膨らませて彼女---夏ははっきりとしたその眉を少し下げた。
「あ。そういえば、田中さんがなっちゃんのこと呼んでたよ」
「え?」
「そろそろ回診の時間じゃない?」
「あっ!大変!」
腕時計の時間を確認した途端にバタバタと慌て出した夏は、部屋の入口で一度こちらを振り向いて僕を指差した。
「それじゃあ先生!わたしは仕事に戻りますけど、先生はちゃんと家に帰って休んでくださいね!山谷さん!」
「はいはーい、まかせて」
ソファの肘掛に腰掛けながら、眞秀がひらひらと手を振った。
廊下を駆けていく夏の足音を聞きながら、その薄い唇がくすくすと笑う。
「駄目でしょ、看護師さん困らせちゃ」
「うん……気をつけてるつもりなんだけど」
「変わらないね、縁日は」
「えっ?わっ……!」
肘掛に座っていた眞秀の背中がぐらりと揺れる。
重力に逆らうことなく後ろに倒れた体はそのままソファの上に着地した。
青みを増した月白色の髪がソファに広がる。
それを整えるように指で梳くと、逆さに僕を映す瞳が猫のように瞬きをした。
「ごめんね」
「? なにが?」
「やっぱり暑かったでしょ?顔、少し赤い」
「………」
一瞬何かに耐えるように強く目を閉じた眞秀は、勢いよく起き上がってこちらを向いた。
「眞秀?」
「……ほんと変わらない。馬鹿」
「えっ?んっ……む……」
鼻先に、柔らかい頬の感触。
それ以上に柔らかいものが、僕の唇に触れていた。
いつかの、花弁越しではない。
眞秀の唇が、そこにあった。
じゅわり、と湧き立つ匂い。
触れた頬が、春の日差しを浴びたようにほんのりと暖かい。
「この匂い」
「ん?」
「これ嗅いで、こんな気持ちになるとは思わなかったなぁ」
「なにそれ」
いつだって、この香りが香るたびに感じたのは
言いようもない息苦しさだけだった。
唇が触れたまま、眞秀が小さく笑う。
「俺も知らなかったよ」
「うん?」
「縁日は、梔子の花より甘い」
「えー?」
首に腕を回して擦り寄ってくる頬が擽ったい。
僕の鎖骨に唇を押し当てて、眞秀は深く息を吐いた。
「人の体温は、まだ慣れない?」
「って言っても、縁日しか知らないし」
顔を上げた眞秀の頬に触れる。
滑らかな肌に指を滑らせるたび、擽ったそうにその目を細めた。
「好きだよ、縁日の手。冷たくて気持ちいい」
「もう水越しじゃない」
「花弁越しでもないね」
そう言って笑うと、眞秀はもう一度僕にキスをした。
「それで?俺の花贄さまは、今度は徹夜でなにを調べてたの?」
「調べてたっていうか、悩んでたっていうか……」
「悩む?」
「今度のスピーチ、どうしようなって。何も浮かばないんだよね……」
「あー……」
浄見の逮捕から6年が経った。
花酔いの治療薬は、未だ完成には至っていない。
けれど眞秀は僕に触れられるし、僕も眞秀に触れられる。
眞秀の体液を舐めても、僕は花酔いに感染しない。
研究段階から臨床試験を経て、そしてついに治験へと進むことが決まった花酔いの治療法---”花贄”
ワクチンを投与された健常者の体液を取り込むことで、その抗体を利用してウイルスを弱めるという花酔い初の治療法。
健常者が摂取するワクチンは花酔いウイルスを元に作られる為、あまりにリスキーだと発表当初は批判殺到だったけれど
他でもない花酔いたちの後押しもあって、条件付きではあるものの徐々に臨床数を増やしてきている。
「論文を発表するってことは、その治療法を推進するってことでしょ?でも僕は、この方法を人に薦めたいわけじゃないから」
「縁日……」
「花酔いに感染するリスクを侵してまで、とかいろいろ言われたけど、……まぁそうなんだよね、他の人にとっては」
批判された理由は、それだけじゃなかった。
花酔いウイルスは花酔いによって遺伝子構造が少しずつ異なる。
そのため、他の花酔いのウイルスから生成した抗体を取り込むと、病原体と同じような過剰反応が出てしまう。
だからこそ、健常者の体液を介して花酔いに送られる抗体は、その花酔い自身のウイルスから生成した抗体でなければならない。
つまり、花酔いとその花酔いの抗体をもつ健常者は、どちらかが死ぬまで、一生体液の交換をしていくことになる。
それが”花贄”と呼ばれる理由だ。
「眞秀の花酔いが治らないなら、僕が花酔いになるしかないと思ってたし、それは眞秀とずっと一緒にいたいと思ったからだから」
でもそれが、他の人もそうだとは限らない。
治療法だと言って、人の一生を簡単に押し付けるわけにはいかない。
「それ、そのまま全部言ったらいいんじゃない?」
「え?」
「スピーチ」
小さく笑って、眞秀は僕の前髪に触れた。
指先が離れていく。熟した桃のような香りが、前髪の先に残った。
「俺だって、一緒に生きたいと思う人がいなかったら治療しようなんて思ってないよ」
「眞秀……」
「それでいいんじゃない?誰かと生きたいと思う花酔いが自分の意思で受ける治療で」
6年前より青白くなった僕の手に、眞秀の手が触れる。
こんなふうに触れられる。
それだけでも、こんなにも嬉しい。
「花酔いだって人を好きになっていい。それを伝えていい。生きていい。そう思える免罪符だと思うよ。この治療法は」
伏せた長い睫毛が、光を含んで光りながら透ける。
それに見惚れているうちに、唇に、唇が触れた。
あの日。
花弁越しにした口付けは、胸が張り裂けそうなほど苦しかった。
あんな思いをする花酔いが、この世界から一人でも減ればいい。
あんなに悲しい顔で笑う花酔いが、この世界からいなくなればいい。
泣きたいと思うときに、泣いて欲しい。
その涙が頬を流れなくても、その目から溢れる花弁を拭わせてほしい。
その花びらが、いつか本物の涙になっても―――
「---もし、眞秀が花酔いじゃなくなっても」
もし、僕が必要じゃなくなっても
それでも、その未来で---
「それでも、僕の隣にいてくれる?」
”いつか”---その言葉を、もっと簡単に使えるように。
その未来を、一緒に生きていけるように。
「喜んで。俺の花贄さま」
その笑顔に、触れていられるように。
---…………と呼ぶにはあまりにリスキーであるため一概にこの方法を推薦することはできない。それでも---
それでも
そのリスクを冒してでも
触れたいと
ただ
そう願う花酔いが貴方にいるのであれば
自分が花酔いになってもいいと
そう思えるほどの覚悟が
貴方にあるのであれば
わたしはそのための努力と協力を惜しまない。
これは、わたしと彼が生きた記録である。
---花酔いと花贄--- 斉藤 縁日【著】
と、下手糞な鶯の泣き声が遠くに聞こえた。
うっすらと目を開けた先に、金色に光る空気に舞う埃。
開け放した窓からぶわりと風が吹いてレースのカーテンが膨らんだ。
鼻先に、微かに残る桜の香りがした。
開いたばかりの瞼が勝手に落ちていく。
眠ってしまえ、と脳が---
「先生!」
「…っう!?は、はい!はいっ!?」
勢いよく起き上がった拍子に、腹に載せていた本が床に落ちた。
それを拾い上げようと伸ばした手は、顔を覗き込んできた鬼の形相にびくりと止まる。
童顔の頬を膨らませて、ふんと彼女は鼻から息を吐いた。
「またここで寝てたんですね?っていうかまた泊まったんですね?まったくもう、身体壊したらどうするんですか!あぁ!またこんなに散らかして……!夕凪さんに見られたらお説教じゃ済みませんよ!?この間だって、ろくに食事もしていないのがバレて大変だったじゃないですか!いつになったら先生は、自分で自分の管理ができるようになるんですか!」
「はい……ごめんなさい」
「反省するなら反復しないでください」
「はい……すいません」
ソファの上で正座をして謝る僕を一瞥して、彼女は床に散らばる本を拾い上げ始めた。
それでもその小さな口から溢れるお小言は止まらない。
「まったく……もう少しご自身の立場を弁えてください。あの!斉藤 縁日大先生が!本当はこんな人だなんて知ったらみんな卒倒しますよ」
「その大先生ってやめてってば……それに、医者なんてみんなこんなものだよ」
「自分の悪癖を医者というカテゴリーで正当化しないでください」
「はい、すいません」
「先生のほうが身体壊してたら笑えませんからね」
「はは……」
「笑い事じゃありません!」
いつのまにか両腕に山積みになった本をどん、とテーブルの上に置いて彼女はまた僕を見下ろした。
「先生が発表した論文があるからこそ、花酔いの寿命は飛躍的に伸びたんですよ。いまや花酔いは御伽話の中の奇病ではなくなりました。先生が花酔いを救ったんです」
「救えたらいいんだけどね、本当に」
いつ淹れたか分からない珈琲に手を伸ばすと、咎めるようにその手を叩かれた。
「……まだ完治できるわけじゃない。花酔いが健常者とまったく同じ生活が遅れるわけじゃないし、症状の重さによっては昔の花酔いとなんら変わらない人もいる。まだまだだよ」
「だから!先生には長生きしてもらわないと困るんです」
「はいはい」
さっき僕が飲もうとした珈琲を片付けながら、彼女は呆れたように溜息を吐いた。
「まったく、本当に分かってるんですか?ちゃんとしないと小児科の子供たちに言いつけちゃいますからね」
「---もう知ってるよ」
部屋中の光が、一斉にその声に集まった。
昔より僅かに色味を増した髪、それでも光に透ける肌。
「縁日先生はいっつもナツお姉ちゃんに怒られてるんだーって、みんな俺に報告してくれるからね」
にやりと笑った、その頬に微かな桃色。
「眞秀!」
「おはよう縁日。おつかれさま」
「山谷さん!待っていてくださいと言ったのに!中庭は暑かったでしょう?」
「日陰を歩いてきたからね、大丈夫だよ。それにどうせお説教中だろうなぁ、とも思ったし?」
そう言いながら、眞秀は手に持っていたコーヒーショップのカップを僕に手渡した。
「山谷さんからも何か言ってください!先生ってばどうせ今日も徹夜してたんですよ?」
「十影が言っても治らないのに、俺が言って治るわけないじゃない」
そう言って肩を竦めると、眞秀は手に持っていた紙袋の中から一冊の本を取り出した。
「これ、届いてたよ。見本だって」
「あぁ、ありがとう」
「うわぁっ!とうとう出来上がったんですね!先生の本!」
「本っていうか、ただの論文だけど」
「ただの論文じゃないです!本当にすごいことなんですから!ねぇ?山谷さん」
そう話をふられた眞秀は、少し呆れたような、困ったような顔をして小さく笑った。
「まぁ、自覚ないのが縁日のいいとこだから」
「そうですけどぉ」
ぷう、と頬を膨らませて彼女---夏ははっきりとしたその眉を少し下げた。
「あ。そういえば、田中さんがなっちゃんのこと呼んでたよ」
「え?」
「そろそろ回診の時間じゃない?」
「あっ!大変!」
腕時計の時間を確認した途端にバタバタと慌て出した夏は、部屋の入口で一度こちらを振り向いて僕を指差した。
「それじゃあ先生!わたしは仕事に戻りますけど、先生はちゃんと家に帰って休んでくださいね!山谷さん!」
「はいはーい、まかせて」
ソファの肘掛に腰掛けながら、眞秀がひらひらと手を振った。
廊下を駆けていく夏の足音を聞きながら、その薄い唇がくすくすと笑う。
「駄目でしょ、看護師さん困らせちゃ」
「うん……気をつけてるつもりなんだけど」
「変わらないね、縁日は」
「えっ?わっ……!」
肘掛に座っていた眞秀の背中がぐらりと揺れる。
重力に逆らうことなく後ろに倒れた体はそのままソファの上に着地した。
青みを増した月白色の髪がソファに広がる。
それを整えるように指で梳くと、逆さに僕を映す瞳が猫のように瞬きをした。
「ごめんね」
「? なにが?」
「やっぱり暑かったでしょ?顔、少し赤い」
「………」
一瞬何かに耐えるように強く目を閉じた眞秀は、勢いよく起き上がってこちらを向いた。
「眞秀?」
「……ほんと変わらない。馬鹿」
「えっ?んっ……む……」
鼻先に、柔らかい頬の感触。
それ以上に柔らかいものが、僕の唇に触れていた。
いつかの、花弁越しではない。
眞秀の唇が、そこにあった。
じゅわり、と湧き立つ匂い。
触れた頬が、春の日差しを浴びたようにほんのりと暖かい。
「この匂い」
「ん?」
「これ嗅いで、こんな気持ちになるとは思わなかったなぁ」
「なにそれ」
いつだって、この香りが香るたびに感じたのは
言いようもない息苦しさだけだった。
唇が触れたまま、眞秀が小さく笑う。
「俺も知らなかったよ」
「うん?」
「縁日は、梔子の花より甘い」
「えー?」
首に腕を回して擦り寄ってくる頬が擽ったい。
僕の鎖骨に唇を押し当てて、眞秀は深く息を吐いた。
「人の体温は、まだ慣れない?」
「って言っても、縁日しか知らないし」
顔を上げた眞秀の頬に触れる。
滑らかな肌に指を滑らせるたび、擽ったそうにその目を細めた。
「好きだよ、縁日の手。冷たくて気持ちいい」
「もう水越しじゃない」
「花弁越しでもないね」
そう言って笑うと、眞秀はもう一度僕にキスをした。
「それで?俺の花贄さまは、今度は徹夜でなにを調べてたの?」
「調べてたっていうか、悩んでたっていうか……」
「悩む?」
「今度のスピーチ、どうしようなって。何も浮かばないんだよね……」
「あー……」
浄見の逮捕から6年が経った。
花酔いの治療薬は、未だ完成には至っていない。
けれど眞秀は僕に触れられるし、僕も眞秀に触れられる。
眞秀の体液を舐めても、僕は花酔いに感染しない。
研究段階から臨床試験を経て、そしてついに治験へと進むことが決まった花酔いの治療法---”花贄”
ワクチンを投与された健常者の体液を取り込むことで、その抗体を利用してウイルスを弱めるという花酔い初の治療法。
健常者が摂取するワクチンは花酔いウイルスを元に作られる為、あまりにリスキーだと発表当初は批判殺到だったけれど
他でもない花酔いたちの後押しもあって、条件付きではあるものの徐々に臨床数を増やしてきている。
「論文を発表するってことは、その治療法を推進するってことでしょ?でも僕は、この方法を人に薦めたいわけじゃないから」
「縁日……」
「花酔いに感染するリスクを侵してまで、とかいろいろ言われたけど、……まぁそうなんだよね、他の人にとっては」
批判された理由は、それだけじゃなかった。
花酔いウイルスは花酔いによって遺伝子構造が少しずつ異なる。
そのため、他の花酔いのウイルスから生成した抗体を取り込むと、病原体と同じような過剰反応が出てしまう。
だからこそ、健常者の体液を介して花酔いに送られる抗体は、その花酔い自身のウイルスから生成した抗体でなければならない。
つまり、花酔いとその花酔いの抗体をもつ健常者は、どちらかが死ぬまで、一生体液の交換をしていくことになる。
それが”花贄”と呼ばれる理由だ。
「眞秀の花酔いが治らないなら、僕が花酔いになるしかないと思ってたし、それは眞秀とずっと一緒にいたいと思ったからだから」
でもそれが、他の人もそうだとは限らない。
治療法だと言って、人の一生を簡単に押し付けるわけにはいかない。
「それ、そのまま全部言ったらいいんじゃない?」
「え?」
「スピーチ」
小さく笑って、眞秀は僕の前髪に触れた。
指先が離れていく。熟した桃のような香りが、前髪の先に残った。
「俺だって、一緒に生きたいと思う人がいなかったら治療しようなんて思ってないよ」
「眞秀……」
「それでいいんじゃない?誰かと生きたいと思う花酔いが自分の意思で受ける治療で」
6年前より青白くなった僕の手に、眞秀の手が触れる。
こんなふうに触れられる。
それだけでも、こんなにも嬉しい。
「花酔いだって人を好きになっていい。それを伝えていい。生きていい。そう思える免罪符だと思うよ。この治療法は」
伏せた長い睫毛が、光を含んで光りながら透ける。
それに見惚れているうちに、唇に、唇が触れた。
あの日。
花弁越しにした口付けは、胸が張り裂けそうなほど苦しかった。
あんな思いをする花酔いが、この世界から一人でも減ればいい。
あんなに悲しい顔で笑う花酔いが、この世界からいなくなればいい。
泣きたいと思うときに、泣いて欲しい。
その涙が頬を流れなくても、その目から溢れる花弁を拭わせてほしい。
その花びらが、いつか本物の涙になっても―――
「---もし、眞秀が花酔いじゃなくなっても」
もし、僕が必要じゃなくなっても
それでも、その未来で---
「それでも、僕の隣にいてくれる?」
”いつか”---その言葉を、もっと簡単に使えるように。
その未来を、一緒に生きていけるように。
「喜んで。俺の花贄さま」
その笑顔に、触れていられるように。
---…………と呼ぶにはあまりにリスキーであるため一概にこの方法を推薦することはできない。それでも---
それでも
そのリスクを冒してでも
触れたいと
ただ
そう願う花酔いが貴方にいるのであれば
自分が花酔いになってもいいと
そう思えるほどの覚悟が
貴方にあるのであれば
わたしはそのための努力と協力を惜しまない。
これは、わたしと彼が生きた記録である。
---花酔いと花贄--- 斉藤 縁日【著】