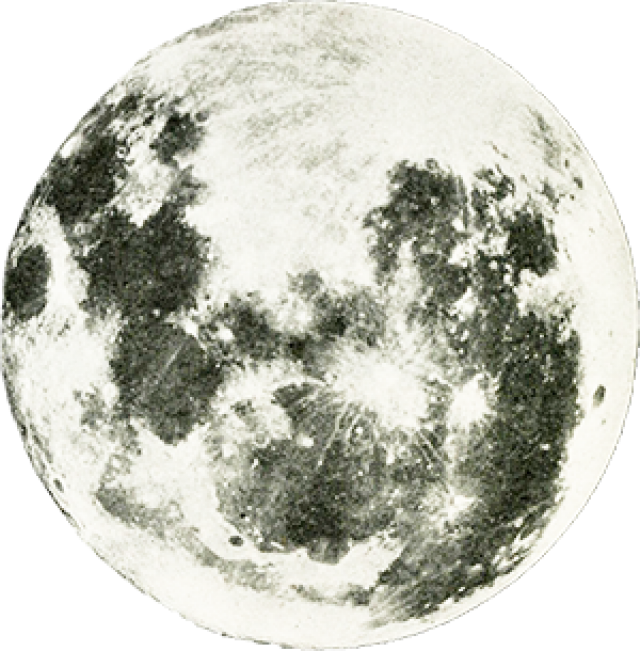-13-梔子
文字数 2,390文字
僕が育った修道院は、純白でも清廉でもなかった―――ただ、それだけのことだ。
物心がついたときには、もう自分が他の孤児とは違う扱いをされていることに気付いていた。
というか、僕以外にいた他の孤児は皆どこかへ行ってしまったのだ。
新しい孤児が来ては、いつもどこかへ消えていく。
ずっとこの場所にいるのは僕ひとりだけだった。
始めてそれを疑問に思ったのは、たしか5歳の時だったと思う。
シロツメクサの花冠を作ろうと約束してくれた女の子が、いなくなってしまった日だ。
どうして?と聞いた僕に返ってきた答えは「貴方が特別な存在だから」―――だった。
自分は特別な存在だから、ここにいなくてはいけない。
みんなはそうじゃないから消えてしまうんだと、そう教えられた。
金持ちに売られているんだと気付くのに、そんなに時間はかからなかった。
孤児を引き取り金に換え、麻薬と酒の餌になる。
じゃあどうして自分はそうされないのだろうと、その時はもう聞こうともしなかったけれど。
“それ”が始まったのは10歳になる年の初夏のことだった。
その日、僕の部屋を訪れた神父の目がどこか虚ろだったことは覚えている。
それ以外のことを、実はあまり覚えていない。
湿気と埃とカビの臭い。生臭い人間の臭い。皮膚の臭い。息の臭い。青臭い体液の臭い。
鉄の味。汗の味。涙の味。人の粘膜の感触。縛られた手首の痛み。裂けるような鋭い痛み。身体の奥の鈍痛。
―――救いのような雨に濡れる梔子の匂い。
幾度となく、そんな夜が重なった。
何年も。何回も。
“謎”が“不快”になり、やがて“諦め”に変わって“無”になった。
その行為が“凌辱”と呼ばれることを知ったのは、十影に出会ってからのことだ。
いつも修道院には泊まらない十影が、その夜どうしてだか僕の部屋に来た。
そこには神父もいて―――事が露呈した。
十影は神父を―――自分の叔父を警察に通報した。
その日の夜―――警察を抜け出した神父が訪れたのは僕の部屋だった。
「私の天使が、どこかへ飛び立っていってしまわないように」「この羽根を捥いでしまわねばいけない」「もうどこへも行けないように」
神父は譫言のように繰り返しそう呟きながら、あるはずのない天使の羽根を、僕の背中を、ひたすらにナイフで切りつけ続けた。
そうして出来た2つの傷痕は、僕というより十影の心に大きな傷を残した。
肩甲骨はむかし人間に羽根があった名残―――この傷を見ていると、本当にそうだったんじゃないかと思えてくる。
翼を捥がれた天使―――僕は堕天使になった。
事を理解していなかったこともあって、あまりトラウマという形には残らなかった。
その先の人格形成でなんの障害にもならなかったかと聞かれると、素直に頷けないけれど。
じめついた空気を、風が払っていく。
芳香を放つ真っ白な花弁から、降り止んだ雨の雫が落ちた。
さっき帰っていった十影は、どうやら雨に濡れずに済んだらしい。
僕は十影の表情を思い出していた。
(ただの同情だ――……って、言われると思ってたな)
もしくは、同じ境遇同士の共依存。
結局、十影はそんなこと言わなかったけれど。
“好き”にも色々な意味があるという。
その全てを、きっと僕はちゃんと理解できていない。
十影が好きだ。
甘いものが好きだ。
本が好きだ。
紅茶が好きだ。
けれどその中でたったひとつ、その“好き”とは違うものがある。
―――マホロが好きだ。
でも、好きなだけじゃない。
ほんの少しだけ胸の奥に巣食うこの不快感も、きっとマホロの所為なんだろう。
(分からないことばっかだ………)
他人と身体を重ねる行為の意味はひとつじゃない。
子孫を残すため、性的欲求を満たすため、愛情表現……あの浄見という男は花酔いの体液を得るために道具のようにマホロと身体を重ねる。
“あの人”は―――僕の翼を奪ったあの人は、どうして僕を抱いたんだろう。
(考えたこともなかった、な)
人を好きになるということは、自分のことも顧みないといけない。
それだけならいい。
どうせ過去のことだ。どんなに辛いことでも今更それに傷つけられることなんてない。
けれど、相手がどれだけ消したいと思うようなことでも、知りたいと願ってしまうのは―――
それは酷く残酷なことのように思えた。僕の勝手なエゴでもある。
あの焦げた匂いのする夜のことは―――きっとマホロが知られたくないと思っていることだ。
だからこそ僕は、あの男をマホロから引き剥がすことが出来なかったんだろう。
怖かったんだ。
あの男よりも、何よりも。
マホロの顔を見ることが。
だから僕は、見なかったふりをした。
あの日、十影は僕を助けてくれたのに。
僕はマホロを助けられなかった。
「………あ」
そういうことか、と。
理解した瞬間に、勝手に眉根が寄った。
___『マホロに―――花酔いに、感情移入するな』
___『傷付いて欲しくないからだ。お前たち2人に』
___『そういう人間の闇の部分に、自分の大切な人が晒されたときの恐怖を』
___『お前は知らないんだよ』
立っていられなくなって、僕はその場にしゃがみ込んだ。
水分を含んだひんやりとした風が僕の頭上を吹いていく。
「いた………」
引き攣るような心臓の痛みに小さく呻いた。
初めての痛みだった。
この痛みが、十影のいう『傷付く』ということなら、もう僕は傷ついてしまったことになる。
「ごめん、十影………」
キリキリと締め付ける痛みに、こほっと息が漏れた。
熱く滲む目頭を、自分の膝に押し付ける。
「それでも好きなんだ……」
梔子の香りがする雨粒がひとつ、首に落ちて背中に流れた。
物心がついたときには、もう自分が他の孤児とは違う扱いをされていることに気付いていた。
というか、僕以外にいた他の孤児は皆どこかへ行ってしまったのだ。
新しい孤児が来ては、いつもどこかへ消えていく。
ずっとこの場所にいるのは僕ひとりだけだった。
始めてそれを疑問に思ったのは、たしか5歳の時だったと思う。
シロツメクサの花冠を作ろうと約束してくれた女の子が、いなくなってしまった日だ。
どうして?と聞いた僕に返ってきた答えは「貴方が特別な存在だから」―――だった。
自分は特別な存在だから、ここにいなくてはいけない。
みんなはそうじゃないから消えてしまうんだと、そう教えられた。
金持ちに売られているんだと気付くのに、そんなに時間はかからなかった。
孤児を引き取り金に換え、麻薬と酒の餌になる。
じゃあどうして自分はそうされないのだろうと、その時はもう聞こうともしなかったけれど。
“それ”が始まったのは10歳になる年の初夏のことだった。
その日、僕の部屋を訪れた神父の目がどこか虚ろだったことは覚えている。
それ以外のことを、実はあまり覚えていない。
湿気と埃とカビの臭い。生臭い人間の臭い。皮膚の臭い。息の臭い。青臭い体液の臭い。
鉄の味。汗の味。涙の味。人の粘膜の感触。縛られた手首の痛み。裂けるような鋭い痛み。身体の奥の鈍痛。
―――救いのような雨に濡れる梔子の匂い。
幾度となく、そんな夜が重なった。
何年も。何回も。
“謎”が“不快”になり、やがて“諦め”に変わって“無”になった。
その行為が“凌辱”と呼ばれることを知ったのは、十影に出会ってからのことだ。
いつも修道院には泊まらない十影が、その夜どうしてだか僕の部屋に来た。
そこには神父もいて―――事が露呈した。
十影は神父を―――自分の叔父を警察に通報した。
その日の夜―――警察を抜け出した神父が訪れたのは僕の部屋だった。
「私の天使が、どこかへ飛び立っていってしまわないように」「この羽根を捥いでしまわねばいけない」「もうどこへも行けないように」
神父は譫言のように繰り返しそう呟きながら、あるはずのない天使の羽根を、僕の背中を、ひたすらにナイフで切りつけ続けた。
そうして出来た2つの傷痕は、僕というより十影の心に大きな傷を残した。
肩甲骨はむかし人間に羽根があった名残―――この傷を見ていると、本当にそうだったんじゃないかと思えてくる。
翼を捥がれた天使―――僕は堕天使になった。
事を理解していなかったこともあって、あまりトラウマという形には残らなかった。
その先の人格形成でなんの障害にもならなかったかと聞かれると、素直に頷けないけれど。
じめついた空気を、風が払っていく。
芳香を放つ真っ白な花弁から、降り止んだ雨の雫が落ちた。
さっき帰っていった十影は、どうやら雨に濡れずに済んだらしい。
僕は十影の表情を思い出していた。
(ただの同情だ――……って、言われると思ってたな)
もしくは、同じ境遇同士の共依存。
結局、十影はそんなこと言わなかったけれど。
“好き”にも色々な意味があるという。
その全てを、きっと僕はちゃんと理解できていない。
十影が好きだ。
甘いものが好きだ。
本が好きだ。
紅茶が好きだ。
けれどその中でたったひとつ、その“好き”とは違うものがある。
―――マホロが好きだ。
でも、好きなだけじゃない。
ほんの少しだけ胸の奥に巣食うこの不快感も、きっとマホロの所為なんだろう。
(分からないことばっかだ………)
他人と身体を重ねる行為の意味はひとつじゃない。
子孫を残すため、性的欲求を満たすため、愛情表現……あの浄見という男は花酔いの体液を得るために道具のようにマホロと身体を重ねる。
“あの人”は―――僕の翼を奪ったあの人は、どうして僕を抱いたんだろう。
(考えたこともなかった、な)
人を好きになるということは、自分のことも顧みないといけない。
それだけならいい。
どうせ過去のことだ。どんなに辛いことでも今更それに傷つけられることなんてない。
けれど、相手がどれだけ消したいと思うようなことでも、知りたいと願ってしまうのは―――
それは酷く残酷なことのように思えた。僕の勝手なエゴでもある。
あの焦げた匂いのする夜のことは―――きっとマホロが知られたくないと思っていることだ。
だからこそ僕は、あの男をマホロから引き剥がすことが出来なかったんだろう。
怖かったんだ。
あの男よりも、何よりも。
マホロの顔を見ることが。
だから僕は、見なかったふりをした。
あの日、十影は僕を助けてくれたのに。
僕はマホロを助けられなかった。
「………あ」
そういうことか、と。
理解した瞬間に、勝手に眉根が寄った。
___『マホロに―――花酔いに、感情移入するな』
___『傷付いて欲しくないからだ。お前たち2人に』
___『そういう人間の闇の部分に、自分の大切な人が晒されたときの恐怖を』
___『お前は知らないんだよ』
立っていられなくなって、僕はその場にしゃがみ込んだ。
水分を含んだひんやりとした風が僕の頭上を吹いていく。
「いた………」
引き攣るような心臓の痛みに小さく呻いた。
初めての痛みだった。
この痛みが、十影のいう『傷付く』ということなら、もう僕は傷ついてしまったことになる。
「ごめん、十影………」
キリキリと締め付ける痛みに、こほっと息が漏れた。
熱く滲む目頭を、自分の膝に押し付ける。
「それでも好きなんだ……」
梔子の香りがする雨粒がひとつ、首に落ちて背中に流れた。