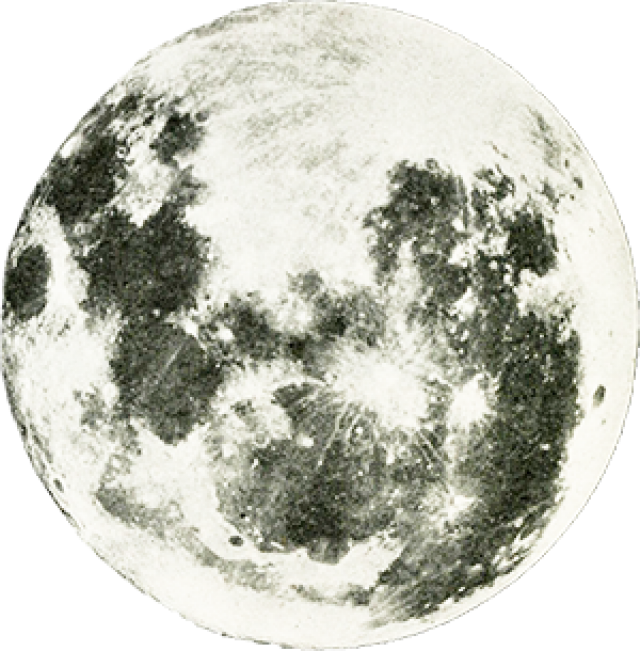-2-薄荷
文字数 2,796文字
『透き通るような白い肌』―――という定義を思い直さなければいけないな、と思った。
春と呼ぶには暑すぎて、それでも夏にはなりきれていない、そんな半端な季節だった。
気温は既に夏日を記録していて、それでも然程暑さを感じないのは空気が乾いているからだろうと思う。
真上に上がった太陽から降り注がれる白い光が、決して広くはないその庭の緑に反射して輝いている。
ラベンダー、カモミール、バジル、ミント、ローズマリー、タイム、セージ……庭一面に植えられたハーブの中に、
その人は居た。
風を含んだシャツから覗くその腕が、日差しを浴びて眩しいほどに輝いて見えたのだ。
その肌だけじゃない。
月白色のその髪も、風に揺れるその毛先まで余すところなく光を含んで、きらきらと光っていた。
その光がひとつ、彼から離れる。
はらりと零れたそれは、桃色の花びらのように見えた。
ふ、とその身体が動いた。
光が、一斉にこちらを向く。
「………っ……ぁ」
「………誰?」
アクアマリンのような、透き通ったその瞳が、真っすぐに僕を見た。
「………え、と」
「不審者?」
風がハーブを揺らす音の中に、硝子のように繊細な、それでいて強い声だけが浮いて聞こえた。
不審者かと問いながらも、その表情は好奇心に満ちて見える。
僕が言葉を失くしているうちに、その宝石のような瞳は僕の目の前に来ていた。
白く、透き通る肌。
仄かな、甘い香り。
光が―――その光を纏った月白色の毛先が。はらり、と毀れた。
「お?」
殆ど、無意識だった。
その、ニキビの痕ひとつない頬にかかる髪を払おうと、手を伸ばす。
その手の行き先を追っていた、彼の綺麗過ぎるその瞳が、ふと僕の肩口に移動した。
日差しに、影が差す。
「あ。」
「…………っ!?」
中指の爪先が、その頬に触れそうになった瞬間。
パシッと乾いた音がして、僕のその手が弾き飛ばされていた。
彼の手にではない。
鼻先に、新しい匂い。“その匂い”を振り向く。
「十影!」
「十影“さん”だっつってんだろうが」
「………十影、さん」
「ったく、広間で待ってろっつったろ」
「ごめん……」
「お前もだ―――マホロ!」
十影が咎めるように視線を投げた。
振り返るともう彼は僕たちの傍から離れてミントの株木を観察している。
「お前も簡単に触らせようとするな」
「でも、彼は俺に触れなかったよ?」
「俺が来たからだろうが」
「十影が来たから、だよ」
そんな、よく分からない返しをして彼は僕たちに背を向けた。
気分でも害したのだろうかと思っていたら、その背中の向こうから微かな鼻歌が聞こえ始めた。
気分を害したのではなく、興味がそれたらしい。
呆れたような溜息を十影が吐く。
「あの……?」
「いや、いい。気にするな。お前は……―――」
何故かそこで言葉を止めて、十影はもう一度大きな溜息を吐いた。
言葉の続きを待つ僕の頭をその大きな手で撫でてから、十影の視線が彼に向く。
「先に紹介しておく。マホロ、こいつが斎藤 縁日。今日からここで書生として住むことになった」
「うん。覚えてるよ」
「で、あいつが山谷 眞秀。お前の雇い主で―――花酔いだ」
「えっ?」
さらっと。なんでもないことのように。十影が最後に付け加えた言葉の意味を考える。
『花酔い』―――治療法のない、第5類感染症。世界一美しい奇病。
そして
―――花酔いに、触れてはいけない。
「正しくは俺の父親なんだけどね。君の雇い主」
「すっ……」
「ん?」
こちらを向いた彼―――マホロに向かって、僕は思い切り頭を下げた。
「すいませんごめんなさい!僕、知らなくて……っ、まさか……触れようとするなんて……っ」
「やだ。許さない」
「っ」
す、と温度が下がった。
しかしすぐにそれは溶けていく。
微かに聞こえる音に耳を澄ます。それが何かを押し殺すような笑い声だということに気付いて僕は顔を上げた。
さっきまでと何も変わらない緑の中。
口元に手を当てて、可笑しそうに笑うマホロが居た。
「………あまりこいつを揶揄うな、マホロ」
「うん、ごめんごめん。必死だから、つい」
ひとしきり笑ったあと、マホロはその綺麗な瞳で僕を見た。
柔らかな日差しが、まるで彼を守るように纏わりついている。
「さっき十影も言ってたけど、止めなかった俺も悪いからね。気にしてないし、気にしないで」
「でもっ……」
「最初に言ってなかった俺も悪い。すまん」
そう言って十影は僕に向かって頭を下げた。
180㎝を超える大男が頭を下げると、それはそれで威圧感がすごい。
マホロも僕と同じことを思ったのか困ったような顔をして笑っている。
その視線が、僕に向いた。
「でも、ちょっと吃驚はしたよ。君、見かけによらないんだね?」
「すいません……」
「いや、そのまんま見かけどおりの奴だぞ。ただ、考えるより先に行動しちまう悪い癖があるだけで」
「そっ………」
そんなことない、と言おうとしてやめた。そんなことある。
2人の言う“見かけ”がどんな意味なのかは深く考えないようにして、僕はもう一度「すいません」と謝った。
強い風が吹いた。庭中の緑が靡いて、空間そのものが揺れる。
太陽を見上げた十影が、小さい声で「あつい」と洩らした。
「詳しい話はあとだな。マホロ、そろそろ中に這入れ。今日は日差しが強い」
「はーい」
「縁も先に行ってろ。俺は茶を淹れてくるから」
「うん」
僕の肩をぽん、と軽く叩いて十影は屋敷の中に這入っていった。
その後ろ姿をぼんやりと見送っていると、背後に視線を感じて僕はまた庭の方へ向き直った。
どきり、と心臓が跳ねた。
透き通った宝石が、僕を真っ直ぐに見つめている。
さっきと同じ―――気が付けばマホロは、僕の目の前にいた。
「………ぁ…」
にこり、とその瞳が笑う。
ゆっくりと、細く靭やかな指先が僕に向かって伸ばされた。
―――花酔いに、触れてはいけない。
今度はそれを、忘れたわけではなかった。
それでも僕はその場から身じろぐことすら出来ずに、ただ目の前の瞳を見つめていた。
「っ!」
ふに、と唇に何かが触れる。
マホロの指先―――ではない。
唇に押し付けられた“それ”を思わず食むと、どこか満足したような笑みを浮かべてマホロは指を離した。
そのまま僕の脇を通りすぎて、屋敷の中に這入っていく。
微かに甘い匂いを含んだ風が一瞬だけ鼻先を掠めた。それを上書きするように、噛み締めた場所から爽やかな薄荷の香りが鼻に抜ける。
「ミント……?」
まるで返事でもするように、庭中のハーブが風に揺れた。
春と呼ぶには暑すぎて、それでも夏にはなりきれていない、そんな半端な季節だった。
気温は既に夏日を記録していて、それでも然程暑さを感じないのは空気が乾いているからだろうと思う。
真上に上がった太陽から降り注がれる白い光が、決して広くはないその庭の緑に反射して輝いている。
ラベンダー、カモミール、バジル、ミント、ローズマリー、タイム、セージ……庭一面に植えられたハーブの中に、
その人は居た。
風を含んだシャツから覗くその腕が、日差しを浴びて眩しいほどに輝いて見えたのだ。
その肌だけじゃない。
月白色のその髪も、風に揺れるその毛先まで余すところなく光を含んで、きらきらと光っていた。
その光がひとつ、彼から離れる。
はらりと零れたそれは、桃色の花びらのように見えた。
ふ、とその身体が動いた。
光が、一斉にこちらを向く。
「………っ……ぁ」
「………誰?」
アクアマリンのような、透き通ったその瞳が、真っすぐに僕を見た。
「………え、と」
「不審者?」
風がハーブを揺らす音の中に、硝子のように繊細な、それでいて強い声だけが浮いて聞こえた。
不審者かと問いながらも、その表情は好奇心に満ちて見える。
僕が言葉を失くしているうちに、その宝石のような瞳は僕の目の前に来ていた。
白く、透き通る肌。
仄かな、甘い香り。
光が―――その光を纏った月白色の毛先が。はらり、と毀れた。
「お?」
殆ど、無意識だった。
その、ニキビの痕ひとつない頬にかかる髪を払おうと、手を伸ばす。
その手の行き先を追っていた、彼の綺麗過ぎるその瞳が、ふと僕の肩口に移動した。
日差しに、影が差す。
「あ。」
「…………っ!?」
中指の爪先が、その頬に触れそうになった瞬間。
パシッと乾いた音がして、僕のその手が弾き飛ばされていた。
彼の手にではない。
鼻先に、新しい匂い。“その匂い”を振り向く。
「十影!」
「十影“さん”だっつってんだろうが」
「………十影、さん」
「ったく、広間で待ってろっつったろ」
「ごめん……」
「お前もだ―――マホロ!」
十影が咎めるように視線を投げた。
振り返るともう彼は僕たちの傍から離れてミントの株木を観察している。
「お前も簡単に触らせようとするな」
「でも、彼は俺に触れなかったよ?」
「俺が来たからだろうが」
「十影が来たから、だよ」
そんな、よく分からない返しをして彼は僕たちに背を向けた。
気分でも害したのだろうかと思っていたら、その背中の向こうから微かな鼻歌が聞こえ始めた。
気分を害したのではなく、興味がそれたらしい。
呆れたような溜息を十影が吐く。
「あの……?」
「いや、いい。気にするな。お前は……―――」
何故かそこで言葉を止めて、十影はもう一度大きな溜息を吐いた。
言葉の続きを待つ僕の頭をその大きな手で撫でてから、十影の視線が彼に向く。
「先に紹介しておく。マホロ、こいつが斎藤 縁日。今日からここで書生として住むことになった」
「うん。覚えてるよ」
「で、あいつが山谷 眞秀。お前の雇い主で―――花酔いだ」
「えっ?」
さらっと。なんでもないことのように。十影が最後に付け加えた言葉の意味を考える。
『花酔い』―――治療法のない、第5類感染症。世界一美しい奇病。
そして
―――花酔いに、触れてはいけない。
「正しくは俺の父親なんだけどね。君の雇い主」
「すっ……」
「ん?」
こちらを向いた彼―――マホロに向かって、僕は思い切り頭を下げた。
「すいませんごめんなさい!僕、知らなくて……っ、まさか……触れようとするなんて……っ」
「やだ。許さない」
「っ」
す、と温度が下がった。
しかしすぐにそれは溶けていく。
微かに聞こえる音に耳を澄ます。それが何かを押し殺すような笑い声だということに気付いて僕は顔を上げた。
さっきまでと何も変わらない緑の中。
口元に手を当てて、可笑しそうに笑うマホロが居た。
「………あまりこいつを揶揄うな、マホロ」
「うん、ごめんごめん。必死だから、つい」
ひとしきり笑ったあと、マホロはその綺麗な瞳で僕を見た。
柔らかな日差しが、まるで彼を守るように纏わりついている。
「さっき十影も言ってたけど、止めなかった俺も悪いからね。気にしてないし、気にしないで」
「でもっ……」
「最初に言ってなかった俺も悪い。すまん」
そう言って十影は僕に向かって頭を下げた。
180㎝を超える大男が頭を下げると、それはそれで威圧感がすごい。
マホロも僕と同じことを思ったのか困ったような顔をして笑っている。
その視線が、僕に向いた。
「でも、ちょっと吃驚はしたよ。君、見かけによらないんだね?」
「すいません……」
「いや、そのまんま見かけどおりの奴だぞ。ただ、考えるより先に行動しちまう悪い癖があるだけで」
「そっ………」
そんなことない、と言おうとしてやめた。そんなことある。
2人の言う“見かけ”がどんな意味なのかは深く考えないようにして、僕はもう一度「すいません」と謝った。
強い風が吹いた。庭中の緑が靡いて、空間そのものが揺れる。
太陽を見上げた十影が、小さい声で「あつい」と洩らした。
「詳しい話はあとだな。マホロ、そろそろ中に這入れ。今日は日差しが強い」
「はーい」
「縁も先に行ってろ。俺は茶を淹れてくるから」
「うん」
僕の肩をぽん、と軽く叩いて十影は屋敷の中に這入っていった。
その後ろ姿をぼんやりと見送っていると、背後に視線を感じて僕はまた庭の方へ向き直った。
どきり、と心臓が跳ねた。
透き通った宝石が、僕を真っ直ぐに見つめている。
さっきと同じ―――気が付けばマホロは、僕の目の前にいた。
「………ぁ…」
にこり、とその瞳が笑う。
ゆっくりと、細く靭やかな指先が僕に向かって伸ばされた。
―――花酔いに、触れてはいけない。
今度はそれを、忘れたわけではなかった。
それでも僕はその場から身じろぐことすら出来ずに、ただ目の前の瞳を見つめていた。
「っ!」
ふに、と唇に何かが触れる。
マホロの指先―――ではない。
唇に押し付けられた“それ”を思わず食むと、どこか満足したような笑みを浮かべてマホロは指を離した。
そのまま僕の脇を通りすぎて、屋敷の中に這入っていく。
微かに甘い匂いを含んだ風が一瞬だけ鼻先を掠めた。それを上書きするように、噛み締めた場所から爽やかな薄荷の香りが鼻に抜ける。
「ミント……?」
まるで返事でもするように、庭中のハーブが風に揺れた。