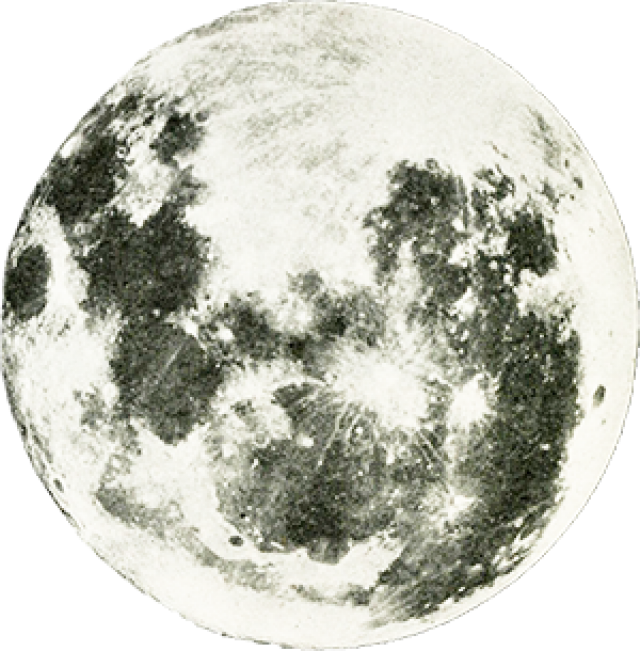-14-融解
文字数 4,378文字
たまに姿を見せる青空の色が濃くなったような気がする。―――夏が来るのだ。
「マホロー、氷と紅茶もってき―――……大丈夫?」
「あ゛ぅ」
平熱36.5℃の僕だって暑いと感じるのだ。
いくら風が通るとはいえ、花酔いにとってこの気温は辛いだろう。
熱が篭る2階の自室から屋敷の東側にあるこの部屋に一時的に避難しているマホロは、ベッドに四肢を投げ出してうつ伏せに寝ていた。
旧式の扇風機から送られる微弱な風に、その月白色の髪が揺れている。
「少し起きて。シーツ変えるから。氷も」
「んん」
もぞりと動いた華奢な身体が、億劫そうに身体を起こした。
マホロの身体を冷やしていた氷嚢の水滴でシーツが濡れてしまっている。
寝癖のついた柔らかい前髪からみえる眉間にくっきりと皺を刻んだまま、マホロはスタンド型のハンギングチェアーにどかりと腰を下ろした。
その反動でチェアーが揺れる。マホロがしんどそうに天井を仰いだ。
「あっづ」
「紅茶のむ?」
「ん」
頷いたマホロにグラスを差し出すと、それを受け取ったマホロの気怠けな目が少しだけ見開いた。
水滴の浮いたグラスを少し掲げるようにしてその中を見ている。
「ミント?」
「そう。この気温ですごい増えたからさ。氷作るときに中に入れたんだ」
「へぇ」
子どものような顔で、ミントを閉じ込めた氷の表面をつついている。
ほんの少しだけ、マホロの瞳に輝きが戻った気がして僕は胸を撫で下ろした。
冷たい紅茶をぐいっと煽ったマホロは、扇風機を抱き込むようにして風を受けている。
リネンのシャツが風を含んで膨らむ。
濡れたシーツをベッドから外して、新しいものと取り換える。
大きなベッドのシーツを替えるのも、この3か月で随分慣れた。
「暑いなら半袖着ればいいのに」
「んー」
曖昧な返事を背中に受けながら、僕は気付かれないように小さく笑った。
マホロがどんなに暑くても長袖を着る理由を本当は知っている。
身体に、あの男の痕があるからだ。
ちょうど大人の男の手のひら大の火傷の痕が。
「紅茶のおかわり、いる?」
「ううん。あんまり飲むと汗出るから」
ミント入りの氷を口の中にいれながら、マホロが首を横に振った。
子どものような歯がガチリとそれを砕く。
「汗もかきたくないの?」
「汗は縁日だってかきたくないでしょー?」
「それはそうだけど」
僕が敷き替えたばかりのシーツの上に浅く腰掛けると、チェアから立ち上がったマホロが勢いよくベッドの上にダイブした。
スプリングの効いたベッドが揺れて、身体が弾む。
「汗も結晶化するよ。ただ他の体液より“効果”は薄いみたい」
濃度にもよるらしいけどね、と枕に顔を埋めながらなんでもないようにマホロが言った。
露わになった首の後ろに新しい氷嚢を乗せると、枕の向こうでマホロが息をついた。
どうやら少しは落ち着いたらしい。
ほっと胸を撫で下ろして窓の外へ視線を向けると、この部屋を影で覆っている木々の隙間から、いかにも夏らしい真っ青な空が広がっていた。
遠くで蝉の声が聞こえている。
もしかしたら梅雨が明けたのかもしれなかった。
去年までは―――そこまで考えていた思考が止まった。
思い出せる気がしなかったからだ。
(なにしてたんだっけ………花火……?なんかする人いないしな……祭なんていかせてもらえるわけないし……)
空を見上げて夏っぽいなんて、思ったこともなかった気がする。
そもそも僕はきっと、夏っぽい空がどんな空かなんてことも知らない。
(向日葵……は、みたことある気がする)
太陽に向かって咲く、あの黄色い花の群れを僕は知っている。
そういえばこの屋敷の庭にはなかったな、と思っていると背中側でぱしゃん、という音がした。
振り向くと、さっきマホロに乗せた氷嚢がシーツの上に落ちている。
2つの澄んだ瞳が僕を―――僕の背中を見つめていた。
「縁日、汗かいてる」
「そりゃ暑いし」
伸びてきたマホロの指先が、汗で背中にはりついた僕のシャツの裾に触れた。
人差し指の爪先が微かな力でゆっくりとシャツを持ち上げていく。
捲れたシャツと背中の間に微かに風が通った。
「マホロ……?」
どうかしたの?と聞くよりも先に、びくりと背中が跳ねた。
マホロの指の爪先が、僕の背中に触れたからだ。
直接肌には触れないように、ゆるゆると皮膚をなぞっていた爪先が、最後何かを掬うようにして離れていく。
僕から離れたその指先に、一粒の水滴がついていた。
暫くそれを見つめていたマホロが、口を開く。
真っ赤な舌が、伸びる。
「………っあ」
その舌先が水滴に触れるより先に我に返ったのは僕のほうだった。
マホロのシャツの袖を強く引く。
なんの抵抗もなくベッドの上に倒れた腕と、その指先についた汗は音もなくシーツに吸収されて消えた。
「あーあ」
「あーあじゃないよ。なに考えてるの」
「あはは、縁日怒ってる」
怒って、いるのだろうか。
感情としては“気恥ずかしい”に近かったような気がするけれど。
マホロにそう見えているのなら、やっぱり僕は怒っているのかもしれない。
溜息を吐いて、掴んだシャツの袖から手を離そうとすると、今度は逆に僕の服の袖をマホロに掴まれてしまった。
「マホロ……?……う、わっ……!?」
戸惑っているうちに、もう片方の袖もマホロが掴む。
まさかその身体に倒れ込むわけにもいかずに、僕は寸での所でベッドに手をついた。
結果、マホロを押し倒すような体勢になってしまったけれど。
「……なに?今日はちょっと、悪戯の度が過ぎるんじゃない?」
「怒ってる?」
「怒ってないよ。呆れてはいるけど」
そう言って身体を起こそうとするけれど、袖を掴んだままのマホロがそれを阻止した。
押し倒す僕を見上げる2つの瞳が、まるで氷のように輝きながら僕の下で揺れている。
「……さっき、僕の汗をどうしようとしたの?」
「舐めようとした」
「やっぱり怒ってる」
「ごめんごめん、嘘!嘘じゃないけど、嘘!」
無理矢理にでも身体を離そうとした僕を、笑いながらマホロが制した。
それでもその手が、僕の服の袖を離そうとはしない。
駄々をこねる子供のような、そんな顔をマホロはしていた。
「暑いの、そんなにつらい?」
「ん」
今度は僕がマホロの皮膚に触れないように、爪先でその前髪をそっとよける。
2、3度ゆっくりと瞬きをしたマホロはそれでもやっぱり僕を見上げた。
「俺、自分が花酔いってことそんなに気にしてないって言ったでしょ?」
「うん」
自嘲するようにマホロの唇が微かに上がる。
その瞳はひどく哀しそうで、光で煌めくその瞳はどこか泣いているようにも見えた。
「それ、嘘じゃないんだ。花酔いが長く生きられないことも、植物しか食べられないことも、自分が利用されるために生まれてきたってことも、俺を生んだせいで母親が死んだってことも、別に悲観したことなんてなかった」
「………これも?」
そう言って僕は、マホロのシャツの裾を捲った。
びくりと跳ねた真っ白な腹に、治りかけの火傷のあとが残っている。
一瞬驚いたような顔をしたマホロは「やっぱり気付いてたか」と弱々しく笑った。
「それはちょっとだけ思ったかな………悲しいっていうより、純粋に嫌だったから」
自分がどんな顔をしていたのかは分からない。けれど決していい気分ではなかったことだけは確かだ。
そんな僕の顔をみたマホロが小さく笑って首を横に振った。
「でも全部、自分で決めたことだからさ」
「自分で……?」
「だって、体液が欲しいだけなら泣けばいいでしょ。実際、小さいときはそうやって採られてた。殴られたり、小鳥とか目の前で殺されたりしてさ。そのうち何されても泣けなくなって、どうして体液採られてるのか知ってからは―――意地でも泣かなくなった」
自分の意思で、泣きたくはないから
不可抗力で花弁が生み出されるあの方法を選んでいるというのか。
そこまでしても、泣きたくないと。あんな―――あんな行為のほうがマシだと。
「―――こんなふうに思うようになるなんて、思ってなかったんだ」
ぽつり、と呟くようにマホロがそう言った。
僕の前髪に、マホロの指先が触れる。
皮膚に触れることは、許されない。
「この距離が、俺と縁日の精一杯」
そう言った声が、僕の髪に触れたその指先が、僕を見つめるその瞳が、小さく震えていた。
(そうか。マホロだって―――)
泣かないだけで、泣きたくなるときがないわけじゃない。
「どんなに知りたいと思っても俺は、縁日の体温も、肌の感触も分からない。………この距離が―――」
「そんなことないよ」
「………えっ?」
サイドテーブルから、さっきマホロが飲んでいた紅茶のグラスを取り上げる。
残っていた氷を一粒、口の中に入れた。
ひんやりとした冷たさが舌の上で微かに溶けて、閉じ込めたミントの香りが鼻に抜けた。
「縁日……?」
「口、開けちゃ駄目だよ」
「へっ?むっ……ん…」
その氷を、マホロの唇に押し当てた。
主に僕の熱で溶けていく氷が、マホロの唇の上から溢れて顎に流れる。
僕の下で、マホロが小さく身じろいだ。
お互いの唇に触れる氷の感触が冷たいのか痛いのか分からない。ただ微かに甘いような気がした。
氷が溶けて、マホロの唇に最後に残ったミントの葉を、冷えた舌先で掬い取った。
ミントの葉の質感に混じって、微かに柔らかな感触が舌先に触れる。
火傷はしていない筈なのに、じゅわりと熟した桃の香りがして身体を離す。
清流のような瞳が、わずかな熱を持って揺れていた。
真っ白な頬が、いつかと同じように上気している。
それを隠すように、マホロは両手の甲で目元を覆った。
「マホロ」
「いやだ。俺、泣かないよ」
「今は僕しかいないのに?」
「っ!」
薄く開いた唇が小さく息を呑む。
その息が、小さく震えていた。
「マホロが流したもの全部、僕がなかったことにしてあげる。だから、泣いていいよ」
「えん……に、ち……っ」
目元を覆った手の隙間から、涙が溢れた。
あとからあとから流れるそれは、決してその頬を濡らすことなく、シーツの上で桃色の花弁になっていく。
魅惑の花弁。マホロはこれを卑しいと言うけれど、僕の目に映るそれはやっぱりどこまでも綺麗で、それでいてちょっとだけ怖い。
耳の奥で氷の溶ける音がした。
夏が来たのだ―――そう思った。
「マホロー、氷と紅茶もってき―――……大丈夫?」
「あ゛ぅ」
平熱36.5℃の僕だって暑いと感じるのだ。
いくら風が通るとはいえ、花酔いにとってこの気温は辛いだろう。
熱が篭る2階の自室から屋敷の東側にあるこの部屋に一時的に避難しているマホロは、ベッドに四肢を投げ出してうつ伏せに寝ていた。
旧式の扇風機から送られる微弱な風に、その月白色の髪が揺れている。
「少し起きて。シーツ変えるから。氷も」
「んん」
もぞりと動いた華奢な身体が、億劫そうに身体を起こした。
マホロの身体を冷やしていた氷嚢の水滴でシーツが濡れてしまっている。
寝癖のついた柔らかい前髪からみえる眉間にくっきりと皺を刻んだまま、マホロはスタンド型のハンギングチェアーにどかりと腰を下ろした。
その反動でチェアーが揺れる。マホロがしんどそうに天井を仰いだ。
「あっづ」
「紅茶のむ?」
「ん」
頷いたマホロにグラスを差し出すと、それを受け取ったマホロの気怠けな目が少しだけ見開いた。
水滴の浮いたグラスを少し掲げるようにしてその中を見ている。
「ミント?」
「そう。この気温ですごい増えたからさ。氷作るときに中に入れたんだ」
「へぇ」
子どものような顔で、ミントを閉じ込めた氷の表面をつついている。
ほんの少しだけ、マホロの瞳に輝きが戻った気がして僕は胸を撫で下ろした。
冷たい紅茶をぐいっと煽ったマホロは、扇風機を抱き込むようにして風を受けている。
リネンのシャツが風を含んで膨らむ。
濡れたシーツをベッドから外して、新しいものと取り換える。
大きなベッドのシーツを替えるのも、この3か月で随分慣れた。
「暑いなら半袖着ればいいのに」
「んー」
曖昧な返事を背中に受けながら、僕は気付かれないように小さく笑った。
マホロがどんなに暑くても長袖を着る理由を本当は知っている。
身体に、あの男の痕があるからだ。
ちょうど大人の男の手のひら大の火傷の痕が。
「紅茶のおかわり、いる?」
「ううん。あんまり飲むと汗出るから」
ミント入りの氷を口の中にいれながら、マホロが首を横に振った。
子どものような歯がガチリとそれを砕く。
「汗もかきたくないの?」
「汗は縁日だってかきたくないでしょー?」
「それはそうだけど」
僕が敷き替えたばかりのシーツの上に浅く腰掛けると、チェアから立ち上がったマホロが勢いよくベッドの上にダイブした。
スプリングの効いたベッドが揺れて、身体が弾む。
「汗も結晶化するよ。ただ他の体液より“効果”は薄いみたい」
濃度にもよるらしいけどね、と枕に顔を埋めながらなんでもないようにマホロが言った。
露わになった首の後ろに新しい氷嚢を乗せると、枕の向こうでマホロが息をついた。
どうやら少しは落ち着いたらしい。
ほっと胸を撫で下ろして窓の外へ視線を向けると、この部屋を影で覆っている木々の隙間から、いかにも夏らしい真っ青な空が広がっていた。
遠くで蝉の声が聞こえている。
もしかしたら梅雨が明けたのかもしれなかった。
去年までは―――そこまで考えていた思考が止まった。
思い出せる気がしなかったからだ。
(なにしてたんだっけ………花火……?なんかする人いないしな……祭なんていかせてもらえるわけないし……)
空を見上げて夏っぽいなんて、思ったこともなかった気がする。
そもそも僕はきっと、夏っぽい空がどんな空かなんてことも知らない。
(向日葵……は、みたことある気がする)
太陽に向かって咲く、あの黄色い花の群れを僕は知っている。
そういえばこの屋敷の庭にはなかったな、と思っていると背中側でぱしゃん、という音がした。
振り向くと、さっきマホロに乗せた氷嚢がシーツの上に落ちている。
2つの澄んだ瞳が僕を―――僕の背中を見つめていた。
「縁日、汗かいてる」
「そりゃ暑いし」
伸びてきたマホロの指先が、汗で背中にはりついた僕のシャツの裾に触れた。
人差し指の爪先が微かな力でゆっくりとシャツを持ち上げていく。
捲れたシャツと背中の間に微かに風が通った。
「マホロ……?」
どうかしたの?と聞くよりも先に、びくりと背中が跳ねた。
マホロの指の爪先が、僕の背中に触れたからだ。
直接肌には触れないように、ゆるゆると皮膚をなぞっていた爪先が、最後何かを掬うようにして離れていく。
僕から離れたその指先に、一粒の水滴がついていた。
暫くそれを見つめていたマホロが、口を開く。
真っ赤な舌が、伸びる。
「………っあ」
その舌先が水滴に触れるより先に我に返ったのは僕のほうだった。
マホロのシャツの袖を強く引く。
なんの抵抗もなくベッドの上に倒れた腕と、その指先についた汗は音もなくシーツに吸収されて消えた。
「あーあ」
「あーあじゃないよ。なに考えてるの」
「あはは、縁日怒ってる」
怒って、いるのだろうか。
感情としては“気恥ずかしい”に近かったような気がするけれど。
マホロにそう見えているのなら、やっぱり僕は怒っているのかもしれない。
溜息を吐いて、掴んだシャツの袖から手を離そうとすると、今度は逆に僕の服の袖をマホロに掴まれてしまった。
「マホロ……?……う、わっ……!?」
戸惑っているうちに、もう片方の袖もマホロが掴む。
まさかその身体に倒れ込むわけにもいかずに、僕は寸での所でベッドに手をついた。
結果、マホロを押し倒すような体勢になってしまったけれど。
「……なに?今日はちょっと、悪戯の度が過ぎるんじゃない?」
「怒ってる?」
「怒ってないよ。呆れてはいるけど」
そう言って身体を起こそうとするけれど、袖を掴んだままのマホロがそれを阻止した。
押し倒す僕を見上げる2つの瞳が、まるで氷のように輝きながら僕の下で揺れている。
「……さっき、僕の汗をどうしようとしたの?」
「舐めようとした」
「やっぱり怒ってる」
「ごめんごめん、嘘!嘘じゃないけど、嘘!」
無理矢理にでも身体を離そうとした僕を、笑いながらマホロが制した。
それでもその手が、僕の服の袖を離そうとはしない。
駄々をこねる子供のような、そんな顔をマホロはしていた。
「暑いの、そんなにつらい?」
「ん」
今度は僕がマホロの皮膚に触れないように、爪先でその前髪をそっとよける。
2、3度ゆっくりと瞬きをしたマホロはそれでもやっぱり僕を見上げた。
「俺、自分が花酔いってことそんなに気にしてないって言ったでしょ?」
「うん」
自嘲するようにマホロの唇が微かに上がる。
その瞳はひどく哀しそうで、光で煌めくその瞳はどこか泣いているようにも見えた。
「それ、嘘じゃないんだ。花酔いが長く生きられないことも、植物しか食べられないことも、自分が利用されるために生まれてきたってことも、俺を生んだせいで母親が死んだってことも、別に悲観したことなんてなかった」
「………これも?」
そう言って僕は、マホロのシャツの裾を捲った。
びくりと跳ねた真っ白な腹に、治りかけの火傷のあとが残っている。
一瞬驚いたような顔をしたマホロは「やっぱり気付いてたか」と弱々しく笑った。
「それはちょっとだけ思ったかな………悲しいっていうより、純粋に嫌だったから」
自分がどんな顔をしていたのかは分からない。けれど決していい気分ではなかったことだけは確かだ。
そんな僕の顔をみたマホロが小さく笑って首を横に振った。
「でも全部、自分で決めたことだからさ」
「自分で……?」
「だって、体液が欲しいだけなら泣けばいいでしょ。実際、小さいときはそうやって採られてた。殴られたり、小鳥とか目の前で殺されたりしてさ。そのうち何されても泣けなくなって、どうして体液採られてるのか知ってからは―――意地でも泣かなくなった」
自分の意思で、泣きたくはないから
不可抗力で花弁が生み出されるあの方法を選んでいるというのか。
そこまでしても、泣きたくないと。あんな―――あんな行為のほうがマシだと。
「―――こんなふうに思うようになるなんて、思ってなかったんだ」
ぽつり、と呟くようにマホロがそう言った。
僕の前髪に、マホロの指先が触れる。
皮膚に触れることは、許されない。
「この距離が、俺と縁日の精一杯」
そう言った声が、僕の髪に触れたその指先が、僕を見つめるその瞳が、小さく震えていた。
(そうか。マホロだって―――)
泣かないだけで、泣きたくなるときがないわけじゃない。
「どんなに知りたいと思っても俺は、縁日の体温も、肌の感触も分からない。………この距離が―――」
「そんなことないよ」
「………えっ?」
サイドテーブルから、さっきマホロが飲んでいた紅茶のグラスを取り上げる。
残っていた氷を一粒、口の中に入れた。
ひんやりとした冷たさが舌の上で微かに溶けて、閉じ込めたミントの香りが鼻に抜けた。
「縁日……?」
「口、開けちゃ駄目だよ」
「へっ?むっ……ん…」
その氷を、マホロの唇に押し当てた。
主に僕の熱で溶けていく氷が、マホロの唇の上から溢れて顎に流れる。
僕の下で、マホロが小さく身じろいだ。
お互いの唇に触れる氷の感触が冷たいのか痛いのか分からない。ただ微かに甘いような気がした。
氷が溶けて、マホロの唇に最後に残ったミントの葉を、冷えた舌先で掬い取った。
ミントの葉の質感に混じって、微かに柔らかな感触が舌先に触れる。
火傷はしていない筈なのに、じゅわりと熟した桃の香りがして身体を離す。
清流のような瞳が、わずかな熱を持って揺れていた。
真っ白な頬が、いつかと同じように上気している。
それを隠すように、マホロは両手の甲で目元を覆った。
「マホロ」
「いやだ。俺、泣かないよ」
「今は僕しかいないのに?」
「っ!」
薄く開いた唇が小さく息を呑む。
その息が、小さく震えていた。
「マホロが流したもの全部、僕がなかったことにしてあげる。だから、泣いていいよ」
「えん……に、ち……っ」
目元を覆った手の隙間から、涙が溢れた。
あとからあとから流れるそれは、決してその頬を濡らすことなく、シーツの上で桃色の花弁になっていく。
魅惑の花弁。マホロはこれを卑しいと言うけれど、僕の目に映るそれはやっぱりどこまでも綺麗で、それでいてちょっとだけ怖い。
耳の奥で氷の溶ける音がした。
夏が来たのだ―――そう思った。