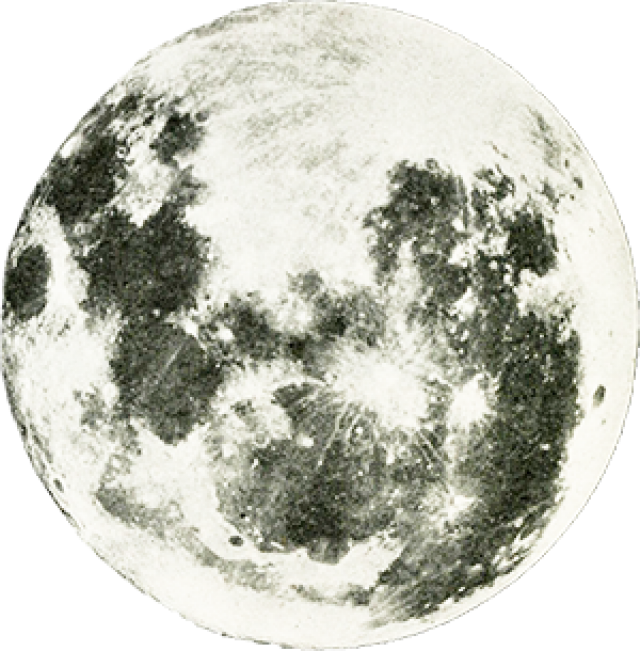‐18‐確執
文字数 4,725文字
どうして自分は―――“こんな時”いつも冷静でいられるのだろうと。そう考えたら少し泣きたくなった。
背中の傷が疼くのは―――目の前にいるこの男が、“あの人”に似ていたからだろうか。
「あ………」
「こんにちは」
その男はそう言って、にこりと笑った。
ただ細められたその瞳は、まるで値踏みでもするように僕を探っている。
僕の一挙手一投足、一言一句を、待っている。
満開に咲いたダチュラの花を背景に、その男が僕に近付いた。
男が纏う全ての黒を、風が揺らした。
あの、甘い匂いがする。
マホロの匂いとはまた少し違う。それでも似ている、パウダリーな甘い匂い。
花酔いの―――匂い。
「私は浄見 友親と言います。息子がお世話になっています。挨拶が遅くなってしまって」
すまなかったね、と笑みを貼り付けただけの唇がそう言った。
膝の裏に当たった百合の花が、僕の逃げ道を奪った。
「は、はじめまして。斎藤 縁日です」
「はじめまして―――ではないかな?」
「……え?」
思いがけない言葉に、思わずその男の目を、瞳を、見てしまった。
当たり前のようにマホロとは違う黒い瞳。その瞳の奥に、僕が映っている。
その向こうに、ここにあるはずもない向日葵の花が―――
「………あ?」
「思い出してくれたかな?」
「あ…ぁ……」
脳が拒む。
思い出すな、と咽喉が震える。
鼻を掠めた甘い香り。
視界を遮った、黒い服。
「背中の傷は、もう治った?」
「っ!」
「おっ、と」
思わずその男を突き放していた。
一瞬驚いたような顔をしてよろけながらも、その男はやっぱり笑っている。
さっきまでの笑みとは違う。
本当に面白そうに、その男は笑っていた。
「だ……めだ……」
駄目だ。
逃げるな。
思い出せ。
全部、思い出せ。
「……思い、出した…」
「ん?」
「あんた……あんたが、みんなを……っ」
嘲けるように、男は鼻で笑ってわざとらしく眉をハの字に曲げた。
「心外だなぁ。是非に、と声をかけてきたのは“あの神父”のほうだよ?」
「っ!」
「うん……でも、そう。確かにあの修道院の孤児たちを金で買っていたのは私だよ。私……というか機関、が正しいかな」
「機関……?」
「あれ?どうせ夕凪の奴がとっくに話しているものだと思っていたけれど……」
伸びてきた指先が、僕の頬に触れた。
ゆっくりとした手つきで僕の髪を耳にかけていく。
金縛りにあったように、僕は身じろぐことすら出来なかった。
「その様子じゃあ“あれ”にも話してないんだろうねぇ。まったく……過保護だねぇ、あいつも」
髪から離れた指先が、そのまま僕の頸動脈に触れた。
ドクドクと脈打つそれに、男が吐き捨てるように笑った。
「彼らは花酔いになったよ。一人残らず全員ね」
「っは?」
「そして全員死んだ」
「っ!」
反射的にその手を振りほどこうといた僕の首を、頸動脈に触れていたその手がいとも簡単に握り込んだ。
微かに残された気道から吸い込まれる空気がひゅうひゅうと音を立てる。
「は……なせ…っ」
「嫌だよ。離したら逃げるでしょう、君。今日はね、君にちょっとお願いがあって来たんだ」
「あ、んたの……願いなんか、知らない……っ」
「うん。まぁ、そういうだろうとは思ったけどね。大丈夫、大したお願いじゃないから」
「か…っ、は!」
そう言って男は、僕の首を絞める力を少しだけ強めた。
残されていた気道が塞がる。
急速に脳に溜まっていく血の音が、耳の奥で聞こえた。
涙で滲む視界の奥の、男の影を精一杯に睨んだ。
「あはは、成程。いい目をするねぇ。あの男が最後まで君を手放さなかった理由が分かるよ」
「う、るさい……っ」
「だからあの男にも花弁を渡したんだ。そしたら……君を天使だなんて言うようになってねぇ!」
そう言って、男が高笑いをした瞬間。
氷水でも浴びせられたように背中に悪寒が走った。
「あ、んたっ……あんたが……っ!」
「それは違うな。あの花弁はね、人間が普段心の奥に秘めている欲望を曝け出させるだけだ。人を狂わせるだけのドラッグとは違う。あの男が花弁を食べて、それで君のことを天使だと言ったのなら……それは普段、あの男が思っていたことだ」
「ち、がうっ……」
「あの男は普段から君を天使だと思っていたのさ。君を自分だけの天使にしたい、君の羽根を捥いでしまいたい、―――君を犯したい、とね」
「違う!」
「なにも違わないよ」
冷たくそう言い放って、男は僕から手を離した。
急速に大量の酸素が送り込まれた脳がくらりとする。
思わず膝をついて激しく咳き込んだ僕の視界に、黒い革靴。
はっとして顔を上げた時にはもう、胸倉が掴み上げられていた。
「ぐっ……」
「その背中にある傷は、奴の欲望の証だよ、縁日くん。奴がまともじゃなかった証拠さ」
「あんた、だって……まともじゃない!」
「あはは!そうだねぇ。君も、夕凪も、眞秀だってまともじゃない」
「あんたがマホロの名前を呼ぶな!」
一瞬見開かれた男の目が、面白そうに歪んだ。
「へぇ……。君は、“あれ”のことが好きなのかな」
「っ!」
「“あれ”は……卑しいだろう?」
「は……?」
「昔からいつだって人のことを惑わす……。卑しくて、汚らわしい。そして愚かだ」
どん、と強い力を伴って掴まれていたシャツが離された。
反動で傾いた身体が地面に伏した。
男はそんな僕に見向きもせずに、どこか遠い目でダチュラの花を見ている。
「私は“あれ”が嫌いだよ」
ゆっくりと、視線が戻ってくる。
その声が、瞳が、ぞっとするほど冷たい。
「……あぁ、そうか。君のせいか」
見下すように僕を見下ろすその目に、先ほどまでの笑みはなかった。
「……え?」
「最近“あれ”が私を拒むようになってねぇ。困っていたんだ」
「っ!」
「可愛くはないが聞き分けはいい子だった。それなのに最近はやたらと反抗的でねぇ……そうか、君が……」
再び伸びてきた手。
逃げるより前に、その手が僕の顎を強く掴んだ。
「“あれ”のは上質でねぇ、中々の値がつく。でも残念ながら私は“あれ”に嫌われていてね。だから―――君が採ってくれないかな」
「は……?」
「なに。難しいことじゃない。君は“あれ”を抱けばいい。そして“あれ”の体液を私に渡してさえくれれば―――」
男の目が、嘲けるように弧を描いた。
「“あれ”は君にあげよう」
「っ!」
思わず振り上げた手を払うと、男は僕の顎を掴む手に益々力を込めた。
「マホロはあんたのものじゃない!」
「どうかな。私がいなければ“あれ”は生まれてすらいない」
「だからってあんたのものとは言えない!」
怒りに飲み込まれてはいけない。
この男には、勝てないと思っていた。
けれど。
負けてはいけない。
この男にだけは、マホロを渡してはいけない。
「マホロはマホロだ!誰かのものじゃない!あんたに!生かされてるわけじゃない!」
「青臭いなぁ」
「青臭くたっていい!あんたみたいに人の欲を嘲笑って生きるしかないより、ずっといい」
「あはは!それを君が言うんだね?」
大きく息を吸いこんで、男の目を、真っ直ぐに見上げる。
漆黒の瞳が、ほんの少しだけたじろぐように揺れて見えた。
「人の欲望は、確かに綺麗じゃないかもしれない。醜いかもしれない。人を陥れるし、惑わす。そうやって、身を滅ぼすことだってあるのかもしれない。だからこそ人は自分の欲を隠す。知られたくない秘密として、自分の心の奥にしまい込んで鍵をかける。そうやって、生きていくしかないんでしょう。だからあの人のしたことは……きっと許されることじゃない」
その欲望に、他人を―――僕を巻き込んではいけなかったのだ。
あの人は、自分の欲望の鍵を自分で開けてしまった。
自分で自分を許してしまった。
あの人が間違えたのは、そこだけなんだろう。あの人が、きっと誰より苦しんだ筈なのだ。
「その欲望ごと、その人を愛せるかどうかなんじゃないんですか……。……僕は、あの人の全てを愛せなかったけど」
許容することしか、出来なかったけれど。
「僕はそんな風に思ったことはないけど、でも。もし喩えあんたの言う通りマホロが卑しかったとしても、人を惑わすんだとしても、それでも僕は、それも全部ひっくるめて、彼が好きです。その欲を僕に全部ぶつけて欲しいと思うくらい―――それが、僕の欲です」
「馬鹿馬鹿しい」
「あんたが知らないからですよ」
「いや……君が知らないから、かな」
「えっ?」
がっ、と強い力で上を向かされた唇に、何かが押し付けられる。
鼻先に甘い香り。“それ”を認識した途端に、軽い眩暈がした。
「君はこれを知らないからそんなふうに言えるんだよ。ほら、口を開けなさい。これはね。君の大好きな―――眞秀の体液だよ」
「っ!」
いやいやと首をふると、花弁の表面が唇に擦れて徐々に解けていく。
甘い香りが鼻についた。
「どうして嫌がる?欲望ごとあれのことが好きなんだろう?」
「ん、ん……っ」
これはマホロの欲望ではなく、あんたの欲望だろう、と睨みつければ狂気的な笑みと目が合った。
「あぁ、それとも―――」
ぞっとするほどの笑みを浮かべて、男がそう口を開いた瞬間ドタドタと騒がしい音がした。
どこか、ほっとしていた。
僕の部屋のカーテンが、破れそうな勢いで激しく開け放たれる。
庭にいる僕を捉えた途端、十影はその目を大きく見開いた。
「縁!」
「あーあ、残念だ。時間切れだよ、縁日くん」
「かっ、は……っ」
「あんた……っ、縁日になにした!」
庭に降りて駆け寄ってきた十影は、地面に落ちた花弁を見つけて男を鋭く睨みつけた。
僕には効果的なその目も、男にとってはどこ吹く風らしい。
乱れた衣服を整えながら、何でもないように笑っている。
「別になにもしていないさ。ただ、何も知らなかったお子様に教えてあげようとしただけだよ」
「あんたがこいつに教えられることなんて何もないだろ」
「そうかな?色々あると思うよ。どうも彼の家庭教師はあまりに過保護すぎるらしいからねぇ。教えられない……教えたくないんだろう?お前は」
「っ!」
言葉に詰まった十影を嘲るような視線を投げて、男はざっとダチュラに背を向けた。
黒いシルエットが庭に浮かび上がる。
「お前のその甘さも大概にしなさい。じゃないと、あの男みたいになるよ」
「俺は……っ、あいつのようにはならないっ……」
「どうだか」
震える十影の肩を叩いて、男が通り過ぎる。
僕に向かって嫌な笑みを浮かべたその唇が、十影には気付かれないように静かに動いた。
「――― ………………」
「っ!」
唇の上で微かに溶けた花酔いの花弁のせいだろうか。
くらりと眩んだ脳に血が昇って、僕はたまらず男から目を逸らした。
黒い影が、庭から出ていく。
風が吹く。身体中に籠った嫌な熱を、鼻で笑うようなあの空気の擦れる音を、あの甘ったるい香りを。
晩夏の風が洗い流して、僕はやっと息を吐いた。
心臓が、徐々にいつものスピードに戻っていく。
ちらりと十影を見上げる。
「十影 ……」
あの日―――僕を見つけた日と同じ顔を、僕よりも傷付いたような顔を、十影はまた、していた。
背中の傷が疼くのは―――目の前にいるこの男が、“あの人”に似ていたからだろうか。
「あ………」
「こんにちは」
その男はそう言って、にこりと笑った。
ただ細められたその瞳は、まるで値踏みでもするように僕を探っている。
僕の一挙手一投足、一言一句を、待っている。
満開に咲いたダチュラの花を背景に、その男が僕に近付いた。
男が纏う全ての黒を、風が揺らした。
あの、甘い匂いがする。
マホロの匂いとはまた少し違う。それでも似ている、パウダリーな甘い匂い。
花酔いの―――匂い。
「私は浄見 友親と言います。息子がお世話になっています。挨拶が遅くなってしまって」
すまなかったね、と笑みを貼り付けただけの唇がそう言った。
膝の裏に当たった百合の花が、僕の逃げ道を奪った。
「は、はじめまして。斎藤 縁日です」
「はじめまして―――ではないかな?」
「……え?」
思いがけない言葉に、思わずその男の目を、瞳を、見てしまった。
当たり前のようにマホロとは違う黒い瞳。その瞳の奥に、僕が映っている。
その向こうに、ここにあるはずもない向日葵の花が―――
「………あ?」
「思い出してくれたかな?」
「あ…ぁ……」
脳が拒む。
思い出すな、と咽喉が震える。
鼻を掠めた甘い香り。
視界を遮った、黒い服。
「背中の傷は、もう治った?」
「っ!」
「おっ、と」
思わずその男を突き放していた。
一瞬驚いたような顔をしてよろけながらも、その男はやっぱり笑っている。
さっきまでの笑みとは違う。
本当に面白そうに、その男は笑っていた。
「だ……めだ……」
駄目だ。
逃げるな。
思い出せ。
全部、思い出せ。
「……思い、出した…」
「ん?」
「あんた……あんたが、みんなを……っ」
嘲けるように、男は鼻で笑ってわざとらしく眉をハの字に曲げた。
「心外だなぁ。是非に、と声をかけてきたのは“あの神父”のほうだよ?」
「っ!」
「うん……でも、そう。確かにあの修道院の孤児たちを金で買っていたのは私だよ。私……というか機関、が正しいかな」
「機関……?」
「あれ?どうせ夕凪の奴がとっくに話しているものだと思っていたけれど……」
伸びてきた指先が、僕の頬に触れた。
ゆっくりとした手つきで僕の髪を耳にかけていく。
金縛りにあったように、僕は身じろぐことすら出来なかった。
「その様子じゃあ“あれ”にも話してないんだろうねぇ。まったく……過保護だねぇ、あいつも」
髪から離れた指先が、そのまま僕の頸動脈に触れた。
ドクドクと脈打つそれに、男が吐き捨てるように笑った。
「彼らは花酔いになったよ。一人残らず全員ね」
「っは?」
「そして全員死んだ」
「っ!」
反射的にその手を振りほどこうといた僕の首を、頸動脈に触れていたその手がいとも簡単に握り込んだ。
微かに残された気道から吸い込まれる空気がひゅうひゅうと音を立てる。
「は……なせ…っ」
「嫌だよ。離したら逃げるでしょう、君。今日はね、君にちょっとお願いがあって来たんだ」
「あ、んたの……願いなんか、知らない……っ」
「うん。まぁ、そういうだろうとは思ったけどね。大丈夫、大したお願いじゃないから」
「か…っ、は!」
そう言って男は、僕の首を絞める力を少しだけ強めた。
残されていた気道が塞がる。
急速に脳に溜まっていく血の音が、耳の奥で聞こえた。
涙で滲む視界の奥の、男の影を精一杯に睨んだ。
「あはは、成程。いい目をするねぇ。あの男が最後まで君を手放さなかった理由が分かるよ」
「う、るさい……っ」
「だからあの男にも花弁を渡したんだ。そしたら……君を天使だなんて言うようになってねぇ!」
そう言って、男が高笑いをした瞬間。
氷水でも浴びせられたように背中に悪寒が走った。
「あ、んたっ……あんたが……っ!」
「それは違うな。あの花弁はね、人間が普段心の奥に秘めている欲望を曝け出させるだけだ。人を狂わせるだけのドラッグとは違う。あの男が花弁を食べて、それで君のことを天使だと言ったのなら……それは普段、あの男が思っていたことだ」
「ち、がうっ……」
「あの男は普段から君を天使だと思っていたのさ。君を自分だけの天使にしたい、君の羽根を捥いでしまいたい、―――君を犯したい、とね」
「違う!」
「なにも違わないよ」
冷たくそう言い放って、男は僕から手を離した。
急速に大量の酸素が送り込まれた脳がくらりとする。
思わず膝をついて激しく咳き込んだ僕の視界に、黒い革靴。
はっとして顔を上げた時にはもう、胸倉が掴み上げられていた。
「ぐっ……」
「その背中にある傷は、奴の欲望の証だよ、縁日くん。奴がまともじゃなかった証拠さ」
「あんた、だって……まともじゃない!」
「あはは!そうだねぇ。君も、夕凪も、眞秀だってまともじゃない」
「あんたがマホロの名前を呼ぶな!」
一瞬見開かれた男の目が、面白そうに歪んだ。
「へぇ……。君は、“あれ”のことが好きなのかな」
「っ!」
「“あれ”は……卑しいだろう?」
「は……?」
「昔からいつだって人のことを惑わす……。卑しくて、汚らわしい。そして愚かだ」
どん、と強い力を伴って掴まれていたシャツが離された。
反動で傾いた身体が地面に伏した。
男はそんな僕に見向きもせずに、どこか遠い目でダチュラの花を見ている。
「私は“あれ”が嫌いだよ」
ゆっくりと、視線が戻ってくる。
その声が、瞳が、ぞっとするほど冷たい。
「……あぁ、そうか。君のせいか」
見下すように僕を見下ろすその目に、先ほどまでの笑みはなかった。
「……え?」
「最近“あれ”が私を拒むようになってねぇ。困っていたんだ」
「っ!」
「可愛くはないが聞き分けはいい子だった。それなのに最近はやたらと反抗的でねぇ……そうか、君が……」
再び伸びてきた手。
逃げるより前に、その手が僕の顎を強く掴んだ。
「“あれ”のは上質でねぇ、中々の値がつく。でも残念ながら私は“あれ”に嫌われていてね。だから―――君が採ってくれないかな」
「は……?」
「なに。難しいことじゃない。君は“あれ”を抱けばいい。そして“あれ”の体液を私に渡してさえくれれば―――」
男の目が、嘲けるように弧を描いた。
「“あれ”は君にあげよう」
「っ!」
思わず振り上げた手を払うと、男は僕の顎を掴む手に益々力を込めた。
「マホロはあんたのものじゃない!」
「どうかな。私がいなければ“あれ”は生まれてすらいない」
「だからってあんたのものとは言えない!」
怒りに飲み込まれてはいけない。
この男には、勝てないと思っていた。
けれど。
負けてはいけない。
この男にだけは、マホロを渡してはいけない。
「マホロはマホロだ!誰かのものじゃない!あんたに!生かされてるわけじゃない!」
「青臭いなぁ」
「青臭くたっていい!あんたみたいに人の欲を嘲笑って生きるしかないより、ずっといい」
「あはは!それを君が言うんだね?」
大きく息を吸いこんで、男の目を、真っ直ぐに見上げる。
漆黒の瞳が、ほんの少しだけたじろぐように揺れて見えた。
「人の欲望は、確かに綺麗じゃないかもしれない。醜いかもしれない。人を陥れるし、惑わす。そうやって、身を滅ぼすことだってあるのかもしれない。だからこそ人は自分の欲を隠す。知られたくない秘密として、自分の心の奥にしまい込んで鍵をかける。そうやって、生きていくしかないんでしょう。だからあの人のしたことは……きっと許されることじゃない」
その欲望に、他人を―――僕を巻き込んではいけなかったのだ。
あの人は、自分の欲望の鍵を自分で開けてしまった。
自分で自分を許してしまった。
あの人が間違えたのは、そこだけなんだろう。あの人が、きっと誰より苦しんだ筈なのだ。
「その欲望ごと、その人を愛せるかどうかなんじゃないんですか……。……僕は、あの人の全てを愛せなかったけど」
許容することしか、出来なかったけれど。
「僕はそんな風に思ったことはないけど、でも。もし喩えあんたの言う通りマホロが卑しかったとしても、人を惑わすんだとしても、それでも僕は、それも全部ひっくるめて、彼が好きです。その欲を僕に全部ぶつけて欲しいと思うくらい―――それが、僕の欲です」
「馬鹿馬鹿しい」
「あんたが知らないからですよ」
「いや……君が知らないから、かな」
「えっ?」
がっ、と強い力で上を向かされた唇に、何かが押し付けられる。
鼻先に甘い香り。“それ”を認識した途端に、軽い眩暈がした。
「君はこれを知らないからそんなふうに言えるんだよ。ほら、口を開けなさい。これはね。君の大好きな―――眞秀の体液だよ」
「っ!」
いやいやと首をふると、花弁の表面が唇に擦れて徐々に解けていく。
甘い香りが鼻についた。
「どうして嫌がる?欲望ごとあれのことが好きなんだろう?」
「ん、ん……っ」
これはマホロの欲望ではなく、あんたの欲望だろう、と睨みつければ狂気的な笑みと目が合った。
「あぁ、それとも―――」
ぞっとするほどの笑みを浮かべて、男がそう口を開いた瞬間ドタドタと騒がしい音がした。
どこか、ほっとしていた。
僕の部屋のカーテンが、破れそうな勢いで激しく開け放たれる。
庭にいる僕を捉えた途端、十影はその目を大きく見開いた。
「縁!」
「あーあ、残念だ。時間切れだよ、縁日くん」
「かっ、は……っ」
「あんた……っ、縁日になにした!」
庭に降りて駆け寄ってきた十影は、地面に落ちた花弁を見つけて男を鋭く睨みつけた。
僕には効果的なその目も、男にとってはどこ吹く風らしい。
乱れた衣服を整えながら、何でもないように笑っている。
「別になにもしていないさ。ただ、何も知らなかったお子様に教えてあげようとしただけだよ」
「あんたがこいつに教えられることなんて何もないだろ」
「そうかな?色々あると思うよ。どうも彼の家庭教師はあまりに過保護すぎるらしいからねぇ。教えられない……教えたくないんだろう?お前は」
「っ!」
言葉に詰まった十影を嘲るような視線を投げて、男はざっとダチュラに背を向けた。
黒いシルエットが庭に浮かび上がる。
「お前のその甘さも大概にしなさい。じゃないと、あの男みたいになるよ」
「俺は……っ、あいつのようにはならないっ……」
「どうだか」
震える十影の肩を叩いて、男が通り過ぎる。
僕に向かって嫌な笑みを浮かべたその唇が、十影には気付かれないように静かに動いた。
「――― ………………」
「っ!」
唇の上で微かに溶けた花酔いの花弁のせいだろうか。
くらりと眩んだ脳に血が昇って、僕はたまらず男から目を逸らした。
黒い影が、庭から出ていく。
風が吹く。身体中に籠った嫌な熱を、鼻で笑うようなあの空気の擦れる音を、あの甘ったるい香りを。
晩夏の風が洗い流して、僕はやっと息を吐いた。
心臓が、徐々にいつものスピードに戻っていく。
ちらりと十影を見上げる。
「十影 ……」
あの日―――僕を見つけた日と同じ顔を、僕よりも傷付いたような顔を、十影はまた、していた。