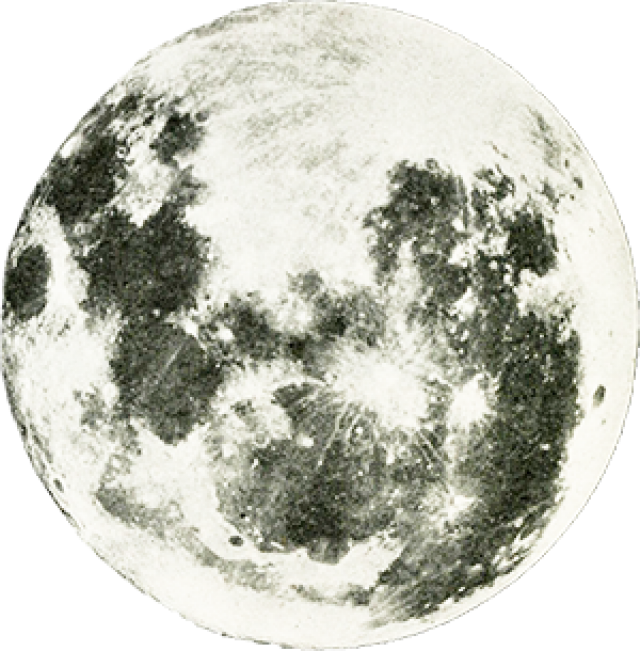-20-憶測
文字数 3,056文字
「―――……ち!………縁日!」
「ぅ、ん……ん?」
「っ!縁日!起きた!」
深海から浮上するように、意識が急激に呼び起こされた。
起きたくないと思うほど憂鬱な感情が腹の底にあったはずなのに、目を開いて飛び込んできたその瞳の美しさに、
そんな不快感は全てどこかへ吹き飛んでしまった。
「はー、よかった。十影―!!縁日、目ぇ覚めたー!!」
そうマホロが声を張った瞬間、ドタドタと床を踏み鳴らす音が響いて、髪を乱した十影が部屋に入ってきた。
「縁!」
「え、と………う、ぶっ!?」
「縁日!」
部屋に入ってきた勢いそのままに十影に抱き竦められて、危うく気道が塞がるところだった。
もぞもぞと動いてやっと鼻先だけ十影の胸板から脱出させても、その力は一向に弱まることはない。
「と…十影、苦しい……」
「………よかった…縁日……」
「大袈裟だよ……」
「そうでもないかもよ?」
「えっ?」
やっとの思いで十影の腕から抜け出して声の方を見ると、珍しくマホロがお茶を淹れているところだった。
透き通ったグラスの中に注がれる綺麗な翡翠色のお茶の中に、ゆらゆらと緑茶の茶葉が揺れている。
差し出されたそれを受け取ると、十影はやっと僕から離れてベッドの脇に座った。
重々しい空気が確かにそこにあった。
僕だけが、何かについていけていない。
「えっ……と、ごめん。僕、どうしたんだっけ?」
「意識を失ったんだよ。あの人が帰ってすぐに」
「そ、うだったんだ……」
「花弁、飲まされたんだって?」
単刀直入にそう聞いてきたマホロの声は静かに怒っていた。
端正なその顔立ちが歪むことなく、ただ鋭さを増して何かをきつく睨みつけている。
始めてみるその表情に威圧されて声を失った僕が曖昧に頷くと、眉根を寄せたマホロが吐き捨てるように舌打ちをした。
「あいつそろそろ殺そうかな」
「マホロ」
「はいはい嘘ですすいませんごめんなさい」
投げやりにそう言うと、マホロはチェアの背凭れに凭れて天を仰いだ。
「で、でもちょっと口に入っただけだし、倒れたのは花弁のせいじゃ……」
「花弁のせいなんだよ」
シガーケースの淵を指先でなぞりながら、十影が溜息交じりにそう言った。
天井を見上げたまま、マホロは微動だにしない。
「……え?」
「副作用や過剰反応がないわけじゃないんだ、花弁にだって」
「副作用?」
「吐き気や頭痛、幻覚、幻聴、強い強迫観念に襲われるようになったり意識を失ったり……それは人によって様々だが―――」
「だから倒れたって……?」
「その時の精神状態や体調も関係してくるらしいけどな。……それだって、そういう前例があったってだけで何かが解明されてるわけじゃない。可能性と憶測の域を出ない。だけど―――」
そこで言葉を止めると、十影は微かにマホロを気にした後その視線を僕に向けた。
お前とマホロは免疫細胞のレベルで見合わないんだと―――暗にそう言われたような気持ちになった。
だからなんだって言うんだ、と口の中でだけ呟く。
マホロと同じになれないんだとしても
マホロに触れられないままでも
僕は―――
「可能性と、憶測……」
何故かやけに耳に残ったままのその言葉を、唇が勝手に繰り返した。
「? 縁日?」
「あの人は……孤児を集めて花酔いにしてるんだよね。花酔いの花弁を集めるために……」
「……っ!」
一瞬見開かれた瞳が気まずそうに逸らされた。
唸りとも溜息ともとれる声が、グリーンティーの表面を微かに揺らす。
「そんなことまで……聞いたのか」
「あの修道院のみんなも花酔いになったって言ってた。それで全員死んだって……。それも、副作用とかの所為なのかな?」
「ん?」
「花酔いは短命なんだよね。感染症にも罹り易い……。だけど花酔いウイルス自体は、身体を蝕んでいくようなものじゃないよね」
「それはそうだが……」
「それなのに、全員死んだ?何十人が?」
彼らが花酔いに感染したことで死んだことは間違いない。
けれど、どうして死んだのかが問題だ。
何十人が感染症に罹って死んだのだとしたら、あの男自体にも相当なリスクがあったはず。
「(それに……)」
孤児を集めて花酔いに感染させ、結果何十人が死んだのだとしたらそれはもう立派な殺人だ。
あの男は―――浄見 友親は。
花弁を集めるためだけに、そこまでのリスクを負う男だろうか。
「花酔いを集めて、本当は何をしてたの……?」
花酔いが必要で、かつ花酔いの命を奪うような。
なにを―――。
―――私はあれが嫌いだよ
ふと、あの男の言葉と、冷めたような瞳を思い出した。
「………ん?」
「………あ?」
「………あ。」
次から次へと脳へ流れ込んでくる疑問と憶測が、処理される前に消えていく。
最後に残ったひとつの疑問に、3人が同時に思い至った。
花酔いのウイルスは、その体液によって濃度が違う。
汗が一番濃度が薄く、涙、唾液、血液、そして精液という順番で濃くなっていく。
花酔いと性交を行う非感染者なんて前例がないから断言はできない。断言は出来ないが―――
あの男―――浄見。
花酔いの体液を得るためマホロを抱くあの男は、どうしてなんの躊躇もなく花酔いを抱ける?
花酔いウイルスの危険性を誰よりも熟知している筈の男が。どうして―――
「おかしい、な」
「うん。なんで今まで気づかなかったんだろ……」
例えば妊娠。避妊具を使ったところでその避妊率は100%ではないらしい。
性病ともなればそのリスクはもっと高い。そしてそれは花酔いにだって言えることだ。
花酔いについて誰よりも知識がある筈のあの男が、最も感染リスクが高い行為を平気で行えるとは思えない。
感情が作用している?
でも「嫌いだ」と吐き捨てるように言ったあの言葉は、視線は、嘘だとは思えなかった。
あの男は本当に花酔いを嫌悪しているのだろう。
だからこそ、道具のようにマホロを扱える。
違う。
もっと。もっと違う理由が。
自分は花酔いに感染しないという確固たる自信があるから―――
「感染しない自信……」
「ウイルスを取り込めば花酔いに感染する。それはもう証明されてることだ」
「だから」
「だから?」
まだ、証明されていないこと。
花酔いを犠牲にして、行われているであろう実験。
「――― 血清?」
「……っ!あぁ!」
「え?なに?どういうこと?」
マホロだけが、首を傾げた。
きっと邪魔になりそうな知識を与えていないのだ。
「抗毒血清か。主に毒蛇に噛まれたときの治療で用いられる、解毒剤みたいなもの―――その生成には蛇の毒そのものが使われる」
「それがなに?分かんないんだけど」
「花酔いも、そのウイルスによって血清が作られた……?」
「憶測だけどな。可能性は高い」
「花酔いの治療薬が開発されてるってこと?」
「というより、治療薬開発の過程でできたワクチン―――か」
「…………」
十影の言うとおり、それはただの憶測だったのだけど。
限りなく、確信に近かったと思う。
希望、なんて大袈裟なものじゃないかもしれない。
けれど、間違いなくそれは嬉しいことだった―――はずなのに。
戸惑ったような、困ったような顔をしたマホロの瞳は、何故か、傷付いたように揺らいでいた。
「ぅ、ん……ん?」
「っ!縁日!起きた!」
深海から浮上するように、意識が急激に呼び起こされた。
起きたくないと思うほど憂鬱な感情が腹の底にあったはずなのに、目を開いて飛び込んできたその瞳の美しさに、
そんな不快感は全てどこかへ吹き飛んでしまった。
「はー、よかった。十影―!!縁日、目ぇ覚めたー!!」
そうマホロが声を張った瞬間、ドタドタと床を踏み鳴らす音が響いて、髪を乱した十影が部屋に入ってきた。
「縁!」
「え、と………う、ぶっ!?」
「縁日!」
部屋に入ってきた勢いそのままに十影に抱き竦められて、危うく気道が塞がるところだった。
もぞもぞと動いてやっと鼻先だけ十影の胸板から脱出させても、その力は一向に弱まることはない。
「と…十影、苦しい……」
「………よかった…縁日……」
「大袈裟だよ……」
「そうでもないかもよ?」
「えっ?」
やっとの思いで十影の腕から抜け出して声の方を見ると、珍しくマホロがお茶を淹れているところだった。
透き通ったグラスの中に注がれる綺麗な翡翠色のお茶の中に、ゆらゆらと緑茶の茶葉が揺れている。
差し出されたそれを受け取ると、十影はやっと僕から離れてベッドの脇に座った。
重々しい空気が確かにそこにあった。
僕だけが、何かについていけていない。
「えっ……と、ごめん。僕、どうしたんだっけ?」
「意識を失ったんだよ。あの人が帰ってすぐに」
「そ、うだったんだ……」
「花弁、飲まされたんだって?」
単刀直入にそう聞いてきたマホロの声は静かに怒っていた。
端正なその顔立ちが歪むことなく、ただ鋭さを増して何かをきつく睨みつけている。
始めてみるその表情に威圧されて声を失った僕が曖昧に頷くと、眉根を寄せたマホロが吐き捨てるように舌打ちをした。
「あいつそろそろ殺そうかな」
「マホロ」
「はいはい嘘ですすいませんごめんなさい」
投げやりにそう言うと、マホロはチェアの背凭れに凭れて天を仰いだ。
「で、でもちょっと口に入っただけだし、倒れたのは花弁のせいじゃ……」
「花弁のせいなんだよ」
シガーケースの淵を指先でなぞりながら、十影が溜息交じりにそう言った。
天井を見上げたまま、マホロは微動だにしない。
「……え?」
「副作用や過剰反応がないわけじゃないんだ、花弁にだって」
「副作用?」
「吐き気や頭痛、幻覚、幻聴、強い強迫観念に襲われるようになったり意識を失ったり……それは人によって様々だが―――」
「だから倒れたって……?」
「その時の精神状態や体調も関係してくるらしいけどな。……それだって、そういう前例があったってだけで何かが解明されてるわけじゃない。可能性と憶測の域を出ない。だけど―――」
そこで言葉を止めると、十影は微かにマホロを気にした後その視線を僕に向けた。
お前とマホロは免疫細胞のレベルで見合わないんだと―――暗にそう言われたような気持ちになった。
だからなんだって言うんだ、と口の中でだけ呟く。
マホロと同じになれないんだとしても
マホロに触れられないままでも
僕は―――
「可能性と、憶測……」
何故かやけに耳に残ったままのその言葉を、唇が勝手に繰り返した。
「? 縁日?」
「あの人は……孤児を集めて花酔いにしてるんだよね。花酔いの花弁を集めるために……」
「……っ!」
一瞬見開かれた瞳が気まずそうに逸らされた。
唸りとも溜息ともとれる声が、グリーンティーの表面を微かに揺らす。
「そんなことまで……聞いたのか」
「あの修道院のみんなも花酔いになったって言ってた。それで全員死んだって……。それも、副作用とかの所為なのかな?」
「ん?」
「花酔いは短命なんだよね。感染症にも罹り易い……。だけど花酔いウイルス自体は、身体を蝕んでいくようなものじゃないよね」
「それはそうだが……」
「それなのに、全員死んだ?何十人が?」
彼らが花酔いに感染したことで死んだことは間違いない。
けれど、どうして死んだのかが問題だ。
何十人が感染症に罹って死んだのだとしたら、あの男自体にも相当なリスクがあったはず。
「(それに……)」
孤児を集めて花酔いに感染させ、結果何十人が死んだのだとしたらそれはもう立派な殺人だ。
あの男は―――浄見 友親は。
花弁を集めるためだけに、そこまでのリスクを負う男だろうか。
「花酔いを集めて、本当は何をしてたの……?」
花酔いが必要で、かつ花酔いの命を奪うような。
なにを―――。
―――私はあれが嫌いだよ
ふと、あの男の言葉と、冷めたような瞳を思い出した。
「………ん?」
「………あ?」
「………あ。」
次から次へと脳へ流れ込んでくる疑問と憶測が、処理される前に消えていく。
最後に残ったひとつの疑問に、3人が同時に思い至った。
花酔いのウイルスは、その体液によって濃度が違う。
汗が一番濃度が薄く、涙、唾液、血液、そして精液という順番で濃くなっていく。
花酔いと性交を行う非感染者なんて前例がないから断言はできない。断言は出来ないが―――
あの男―――浄見。
花酔いの体液を得るためマホロを抱くあの男は、どうしてなんの躊躇もなく花酔いを抱ける?
花酔いウイルスの危険性を誰よりも熟知している筈の男が。どうして―――
「おかしい、な」
「うん。なんで今まで気づかなかったんだろ……」
例えば妊娠。避妊具を使ったところでその避妊率は100%ではないらしい。
性病ともなればそのリスクはもっと高い。そしてそれは花酔いにだって言えることだ。
花酔いについて誰よりも知識がある筈のあの男が、最も感染リスクが高い行為を平気で行えるとは思えない。
感情が作用している?
でも「嫌いだ」と吐き捨てるように言ったあの言葉は、視線は、嘘だとは思えなかった。
あの男は本当に花酔いを嫌悪しているのだろう。
だからこそ、道具のようにマホロを扱える。
違う。
もっと。もっと違う理由が。
自分は花酔いに感染しないという確固たる自信があるから―――
「感染しない自信……」
「ウイルスを取り込めば花酔いに感染する。それはもう証明されてることだ」
「だから」
「だから?」
まだ、証明されていないこと。
花酔いを犠牲にして、行われているであろう実験。
「――― 血清?」
「……っ!あぁ!」
「え?なに?どういうこと?」
マホロだけが、首を傾げた。
きっと邪魔になりそうな知識を与えていないのだ。
「抗毒血清か。主に毒蛇に噛まれたときの治療で用いられる、解毒剤みたいなもの―――その生成には蛇の毒そのものが使われる」
「それがなに?分かんないんだけど」
「花酔いも、そのウイルスによって血清が作られた……?」
「憶測だけどな。可能性は高い」
「花酔いの治療薬が開発されてるってこと?」
「というより、治療薬開発の過程でできたワクチン―――か」
「…………」
十影の言うとおり、それはただの憶測だったのだけど。
限りなく、確信に近かったと思う。
希望、なんて大袈裟なものじゃないかもしれない。
けれど、間違いなくそれは嬉しいことだった―――はずなのに。
戸惑ったような、困ったような顔をしたマホロの瞳は、何故か、傷付いたように揺らいでいた。