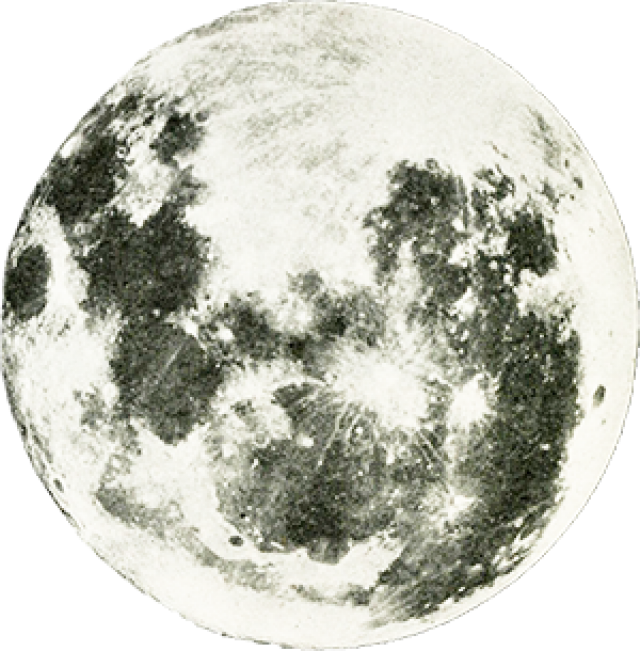-9-花弁
文字数 3,516文字
深い赤色の粒が、まるで宝石のように煌めいていた。
目の前に差し出されたチェリータルトを前に、思わず感嘆符が漏れる。
「タルトだ……!」
「子どもかよ」
「好きなの?甘いもの」
「うん」
フォークで口に運ぶと、とろりとしたカスタードの甘みが口の中に広がった。
噛み締めたチェリーから果汁が溢れる。
さくっとしたタルト地がほろりとほどけた。
「ふぉおおおおお」
「よかったねぇ」
「お前はこっち」
ことり、と十影がテーブルの上に小瓶を置いた。
小さなジャム瓶くらいの大きさのそれに、ぎっしりと赤いバラの花びらが詰まっている。
「ありがと」
「……バラの花?」
「砂糖漬けだ。もちろん、オーガニックシュガーと蜂蜜を使ってる」
「……もしかして十影の手作り?」
「なにか問題が?」
「いえ……なんでもない、です」
十影の視線から逃れるように、僕はもう一度その小瓶に視線を移した。
よく見れば、花びらの表面が水滴を纏うようにきらきらと輝いて見える。
一瞬それが、花酔いのあの体液と重なって見えて、僕はそれからも目を逸らした。
「十影ってこういうとこあるよねぇ」
指先で瓶をこつこつと突きながら、マホロが小さく笑った。
「こういうところ?」
「人妻っぽいっていうか」
「蜂蜜レモン作ってくる女子マネっぽい?」
「それ!」
「あぁ?」
怒るのかと思っていたら、何故か十影は呆れたような目をして僕を見た。
「縁……お前また変な本読んだな?」
「変じゃないよ。書庫にあった本」
「………マホロ」
「おっかしいなぁ、片付けたんだけどなぁ」
溜息交じりに十影は自分の皿に乗ったザッハトルテを殆ど手つかずのまま、僕の前に差し出した。
つやつやとしたチョコレートの表面に金粉が揺れている。
まだ口の中に残るカスタードの甘みを、ほろ苦いガナッシュと洋酒の香りが上書きした。
「蜂蜜レモン作ってくる女子マネとはくっつかなかったんだよ、結局」
「は?」
「野球部エース。結局その女子マネじゃなくて、引退した元主将と付き合うことになったんだ」
「………マホロ」
「おっかしいなぁ、片付けたんだけどなぁ」
咽喉の奥で小さく笑いながら、マホロはそろりとグラスから紅茶を飲んだ。
「文化遺産レベルの書庫にお前の趣味で薄い本を混ぜるな」
「書庫に本おいて何が悪いんだよ」
「歴史的文章の隣にBL本置くなっつってんだよ!……縁。お前も手当たり次第に本読む癖やめろ」
「十影が本読んで知識と感受性を養えって言ったんじゃんか」
「内容を選べっつってんだよ」
「読まなきゃ内容分かんないよ」
盛大に溜息を吐いて、十影はカップの中の紅茶を煽った。
「なんでそんな顔するんだよ。エースが女子マネとくっつく話だったらいいの?」
「そうじゃねえよ」
紅茶を注ぎながら十影が顔を顰める。
そんな話をしているうちに、僕は2つ目のケーキを平らげていた。
「ジェンダーに対して偏見がないのはいいことだよ。現代っ子らしいとも言えるけどな。ただお前は、そこを理解するまえにまず世間一般的な
“普通”ってのが分かってないだろ」
「分かってはいるよ。理解はしてないけど」
「俺はお前のそういうとこが怖いんだよ」
一度持ち上げたカップをソーサーの上に戻して、十影は僕の額を小突いた。
「新しい知識全部、真っ新な脳みそに吸収しちまう。経験値が無いから使い道も意味も分かんねぇくせに、とりあえず“そういうもんもある”って納得しちまう」
「それのなにが怖いんだよ」
「いざってときに流されるかもしんねぇだろ」
「………ん?」
「分かってないよ、これは」
そう言うマホロはどこか楽しそうな顔をしていた。
「十影はね、縁日がいつか無自覚のうちに野球部エースみたいになっちゃわないか心配なんだよ」
「なんで?笑ってたよ」
「そう?そのまま女子マネと付き合ってた方が幸せになれたんじゃない?」
変わらないマホロの声音が、何故か摺り硝子のように鋭く響いた。
その言葉の意味が、やっぱり僕には分からなかったけれど。
「同性同士だと幸せになれないってこと?」
「そうじゃないよ。でも世間的にはそうだね」
「んー………?」
「マホロ、そのくらいでいいだろ」
胸ポケットから煙草を取り出しながら、十影がそう言った。
テーブルの上の灰皿を掴むとそのまま庭の外に出ていく。
閉じられたレースカーテンに、十影の黒いシルエットが浮かび上がった。
晴天の空気に吐き出された煙が、カーテン越しに空へ昇っていく。
それでもいつものあのバニラの香りはここには届かなかった。
隠すことはしなくても、マホロの前では吸わないらしい。
ことり、と音がして僕は意識をそちらに向けた。
バラの砂糖漬けが入った小瓶の底を、マホロがぼんやりと光に透かすようにして眺めている。
マホロのアクアマリン色の瞳に、真っ赤なバラの花弁が映る。
それでもその澄んだ色は、バラの色に負けることはなかった。
「―――ちゃんと寝てる?」
「え?」
唐突過ぎるその質問に、僕の心臓が跳ねた。
その質問に、その質問以上の何かを感じ取ってしまったからだ。
「ど、うして?」
「部屋、戻ってないよね」
「っ!」
そう言われて僕はやっと気が付いた。
昼間から戻らない部屋にはカーテンが開け放たれたままで、灯りが付くこともない。
庭から部屋を覗かずとも、部屋の主が不在ということくらい簡単に分かってしまう。
「つ、つい勉強に夢中になっちゃって……気付いたら書斎で寝てたり、する……」
「ふぅん」
納得していない声だった。
マホロの指先が小瓶のリボンを解く。
「いや、違うんならいいんだけどさ」
ことり、と硝子で出来た蓋がテーブルの上に置かれた。
白い指先が、真っ赤なバラの花弁を摘まみ取る。
「もしかして」
薄い唇から覗いた真っ赤な舌が、その花弁を攫って行った。
「俺の所為かなって思って」
どくり、と耳の奥で熱い音がした。
月夜の下のあの光景が、浮かぶ。
虚ろな目が。空虚な瞳が。
ゆっくりと僕を見て。
笑った。
「ッ!」
「なんてね」
指先についた砂糖の粒を紅茶の中に落としながら、マホロは僕を見てもう一度小さく笑った。
心臓の動きがゆっくりと元に戻っていく。けれどその音だけは鼓膜の奥で煩く響いていた。
「………ごめん」
「なんで謝るの?」
「だって……」
ついさっきとまったく同じ問答に、僕は俯くしかなかった。
さっきとは違う。あからさまに、マホロが傷付いたような目をしたからだ。
「引いた?」
僕は首を横に振った。
するとマホロは、少しだけ意外そうな顔をした。
「引いたりは……して、ない。ただ……」
「うん」
「………ごめん。よく、分からない」
考えて、僕はやっとそう答えた。
答えには、なっていなかったけれど。
落胆でも、傷付いた感じでもない、極自然にマホロの視線が庭の方に向く。
極採色の庭の中に、ひとつの影。
真っ青な空に昇るバニラの香り。
「俺が煙草吸ったら、どうなっちゃうのかな」
「………え?」
「なんてね」
なんてね、なんて言っている表情ではなかった。
その言葉の真意が読み取れずに、かと言ってマホロにそれを聞くことも出来ずに、僕はただ冷めた紅茶の表面を見つめた。
「縁日はさ、インキュバスって知ってる?」
「インキュ………悪魔の名前だっけ」
「そう、正確には夢魔。美しさで人を誘惑して、その精気を吸い取って自分の欲を満たす淫魔」
マホロは瓶の中から花弁を取り出して、それをそっとグラスの中へ落とした。
紅茶の表面で浮かんでいた花弁の砂糖が徐々に取れて、真っ赤な花弁がグラスの底へ沈んでいく。
「俺みたいでしょ」
「えっ?」
「折角きれいに咲いた花の精気を吸って、俺は生きてる。それなのに、俺に流れる血は、体液は、こんなにも汚い」
す、と僕に向かってその白い腕が差し出された。
手首に浮く青い血管が、マホロの鼓動に沿って動いている。
「だからね」
腕がマホロの元へと戻っていく。
その先で、ほんの少し悲しそうに、それでも、今まで見たよりも一番強い笑顔を、マホロは見せていた。
「俺は絶対に、泣かないんだ」
ぶわり、と強い風がカーテンを突き抜けた。
鼻先に感じた微かなバニラの香りに毒素が含まれていないことを、僕は心から願った。
目の前に差し出されたチェリータルトを前に、思わず感嘆符が漏れる。
「タルトだ……!」
「子どもかよ」
「好きなの?甘いもの」
「うん」
フォークで口に運ぶと、とろりとしたカスタードの甘みが口の中に広がった。
噛み締めたチェリーから果汁が溢れる。
さくっとしたタルト地がほろりとほどけた。
「ふぉおおおおお」
「よかったねぇ」
「お前はこっち」
ことり、と十影がテーブルの上に小瓶を置いた。
小さなジャム瓶くらいの大きさのそれに、ぎっしりと赤いバラの花びらが詰まっている。
「ありがと」
「……バラの花?」
「砂糖漬けだ。もちろん、オーガニックシュガーと蜂蜜を使ってる」
「……もしかして十影の手作り?」
「なにか問題が?」
「いえ……なんでもない、です」
十影の視線から逃れるように、僕はもう一度その小瓶に視線を移した。
よく見れば、花びらの表面が水滴を纏うようにきらきらと輝いて見える。
一瞬それが、花酔いのあの体液と重なって見えて、僕はそれからも目を逸らした。
「十影ってこういうとこあるよねぇ」
指先で瓶をこつこつと突きながら、マホロが小さく笑った。
「こういうところ?」
「人妻っぽいっていうか」
「蜂蜜レモン作ってくる女子マネっぽい?」
「それ!」
「あぁ?」
怒るのかと思っていたら、何故か十影は呆れたような目をして僕を見た。
「縁……お前また変な本読んだな?」
「変じゃないよ。書庫にあった本」
「………マホロ」
「おっかしいなぁ、片付けたんだけどなぁ」
溜息交じりに十影は自分の皿に乗ったザッハトルテを殆ど手つかずのまま、僕の前に差し出した。
つやつやとしたチョコレートの表面に金粉が揺れている。
まだ口の中に残るカスタードの甘みを、ほろ苦いガナッシュと洋酒の香りが上書きした。
「蜂蜜レモン作ってくる女子マネとはくっつかなかったんだよ、結局」
「は?」
「野球部エース。結局その女子マネじゃなくて、引退した元主将と付き合うことになったんだ」
「………マホロ」
「おっかしいなぁ、片付けたんだけどなぁ」
咽喉の奥で小さく笑いながら、マホロはそろりとグラスから紅茶を飲んだ。
「文化遺産レベルの書庫にお前の趣味で薄い本を混ぜるな」
「書庫に本おいて何が悪いんだよ」
「歴史的文章の隣にBL本置くなっつってんだよ!……縁。お前も手当たり次第に本読む癖やめろ」
「十影が本読んで知識と感受性を養えって言ったんじゃんか」
「内容を選べっつってんだよ」
「読まなきゃ内容分かんないよ」
盛大に溜息を吐いて、十影はカップの中の紅茶を煽った。
「なんでそんな顔するんだよ。エースが女子マネとくっつく話だったらいいの?」
「そうじゃねえよ」
紅茶を注ぎながら十影が顔を顰める。
そんな話をしているうちに、僕は2つ目のケーキを平らげていた。
「ジェンダーに対して偏見がないのはいいことだよ。現代っ子らしいとも言えるけどな。ただお前は、そこを理解するまえにまず世間一般的な
“普通”ってのが分かってないだろ」
「分かってはいるよ。理解はしてないけど」
「俺はお前のそういうとこが怖いんだよ」
一度持ち上げたカップをソーサーの上に戻して、十影は僕の額を小突いた。
「新しい知識全部、真っ新な脳みそに吸収しちまう。経験値が無いから使い道も意味も分かんねぇくせに、とりあえず“そういうもんもある”って納得しちまう」
「それのなにが怖いんだよ」
「いざってときに流されるかもしんねぇだろ」
「………ん?」
「分かってないよ、これは」
そう言うマホロはどこか楽しそうな顔をしていた。
「十影はね、縁日がいつか無自覚のうちに野球部エースみたいになっちゃわないか心配なんだよ」
「なんで?笑ってたよ」
「そう?そのまま女子マネと付き合ってた方が幸せになれたんじゃない?」
変わらないマホロの声音が、何故か摺り硝子のように鋭く響いた。
その言葉の意味が、やっぱり僕には分からなかったけれど。
「同性同士だと幸せになれないってこと?」
「そうじゃないよ。でも世間的にはそうだね」
「んー………?」
「マホロ、そのくらいでいいだろ」
胸ポケットから煙草を取り出しながら、十影がそう言った。
テーブルの上の灰皿を掴むとそのまま庭の外に出ていく。
閉じられたレースカーテンに、十影の黒いシルエットが浮かび上がった。
晴天の空気に吐き出された煙が、カーテン越しに空へ昇っていく。
それでもいつものあのバニラの香りはここには届かなかった。
隠すことはしなくても、マホロの前では吸わないらしい。
ことり、と音がして僕は意識をそちらに向けた。
バラの砂糖漬けが入った小瓶の底を、マホロがぼんやりと光に透かすようにして眺めている。
マホロのアクアマリン色の瞳に、真っ赤なバラの花弁が映る。
それでもその澄んだ色は、バラの色に負けることはなかった。
「―――ちゃんと寝てる?」
「え?」
唐突過ぎるその質問に、僕の心臓が跳ねた。
その質問に、その質問以上の何かを感じ取ってしまったからだ。
「ど、うして?」
「部屋、戻ってないよね」
「っ!」
そう言われて僕はやっと気が付いた。
昼間から戻らない部屋にはカーテンが開け放たれたままで、灯りが付くこともない。
庭から部屋を覗かずとも、部屋の主が不在ということくらい簡単に分かってしまう。
「つ、つい勉強に夢中になっちゃって……気付いたら書斎で寝てたり、する……」
「ふぅん」
納得していない声だった。
マホロの指先が小瓶のリボンを解く。
「いや、違うんならいいんだけどさ」
ことり、と硝子で出来た蓋がテーブルの上に置かれた。
白い指先が、真っ赤なバラの花弁を摘まみ取る。
「もしかして」
薄い唇から覗いた真っ赤な舌が、その花弁を攫って行った。
「俺の所為かなって思って」
どくり、と耳の奥で熱い音がした。
月夜の下のあの光景が、浮かぶ。
虚ろな目が。空虚な瞳が。
ゆっくりと僕を見て。
笑った。
「ッ!」
「なんてね」
指先についた砂糖の粒を紅茶の中に落としながら、マホロは僕を見てもう一度小さく笑った。
心臓の動きがゆっくりと元に戻っていく。けれどその音だけは鼓膜の奥で煩く響いていた。
「………ごめん」
「なんで謝るの?」
「だって……」
ついさっきとまったく同じ問答に、僕は俯くしかなかった。
さっきとは違う。あからさまに、マホロが傷付いたような目をしたからだ。
「引いた?」
僕は首を横に振った。
するとマホロは、少しだけ意外そうな顔をした。
「引いたりは……して、ない。ただ……」
「うん」
「………ごめん。よく、分からない」
考えて、僕はやっとそう答えた。
答えには、なっていなかったけれど。
落胆でも、傷付いた感じでもない、極自然にマホロの視線が庭の方に向く。
極採色の庭の中に、ひとつの影。
真っ青な空に昇るバニラの香り。
「俺が煙草吸ったら、どうなっちゃうのかな」
「………え?」
「なんてね」
なんてね、なんて言っている表情ではなかった。
その言葉の真意が読み取れずに、かと言ってマホロにそれを聞くことも出来ずに、僕はただ冷めた紅茶の表面を見つめた。
「縁日はさ、インキュバスって知ってる?」
「インキュ………悪魔の名前だっけ」
「そう、正確には夢魔。美しさで人を誘惑して、その精気を吸い取って自分の欲を満たす淫魔」
マホロは瓶の中から花弁を取り出して、それをそっとグラスの中へ落とした。
紅茶の表面で浮かんでいた花弁の砂糖が徐々に取れて、真っ赤な花弁がグラスの底へ沈んでいく。
「俺みたいでしょ」
「えっ?」
「折角きれいに咲いた花の精気を吸って、俺は生きてる。それなのに、俺に流れる血は、体液は、こんなにも汚い」
す、と僕に向かってその白い腕が差し出された。
手首に浮く青い血管が、マホロの鼓動に沿って動いている。
「だからね」
腕がマホロの元へと戻っていく。
その先で、ほんの少し悲しそうに、それでも、今まで見たよりも一番強い笑顔を、マホロは見せていた。
「俺は絶対に、泣かないんだ」
ぶわり、と強い風がカーテンを突き抜けた。
鼻先に感じた微かなバニラの香りに毒素が含まれていないことを、僕は心から願った。