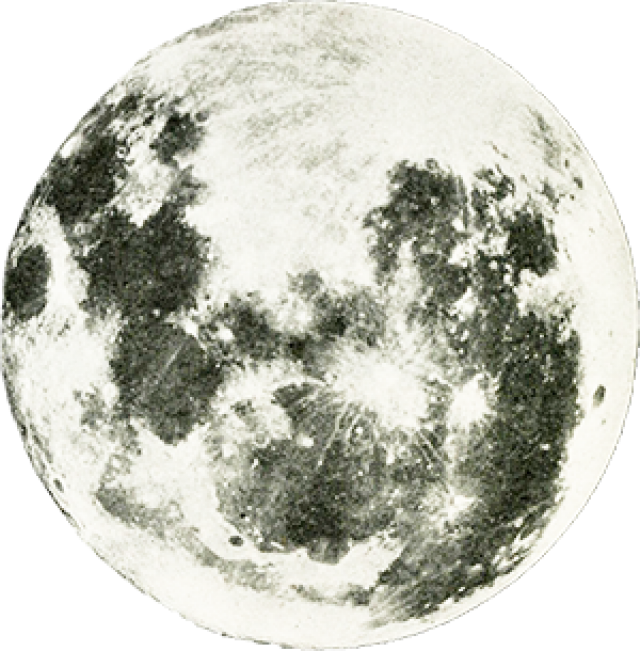-26-散花
文字数 4,814文字
「さて、なにから話しましょうか」
十影が淹れたスミレの花弁が浮かぶ紅茶に一頻り騒いだ後、ひどく穏やかな口調で吉永はそう切り出した。
伺うようにちらりと動いたその視線を追うと、ソファの肘掛に浅く腰掛けた眞秀の横顔があった。
潤いで満ちた色素の薄い瞳が、ぼんやりと窓の外を見ている。
興味があるのかないのか、それとも聞くことが怖いのか。
感情をうまく表現出来ないその表情に小さく笑って、吉永は何故か縁日を見た。
「浄見 友親を逮捕しました」
「っ!」
単刀直入に切り出された一言に、息を呑んだのは縁日だけだった。
穏やかなようでいて張り詰めている空気に、それでも吉永は容赦無く針を落としていく。
「罪状は、研究費と偽り不正に金を受け取っていたとする詐欺罪です。---表向きは、ですが」
組んでいた足を組み替えて、吉永は静かにそう言った。
「本当の罪状は花酔い関係ということですか」
「詐欺も嘘じゃないよ、夕凪。ただ……まぁ、そうだね。花酔いに関しては公にしていないこと、できないことが多すぎる。彼の余罪の殆どは花酔いに関することだからね。公表するかしないかで揉めているんだよ」
長い指がカップの縁をなぞる。
言葉を選ぶように吉永は続けた。
「ただこれはもう、我々警察だけの話じゃないね。主体になって決めていくのは政府だ。おそらく後何年かで花酔いに関する法律や制度が変わっていく。それが……良いことかそうじゃないかは僕には分からないけれど」
眞秀は変わらず窓の外を見ていた。
雨上がりの光に透ける綺麗な髪が、その表情も、感情も、隠している。
「今回の浄見の逮捕が、良くも悪くもきっかけになることは間違いないと僕は思う。ただ彼の処遇については……少し意見が割れている」
「割れる?」
「刑の重さを巡ってね。浄見は、花酔いの花弁に含まれる麻薬物質を利用して、まったく新しいドラッグを造っていた。どんな検査にも引っかからず、それでいて大麻や阿片にも勝る強烈な快楽を得られる新型のセックスドラッグ」
そこで吉永は言葉を止め、また眞秀を見た。
ゆっくりとその横顔がこちらを向く。
静かに、それでいて強い眼差しが、今度はしっかりと吉永を見据えた。
何も言わなかった。
けれど、吉永は小さく頷いてゆっくりと口を開く。
「花酔いの花弁は、その体液によって効果の強さが変わるのは知っていると思うけれど、全ての花弁をひとつにして、均一な濃度のドラッグにすることは、どうやらそんなに難しいことではなかったようだね。けれど浄見はあえてそうしなかった」
「あ?」
「あえて粗悪品を作ったんだ。グレードをつけたと言ったほうがいいかな。格安なものから、とても一般市民じゃ手の届かないような価格のものまで」
「それだけ儲ける幅を作ったってことか」
「そう。それともうひとつ。浄見には算段があった」
「算段?」
「ドラッグにも、花弁と同じような副作用が残ってしまった。得られるのは快楽か死。ふたつにひとつ。グレードが高ければ高いほど、副作用が出る確率は低くなるけれど……それでも0にはならない。どうやら副作用は体質によるところが大きいみたいだからね。だから浄見は、造ったんだ」
吉永はそう言って、スーツの内ポケットからアルミのケースを取り出した。
蓋を開いて、テーブルの上に置く。
中には桜色に光る液体の入ったアンプルがひとつだけ収まっていた。
「これは?」
「血清だよ」
「なっ!?」
「どんなに都合がいいドラッグでも、死んでしまうかもしれないなんて話にならないからね。血清を造り、ドラッグと一緒に売った。グレードが低くでも、ドラッグは売れた」
「完成……してたのか」
呟くようにそう言って、十影は頭を抱えた。
テーブルの上で、アンプルの桜色が妖しく光っている。
「どうして……」
「うん?」
「それでどうして、刑を軽くしようという意見が出るんでしょうか」
少しだけ困ったように、眼鏡の奥の瞳は縁日を見た。
「刑を軽くしよう、というより化学の……医学の功績でもあるんだよ、彼の行っていた研究は---そしてその結果は」
「………」
「僕も正直そう思う。だからと言って、彼がしたことが許されるとは思わないし、刑を軽くしたほうがいいとは到底思えない。ごく一部の意見だよ」
「それでも……っ」
辛い思いを、苦しい思いをした花酔いがたくさんいて
傷ついて、傷つけられて、踏みにじられた人が、たくさんいて
それなのに---
「先輩」
十影が、静かな声でそう吉永を呼んだ。
「浄見の功績というのは、血清を作ったことですか?それとも」
「そうだよ、夕凪」
十影の言わんとしていることを察して、吉永が小さく頷く。
「血清の研究途中で、副産物としてできたもの---」
吉永はテーブルの上のケースに手を伸ばした。
アンプルの収められている台の底を、ゆっくりと持ち上げる。
「っ!」
何の変哲もない、白いカプセル。
風邪薬となんら変わらないそれに、十影だけが息を飲んだ。
「こ…れは……ま、さか」
「そう、薬だよ。花酔いのね」
「っ!」
浅く息を吐きながら、吉永はゆっくりとケースの蓋を閉じ、内ポケットにしまった。
「完成品ではないし、正しくは治療薬ではないそうだよ。治癒ではなく、あくまで花酔いの症状を緩和させる程度のものらしい。浄見にとっては、これより血清の研究のほうが大事だったようだね。偶然造り出した以降、これを研究した形跡はなかったよ」
「クソ……!」
「ただまぁ、情報は国の研究機関にそのまま譲渡される。これが完成する日も、そう遠くはないのかもしれない。そう考えると、この胸糞悪い状況も少しはマシに思えるね」
冷めた紅茶を飲みながら、吉永は口の端を小さく吊り上げた。
「ねぇ」
その声に、吉永の視線が上がる。
縁日の頭上で止まったその視線を追うと、無表情のままの眞秀が立っていた。
「さっきの人、俺に用事がある感じだったけど。話ってこれじゃないよね?」
「……まったく。本当に使えない部下を持ったようです。僕は」
溜息を隠しもせず、吉永は苦々しげに笑いながらカップをソーサーの上に戻した。
「正直に言うと、今し方お伝えした話は僕にはあまり関係ありません。ドラッグも、研究費の不正受け渡しも、動くのは他の班であって僕じゃない」
長い指が眼鏡を押し上げる。一瞬だけ見えた瞳が、真っ直ぐに縁日を見ていた。
「お話を伺いたかったのは、眞秀くんというより貴方ですよ。縁日くん」
「僕?」
「花酔いの花弁を量産する為、身寄りのない孤児を買取り、花酔いに故意に感染させ、結果、その全員を死に至らしめた。過失致死---いや、僕たち公安は、浄見 友親を殺人罪で立件しようとしています」
「っ!」
「殺意はなかったと弁護されても、人数が人数です。おそらく彼は二度と、外の世界には出られないでしょう」
安堵と、憤りと、そして何故か、少しの焦燥。
自分の中に渦巻く感情をうまく処理できずに、縁日は小さく息を吐いた。
後ろで、微かに息が乱れた眞秀の気配がした。
「本当……だったんですね。売られた孤児みんな、死んだって」
「感染の仕方も、花弁を採るために強要されていた行為も良くなかったようですね。浄見の元へ行ってから、長く持った子で、1年」
「っ……!」
引き攣った眞秀の声に息も吐けなかった。
霞んだ記憶に、真っ白なダチュラがやけに鮮明に浮かんでいた。
きっと、あの日の記憶はこの先も消えない。
消してしまっては、いけないのだろうと思う。
自分だって、あの修道院の孤児であることに変わりはないんだから。
眞秀を見る。
アクアマリン色の瞳が、水面のように揺れていた。
その中に映った自分が、不器用に笑う。
眞秀もつられて、困ったように笑った。
「吉永さん」
「はい」
「僕は、修道院の孤児が一定期間でどこかへ行ってしまうことしか知りませんでした。どこへ行ったのかも、どうしていなくなったのかも分からなかった。浄見の存在を知ったのも、この家に来てからです。警察の役に立つような情報を、僕は持っていません」
「そうですか……」
さして残念がることもなく、吉永はまたその目を細めた。
「分かりました。ご協力、感謝いたします」
「いえ、お役に立なくて……すいません」
「いえいえ、とんでもない。こちらこそ急に押しかけて申し訳ありませんでした」
吉永はそう言って、深々と頭を下げた。
「先輩」
「うん?」
「治療薬の研究を進める為に司法取引……なんてことには?」
「あぁ、その心配もどうやらないようだよ」
どこか少し楽しそうに吉永は十影に向き直った。
先輩と呼ばれたことが嬉しかったのかもしれない。
「今まで花酔いの研究がなかなか進まずにいたのは、単純にサンプルとデータの不足によるところが大きいんだと思うよ。未だに花酔いが空想上の奇病だと信じている学者も多い。僕だって、今日 彼に会うまでは花酔いに会ったことはなかったからね。殆どの人は、一生のうちに花酔いに出会うことすらないのかもしれない。それは純粋に花酔いが世間に紛れて生活できないその性質によるのだろうね。その花酔いの花弁を浄見は手に入れることができた。彼が花酔いの研究を進めることができた理由は、ただそのひとつだけなんだよ。……もしそうでないとしても、彼はもう、花酔いに関わってはいけない」
この国も、警察も、そこまで馬鹿ではないよ。と本気とも冗談ともとれる口調でそう言って、
吉永は眞秀を見上げた。
「浄見の一番の被害者は貴方です、眞秀くん。被害者として、親族として、そして花酔いとして……
貴方が矢面に立たされることもこの先、少なくないと思います。無論、僕も尽力はしていくつもりですが……」
小さく首を横に振って、吉永の言葉を遮ると
眞秀は微かに眉尻を下げて笑った。
「だいじょうぶ」
まるで自分に言い聞かせるように
子どものような発音で、それでもはっきり眞秀は言った。
「俺はひとりじゃないから」
カーテンが、ぶわりと風を含んで膨らんだ。
部屋に微かに残る夏の熱を、秋の風が攫っていく。
部屋に残された金木犀の残り香が、縁日の鼻先を擽った。
「無気力で、無愛想で堅物で」
にっこりと満面の笑みを浮かべた吉永が、急にそう口を開いた。
「何を考えているのか一向に分からない後輩が、あれだけ溺愛していたお二人に会えてよかった」
「せっ…んぱい…!」
「無気力……」
「溺愛……」
眞秀と縁日の視線から逃げるように顔をそらした十影の耳が微かに赤い。
「隠し子がいるって噂されてたの、夕凪知らないでしょ」
「知ってますよ!そもそもその噂流したの先輩でしょうに!」
「違うよ。僕はただ、子を守る親熊みたいだよねって言っただけだよ」
「確信犯じゃないですか……!」
はははと笑って、吉永はちらりと腕時計を見た。
「あぁ、暗いと思ったらもうこんな時間ですね。いやはや長居してしまって申し訳ありません」
「先輩……さっきの人、待たせっぱなしじゃないですか?」
「うん。さすがに悪いと思うし、そろそろ失礼するよ」
「全然悪いと思ってなさそうですけどね」
腰を上げた吉永を玄関まで送ろうとする十影を右手で制して、その瞳が眞秀と縁日に向く。
「それじゃあ、縁日くん、眞秀くん」
初めてその眼鏡の奥に、吉永の感情が見えた気がした。
「またお会いできたら嬉しいです。今度はもっと、別の形で」
思わず縁日は眞秀を見た。
眞秀もまた、縁日を見ていた。
吹き出して、笑い合う。
部屋中の金木犀の香りが、一瞬、何かの香りに負けて消えた。
十影が淹れたスミレの花弁が浮かぶ紅茶に一頻り騒いだ後、ひどく穏やかな口調で吉永はそう切り出した。
伺うようにちらりと動いたその視線を追うと、ソファの肘掛に浅く腰掛けた眞秀の横顔があった。
潤いで満ちた色素の薄い瞳が、ぼんやりと窓の外を見ている。
興味があるのかないのか、それとも聞くことが怖いのか。
感情をうまく表現出来ないその表情に小さく笑って、吉永は何故か縁日を見た。
「浄見 友親を逮捕しました」
「っ!」
単刀直入に切り出された一言に、息を呑んだのは縁日だけだった。
穏やかなようでいて張り詰めている空気に、それでも吉永は容赦無く針を落としていく。
「罪状は、研究費と偽り不正に金を受け取っていたとする詐欺罪です。---表向きは、ですが」
組んでいた足を組み替えて、吉永は静かにそう言った。
「本当の罪状は花酔い関係ということですか」
「詐欺も嘘じゃないよ、夕凪。ただ……まぁ、そうだね。花酔いに関しては公にしていないこと、できないことが多すぎる。彼の余罪の殆どは花酔いに関することだからね。公表するかしないかで揉めているんだよ」
長い指がカップの縁をなぞる。
言葉を選ぶように吉永は続けた。
「ただこれはもう、我々警察だけの話じゃないね。主体になって決めていくのは政府だ。おそらく後何年かで花酔いに関する法律や制度が変わっていく。それが……良いことかそうじゃないかは僕には分からないけれど」
眞秀は変わらず窓の外を見ていた。
雨上がりの光に透ける綺麗な髪が、その表情も、感情も、隠している。
「今回の浄見の逮捕が、良くも悪くもきっかけになることは間違いないと僕は思う。ただ彼の処遇については……少し意見が割れている」
「割れる?」
「刑の重さを巡ってね。浄見は、花酔いの花弁に含まれる麻薬物質を利用して、まったく新しいドラッグを造っていた。どんな検査にも引っかからず、それでいて大麻や阿片にも勝る強烈な快楽を得られる新型のセックスドラッグ」
そこで吉永は言葉を止め、また眞秀を見た。
ゆっくりとその横顔がこちらを向く。
静かに、それでいて強い眼差しが、今度はしっかりと吉永を見据えた。
何も言わなかった。
けれど、吉永は小さく頷いてゆっくりと口を開く。
「花酔いの花弁は、その体液によって効果の強さが変わるのは知っていると思うけれど、全ての花弁をひとつにして、均一な濃度のドラッグにすることは、どうやらそんなに難しいことではなかったようだね。けれど浄見はあえてそうしなかった」
「あ?」
「あえて粗悪品を作ったんだ。グレードをつけたと言ったほうがいいかな。格安なものから、とても一般市民じゃ手の届かないような価格のものまで」
「それだけ儲ける幅を作ったってことか」
「そう。それともうひとつ。浄見には算段があった」
「算段?」
「ドラッグにも、花弁と同じような副作用が残ってしまった。得られるのは快楽か死。ふたつにひとつ。グレードが高ければ高いほど、副作用が出る確率は低くなるけれど……それでも0にはならない。どうやら副作用は体質によるところが大きいみたいだからね。だから浄見は、造ったんだ」
吉永はそう言って、スーツの内ポケットからアルミのケースを取り出した。
蓋を開いて、テーブルの上に置く。
中には桜色に光る液体の入ったアンプルがひとつだけ収まっていた。
「これは?」
「血清だよ」
「なっ!?」
「どんなに都合がいいドラッグでも、死んでしまうかもしれないなんて話にならないからね。血清を造り、ドラッグと一緒に売った。グレードが低くでも、ドラッグは売れた」
「完成……してたのか」
呟くようにそう言って、十影は頭を抱えた。
テーブルの上で、アンプルの桜色が妖しく光っている。
「どうして……」
「うん?」
「それでどうして、刑を軽くしようという意見が出るんでしょうか」
少しだけ困ったように、眼鏡の奥の瞳は縁日を見た。
「刑を軽くしよう、というより化学の……医学の功績でもあるんだよ、彼の行っていた研究は---そしてその結果は」
「………」
「僕も正直そう思う。だからと言って、彼がしたことが許されるとは思わないし、刑を軽くしたほうがいいとは到底思えない。ごく一部の意見だよ」
「それでも……っ」
辛い思いを、苦しい思いをした花酔いがたくさんいて
傷ついて、傷つけられて、踏みにじられた人が、たくさんいて
それなのに---
「先輩」
十影が、静かな声でそう吉永を呼んだ。
「浄見の功績というのは、血清を作ったことですか?それとも」
「そうだよ、夕凪」
十影の言わんとしていることを察して、吉永が小さく頷く。
「血清の研究途中で、副産物としてできたもの---」
吉永はテーブルの上のケースに手を伸ばした。
アンプルの収められている台の底を、ゆっくりと持ち上げる。
「っ!」
何の変哲もない、白いカプセル。
風邪薬となんら変わらないそれに、十影だけが息を飲んだ。
「こ…れは……ま、さか」
「そう、薬だよ。花酔いのね」
「っ!」
浅く息を吐きながら、吉永はゆっくりとケースの蓋を閉じ、内ポケットにしまった。
「完成品ではないし、正しくは治療薬ではないそうだよ。治癒ではなく、あくまで花酔いの症状を緩和させる程度のものらしい。浄見にとっては、これより血清の研究のほうが大事だったようだね。偶然造り出した以降、これを研究した形跡はなかったよ」
「クソ……!」
「ただまぁ、情報は国の研究機関にそのまま譲渡される。これが完成する日も、そう遠くはないのかもしれない。そう考えると、この胸糞悪い状況も少しはマシに思えるね」
冷めた紅茶を飲みながら、吉永は口の端を小さく吊り上げた。
「ねぇ」
その声に、吉永の視線が上がる。
縁日の頭上で止まったその視線を追うと、無表情のままの眞秀が立っていた。
「さっきの人、俺に用事がある感じだったけど。話ってこれじゃないよね?」
「……まったく。本当に使えない部下を持ったようです。僕は」
溜息を隠しもせず、吉永は苦々しげに笑いながらカップをソーサーの上に戻した。
「正直に言うと、今し方お伝えした話は僕にはあまり関係ありません。ドラッグも、研究費の不正受け渡しも、動くのは他の班であって僕じゃない」
長い指が眼鏡を押し上げる。一瞬だけ見えた瞳が、真っ直ぐに縁日を見ていた。
「お話を伺いたかったのは、眞秀くんというより貴方ですよ。縁日くん」
「僕?」
「花酔いの花弁を量産する為、身寄りのない孤児を買取り、花酔いに故意に感染させ、結果、その全員を死に至らしめた。過失致死---いや、僕たち公安は、浄見 友親を殺人罪で立件しようとしています」
「っ!」
「殺意はなかったと弁護されても、人数が人数です。おそらく彼は二度と、外の世界には出られないでしょう」
安堵と、憤りと、そして何故か、少しの焦燥。
自分の中に渦巻く感情をうまく処理できずに、縁日は小さく息を吐いた。
後ろで、微かに息が乱れた眞秀の気配がした。
「本当……だったんですね。売られた孤児みんな、死んだって」
「感染の仕方も、花弁を採るために強要されていた行為も良くなかったようですね。浄見の元へ行ってから、長く持った子で、1年」
「っ……!」
引き攣った眞秀の声に息も吐けなかった。
霞んだ記憶に、真っ白なダチュラがやけに鮮明に浮かんでいた。
きっと、あの日の記憶はこの先も消えない。
消してしまっては、いけないのだろうと思う。
自分だって、あの修道院の孤児であることに変わりはないんだから。
眞秀を見る。
アクアマリン色の瞳が、水面のように揺れていた。
その中に映った自分が、不器用に笑う。
眞秀もつられて、困ったように笑った。
「吉永さん」
「はい」
「僕は、修道院の孤児が一定期間でどこかへ行ってしまうことしか知りませんでした。どこへ行ったのかも、どうしていなくなったのかも分からなかった。浄見の存在を知ったのも、この家に来てからです。警察の役に立つような情報を、僕は持っていません」
「そうですか……」
さして残念がることもなく、吉永はまたその目を細めた。
「分かりました。ご協力、感謝いたします」
「いえ、お役に立なくて……すいません」
「いえいえ、とんでもない。こちらこそ急に押しかけて申し訳ありませんでした」
吉永はそう言って、深々と頭を下げた。
「先輩」
「うん?」
「治療薬の研究を進める為に司法取引……なんてことには?」
「あぁ、その心配もどうやらないようだよ」
どこか少し楽しそうに吉永は十影に向き直った。
先輩と呼ばれたことが嬉しかったのかもしれない。
「今まで花酔いの研究がなかなか進まずにいたのは、単純にサンプルとデータの不足によるところが大きいんだと思うよ。未だに花酔いが空想上の奇病だと信じている学者も多い。僕だって、今日 彼に会うまでは花酔いに会ったことはなかったからね。殆どの人は、一生のうちに花酔いに出会うことすらないのかもしれない。それは純粋に花酔いが世間に紛れて生活できないその性質によるのだろうね。その花酔いの花弁を浄見は手に入れることができた。彼が花酔いの研究を進めることができた理由は、ただそのひとつだけなんだよ。……もしそうでないとしても、彼はもう、花酔いに関わってはいけない」
この国も、警察も、そこまで馬鹿ではないよ。と本気とも冗談ともとれる口調でそう言って、
吉永は眞秀を見上げた。
「浄見の一番の被害者は貴方です、眞秀くん。被害者として、親族として、そして花酔いとして……
貴方が矢面に立たされることもこの先、少なくないと思います。無論、僕も尽力はしていくつもりですが……」
小さく首を横に振って、吉永の言葉を遮ると
眞秀は微かに眉尻を下げて笑った。
「だいじょうぶ」
まるで自分に言い聞かせるように
子どものような発音で、それでもはっきり眞秀は言った。
「俺はひとりじゃないから」
カーテンが、ぶわりと風を含んで膨らんだ。
部屋に微かに残る夏の熱を、秋の風が攫っていく。
部屋に残された金木犀の残り香が、縁日の鼻先を擽った。
「無気力で、無愛想で堅物で」
にっこりと満面の笑みを浮かべた吉永が、急にそう口を開いた。
「何を考えているのか一向に分からない後輩が、あれだけ溺愛していたお二人に会えてよかった」
「せっ…んぱい…!」
「無気力……」
「溺愛……」
眞秀と縁日の視線から逃げるように顔をそらした十影の耳が微かに赤い。
「隠し子がいるって噂されてたの、夕凪知らないでしょ」
「知ってますよ!そもそもその噂流したの先輩でしょうに!」
「違うよ。僕はただ、子を守る親熊みたいだよねって言っただけだよ」
「確信犯じゃないですか……!」
はははと笑って、吉永はちらりと腕時計を見た。
「あぁ、暗いと思ったらもうこんな時間ですね。いやはや長居してしまって申し訳ありません」
「先輩……さっきの人、待たせっぱなしじゃないですか?」
「うん。さすがに悪いと思うし、そろそろ失礼するよ」
「全然悪いと思ってなさそうですけどね」
腰を上げた吉永を玄関まで送ろうとする十影を右手で制して、その瞳が眞秀と縁日に向く。
「それじゃあ、縁日くん、眞秀くん」
初めてその眼鏡の奥に、吉永の感情が見えた気がした。
「またお会いできたら嬉しいです。今度はもっと、別の形で」
思わず縁日は眞秀を見た。
眞秀もまた、縁日を見ていた。
吹き出して、笑い合う。
部屋中の金木犀の香りが、一瞬、何かの香りに負けて消えた。