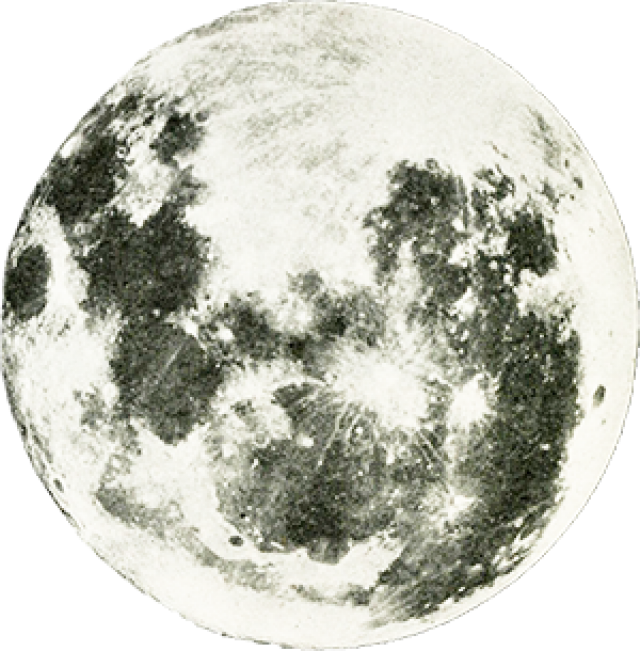-24-陽炎
文字数 2,568文字
熱に浮かされたようにぼんやりとしている記憶の中にあるのは、太陽の陽に焼かれて揺れる、どこまでも続くアスファルトの一本道と
痛々しいまでに青く輝く空を、覆いつくさんばかりの黄色い向日葵の群れ。
その花のどれもがまるで部外者を排除しようとしているかのように全て縁日を向いていた。
それが、怖かったのは覚えている。
このままこの花達に呑み込まれて消えてしまいそうで。
それでもどこか、あるはずもないそんなことを心の奥で望んでいた自分も、怖かった。
死にたかったのだ。
自覚はしていなかったけれど。
徹底的に無を装っていたつもりでいて、こうやってどこだか分からない場所に逃げ出してきてしまうほどに。
死にたくて、消えたくて、でもそれが叶わないことも知っているから、こうやって逃げ出した。
いつか誰かに見つかってしまうという焦燥感は裏を返せば確かな安心感でもあった。
だからそれまで。見つかってしまうまでの間だけは、ただ一人になりなかった。
旧式のバスに揺られて1時間。
街を抜け、田舎を超え、山を越えて現れた一本道に、縁日はそっと息を吐いた。
あの日、壊れて調整の出来なくなったバスの効き過ぎた冷房は、今はもう止まっている。
必要がないからだ。
窓から注ぐ太陽は幾分柔らかいし、空もほんの少しだけ白が混じっている。
ただ、ところどころ破れてスポンジが剥き出しになった座席の質感と、縁日以外誰もいない乗客は、あの日と同じだった。
アナウンスもなしにバスが止まる。
バス停の名前を憶えていたわけではないけれど、縁日は無意識に立ち上がってバスを降りた。
靴底が地面と擦れる感触。
身体に纏っていた車内の空気が、風に一掃されて消えた。
背後でバスが発車した。
空気を吸い込む。
あの日は咽返りそうだった熱気は、今はもうない。
代わりにほんの少しだけ埃っぽい土の香りがした。
アスファルトの一本道。
その両脇に、どこまでも広がる向日葵の群生。
さすがに山吹色とまではいかないけれど、かろうじてまだその花を保っている。
「低……」
自分の身長が伸びたからか、それとも花の盛りが過ぎたからか、昔よりも幾分低く感じる向日葵の中を歩いていく。
あの日、不安と緊張と高揚に入り混じって忙しなかった心臓は今は酷く穏やかに脈打っている。
不思議な感情だった。きっとこれが“懐かしい”なんて言われるものなんだろう。
たった一度訪れただけのこの場所を、そんな風に思えるのが少しおかしかった。
死んでるように生きていた、あの日々が全て現実だと言われているようで。
それは絶望であるはずなのに、今はそれが少し嬉しい。
たった一人だ。
たった一人。
ただそれだけの存在が、変えられないはずの過去ですら変えてしまった。
たった一人。
自分も、誰かにとってそんな存在になっているのだろうか。
自分のせいで、あの人はおかしくなってしまった。
自分が逃げたから、あの人は変わってしまった。
―――その背中にある傷は、奴の欲望の証だよ
だからこの傷は、
「違う……」
背中に残るこの羽根の痕は、
「これは」
―――ただの罰だ。
「だからもう逃げないって決めたんだ」
父さん、と呼んだ先に酷くやつれたその人の姿があった。
縁日を捉えて見開いた瞳が、ゆっくりと困ったように笑う。その目尻にだけ、昔の面影があった。
「……もう、そんなふうには呼んでもらえないと思ってたよ」
「うん。でも、僕の父さんは父さんだけだから」
戸惑うように瞳が揺れた。
その瞳がゆっくりと、縁日を見上げる。
「大きくなったなあ」
「十影みたいにはなれなかったけどね」
「はは、十影なぁ。あいつは……」
怒っているだろうなあ、とどこか他人事のようにそう言って、その人は―――空を見上げた。
「最初のうちはよく怒鳴りに来ていたが、裁判が終わってからは一度も来なかった」
「僕の分まで怒ってくれてたんだよ、十影は」
自分を捨てた本当の父親に出来なかったようにまた、この人のことも怒ることが出来なかった。
怒る、という感情すらよく分かっていなかったからかもしれない。
だからいつも十影は、縁日の代わりに怒ってくれた。悲しんで、苦しんで、悩んで、そしてたぶん、泣いてくれていた。
「僕は、僕が100%被害者だとは思ってない。こんなこと言ったらそれこそ十影に怒られそうだけど、僕は、きっと貴方を心から憎めない」
「縁日……」
「はは、父さんが僕をそうやって呼ぶのも久しぶりだね」
正真正銘の、懐かしさがじんわりと身体の中心に広がった。ほんの少しの歯痒さと一緒に。
「本当は、憎まないといけないんだと思う。貴方のしたことを、肯定しちゃ駄目だと思うから。憎まなきゃ。恨まなきゃって、ずっと思ってた。だけどやっぱり、僕にそれは難しいから」
なにかにつけて付きまとうその人の感触を、声を、音を、消すことが出来ないのならばいっそ、憎んでしまえと、何度そう思ったか分からない。
けれど出来なかった。
恨めるほど、憎めるほど、嫌いにはなれなかった。
「だから、これが最後だよ。父さん」
見渡す限りの向日葵畑に、縁日の声だけが静かに響いた。
「僕が貴方を父さんと呼ぶのも、貴方が僕の名前を呼ぶのも。あの日のことを思い出すのも、ぜんぶ、最後」
消せない過去なら、全て置いていってしまおう。
憎めないなら、全て、失くしてしまおう。
「そう、か……うん、そうだな…」
そう小さく呟いたあと、その人は真っ直ぐに縁日を見つめた。
「縁日……」
「うん」
「すまなかった……―――」
そう言って頭を下げたその人に小さく笑って、縁日は空を見上げた。
もうすっかり秋色をした空に、季節外れの入道雲があった。
もしかしたら夕立ちでもくるのかもしれない。
洗濯物を取り込まなくちゃ。
今日の夕ご飯はなににしよう。
何も言わずに出てきてしまったけれど、彼は大丈夫だろうか。
はやく帰りたい。帰らなくちゃいけない。
「あのね、父さん」
もう、帰る場所がないわけじゃないんだから。
「僕、好きな人ができたよ」
痛々しいまでに青く輝く空を、覆いつくさんばかりの黄色い向日葵の群れ。
その花のどれもがまるで部外者を排除しようとしているかのように全て縁日を向いていた。
それが、怖かったのは覚えている。
このままこの花達に呑み込まれて消えてしまいそうで。
それでもどこか、あるはずもないそんなことを心の奥で望んでいた自分も、怖かった。
死にたかったのだ。
自覚はしていなかったけれど。
徹底的に無を装っていたつもりでいて、こうやってどこだか分からない場所に逃げ出してきてしまうほどに。
死にたくて、消えたくて、でもそれが叶わないことも知っているから、こうやって逃げ出した。
いつか誰かに見つかってしまうという焦燥感は裏を返せば確かな安心感でもあった。
だからそれまで。見つかってしまうまでの間だけは、ただ一人になりなかった。
旧式のバスに揺られて1時間。
街を抜け、田舎を超え、山を越えて現れた一本道に、縁日はそっと息を吐いた。
あの日、壊れて調整の出来なくなったバスの効き過ぎた冷房は、今はもう止まっている。
必要がないからだ。
窓から注ぐ太陽は幾分柔らかいし、空もほんの少しだけ白が混じっている。
ただ、ところどころ破れてスポンジが剥き出しになった座席の質感と、縁日以外誰もいない乗客は、あの日と同じだった。
アナウンスもなしにバスが止まる。
バス停の名前を憶えていたわけではないけれど、縁日は無意識に立ち上がってバスを降りた。
靴底が地面と擦れる感触。
身体に纏っていた車内の空気が、風に一掃されて消えた。
背後でバスが発車した。
空気を吸い込む。
あの日は咽返りそうだった熱気は、今はもうない。
代わりにほんの少しだけ埃っぽい土の香りがした。
アスファルトの一本道。
その両脇に、どこまでも広がる向日葵の群生。
さすがに山吹色とまではいかないけれど、かろうじてまだその花を保っている。
「低……」
自分の身長が伸びたからか、それとも花の盛りが過ぎたからか、昔よりも幾分低く感じる向日葵の中を歩いていく。
あの日、不安と緊張と高揚に入り混じって忙しなかった心臓は今は酷く穏やかに脈打っている。
不思議な感情だった。きっとこれが“懐かしい”なんて言われるものなんだろう。
たった一度訪れただけのこの場所を、そんな風に思えるのが少しおかしかった。
死んでるように生きていた、あの日々が全て現実だと言われているようで。
それは絶望であるはずなのに、今はそれが少し嬉しい。
たった一人だ。
たった一人。
ただそれだけの存在が、変えられないはずの過去ですら変えてしまった。
たった一人。
自分も、誰かにとってそんな存在になっているのだろうか。
自分のせいで、あの人はおかしくなってしまった。
自分が逃げたから、あの人は変わってしまった。
―――その背中にある傷は、奴の欲望の証だよ
だからこの傷は、
「違う……」
背中に残るこの羽根の痕は、
「これは」
―――ただの罰だ。
「だからもう逃げないって決めたんだ」
父さん、と呼んだ先に酷くやつれたその人の姿があった。
縁日を捉えて見開いた瞳が、ゆっくりと困ったように笑う。その目尻にだけ、昔の面影があった。
「……もう、そんなふうには呼んでもらえないと思ってたよ」
「うん。でも、僕の父さんは父さんだけだから」
戸惑うように瞳が揺れた。
その瞳がゆっくりと、縁日を見上げる。
「大きくなったなあ」
「十影みたいにはなれなかったけどね」
「はは、十影なぁ。あいつは……」
怒っているだろうなあ、とどこか他人事のようにそう言って、その人は―――空を見上げた。
「最初のうちはよく怒鳴りに来ていたが、裁判が終わってからは一度も来なかった」
「僕の分まで怒ってくれてたんだよ、十影は」
自分を捨てた本当の父親に出来なかったようにまた、この人のことも怒ることが出来なかった。
怒る、という感情すらよく分かっていなかったからかもしれない。
だからいつも十影は、縁日の代わりに怒ってくれた。悲しんで、苦しんで、悩んで、そしてたぶん、泣いてくれていた。
「僕は、僕が100%被害者だとは思ってない。こんなこと言ったらそれこそ十影に怒られそうだけど、僕は、きっと貴方を心から憎めない」
「縁日……」
「はは、父さんが僕をそうやって呼ぶのも久しぶりだね」
正真正銘の、懐かしさがじんわりと身体の中心に広がった。ほんの少しの歯痒さと一緒に。
「本当は、憎まないといけないんだと思う。貴方のしたことを、肯定しちゃ駄目だと思うから。憎まなきゃ。恨まなきゃって、ずっと思ってた。だけどやっぱり、僕にそれは難しいから」
なにかにつけて付きまとうその人の感触を、声を、音を、消すことが出来ないのならばいっそ、憎んでしまえと、何度そう思ったか分からない。
けれど出来なかった。
恨めるほど、憎めるほど、嫌いにはなれなかった。
「だから、これが最後だよ。父さん」
見渡す限りの向日葵畑に、縁日の声だけが静かに響いた。
「僕が貴方を父さんと呼ぶのも、貴方が僕の名前を呼ぶのも。あの日のことを思い出すのも、ぜんぶ、最後」
消せない過去なら、全て置いていってしまおう。
憎めないなら、全て、失くしてしまおう。
「そう、か……うん、そうだな…」
そう小さく呟いたあと、その人は真っ直ぐに縁日を見つめた。
「縁日……」
「うん」
「すまなかった……―――」
そう言って頭を下げたその人に小さく笑って、縁日は空を見上げた。
もうすっかり秋色をした空に、季節外れの入道雲があった。
もしかしたら夕立ちでもくるのかもしれない。
洗濯物を取り込まなくちゃ。
今日の夕ご飯はなににしよう。
何も言わずに出てきてしまったけれど、彼は大丈夫だろうか。
はやく帰りたい。帰らなくちゃいけない。
「あのね、父さん」
もう、帰る場所がないわけじゃないんだから。
「僕、好きな人ができたよ」