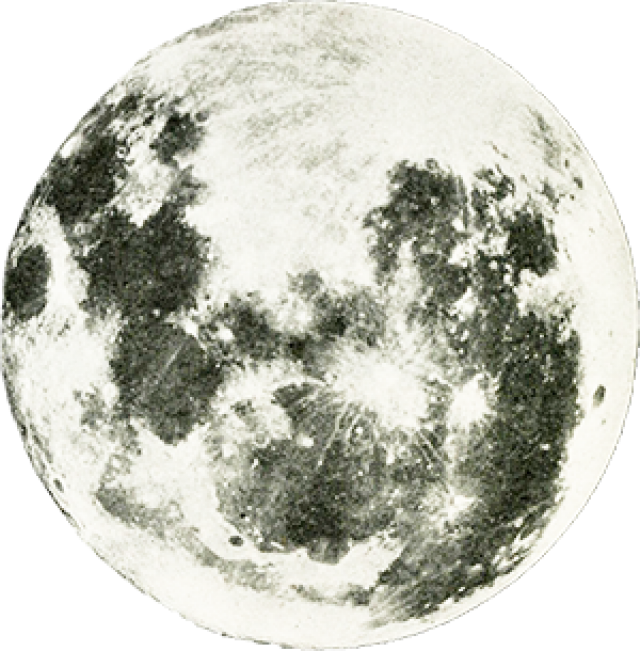-22-月光
文字数 2,557文字
カーテンを開け放した窓から注ぐ仄青い月の光が、シーツの上で揺れていた。
そこに散る無数の真っ白な花弁。
若干の湿り気を帯びたその花弁は、パウダリーな花酔いの花弁ではなく、本物の銀木犀の花粒だった。
金木犀ほど強烈でも、甘ったるくもない、ほんの少しジャスミンにも似た香りが、僕の部屋と、この空間に充満していた。
肩甲骨にそうように背中をなぞるその擽ったさに僕は小さく身じろいで後ろを振り向く。
それでもマホロの瞳は、僕の背中の傷に注がれたまま動かなかった。
「羽根の痕みたい」
そう言った、マホロの視線を遮るように僕はベッドに横になった。
マットが弾んで銀木犀の花粒が宙を舞う。
「そうだよ」
「そうって?」
「僕は堕天使だから。羽根を捥がれたの。神様のところに帰れないように」
「なにそれ―――……え、冗談でしょ?」
「んーん、本当。残念なことに―――半分は」
溜息を吐くついでにそう言って、それから僕はマホロを抱きしめる代わりに深く息を吸った。
甘い香りを肺いっぱいに詰め込めば、全てどうでもよくなるような気がした。
「それが、あの人が握ってる僕の弱み。それから、十影が僕に過保護な理由」
「……痛い?」
「まさか。もう何年も前の傷だし。これ以上癒えることはないかもしれないけど、抉れることも絶対ないから」
シーツの上。月光を受けて輝く白い足が泳ぐように動いて、緩やかな波を作る。
零れる銀木犀の花粒。溢れ出すじれったい香り。
微かな水音がして、こほっと空気が揺れた。
シーツの上。銀木犀の上に、桃色の花弁が落ちる。
「目、痛くない?」
「濡れないから。腫れたりしないよ」
どんなに泣いても―――と、マホロはまたその瞳から花弁を零した。
頬を滑る、その花弁をシーツへ払うと擽ったそうにマホロは身じろいだ。
「それ一枚に、どれだけの価値があると思う?」
「少なくとも、その質問よりはあるかな」
「あはは、ごめん。冗談だよ」
小さく笑いながら、マホロは僕の前髪の先に触れた。
その影になって、表情が隠れる。
短く息を吸ったマホロの咽喉が、小さく震えた。
「マホロ?」
「……俺、の」
そう吐き出した言葉は、可笑しいくらいに震えていた。
シーツごと、僕の前髪に触れるその小さな手のひらを握り込む。
一度強く息を吸い込んだマホロは、ゆっくりと細くその息を吐いた。
「俺の、母親は……普通の人間だったんだ」
「……うん」
「ある時期に突然、花酔いに感染したって聞いた。どうやって感染したのかはまぁ分かるけど母さんは……誰から感染したのかを、絶対に誰にも言わなかった」
唇の端で、何故かマホロは小さく笑った。
「一時期、憎んでたことがあるんだ。母さんのこと。花酔いになんて感染するから、こんなところに死ぬまでずっと閉じ込められて、好きでもない男と望まれてもいない子どもを作る羽目になるんだって。俺なんて生まれてこなくても済んだのに、自分が死ぬことだってなかったのにって」
もう半分泣いているような声で、マホロは笑う。
けれどその瞳は真っ直ぐに僕を捉えて、「でも」と柔らかく滲んだ。
「少し前に、書庫の本の中にシークレットボックスを見つけたんだ。―――たくさんの手紙が入ってた」
「手紙?」
「ラブレター。恥ずかしすぎて、1枚も読めなかったけど。シェイクスピアかと思うくらい熱烈な、母さんと父さんの」
「父さんって……」
「本当のだよ。俺の父さん」
シーツの上を、マホロの指が滑る。
無数の銀木犀の粒を攫って、波のような線を描く。
「偶然か、それともあの男に少しでも良心があったのかは分からないけど、でも―――母さんが感染したのと、俺の父親は同じ花酔いだってこと」
「そ、れ……」
「ずっと、自分は花酔いとして利用される為だけに生まれてきたんだと思ってた。あの男に使われる為だけに母さんは好きでもない花酔いとの間に俺を作らされたんだって。そう……思ってたのに」
その瞳から、花弁が溢れ出す。
「ちゃんと、愛されて生まれてきてた」
「……しかも、自分が花酔いになってもいいって思えるくらい、大事な人と」
「ん……」
それがどんな思いなのか、今の僕には痛いくらいに分かった。
苦しいくらいに幸せで、それでいて決して甘いだけではないその想いを。
「それでもマホロは、僕に花酔いになって欲しくない?」
「さっきも言ったでしょ。縁日の特別でいたいんだよ、俺は」
マホロがぐっと自分の鼻先を僕の鼻先に近付けた。
触れてしまいそうな距離で、ふっと僕の唇に息を吹きかける。
まるで、キスをする代わりみたいに。
「それに縁日は、花酔いになれないよ」
「どうして?」
「俺の花弁舐めて倒れたの、忘れちゃったの?」
「あ……」
さっきあれだけ落ち込んだばかりなのに、すっかり失念していた。
呆れたようにマホロも笑う。
「縁日は花酔いになれないし、俺は縁日と同じにはなれない」
ぼふりとシーツに頬を沈めたマホロの瞳は、それでもどこか満たされたようにゆっくりと瞬きを繰り返した。
「でも、それでいいんだ」
「マホロ……」
「花酔いになってもいいって縁日が思ってくれたから。それだけでいい」
シーツに包まれた、その胸元に唇を寄せる。
体温ごと少しずつ伝わってくる匂い。
ほんの少し戸惑うような指先が、僕の髪に触れた。
「このまま世界が終わればいいのに」
「シェイクスピアみたいだね、縁日」
「これは悲劇なんかじゃないよ、眞秀」
僕の髪を遠慮がちに抱き込んでいるその身体を、シーツごと反転させた。
押し倒されてシーツに散った柔らかな月白色の髪に隠されていた真っ白な頬が、桃の果実のようにじれったく染まっている。
脆い鉱石で水を閉じ込めたような2つのアクアマリンが、どこか期待するように僕を見上げて揺れていた。
薄い布越しに触れ合う熱が、甘い香りが増すごとにその温度を上げていく。
「好きだよ、眞秀」
「えん、にち……っ」
愚図るように僕を呼ぶ、その唇にキスしてしまわないように、僕は小さく息を止めてその熱を求めた。
そこに散る無数の真っ白な花弁。
若干の湿り気を帯びたその花弁は、パウダリーな花酔いの花弁ではなく、本物の銀木犀の花粒だった。
金木犀ほど強烈でも、甘ったるくもない、ほんの少しジャスミンにも似た香りが、僕の部屋と、この空間に充満していた。
肩甲骨にそうように背中をなぞるその擽ったさに僕は小さく身じろいで後ろを振り向く。
それでもマホロの瞳は、僕の背中の傷に注がれたまま動かなかった。
「羽根の痕みたい」
そう言った、マホロの視線を遮るように僕はベッドに横になった。
マットが弾んで銀木犀の花粒が宙を舞う。
「そうだよ」
「そうって?」
「僕は堕天使だから。羽根を捥がれたの。神様のところに帰れないように」
「なにそれ―――……え、冗談でしょ?」
「んーん、本当。残念なことに―――半分は」
溜息を吐くついでにそう言って、それから僕はマホロを抱きしめる代わりに深く息を吸った。
甘い香りを肺いっぱいに詰め込めば、全てどうでもよくなるような気がした。
「それが、あの人が握ってる僕の弱み。それから、十影が僕に過保護な理由」
「……痛い?」
「まさか。もう何年も前の傷だし。これ以上癒えることはないかもしれないけど、抉れることも絶対ないから」
シーツの上。月光を受けて輝く白い足が泳ぐように動いて、緩やかな波を作る。
零れる銀木犀の花粒。溢れ出すじれったい香り。
微かな水音がして、こほっと空気が揺れた。
シーツの上。銀木犀の上に、桃色の花弁が落ちる。
「目、痛くない?」
「濡れないから。腫れたりしないよ」
どんなに泣いても―――と、マホロはまたその瞳から花弁を零した。
頬を滑る、その花弁をシーツへ払うと擽ったそうにマホロは身じろいだ。
「それ一枚に、どれだけの価値があると思う?」
「少なくとも、その質問よりはあるかな」
「あはは、ごめん。冗談だよ」
小さく笑いながら、マホロは僕の前髪の先に触れた。
その影になって、表情が隠れる。
短く息を吸ったマホロの咽喉が、小さく震えた。
「マホロ?」
「……俺、の」
そう吐き出した言葉は、可笑しいくらいに震えていた。
シーツごと、僕の前髪に触れるその小さな手のひらを握り込む。
一度強く息を吸い込んだマホロは、ゆっくりと細くその息を吐いた。
「俺の、母親は……普通の人間だったんだ」
「……うん」
「ある時期に突然、花酔いに感染したって聞いた。どうやって感染したのかはまぁ分かるけど母さんは……誰から感染したのかを、絶対に誰にも言わなかった」
唇の端で、何故かマホロは小さく笑った。
「一時期、憎んでたことがあるんだ。母さんのこと。花酔いになんて感染するから、こんなところに死ぬまでずっと閉じ込められて、好きでもない男と望まれてもいない子どもを作る羽目になるんだって。俺なんて生まれてこなくても済んだのに、自分が死ぬことだってなかったのにって」
もう半分泣いているような声で、マホロは笑う。
けれどその瞳は真っ直ぐに僕を捉えて、「でも」と柔らかく滲んだ。
「少し前に、書庫の本の中にシークレットボックスを見つけたんだ。―――たくさんの手紙が入ってた」
「手紙?」
「ラブレター。恥ずかしすぎて、1枚も読めなかったけど。シェイクスピアかと思うくらい熱烈な、母さんと父さんの」
「父さんって……」
「本当のだよ。俺の父さん」
シーツの上を、マホロの指が滑る。
無数の銀木犀の粒を攫って、波のような線を描く。
「偶然か、それともあの男に少しでも良心があったのかは分からないけど、でも―――母さんが感染したのと、俺の父親は同じ花酔いだってこと」
「そ、れ……」
「ずっと、自分は花酔いとして利用される為だけに生まれてきたんだと思ってた。あの男に使われる為だけに母さんは好きでもない花酔いとの間に俺を作らされたんだって。そう……思ってたのに」
その瞳から、花弁が溢れ出す。
「ちゃんと、愛されて生まれてきてた」
「……しかも、自分が花酔いになってもいいって思えるくらい、大事な人と」
「ん……」
それがどんな思いなのか、今の僕には痛いくらいに分かった。
苦しいくらいに幸せで、それでいて決して甘いだけではないその想いを。
「それでもマホロは、僕に花酔いになって欲しくない?」
「さっきも言ったでしょ。縁日の特別でいたいんだよ、俺は」
マホロがぐっと自分の鼻先を僕の鼻先に近付けた。
触れてしまいそうな距離で、ふっと僕の唇に息を吹きかける。
まるで、キスをする代わりみたいに。
「それに縁日は、花酔いになれないよ」
「どうして?」
「俺の花弁舐めて倒れたの、忘れちゃったの?」
「あ……」
さっきあれだけ落ち込んだばかりなのに、すっかり失念していた。
呆れたようにマホロも笑う。
「縁日は花酔いになれないし、俺は縁日と同じにはなれない」
ぼふりとシーツに頬を沈めたマホロの瞳は、それでもどこか満たされたようにゆっくりと瞬きを繰り返した。
「でも、それでいいんだ」
「マホロ……」
「花酔いになってもいいって縁日が思ってくれたから。それだけでいい」
シーツに包まれた、その胸元に唇を寄せる。
体温ごと少しずつ伝わってくる匂い。
ほんの少し戸惑うような指先が、僕の髪に触れた。
「このまま世界が終わればいいのに」
「シェイクスピアみたいだね、縁日」
「これは悲劇なんかじゃないよ、眞秀」
僕の髪を遠慮がちに抱き込んでいるその身体を、シーツごと反転させた。
押し倒されてシーツに散った柔らかな月白色の髪に隠されていた真っ白な頬が、桃の果実のようにじれったく染まっている。
脆い鉱石で水を閉じ込めたような2つのアクアマリンが、どこか期待するように僕を見上げて揺れていた。
薄い布越しに触れ合う熱が、甘い香りが増すごとにその温度を上げていく。
「好きだよ、眞秀」
「えん、にち……っ」
愚図るように僕を呼ぶ、その唇にキスしてしまわないように、僕は小さく息を止めてその熱を求めた。