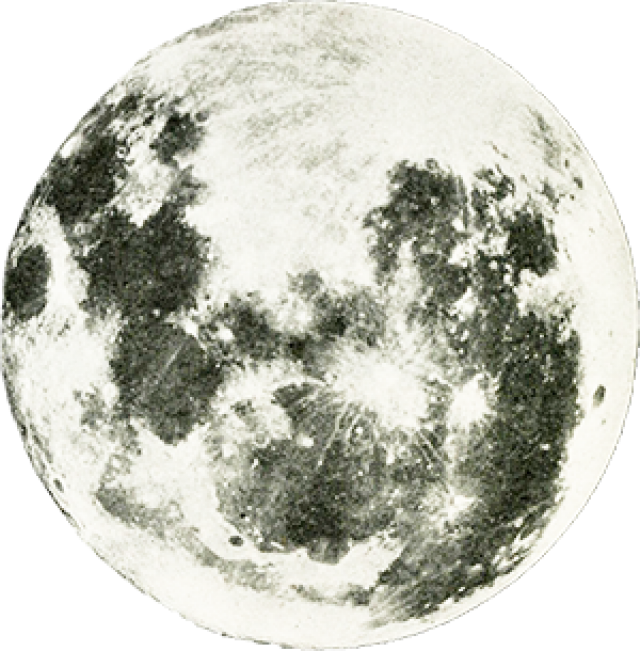-4-体液 (2)
文字数 8,105文字
僕には親がいなかった。
飛行機事故で両親が死んだとか、何か凶悪犯罪に巻き込まれて死んだとか、そういうんじゃない。
ただ純粋に、端的に。
生まれて間もなかった僕は、町の外れにある小さな修道院に捨てられたのだ。
それが母親だったのか、父親だったのか、はたまた両親だったのかは分からない。
とにかく僕は捨てられて、孤児になった。
土砂降りの、凍えるような冬の日だったらしい。
タオルケット一枚に包まれて捨てられていた僕を拾ったのが、この修道院の神父で、十影の叔父にあたる人だった。
この十影の叔父という人を、実を言うと僕はよく覚えていない。
何不自由ない暮らしをさせてもらってきておいて、あまりに薄情だとは思うけれど。
背の高い、黒い服を着た男の人―――精々それくらいの記憶しかない。
そもそも、子どもの僕からしたら大体の大人は背が高かったし
修道院に居る人はみんな黒い服を着ていたから、この記憶がその叔父さんのものかどうかは分からないけれど。
黒い服を着た背の高い男―――その認識を“十影”に塗り替えたのは僕が13歳の時だった。
流石に学校に行かせてはもらえなかった僕の教育係として、当時大学生だった十影が修道院にやってくるようになった時だ。
歴史や漢字、外国語や計算式……十影が教えてくれる色々なもの、その全てが新しく刺激的で、恐らく僕はこの歳ではじめて「面白い」という感情を知った。
喜怒哀楽、その他諸々の感情を見事に理解していなかった僕にとって、十影は先生であり、親であり、友達のような存在だった。
それは今も変わらないけど。
修道院で育っておきながら、信仰心というものがまるでないまま大人になってしまったこの僕が
いつまでも修道院に世話になるのはさすがに気が引けて、20歳になるこの年に独り立ちをしようと決めた。
でも学校生活や、まして限られた人間としか関係を持ってこなかった僕がいきなり社会に出られるはずもなく
丁度今年から大学の教師として働くことになった十影の代わりに、この屋敷に書生として住むことになったのだ。
自分を捨てた親を憎いと思わないのは、僕が可笑しいから?―――昔、十影にそう聞いたことがある。
十影は笑って、「今が幸せなら、寧ろ捨ててくれた両親に感謝すべきじゃないのか」と言った。
自分が今幸せと思えるかどうか、それが全てだと―――そう言った。
(僕が今、幸せだと思えるかどうか―――)
“幸せ”の意味さえ、あの頃の僕は知らなかったと思う。
何かを擦るような音が聞こえて、僕は我に返った。
目の前に視線を戻すと十影がマッチで煙草に火をつけているところだった。
黒い煙草の先に一瞬火が灯る。すぐにそれはバニラの香りを纏う煙になって揺れるように宙に昇った。
「花酔いってもっと脆弱な人たちだと思ってたよ」
「あ?……あぁ、あいつはまた花酔いの中でも特殊だからな」
特殊―――その言葉に覚えた違和感を僕が探り切れないうちに、十影は口を開いた。
ぶわり、その吐き出された煙がその表情を覆い隠す。
「どうして花酔いに触れてはいけないのか……分かるか」
接触感染はしないはずの花酔いに、触れてはいけない理由―――そう言えば考えたこともなかった。
揺らめきながら薄れていく紫煙の中で見えた十影の口元が、首を横に振った僕に苦笑いとも自嘲ともとれる笑みを浮かべる。
「人間の体温でさえ、火傷するからだ」
「やけど……?」
「だから感染症にだって罹りやすい。そうじゃなくても花酔いは―――」
そこまで言って、十影はまた煙草を吸った。
風のない室内で動けなくなった煙を吹き消すように吐かれた息から、また新しい煙が生まれる。
「そうじゃなくても花酔いは、短命だ」
煙と共に吐き捨てられたその言葉の意味を理解するのに、少しだけ時間がかかった。
「え?」
淡々と、十影は言った。
もくもくと、煙草の煙が宙を泳ぐ。
「あいつがあんなんだから、意識しづらいけどな」
弱々しく笑って、十影は静かに息を吐いた。
その笑みに、マホロの笑顔が重なる。
どこか切なさを感じるほどに美しいその容姿にどこか不釣り合いな、人間味を帯びたあの笑顔に
一体どれだけの想いが、苦しみがあるのか―――僕は初めて、マホロの裏側を見た気がした。
「自分の生活をすればいいとは言ったが……それだけは、把握しといてやってくれ」
僕が頷くと、十影は小さく笑った。
灰皿に煙草を押し付けて、両腕を上げると大きく伸びをする。
黒い服やその体躯の大きさのせいで、その姿はまるで熊みたいだ。
「じゃあまぁ、俺もそろそろ帰るかな」
「えっ?もう?」
「なんだ、さっそくホームシックか」
「や、違うけど」
「だろうな」
テーブルの上のカップやグラスを盆の上に片しながら、十影は半ば呆れたように言った。
「ホームシックに罹るような繊細さはお前にはねぇな」
「ホームシックに罹るようなホームが僕にはないんだよ」
正しくは、ホームシックに罹れるほどの思い出がない、という意味だけれど。
十影のいうこともまぁ、間違ってはいない。
本当はもっと花酔いの―――マホロの話を聞きたかっただけなんだけれど
こんなにあからさまに話を切り上げられてはそうも言いにくい。
「で?心細いわけじゃないなら、一体どうした?」
「や、どうしたってわけでもないんだけど……えと……あ!ぼ、僕の部屋は?」
「あ?お前の部屋?」
「そう!せめてそこだけでも案内してもらえると助かるんだけど」
「案内もなにも、ここだよ」
「え?」
思わず僕は部屋を見渡した。
明治時代の華族が住んでいた西洋風の屋敷をそのまま現代に持ってきたような造りをしていたのは、その外観だけではなかった。
豪華なシャンデリアが吊るされたエントランスを抜けた先に通されたこの部屋もまた、外観通りの凝った造りをしている。
床中に敷き詰められた深紅の絨毯は、いっそ裸足で踏みたいくらい上等なものだ。
部屋に置かれた棚やクローゼットの全てが、高級そうな気品を漂わせている。
「お前の荷物、そこにあるだろ」
そう言って十影が指さした先。
クイーンサイズはあろうかという大きな天蓋付きのベッドの脇に、申し訳程度の僕の荷物が置かれていた。
「こっ、ここ客間じゃないの!?」
「客間にベッドなんかねぇだろ」
「そ、それはそうだけど……。む、無理だよ!こんなに広い部屋!」
持て余し過ぎて申し訳なさ過ぎる。
4畳で事足りる僕にとって、この部屋の広さは部屋じゃないのも同然だ。
「つっても、物置だって修道院の寝室より広いぞ。この屋敷」
「そっ……!」
「このクソ広い屋敷の掃除をするのはお前だ。その駄賃だとでも思っとけ」
駄賃だとしても余るくらいだ、と言おうとして僕は口を噤んだ。
僕が困ることを分かっていて黙っていた―――つまりは純粋に面白がっている十影の顔が、そこにあったからだ。
「華族様のお屋敷だからな。お前の気持ちも分からんではないが……まぁすぐ慣れる」
「華族……?」
「勿論“旧”華族な。この屋敷は、唯一残されたその名残だ」
「そんなに古いんだね」
華族の名残であるならば悠に築100年は越えているはずだが、この屋敷にそういう意味での古臭さは感じなかった。
小物や調度品にはそれなりの時代を越えてきた年季を感じるが、手入れが行き届いていることもあって朽ちた感じは見受けられない。
「まぁ、耐震の問題もあって建物自体は改装されてるらしいからな。精々築40年ってとこだろ」
それでも十分に古い建物だった。
木目調の柱や廊下が陽を浴びずとも輝いているのは、細かな清掃を怠っていないからだろう。
その役目が自分に回ってくるのだと思うと、少々気が重い。
「こんなに広い屋敷に、マホロ一人で住んでるの?」
そこで漸く、僕は気になっていたことを聞いた。
勿論今まで十影が住んでいたことは知っていたけれど、それは書生としてだ。家族ではない。
「十影……?」
「あ?あぁ……」
十影は何故か一瞬面食らった顔をして、そのまま視線を窓の外へ投げた。
窓にかかっているレースカーテンから透ける庭は、先ほどまでのハーブ園とは違って色とりどりの花が咲いている。
鮮やかなそれを背景にした十影はの横顔は、何か思いつめたような顔をしていた。
やがて大きな溜息を吐いたその顔が、開き直ったように前を向く。
胸ポケットから取り出したシガレットケースから煙草を一本抜き取ると、十影は慣れた手つきで火をつけた。
「ここは、檻なんだよ」
酷く静かな声でそう言って、肺いっぱいに吸い込んだ煙を吐く。
白い靄のようなその煙が、カーテンやソファの葡萄色を纏いながら宙へ浮かんだ。
「檻?」
「花酔いを囲うための、な」
「っ!?」
どうやら僕は、踏み込んではいけない部分に踏み込んでしまったのかもしれない。
そう思った時にはもう遅かった。
自分で作り出している煙を鬱陶しそうに手で払いながら、十影は口を開く。
「―――山谷公爵はマホロの曾祖父にあたる人物だ。聡明な人で、華族制度が廃止された後、議員を辞めると事業を起こし、たった数年でそこそこ名の知れた資産家になるまでに昇りつめた。元々議員先生に収まるより、商人向きだったんだろうな。華族時代よりも裕福になったほどらしい」
そこまで聞いて僕は漸く“山谷財閥”の名前を思い出した。
マホロの名前を聞いたときには思いもしなかったことだ。僕が育った修道院に、何故か多額の寄付をしている財閥だったと思う。
「自分の息子―――マホロのじいさんに会社を譲ったとき、とうとうこの屋敷を売却して都会で新しい事業でも始めようかという話になった。しかしそんな時――― 一族に花酔いが出てしまった」
それがマホロの母親だった。
16歳の時だったらしい。
花酔いは感染源や感染経路が明確なはずだが、彼女は決してそれを話さなかったという。
「制度が廃止されても、華族のプライドってのはそんなに簡単にはなくならない。一族に花酔いが出てしまった。それをなんとか隠そうとして、じいさんはこの屋敷を残し、そこに自分の娘を―――花酔いを隠すことにした」
まるでお伽噺でも読むように、淡々と十影は話した。
「表向きには結核の療養中ってことにしてたらしい。何年も何年も、じいさんは自分の娘を軟禁し続けた。しかしここでまたひとつ、新たな問題が出来た」
「問題?」
「代を跨いで大きく築き上げてきた山谷財閥の跡取りがいなかったんだ」
なんて身勝手話なんだろうと、そう思う。
親というものがどういうものか、僕には分かるはずもないけれど。
捨てられた身だからこそ、こんなふうに思ってしまうのかもしれないけれど。
「山谷夫妻には娘以外に子どもがいなかった。婿養子を貰おうにも、花酔いの娘に結婚相手なんているはずもない。いっそ自分たちが養子でもと考えた時――― 一人の男が夫妻を訪ねてきた」
十影の口元には笑みが浮かんでいる。
しかしそれは楽しんでいるわけでも、面白がっているわけでもなかった。
確かな侮蔑と軽蔑が、その瞳には滲んでいる。
「浄見 友親―――後に、マホロの父親になる男だ」
「っ!?」
じわり、と心臓が嫌な音をたてた。
嫌な予感、というのが正しいのかもしれない。
確かな違和感が十影の言葉に纏わりついている。
「奴はどこからか、2人の娘が花酔いであることを嗅ぎつけていた。花酔いでも、婿養子でもいい。彼女と結婚させて欲しいと―――奴はそう言ったそうだ」
最初は、山谷財閥の資産目当てかと思ったらしい。
しかし男は資産なんかいらない。娘さんと結婚させて欲しいだけだ、と。そう言い貫いたらしい。
口先だけかと思いつつも、跡取りが出来るならばと山谷氏は了承した。
「そして2人は結婚した」
違和感が、大きなものになる。
花酔いの結婚。相手は浄見という男で、花酔いではない。
―――じゃあマホロはどうやって……
違和感が、姿を現した。
「………じゃあ、マホロは…………」
苦虫を嚙み潰したような顔をして、十影は沈黙した。
違和感の正体。
『マホロの父親になる男』だと、十影は言っていた。
普通『マホロの父親』だと言うべきところで。
そして、花酔いには触れられないというルール。
「浄見の目的は確かに財閥の資産なんかじゃなかった。正真正銘、花酔いと結婚することにあったんだよ」
「でも、どうして……?」
「花酔いビジネス」
初めて聞く、言葉だった。
十影の吐き捨てるような言い方からして、いいものではないんだろう。
「昔、花酔いは花喰いと呼ばれていた。その名の通り、花を食うからだ」
短くなった煙草を消しながら、十影は続けた。
「花酔いの研究は、実は国家機密レベルの組織で暗直下に進められている。その研究成果のひとつによって、花喰いは花酔いと呼ばれるようになった。その理由が―――これだ」
十影は胸ポケットから縮緬布で出来た小さな巾着袋を取り出した。
桃色のそれは十影が持つにはあまりに可愛らしすぎる。
その袋の中から透明なブラスチックケースが取り出された。
中には、淡い薄紅色のバラの花びらが一枚、収められている。
「これは……?」
「花酔いの体液だよ」
「っ!?」
手のひらに乗せられたケース越しのその花びらを僕は見つめた。
粒子の細かい砂糖を敷き詰めているように、その花びらの表面はきらきらと光ってみえる。
「花酔いの体液は、直接舐めたり体内に取り込むと花酔いに感染する。でも、一度空気に触れてしまえばウイルスは死滅し、こんなふうに凝固して無毒なものになる」
「花酔いの傷口を直接舐めたりしない限りは感染しないってこと?」
「そうだな。唾液を交換するようなキスやセックスでも感染するが―――まぁそれ以前に花酔いに触れられないんだからその可能性は低いけど」
触れられるだけで火傷してしまうのだ。
軽いキスくらいなら軽傷で済みそうだが、セックスとなると命を落としかねないだろう。
「で、花酔いが創り出すこの花弁。あろうことかこいつを、食った奴がいた」
「っえ!?」
「しかもこいつの無毒性が証明されるよりも前の話だ。自分が花酔いに感染するリスクを侵してそいつはコレを食った。やばいだろ?でもまぁ、そのおかげで―――というかせいで、花酔いの研究は進められることになったわけだが……」
一見すると甘い砂糖菓子のように見える無毒化された結晶だと分かっていても、それを口にいえるのは相当の勇気が必要だと思う。
それなのに、無毒であることが証明されるよりも前―――花酔いに感染するリスク込みでこの花びらを口に入れた、その真意はなんだろう。
「いわゆる“ハイ”の状態で職質受けた男の薬物検査がどれも悉く陰性で、よくよく話を聞くと『花酔いの花弁を食った』と答えたらしい。そこに、研究機関が目をつけた。成分分析の結果、特に怪しい成分はなかったらしい。ただ被験者に花弁を与えたところ、多幸感や高揚感、疲労感の麻痺、ふわふわとした浮遊感、そして強い催淫作用が認められた」
「なっ!?」
「それに、浄見は目をつけたんだよ」
虫唾が走る―――とはこのことだろうと、僕は生まれて初めてそう思った。
ぞわりという不快感が腹の奥に溜まる。
吐き出そうとすれば吐き気にも似た感覚が咽喉を締めた。
「ドラッグのような効果を合法的に引き起こすことが出来る。しかもその事実は機密保持されて外に出回ることはない。国の上層部分を顧客につけることが出来れば、そしてそれが外交に繋がることにもなれば―――ブラックマーケット下において、それは一大産業になる。浄見の目的はそこにあった」
胃液がチリチリと食道を焼いているのが分かった。
ぐるぐると不快感が巡る。腹の底に鉛でも溜まっているみたいだった。
「この花弁を集めるため、浄見は花酔いと結婚し、そして、花酔いを産ませた」
その言葉にまたさっきの違和感があった。
花酔いには触れられない。触れなければ、子どもは作れないはずだ。
―――じゃあマホロはどうやって生まれたのか
「………っ!ま、さか……!」
「浄見は自分の妻に、同じ花酔いの男をあてがった。花酔い同士は触れることが出来るからな。そうやって出来たのが―――マホロだ」
花酔いになるべくして生まれた花酔い―――それが、さっき十影が言っていた「特殊」という意味なんだろう。
道具にされるために結婚したマホロの母親。
そして、道具として生まれてきたマホロ。
鼻の奥がつん、とした。
「その事実を知る前にじいさんが心不全で呆気なく逝って……ばあさんも後を追うようにして死んだ。残されたあの人もマホロを生んでそのまま―――……」
そうしてマホロだけが残ったというのか。
この屋敷に。この檻に。
気が付けば僕は自分の膝の上に視線を落としていた。
十影を見るのが、それ以上を聞くのが怖かった。
思っていたよりも、もっとずっと、繊細で脆く弱い、花酔いという性質。
―――それなのに何故。それなのに、何故。
なんでもないような顔をして、彼は、
マホロは―――……
「別に絆されて欲しくて話してるんじゃない。俺は寧ろ、お前にそうなって欲しくない」
「………でも」
「あいつに同情なんかするな」
急に突き放したように、十影は言った。
膝の上で握りしめたプラスチックケースに、ぽたりと何かが落ちた。
透明な水滴。鼻の奥が、むず痒くて、少し痛い。
「…………んだよ、それ」
「……………」
「なんだよ、それ!」
そう叫ぶように言った僕の声が、毛足の長い絨毯に吸収された。
遅れてやってきた膝の痛み。ぶつかったテーブルが揺れて、盆の上のグラスが倒れた。
それでも十影は酷く落ち着いていて、憐れむような目で立ち上がった僕を見上げている。
「十影はそれでいいの!?そこまで分かってて……どうして……っ、どうして、そんな……っ」
僕の知る十影は、面倒くさがりで、意地悪で、そのくせ弱い人を放ってはおけない、優しい人だ。
僕にとって十影だけが、心を開ける唯一の存在だった。
そんな十影が、そんなことを言うところを、見たくなかった。
今にも壊れてしまいそうな存在が目の前にいるのに、ずっとそばにいたのに。
あんな顔で、笑わせていて欲しくなかった。
あんな、全てを諦めたような、開き直ったような顔で―――
「マホロは……受け入れてるっていうの……」
「…………あぁ」
「っ!」
十影が立ちあがる。
俯いたままの僕の肩が、反射で震えた。
「あいつは全部受け入れてる」
そうじゃなきゃ、辛いだろ―――消え去りそうな声でそう言って、十影は僕を抱きしめた。
ほんの少しだけスパイシーなバニラの香りが、僕の涙と混じって少し水っぽく香る。
熱いくらいの温もりが、僕を包んだ。
十影もまた、受け入れざるを得なかったのだろう。
マホロと同じように。開き直って笑うしか、ないのだ。
「僕には……無理だよ」
「あぁ……」
他人の不幸を抱え込んで笑えるほど、僕は強くない。
自分の幸せすら分からないのに、他人の為に不幸になれない。
「だからお前は―――」
僕の後頭部に回された手が、ぎゅっと僕を自分の胸に押し付けた。
酷く穏やかな心臓の音が、僕の涙を吸い込んでいく。
さらさらと流れる血流の音がした。
十影が泣いてるみたいだ―――そう思った。
飛行機事故で両親が死んだとか、何か凶悪犯罪に巻き込まれて死んだとか、そういうんじゃない。
ただ純粋に、端的に。
生まれて間もなかった僕は、町の外れにある小さな修道院に捨てられたのだ。
それが母親だったのか、父親だったのか、はたまた両親だったのかは分からない。
とにかく僕は捨てられて、孤児になった。
土砂降りの、凍えるような冬の日だったらしい。
タオルケット一枚に包まれて捨てられていた僕を拾ったのが、この修道院の神父で、十影の叔父にあたる人だった。
この十影の叔父という人を、実を言うと僕はよく覚えていない。
何不自由ない暮らしをさせてもらってきておいて、あまりに薄情だとは思うけれど。
背の高い、黒い服を着た男の人―――精々それくらいの記憶しかない。
そもそも、子どもの僕からしたら大体の大人は背が高かったし
修道院に居る人はみんな黒い服を着ていたから、この記憶がその叔父さんのものかどうかは分からないけれど。
黒い服を着た背の高い男―――その認識を“十影”に塗り替えたのは僕が13歳の時だった。
流石に学校に行かせてはもらえなかった僕の教育係として、当時大学生だった十影が修道院にやってくるようになった時だ。
歴史や漢字、外国語や計算式……十影が教えてくれる色々なもの、その全てが新しく刺激的で、恐らく僕はこの歳ではじめて「面白い」という感情を知った。
喜怒哀楽、その他諸々の感情を見事に理解していなかった僕にとって、十影は先生であり、親であり、友達のような存在だった。
それは今も変わらないけど。
修道院で育っておきながら、信仰心というものがまるでないまま大人になってしまったこの僕が
いつまでも修道院に世話になるのはさすがに気が引けて、20歳になるこの年に独り立ちをしようと決めた。
でも学校生活や、まして限られた人間としか関係を持ってこなかった僕がいきなり社会に出られるはずもなく
丁度今年から大学の教師として働くことになった十影の代わりに、この屋敷に書生として住むことになったのだ。
自分を捨てた親を憎いと思わないのは、僕が可笑しいから?―――昔、十影にそう聞いたことがある。
十影は笑って、「今が幸せなら、寧ろ捨ててくれた両親に感謝すべきじゃないのか」と言った。
自分が今幸せと思えるかどうか、それが全てだと―――そう言った。
(僕が今、幸せだと思えるかどうか―――)
“幸せ”の意味さえ、あの頃の僕は知らなかったと思う。
何かを擦るような音が聞こえて、僕は我に返った。
目の前に視線を戻すと十影がマッチで煙草に火をつけているところだった。
黒い煙草の先に一瞬火が灯る。すぐにそれはバニラの香りを纏う煙になって揺れるように宙に昇った。
「花酔いってもっと脆弱な人たちだと思ってたよ」
「あ?……あぁ、あいつはまた花酔いの中でも特殊だからな」
特殊―――その言葉に覚えた違和感を僕が探り切れないうちに、十影は口を開いた。
ぶわり、その吐き出された煙がその表情を覆い隠す。
「どうして花酔いに触れてはいけないのか……分かるか」
接触感染はしないはずの花酔いに、触れてはいけない理由―――そう言えば考えたこともなかった。
揺らめきながら薄れていく紫煙の中で見えた十影の口元が、首を横に振った僕に苦笑いとも自嘲ともとれる笑みを浮かべる。
「人間の体温でさえ、火傷するからだ」
「やけど……?」
「だから感染症にだって罹りやすい。そうじゃなくても花酔いは―――」
そこまで言って、十影はまた煙草を吸った。
風のない室内で動けなくなった煙を吹き消すように吐かれた息から、また新しい煙が生まれる。
「そうじゃなくても花酔いは、短命だ」
煙と共に吐き捨てられたその言葉の意味を理解するのに、少しだけ時間がかかった。
「え?」
淡々と、十影は言った。
もくもくと、煙草の煙が宙を泳ぐ。
「あいつがあんなんだから、意識しづらいけどな」
弱々しく笑って、十影は静かに息を吐いた。
その笑みに、マホロの笑顔が重なる。
どこか切なさを感じるほどに美しいその容姿にどこか不釣り合いな、人間味を帯びたあの笑顔に
一体どれだけの想いが、苦しみがあるのか―――僕は初めて、マホロの裏側を見た気がした。
「自分の生活をすればいいとは言ったが……それだけは、把握しといてやってくれ」
僕が頷くと、十影は小さく笑った。
灰皿に煙草を押し付けて、両腕を上げると大きく伸びをする。
黒い服やその体躯の大きさのせいで、その姿はまるで熊みたいだ。
「じゃあまぁ、俺もそろそろ帰るかな」
「えっ?もう?」
「なんだ、さっそくホームシックか」
「や、違うけど」
「だろうな」
テーブルの上のカップやグラスを盆の上に片しながら、十影は半ば呆れたように言った。
「ホームシックに罹るような繊細さはお前にはねぇな」
「ホームシックに罹るようなホームが僕にはないんだよ」
正しくは、ホームシックに罹れるほどの思い出がない、という意味だけれど。
十影のいうこともまぁ、間違ってはいない。
本当はもっと花酔いの―――マホロの話を聞きたかっただけなんだけれど
こんなにあからさまに話を切り上げられてはそうも言いにくい。
「で?心細いわけじゃないなら、一体どうした?」
「や、どうしたってわけでもないんだけど……えと……あ!ぼ、僕の部屋は?」
「あ?お前の部屋?」
「そう!せめてそこだけでも案内してもらえると助かるんだけど」
「案内もなにも、ここだよ」
「え?」
思わず僕は部屋を見渡した。
明治時代の華族が住んでいた西洋風の屋敷をそのまま現代に持ってきたような造りをしていたのは、その外観だけではなかった。
豪華なシャンデリアが吊るされたエントランスを抜けた先に通されたこの部屋もまた、外観通りの凝った造りをしている。
床中に敷き詰められた深紅の絨毯は、いっそ裸足で踏みたいくらい上等なものだ。
部屋に置かれた棚やクローゼットの全てが、高級そうな気品を漂わせている。
「お前の荷物、そこにあるだろ」
そう言って十影が指さした先。
クイーンサイズはあろうかという大きな天蓋付きのベッドの脇に、申し訳程度の僕の荷物が置かれていた。
「こっ、ここ客間じゃないの!?」
「客間にベッドなんかねぇだろ」
「そ、それはそうだけど……。む、無理だよ!こんなに広い部屋!」
持て余し過ぎて申し訳なさ過ぎる。
4畳で事足りる僕にとって、この部屋の広さは部屋じゃないのも同然だ。
「つっても、物置だって修道院の寝室より広いぞ。この屋敷」
「そっ……!」
「このクソ広い屋敷の掃除をするのはお前だ。その駄賃だとでも思っとけ」
駄賃だとしても余るくらいだ、と言おうとして僕は口を噤んだ。
僕が困ることを分かっていて黙っていた―――つまりは純粋に面白がっている十影の顔が、そこにあったからだ。
「華族様のお屋敷だからな。お前の気持ちも分からんではないが……まぁすぐ慣れる」
「華族……?」
「勿論“旧”華族な。この屋敷は、唯一残されたその名残だ」
「そんなに古いんだね」
華族の名残であるならば悠に築100年は越えているはずだが、この屋敷にそういう意味での古臭さは感じなかった。
小物や調度品にはそれなりの時代を越えてきた年季を感じるが、手入れが行き届いていることもあって朽ちた感じは見受けられない。
「まぁ、耐震の問題もあって建物自体は改装されてるらしいからな。精々築40年ってとこだろ」
それでも十分に古い建物だった。
木目調の柱や廊下が陽を浴びずとも輝いているのは、細かな清掃を怠っていないからだろう。
その役目が自分に回ってくるのだと思うと、少々気が重い。
「こんなに広い屋敷に、マホロ一人で住んでるの?」
そこで漸く、僕は気になっていたことを聞いた。
勿論今まで十影が住んでいたことは知っていたけれど、それは書生としてだ。家族ではない。
「十影……?」
「あ?あぁ……」
十影は何故か一瞬面食らった顔をして、そのまま視線を窓の外へ投げた。
窓にかかっているレースカーテンから透ける庭は、先ほどまでのハーブ園とは違って色とりどりの花が咲いている。
鮮やかなそれを背景にした十影はの横顔は、何か思いつめたような顔をしていた。
やがて大きな溜息を吐いたその顔が、開き直ったように前を向く。
胸ポケットから取り出したシガレットケースから煙草を一本抜き取ると、十影は慣れた手つきで火をつけた。
「ここは、檻なんだよ」
酷く静かな声でそう言って、肺いっぱいに吸い込んだ煙を吐く。
白い靄のようなその煙が、カーテンやソファの葡萄色を纏いながら宙へ浮かんだ。
「檻?」
「花酔いを囲うための、な」
「っ!?」
どうやら僕は、踏み込んではいけない部分に踏み込んでしまったのかもしれない。
そう思った時にはもう遅かった。
自分で作り出している煙を鬱陶しそうに手で払いながら、十影は口を開く。
「―――山谷公爵はマホロの曾祖父にあたる人物だ。聡明な人で、華族制度が廃止された後、議員を辞めると事業を起こし、たった数年でそこそこ名の知れた資産家になるまでに昇りつめた。元々議員先生に収まるより、商人向きだったんだろうな。華族時代よりも裕福になったほどらしい」
そこまで聞いて僕は漸く“山谷財閥”の名前を思い出した。
マホロの名前を聞いたときには思いもしなかったことだ。僕が育った修道院に、何故か多額の寄付をしている財閥だったと思う。
「自分の息子―――マホロのじいさんに会社を譲ったとき、とうとうこの屋敷を売却して都会で新しい事業でも始めようかという話になった。しかしそんな時――― 一族に花酔いが出てしまった」
それがマホロの母親だった。
16歳の時だったらしい。
花酔いは感染源や感染経路が明確なはずだが、彼女は決してそれを話さなかったという。
「制度が廃止されても、華族のプライドってのはそんなに簡単にはなくならない。一族に花酔いが出てしまった。それをなんとか隠そうとして、じいさんはこの屋敷を残し、そこに自分の娘を―――花酔いを隠すことにした」
まるでお伽噺でも読むように、淡々と十影は話した。
「表向きには結核の療養中ってことにしてたらしい。何年も何年も、じいさんは自分の娘を軟禁し続けた。しかしここでまたひとつ、新たな問題が出来た」
「問題?」
「代を跨いで大きく築き上げてきた山谷財閥の跡取りがいなかったんだ」
なんて身勝手話なんだろうと、そう思う。
親というものがどういうものか、僕には分かるはずもないけれど。
捨てられた身だからこそ、こんなふうに思ってしまうのかもしれないけれど。
「山谷夫妻には娘以外に子どもがいなかった。婿養子を貰おうにも、花酔いの娘に結婚相手なんているはずもない。いっそ自分たちが養子でもと考えた時――― 一人の男が夫妻を訪ねてきた」
十影の口元には笑みが浮かんでいる。
しかしそれは楽しんでいるわけでも、面白がっているわけでもなかった。
確かな侮蔑と軽蔑が、その瞳には滲んでいる。
「浄見 友親―――後に、マホロの父親になる男だ」
「っ!?」
じわり、と心臓が嫌な音をたてた。
嫌な予感、というのが正しいのかもしれない。
確かな違和感が十影の言葉に纏わりついている。
「奴はどこからか、2人の娘が花酔いであることを嗅ぎつけていた。花酔いでも、婿養子でもいい。彼女と結婚させて欲しいと―――奴はそう言ったそうだ」
最初は、山谷財閥の資産目当てかと思ったらしい。
しかし男は資産なんかいらない。娘さんと結婚させて欲しいだけだ、と。そう言い貫いたらしい。
口先だけかと思いつつも、跡取りが出来るならばと山谷氏は了承した。
「そして2人は結婚した」
違和感が、大きなものになる。
花酔いの結婚。相手は浄見という男で、花酔いではない。
―――じゃあマホロはどうやって……
違和感が、姿を現した。
「………じゃあ、マホロは…………」
苦虫を嚙み潰したような顔をして、十影は沈黙した。
違和感の正体。
『マホロの父親になる男』だと、十影は言っていた。
普通『マホロの父親』だと言うべきところで。
そして、花酔いには触れられないというルール。
「浄見の目的は確かに財閥の資産なんかじゃなかった。正真正銘、花酔いと結婚することにあったんだよ」
「でも、どうして……?」
「花酔いビジネス」
初めて聞く、言葉だった。
十影の吐き捨てるような言い方からして、いいものではないんだろう。
「昔、花酔いは花喰いと呼ばれていた。その名の通り、花を食うからだ」
短くなった煙草を消しながら、十影は続けた。
「花酔いの研究は、実は国家機密レベルの組織で暗直下に進められている。その研究成果のひとつによって、花喰いは花酔いと呼ばれるようになった。その理由が―――これだ」
十影は胸ポケットから縮緬布で出来た小さな巾着袋を取り出した。
桃色のそれは十影が持つにはあまりに可愛らしすぎる。
その袋の中から透明なブラスチックケースが取り出された。
中には、淡い薄紅色のバラの花びらが一枚、収められている。
「これは……?」
「花酔いの体液だよ」
「っ!?」
手のひらに乗せられたケース越しのその花びらを僕は見つめた。
粒子の細かい砂糖を敷き詰めているように、その花びらの表面はきらきらと光ってみえる。
「花酔いの体液は、直接舐めたり体内に取り込むと花酔いに感染する。でも、一度空気に触れてしまえばウイルスは死滅し、こんなふうに凝固して無毒なものになる」
「花酔いの傷口を直接舐めたりしない限りは感染しないってこと?」
「そうだな。唾液を交換するようなキスやセックスでも感染するが―――まぁそれ以前に花酔いに触れられないんだからその可能性は低いけど」
触れられるだけで火傷してしまうのだ。
軽いキスくらいなら軽傷で済みそうだが、セックスとなると命を落としかねないだろう。
「で、花酔いが創り出すこの花弁。あろうことかこいつを、食った奴がいた」
「っえ!?」
「しかもこいつの無毒性が証明されるよりも前の話だ。自分が花酔いに感染するリスクを侵してそいつはコレを食った。やばいだろ?でもまぁ、そのおかげで―――というかせいで、花酔いの研究は進められることになったわけだが……」
一見すると甘い砂糖菓子のように見える無毒化された結晶だと分かっていても、それを口にいえるのは相当の勇気が必要だと思う。
それなのに、無毒であることが証明されるよりも前―――花酔いに感染するリスク込みでこの花びらを口に入れた、その真意はなんだろう。
「いわゆる“ハイ”の状態で職質受けた男の薬物検査がどれも悉く陰性で、よくよく話を聞くと『花酔いの花弁を食った』と答えたらしい。そこに、研究機関が目をつけた。成分分析の結果、特に怪しい成分はなかったらしい。ただ被験者に花弁を与えたところ、多幸感や高揚感、疲労感の麻痺、ふわふわとした浮遊感、そして強い催淫作用が認められた」
「なっ!?」
「それに、浄見は目をつけたんだよ」
虫唾が走る―――とはこのことだろうと、僕は生まれて初めてそう思った。
ぞわりという不快感が腹の奥に溜まる。
吐き出そうとすれば吐き気にも似た感覚が咽喉を締めた。
「ドラッグのような効果を合法的に引き起こすことが出来る。しかもその事実は機密保持されて外に出回ることはない。国の上層部分を顧客につけることが出来れば、そしてそれが外交に繋がることにもなれば―――ブラックマーケット下において、それは一大産業になる。浄見の目的はそこにあった」
胃液がチリチリと食道を焼いているのが分かった。
ぐるぐると不快感が巡る。腹の底に鉛でも溜まっているみたいだった。
「この花弁を集めるため、浄見は花酔いと結婚し、そして、花酔いを産ませた」
その言葉にまたさっきの違和感があった。
花酔いには触れられない。触れなければ、子どもは作れないはずだ。
―――じゃあマホロはどうやって生まれたのか
「………っ!ま、さか……!」
「浄見は自分の妻に、同じ花酔いの男をあてがった。花酔い同士は触れることが出来るからな。そうやって出来たのが―――マホロだ」
花酔いになるべくして生まれた花酔い―――それが、さっき十影が言っていた「特殊」という意味なんだろう。
道具にされるために結婚したマホロの母親。
そして、道具として生まれてきたマホロ。
鼻の奥がつん、とした。
「その事実を知る前にじいさんが心不全で呆気なく逝って……ばあさんも後を追うようにして死んだ。残されたあの人もマホロを生んでそのまま―――……」
そうしてマホロだけが残ったというのか。
この屋敷に。この檻に。
気が付けば僕は自分の膝の上に視線を落としていた。
十影を見るのが、それ以上を聞くのが怖かった。
思っていたよりも、もっとずっと、繊細で脆く弱い、花酔いという性質。
―――それなのに何故。それなのに、何故。
なんでもないような顔をして、彼は、
マホロは―――……
「別に絆されて欲しくて話してるんじゃない。俺は寧ろ、お前にそうなって欲しくない」
「………でも」
「あいつに同情なんかするな」
急に突き放したように、十影は言った。
膝の上で握りしめたプラスチックケースに、ぽたりと何かが落ちた。
透明な水滴。鼻の奥が、むず痒くて、少し痛い。
「…………んだよ、それ」
「……………」
「なんだよ、それ!」
そう叫ぶように言った僕の声が、毛足の長い絨毯に吸収された。
遅れてやってきた膝の痛み。ぶつかったテーブルが揺れて、盆の上のグラスが倒れた。
それでも十影は酷く落ち着いていて、憐れむような目で立ち上がった僕を見上げている。
「十影はそれでいいの!?そこまで分かってて……どうして……っ、どうして、そんな……っ」
僕の知る十影は、面倒くさがりで、意地悪で、そのくせ弱い人を放ってはおけない、優しい人だ。
僕にとって十影だけが、心を開ける唯一の存在だった。
そんな十影が、そんなことを言うところを、見たくなかった。
今にも壊れてしまいそうな存在が目の前にいるのに、ずっとそばにいたのに。
あんな顔で、笑わせていて欲しくなかった。
あんな、全てを諦めたような、開き直ったような顔で―――
「マホロは……受け入れてるっていうの……」
「…………あぁ」
「っ!」
十影が立ちあがる。
俯いたままの僕の肩が、反射で震えた。
「あいつは全部受け入れてる」
そうじゃなきゃ、辛いだろ―――消え去りそうな声でそう言って、十影は僕を抱きしめた。
ほんの少しだけスパイシーなバニラの香りが、僕の涙と混じって少し水っぽく香る。
熱いくらいの温もりが、僕を包んだ。
十影もまた、受け入れざるを得なかったのだろう。
マホロと同じように。開き直って笑うしか、ないのだ。
「僕には……無理だよ」
「あぁ……」
他人の不幸を抱え込んで笑えるほど、僕は強くない。
自分の幸せすら分からないのに、他人の為に不幸になれない。
「だからお前は―――」
僕の後頭部に回された手が、ぎゅっと僕を自分の胸に押し付けた。
酷く穏やかな心臓の音が、僕の涙を吸い込んでいく。
さらさらと流れる血流の音がした。
十影が泣いてるみたいだ―――そう思った。