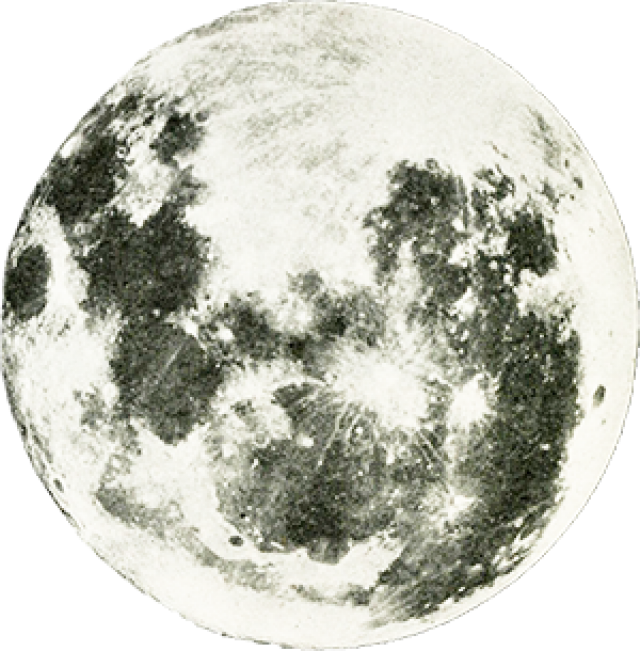-15-花吻
文字数 2,931文字
日中は消魂しいほどに蝉の鳴き声が響く庭も、陽が沈むと逆にひっそりとしている。
陽が長いせいで空が夜になりきれていないのか、それとも頭上に昇った月のおかげか。庭は闇に沈むことなく、紺色の中に紛れていた。
その紺色の中に、無数の白い花が蛍の光のように光っている。その花独特の甘い香りが夏の匂いに混ざって香っていた。
僕の足音に気付いたのか、マホロの背中が動く。
その光の中から一枚の花弁がひらりと落ちた。
瑞々しい本物の月下美人だった。
「咲いたんだ。月下美人」
「うん。縁日が世話してくれてたからね」
小さく笑って、マホロは何故か触れていた月下美人から指先を離した。
その白い花はまるで自ら発光するように月の光を浴びて金色に光っている。
僕は躊躇うことなく、その花のひとつを摘み取った。
「縁日……?」
僕の行動を追っていたマホロの目が、すぐに驚いたような、咎めるようなそれに変わった。
月下美人を口の中に放り込んだ僕を、信じられないとでも言いたげにただ凝視している。
むわりとするほど庭中に香っている甘ったるい香りが鼻に抜けた。
噛み締めると、何とも言えない植物の味とほろ苦さが口中に広がる。
どうやらその甘い香りは、味覚には作用しないらしい。
「にがい……」
「当たり前でしょ。何やってんの……」
呆れたようにそう言いながら、マホロは月下美人の奥に咲く花をぷちっと摘んだ。
月明かりに染まっているわけではない、その金色の花弁からもジャスミンに似た甘い香りがしている。
マホロはそれを僕に差し出した。
「これは?」
「忍冬。こうやって銜えてみて。噛んじゃ駄目だよ」
そう言ってマホロはその花の根元を唇に銜えた。
それを真似て受け取った花を銜えると、鼻先に香る花の香りに混じって甘い蜜が咥内に広がる。
「あまい!」
「花の蜜は基本的に甘いよ。ただそれが、人間に感じられる強さかどうかなだけ」
「へぇ!」
そわそわと庭を見渡す僕に何かを察したのか、マホロが十影のような表情をして溜息を吐いた。
「だからって何でもかんでも口にいれちゃ駄目だからね、縁日」
「ぅへぇ?」
「特にあれとかは絶対駄目」
そうマホロが指さしたのは、子どもくらいの背丈の株に実成りに咲いている白い花だった。
月下美人と同じように月の光に妖しく光ながら、微かな風にまるで僕を誘うように揺れている。
「あさが………夕顔?」
「ダチュラだよ」
「だちゅら?」
「そう。朝鮮朝顔」
マホロが動いた。
光が。月の光が、それに伴って移動する。
舞台上の俳優に当たるスポットライトが、一斉に動くように。
マホロが立ち止まれば、光もそこにとどまった。
「毒があるから。縁日は食べちゃ駄目」
振り返って、そう笑った。
マホロはいいの?―――とは、とても聞けなかった。
微かに庭中に注ぐ光が弱くなった気がして、僕は空を見上げた。
薄い雲が丸い月にかかって、高速に移動している。
秋の空気を孕んだ風が、庭に咲く無数の花の蕾を揺らした。
「今はないけどアネモネも駄目かな。―――それは大丈夫なやつ」
マホロが指さした先にあったのは梔子の花だった。
季節が終わりかけているのだろう。一時期その香りばかりだったこの庭も、今は他の花の香りが埋め尽くして梔子は負けている。
夕顔や月下美人とはまた違った白さのその花をひとつ摘むと、マホロはその根元側を僕の唇に差し出した。
鼻先に梔子の香り弱く感じる。
反射的にその根元を食むと、独特の青臭さが舌先に乗った。
「ん、ん?マホロ、これ甘くな―――」
一瞬、庭中のありとあらゆる花の香りが、それに負けた―――桃のような甘ったるい匂い。
空に浮かぶ満月のような2つの瞳が、目の前にあった。
きっと、触れているか触れていないか分からないくらいの距離感で、鼻先が触れた。
ぷちり、と音がする。
マホロの薄い唇から覗いた小さな歯が、僕の銜える梔子の花の花弁を一枚とっていった。
白い花びらが、マホロの中に消える。
また、鼻先に微かな熱。
ぷちり、ぷちり、と僕の唇から花弁がなくなっていく。
最後の花弁がマホロの中に消えた。
それでもマホロはまた、僕に近付いた。
僕の唇に残った花のガクを、マホロが銜える。
微かに。本当に微かに。マホロの唇が、触れた。
するり、と僕の唇から花が奪われていく。
マホロはそれを―――僕の唾液がついたそれを、花弁よりも味わうようにして食べた。
「……マホロってたまに吃驚するようなことするよね」
「それ、縁日が言う?」
「え?僕……?」
「ほら、無自覚」
俺より性質悪いよね、と言ってマホロは小さく笑った。
風が吹く。
ほんの少しだけ切なさを孕んだ風が、庭を揺らして、月にかかった雲を晴らす。
ひらり、と目の前を銀色に光る何かが横切った。
月白色の花弁が、ふわりと風に乗ってとんでいく。
月下美人の花弁だった。マホロのものではないと分かっていても、そのまま飛ばしてしまうのは惜しい気がして僕は手を伸ばす。
そんな僕を、マホロの声が制した。
「―――縁日」
少しだけ、咎めるような色を含んだその声に僕が振り向くと
思いのほか目の前に、マホロの顔があった。
拗ねた子どものような、それでいてどこかバツが悪そうな、そんな顔をして
身体には触れないように僕のシャツを掴んでいる。
「マホロ?」
「……なんでもない」
なんでもないけど……―――と、やっと聞き取れるくらいの声でそう言ったままマホロは気まずそうに視線をそらしてしまった。
そんなマホロが可愛くて思わず小さく笑うと、びくりと跳ねた肩が小さく震えて、マホロはますます拗ねたような顔をして下を俯いた。
僕のシャツに埋めた微かに見える頬が、桃のように染まっている。
「マホロ?どうしたの?」
「だからなんでもないってば。ばか」
そう言いながら、マホロは僕のシャツを掴む力を益々強めてしまった。
マホロに気付かれないように僕はまた笑って、すぐそばにあった梔子の花に手を伸ばした。
その花の花弁を一枚とって、マホロの前髪を中指の爪先でそっとよける。
また、マホロの薄い肩がびくりと跳ねた。
「マホロ」
「っ」
「マホロ。ねぇ、マホロ」
「な、に……」
「眞秀」
「っ!」
勢いよく顔を上げたその頬が、耳が、目元が、額が、赤くて。水を込めたような瞳が僕だけを映したまま泣きそうに震えていた。
「っ」
マホロの唇に、梔子の花弁を乗せた。
水分を含んだ睫毛が何かを察して小さく戸惑った後、それでもそっと伏せる。
一瞬、鼻先に梔子の香りがして、それでもそれはすぐに甘ったるい果実の香りに負けた。
熟しきって、熱せられて、融かされてしまったような桃のただ甘い香りがした。
しっとりとした梔子の花弁を一枚隔てた口付けが、その場にあった全ての音と香りを遮断する。
マホロの唇も、こんなふうにひんやりとしているのだろうか。
2人だけしかいない空間の中で僕は、そんなことを思った。
陽が長いせいで空が夜になりきれていないのか、それとも頭上に昇った月のおかげか。庭は闇に沈むことなく、紺色の中に紛れていた。
その紺色の中に、無数の白い花が蛍の光のように光っている。その花独特の甘い香りが夏の匂いに混ざって香っていた。
僕の足音に気付いたのか、マホロの背中が動く。
その光の中から一枚の花弁がひらりと落ちた。
瑞々しい本物の月下美人だった。
「咲いたんだ。月下美人」
「うん。縁日が世話してくれてたからね」
小さく笑って、マホロは何故か触れていた月下美人から指先を離した。
その白い花はまるで自ら発光するように月の光を浴びて金色に光っている。
僕は躊躇うことなく、その花のひとつを摘み取った。
「縁日……?」
僕の行動を追っていたマホロの目が、すぐに驚いたような、咎めるようなそれに変わった。
月下美人を口の中に放り込んだ僕を、信じられないとでも言いたげにただ凝視している。
むわりとするほど庭中に香っている甘ったるい香りが鼻に抜けた。
噛み締めると、何とも言えない植物の味とほろ苦さが口中に広がる。
どうやらその甘い香りは、味覚には作用しないらしい。
「にがい……」
「当たり前でしょ。何やってんの……」
呆れたようにそう言いながら、マホロは月下美人の奥に咲く花をぷちっと摘んだ。
月明かりに染まっているわけではない、その金色の花弁からもジャスミンに似た甘い香りがしている。
マホロはそれを僕に差し出した。
「これは?」
「忍冬。こうやって銜えてみて。噛んじゃ駄目だよ」
そう言ってマホロはその花の根元を唇に銜えた。
それを真似て受け取った花を銜えると、鼻先に香る花の香りに混じって甘い蜜が咥内に広がる。
「あまい!」
「花の蜜は基本的に甘いよ。ただそれが、人間に感じられる強さかどうかなだけ」
「へぇ!」
そわそわと庭を見渡す僕に何かを察したのか、マホロが十影のような表情をして溜息を吐いた。
「だからって何でもかんでも口にいれちゃ駄目だからね、縁日」
「ぅへぇ?」
「特にあれとかは絶対駄目」
そうマホロが指さしたのは、子どもくらいの背丈の株に実成りに咲いている白い花だった。
月下美人と同じように月の光に妖しく光ながら、微かな風にまるで僕を誘うように揺れている。
「あさが………夕顔?」
「ダチュラだよ」
「だちゅら?」
「そう。朝鮮朝顔」
マホロが動いた。
光が。月の光が、それに伴って移動する。
舞台上の俳優に当たるスポットライトが、一斉に動くように。
マホロが立ち止まれば、光もそこにとどまった。
「毒があるから。縁日は食べちゃ駄目」
振り返って、そう笑った。
マホロはいいの?―――とは、とても聞けなかった。
微かに庭中に注ぐ光が弱くなった気がして、僕は空を見上げた。
薄い雲が丸い月にかかって、高速に移動している。
秋の空気を孕んだ風が、庭に咲く無数の花の蕾を揺らした。
「今はないけどアネモネも駄目かな。―――それは大丈夫なやつ」
マホロが指さした先にあったのは梔子の花だった。
季節が終わりかけているのだろう。一時期その香りばかりだったこの庭も、今は他の花の香りが埋め尽くして梔子は負けている。
夕顔や月下美人とはまた違った白さのその花をひとつ摘むと、マホロはその根元側を僕の唇に差し出した。
鼻先に梔子の香り弱く感じる。
反射的にその根元を食むと、独特の青臭さが舌先に乗った。
「ん、ん?マホロ、これ甘くな―――」
一瞬、庭中のありとあらゆる花の香りが、それに負けた―――桃のような甘ったるい匂い。
空に浮かぶ満月のような2つの瞳が、目の前にあった。
きっと、触れているか触れていないか分からないくらいの距離感で、鼻先が触れた。
ぷちり、と音がする。
マホロの薄い唇から覗いた小さな歯が、僕の銜える梔子の花の花弁を一枚とっていった。
白い花びらが、マホロの中に消える。
また、鼻先に微かな熱。
ぷちり、ぷちり、と僕の唇から花弁がなくなっていく。
最後の花弁がマホロの中に消えた。
それでもマホロはまた、僕に近付いた。
僕の唇に残った花のガクを、マホロが銜える。
微かに。本当に微かに。マホロの唇が、触れた。
するり、と僕の唇から花が奪われていく。
マホロはそれを―――僕の唾液がついたそれを、花弁よりも味わうようにして食べた。
「……マホロってたまに吃驚するようなことするよね」
「それ、縁日が言う?」
「え?僕……?」
「ほら、無自覚」
俺より性質悪いよね、と言ってマホロは小さく笑った。
風が吹く。
ほんの少しだけ切なさを孕んだ風が、庭を揺らして、月にかかった雲を晴らす。
ひらり、と目の前を銀色に光る何かが横切った。
月白色の花弁が、ふわりと風に乗ってとんでいく。
月下美人の花弁だった。マホロのものではないと分かっていても、そのまま飛ばしてしまうのは惜しい気がして僕は手を伸ばす。
そんな僕を、マホロの声が制した。
「―――縁日」
少しだけ、咎めるような色を含んだその声に僕が振り向くと
思いのほか目の前に、マホロの顔があった。
拗ねた子どものような、それでいてどこかバツが悪そうな、そんな顔をして
身体には触れないように僕のシャツを掴んでいる。
「マホロ?」
「……なんでもない」
なんでもないけど……―――と、やっと聞き取れるくらいの声でそう言ったままマホロは気まずそうに視線をそらしてしまった。
そんなマホロが可愛くて思わず小さく笑うと、びくりと跳ねた肩が小さく震えて、マホロはますます拗ねたような顔をして下を俯いた。
僕のシャツに埋めた微かに見える頬が、桃のように染まっている。
「マホロ?どうしたの?」
「だからなんでもないってば。ばか」
そう言いながら、マホロは僕のシャツを掴む力を益々強めてしまった。
マホロに気付かれないように僕はまた笑って、すぐそばにあった梔子の花に手を伸ばした。
その花の花弁を一枚とって、マホロの前髪を中指の爪先でそっとよける。
また、マホロの薄い肩がびくりと跳ねた。
「マホロ」
「っ」
「マホロ。ねぇ、マホロ」
「な、に……」
「眞秀」
「っ!」
勢いよく顔を上げたその頬が、耳が、目元が、額が、赤くて。水を込めたような瞳が僕だけを映したまま泣きそうに震えていた。
「っ」
マホロの唇に、梔子の花弁を乗せた。
水分を含んだ睫毛が何かを察して小さく戸惑った後、それでもそっと伏せる。
一瞬、鼻先に梔子の香りがして、それでもそれはすぐに甘ったるい果実の香りに負けた。
熟しきって、熱せられて、融かされてしまったような桃のただ甘い香りがした。
しっとりとした梔子の花弁を一枚隔てた口付けが、その場にあった全ての音と香りを遮断する。
マホロの唇も、こんなふうにひんやりとしているのだろうか。
2人だけしかいない空間の中で僕は、そんなことを思った。