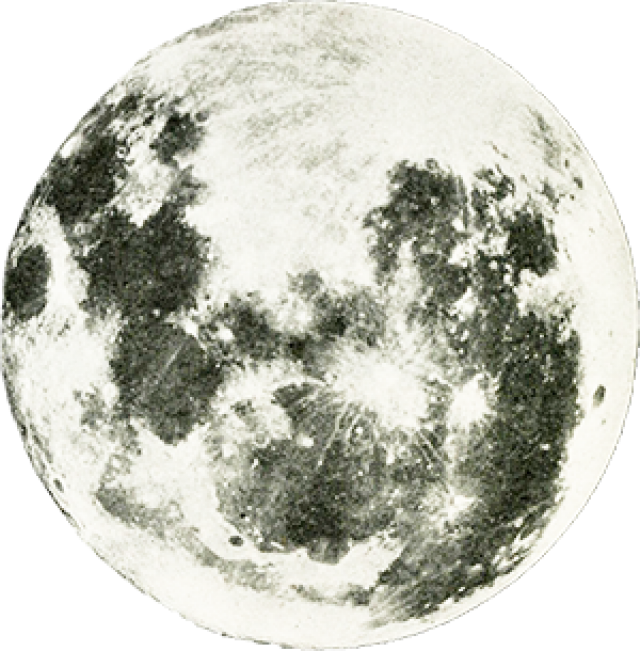-8-焦溶
文字数 4,731文字
南の方ではもう梅雨入りしたらしい。本州の梅雨入りはもう少し先になるだろうな、と
清々しいほどに晴れ渡った空を見上げながら、そんな今朝のニュースを僕は思い出していた。
「ふ、わぁ……」
今日何度目かの欠伸を噛み殺しながら、ホースの先端を軽く押し潰す。
扇状に広がった水が広範囲に広がっていく。日光と反射して虹を作り出しながら、庭のハーブを濡らしていった。
結局あの日から、書斎で夜を明かす生活を続けている。
マホロが毎日あそこで『食事』をしているかは分からないし、カーテンを閉じてしまえばいいとは思うけれど
なんだか少し、落ち着かないのだ。
脳裏にまだ、あの光景が残っている。
その光景がカーテン越しに行われているかと思うだけで、なんだかちょっと妙な気分になる、というか。
(親の情事を覗いてしまった、みたいな……)
親居ないから分かんないけど、と自分でつっこみながら、僕は静かに息を吐いた。
親の情事を覗くという行為が実際どういうものなのか、小説で読む以外の知識を僕が知る筈もないけれど、
でもきっと今感じているこの後ろめたさや気まずさは、それと同意だと思う。
ただの食事シーンではなかったのだ。
捕食―――あれは、捕食だったと思う。
残酷で美しい肉食獣に、捕らえられてしまったのだ。そして捕らえられたのは、薔薇の花だけではなかった。
「なんか変だ、僕……」
胸がざわつく。
その真意を解き明かそうと自分の思考を探ると、途端になんだか居た堪れなくなって、恥ずかしくなる。
そしていつも脳裏に残るのは、月明かりに発光する白い肌と、真っ赤なバラの花だった。
そわそわする―――それが一番しっくりくるかもしれない。
水滴を弾いて輝くハーブのその溌剌さに僕は小さく溜息を吐いて、蛇口の水を止めた。
少し遅れて止まるホースの口をぼんやりと見つめていると、桜の木の上で鶯がチチチ、と鳴いた。
「頑張るねぇ」
「っ!?……マ、ホロ!」
急に聞こえた声に後ろを振り返ると、廊下の軒下にマホロが腰掛けていた。
投げ出されて揺れる2本の足が、日陰の中で薄青色に光っている。
「びっくりし………誰、かと思った……」
驚いた僕を見てマホロは可笑しそうに「他に誰がいるのさ」と笑った。
その顔に『あの時』の妖しさは無い。僕は小さく、胸を撫で下ろした。
「そんなに根詰めてやらなくてもいいんだよ?」
「うん、でも息抜きも兼ねてるから」
「そう?ならいいけど」
十影がうるさそうだし、とは言わずにおいた。
ホースを片付ける僕の一挙手一投足をマホロがじっと見ている。
何かを探るようなその視線に堪らなくなって、僕はゆっくり後ろを振り向いた。
「な、なに、かな……」
「縁日はさ、何になりたいの?」
「えっ?」
「えっ?」
驚いた僕に驚いたように、マホロはその目を見開いた。
「何かになりたくて、勉強してるんじゃないのか」
「あー……うーん……んー?」
そういえば。考えたこともなかった、と。
伸びすぎたミントの葉を数枚摘んで蛇口で洗いながら、僕は首を捻った。
軽く水気のきったそれをマホロに手渡して隣に座る。
まるで砂糖菓子のようにミントを食べるマホロを見ても、『あの光景』は何故か浮かばなかった。
「僕、さ。修道院で育ったんだけど」
「うん。十影から聞いてるよ」
「不満とか不自由とかはなにもなくて。でもさすがに学校には通えなかったから、勉強って簡単な計算とか文字の読み書きとかしかやってこなかったんだけど……。修道院に十影が来るようになって色々教わって、それがすごく楽しくてさ」
それまでの13年間を、僕は十影と会ってからの数年で取り戻した。
残念ながら感受性を培うには13歳では遅すぎたらしかったけれど。
一応の常識は理解しているつもりだけれど、十影に言わせれば僕はやっぱり立派な『世間知らず』らしい。
「知らないことを知るのは、今でもすごく楽しいし面白いよ。“何かになりたい”と思うには、僕にはまだ、知らないことが多すぎると思うんだよね」
「そっか」
「うん。だから“何かになりたくて勉強してる”っていうよりは、ただ面白いから勉強してる―――だけ、かなぁ」
それに『面白い』と思うのは勉強の内容だけではなくて、真っ新な状態の脳に情報が足されていく感覚、だ。
昨日知らなかったことを、今日の僕は知っている。その感覚が、僕を毎日机に向かわせる理由のひとつだ。
「わっかんないなぁ、その気持ち」
ごろん、とそのまま後ろに背中を倒したマホロが少し投げやりにそう言った。
一番上のボタンが外されたベルトカラーのシャツから、真っ白な鎖骨が覗いている。
「俺もまぁこんなんだから学校とか行けなくて、十影に勉強教えてもらってたけど、面白いとか一回も思ったことなかったよ」
「そうなの?世界史とか面白いと思うけど……」
「だって、覚えたとこで意味ないしさ」
なんでもないように、マホロはそう言った。
自虐でも自嘲でもなく、そう答えるのが当たり前であるかのような言い方だった。
前までだったら笑えていたのかもしれない。けれど、僕はもう知ってしまっている。
長く生きることの出来ない花酔いが言う『意味がない』の重みを、感じてしまっている。
どう答えるべきか僕が迷っていると、寝ころんだままのマホロが可笑しそうに噴き出した。
「ごめんごめん!違うよ、縁日。“そういう意味”じゃなくてさ」
咽喉の奥で笑いを噛み殺しながら、マホロはその綺麗な瞳で僕を見上げた。
「ただ単に勉強嫌いなだけ。必要最低限の知識があれば成立する生活だしさ」
ほんの少し困ったような顔をして、マホロはそう言った。
途端に猛烈な自己嫌悪が僕を襲う。
「………ごめん」
「んん?なんで謝った?」
「だって……」
マホロを傷付けないようにすればするほど、からまわってしまう。
さっきの深読みも、日頃の下手糞な距離の測り方も。
気にしなくていいようなことまで気にして―――これでは、差別しているようなものだ。
それをどう伝えればいいのか考えているうちに、また小さな笑い声が聞こえた。
「マホロ……?」
「十影が言ってたでしょ?余計なこと考えなくていいって。あれ、別に十影が俺を突き放してるとかじゃないからね?」
上体を起こしながら、マホロがそう言った。
梅雨前の独特の熱を孕んだ空気の中、何故かひんやりとした風が緩やかに僕とマホロの間を通っていく。
「自分が花酔いだからどうとか、普通の人間だったらなぁとか考えたこと本当にないんだよ。俺は俺だし、自分のしたいことをして生きてるつもり。だから縁日もそんなに構えないでよ」
また、あの笑顔だった。
容姿と言動がちくはぐなマホロがたまに見せる、容姿通りの完璧な笑顔だ。
その笑顔に、十影の苦し気な顔が重なる。
「って言っても縁日は、“花酔い”ってやっぱり気になっちゃうかもしれないけど」
「そっ、そんなこと、ない!」
勢いよく立ち上がった僕を、驚いたような顔でマホロが見上げた。
「え、縁日……?」
「ご、ごめん!あの、違くて!違う……くて、ですね!」
「うん?」
「花酔いとかたぶんちょっとは気にしてるんだと思う。だけど、そうじゃなくて…‥怖いとか、接し方が分からないとかそういうんじゃなくて……」
触れたら感染するかもしれない。発症例がないだけで、飛沫感染の可能性だってあるのかもしれない。
懸念がそんな類のものだったら、僕はきっともうマホロに触れてしまっている。
けれどそうじゃないのだ。
もし、触れてしまったら。
傷を負うのは、僕ではなく、マホロだ。
ただそれだけが、僕がマホロにとってしまう不自然な距離の理由だった。マホロの前で、気を抜けない理由のひとつだった。
「マホロが綺麗だから」
「………え?」
「マホロが綺麗だから触れそうになるんだ。でもそんなことしたら怪我するのはマホロだし、だから安易に近づけないというか気を抜けないというか、ただ本当にそれだけで、花酔いが怖いとか嫌とかじゃないから!」
そこまでを一息に言い切って、僕は大きく息を吸い込んだ。
「マホロのこと、大事にしたいだけだよ!」
僕を見上げて大きく見開かれたままのその瞳に、じんわりと水の膜が張っていた。
まるで清流の水でも閉じ込めたようにアクアマリン色の瞳が微かに揺らめいている。
春のような乾いた風に月白色の髪が靡いて、その目元を隠してしまう。
ただその隙間から覗いた真っ新な頬が、いつものように透き通ることなく、仄かに赤味が差して見えた。
「………ば」
薄く開いた唇から吐き出されたその声は、可笑しいくらいに震えていた。
「ばかじゃないの!」
いつものマホロらしくない、そんな言葉を吐いて立ち上がるとマホロは速足で桜の木陰に這入って行ってしまった。
「ま、マホロ……さん?」
「うるっさい!」
「えぇ……」
「―――お前ら馬鹿だろ」
ふいに聞こえた声に、僕は後ろを振り向いた。
エントランスに繋がる廊下に、心底呆れたような顔をした十影が立っている。
「十影!」
「十影“さん”な。ったくお前は……」
ほら、と手渡されたのは小さなケーキボックスだった。
「ケーキだ!」
「茶淹れてくるから、お前それ持って自分の部屋の窓開けてこい」
「当たり前のように僕の部屋使うね」
「ちゃんと片付けてるか確認な」
「してるよ」
「どうだか」
柔らかく笑って僕の頭を撫でると、十影は視線をマホロのほうに投げた。
「マホロも―――“それ”治まったら来いよ」
「分かってるよ……」
「マホロ……?」
両手で頬を抑えながらこちらを振り向いたマホロは、ほんの少しだけ不機嫌そうな顔をしていた。
やっぱりその頬は、太陽の光を受けてもいつものように光ることなく微かに赤味を差している。
そこで僕ははっとした。
「マホロ大変!はやく部屋の中這入って!」
「え?」
「ごめん。今日暑いのに、全然気にしてなかった……」
「え、ちょ、なに?」
「なにってマホロ、逆上せたんでしょ?」
「ぶっ……」
僕の背後で十影が激しく噴き出した。
マホロはというと、その眉間の皺をより濃くしてバツが悪そうにこちらを見ている。
心なしか、その頬の赤さが顔全体に広がったように見える。
「十影、笑い過ぎ」
「いや……っ…だっ……笑うだろ……まじか……縁、お前まじか……」
「え?なに?」
「もういいから!縁日もはやく行って!十影もいい加減にしろよ」
「あっはは、ひひ」
笑いながら十影は廊下の奥に消えて行ってしまった。
また、空間に2人が取り残される。
けれどそこにある空気が、さっきまでとは明らかに違っていた。
それが何かは分からなかったけれど。
乾いた風が、庭の緑を揺らして去っていく。
じゅわり、と桃の熟したような匂いがした。
「マホロ……?」
「本当に……なんでもないよ。大丈夫」
「ならいいけど……」
「さきに行ってて。もう少ししたら俺も行くから」
「……分かった」
僕が頷くとマホロは小さく笑って、くるりと背を向けてしまった。
桜の木を見上げるその後ろ姿が風に靡く。
また、あの甘い香りがした。
揺れる緑の中で、月白色がきらきらと光る。
その毛先から、またあの桃色の花弁が風に零れたような気がした。
清々しいほどに晴れ渡った空を見上げながら、そんな今朝のニュースを僕は思い出していた。
「ふ、わぁ……」
今日何度目かの欠伸を噛み殺しながら、ホースの先端を軽く押し潰す。
扇状に広がった水が広範囲に広がっていく。日光と反射して虹を作り出しながら、庭のハーブを濡らしていった。
結局あの日から、書斎で夜を明かす生活を続けている。
マホロが毎日あそこで『食事』をしているかは分からないし、カーテンを閉じてしまえばいいとは思うけれど
なんだか少し、落ち着かないのだ。
脳裏にまだ、あの光景が残っている。
その光景がカーテン越しに行われているかと思うだけで、なんだかちょっと妙な気分になる、というか。
(親の情事を覗いてしまった、みたいな……)
親居ないから分かんないけど、と自分でつっこみながら、僕は静かに息を吐いた。
親の情事を覗くという行為が実際どういうものなのか、小説で読む以外の知識を僕が知る筈もないけれど、
でもきっと今感じているこの後ろめたさや気まずさは、それと同意だと思う。
ただの食事シーンではなかったのだ。
捕食―――あれは、捕食だったと思う。
残酷で美しい肉食獣に、捕らえられてしまったのだ。そして捕らえられたのは、薔薇の花だけではなかった。
「なんか変だ、僕……」
胸がざわつく。
その真意を解き明かそうと自分の思考を探ると、途端になんだか居た堪れなくなって、恥ずかしくなる。
そしていつも脳裏に残るのは、月明かりに発光する白い肌と、真っ赤なバラの花だった。
そわそわする―――それが一番しっくりくるかもしれない。
水滴を弾いて輝くハーブのその溌剌さに僕は小さく溜息を吐いて、蛇口の水を止めた。
少し遅れて止まるホースの口をぼんやりと見つめていると、桜の木の上で鶯がチチチ、と鳴いた。
「頑張るねぇ」
「っ!?……マ、ホロ!」
急に聞こえた声に後ろを振り返ると、廊下の軒下にマホロが腰掛けていた。
投げ出されて揺れる2本の足が、日陰の中で薄青色に光っている。
「びっくりし………誰、かと思った……」
驚いた僕を見てマホロは可笑しそうに「他に誰がいるのさ」と笑った。
その顔に『あの時』の妖しさは無い。僕は小さく、胸を撫で下ろした。
「そんなに根詰めてやらなくてもいいんだよ?」
「うん、でも息抜きも兼ねてるから」
「そう?ならいいけど」
十影がうるさそうだし、とは言わずにおいた。
ホースを片付ける僕の一挙手一投足をマホロがじっと見ている。
何かを探るようなその視線に堪らなくなって、僕はゆっくり後ろを振り向いた。
「な、なに、かな……」
「縁日はさ、何になりたいの?」
「えっ?」
「えっ?」
驚いた僕に驚いたように、マホロはその目を見開いた。
「何かになりたくて、勉強してるんじゃないのか」
「あー……うーん……んー?」
そういえば。考えたこともなかった、と。
伸びすぎたミントの葉を数枚摘んで蛇口で洗いながら、僕は首を捻った。
軽く水気のきったそれをマホロに手渡して隣に座る。
まるで砂糖菓子のようにミントを食べるマホロを見ても、『あの光景』は何故か浮かばなかった。
「僕、さ。修道院で育ったんだけど」
「うん。十影から聞いてるよ」
「不満とか不自由とかはなにもなくて。でもさすがに学校には通えなかったから、勉強って簡単な計算とか文字の読み書きとかしかやってこなかったんだけど……。修道院に十影が来るようになって色々教わって、それがすごく楽しくてさ」
それまでの13年間を、僕は十影と会ってからの数年で取り戻した。
残念ながら感受性を培うには13歳では遅すぎたらしかったけれど。
一応の常識は理解しているつもりだけれど、十影に言わせれば僕はやっぱり立派な『世間知らず』らしい。
「知らないことを知るのは、今でもすごく楽しいし面白いよ。“何かになりたい”と思うには、僕にはまだ、知らないことが多すぎると思うんだよね」
「そっか」
「うん。だから“何かになりたくて勉強してる”っていうよりは、ただ面白いから勉強してる―――だけ、かなぁ」
それに『面白い』と思うのは勉強の内容だけではなくて、真っ新な状態の脳に情報が足されていく感覚、だ。
昨日知らなかったことを、今日の僕は知っている。その感覚が、僕を毎日机に向かわせる理由のひとつだ。
「わっかんないなぁ、その気持ち」
ごろん、とそのまま後ろに背中を倒したマホロが少し投げやりにそう言った。
一番上のボタンが外されたベルトカラーのシャツから、真っ白な鎖骨が覗いている。
「俺もまぁこんなんだから学校とか行けなくて、十影に勉強教えてもらってたけど、面白いとか一回も思ったことなかったよ」
「そうなの?世界史とか面白いと思うけど……」
「だって、覚えたとこで意味ないしさ」
なんでもないように、マホロはそう言った。
自虐でも自嘲でもなく、そう答えるのが当たり前であるかのような言い方だった。
前までだったら笑えていたのかもしれない。けれど、僕はもう知ってしまっている。
長く生きることの出来ない花酔いが言う『意味がない』の重みを、感じてしまっている。
どう答えるべきか僕が迷っていると、寝ころんだままのマホロが可笑しそうに噴き出した。
「ごめんごめん!違うよ、縁日。“そういう意味”じゃなくてさ」
咽喉の奥で笑いを噛み殺しながら、マホロはその綺麗な瞳で僕を見上げた。
「ただ単に勉強嫌いなだけ。必要最低限の知識があれば成立する生活だしさ」
ほんの少し困ったような顔をして、マホロはそう言った。
途端に猛烈な自己嫌悪が僕を襲う。
「………ごめん」
「んん?なんで謝った?」
「だって……」
マホロを傷付けないようにすればするほど、からまわってしまう。
さっきの深読みも、日頃の下手糞な距離の測り方も。
気にしなくていいようなことまで気にして―――これでは、差別しているようなものだ。
それをどう伝えればいいのか考えているうちに、また小さな笑い声が聞こえた。
「マホロ……?」
「十影が言ってたでしょ?余計なこと考えなくていいって。あれ、別に十影が俺を突き放してるとかじゃないからね?」
上体を起こしながら、マホロがそう言った。
梅雨前の独特の熱を孕んだ空気の中、何故かひんやりとした風が緩やかに僕とマホロの間を通っていく。
「自分が花酔いだからどうとか、普通の人間だったらなぁとか考えたこと本当にないんだよ。俺は俺だし、自分のしたいことをして生きてるつもり。だから縁日もそんなに構えないでよ」
また、あの笑顔だった。
容姿と言動がちくはぐなマホロがたまに見せる、容姿通りの完璧な笑顔だ。
その笑顔に、十影の苦し気な顔が重なる。
「って言っても縁日は、“花酔い”ってやっぱり気になっちゃうかもしれないけど」
「そっ、そんなこと、ない!」
勢いよく立ち上がった僕を、驚いたような顔でマホロが見上げた。
「え、縁日……?」
「ご、ごめん!あの、違くて!違う……くて、ですね!」
「うん?」
「花酔いとかたぶんちょっとは気にしてるんだと思う。だけど、そうじゃなくて…‥怖いとか、接し方が分からないとかそういうんじゃなくて……」
触れたら感染するかもしれない。発症例がないだけで、飛沫感染の可能性だってあるのかもしれない。
懸念がそんな類のものだったら、僕はきっともうマホロに触れてしまっている。
けれどそうじゃないのだ。
もし、触れてしまったら。
傷を負うのは、僕ではなく、マホロだ。
ただそれだけが、僕がマホロにとってしまう不自然な距離の理由だった。マホロの前で、気を抜けない理由のひとつだった。
「マホロが綺麗だから」
「………え?」
「マホロが綺麗だから触れそうになるんだ。でもそんなことしたら怪我するのはマホロだし、だから安易に近づけないというか気を抜けないというか、ただ本当にそれだけで、花酔いが怖いとか嫌とかじゃないから!」
そこまでを一息に言い切って、僕は大きく息を吸い込んだ。
「マホロのこと、大事にしたいだけだよ!」
僕を見上げて大きく見開かれたままのその瞳に、じんわりと水の膜が張っていた。
まるで清流の水でも閉じ込めたようにアクアマリン色の瞳が微かに揺らめいている。
春のような乾いた風に月白色の髪が靡いて、その目元を隠してしまう。
ただその隙間から覗いた真っ新な頬が、いつものように透き通ることなく、仄かに赤味が差して見えた。
「………ば」
薄く開いた唇から吐き出されたその声は、可笑しいくらいに震えていた。
「ばかじゃないの!」
いつものマホロらしくない、そんな言葉を吐いて立ち上がるとマホロは速足で桜の木陰に這入って行ってしまった。
「ま、マホロ……さん?」
「うるっさい!」
「えぇ……」
「―――お前ら馬鹿だろ」
ふいに聞こえた声に、僕は後ろを振り向いた。
エントランスに繋がる廊下に、心底呆れたような顔をした十影が立っている。
「十影!」
「十影“さん”な。ったくお前は……」
ほら、と手渡されたのは小さなケーキボックスだった。
「ケーキだ!」
「茶淹れてくるから、お前それ持って自分の部屋の窓開けてこい」
「当たり前のように僕の部屋使うね」
「ちゃんと片付けてるか確認な」
「してるよ」
「どうだか」
柔らかく笑って僕の頭を撫でると、十影は視線をマホロのほうに投げた。
「マホロも―――“それ”治まったら来いよ」
「分かってるよ……」
「マホロ……?」
両手で頬を抑えながらこちらを振り向いたマホロは、ほんの少しだけ不機嫌そうな顔をしていた。
やっぱりその頬は、太陽の光を受けてもいつものように光ることなく微かに赤味を差している。
そこで僕ははっとした。
「マホロ大変!はやく部屋の中這入って!」
「え?」
「ごめん。今日暑いのに、全然気にしてなかった……」
「え、ちょ、なに?」
「なにってマホロ、逆上せたんでしょ?」
「ぶっ……」
僕の背後で十影が激しく噴き出した。
マホロはというと、その眉間の皺をより濃くしてバツが悪そうにこちらを見ている。
心なしか、その頬の赤さが顔全体に広がったように見える。
「十影、笑い過ぎ」
「いや……っ…だっ……笑うだろ……まじか……縁、お前まじか……」
「え?なに?」
「もういいから!縁日もはやく行って!十影もいい加減にしろよ」
「あっはは、ひひ」
笑いながら十影は廊下の奥に消えて行ってしまった。
また、空間に2人が取り残される。
けれどそこにある空気が、さっきまでとは明らかに違っていた。
それが何かは分からなかったけれど。
乾いた風が、庭の緑を揺らして去っていく。
じゅわり、と桃の熟したような匂いがした。
「マホロ……?」
「本当に……なんでもないよ。大丈夫」
「ならいいけど……」
「さきに行ってて。もう少ししたら俺も行くから」
「……分かった」
僕が頷くとマホロは小さく笑って、くるりと背を向けてしまった。
桜の木を見上げるその後ろ姿が風に靡く。
また、あの甘い香りがした。
揺れる緑の中で、月白色がきらきらと光る。
その毛先から、またあの桃色の花弁が風に零れたような気がした。