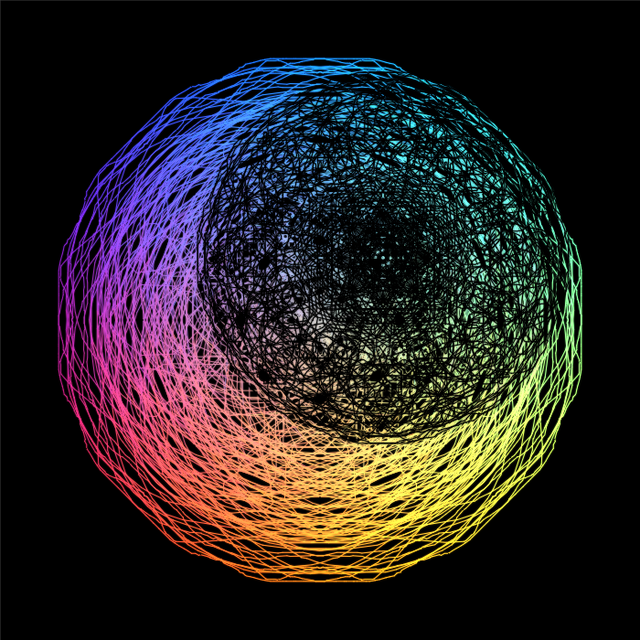14. 机上にて、赤の暴虐
文字数 4,399文字
バルコニーに続く大窓の前に、胸ぐらいの高さの氷柱 が三本生えている。
先の丸まった形は本の挿絵で見た石筍に似ていて、磨り硝子のように半透明の表面は、レースのカーテンが翻るたびに陽光を受けぼんやり輝く。日常に非日常が混ざりこむ、なんだかわくわくする光景だった。
アマリリスの部屋には風の魔晶を嵌めた設置型の術具があり、窓から窓、そして開け放った扉に優しい気流を作り出している。風は最初に氷柱の間を吹き抜け、涼気を含んで部屋全体をほどよく冷やす。
真昼は風だけだと暑さを誤魔化せなくなってきて、へばるアマリリスを見かねたフロウが出してくれたのだ。世話を掛けてばかりで彼には申し訳ない。
(溶けない氷かぁ。契約してるうちに私もやってみたいけど、時間が足りなそうね。……もう残り一月半を切ってるんだもの)
正面に視線を戻す。フロウはテーブルを挟んだ向かいで、透明な身体から伸びたでっぱりで白い駒をつまんでゆらゆらしている。
あちら、こちら、と彷徨っていたそれが、不意にぴたりと止まって、六角形の盤上に駒を置いた。
「うん……? オレの負けか?」
「私がここに置いて、決着ねぇ」
アマリリスも赤の駒を取り、盤の格子の決定的 な一点にそっと乗せた。
白は駒を置くことも動かすこともできなくなって、赤の勝ち。
「難しいな」
「どう? ゲーム、面白い?」
「まだなんとも。ただ……エドウィンといたときは縁がなかったから、新鮮だ」
興ずるは、貴族のサロンから町の子供まで広く親しまれる、二人対戦のボードゲーム。赤と白で盤面を制し合う陣取りの一種だ。屋敷にあるセットは堅い木を何度も染めて磨いた品で、鏡面のような漆黒の盤に入り乱れる二色、それぞれに浮かんだ木目が美しい。
せっかく彼と話す時間ができて、熟考した質問を喉元まで持ってきても、『まだこれを訊くには早いのでは』と逡巡してしまう。そんなことを繰り返して数回。いい加減アマリリスは自分の優柔不断さを見限った。
考えすぎるからいけないんだ、もっと気軽なところから始めよう。
というわけで息抜きに――そして歴史の件以来なにも見返りを求めてくれないフロウにせめて楽しんでもらうため、駒を戦わせながらお喋りしているのだった。
「エドウィンさんとはこういうのしなかったのね」
「研究が趣味のような奴で、他のことはあまり。酒に付き合ったりはした。オレは酔わないが」
「わぁ、ストランジ の家系みたい……他人事とは思えないわねぇ」
取り留めのないことを、思い浮かぶままに問い掛ければ、フロウは機嫌を損ねることもなく教えてくれた。
例えば昔、数十年も王都で魔術師と暮らしていたこと。
魔術に関する知識はその人の講釈から得たこと。
エドウィンというのが、その元同居人の名である。
「というか、あなたって何歳なのかしら」
「正確には分からない。あいつの当時の見立てだと、今は……三百五十くらいか」
「さんびゃっ!?」
人の寿命からしたら、あまりに壮大な時間だ。けれど精霊は歳を重ねるほど姿形がはっきりすると言われている。仮に実体を持つのがその延長線上にあるなら、永く生きていると言われた方が納得できる――かも。
フロウはこちらの驚愕にも我関せずで、盤に置かれた白の駒だけをちょんちょんと拾い上げていく。花びらみたいに散った赤の駒をアマリリスがかき集めたら、机上のフィールドはまっさらになった。
盤外に行儀よく駒を並べ終え、椅子に乗った水はぴたりと動きを止める。失礼な想像だけれど。遊んでほしそうな仔犬の幻が重なって見える。
「……もう一回やる?」
「やる」
結局その後、五戦した。
アマリリスの全勝だった。
◆
「勝てない……」
透明な腕先が駒を弄 んで、ぽそんと呟いた。
別の細いでっぱりがグラスからハーブティーを吸い上げる。液体はフロウの無色の身体の中に幾つもの檸檬石 の玉となって浮かび、混ざり合わぬまま徐々に薄れて消えていく。
なんとも不可思議で美しい。だが、アマリリスの内心はそれどころではなかった。
(や、やらかしたわぁ……!)
痛恨のミスだ。彼に初めてのゲームを満喫してもらうはずだったのに。
けして勝利の快感に酔って本気で圧倒したわけではない。というかアマリリスは本気を出してもそんなに強くない。この前なんて九歳の弟に負けたほどだ。
だが習熟していないことが逆に仇となった。
ルールを覚えたばかりの相手に、しかも雑談しながら、適度に勝ったり負けたりできる腕がなかったのである。
「リィリ、これはどうやったら勝てるんだ」
フロウは駒を持ったままふよんと震える。声音は普段通りだが、しょげているように見えてきて良心が疼いた。
「え、えぇとね、一番は慣れよ。けれど、すぐに上手くなりたいのなら戦術や定跡を覚えるのがいいかも」
「なるほど。教えてくれるか?」
「んんん、実は私もあまり詳しくなくて。ノアも運の絡まないゲームは苦手だって言ってたし……」
答えながら、表情を持たない水の姿の精霊をじぃっと凝視する。
(……うぅん。落ち込んでると思ったのは、先入観かもしれないわぁ。辛そうな感じはしないもの)
負けて悔しいのではなく、本当に負けた理由と勝ち筋が知りたいだけ、なのだろうか。それなら挽回の余地はあるのだけれど。
足音を殺す猫の気持ちで、彼の様子に神経を集中する。
「ジェフリーはどうかしら。なんだかあの人、強そうじゃない?」
「そうか。次に見回りに付いていくときあいつに訊いてみる」
ふむ、と頷くように揺れて、フロウは駒を箱の中にしまった。すぐに答えが得られたわけではないけれど、彼の身体は少し張りが良くなって満足げな――気がする。
アマリリスはほっと背もたれに体重を預けて、銀の取っ手のついた綺麗な硝子瓶から空のグラスに中身を注いだ。手汗が滑り、瓶を取り落としそうになった。
とろりと綺麗なアイスハーブティーはノアが淹れていってくれたものだ。甘い香りと鼻に抜ける爽快感を楽しみながら口をつければ、きゅっと鼻筋に皺が寄る。
すっぱい。けれど舌はすぐに慣れて、ライムの酸味が喉通りも良く滑り降りていく。
「そうだ。やり方が分かったら、それで勝てるか試したい。今度また相手をしてくれ」
「んっ……けほっ、んんっ! ……えぇ、またやりましょ!」
油断したところに不意打ちを食らって、ひどくむせた。
――もう残り一月半、だ。
アマリリスは彼の核心にほとんど触れられておらず、望みを知らず、投げ掛けたのは当たり障りのない質問ばかり。
(それでも……あなたにとって少しは意味のある時間になっていると、思ってもいいの?)
いまだフロウには貰う一方で、アマリリスは大したものを返せていない。そんな中で、彼から『また』を請われることが、どれだけ嬉しいか。
心配そうに伸び上がってこちらを伺ってくれるフロウ本人にだって、想像もつかないに違いない。
◆
「納涼の宴……」
「そう。夏の最初の新月の晩、暑さが厳しくなる前にぱぁっと宴会をするの」
今夏は、明後日がその日にあたる。
納涼の宴は、建国祭や収穫祭、新年祭といった大がかりなイベントではない。『家族や仲間と楽しく飲んで、今夏も元気に乗り切ろう』というこの地方の慣習のようなものだ。とはいえ食堂や物売りがこぞって屋台を出すから、町は昼から賑やかになる。
屋敷でも、宴会まではしないけれど、美味しくて精のつく季節料理を食べようと話していた。
「きっと冷製のスープも出るし、お酒もあるわぁ。……酔わないって言ってたけれど、味が嫌じゃないなら飲んでみてね」
「是非とも。楽しみだ」
「ノアも、そのために料理番と町に行ってるのよ」
「だから誰もいないのか」
ジェフリーも買い出しに随行している。つまり、今ここにいるのはフロウとアマリリスだけ。
――ただし扉を全開にし、室内が廊下から見えるようにしてある。ボードゲームで遊ぶ水精は、通りがかった家の者を唖然とさせていた。
魔物狩りと、さらに見回りへの協力を経て、フロウの行動制限はだいぶ緩和された。具体的には人目のない場所で二人きりにならなければいいことになった。
けどそれは、ノアが彼を信用してくれたんじゃない。外敵への備えを優先したから、護衛の代わりになるからだ。
「……フロウ。傍についていてくれてありがとう。それに、ごめんなさい」
「ごめん?」
フロウはきょとんと復唱する。
ここ数日アマリリスは、別荘の敷地から出ないよう言い含められている。学生の本分である毎日の訓練だって屋敷の裏手でひっそり行うのみ。
そんな生活に彼も合わせてくれるため、日中はどうしても部屋に籠りがちだった。
「ずっと家にいるの、好きでないでしょ?」
「どうして」
「どうしてって、そのぅ、屋内は魔力も弱いし」
「…………」
なんだか困ったふうにフロウは押し黙ってしまう。
そうしてしばらく言葉を迷うような間があって、前触れなく水の身体がするする伸びてきた。
蛇のごとき透明の腕はテーブルごしにアマリリスの右手をつつき、くるんと絡みついてくる。
「ふゃ!?」
心臓が跳ねる。その早まった鼓動のままに――緊張がとろけた。
ひんやりした水は指を濡らすことなく、柔らかく馴染む。少し引っ張ったら千切れてしまいそうな頼りない感触なのに、帯びた魔力は深く、肌に沿って手の全体を包んでいる。
ただ触れているだけ。それだけで、さながら春の泉に小舟を浮かべたように、身体が和らいでいく。
「リィリ。精霊 は自分で望まないことを嫌々やったりしない。契約も、今一緒にいるのも、したいからしている」
「ぇ、と。でも、」
「無理してお前に合わせている、なんてことはない」
とくん。
とん、とくん。
凪の水面に、仄かな心音がまあるく波打っている。
(私が食い下がったから、仕方なく期限付きの契約に付き合ってくれているんじゃないの……? だって、最初は断ったんだもの。そうでないなら、)
期待してしまいそうになる。
契約に応じられない理由がぽんと無造作に置いてあって、それさえどければずっと一緒にいてくれるのでは。なんて。
「……ありがとう。あなたが嫌な思いをしていないなら、良かったわぁ」
「ん」
でもそんな考え自体、最初に契約を迫った時と同じくアマリリスの身勝手だ。
(願望を押し付けてどうするの。人の心を都合良く解釈しちゃだめ)
きゅ、と、指に纏わる水を一度、握り返す。
フロウはくすぐったそうに震え、手の形をなぞり離れていった。
◆
◆
◆
【魔晶】
自然から産出される、物質化した魔力の塊を魔晶といいます。比喩的に結晶と表現されますが鉱物ではありません。
火水地風の四属性があり、属性の力が偏った環境から、その属性の魔晶が採れることが多いです。(活火山から火の魔晶が採れるなど)
また生物の体内から無属性の魔晶が採れることがありますが、非常に希少です。
先の丸まった形は本の挿絵で見た石筍に似ていて、磨り硝子のように半透明の表面は、レースのカーテンが翻るたびに陽光を受けぼんやり輝く。日常に非日常が混ざりこむ、なんだかわくわくする光景だった。
アマリリスの部屋には風の魔晶を嵌めた設置型の術具があり、窓から窓、そして開け放った扉に優しい気流を作り出している。風は最初に氷柱の間を吹き抜け、涼気を含んで部屋全体をほどよく冷やす。
真昼は風だけだと暑さを誤魔化せなくなってきて、へばるアマリリスを見かねたフロウが出してくれたのだ。世話を掛けてばかりで彼には申し訳ない。
(溶けない氷かぁ。契約してるうちに私もやってみたいけど、時間が足りなそうね。……もう残り一月半を切ってるんだもの)
正面に視線を戻す。フロウはテーブルを挟んだ向かいで、透明な身体から伸びたでっぱりで白い駒をつまんでゆらゆらしている。
あちら、こちら、と彷徨っていたそれが、不意にぴたりと止まって、六角形の盤上に駒を置いた。
「うん……? オレの負けか?」
「私がここに置いて、決着ねぇ」
アマリリスも赤の駒を取り、盤の格子の
白は駒を置くことも動かすこともできなくなって、赤の勝ち。
「難しいな」
「どう? ゲーム、面白い?」
「まだなんとも。ただ……エドウィンといたときは縁がなかったから、新鮮だ」
興ずるは、貴族のサロンから町の子供まで広く親しまれる、二人対戦のボードゲーム。赤と白で盤面を制し合う陣取りの一種だ。屋敷にあるセットは堅い木を何度も染めて磨いた品で、鏡面のような漆黒の盤に入り乱れる二色、それぞれに浮かんだ木目が美しい。
せっかく彼と話す時間ができて、熟考した質問を喉元まで持ってきても、『まだこれを訊くには早いのでは』と逡巡してしまう。そんなことを繰り返して数回。いい加減アマリリスは自分の優柔不断さを見限った。
考えすぎるからいけないんだ、もっと気軽なところから始めよう。
というわけで息抜きに――そして歴史の件以来なにも見返りを求めてくれないフロウにせめて楽しんでもらうため、駒を戦わせながらお喋りしているのだった。
「エドウィンさんとはこういうのしなかったのね」
「研究が趣味のような奴で、他のことはあまり。酒に付き合ったりはした。オレは酔わないが」
「わぁ、
取り留めのないことを、思い浮かぶままに問い掛ければ、フロウは機嫌を損ねることもなく教えてくれた。
例えば昔、数十年も王都で魔術師と暮らしていたこと。
魔術に関する知識はその人の講釈から得たこと。
エドウィンというのが、その元同居人の名である。
「というか、あなたって何歳なのかしら」
「正確には分からない。あいつの当時の見立てだと、今は……三百五十くらいか」
「さんびゃっ!?」
人の寿命からしたら、あまりに壮大な時間だ。けれど精霊は歳を重ねるほど姿形がはっきりすると言われている。仮に実体を持つのがその延長線上にあるなら、永く生きていると言われた方が納得できる――かも。
フロウはこちらの驚愕にも我関せずで、盤に置かれた白の駒だけをちょんちょんと拾い上げていく。花びらみたいに散った赤の駒をアマリリスがかき集めたら、机上のフィールドはまっさらになった。
盤外に行儀よく駒を並べ終え、椅子に乗った水はぴたりと動きを止める。失礼な想像だけれど。遊んでほしそうな仔犬の幻が重なって見える。
「……もう一回やる?」
「やる」
結局その後、五戦した。
アマリリスの全勝だった。
◆
「勝てない……」
透明な腕先が駒を
別の細いでっぱりがグラスからハーブティーを吸い上げる。液体はフロウの無色の身体の中に幾つもの
なんとも不可思議で美しい。だが、アマリリスの内心はそれどころではなかった。
(や、やらかしたわぁ……!)
痛恨のミスだ。彼に初めてのゲームを満喫してもらうはずだったのに。
けして勝利の快感に酔って本気で圧倒したわけではない。というかアマリリスは本気を出してもそんなに強くない。この前なんて九歳の弟に負けたほどだ。
だが習熟していないことが逆に仇となった。
ルールを覚えたばかりの相手に、しかも雑談しながら、適度に勝ったり負けたりできる腕がなかったのである。
「リィリ、これはどうやったら勝てるんだ」
フロウは駒を持ったままふよんと震える。声音は普段通りだが、しょげているように見えてきて良心が疼いた。
「え、えぇとね、一番は慣れよ。けれど、すぐに上手くなりたいのなら戦術や定跡を覚えるのがいいかも」
「なるほど。教えてくれるか?」
「んんん、実は私もあまり詳しくなくて。ノアも運の絡まないゲームは苦手だって言ってたし……」
答えながら、表情を持たない水の姿の精霊をじぃっと凝視する。
(……うぅん。落ち込んでると思ったのは、先入観かもしれないわぁ。辛そうな感じはしないもの)
負けて悔しいのではなく、本当に負けた理由と勝ち筋が知りたいだけ、なのだろうか。それなら挽回の余地はあるのだけれど。
足音を殺す猫の気持ちで、彼の様子に神経を集中する。
「ジェフリーはどうかしら。なんだかあの人、強そうじゃない?」
「そうか。次に見回りに付いていくときあいつに訊いてみる」
ふむ、と頷くように揺れて、フロウは駒を箱の中にしまった。すぐに答えが得られたわけではないけれど、彼の身体は少し張りが良くなって満足げな――気がする。
アマリリスはほっと背もたれに体重を預けて、銀の取っ手のついた綺麗な硝子瓶から空のグラスに中身を注いだ。手汗が滑り、瓶を取り落としそうになった。
とろりと綺麗なアイスハーブティーはノアが淹れていってくれたものだ。甘い香りと鼻に抜ける爽快感を楽しみながら口をつければ、きゅっと鼻筋に皺が寄る。
すっぱい。けれど舌はすぐに慣れて、ライムの酸味が喉通りも良く滑り降りていく。
「そうだ。やり方が分かったら、それで勝てるか試したい。今度また相手をしてくれ」
「んっ……けほっ、んんっ! ……えぇ、またやりましょ!」
油断したところに不意打ちを食らって、ひどくむせた。
――もう残り一月半、だ。
アマリリスは彼の核心にほとんど触れられておらず、望みを知らず、投げ掛けたのは当たり障りのない質問ばかり。
(それでも……あなたにとって少しは意味のある時間になっていると、思ってもいいの?)
いまだフロウには貰う一方で、アマリリスは大したものを返せていない。そんな中で、彼から『また』を請われることが、どれだけ嬉しいか。
心配そうに伸び上がってこちらを伺ってくれるフロウ本人にだって、想像もつかないに違いない。
◆
「納涼の宴……」
「そう。夏の最初の新月の晩、暑さが厳しくなる前にぱぁっと宴会をするの」
今夏は、明後日がその日にあたる。
納涼の宴は、建国祭や収穫祭、新年祭といった大がかりなイベントではない。『家族や仲間と楽しく飲んで、今夏も元気に乗り切ろう』というこの地方の慣習のようなものだ。とはいえ食堂や物売りがこぞって屋台を出すから、町は昼から賑やかになる。
屋敷でも、宴会まではしないけれど、美味しくて精のつく季節料理を食べようと話していた。
「きっと冷製のスープも出るし、お酒もあるわぁ。……酔わないって言ってたけれど、味が嫌じゃないなら飲んでみてね」
「是非とも。楽しみだ」
「ノアも、そのために料理番と町に行ってるのよ」
「だから誰もいないのか」
ジェフリーも買い出しに随行している。つまり、今ここにいるのはフロウとアマリリスだけ。
――ただし扉を全開にし、室内が廊下から見えるようにしてある。ボードゲームで遊ぶ水精は、通りがかった家の者を唖然とさせていた。
魔物狩りと、さらに見回りへの協力を経て、フロウの行動制限はだいぶ緩和された。具体的には人目のない場所で二人きりにならなければいいことになった。
けどそれは、ノアが彼を信用してくれたんじゃない。外敵への備えを優先したから、護衛の代わりになるからだ。
「……フロウ。傍についていてくれてありがとう。それに、ごめんなさい」
「ごめん?」
フロウはきょとんと復唱する。
ここ数日アマリリスは、別荘の敷地から出ないよう言い含められている。学生の本分である毎日の訓練だって屋敷の裏手でひっそり行うのみ。
そんな生活に彼も合わせてくれるため、日中はどうしても部屋に籠りがちだった。
「ずっと家にいるの、好きでないでしょ?」
「どうして」
「どうしてって、そのぅ、屋内は魔力も弱いし」
「…………」
なんだか困ったふうにフロウは押し黙ってしまう。
そうしてしばらく言葉を迷うような間があって、前触れなく水の身体がするする伸びてきた。
蛇のごとき透明の腕はテーブルごしにアマリリスの右手をつつき、くるんと絡みついてくる。
「ふゃ!?」
心臓が跳ねる。その早まった鼓動のままに――緊張がとろけた。
ひんやりした水は指を濡らすことなく、柔らかく馴染む。少し引っ張ったら千切れてしまいそうな頼りない感触なのに、帯びた魔力は深く、肌に沿って手の全体を包んでいる。
ただ触れているだけ。それだけで、さながら春の泉に小舟を浮かべたように、身体が和らいでいく。
「リィリ。
「ぇ、と。でも、」
「無理してお前に合わせている、なんてことはない」
とくん。
とん、とくん。
凪の水面に、仄かな心音がまあるく波打っている。
(私が食い下がったから、仕方なく期限付きの契約に付き合ってくれているんじゃないの……? だって、最初は断ったんだもの。そうでないなら、)
期待してしまいそうになる。
契約に応じられない理由がぽんと無造作に置いてあって、それさえどければずっと一緒にいてくれるのでは。なんて。
「……ありがとう。あなたが嫌な思いをしていないなら、良かったわぁ」
「ん」
でもそんな考え自体、最初に契約を迫った時と同じくアマリリスの身勝手だ。
(願望を押し付けてどうするの。人の心を都合良く解釈しちゃだめ)
きゅ、と、指に纏わる水を一度、握り返す。
フロウはくすぐったそうに震え、手の形をなぞり離れていった。
◆
◆
◆
【魔晶】
自然から産出される、物質化した魔力の塊を魔晶といいます。比喩的に結晶と表現されますが鉱物ではありません。
火水地風の四属性があり、属性の力が偏った環境から、その属性の魔晶が採れることが多いです。(活火山から火の魔晶が採れるなど)
また生物の体内から無属性の魔晶が採れることがありますが、非常に希少です。