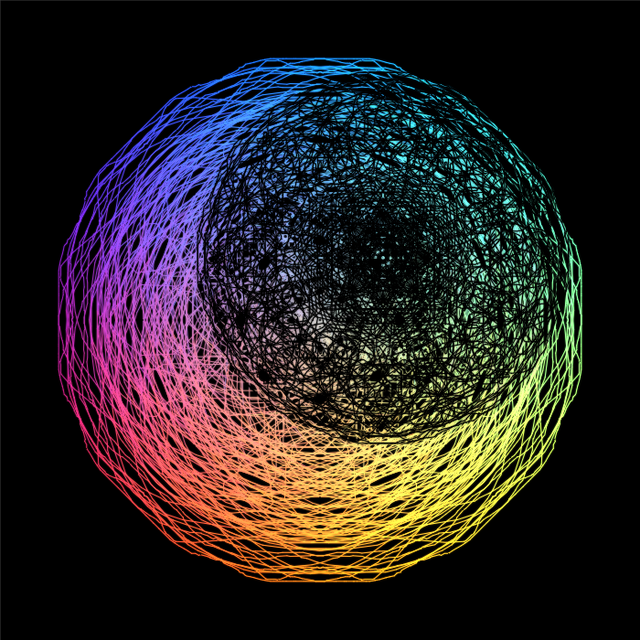25. あなたと道を違えたならば
文字数 5,065文字
ストランジ家当主の妻ハイドランジアは書架から焦茶の背表紙を抜き出し、振り返った。
夫は別室で現地の自警団員らと会議に入っており、執務室に人間は自分一人だ。応接用のソファでは人間でないものが平淡にこちらを見ている。整った顔立ちだが、愛想がない。
テーブルの上の紅茶は両方とも二杯目。今回の件への感謝や、協力者への礼儀としての状況共有――そういった重要な話をする間に、既に半分減っていた。味は覚えていない。
「それは?」
「精霊に関する本よ。残念だけれど実体を持つ精霊については書かれていなさそうね」
章題をざっと眺め、すぐに諦めた。この部屋の蔵書はカザヤで役に立つかを基準に選ばれている。手元のこれも精霊が引き起こす事故や、精霊の様子から災害を予測できるか等の実用的な内容だった。
閉じた本をテーブルに置き、対面にゆったりと掛け直す。それから少しだけ首を傾げて柔らかく訊ねた。
「魔力属性以外、人と変わりない見た目。貴方は一体何者なのかしら」
「分からない。昔、知人も色々と調べて、見当がつかなかったらしい。オレは自分を半端な存在に感じているが」
和やかな、砕けた雑談の調子を意識したが、フロウの態度はそっけない。話術に付き合う気はなさそうだ。
「ああ、魔術師の知り合いがいたのよね。お名前を聞いても?」
「エドウィン……エドウィン・オスタード。どこかに名が残っていたりするか?」
「調べてみないことにはなんとも。一口に魔術といっても分野は多岐に渡るから」
ただし魔術の領域外 には心当たりがある。
エドウィンとは、アマリリスから事前に聞いていた通りの名。そしてオズワルドから、もしやと共有された人物と姓までが一致している。
本邸書庫の、歴代当主のみが入ることを許される特別室の一角、およそ百年前の当主の手記によれば――。エドウィンという老貴族が王都から訪れ、領 内 に 封 じ ら れ て い る 存 在 の記録を抹消するよう、懇願してきたらしい。
『それで諾々と記録の大半を破棄したなんて書いてあるから、若かりし頃の私は衝撃を受けたよ。知の蓄積への冒涜だってね。おかげで印象に残っていたんだ。今は相応の理由あっての判断だろうと冷静に考えられるけど……。全ての記録が残っていれば彼の正体も分かったろうに、口惜しいことだ』
脳裏に甦る身振り手振りたっぷりの主張を脇に押しやって、ハイドランジアは破棄を免れた重要な情報をゆっくりと反芻した。
「踏み込んだことを訊かせてもらうわ。境界を冒すもの 、貴方は己を封じた者を恨んでいる?」
「良い感情は一切無いが、恨みとまでは……。消されなかっただけマシだ」
「生かしておけば利用価値があるからでしょうね」
――この精霊への対処は任されている。もしもの際の手筈も別荘中の戦力に共有した。
行儀悪く自らの膝に肘をつき、いかにも意地悪く笑ってみせる。
「貴方を襲った魔術師達の、指揮を執っていたのは当家の縁者よ。どう、ストランジ やアマリリス に、一矢報いたい?」
そこまで明言してようやく、無表情が崩れた。
◆
車輪と地面の軋轢が、緩衝材や座面のクッションを経て、ゆらゆらとアマリリスの腿に伝わってくる。ときおり窓の外に樹が現れては流れ去り、平野の奥の段々畑は緑と茶色の模様を織っている。
両親が来て数日で、本邸に戻る手筈が整った。お世話になった人々に挨拶し、町の警戒にストランジの護衛をいくらか残し、巻き込まれた子の家には見舞いを出して。
(フロウ、当たり前みたいに一緒に来てくれてるのよねぇ。嬉しい、けど……)
彼は今ここにはいない。アマリリスは父オズワルドと馬車の中で向かい合い、他の皆はそれぞれ別の車両に乗っている。
もともと夏季休暇いっぱいカザヤに滞在する前提で契約した。アマリリスが予定を変更して帰るのは、フロウにとって契約を切り上げる良い機会だったはずだ。それに両親も積極的に引き離しにくると思っていた。
大事な話は落ち着いてから、ということなのかもしれないが――どっちつかずな状態は期待と不安を交互に煽ってきて、始終気持ちがざわついている。
ともあれ猶予があるとは、足掻けるということだ。
「お父様、そこの氷柱 なのだけれど」
「うん?」
「ちょっと触ってみてくれないかしらぁ」
乗降口とは反対の側面、足元の通風溝のまん前に、脛ぐらいの高さの可愛らしい氷筍が五本並んでいる。出発前にフロウに作ってもらった、魔力を帯びる『溶けない氷』。
アマリリスも座席の端に屈んで、手前の一本にそっと触れた。先は潰れて丸く、今もキンと冷たい。
「ふむ。濡れているのは結露だねえ」
「それで、もっと下までいくと……」
「なんと! 冷たくないな」
アマリリスが指を下げていくのを父も真似て、それから面白そうに目を丸くした。天辺が一番低温で、根元は常温。また細長い円錐形は下の方だけでこぼこと、節のようになっている。
「アマリリスがこうするよう頼んだのかい」
「いえ、私は氷を出してとお願いしただけよ」
「これは馬車が傷まないように……だろうね」
フロウ本人には確認していないが――アマリリスも父と同じ結論に達している。
床に垂れた水は、木材や塗装を少しづつ駄目にする。根元の節はそこで雫を受け止めるため、下が常温なのは床近くや建材の中に結露を生じさせないためだ。
「昔誰かに教わったのかもしれないわぁ。でも、律儀にこんな細かい気遣いをしてくれるのは、あの人自身の善良さだと思うの」
言ってからちらりと様子を伺う。露骨な擁護にオズワルドは苦笑を浮かべていた。ここまでの道中だって、彼に危険性はないとあの手この手で語ってきた。そろそろ食傷させてしまったかも。
だが。次に聞こえてきたのは呆れではなく、不意打ちのように真面目な声だった。
「うん。……うん、そうだね。今は丁度二人きりだ。彼のこと、契約のことを話そうか」
父は両手を広げ、あくまで穏やかに切り出した。学園に入る前、よく家訓や領地や難しい研究のことを、聞かせてくれた口調で。
「アマリリスは、フロウ君との契約をどうしたいと思っている?」
「叶うならいつまでだって結んでいたいわぁ。けれどあの人がそれを望まないから……せめて手を離されるまで、私からは絶対に離したくない」
「やはり、契約は続けたいのだね。……ハイドランジアとも、彼がアマリリスや周囲の者に牙を剥く可能性は低いと、見解は一致しているよ。強大な精霊と契約する利がどれほどかも理解している」
寄り添うような言葉の陰から、馴染んだ『でも』の気配が見え隠れする。ついで告げられるだろうそれに挫かれぬよう、虚勢で胸を張る。
――思い返せば。周りばかり見て溺れていたアマリリスが心の底から望んだのは、フロウとの再会であり共に居ることだった、この夏の最初から。
アマリリスに向けて鷹揚に開かれていた父の両手の指が、ゆっくりと組まれた。
「問題は三つある。依然、彼の特異性を私達が把握しきれないこと。ただの学生が契約を結ぶには稀有すぎること。そして、ユインらの復讐の対象に彼も入っているだろうことだ」
厳かな古書の色の目は、もっともな道理そのものとして、立ち塞がる。
「フロウ君はとても頼もしい。しかし、彼の存在そのものが余計な危険を引き寄せるかもしれないことを……承知の上かい」
◆
――水精は眉根を寄せ、透明な葉鳴りの声を僅かに低めた。
「お前達の家は、リーヴァン領の内乱に無関心だったと聞いた」
「当主はそうだったようね。でも野心ある傍流の者が積極的に介入していたの。リーヴァンに協力することで取り入りながら、背信の証拠を掴み、王家に売った。隣領だからといって訳もなく併合されるのはおかしいでしょう? 歴史書に記せない裏事情ね」
「……。そうだとして、血筋だけで憎むかと問われても、困る。オレを解放したリィリには……感謝している」
一度掻き乱してしまえば、ハイドランジアにとってフロウの反応は人間より余程分かりやすい。
内乱の経緯はアマリリスに教わったのだろう。それが嘘だったのかという衝撃に始まり、自分の心を躊躇いがちに確かめる気配までが見てとれた。
「貴方は領地のついでにストランジ家の手中に落ちた副賞のようなもの。仕舞われていた箱をたまたま開けたのが、アマリリスというだけよ」
更なる挑発にフロウはきょとんとした。怪訝そうな顔は、しかし考え込むように伏せられていく。
太陽光の射さない室内はまるで研究所の隔離室だった。いつ暴れ出すか知れない存在と閉じ込められている――。そんな錯覚は、言葉の棘を向ける後ろめたさの裏返しだろう。この精霊の気性を探るため、自らも身体を張っているのだと、脳が言い訳したがっている。
現に水の魔力はそよそよ漂うばかりでハイドランジアを害することはない。攻撃性の低さは予想通りだ。
だが、何故か安心できない。根拠のない胸騒ぎがある。十年前と同じように。
つと上げられた水色は凪いで、真っ直ぐな意思を宿していた。
「リィリは、オレをそういう風に思っていない。オレはあいつの敵にはならない」
ハイドランジアは正面からその瞳を射貫いた。どんな小さな悪意も逃さず、暴きたてるために。
◆
――アマリリスは拳を握り、答えた。緊張に唇がわなないたが、声は震えなかった。
「フロウといたために起こることを、あの人のせいで余計な災難に巻き込まれたとは、思わないわぁ」
父は返事を吟味するように一呼吸おいて、優しく静かなまま問いを重ねる。
「ではそれがストランジ家に大きな不利益をもたらしたなら、引責として家名を返上できるかい?」
「……最初の授業で習ったの。魔術師は貴族である前に、女である前に、子供である前に、魔術師なのだって。私は凡庸だから、嫁ぐ方が役に立てると考えているけれど……。貴族でなくなっても、魔術師としてこの国のために働くことはできるわ」
「では彼が本当はとても邪悪で、取り返しのつかない罪を犯したなら、アマリリスは毒杯を呷れるかい?」
あんまりな単語が頬をひっ叩く。
毒杯。すなわち死。
そんなものを天秤に掛けられるほど、少しでもフロウの傍にいたいという願いは、許されざるものなのだろうか。自らの死に様を想像しようとすると、覚えたばかりの恐怖が足先を舐める。また暗に示された、自分の判断が惨事を招く可能性が――おそろしさが、全身を浸す。
怯えを払いのける強さをアマリリスは未だ持たない。しかしこれは、彼のことがなくたって一生付き纏うものだ。思考が父の問いを足掛かりに、何かを掴もうと手を伸ばす。
「……怖い、わぁ。でも、フロウが邪悪かもしれないなんて仮定では、納得できない」
状況は本質的に、別荘でノアとフロウを引き合わせた時のまま。
あれから彼の人柄に触れてきて、幼い盲信は拠り所のある信頼になった。だが『本当は』『もしかしたら』『隠しているだけで』と言い募られたとき、ちっぽけな信頼が何になろう。
内心の証明などできるわけがない。人間同士だって。血を分けた家族だって。
だから。
「あの人も私も……意思があって言葉が通じるのよ。様子がおかしければ話を聞くし、誰かを傷付けようとするなら止める。万に一つ、本当は悪い人なのだったら、説得するわぁ」
語れるのは自分の想いひとつ。
ぐしゃりと視界が歪んで、右頬を涙が滑り落ちていく。アマリリスは構わず続けた。
「それで、もし、っ……説得も届かず、罪を犯すのを防げなかったなら。あの人を討つために尽力して、……私は私の愚かさのために、毒を飲みます」
父は辛抱強く最後まで聞いてくれた。
泣きながら訴えかけるみっともない姿を咎めることはなかったし、かといってほだされるでもない。流れ出す涙と嗚咽をぐすぐすとハンカチで拭うところを、オズワルドは何事もないかのように見守っている。
そうして。息が整った頃に掛けられた言葉は、訥々と、少し寂しげに響いた。
「……アマリリス。ならば私達は口を出すまい。危険だから契約を断ち切れとも、有能な精霊を繋ぎ止めろとも言わない。二人のことを、二人で決めなさい」
◆
◆
◆
【精霊の強さ――番外:人型精霊】
形のない低位精霊を除き、精霊は単一の生物、または複数の生物が混じった姿を持ちます。
これについて、より賢い生物の姿であるほど優秀で、人間の部位を持つ人型精霊が最たるもの――という俗説があります。実際は若干の相関こそあれ例外の方が多いようです。
パートナーが人型精霊でないことを悲観する必要はないと言えるでしょう。
夫は別室で現地の自警団員らと会議に入っており、執務室に人間は自分一人だ。応接用のソファでは人間でないものが平淡にこちらを見ている。整った顔立ちだが、愛想がない。
テーブルの上の紅茶は両方とも二杯目。今回の件への感謝や、協力者への礼儀としての状況共有――そういった重要な話をする間に、既に半分減っていた。味は覚えていない。
「それは?」
「精霊に関する本よ。残念だけれど実体を持つ精霊については書かれていなさそうね」
章題をざっと眺め、すぐに諦めた。この部屋の蔵書はカザヤで役に立つかを基準に選ばれている。手元のこれも精霊が引き起こす事故や、精霊の様子から災害を予測できるか等の実用的な内容だった。
閉じた本をテーブルに置き、対面にゆったりと掛け直す。それから少しだけ首を傾げて柔らかく訊ねた。
「魔力属性以外、人と変わりない見た目。貴方は一体何者なのかしら」
「分からない。昔、知人も色々と調べて、見当がつかなかったらしい。オレは自分を半端な存在に感じているが」
和やかな、砕けた雑談の調子を意識したが、フロウの態度はそっけない。話術に付き合う気はなさそうだ。
「ああ、魔術師の知り合いがいたのよね。お名前を聞いても?」
「エドウィン……エドウィン・オスタード。どこかに名が残っていたりするか?」
「調べてみないことにはなんとも。一口に魔術といっても分野は多岐に渡るから」
ただし魔術の領域
エドウィンとは、アマリリスから事前に聞いていた通りの名。そしてオズワルドから、もしやと共有された人物と姓までが一致している。
本邸書庫の、歴代当主のみが入ることを許される特別室の一角、およそ百年前の当主の手記によれば――。エドウィンという老貴族が王都から訪れ、
『それで諾々と記録の大半を破棄したなんて書いてあるから、若かりし頃の私は衝撃を受けたよ。知の蓄積への冒涜だってね。おかげで印象に残っていたんだ。今は相応の理由あっての判断だろうと冷静に考えられるけど……。全ての記録が残っていれば彼の正体も分かったろうに、口惜しいことだ』
脳裏に甦る身振り手振りたっぷりの主張を脇に押しやって、ハイドランジアは破棄を免れた重要な情報をゆっくりと反芻した。
「踏み込んだことを訊かせてもらうわ。
「良い感情は一切無いが、恨みとまでは……。消されなかっただけマシだ」
「生かしておけば利用価値があるからでしょうね」
――この精霊への対処は任されている。もしもの際の手筈も別荘中の戦力に共有した。
行儀悪く自らの膝に肘をつき、いかにも意地悪く笑ってみせる。
「貴方を襲った魔術師達の、指揮を執っていたのは当家の縁者よ。どう、
そこまで明言してようやく、無表情が崩れた。
◆
車輪と地面の軋轢が、緩衝材や座面のクッションを経て、ゆらゆらとアマリリスの腿に伝わってくる。ときおり窓の外に樹が現れては流れ去り、平野の奥の段々畑は緑と茶色の模様を織っている。
両親が来て数日で、本邸に戻る手筈が整った。お世話になった人々に挨拶し、町の警戒にストランジの護衛をいくらか残し、巻き込まれた子の家には見舞いを出して。
(フロウ、当たり前みたいに一緒に来てくれてるのよねぇ。嬉しい、けど……)
彼は今ここにはいない。アマリリスは父オズワルドと馬車の中で向かい合い、他の皆はそれぞれ別の車両に乗っている。
もともと夏季休暇いっぱいカザヤに滞在する前提で契約した。アマリリスが予定を変更して帰るのは、フロウにとって契約を切り上げる良い機会だったはずだ。それに両親も積極的に引き離しにくると思っていた。
大事な話は落ち着いてから、ということなのかもしれないが――どっちつかずな状態は期待と不安を交互に煽ってきて、始終気持ちがざわついている。
ともあれ猶予があるとは、足掻けるということだ。
「お父様、そこの
「うん?」
「ちょっと触ってみてくれないかしらぁ」
乗降口とは反対の側面、足元の通風溝のまん前に、脛ぐらいの高さの可愛らしい氷筍が五本並んでいる。出発前にフロウに作ってもらった、魔力を帯びる『溶けない氷』。
アマリリスも座席の端に屈んで、手前の一本にそっと触れた。先は潰れて丸く、今もキンと冷たい。
「ふむ。濡れているのは結露だねえ」
「それで、もっと下までいくと……」
「なんと! 冷たくないな」
アマリリスが指を下げていくのを父も真似て、それから面白そうに目を丸くした。天辺が一番低温で、根元は常温。また細長い円錐形は下の方だけでこぼこと、節のようになっている。
「アマリリスがこうするよう頼んだのかい」
「いえ、私は氷を出してとお願いしただけよ」
「これは馬車が傷まないように……だろうね」
フロウ本人には確認していないが――アマリリスも父と同じ結論に達している。
床に垂れた水は、木材や塗装を少しづつ駄目にする。根元の節はそこで雫を受け止めるため、下が常温なのは床近くや建材の中に結露を生じさせないためだ。
「昔誰かに教わったのかもしれないわぁ。でも、律儀にこんな細かい気遣いをしてくれるのは、あの人自身の善良さだと思うの」
言ってからちらりと様子を伺う。露骨な擁護にオズワルドは苦笑を浮かべていた。ここまでの道中だって、彼に危険性はないとあの手この手で語ってきた。そろそろ食傷させてしまったかも。
だが。次に聞こえてきたのは呆れではなく、不意打ちのように真面目な声だった。
「うん。……うん、そうだね。今は丁度二人きりだ。彼のこと、契約のことを話そうか」
父は両手を広げ、あくまで穏やかに切り出した。学園に入る前、よく家訓や領地や難しい研究のことを、聞かせてくれた口調で。
「アマリリスは、フロウ君との契約をどうしたいと思っている?」
「叶うならいつまでだって結んでいたいわぁ。けれどあの人がそれを望まないから……せめて手を離されるまで、私からは絶対に離したくない」
「やはり、契約は続けたいのだね。……ハイドランジアとも、彼がアマリリスや周囲の者に牙を剥く可能性は低いと、見解は一致しているよ。強大な精霊と契約する利がどれほどかも理解している」
寄り添うような言葉の陰から、馴染んだ『でも』の気配が見え隠れする。ついで告げられるだろうそれに挫かれぬよう、虚勢で胸を張る。
――思い返せば。周りばかり見て溺れていたアマリリスが心の底から望んだのは、フロウとの再会であり共に居ることだった、この夏の最初から。
アマリリスに向けて鷹揚に開かれていた父の両手の指が、ゆっくりと組まれた。
「問題は三つある。依然、彼の特異性を私達が把握しきれないこと。ただの学生が契約を結ぶには稀有すぎること。そして、ユインらの復讐の対象に彼も入っているだろうことだ」
厳かな古書の色の目は、もっともな道理そのものとして、立ち塞がる。
「フロウ君はとても頼もしい。しかし、彼の存在そのものが余計な危険を引き寄せるかもしれないことを……承知の上かい」
◆
――水精は眉根を寄せ、透明な葉鳴りの声を僅かに低めた。
「お前達の家は、リーヴァン領の内乱に無関心だったと聞いた」
「当主はそうだったようね。でも野心ある傍流の者が積極的に介入していたの。リーヴァンに協力することで取り入りながら、背信の証拠を掴み、王家に売った。隣領だからといって訳もなく併合されるのはおかしいでしょう? 歴史書に記せない裏事情ね」
「……。そうだとして、血筋だけで憎むかと問われても、困る。オレを解放したリィリには……感謝している」
一度掻き乱してしまえば、ハイドランジアにとってフロウの反応は人間より余程分かりやすい。
内乱の経緯はアマリリスに教わったのだろう。それが嘘だったのかという衝撃に始まり、自分の心を躊躇いがちに確かめる気配までが見てとれた。
「貴方は領地のついでにストランジ家の手中に落ちた副賞のようなもの。仕舞われていた箱をたまたま開けたのが、アマリリスというだけよ」
更なる挑発にフロウはきょとんとした。怪訝そうな顔は、しかし考え込むように伏せられていく。
太陽光の射さない室内はまるで研究所の隔離室だった。いつ暴れ出すか知れない存在と閉じ込められている――。そんな錯覚は、言葉の棘を向ける後ろめたさの裏返しだろう。この精霊の気性を探るため、自らも身体を張っているのだと、脳が言い訳したがっている。
現に水の魔力はそよそよ漂うばかりでハイドランジアを害することはない。攻撃性の低さは予想通りだ。
だが、何故か安心できない。根拠のない胸騒ぎがある。十年前と同じように。
つと上げられた水色は凪いで、真っ直ぐな意思を宿していた。
「リィリは、オレをそういう風に思っていない。オレはあいつの敵にはならない」
ハイドランジアは正面からその瞳を射貫いた。どんな小さな悪意も逃さず、暴きたてるために。
◆
――アマリリスは拳を握り、答えた。緊張に唇がわなないたが、声は震えなかった。
「フロウといたために起こることを、あの人のせいで余計な災難に巻き込まれたとは、思わないわぁ」
父は返事を吟味するように一呼吸おいて、優しく静かなまま問いを重ねる。
「ではそれがストランジ家に大きな不利益をもたらしたなら、引責として家名を返上できるかい?」
「……最初の授業で習ったの。魔術師は貴族である前に、女である前に、子供である前に、魔術師なのだって。私は凡庸だから、嫁ぐ方が役に立てると考えているけれど……。貴族でなくなっても、魔術師としてこの国のために働くことはできるわ」
「では彼が本当はとても邪悪で、取り返しのつかない罪を犯したなら、アマリリスは毒杯を呷れるかい?」
あんまりな単語が頬をひっ叩く。
毒杯。すなわち死。
そんなものを天秤に掛けられるほど、少しでもフロウの傍にいたいという願いは、許されざるものなのだろうか。自らの死に様を想像しようとすると、覚えたばかりの恐怖が足先を舐める。また暗に示された、自分の判断が惨事を招く可能性が――おそろしさが、全身を浸す。
怯えを払いのける強さをアマリリスは未だ持たない。しかしこれは、彼のことがなくたって一生付き纏うものだ。思考が父の問いを足掛かりに、何かを掴もうと手を伸ばす。
「……怖い、わぁ。でも、フロウが邪悪かもしれないなんて仮定では、納得できない」
状況は本質的に、別荘でノアとフロウを引き合わせた時のまま。
あれから彼の人柄に触れてきて、幼い盲信は拠り所のある信頼になった。だが『本当は』『もしかしたら』『隠しているだけで』と言い募られたとき、ちっぽけな信頼が何になろう。
内心の証明などできるわけがない。人間同士だって。血を分けた家族だって。
だから。
「あの人も私も……意思があって言葉が通じるのよ。様子がおかしければ話を聞くし、誰かを傷付けようとするなら止める。万に一つ、本当は悪い人なのだったら、説得するわぁ」
語れるのは自分の想いひとつ。
ぐしゃりと視界が歪んで、右頬を涙が滑り落ちていく。アマリリスは構わず続けた。
「それで、もし、っ……説得も届かず、罪を犯すのを防げなかったなら。あの人を討つために尽力して、……私は私の愚かさのために、毒を飲みます」
父は辛抱強く最後まで聞いてくれた。
泣きながら訴えかけるみっともない姿を咎めることはなかったし、かといってほだされるでもない。流れ出す涙と嗚咽をぐすぐすとハンカチで拭うところを、オズワルドは何事もないかのように見守っている。
そうして。息が整った頃に掛けられた言葉は、訥々と、少し寂しげに響いた。
「……アマリリス。ならば私達は口を出すまい。危険だから契約を断ち切れとも、有能な精霊を繋ぎ止めろとも言わない。二人のことを、二人で決めなさい」
◆
◆
◆
【精霊の強さ――番外:人型精霊】
形のない低位精霊を除き、精霊は単一の生物、または複数の生物が混じった姿を持ちます。
これについて、より賢い生物の姿であるほど優秀で、人間の部位を持つ人型精霊が最たるもの――という俗説があります。実際は若干の相関こそあれ例外の方が多いようです。
パートナーが人型精霊でないことを悲観する必要はないと言えるでしょう。