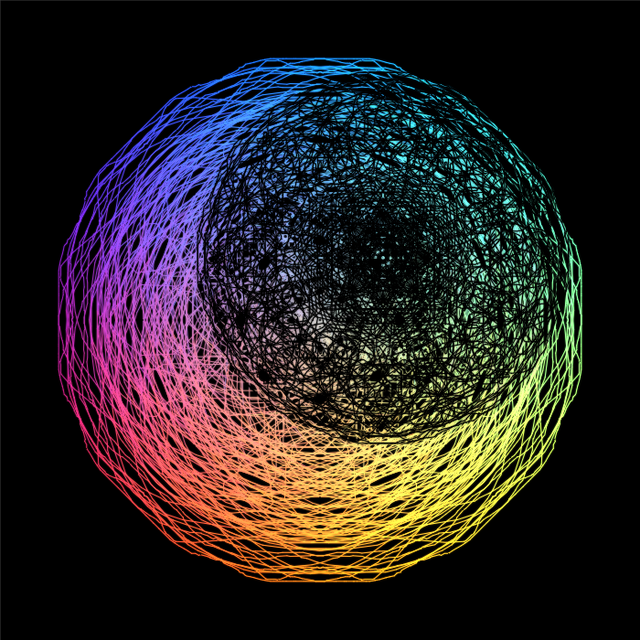10. 属性術
文字数 4,183文字
それから数日。二人の望みは、宙ぶらりんのままだった。
アマリリスは教養として、国や領地の歴史は学園に入る前から叩き込まれている。しかしきちんとした書物を参照した方が正確なので、カザヤの図書館に資料を返しに行くときに、一緒に歴史書を紐解くことにした。
(こういう分野は本邸の書庫が豊富だけれど……距離があるし、お父様やお母様とフロウを会わせるわけにも、ねぇ)
借りた資料を読み終えるタイミングと、御者を務めるジェフリーの予定上、カザヤにはさらに数日後に行くことになっている。それはフロウも了承済みだ。
とはいえ、彼の知りたいことを先延ばしにしているので、アマリリスもあれこれ訊くのは気が引けた。常にノアが居合わせる中、どれくらい踏み込んでよいのか分かりかねたし。
「フロウ、おはよう」
「おはよう」
岸辺でしゃがみ込んで声をかけると、底に揺蕩っていた密な魔力が浮上して、一筋の水となって流れから抜け出た。水――フロウは草の上でくるんと丸くなる。
今日は水術を練習するため、彼が寝室代わりにしている川で落ち合うことにしていた。そこそこの広さがあって、それに人が来ないので魔術が変に失敗しても巻き込む心配がない。水辺なのも都合がいい。
「じゃあやってみましょうか、お嬢様。水属性のことは詳しくないですけど、基本的なことならお伝えできると思います」
「えぇ。付き合ってくれてありがとう」
どうせ傍に待機するのだからと、ジェフリーがアドバイスを買って出てくれた。
その瞳は少し年経た真鍮の色だ。地の単属性で魔術の腕はそれなり――なんて自称していたけれど、護衛として雇われるくらいなので謙遜だと思う。
フロウもすぐ近くでこちらを注視している、気がする。アマリリスの魔術をもっと見てみたいと言うので、あえて彼と過ごす時間に練習することにしたのだ。
アマリリスは呼吸を整えて、瞼を伏せた。視覚を閉ざしたぶん他の感覚が研ぎ澄まされていく。
全身からにじみ出し、肌の上をゆらゆら漂う魔力は無属性。しばしば白か透明にたとえられる、素 の力。
(すごい……。知覚できる だけで、全然違う)
不随意に揺らめいていたそれに芯を通すよう意識していると、だんだんぶれが小さくなっていった。
魔力の把握は扱いの精度に直結する。特に属性術は感性に依存しやすく、《精霊契約 》で魔力知覚を得るのが大前提と言われている。
(いい感じ。あとは水の魔力に染 め ればいいのよねぇ?)
魔力を変換する感覚は人や属性によって違うらしい。アマリリスは教科書通り、水属性の王道だという心臓を核としたイメージを脳裏に描いた。
体内に巡る水の源泉――鼓動を感じ、血流に沿って染め変える。無垢から水に。
「んんんんん……?」
「使う属性の力を、具体的に意識するといいですよ」
「意識してる、つもりなのだけど……んんんっ」
目を開き、ぐるりと辺りを見渡す。
川の流れからは飛沫とともに水の魔力が散乱しているし、近くで興味深そうにしているフロウは静かに力を湛えた泉のようだ。参考には事欠かない。
視線を受けてフロウが問うように揺れる。つられてこてんと首を傾げていると、記憶の表層がちかちか瞬いた。
(そうだわぁ。あの綺麗な深い青……)
彼が身体を癒してくれた時の、夜を上描く魔力光。
強く抱きしめられるまま想起した大河の幻像。
あらゆる痛みを押し流してアマリリスを満たしたもの。
契約前でも鮮烈に感じた涼やかな奔流は、まさに水の力だった。
流動。されど静謐。あるいは浸透。あの心地好さは今もありありと思い描ける。
「あ、できてますね」
「んん……んぇ!?」
――本当だ。アマリリスはばっ、と両手を見つめた。
ひ た ひ た でざ ぶ ざ ぶ な感じが確かにある。回想の産物ではなくて、現実に身体を取り巻いている。
適性が低いために染めた後の魔力量はがくっと落ちるが、水の力は滑らかで、波打つように肌の上を踊る。集中を切らしたらすぐ元に戻ってしまいそうだけれど。
「今のうちに! えぇと、えと、」
短杖 をベルトからひっこ抜き、慌てて初歩の水術を唱えた。
「…………あ、《水雫 》!」
杖の芯を魔力が流れ、杖先から少しの空中に、ぷくりと小さな水滴が浮く。それは青い魔力光を帯びながらもがき、伸縮して、じわじわ握りこぶしぐらいまで大きくなった。
拍子抜けするくらいあっさり形になった水の球は、ふるふる震え、夏の深緑を透かしてきらめいていた。
「やった……っ、上手くいったわぁ!」
「どうです? 以前に比べてやりやすいですか?」
「えぇ、やっぱり魔力知覚って大事なのね。授業では何十回も詠唱して、まぐれで一度しか成功しなかったのに。……あっ」
気を逸らした瞬間、球はとろりと崩れて、幻のように消えてしまった。
魔術で作り出した水はそのままでは不安定な現象にすぎず、術を解けば無に帰す。手を洗うとか一時的な用途ならその方が便利だけど、飲料水にしたり水風呂を浴びるには適さない。
「そうですねえ、次は水の状態で固定してみましょうか。……や、それよりも」
ジェフリーはひたと足元に目を向けた。
「フロウさん、ちょっとお手本見せていただけません?」
「手本? 精霊に魔術は使えない」
「だからこそです。人の魔術と違って、精霊 の振る舞いはごく自然で無駄がない。一種の完成形なんですよね」
ふうん、と――緩やかな了承とともに、アマリリスの目の前にぽかりと水が現れた。さっきの《水雫 》と同じこぶし大だが、表面は少しも揺らがずに球形を保っている。
「どうだ?」
「わ……綺麗ねぇ! けどその、お手本になるかというと、一瞬のことで何が何だか」
「ん、そうか。もっとゆっくり……手本、手本か」
フロウは思案げに呟く。それから木陰で本を読んでいたノアに寄って数言交わし、するりと人の姿に変わった。
――そういえばどこからともなく彼の身体を覆う服も、彼の力でできているのだと、今は分かる。糸ほどに繊細な水を編んで重ねているみたい。どうりでいつも白い服なはずだ。
と。おもむろに差し出された手とフロウの顔を見比べて、アマリリスはぱちぱち瞬いた。
「リィリ、杖を貸してくれ」
◆
学生のための素朴な短杖 を無造作に構えてすら、薄明に物音が途絶える瞬間のごとき佇まいで、さまになっている。
淡青の視線が横目にこちらを掠め、杖先に戻る。心臓が小さく高鳴って、アマリリスは胸元を押さえた。
――呟きは短く、澄みわたる。
「
どう、と、感覚で追える速さで杖の中を魔力が迸る。流れは細いが強く、杖先から溢れてわずかに広がったあと、ぎゅっと一点に集まっていく。
魔力光が仄かに漏れ出して、空気が薄青に染まる。
その中心の、力の一番重いところが、さらに縒り合わせるように凝縮される。
(あ、水の気配がする……)
――霧のような、匂いともいえぬ匂い。
やがて力は臨界を迎え、一握りの水が音もなく実体に零れだした。
宙に留まる水はやはり水晶玉のように丸い。派手に光を反射することはなく、透明な艶の内に景色を吸い込んでいた。
「すごい……」
背筋を痺れが這い上がる。ぞわぞわと――精神が昂っている。
これまでアマリリスの魔力知覚がほぼなかったのを差し引いても、学園のどの先生の術より精緻で美しい。『完成形』という表現では言い尽くせない。
精霊は自然に漂う魔力の化身、言い換えれば意識を持つ魔力の塊のようなもの。人が喉の震わせ方を考えなくとも話せるように、自在に魔力を扱う。そういう常識はあったが、丁寧に実演されると、ただ圧倒されるばかりだ。
「……あれ? でもあなた、魔術は使えないって」
「杖も詠唱もただのフ リ だ」
短杖 をぽんと手渡される。そこに彼の力は残っていないが、ひんやりと名残を感じて、アマリリスは思わず両手で握りしめた。
同じく見入っていたジェフリーが、興奮もあらわにフロウに詰め寄る。
「いやいやいや。それっぽい単語を添えただけにしても、ちゃんと魔術語でしたよね。知識はあるってことですか? 杖に魔力流すフリだって手慣れてましたし」
「昔、魔術師の知人がいて、色々教わった。徒手で何かすると目立つから、人前では魔術師の真似事をすればいいと」
「……おおう。慧眼ですねえ、その方。じゃ、ちょっと光ってたのは?」
「これも受け売りだが……魔力光 は魔力の浪費 だから、適当に無駄遣いすれば光る、らしい」
――似たような内容を、アマリリスは『魔力論』の授業で聞いたことがあった。同じ魔術でも、熟練者より初心者の方が粗があるため魔力を余分に使ってしまい、やたらぴかぴか光るのだとか。
そして精霊がありのままに振るう力は、人の魔術と似て非なるもので、無駄なく完成されているから光らない。フロウが最初に水の球を出してくれた時のように。
今回わざと光らせたのが、例外ということだ。
(ん……? 変ねぇ、何か引っ掛かるわ)
どんどんぬるくなっていく短杖 を手の中でもてあそぶ。どうしてだろう、目の前に堂々とあるものを、見逃している気がする。
「なるほど……。ともあれお嬢様、今のを理想として練習してみましょう」
「あ……はぁい!」
「まずは杖に魔力を通すとき、収束点、つまりは術の起点を強く意識するとよいかと。あと慣れてきたら、発動に必要な分だけをきっちり流せば疲れにくいです」
「分かりました、先生。フロウもありがとうねぇ」
ん、と小さく返して、フロウは水の身体に戻ってしまう。――少し残念だった。どちらの彼も好きだけれど。
彼が人間態でいるのはスープやお茶を飲むときだけで、あの無表情なのにふわりとした容姿を見られる時間は少ない。なにせノアが厳しいから。飲食だって、人の姿の方が味覚が鋭敏だという理由で、かろうじて目こぼしをもらっているくらいだ。
ともあれ術の練習を再開したために、アマリリスは疑問をすっかり棚上げしてしまい。違和感の正体に辿り着いたのは、しばらく経った後だった。
◆
◆
◆
【魔術語】
魔術の詠唱には魔術語と呼ばれる独自の言語を用います。遠い過去、魔術が今よりも盛んだった時代に生まれたものです。
日用語に比べ文法が複雑で、また汎用性の低いニッチな単語が大量にあります。
語彙は一朝一夕に学べる量ではないため、魔術師としての向上を目指す限り魔術語の勉強はずっとつきまといます。つらい。
アマリリスは教養として、国や領地の歴史は学園に入る前から叩き込まれている。しかしきちんとした書物を参照した方が正確なので、カザヤの図書館に資料を返しに行くときに、一緒に歴史書を紐解くことにした。
(こういう分野は本邸の書庫が豊富だけれど……距離があるし、お父様やお母様とフロウを会わせるわけにも、ねぇ)
借りた資料を読み終えるタイミングと、御者を務めるジェフリーの予定上、カザヤにはさらに数日後に行くことになっている。それはフロウも了承済みだ。
とはいえ、彼の知りたいことを先延ばしにしているので、アマリリスもあれこれ訊くのは気が引けた。常にノアが居合わせる中、どれくらい踏み込んでよいのか分かりかねたし。
「フロウ、おはよう」
「おはよう」
岸辺でしゃがみ込んで声をかけると、底に揺蕩っていた密な魔力が浮上して、一筋の水となって流れから抜け出た。水――フロウは草の上でくるんと丸くなる。
今日は水術を練習するため、彼が寝室代わりにしている川で落ち合うことにしていた。そこそこの広さがあって、それに人が来ないので魔術が変に失敗しても巻き込む心配がない。水辺なのも都合がいい。
「じゃあやってみましょうか、お嬢様。水属性のことは詳しくないですけど、基本的なことならお伝えできると思います」
「えぇ。付き合ってくれてありがとう」
どうせ傍に待機するのだからと、ジェフリーがアドバイスを買って出てくれた。
その瞳は少し年経た真鍮の色だ。地の単属性で魔術の腕はそれなり――なんて自称していたけれど、護衛として雇われるくらいなので謙遜だと思う。
フロウもすぐ近くでこちらを注視している、気がする。アマリリスの魔術をもっと見てみたいと言うので、あえて彼と過ごす時間に練習することにしたのだ。
アマリリスは呼吸を整えて、瞼を伏せた。視覚を閉ざしたぶん他の感覚が研ぎ澄まされていく。
全身からにじみ出し、肌の上をゆらゆら漂う魔力は無属性。しばしば白か透明にたとえられる、
(すごい……。
不随意に揺らめいていたそれに芯を通すよう意識していると、だんだんぶれが小さくなっていった。
魔力の把握は扱いの精度に直結する。特に属性術は感性に依存しやすく、《
(いい感じ。あとは水の魔力に
魔力を変換する感覚は人や属性によって違うらしい。アマリリスは教科書通り、水属性の王道だという心臓を核としたイメージを脳裏に描いた。
体内に巡る水の源泉――鼓動を感じ、血流に沿って染め変える。無垢から水に。
「んんんんん……?」
「使う属性の力を、具体的に意識するといいですよ」
「意識してる、つもりなのだけど……んんんっ」
目を開き、ぐるりと辺りを見渡す。
川の流れからは飛沫とともに水の魔力が散乱しているし、近くで興味深そうにしているフロウは静かに力を湛えた泉のようだ。参考には事欠かない。
視線を受けてフロウが問うように揺れる。つられてこてんと首を傾げていると、記憶の表層がちかちか瞬いた。
(そうだわぁ。あの綺麗な深い青……)
彼が身体を癒してくれた時の、夜を上描く魔力光。
強く抱きしめられるまま想起した大河の幻像。
あらゆる痛みを押し流してアマリリスを満たしたもの。
契約前でも鮮烈に感じた涼やかな奔流は、まさに水の力だった。
流動。されど静謐。あるいは浸透。あの心地好さは今もありありと思い描ける。
「あ、できてますね」
「んん……んぇ!?」
――本当だ。アマリリスはばっ、と両手を見つめた。
適性が低いために染めた後の魔力量はがくっと落ちるが、水の力は滑らかで、波打つように肌の上を踊る。集中を切らしたらすぐ元に戻ってしまいそうだけれど。
「今のうちに! えぇと、えと、」
「…………あ、《
杖の芯を魔力が流れ、杖先から少しの空中に、ぷくりと小さな水滴が浮く。それは青い魔力光を帯びながらもがき、伸縮して、じわじわ握りこぶしぐらいまで大きくなった。
拍子抜けするくらいあっさり形になった水の球は、ふるふる震え、夏の深緑を透かしてきらめいていた。
「やった……っ、上手くいったわぁ!」
「どうです? 以前に比べてやりやすいですか?」
「えぇ、やっぱり魔力知覚って大事なのね。授業では何十回も詠唱して、まぐれで一度しか成功しなかったのに。……あっ」
気を逸らした瞬間、球はとろりと崩れて、幻のように消えてしまった。
魔術で作り出した水はそのままでは不安定な現象にすぎず、術を解けば無に帰す。手を洗うとか一時的な用途ならその方が便利だけど、飲料水にしたり水風呂を浴びるには適さない。
「そうですねえ、次は水の状態で固定してみましょうか。……や、それよりも」
ジェフリーはひたと足元に目を向けた。
「フロウさん、ちょっとお手本見せていただけません?」
「手本? 精霊に魔術は使えない」
「だからこそです。人の魔術と違って、
ふうん、と――緩やかな了承とともに、アマリリスの目の前にぽかりと水が現れた。さっきの《
「どうだ?」
「わ……綺麗ねぇ! けどその、お手本になるかというと、一瞬のことで何が何だか」
「ん、そうか。もっとゆっくり……手本、手本か」
フロウは思案げに呟く。それから木陰で本を読んでいたノアに寄って数言交わし、するりと人の姿に変わった。
――そういえばどこからともなく彼の身体を覆う服も、彼の力でできているのだと、今は分かる。糸ほどに繊細な水を編んで重ねているみたい。どうりでいつも白い服なはずだ。
と。おもむろに差し出された手とフロウの顔を見比べて、アマリリスはぱちぱち瞬いた。
「リィリ、杖を貸してくれ」
◆
学生のための素朴な
淡青の視線が横目にこちらを掠め、杖先に戻る。心臓が小さく高鳴って、アマリリスは胸元を押さえた。
――呟きは短く、澄みわたる。
「
こごれ
」どう、と、感覚で追える速さで杖の中を魔力が迸る。流れは細いが強く、杖先から溢れてわずかに広がったあと、ぎゅっと一点に集まっていく。
魔力光が仄かに漏れ出して、空気が薄青に染まる。
その中心の、力の一番重いところが、さらに縒り合わせるように凝縮される。
(あ、水の気配がする……)
――霧のような、匂いともいえぬ匂い。
やがて力は臨界を迎え、一握りの水が音もなく実体に零れだした。
宙に留まる水はやはり水晶玉のように丸い。派手に光を反射することはなく、透明な艶の内に景色を吸い込んでいた。
「すごい……」
背筋を痺れが這い上がる。ぞわぞわと――精神が昂っている。
これまでアマリリスの魔力知覚がほぼなかったのを差し引いても、学園のどの先生の術より精緻で美しい。『完成形』という表現では言い尽くせない。
精霊は自然に漂う魔力の化身、言い換えれば意識を持つ魔力の塊のようなもの。人が喉の震わせ方を考えなくとも話せるように、自在に魔力を扱う。そういう常識はあったが、丁寧に実演されると、ただ圧倒されるばかりだ。
「……あれ? でもあなた、魔術は使えないって」
「杖も詠唱もただの
同じく見入っていたジェフリーが、興奮もあらわにフロウに詰め寄る。
「いやいやいや。それっぽい単語を添えただけにしても、ちゃんと魔術語でしたよね。知識はあるってことですか? 杖に魔力流すフリだって手慣れてましたし」
「昔、魔術師の知人がいて、色々教わった。徒手で何かすると目立つから、人前では魔術師の真似事をすればいいと」
「……おおう。慧眼ですねえ、その方。じゃ、ちょっと光ってたのは?」
「これも受け売りだが……
――似たような内容を、アマリリスは『魔力論』の授業で聞いたことがあった。同じ魔術でも、熟練者より初心者の方が粗があるため魔力を余分に使ってしまい、やたらぴかぴか光るのだとか。
そして精霊がありのままに振るう力は、人の魔術と似て非なるもので、無駄なく完成されているから光らない。フロウが最初に水の球を出してくれた時のように。
今回わざと光らせたのが、例外ということだ。
(ん……? 変ねぇ、何か引っ掛かるわ)
どんどんぬるくなっていく
「なるほど……。ともあれお嬢様、今のを理想として練習してみましょう」
「あ……はぁい!」
「まずは杖に魔力を通すとき、収束点、つまりは術の起点を強く意識するとよいかと。あと慣れてきたら、発動に必要な分だけをきっちり流せば疲れにくいです」
「分かりました、先生。フロウもありがとうねぇ」
ん、と小さく返して、フロウは水の身体に戻ってしまう。――少し残念だった。どちらの彼も好きだけれど。
彼が人間態でいるのはスープやお茶を飲むときだけで、あの無表情なのにふわりとした容姿を見られる時間は少ない。なにせノアが厳しいから。飲食だって、人の姿の方が味覚が鋭敏だという理由で、かろうじて目こぼしをもらっているくらいだ。
ともあれ術の練習を再開したために、アマリリスは疑問をすっかり棚上げしてしまい。違和感の正体に辿り着いたのは、しばらく経った後だった。
◆
◆
◆
【魔術語】
魔術の詠唱には魔術語と呼ばれる独自の言語を用います。遠い過去、魔術が今よりも盛んだった時代に生まれたものです。
日用語に比べ文法が複雑で、また汎用性の低いニッチな単語が大量にあります。
語彙は一朝一夕に学べる量ではないため、魔術師としての向上を目指す限り魔術語の勉強はずっとつきまといます。つらい。