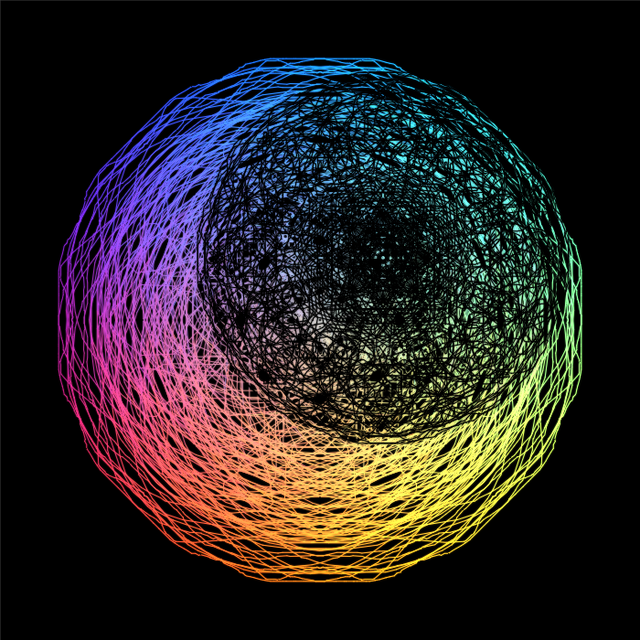11. カザヤの反乱_1
文字数 4,749文字
地図を二枚、机いっぱいに広げた。
古びた丈夫な羊皮紙と、インクの匂い。虫除けのハーブ、微かに感じる黴臭さ。それらが層をなしてアマリリス達をかさりかさりと包み込む。図書館そのものを濃縮したような、慣れ親しんだ空気。知の薫り。
二枚のうち一枚は現在のストランジ領を描いた最近のもので、そしてもう一枚は、同じ地域のおおよそ百年前を描いた古い地図だ。いづれも領地は緑色で縁取られ、範囲が分かりやすい。
「知りたいのは、国家や近隣諸国の広い歴史ではなくて……領内だけでいいのよね?」
「ああ。特に、この近辺を」
「分かったわぁ。地図を見比べれば分かるように、ここカザヤ含め、現在のストランジ領の大半は元々別の家の領地だったの」
百年前の地図において緑で示されるのは、今のストランジ領の東端の方だけ。面積でいえば八分の一ほどにすぎない。その内側には『ストランジ男 爵 領』と、飾り文字で書かれている。
残りの部分は『リーヴァン子爵領』となっていて、リーヴァン領は西側に『インスピア子爵領』と接する。
カザヤはリーヴァン領の北の方に小さく描かれていた。
「リーヴァン、子爵領……」
フロウの滑らかな指が、細かい装飾のたくさん生えた文字を、ゆっくりとなぞる。
ランプの光が影の輪郭を、紙上の世界に落としていた。
再び訪れたカザヤ町図書館の閲覧室は、四人で入るには手狭で、ジェフリーは早々に別の用を済ませに行ってしまった。ただし、ちゃんと『声を上げたら駆け付けられる男手』はいる。町図書館の受付は盗難防止などの警備員を兼ねるので、この館の入口に座っているおじさんも根っからの武闘派なのだ。
アマリリスとフロウは机に顔を突き合わせ、ノアは小部屋の隅で二人を俯瞰している。
カザヤではフロウはずっと人の姿だ。魔術と縁の薄い人にとって、道をふよふよ這う水の球は、奇異に映ってしまうだろうから。傍で横顔が動くたび、柔らかな黒髪がちらついて心臓に悪い。
ジェフリーが手伝いとして呼び寄せた知己の魔術師、ということにして、服もジェフリーに借りて町民らしくしてもらった。フロウの目撃情報が噂になっているのを、ついでに誤魔化せたらいいのだけど。
(綺麗だけど派手な顔立ちではないし、服さえ変えたら町並みにも紛れ……るのは流石に無理かなぁ……?)
ともあれ。
膝に資料を数冊抱えたアマリリスは、記述と知識を照合し、段取りを頭の中でこね回しながら、なるべく丁寧に語り始めた。
「リーヴァン領だったまさに当時の資料はあまり現存していなくて、ストランジ家に編入された後に、過去を振り返って書かれたものがほとんど。だから色眼鏡は掛かっていると思って聞いてねぇ」
「分かった」
「こほん。……リーヴァン家末期の領内は、悪政で酷く荒れていたと記録にあるわ。耐えかねた領民による反乱が何度も起こるほどに。ここ、カザヤでも激しい戦いがあったのよ」
フロウはぴくりともせず、百年前の領地を見つめている。
いつもは透明感がある瞳には灯火の橙が照り返して、ぬらりと底の見えない沼のようだ。中に何者かが――何らかの意思が潜んでいるに違いないのだけれど、水面下に蠢いて影も形も掴めなかった。
◆
――当時は天候不順や疫病が重なって、国全体が疲弊していたの。それに加えて領主、リーヴァン家があまりに腐敗していたものだから、領民は明日も分からぬ生活を送っていたわ。
不作に手を打つこともせず、どころか自分達だけは安泰に生活するため重税を課して、他にも治安維持の放棄、役人の汚職――、悪政と聞いて思い付くもの全部、というありさまよ。末端の汚職もただの賄賂や横領なんてレベルじゃなく、はした金のために賊に便宜を図るようなのが横行していたらしいわぁ。
小規模な暴動とそれに対する弾圧は、数えきれないほど。それに加えて大きな蜂起が散発的に五回起こって、その最後には国が腰を上げ、リーヴァン家はお取り潰しになったの。
「カザヤで起こったのが最後か?」
いいえ。カザヤの反乱は、時系列で四番目。八ヶ月に渡る泥沼の末に、制圧されたそう。
ただ――。リーヴァン子爵家は王家にもあれこれ背信を働いていてねぇ。その証拠がカザヤの反乱の中で、どんな経緯でか国の中枢に伝わったと言われてるのよ。
それが後の騎士団介入の決定打になって、リーヴァンを倒したという見解もあるわ。
「そう、か。つまり、……何でもない、続けてくれ」
――? え、えぇ、分かったわぁ。
リーヴァン家が処断されて領地をどうするかという段になって、隣領だったストランジ男爵家に白羽の矢が立ったの。
当主は寝耳に水だったんですって。ストランジ って昔は今に輪を掛けて野心のない、引きこもりの学者気質だったから。小さな領地をほどほどに治めつつ、学問という名の趣味に打ち込むばかりで――言い方は悪いけれど隣領の荒廃にも知らん顔でいたのに。
一応、長年の魔術研究への寄与を認め封ずる、というのが表向きの理由だけど、実際の思惑は伝わっていないわ。
領地が急に八倍になり、しかも新たな領民は悪政と弾圧の爪痕に弱りきっている――。それでも、田舎の学者貴族なりに手を尽くして、お隣さんになったインスピア子爵家が支援してくれたりもして。
やっと領内の営みが立ち直ってきたところで、増えた領地に見合った子爵位に格上げされたのねぇ。
◆
「ここまでが現在のストランジ子爵領成立の経緯よ。詳しく知りたいことがあれば、分かる限り答えるわぁ」
「…………」
「……あの、えぇと、フロウ?」
フロウは等身大の壁画に塗り込められたように微動だにしない。不安になって、おずおず声をかけた。
地図に置かれたままの手がはっと震え、力なくその場を退く。擦れた紙の音は何故だかアマリリスを咎めるように聞こえた。彼はぼんやり顔を上げ、揺れるランプの火を見ている。
――いや、見てはいなかった。
視界のうちで一番目を引くものに適当に焦点を合わせているだけ、という様子だ。深く沈みゆく彼の意識に、温かい光は届いていない。
アマリリスは考える前に、フロウの腕を掴んでいた。
「っ、」
「あ。ご、ごめんなさい、その、」
「……ありがとうリィリ。大体分かった」
肌が拡散していく感覚にアマリリスの指が溺れると同時、フロウはほうと強ばりを解いた。
しかし――。ゆっくり瞬く彼は、明らかに後ろ髪を引かれている。いつもの凪いだ表情と比べて大きく感情を揺らし、そして押し殺している。
「遠慮しないで、何でも訊いてくれていいのよぅ……?」
「大丈夫だ。もういい」
それでも首を振って否定されたなら、こちらから話せることもない。
彼がまだ疑問を残しているというのは、アマリリスの勝手な想像だ。躊躇いを無理やりこじ開ける勇気は、それで全て終わりになっても受け入れられる覚悟は、まだ持てなかった。
無作法に触れていた手をそっと離すと、どうしようもなく寂しい。
(駄目ね……あなたを知るために契約したのに)
《精霊契約 》の繋がりなんて、少しの拒絶で千切れてしまう頼りないものだから。そんな言い訳を心の内で呟く。
アマリリスの手首に一瞬、青い紋が浮かんだ。
「リィリこそ何か訊きたいんじゃないのか。契約のとき、知りたいと言っていた」
「私、は」
好奇心のポケットをひっくり返せば、順番待ちの質問はいくらでも出てくる。でも今一番知りたいこと、彼の表情の理由には、とても触れられない。
「じゃあ、……あの洞の門のこと。封じられていた、ってどういうことなのかしらぁ。閉じ込められていた訳じゃないのよね。術具を壊すずっと前に、あなたと会っているんだもの」
だから、おそらくノアも気にしていることを問うた。おいおいはノアが彼に抱く敵意も和らいでくれたら嬉しいから。
頷くフロウの目はランプから逸れ、薄暗い中でしんと佇む、いつもの薄青だ。
正体不明の動揺はもうどこかに隠れてしまっていた。
◆
「初めは言葉通り閉じ込められていた。あの門はオレを泉……行き止まりに窪みがあっただろう、その場所に押し留めるものだ。同時に意識を抑えられ、人でいう深い眠りに陥ってもいた」
「え、じゃあ、どうして外に出られたの?」
そこまで言ってから、アマリリスは思い出す。洞にあった術具の一つは欠けていた。
「オレが目を覚ましたのは、リィリが昔、洞に来たとき。何かの拍子に術が薄れたんだな」
「あっ……ふらふらして何度か壁にぶつかったわぁ!」
ということは、結局最初に術具を壊したのもアマリリスだったのか。元から壊れていたと他人事のように思っていたのが無性に恥ずかしくて、口元を押さえた。
「ただ、効果が不完全に残っていた。身体は解放されたものの、意識がぼやけて、まともに物も思えなかった」
「話せなかったのも、そのせい?」
フロウはこくりと首肯する。
精霊の強 さ にはいくつかの尺度があり、その一つが意識の鮮明さだ。大多数の精霊は刹那的で感覚的な内面を持ち、未来に思いを馳せたり、複雑な論理を繰ったりはしない。形のない低位精霊に至っては感情すら薄い、あるがままの自然そのものと言われる。
フロウのように人に近い思考をし人語を解する精霊はまれなのだ。それを普通の精霊ぐらいまで制限されていたのだろう。
完全に結界の抑制下にあった間を眠りと表現するなら、半端に解けた後の状態は夢遊病みたいなものかもしれない。記憶の中の彼が今よりずいぶん儚い雰囲気なのも、きっとそのせい。
「意識にはムラがあったから、術の影響が薄れている間に、リィリに門のことを伝えた」
「なるほどねぇ……。だからあなたの手では壊せなかった、というか壊そうと考えることもできなかったのね」
「そういうことだ」
「……あらぁ? じゃあどうして、あなたはこの辺りに来ていたの? てっきりあなたも門を破ろうとしていたものだと」
ただでさえアマリリスが別荘に来たのと時期が合いすぎて、不思議だったのだ。
フロウは額に拳を当てて、表現を探すようにぽつぽつと言葉を続けた。
「門とは関係ない。おかしな瘴気を感じて……それが、少しづつ移動していた。魔物かと思って追ってきただけだ」
「思考できなくても?」
「瘴気や魔物を厭うのは本能だからな。無意識でも排除することに変わりはない」
――やたらと好戦的だが、精霊は一般に魔物をひどく嫌悪する。力の弱い精霊は魔物を避けるし、強い精霊は魔物を苛烈に攻撃するらしい。
魔物は人間を含む生物だけでなく、自然に害を及ぼすので、自然の魔力と共にある精霊とは相容れないのだろう。
「えぇと、嫌でなければ、封印された経緯も……」
と、本題に戻ろうとしたとき。
コンコン。ノックが響いて、ジェフリーが戻ってきた。外開きのドアから廊下の新鮮な風がぶわりと流れ込む。
「あ、用事はもういいの?」
「はい。それと……盗み聞きするつもりはなかったんですが、魔物とか排除とかお話しされてましたよね」
「? えぇ」
「丁度カザヤの自警団に魔物狩りの相談を受けました」
ジェフリーはそこで言葉を止め、アマリリスをじっと伺う。なんとなく話は見えた。
頷きを返せば、ジェフリーはにっこりと人好きのする笑みを、アマリリスの隣に向ける。
「フロウさん、良かったら、ほんとに僕の仕事手伝ってみません?」
やろう、と。
半ば予想通りにフロウは即答した。
◆
◆
◆
【精霊の強さ①】
精霊の力量の尺度は多角的であり、簡単に強弱を判断できるものではありません。
観点の一つは『意識の鮮明さ』で、複雑な思考ができるかを指します。理性による感情の制御や、時系列や論理など抽象的なことを理解できるか、などを含みます。
主に他の精霊や生物、人間との関わりにより、刺激を受けることで発達します。
古びた丈夫な羊皮紙と、インクの匂い。虫除けのハーブ、微かに感じる黴臭さ。それらが層をなしてアマリリス達をかさりかさりと包み込む。図書館そのものを濃縮したような、慣れ親しんだ空気。知の薫り。
二枚のうち一枚は現在のストランジ領を描いた最近のもので、そしてもう一枚は、同じ地域のおおよそ百年前を描いた古い地図だ。いづれも領地は緑色で縁取られ、範囲が分かりやすい。
「知りたいのは、国家や近隣諸国の広い歴史ではなくて……領内だけでいいのよね?」
「ああ。特に、この近辺を」
「分かったわぁ。地図を見比べれば分かるように、ここカザヤ含め、現在のストランジ領の大半は元々別の家の領地だったの」
百年前の地図において緑で示されるのは、今のストランジ領の東端の方だけ。面積でいえば八分の一ほどにすぎない。その内側には『ストランジ
残りの部分は『リーヴァン子爵領』となっていて、リーヴァン領は西側に『インスピア子爵領』と接する。
カザヤはリーヴァン領の北の方に小さく描かれていた。
「リーヴァン、子爵領……」
フロウの滑らかな指が、細かい装飾のたくさん生えた文字を、ゆっくりとなぞる。
ランプの光が影の輪郭を、紙上の世界に落としていた。
再び訪れたカザヤ町図書館の閲覧室は、四人で入るには手狭で、ジェフリーは早々に別の用を済ませに行ってしまった。ただし、ちゃんと『声を上げたら駆け付けられる男手』はいる。町図書館の受付は盗難防止などの警備員を兼ねるので、この館の入口に座っているおじさんも根っからの武闘派なのだ。
アマリリスとフロウは机に顔を突き合わせ、ノアは小部屋の隅で二人を俯瞰している。
カザヤではフロウはずっと人の姿だ。魔術と縁の薄い人にとって、道をふよふよ這う水の球は、奇異に映ってしまうだろうから。傍で横顔が動くたび、柔らかな黒髪がちらついて心臓に悪い。
ジェフリーが手伝いとして呼び寄せた知己の魔術師、ということにして、服もジェフリーに借りて町民らしくしてもらった。フロウの目撃情報が噂になっているのを、ついでに誤魔化せたらいいのだけど。
(綺麗だけど派手な顔立ちではないし、服さえ変えたら町並みにも紛れ……るのは流石に無理かなぁ……?)
ともあれ。
膝に資料を数冊抱えたアマリリスは、記述と知識を照合し、段取りを頭の中でこね回しながら、なるべく丁寧に語り始めた。
「リーヴァン領だったまさに当時の資料はあまり現存していなくて、ストランジ家に編入された後に、過去を振り返って書かれたものがほとんど。だから色眼鏡は掛かっていると思って聞いてねぇ」
「分かった」
「こほん。……リーヴァン家末期の領内は、悪政で酷く荒れていたと記録にあるわ。耐えかねた領民による反乱が何度も起こるほどに。ここ、カザヤでも激しい戦いがあったのよ」
フロウはぴくりともせず、百年前の領地を見つめている。
いつもは透明感がある瞳には灯火の橙が照り返して、ぬらりと底の見えない沼のようだ。中に何者かが――何らかの意思が潜んでいるに違いないのだけれど、水面下に蠢いて影も形も掴めなかった。
◆
――当時は天候不順や疫病が重なって、国全体が疲弊していたの。それに加えて領主、リーヴァン家があまりに腐敗していたものだから、領民は明日も分からぬ生活を送っていたわ。
不作に手を打つこともせず、どころか自分達だけは安泰に生活するため重税を課して、他にも治安維持の放棄、役人の汚職――、悪政と聞いて思い付くもの全部、というありさまよ。末端の汚職もただの賄賂や横領なんてレベルじゃなく、はした金のために賊に便宜を図るようなのが横行していたらしいわぁ。
小規模な暴動とそれに対する弾圧は、数えきれないほど。それに加えて大きな蜂起が散発的に五回起こって、その最後には国が腰を上げ、リーヴァン家はお取り潰しになったの。
「カザヤで起こったのが最後か?」
いいえ。カザヤの反乱は、時系列で四番目。八ヶ月に渡る泥沼の末に、制圧されたそう。
ただ――。リーヴァン子爵家は王家にもあれこれ背信を働いていてねぇ。その証拠がカザヤの反乱の中で、どんな経緯でか国の中枢に伝わったと言われてるのよ。
それが後の騎士団介入の決定打になって、リーヴァンを倒したという見解もあるわ。
「そう、か。つまり、……何でもない、続けてくれ」
――? え、えぇ、分かったわぁ。
リーヴァン家が処断されて領地をどうするかという段になって、隣領だったストランジ男爵家に白羽の矢が立ったの。
当主は寝耳に水だったんですって。
一応、長年の魔術研究への寄与を認め封ずる、というのが表向きの理由だけど、実際の思惑は伝わっていないわ。
領地が急に八倍になり、しかも新たな領民は悪政と弾圧の爪痕に弱りきっている――。それでも、田舎の学者貴族なりに手を尽くして、お隣さんになったインスピア子爵家が支援してくれたりもして。
やっと領内の営みが立ち直ってきたところで、増えた領地に見合った子爵位に格上げされたのねぇ。
◆
「ここまでが現在のストランジ子爵領成立の経緯よ。詳しく知りたいことがあれば、分かる限り答えるわぁ」
「…………」
「……あの、えぇと、フロウ?」
フロウは等身大の壁画に塗り込められたように微動だにしない。不安になって、おずおず声をかけた。
地図に置かれたままの手がはっと震え、力なくその場を退く。擦れた紙の音は何故だかアマリリスを咎めるように聞こえた。彼はぼんやり顔を上げ、揺れるランプの火を見ている。
――いや、見てはいなかった。
視界のうちで一番目を引くものに適当に焦点を合わせているだけ、という様子だ。深く沈みゆく彼の意識に、温かい光は届いていない。
アマリリスは考える前に、フロウの腕を掴んでいた。
「っ、」
「あ。ご、ごめんなさい、その、」
「……ありがとうリィリ。大体分かった」
肌が拡散していく感覚にアマリリスの指が溺れると同時、フロウはほうと強ばりを解いた。
しかし――。ゆっくり瞬く彼は、明らかに後ろ髪を引かれている。いつもの凪いだ表情と比べて大きく感情を揺らし、そして押し殺している。
「遠慮しないで、何でも訊いてくれていいのよぅ……?」
「大丈夫だ。もういい」
それでも首を振って否定されたなら、こちらから話せることもない。
彼がまだ疑問を残しているというのは、アマリリスの勝手な想像だ。躊躇いを無理やりこじ開ける勇気は、それで全て終わりになっても受け入れられる覚悟は、まだ持てなかった。
無作法に触れていた手をそっと離すと、どうしようもなく寂しい。
(駄目ね……あなたを知るために契約したのに)
《
アマリリスの手首に一瞬、青い紋が浮かんだ。
「リィリこそ何か訊きたいんじゃないのか。契約のとき、知りたいと言っていた」
「私、は」
好奇心のポケットをひっくり返せば、順番待ちの質問はいくらでも出てくる。でも今一番知りたいこと、彼の表情の理由には、とても触れられない。
「じゃあ、……あの洞の門のこと。封じられていた、ってどういうことなのかしらぁ。閉じ込められていた訳じゃないのよね。術具を壊すずっと前に、あなたと会っているんだもの」
だから、おそらくノアも気にしていることを問うた。おいおいはノアが彼に抱く敵意も和らいでくれたら嬉しいから。
頷くフロウの目はランプから逸れ、薄暗い中でしんと佇む、いつもの薄青だ。
正体不明の動揺はもうどこかに隠れてしまっていた。
◆
「初めは言葉通り閉じ込められていた。あの門はオレを泉……行き止まりに窪みがあっただろう、その場所に押し留めるものだ。同時に意識を抑えられ、人でいう深い眠りに陥ってもいた」
「え、じゃあ、どうして外に出られたの?」
そこまで言ってから、アマリリスは思い出す。洞にあった術具の一つは欠けていた。
「オレが目を覚ましたのは、リィリが昔、洞に来たとき。何かの拍子に術が薄れたんだな」
「あっ……ふらふらして何度か壁にぶつかったわぁ!」
ということは、結局最初に術具を壊したのもアマリリスだったのか。元から壊れていたと他人事のように思っていたのが無性に恥ずかしくて、口元を押さえた。
「ただ、効果が不完全に残っていた。身体は解放されたものの、意識がぼやけて、まともに物も思えなかった」
「話せなかったのも、そのせい?」
フロウはこくりと首肯する。
精霊の
フロウのように人に近い思考をし人語を解する精霊はまれなのだ。それを普通の精霊ぐらいまで制限されていたのだろう。
完全に結界の抑制下にあった間を眠りと表現するなら、半端に解けた後の状態は夢遊病みたいなものかもしれない。記憶の中の彼が今よりずいぶん儚い雰囲気なのも、きっとそのせい。
「意識にはムラがあったから、術の影響が薄れている間に、リィリに門のことを伝えた」
「なるほどねぇ……。だからあなたの手では壊せなかった、というか壊そうと考えることもできなかったのね」
「そういうことだ」
「……あらぁ? じゃあどうして、あなたはこの辺りに来ていたの? てっきりあなたも門を破ろうとしていたものだと」
ただでさえアマリリスが別荘に来たのと時期が合いすぎて、不思議だったのだ。
フロウは額に拳を当てて、表現を探すようにぽつぽつと言葉を続けた。
「門とは関係ない。おかしな瘴気を感じて……それが、少しづつ移動していた。魔物かと思って追ってきただけだ」
「思考できなくても?」
「瘴気や魔物を厭うのは本能だからな。無意識でも排除することに変わりはない」
――やたらと好戦的だが、精霊は一般に魔物をひどく嫌悪する。力の弱い精霊は魔物を避けるし、強い精霊は魔物を苛烈に攻撃するらしい。
魔物は人間を含む生物だけでなく、自然に害を及ぼすので、自然の魔力と共にある精霊とは相容れないのだろう。
「えぇと、嫌でなければ、封印された経緯も……」
と、本題に戻ろうとしたとき。
コンコン。ノックが響いて、ジェフリーが戻ってきた。外開きのドアから廊下の新鮮な風がぶわりと流れ込む。
「あ、用事はもういいの?」
「はい。それと……盗み聞きするつもりはなかったんですが、魔物とか排除とかお話しされてましたよね」
「? えぇ」
「丁度カザヤの自警団に魔物狩りの相談を受けました」
ジェフリーはそこで言葉を止め、アマリリスをじっと伺う。なんとなく話は見えた。
頷きを返せば、ジェフリーはにっこりと人好きのする笑みを、アマリリスの隣に向ける。
「フロウさん、良かったら、ほんとに僕の仕事手伝ってみません?」
やろう、と。
半ば予想通りにフロウは即答した。
◆
◆
◆
【精霊の強さ①】
精霊の力量の尺度は多角的であり、簡単に強弱を判断できるものではありません。
観点の一つは『意識の鮮明さ』で、複雑な思考ができるかを指します。理性による感情の制御や、時系列や論理など抽象的なことを理解できるか、などを含みます。
主に他の精霊や生物、人間との関わりにより、刺激を受けることで発達します。