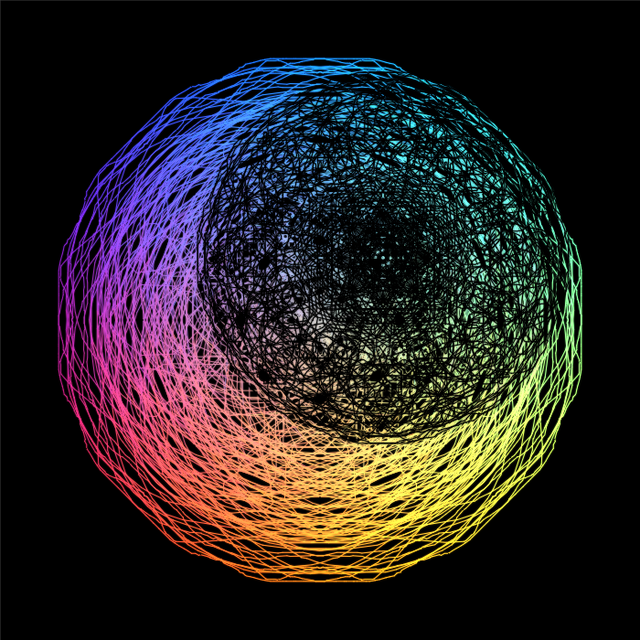小話: 8.1. 施錠されたドアに関する考察
文字数 5,064文字
「あっ」
唇から零れていく音を、アマリリスは慌てて両手で押さえた。
兎のせわしなさで周囲を伺う。夜明けの白く湿った空気が、不用意な声を吸い込んでくれていた。
夏なのにしぃんと冷たいほどの静寂はさながら秘された谷底のよう。そして眼前にそびえる未踏の遺跡こそが、ストランジ家カザヤ別荘である。
すなわち。扉は固く閉ざされている。
「……リィリ? 入らないのか?」
「その、えぇとね。こっそり三階のバルコニーから外に出たって言ったでしょぅ……?」
「ん」
フロウは澄んだ瞳でじっと見下ろしてくる。つらい。皆の前でテオドアに揶揄されるのの百倍はつらい。
曇りなき率直さは、ときに人を居たたまれなくするのだ。
「鍵のこと、考えてなかったわぁ……」
羞恥に耐えかねて、アマリリスは目を泳がせた。
正面エントランスおよび複数の裏口、今はぴたりと閉まった窓の鎧戸。これらの鍵は夜間、別荘を取り仕切る執事が管理している。それに元から施錠されている屋敷の玄関だけでなく、部屋にもわざわざ内から鍵を掛けてきてしまった。自室の鍵は机の引き出しの中だ。
騒ぎにならず目覚めの時間を迎えるには、二重の関門を突破しなければならない。もたもたして誰かに見咎められる前に。
「……ちょっとあっちで作戦会議しましょう!」
「分かった」
小声で宣言して、きょとんと立ち尽くしているフロウを庭木の陰に押していく。ぐいぐい。
言うまでもないが、恥ずかしさで変に上気した顔を誤魔化すためだ。
情けない経緯をなるだけかいつまんで説明すると、フロウはなおさら分からないというふうに首を傾げた。
「あの錠、術具だろう。たとえば合言葉で開くような」
「そういうの、見たことあるの?」
「ある」
意外だなぁ、なんて思うのはやっぱり失礼だろうか。でも術具の普及は中央の方が進んでいて、そして精霊は都市より田舎、田舎より手つかずの自然を好むものだ。古い大岩は豊富に地の魔力を抱いているが、それが石材として加工され荘厳な建築の一部となるときには、ほとんど霧散してしまうらしいので。
ともあれ。
目の前の全てを茫洋と眺めるような彼の視線に従って、アマリリスも屋敷に向き直る。視覚と記憶から『錠がある』と把握している位置に、ぽつぽつと魔力が重なっているのを感じる。こっくり艶めく地の力だ。
それでフロウも術具だと判断したんだろうし、実際その通り、魔晶を用いて常時起動しておくタイプの術具ではある。
「あれね、鍵と錠の仕組みは普通のものなのよぅ。《解錠 》や《開域 》みたいな魔術を無力化して、ついでに凄い音を出すっていう効果なの」
「つまりどうやっても鍵でしか開かないのか」
「そうねぇ。ずば抜けた術者なら反対に術具の効果を無力化できるだろうけれど……、学生がほいほい解けてしまったら防犯にならないわ」
全寮制のイースデイル魔術学園において、鍵に関する魔術はわりと初歩の嗜みである。自分の部屋は自力で守れ、との厳ついお達しだ。だからアマリリスも《施錠 》《解錠 》などを扱えるが、あまり上手くない。
一瞬だけ腰の短杖 に目を落とし、少しだけ口を尖らせる。自分にもっと魔術が使えたなら――いや、貴族邸宅のセキュリティをどうこうしたいなんて、流石に高望みか。
フロウはフロウで考え込んでいるようだったが、前触れなくその全身から色が抜け落ちた。ぴっ、と扉の一つに向けた指が、形はそのままに透けて潤んでいる。
「え、どうしたの」
「普通の錠なら、中をひねれば開くかもしれない」
「……鍵穴に指を突っ込むってこと?」
蜘蛛糸のごとき髪に飾られた、繊細なガラスのおとがいが頷く。
言っていることは全然繊細じゃないのがおかしくて、アマリリスはしのび笑った。
「ふ、ふふ。あなたって結構豪胆ねぇ」
「三階から飛び降りる方が余程じゃないか……? まともに地面とぶつかったら、ただで済まないだろうに」
――緩んだ口元は、至極もっともな指摘に引きつってしまったが。
「んんっ……それより、せっかく考えてくれたのにごめんなさい。『鍵穴に合わせて形を変える鍵』みたいな術具に対抗して、魔力を帯びたものが奥に触れても音が出るようになってるのよ」
「なるほど、それはまずいな」
「ね。どうしようかしら」
カザヤの豊かな山林を渡る風は、ふんわり軽い魔力を含んでいる。それが鍵穴に吹き込むたびに警報が鳴ったりはしないのだから、ある程度強い力にしか反応しないはず。
彼の身体はどうだろう。瞬く間に色づいて人肌そのものとなった手はたっぷりと水の力を滲ませているが、ギリギリいけたりしないものか。
(うぅ……ん、アウトかなぁ)
以前試しに発動された術具は、金属板をフォークで引っ掻くような耐え難い騒音を発した。あんな音が鳴ったら即座に護衛や執事が飛び起きてくる。とりあえずやってみよう、ができないのが悩ましいところだ。
「全部の入り口が施錠されていて、鍵はない。《解錠 》も効かない。あなたは鍵穴を弄れない。私も魔術抜きで鍵開けなんてできないわ。八方塞がりねぇ」
そうこうしている間にも、まばらだったチィチィという声が、あちこちで掛け合いを始めていた。
小鳥のハミングは淡い青天を引き連れ、山が目を醒ます。白んだ空気が溶かされて透き通っていく。その端にちょこんと間借りする屋敷の人々も、もう起き出しているだろう。
「なら、……行こう。見付からないか賭けになるが」
八方塞がりの、はずなのに。
フロウは――邸 内 に 入 る こ と 自 体 に は な ん の 障 害 も な い ような気軽さで、アマリリスを促したのだ。
◆
結果として。
アマリリスは無事部屋に帰り、食事を運んできたノアを待ち構えて事情を打ち明けることができた。ジェフリーには屋敷を抜け出したことまで話していないから、無断外出を知るのは当事者とノアのみだ。
そのノアも単独行動の危険性やフロウへの不信で怒りを燃やしていたため、どうやって施錠をかいくぐり自室に戻ったのかなんて些事を、掘り下げてはこなかった。
だから、あの幻のような時間は、本当に二人だけの間で共有されている。
◆
白が世界を埋め尽くす。
手すりの外に腕を差しのべれば、中ほどまでが飲み込まれ、指の先は霞みがかる。その手すり、あるいは体重を預けた踏み板は無色で、煌めきと透かした白が合わさって銀雪のようでもある。丸く切り取られた空だけが彼の目と同じ薄青だ。
「リィリ、誰か出てくる前に早く」
背後から急かす声に、アマリリスは『えぇ』だか『うん』だか曖昧な返事をした。したと思う。
現実味のない光景に止まっていた足を、次の段に乗せる。引き戻した腕は訓練着ごとしっとり湿っている。
フロウに言われるまま自室の真下まで案内したときには、もう辺りは真っ白だった。彼が歩を進めるごと、消えかけていた朝靄の紗を折り重ね、屋敷を閉じ込めるほど厚くなった天蓋は夜霧の再来。明けの歌声すらも遠のかせてしまう。
砂時計の砂を逆に落とすと時間が戻り、しくじったことをやり直せる――まるでそんなおとぎ話だ。
無言で彼が示した先、幕を開いてぬうと現れた水晶の階 は、急な螺旋を描いていた。
「……上るの?」
「バルコニーから出たならバルコニーから入ればいいだろう」
「それは、そうねぇ」
返した言葉は、あんまりにも間が抜けたもの。
仕方ないのだ。受け止めきれない驚きに直面すると人は無防備になるものなんだ。きっとそう。
きんきんに冷たいのを覚悟して掴んだ手すりは意外とぬるい。氷、ではないのだろうか。その内側、螺旋の中はくり抜いたように霧が途切れていた。
そっと踏んだ最初の段は軋みも滑りもしなかった。そうして、とん、とん――と、アマリリスは白い筒をゆっくり上っている。
すぐ後ろに息遣いが聞こえて、そういえば彼は呼吸をするのだな、とぼんやり考えながら。
◆
「訂正するわぁ。あなたってかなり豪胆ね」
遮るもののない空のもとで二人。バルコニーから眼下を望んでいる。
彼の手を借りて螺旋階段のてっぺんから降り立ってすぐ、アマリリス達を三階まで運んだそれは、微睡みの夢のように霧散してしまった。
「見て、あっちの方まで霧の端っこが届いてる」
「本当だ。……ここは眺めがいいな」
フロウは上体を乗り出し、少し見開いた目にちかちか光を弾かせている。
バルコニーの外には床の高さまで白が波打っていた。霧は広く拡散していって、遠くにいくにつれ樹々がくっきりと頭を出す。厚塗りの中に棒で掻いたような茶色の線はカザヤの町に続く小道で、ずっと辿っていった先に、飾り小箱みたいな家屋が密集している。
「お父様がね、町まで見晴らせて、いっとう風が通る部屋をくれたのよ。気に入ってもらえて嬉しいわぁ」
隣に並んで、アマリリスは稜線と空の合間に両手を伸ばした。
風光明媚な絶景とは違う。けれど雄大な夏山とその麓に拓けた町並みは、一個の人間である自分 を、地に根差した血筋 と結び付けている気がする。この心を形作る原風景のひとつなのだ。
そして――。噴き上がる樹木の息吹と、まだ低いところにある陽の光がぶつかっては散っていく。ここ毎日見ていた景色が、まるきり羽化したように活力を溢れさせている。
深呼吸すれば大気がゆるりと肺を巡った。それを穏やかに吐き出しきって、彼を見上げる。清らかな横顔は白霧の主にふさわしく風景と調和している。
「ね、あなたはきっと色んなものを見てきたのでしょぅ? あなたの心に残っている情景はどんなものなのかしら」
普通の精霊なら縁がない術具のことまで知っているのだ。アマリリスには想像もつかないほどの、並々ならぬ歳月を過ごしてきたんだろう。
フロウはこちらに顔を向け、淡く目を細めた。
「……凍る滝。果ての見えない沼地。地底湖の底に紛れ込んだ光の色」
「すごいわ! いつか行ってみたいわねぇ」
「それらに劣らず、この景色を鮮烈に感じている。今まではあまり見 え て い な か っ た から」
アマリリスは虚を突かれてしまい、それから言葉の意味をじわじわ噛み締めた。契約した直後はあれほど実感していたというのに。
彼にとって、人と同じ視力で見渡す風景は、これが初めてなんだ。アマリリスがいつになく樹々や朝陽を力強く感じたのも、同じこと。屹立する地 、降り注ぐ火 が、感覚に乗っていたからだ。
感覚の相互補完。魔術師ならほとんどの者が当たり前に得ている恩恵。しかしこの場この瞬間において、それはなにか途方もない特別だった。
驚きに麻痺していた思考が、音を立てて流れ出す。
真白の螺旋の中、見つかってはいけないのに、急いで上りきるべきなのに、アマリリスは何度も足を止めた。
気後れのせいだと思っていた。フロウが軽々と披露した力の凄さに尻込みしたのだと。非凡な精霊が凡人の自分と契約しているなんて、期限付きであってもあまりに不釣り合いだ。
だが誤りだった。奇跡みたいに凄 い のは、彼の力や起こした事象そのものよりも――、
「ありがとう、フロウ。私、ちゃんとお礼も言っていなかったわ」
「騒ぎになるのはオレも困る」
「それよぅ! 実際に助けてくれたことだけじゃなくて……、自分の事として一緒に悩んでくれたでしょ?」
問いに相対するとき、一人では考えもつかない答えを見出だしてくれること。
『私』にないものが『あなた』にあること。
――『あなた』にできないことが、もしかしたら『私』にできるということ。
《精霊契約 》は、互いを補い合うという、脆く確かな約束である。
近い未来に失うことが決まっているそれはかけがえなく、刹那の奇跡の儚さで、たまらなく愛おしい。
アマリリスはただ、あ の 階 段 を ず っ と 上 っ て い た か っ た のだ。
けれど、
「あなたとこうして並んで、ここからの景色が見られて嬉しいわぁ。私も、昨日より、十年前より、今日が一番綺麗に思えるの」
「そうだな。とても、綺麗だ」
やわらかな同意。融け合った視線が、示し合わせたように眺望へと戻る。霧は再び薄れ始め、――あぁ、階下には朝仕度の気配。つかの間の夜明けは終わろうとしている。
(ねぇ。もしもあなたが開かないドアの前で困っていたら、私はなんだってするわ)
明日見る景色はもっと綺麗だといい。叶うなら、契約を終えてなお世界を美しく感じられるほどの思い出を、それぞれの心に残したい。
期間限定だろうと分不相応だろうと、今《精霊契約 》を結んでいた事実は消えないのだから。
名残を振り切って彼の袖を引く。背にした山並みに、千の小鳥の誇らしげな歌が響いていた。
唇から零れていく音を、アマリリスは慌てて両手で押さえた。
兎のせわしなさで周囲を伺う。夜明けの白く湿った空気が、不用意な声を吸い込んでくれていた。
夏なのにしぃんと冷たいほどの静寂はさながら秘された谷底のよう。そして眼前にそびえる未踏の遺跡こそが、ストランジ家カザヤ別荘である。
すなわち。扉は固く閉ざされている。
「……リィリ? 入らないのか?」
「その、えぇとね。こっそり三階のバルコニーから外に出たって言ったでしょぅ……?」
「ん」
フロウは澄んだ瞳でじっと見下ろしてくる。つらい。皆の前でテオドアに揶揄されるのの百倍はつらい。
曇りなき率直さは、ときに人を居たたまれなくするのだ。
「鍵のこと、考えてなかったわぁ……」
羞恥に耐えかねて、アマリリスは目を泳がせた。
正面エントランスおよび複数の裏口、今はぴたりと閉まった窓の鎧戸。これらの鍵は夜間、別荘を取り仕切る執事が管理している。それに元から施錠されている屋敷の玄関だけでなく、部屋にもわざわざ内から鍵を掛けてきてしまった。自室の鍵は机の引き出しの中だ。
騒ぎにならず目覚めの時間を迎えるには、二重の関門を突破しなければならない。もたもたして誰かに見咎められる前に。
「……ちょっとあっちで作戦会議しましょう!」
「分かった」
小声で宣言して、きょとんと立ち尽くしているフロウを庭木の陰に押していく。ぐいぐい。
言うまでもないが、恥ずかしさで変に上気した顔を誤魔化すためだ。
情けない経緯をなるだけかいつまんで説明すると、フロウはなおさら分からないというふうに首を傾げた。
「あの錠、術具だろう。たとえば合言葉で開くような」
「そういうの、見たことあるの?」
「ある」
意外だなぁ、なんて思うのはやっぱり失礼だろうか。でも術具の普及は中央の方が進んでいて、そして精霊は都市より田舎、田舎より手つかずの自然を好むものだ。古い大岩は豊富に地の魔力を抱いているが、それが石材として加工され荘厳な建築の一部となるときには、ほとんど霧散してしまうらしいので。
ともあれ。
目の前の全てを茫洋と眺めるような彼の視線に従って、アマリリスも屋敷に向き直る。視覚と記憶から『錠がある』と把握している位置に、ぽつぽつと魔力が重なっているのを感じる。こっくり艶めく地の力だ。
それでフロウも術具だと判断したんだろうし、実際その通り、魔晶を用いて常時起動しておくタイプの術具ではある。
「あれね、鍵と錠の仕組みは普通のものなのよぅ。《
「つまりどうやっても鍵でしか開かないのか」
「そうねぇ。ずば抜けた術者なら反対に術具の効果を無力化できるだろうけれど……、学生がほいほい解けてしまったら防犯にならないわ」
全寮制のイースデイル魔術学園において、鍵に関する魔術はわりと初歩の嗜みである。自分の部屋は自力で守れ、との厳ついお達しだ。だからアマリリスも《
一瞬だけ腰の
フロウはフロウで考え込んでいるようだったが、前触れなくその全身から色が抜け落ちた。ぴっ、と扉の一つに向けた指が、形はそのままに透けて潤んでいる。
「え、どうしたの」
「普通の錠なら、中をひねれば開くかもしれない」
「……鍵穴に指を突っ込むってこと?」
蜘蛛糸のごとき髪に飾られた、繊細なガラスのおとがいが頷く。
言っていることは全然繊細じゃないのがおかしくて、アマリリスはしのび笑った。
「ふ、ふふ。あなたって結構豪胆ねぇ」
「三階から飛び降りる方が余程じゃないか……? まともに地面とぶつかったら、ただで済まないだろうに」
――緩んだ口元は、至極もっともな指摘に引きつってしまったが。
「んんっ……それより、せっかく考えてくれたのにごめんなさい。『鍵穴に合わせて形を変える鍵』みたいな術具に対抗して、魔力を帯びたものが奥に触れても音が出るようになってるのよ」
「なるほど、それはまずいな」
「ね。どうしようかしら」
カザヤの豊かな山林を渡る風は、ふんわり軽い魔力を含んでいる。それが鍵穴に吹き込むたびに警報が鳴ったりはしないのだから、ある程度強い力にしか反応しないはず。
彼の身体はどうだろう。瞬く間に色づいて人肌そのものとなった手はたっぷりと水の力を滲ませているが、ギリギリいけたりしないものか。
(うぅ……ん、アウトかなぁ)
以前試しに発動された術具は、金属板をフォークで引っ掻くような耐え難い騒音を発した。あんな音が鳴ったら即座に護衛や執事が飛び起きてくる。とりあえずやってみよう、ができないのが悩ましいところだ。
「全部の入り口が施錠されていて、鍵はない。《
そうこうしている間にも、まばらだったチィチィという声が、あちこちで掛け合いを始めていた。
小鳥のハミングは淡い青天を引き連れ、山が目を醒ます。白んだ空気が溶かされて透き通っていく。その端にちょこんと間借りする屋敷の人々も、もう起き出しているだろう。
「なら、……行こう。見付からないか賭けになるが」
八方塞がりの、はずなのに。
フロウは――
◆
結果として。
アマリリスは無事部屋に帰り、食事を運んできたノアを待ち構えて事情を打ち明けることができた。ジェフリーには屋敷を抜け出したことまで話していないから、無断外出を知るのは当事者とノアのみだ。
そのノアも単独行動の危険性やフロウへの不信で怒りを燃やしていたため、どうやって施錠をかいくぐり自室に戻ったのかなんて些事を、掘り下げてはこなかった。
だから、あの幻のような時間は、本当に二人だけの間で共有されている。
◆
白が世界を埋め尽くす。
手すりの外に腕を差しのべれば、中ほどまでが飲み込まれ、指の先は霞みがかる。その手すり、あるいは体重を預けた踏み板は無色で、煌めきと透かした白が合わさって銀雪のようでもある。丸く切り取られた空だけが彼の目と同じ薄青だ。
「リィリ、誰か出てくる前に早く」
背後から急かす声に、アマリリスは『えぇ』だか『うん』だか曖昧な返事をした。したと思う。
現実味のない光景に止まっていた足を、次の段に乗せる。引き戻した腕は訓練着ごとしっとり湿っている。
フロウに言われるまま自室の真下まで案内したときには、もう辺りは真っ白だった。彼が歩を進めるごと、消えかけていた朝靄の紗を折り重ね、屋敷を閉じ込めるほど厚くなった天蓋は夜霧の再来。明けの歌声すらも遠のかせてしまう。
砂時計の砂を逆に落とすと時間が戻り、しくじったことをやり直せる――まるでそんなおとぎ話だ。
無言で彼が示した先、幕を開いてぬうと現れた水晶の
「……上るの?」
「バルコニーから出たならバルコニーから入ればいいだろう」
「それは、そうねぇ」
返した言葉は、あんまりにも間が抜けたもの。
仕方ないのだ。受け止めきれない驚きに直面すると人は無防備になるものなんだ。きっとそう。
きんきんに冷たいのを覚悟して掴んだ手すりは意外とぬるい。氷、ではないのだろうか。その内側、螺旋の中はくり抜いたように霧が途切れていた。
そっと踏んだ最初の段は軋みも滑りもしなかった。そうして、とん、とん――と、アマリリスは白い筒をゆっくり上っている。
すぐ後ろに息遣いが聞こえて、そういえば彼は呼吸をするのだな、とぼんやり考えながら。
◆
「訂正するわぁ。あなたってかなり豪胆ね」
遮るもののない空のもとで二人。バルコニーから眼下を望んでいる。
彼の手を借りて螺旋階段のてっぺんから降り立ってすぐ、アマリリス達を三階まで運んだそれは、微睡みの夢のように霧散してしまった。
「見て、あっちの方まで霧の端っこが届いてる」
「本当だ。……ここは眺めがいいな」
フロウは上体を乗り出し、少し見開いた目にちかちか光を弾かせている。
バルコニーの外には床の高さまで白が波打っていた。霧は広く拡散していって、遠くにいくにつれ樹々がくっきりと頭を出す。厚塗りの中に棒で掻いたような茶色の線はカザヤの町に続く小道で、ずっと辿っていった先に、飾り小箱みたいな家屋が密集している。
「お父様がね、町まで見晴らせて、いっとう風が通る部屋をくれたのよ。気に入ってもらえて嬉しいわぁ」
隣に並んで、アマリリスは稜線と空の合間に両手を伸ばした。
風光明媚な絶景とは違う。けれど雄大な夏山とその麓に拓けた町並みは、一個の人間である
そして――。噴き上がる樹木の息吹と、まだ低いところにある陽の光がぶつかっては散っていく。ここ毎日見ていた景色が、まるきり羽化したように活力を溢れさせている。
深呼吸すれば大気がゆるりと肺を巡った。それを穏やかに吐き出しきって、彼を見上げる。清らかな横顔は白霧の主にふさわしく風景と調和している。
「ね、あなたはきっと色んなものを見てきたのでしょぅ? あなたの心に残っている情景はどんなものなのかしら」
普通の精霊なら縁がない術具のことまで知っているのだ。アマリリスには想像もつかないほどの、並々ならぬ歳月を過ごしてきたんだろう。
フロウはこちらに顔を向け、淡く目を細めた。
「……凍る滝。果ての見えない沼地。地底湖の底に紛れ込んだ光の色」
「すごいわ! いつか行ってみたいわねぇ」
「それらに劣らず、この景色を鮮烈に感じている。今まではあまり
アマリリスは虚を突かれてしまい、それから言葉の意味をじわじわ噛み締めた。契約した直後はあれほど実感していたというのに。
彼にとって、人と同じ視力で見渡す風景は、これが初めてなんだ。アマリリスがいつになく樹々や朝陽を力強く感じたのも、同じこと。屹立する
感覚の相互補完。魔術師ならほとんどの者が当たり前に得ている恩恵。しかしこの場この瞬間において、それはなにか途方もない特別だった。
驚きに麻痺していた思考が、音を立てて流れ出す。
真白の螺旋の中、見つかってはいけないのに、急いで上りきるべきなのに、アマリリスは何度も足を止めた。
気後れのせいだと思っていた。フロウが軽々と披露した力の凄さに尻込みしたのだと。非凡な精霊が凡人の自分と契約しているなんて、期限付きであってもあまりに不釣り合いだ。
だが誤りだった。奇跡みたいに
「ありがとう、フロウ。私、ちゃんとお礼も言っていなかったわ」
「騒ぎになるのはオレも困る」
「それよぅ! 実際に助けてくれたことだけじゃなくて……、自分の事として一緒に悩んでくれたでしょ?」
問いに相対するとき、一人では考えもつかない答えを見出だしてくれること。
『私』にないものが『あなた』にあること。
――『あなた』にできないことが、もしかしたら『私』にできるということ。
《
近い未来に失うことが決まっているそれはかけがえなく、刹那の奇跡の儚さで、たまらなく愛おしい。
アマリリスはただ、
けれど、
「あなたとこうして並んで、ここからの景色が見られて嬉しいわぁ。私も、昨日より、十年前より、今日が一番綺麗に思えるの」
「そうだな。とても、綺麗だ」
やわらかな同意。融け合った視線が、示し合わせたように眺望へと戻る。霧は再び薄れ始め、――あぁ、階下には朝仕度の気配。つかの間の夜明けは終わろうとしている。
(ねぇ。もしもあなたが開かないドアの前で困っていたら、私はなんだってするわ)
明日見る景色はもっと綺麗だといい。叶うなら、契約を終えてなお世界を美しく感じられるほどの思い出を、それぞれの心に残したい。
期間限定だろうと分不相応だろうと、今《
名残を振り切って彼の袖を引く。背にした山並みに、千の小鳥の誇らしげな歌が響いていた。