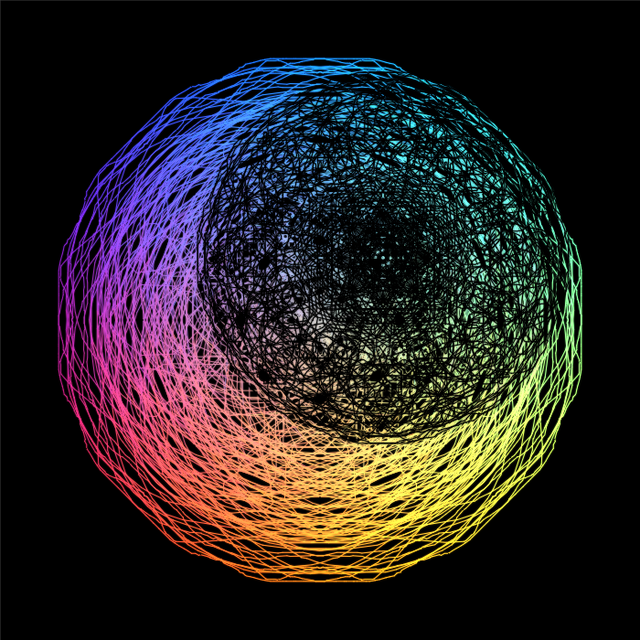26. 契約更新
文字数 4,120文字
西の残り火は藍色の夜に全天を明け渡し、星々は瞬くごとに鋭さを増す。仄白い光がそれらを、また眼下の世界を、かき抱いている。
月は真円。契約を結んだあの日から丁度一巡りだった。
「納涼の宴ではなくなってしまったけれど。やっとゆっくりお食事できるわねぇ」
沢山の料理が並んだ小ぶりな横長のテーブルの向こうで、フロウがもぞもぞと座っている。身に纏うのは水を編んだ服でも、ジェフリーに借りていた町民らしい服でもなく、洗練されたデザインの正装だ。襟元の白が本人の繊細な造形を引き立てる。
遮るものなく降り注ぐ月光に柔らかな髪の筋が照らされ、濡れたように艶めく。しんと静かな瞳には卓上の灯りがとろとろ映り込んでいた。
アマリリスは感嘆を苦笑に紛れさせ、なんとか普段の話し方を取り繕った。
「ゆっくり……にしては堅苦しいかしらぁ。ごめんなさい、みんな張り切っちゃって。窮屈でしょぅ」
「ん、そのうち慣れると思う」
本邸に戻ってやっと落ち着いてきたので、約束していた晩餐をやり直そうということになった。これが執事長の耳に入り、あれよあれよという間にオーダーメイドで一着仕立てられたのである。かくいうアマリリスもベージュに銀の光沢を乗せた夜会用のドレスで、髪をふわふわに結い上げてもらっている。
袖口を気にしながらフロウが小杯を取り上げるのに合わせ、アマリリスも胸の高さに掲げる。芳醇に漂うブドウとオレンジの香りを吸い込んで――、
「栄え繁るこの夏の夜に。……乾杯」
「乾杯」
シロップ割りの赤ワインを、軽快に飲み干した。
◆
ストランジ邸主棟のささやかな屋上には樹木も花壇もない。代わりに水路を模した溝に白砂が波模様を描いて流れ、立ち並ぶ水の像が幾何学的に形を変えていく。風の結界が虫や暑さを遠ざけて、夜には控えめな光球が足元とテーブルに漂う。
先代の当主が血筋への誇りと多大な茶目っ気をもって造り上げた魔術庭園である。
「そういえば別荘にも水像の術具があるの。十年前に見たの、覚えてるかしらぁ」
「記憶にないな……意識が薄いタイミングだったんだろう」
「あなたがつついたら、ぱぁんって水が噴き上がって凄かったのよ」
懐かしさに笑みをこぼすアマリリスとは逆に、フロウは眉を下げた。
「壊したのか? すまない」
「術具の本体は全然壊れてないから平気よぅ。あのね、弾けた飛沫に、虹が二つも掛かってすごく綺麗だったわ」
「なら良いが……」
フロウは曖昧に頷きながら、水のねじれた三角柱が立方体の集積に移り変わるのを、ぼぅっと眺めている。魔力の端っこがゆるゆるそちらに伸び、切り立った水面を撫でても、暴発したりはしなかった。
改めて、食事を口に運ぶ。
「あなたのスープは全部濾してくれたはずなのだけど、大丈夫そう?」
「ああ、飲みやすい。味が……複雑で、密だな。玉葱の匂いが分厚く感じる」
瓜と玉葱の冷製スープは金に透き通っている。一匙含むと、苦味や辛味をほんのアクセントに、なみなみと旨味が押し寄せる。薄切りの実は舌で押せば潰れる軟らかさ。
このスープは具の有無を除いて二人とも全く同じもの。そして固形物が苦手なフロウは他の料理を食べられないので、それぞれに似た食材のスープが用意されている。テーブルの向こう半分は陶器の深皿や両耳の丸っこいカップ、口広の足付きガラス杯などが林立して、変わった趣向の静物画のようだ。
彷徨う左手と丁寧にスプーンを持つ右手だけが生彩を持ち、絵に描いたような場面を実物と知らしめている。
「次はどれにしよう。悩ましい」
給仕はいない。気さくに最初から全部の料理が卓上に並べられ、飲み物も瓶やポットからめいめいに注ぐ。
「鱒のスープはどうかしら。ね、一緒に食べましょ」
アマリリスは鱒の包み焼きの皿を引き寄せた。
折り重なって具材をくるんでいるのは柿の葉だ。上下から鉄板で挟み焼かれ、茶色く焦げたそれをナイフとフォークで切りはがす。溢れ出た湯気が顔にあたると、魚の香りに鼻をくすぐる刺激がひそんでいた。
見えてきたのは赤みが強い一口大の鱒の切り身。黒い粒は胡椒だろう。食べやすく刻まれた葉物たちは良い具合にくたくた、下に敷かれた潰し芋はバターが溶け込んでじゅわじゅわ。
まず鱒だけをぱくりと、次に芋をたっぷり乗せていただく。フロウは壺に似た小さな器から中身を掬っている。
「はふ。シンプルな味付けが染みいるわぁ」
「……辛 い。なんだこれ……、辛 い……」
「口に合わなければ、無理しないでね?」
「いや、後味はとても良い。魚の旨さが、……そうだな、染みいる」
確か料理人曰く、『スパイスをカンカンに効かせた鱒のミルクスープ』だとか。どれくらい辛 いのだろう。時々きゅっと顔をしかめながらもスプーンを止めない姿を見ていると、アマリリスも飲んでみたくなってきた。今度厨房にリクエストしてみよう。
食事は、最後まで楽しかった。
白ブドウのジュースでまた乾杯したし、コクのあるエールを舌と喉で味わった。酒に酔わないというフロウは瓶を片っ端から味見した。
カザヤで買った干し肉と乾燥山菜のおつまみをアマリリスが齧るとき、彼は小さなカップを舐めて驚いていた。塩気と山菜のほろ苦い風味が凝縮された特濃のスープだったらしい。
――照明の術具を止めて、夜空を映した香り高い紅茶を飲む。渋みが薄く食後の口によく馴染む。ほうと息を吐くと冬でもないのに白く見えそうだ。
皿やグラスが月下に、満ち足りた時間の抜け殻を晒している。街は眠りに就きだして、卓の周りだけがぽっかりと、星の中に浮かぶ。
「フロウ」
呼べば穏やかな佇まいで見つめ返された。ティーカップももう空だ。
終 わ っ た な ら 、始 め な け れ ば な ら な い 。
◆
「ねぇ、フロウ。本邸 まで来てくれて、ありがとう」
「? 夏の間の契約だったろう」
「夏はカザヤにいるからその間、の契約だったわ。それに宴の夜、あなたは去るつもりで私を癒してくれたのでしょぅ」
フロウは目を丸くした。どうして知っているんだと言わんばかり。共に過ごすうち、彼はずいぶん気持ちを表すようになった。
そう、百年の冬が徐々にほころぶひとときに、居合わせたことが幸福だ。胸の奥が震えるのは温かさゆえだ。
「ここにいてくれるあなたの心を、義理だとか疑うつもりはないわぁ。でも改めて言葉にさせて。……夏が終わるまで、どうか私と、アマリリス・ストランジと契約を結んでいてほしいの」
彼がこの契約を『夏の間』と捉えていたのなら、敢えて乞うまでもないのかもしれない。だとしても。
不可解そうに拳を顎に当てるフロウが、口を開く前に、声を割り込ます。
「契約を望むのは、ただあなたと一緒にいたいから。あなたといるだけで楽しくて、嬉しいからよ。思慮も必然性もない、そんな我欲で、許されるのなら」
「……リィリ」
耳朶を撫で、夜に溶けていく声に、ざわりと鳥肌が立った。
精霊は不本意なことをしない。ならばカザヤからはるばるついてきてくれたフロウが、残りわずかな日数を断りはしないだろうという自惚れがあり。同時に、だからこそ断られたら立ち直れないという怯えがある。
――色よい返事を思い描いては駄目。
「契約のとき、オレが拒否したから、リィリは期間の縛りをつけたんだよな」
「……っ、えぇ」
あぁ、なのに、柔らかい視線を向けられると期待してしまう。アマリリスはフロウを想えば少しだけ奮い立てるが、面と向かうとぐずぐずに弱くなる。
「元々は無期限の契約がお前の望みだった。……それはまだ変わりないか?」
「か、かわりない、わぁ」
最も都合の良い台詞が。
鼓膜から、脳髄を冒す。
「契約の内容を新しくしよう。オレも夏の終わりを越えて、リィリといたい」
くらくらと今更な酔いが追ってきた。あまりにも己の願望そのまますぎて、夢ではないかと疑ってしまう。
「ぇと……あの。どうして……?」
すぐ肯定すれば良いものを、アマリリスは返事を先延ばしにし、問い返した。喜んで飛びついた瞬間にベッドの上で虚しく目醒めてしまう気がした。もう一月足らずの休暇中だけならともかく、それ以上付き合ってくれる理由が見当たらない。
対するフロウは平然と言う。
「オレは目の前で、誰かが苦しんでいるのが嫌だ。だが遠く離れたところでお前に何かあったら、それに気付きもせずにいるのだとしたら、もっと耐えられないと思った」
そうしてから、口角を少しだけ上げた。
春の泉に花弁が落ちるような淡い笑み――。星月夜に沈んだ透明な瞳だけが、挑むように強くアマリリスを見ている。
「リィリはオレが悲しんだり、後悔したりするのが嫌なんだろう」
「えぇ。あなたに苦い思いをしてほしくない」
「なら、オレがいることで慢心を招くからと離れるより……近くにいた方がお前の身体にも良いはずだ。リィリが無茶をするたび、横でたっぷり悲しんでやる」
密やかに奏でる声音が、脅しじみたことを言う。そのちぐはぐな言葉に、表情に、圧されて息が止まった。
そして知った。
アマリリスが困難を承知で彼といたいと、父との問答で確かめたように。フロウも何かを考え、決めたのだと。
ちぐはぐなのに真っ直ぐな面持ちは、アマリリスの胸の震えを貫いて、紅茶よりも優しく激しい熱を注ぐ。
フロウは身を乗り出して、食器ごしに左手を差し伸べてくる。その手首に青く紋様が走った。二人を結ぶ繋がりを意識すれば、こちらの右手にも同じ光が浮かび上がる。
「うん……喜んで、応じるわぁ。契約の更新に」
重ねた指先が融け合っていく。呪文は必要ない。二人で決めたことが全て。
彼の内心は計り知れず、しかし隣に立って、同じ方を向いている。互いを損ないたくないと思っている。
手を繋いでいるには、それで十分だった。
◆
◆
◆
【ストランジ邸魔術庭園】
ストランジ邸屋上にある魔術庭園は魔術師の間では少々有名です。これを造り上げた先代当主本人が、魔術師ではなかったという点で。
コンプレックスの発露とも、魔力がなくとも知識により魔術を御し得るとの意思表示だとも、まことしやかに噂されています。
なおストランジ家の歴代当主の魔術師率は三割ほどで、国内平均に比べかなりの多さです。
月は真円。契約を結んだあの日から丁度一巡りだった。
「納涼の宴ではなくなってしまったけれど。やっとゆっくりお食事できるわねぇ」
沢山の料理が並んだ小ぶりな横長のテーブルの向こうで、フロウがもぞもぞと座っている。身に纏うのは水を編んだ服でも、ジェフリーに借りていた町民らしい服でもなく、洗練されたデザインの正装だ。襟元の白が本人の繊細な造形を引き立てる。
遮るものなく降り注ぐ月光に柔らかな髪の筋が照らされ、濡れたように艶めく。しんと静かな瞳には卓上の灯りがとろとろ映り込んでいた。
アマリリスは感嘆を苦笑に紛れさせ、なんとか普段の話し方を取り繕った。
「ゆっくり……にしては堅苦しいかしらぁ。ごめんなさい、みんな張り切っちゃって。窮屈でしょぅ」
「ん、そのうち慣れると思う」
本邸に戻ってやっと落ち着いてきたので、約束していた晩餐をやり直そうということになった。これが執事長の耳に入り、あれよあれよという間にオーダーメイドで一着仕立てられたのである。かくいうアマリリスもベージュに銀の光沢を乗せた夜会用のドレスで、髪をふわふわに結い上げてもらっている。
袖口を気にしながらフロウが小杯を取り上げるのに合わせ、アマリリスも胸の高さに掲げる。芳醇に漂うブドウとオレンジの香りを吸い込んで――、
「栄え繁るこの夏の夜に。……乾杯」
「乾杯」
シロップ割りの赤ワインを、軽快に飲み干した。
◆
ストランジ邸主棟のささやかな屋上には樹木も花壇もない。代わりに水路を模した溝に白砂が波模様を描いて流れ、立ち並ぶ水の像が幾何学的に形を変えていく。風の結界が虫や暑さを遠ざけて、夜には控えめな光球が足元とテーブルに漂う。
先代の当主が血筋への誇りと多大な茶目っ気をもって造り上げた魔術庭園である。
「そういえば別荘にも水像の術具があるの。十年前に見たの、覚えてるかしらぁ」
「記憶にないな……意識が薄いタイミングだったんだろう」
「あなたがつついたら、ぱぁんって水が噴き上がって凄かったのよ」
懐かしさに笑みをこぼすアマリリスとは逆に、フロウは眉を下げた。
「壊したのか? すまない」
「術具の本体は全然壊れてないから平気よぅ。あのね、弾けた飛沫に、虹が二つも掛かってすごく綺麗だったわ」
「なら良いが……」
フロウは曖昧に頷きながら、水のねじれた三角柱が立方体の集積に移り変わるのを、ぼぅっと眺めている。魔力の端っこがゆるゆるそちらに伸び、切り立った水面を撫でても、暴発したりはしなかった。
改めて、食事を口に運ぶ。
「あなたのスープは全部濾してくれたはずなのだけど、大丈夫そう?」
「ああ、飲みやすい。味が……複雑で、密だな。玉葱の匂いが分厚く感じる」
瓜と玉葱の冷製スープは金に透き通っている。一匙含むと、苦味や辛味をほんのアクセントに、なみなみと旨味が押し寄せる。薄切りの実は舌で押せば潰れる軟らかさ。
このスープは具の有無を除いて二人とも全く同じもの。そして固形物が苦手なフロウは他の料理を食べられないので、それぞれに似た食材のスープが用意されている。テーブルの向こう半分は陶器の深皿や両耳の丸っこいカップ、口広の足付きガラス杯などが林立して、変わった趣向の静物画のようだ。
彷徨う左手と丁寧にスプーンを持つ右手だけが生彩を持ち、絵に描いたような場面を実物と知らしめている。
「次はどれにしよう。悩ましい」
給仕はいない。気さくに最初から全部の料理が卓上に並べられ、飲み物も瓶やポットからめいめいに注ぐ。
「鱒のスープはどうかしら。ね、一緒に食べましょ」
アマリリスは鱒の包み焼きの皿を引き寄せた。
折り重なって具材をくるんでいるのは柿の葉だ。上下から鉄板で挟み焼かれ、茶色く焦げたそれをナイフとフォークで切りはがす。溢れ出た湯気が顔にあたると、魚の香りに鼻をくすぐる刺激がひそんでいた。
見えてきたのは赤みが強い一口大の鱒の切り身。黒い粒は胡椒だろう。食べやすく刻まれた葉物たちは良い具合にくたくた、下に敷かれた潰し芋はバターが溶け込んでじゅわじゅわ。
まず鱒だけをぱくりと、次に芋をたっぷり乗せていただく。フロウは壺に似た小さな器から中身を掬っている。
「はふ。シンプルな味付けが染みいるわぁ」
「……
「口に合わなければ、無理しないでね?」
「いや、後味はとても良い。魚の旨さが、……そうだな、染みいる」
確か料理人曰く、『スパイスをカンカンに効かせた鱒のミルクスープ』だとか。どれくらい
食事は、最後まで楽しかった。
白ブドウのジュースでまた乾杯したし、コクのあるエールを舌と喉で味わった。酒に酔わないというフロウは瓶を片っ端から味見した。
カザヤで買った干し肉と乾燥山菜のおつまみをアマリリスが齧るとき、彼は小さなカップを舐めて驚いていた。塩気と山菜のほろ苦い風味が凝縮された特濃のスープだったらしい。
――照明の術具を止めて、夜空を映した香り高い紅茶を飲む。渋みが薄く食後の口によく馴染む。ほうと息を吐くと冬でもないのに白く見えそうだ。
皿やグラスが月下に、満ち足りた時間の抜け殻を晒している。街は眠りに就きだして、卓の周りだけがぽっかりと、星の中に浮かぶ。
「フロウ」
呼べば穏やかな佇まいで見つめ返された。ティーカップももう空だ。
◆
「ねぇ、フロウ。
「? 夏の間の契約だったろう」
「夏はカザヤにいるからその間、の契約だったわ。それに宴の夜、あなたは去るつもりで私を癒してくれたのでしょぅ」
フロウは目を丸くした。どうして知っているんだと言わんばかり。共に過ごすうち、彼はずいぶん気持ちを表すようになった。
そう、百年の冬が徐々にほころぶひとときに、居合わせたことが幸福だ。胸の奥が震えるのは温かさゆえだ。
「ここにいてくれるあなたの心を、義理だとか疑うつもりはないわぁ。でも改めて言葉にさせて。……夏が終わるまで、どうか私と、アマリリス・ストランジと契約を結んでいてほしいの」
彼がこの契約を『夏の間』と捉えていたのなら、敢えて乞うまでもないのかもしれない。だとしても。
不可解そうに拳を顎に当てるフロウが、口を開く前に、声を割り込ます。
「契約を望むのは、ただあなたと一緒にいたいから。あなたといるだけで楽しくて、嬉しいからよ。思慮も必然性もない、そんな我欲で、許されるのなら」
「……リィリ」
耳朶を撫で、夜に溶けていく声に、ざわりと鳥肌が立った。
精霊は不本意なことをしない。ならばカザヤからはるばるついてきてくれたフロウが、残りわずかな日数を断りはしないだろうという自惚れがあり。同時に、だからこそ断られたら立ち直れないという怯えがある。
――色よい返事を思い描いては駄目。
「契約のとき、オレが拒否したから、リィリは期間の縛りをつけたんだよな」
「……っ、えぇ」
あぁ、なのに、柔らかい視線を向けられると期待してしまう。アマリリスはフロウを想えば少しだけ奮い立てるが、面と向かうとぐずぐずに弱くなる。
「元々は無期限の契約がお前の望みだった。……それはまだ変わりないか?」
「か、かわりない、わぁ」
最も都合の良い台詞が。
鼓膜から、脳髄を冒す。
「契約の内容を新しくしよう。オレも夏の終わりを越えて、リィリといたい」
くらくらと今更な酔いが追ってきた。あまりにも己の願望そのまますぎて、夢ではないかと疑ってしまう。
「ぇと……あの。どうして……?」
すぐ肯定すれば良いものを、アマリリスは返事を先延ばしにし、問い返した。喜んで飛びついた瞬間にベッドの上で虚しく目醒めてしまう気がした。もう一月足らずの休暇中だけならともかく、それ以上付き合ってくれる理由が見当たらない。
対するフロウは平然と言う。
「オレは目の前で、誰かが苦しんでいるのが嫌だ。だが遠く離れたところでお前に何かあったら、それに気付きもせずにいるのだとしたら、もっと耐えられないと思った」
そうしてから、口角を少しだけ上げた。
春の泉に花弁が落ちるような淡い笑み――。星月夜に沈んだ透明な瞳だけが、挑むように強くアマリリスを見ている。
「リィリはオレが悲しんだり、後悔したりするのが嫌なんだろう」
「えぇ。あなたに苦い思いをしてほしくない」
「なら、オレがいることで慢心を招くからと離れるより……近くにいた方がお前の身体にも良いはずだ。リィリが無茶をするたび、横でたっぷり悲しんでやる」
密やかに奏でる声音が、脅しじみたことを言う。そのちぐはぐな言葉に、表情に、圧されて息が止まった。
そして知った。
アマリリスが困難を承知で彼といたいと、父との問答で確かめたように。フロウも何かを考え、決めたのだと。
ちぐはぐなのに真っ直ぐな面持ちは、アマリリスの胸の震えを貫いて、紅茶よりも優しく激しい熱を注ぐ。
フロウは身を乗り出して、食器ごしに左手を差し伸べてくる。その手首に青く紋様が走った。二人を結ぶ繋がりを意識すれば、こちらの右手にも同じ光が浮かび上がる。
「うん……喜んで、応じるわぁ。契約の更新に」
重ねた指先が融け合っていく。呪文は必要ない。二人で決めたことが全て。
彼の内心は計り知れず、しかし隣に立って、同じ方を向いている。互いを損ないたくないと思っている。
手を繋いでいるには、それで十分だった。
◆
◆
◆
【ストランジ邸魔術庭園】
ストランジ邸屋上にある魔術庭園は魔術師の間では少々有名です。これを造り上げた先代当主本人が、魔術師ではなかったという点で。
コンプレックスの発露とも、魔力がなくとも知識により魔術を御し得るとの意思表示だとも、まことしやかに噂されています。
なおストランジ家の歴代当主の魔術師率は三割ほどで、国内平均に比べかなりの多さです。