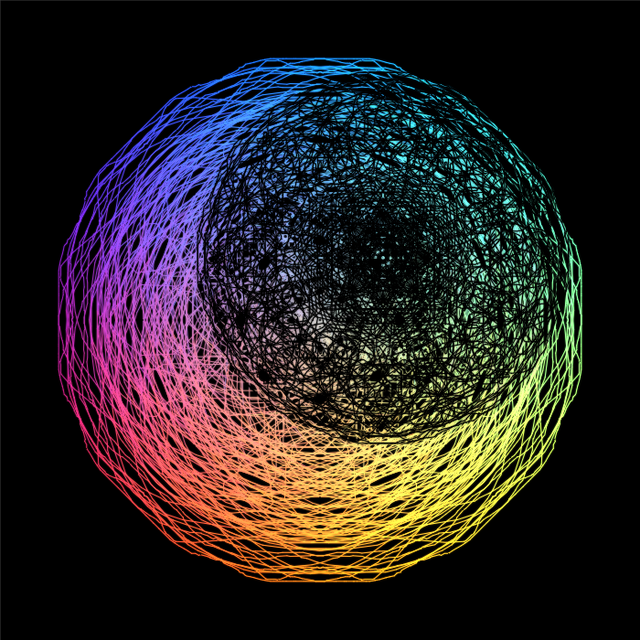27. わらびもち
文字数 4,769文字
アンブローズ・ストランジは姉の褒め言葉が嫌いだ。
姉――アマリリスの話し方には『あなたは優秀、だけど私は違う』といういじけた雰囲気がいつも、ほんの少し表れる。嫉妬や嫌味は一切感じられないことが逆に不安になるほどに。
魔力量や瞳の色 のせいか、契約精霊がなかなか得られないためか、それとも学園で何かあったのか。卑屈の原因を八つ当たりのように問い詰めたこともあるが、姉ははぐらかすばかりで白状しなかった。
その姉が別荘から戻って以降ずっと嬉しそうにしている。正確には、この間の満月の後から。
原因と思われる男は、今目の前でうんうん悩んでいた。
「勝てない……」
屋敷の遊戯室にて。誰もが知っているボードゲームを挟み、姉の契約精霊フロウと向かい合っている。
アンブローズはこの陣取りが得意だが、大人にはまだまだ敵わない。そういう微妙な腕前の自分から見てもフロウの駒運びはたどたどしい。最低限の定跡は何とか覚えました、という程度。
「もう止めよう? 俺、飽きたよ」
「……そうか。練習に付き合ってくれてありがとう」
(めちゃくちゃ上手いんじゃないかって期待したんだけどなー)
ストランジ家には魔術師の出入りが多いため、契約精霊もよく目にしてきた。人語を話す強い個体も。だが透けず、触れられ、人のように生活し、しかも芸術品みたいに綺麗なんて初めて見る。
そんな特別感のある精霊がゲームの相手をしてほしいと言うから、きっと達人級なんだろう、胸を借りるつもりでやってみよう、とわくわくしたのだ。
全くそんなことはなかった。ルールも覚えたてらしい。
「あとさ、俺の手番にやたら話し掛けて考えを邪魔してきたの、わざとでしょ。ああいうのズルくさくて格好悪いと思う」
「まずいのか。これなら勝てると教わったんだが」
「うわ。誰に?」
「ジェフリー」
フロウが涼しい顔で挙げた名に、ん? と少し引っ掛かった。
護衛のジェフリーは気の良い性格だ。必要なら搦め手も使いこなしそうだが、初心者に邪道を吹き込んだりするだろうか。
「……もしかして、アドバイス貰う時、姉さんに勝ちたいって言った?」
「そうだな。今度リィリと再戦するから、そこで勝てる方法を訊いた。何故知っているんだ」
「あー。勘かなー」
首を捻っているのを、適当に流す。
つまり授けられたのは対アマリリス用の小技ということだ。普通の人なら顔を顰める盤外戦術でも姉は怒らないだろう。むしろ真剣勝負より、契約精霊と和やかに過ごす時間を喜ぶかもしれない。
「えっと、さっきのはナシで。姉さんと遊ぶときだけはいっぱい話し掛けて大丈夫。ズルじゃない」
「ふうん……? 分かった。他にもいくつか作戦を習ったが、そっちも同じか?」
「そうかも。とりあえず全部言ってみて」
つらつら並べられた作戦とやらは、やはりゲーム外で動揺を誘う類だった。少しやり過ぎな気がするもののアマリリスなら多分笑って許す範囲だ。二人で話している時の楽しそうな様子からすれば。
ジェフリーも勝つための指南というより、姉と契約精霊がもっと打ち解けられるようにこれらの助言をしたのかもしれない。
「うん。どれも、姉さんとの対戦限定にしとくのが無難なやつだね」
「なるほど」
――姉も自分も魔力を持って生まれた。それはとても不自由でいて、とても自由なことだと父は言う。
父の真意、言葉の重みは、まだ分からない。ただフロウと話す姉の顔を見て思うことがある。何かを諦めたようにアンブローズを褒めそやす姿は、おそらく不自由の上にあったのだと。そして契約精霊と過ごした二月足らずの日々で、そこから解き放たれたのではないかと。
「……やっぱりゲーム、続けよっか。定跡の練習でも搦め手の練習でも付き合うよ。今日だけは俺にもやって良いから」
「本当か、助かる」
アンブローズ・ストランジは姉の褒め言葉が嫌いだった。いじけた雰囲気が出てくると無性にムカムカした。
契約精霊といることで姉があんな顔をしなくてすむなら――末永く仲良くして欲しいと思うのだ。
◆
ストランジの本邸は領地の東端の方、サンドークの中心にある。古くから領主の居地として栄えてきた街だ。元リーヴァン領で併合後に急成長した他の街に比べ、黴臭いだのお堅いだのと言われたりもするが、家の者はそれもストランジらしさだと誇っている。
アマリリスにとって唯一の不満は、西に接するインスピア領から距離があること。たまに地理関係がぐるっとひっくり返らないかと詮ない妄想をしたりする。
「いらっしゃい、キティ! 遠路はるばるありがとう」
「リィリ、こっちこそお招きありがと~! リィリの家に来るの久々だね!」
しばらくぶりに会う親友は少し陽に焼けた顔をきらきら輝かせた。王都で三つの展示会を見に行き、それ以外は主に街角や広場で道行く人のスケッチをしていたという。互いの夏休みのことを話しながら歩けば、エントランスから自室まではすぐだ。
普段なら胸が弾むひととき。しかし今日に限っては、この後の計画に対する心の準備がままならなくて、アマリリスは静かに焦っていた。ノアの手が恭しく扉を開いていく。
足を踏み入れて三歩。親友の笑みがたちまち怪訝な顔に取って変わる。
視線の先はお茶会の準備が整ったテーブルではなく、椅子の上でつやつやしている精霊だった。
「あの。やっぱり驚くわよねぇ? 今日はこのことで相談があって、」
「おっきいわらびもち……」
「もち?」
キャスリンは小さく呟き、物怖じせず彼を間近で観察し始めた。警戒されないだけ幸先が良い――のだろうか。
「その、なんとかもちというのは魔物じゃないだろうな」
「わらびもちが喋った!」
「オレは精霊だ」
「わらびもちの精霊!?」
フロウはフロウで噛み合わないまま平然と話を続けるものだから、親友は猫のように目を丸くした。
普通でない精霊を学園に伴うにあたり、本人と両親を交えて色々話し合ったのだ。能力や特性の確認、人前でどちらの姿でいるべきか、誰に何をどこまで明かすか、などを。
そして別荘でノアがいてくれたように、事情を話せる相手が絶対に必要だと結論した。
学園に使用人を連れていくことはできない。ならば、どの教師よりもキャスリンを頼ろうと考えたのは自然な流れだった。家族ぐるみの付き合いなので両親の信頼も篤い。
「キティ。お土産、食べちゃうわよぅ……?」
「お願い先食べてて! あ、紙で包んでバキバキするといいよ~」
なのでフロウのことをある程度伝えたのだが――。最後に見せた人間姿が琴線にがっつり触れたようで、お茶を放り出してスケッチし始めてしまった。
宝飾デザインの道を志すキャスリン曰く、美しいものに目が無いのだとか。
「もう。お茶が冷めちゃうわ」
キャスリンが王都の商会の物産展で買ってきてくれた煎餅を、皿に敷かれたナプキンごと掴んでばきりと割る。
東の海の果て、絶国からの舶来品はどれも高価だ。独特のしょっぱい匂いが漂ってきて口の中に涎が湧いた。レシピは伝来しているため醤油やそれを使った煎餅などは国内でも細々と作られているが、やはり本場ものは一味違う。
ここでは誰に気を使うこともない。コインぐらいの欠片を口に入れ、ばりぼり音を立てて噛み砕く。ティーカップには同じくお土産の緑茶が注がれていて、乾いた食感に生々しい苦みがよく合った。
一方キャスリンはいつの間にか拡大鏡を取り出し、フロウの手の甲を観察していた。
「うわわわ、ちゃんと男の人の骨格だし色白って訳でもないのに、箱入りのご令嬢みたいな質感 してる……。頭ちぐはぐしちゃう」
「なあ」
「きめ細かあ~」
「なあ。動いて良いか? オレも緑の茶を飲みたい」
「あっどうぞ! ごめんなさい!」
ぱっとフロウを解放したキャスリンは、テーブルに戻るかと思えば再び画帳を構えた。もう満足するまで放っておくしかなさそうだ。
「……気は済んだ?」
「ばっちり! 暴走しちゃってごめんね、スケッチ一枚あげるから許してっ」
「許したわぁ」
テーブルにはお煎餅と、カザヤで買った木の実のクッキー、それにイチジクの小さなタルトなどなど。先に食べていたためもうお腹いっぱいである。
元気にぱくついているキャスリンに、アマリリスはスケッチを吟味しながらふと訊いた。それが契約精霊との生活にどれだけ影響するかなんて、この時は思いもせずに。
「ねぇ。最初に言ってたもちって何の話?」
「わらびもち?」
「そう、それよ」
「絶国のデザートだよ! 透明で、丸っこくて、冷たくて、もっちもちなの。物産展のカフェで食べたんだ~」
人間態のフロウと、思わず顔を見合わせた。透明で、丸っこくて、冷たくて。確かに、もっちもち以外は水の姿の彼と一致する。
「もち、もちか……」
興味を惹かれたのか、フロウはとぷんと姿を変え、何か考え込んでいる。しばらくして身体の一部がキャスリンの方にするする伸びた。
「これでどうだろう」
「えっあたし? 触って良いの?」
「良い」
握手するように、キャスリンが透明な腕先を掴んだ。
「わ、もっちもち!」
「このぐらいの固さか?」
「もうちょっと弾力あるかも……あ、こんな感じ。お~、すご……おお~…………」
「えっ、キティ? そんなにそんな?」
返事のような吐息のような声を漏らして、友は無心にもちもちしている。
アマリリスは置いてけぼりを食らった気分になり、椅子の上に鎮座するフロウをぎゅむっと押した。
――もち、むにににに。むにぅ。
いつものふにゃりとした感触ではなく、適度な抵抗が手のひらを押し返す。それでいて指の間からはみ出す柔らかさがあった。控えめな冷たさも沁みるようで好ましい。
つまり総合的にすこぶる心地よい。
「おぉ…………」
心地よさの遥か彼方で、脳が儚い警鐘を鳴らしている。
ダメだ。これは人をダメにする魔性のもちもちだ。
◆
我に返るまでだいぶ掛かった。
「そんなに良いなら、この姿の時はもちもちでいようか……?」
慕う相手をふしだらにも撫で回し、揉み倒した事実が歴然と残ってしまったが、所詮は過ぎた話である。
フロウの提案に滲む困惑も些細なことである。
――今夜は羞恥心で眠れないだろう。
「ぜひ……じゃなくて、あの、でも、疲れるんじゃぁないの? 身体の弾力を変えるなんて」
「いや、丈夫な泡を作って表面を覆っているだけだ。人間のときの服と同じで、疲れるようなものじゃない」
だとすると困ったことに遠慮する口実がない。
元々フロウの身体は、人の姿でも水の姿でも膚 にしっくりと馴染む独特の質感を持つ。触れたところから浸すように包み込む魔力がそれを助長する。
更に魅惑のもちもちまで加わったらアマリリスは耐えられるのか。あらゆる自由時間を、彼をもちることに費やしてしまわないだろうか。ただでさえ成績が危ういのに。
「リィリが要らないなら止めるが」
「要るわぁ」
理性が負けた。
「泡の温度を上げれば、冬は温かくもできると思う」
ぽよ、と揺れながらフロウが追い討ちをかけてくる。この精霊、ちっぽけな契約者をどれだけダメにする気なのだ。
ずっと静かだと思ったら、キャスリンはとうの昔に気を取り直し、再びスケッチを始めていた。あの手触りのイメージを描き残したかったらしい。
覗き込んだ紙の上ではアマリリスが遠慮なく彼の透明な身体に両手を埋 めている。その表情はでろんでろんにとろけていて、なんとも居たたまれなかった。
◆
◆
◆
【絶国】
大陸から東の海に出、航海の果てに行き着く国、絶国。
その所在は別の大陸とも孤島とも巨大な艦上とも言われます。正確な国名も不明で、絶国というのは仮称です。
全容が定かでないのは、交易品と共に戻った船員は入国前後の記憶を失っているためです。絶国の情報を持ち帰る作戦はどれも失敗しています。
姉――アマリリスの話し方には『あなたは優秀、だけど私は違う』といういじけた雰囲気がいつも、ほんの少し表れる。嫉妬や嫌味は一切感じられないことが逆に不安になるほどに。
魔力量や
その姉が別荘から戻って以降ずっと嬉しそうにしている。正確には、この間の満月の後から。
原因と思われる男は、今目の前でうんうん悩んでいた。
「勝てない……」
屋敷の遊戯室にて。誰もが知っているボードゲームを挟み、姉の契約精霊フロウと向かい合っている。
アンブローズはこの陣取りが得意だが、大人にはまだまだ敵わない。そういう微妙な腕前の自分から見てもフロウの駒運びはたどたどしい。最低限の定跡は何とか覚えました、という程度。
「もう止めよう? 俺、飽きたよ」
「……そうか。練習に付き合ってくれてありがとう」
(めちゃくちゃ上手いんじゃないかって期待したんだけどなー)
ストランジ家には魔術師の出入りが多いため、契約精霊もよく目にしてきた。人語を話す強い個体も。だが透けず、触れられ、人のように生活し、しかも芸術品みたいに綺麗なんて初めて見る。
そんな特別感のある精霊がゲームの相手をしてほしいと言うから、きっと達人級なんだろう、胸を借りるつもりでやってみよう、とわくわくしたのだ。
全くそんなことはなかった。ルールも覚えたてらしい。
「あとさ、俺の手番にやたら話し掛けて考えを邪魔してきたの、わざとでしょ。ああいうのズルくさくて格好悪いと思う」
「まずいのか。これなら勝てると教わったんだが」
「うわ。誰に?」
「ジェフリー」
フロウが涼しい顔で挙げた名に、ん? と少し引っ掛かった。
護衛のジェフリーは気の良い性格だ。必要なら搦め手も使いこなしそうだが、初心者に邪道を吹き込んだりするだろうか。
「……もしかして、アドバイス貰う時、姉さんに勝ちたいって言った?」
「そうだな。今度リィリと再戦するから、そこで勝てる方法を訊いた。何故知っているんだ」
「あー。勘かなー」
首を捻っているのを、適当に流す。
つまり授けられたのは対アマリリス用の小技ということだ。普通の人なら顔を顰める盤外戦術でも姉は怒らないだろう。むしろ真剣勝負より、契約精霊と和やかに過ごす時間を喜ぶかもしれない。
「えっと、さっきのはナシで。姉さんと遊ぶときだけはいっぱい話し掛けて大丈夫。ズルじゃない」
「ふうん……? 分かった。他にもいくつか作戦を習ったが、そっちも同じか?」
「そうかも。とりあえず全部言ってみて」
つらつら並べられた作戦とやらは、やはりゲーム外で動揺を誘う類だった。少しやり過ぎな気がするもののアマリリスなら多分笑って許す範囲だ。二人で話している時の楽しそうな様子からすれば。
ジェフリーも勝つための指南というより、姉と契約精霊がもっと打ち解けられるようにこれらの助言をしたのかもしれない。
「うん。どれも、姉さんとの対戦限定にしとくのが無難なやつだね」
「なるほど」
――姉も自分も魔力を持って生まれた。それはとても不自由でいて、とても自由なことだと父は言う。
父の真意、言葉の重みは、まだ分からない。ただフロウと話す姉の顔を見て思うことがある。何かを諦めたようにアンブローズを褒めそやす姿は、おそらく不自由の上にあったのだと。そして契約精霊と過ごした二月足らずの日々で、そこから解き放たれたのではないかと。
「……やっぱりゲーム、続けよっか。定跡の練習でも搦め手の練習でも付き合うよ。今日だけは俺にもやって良いから」
「本当か、助かる」
アンブローズ・ストランジは姉の褒め言葉が嫌いだった。いじけた雰囲気が出てくると無性にムカムカした。
契約精霊といることで姉があんな顔をしなくてすむなら――末永く仲良くして欲しいと思うのだ。
◆
ストランジの本邸は領地の東端の方、サンドークの中心にある。古くから領主の居地として栄えてきた街だ。元リーヴァン領で併合後に急成長した他の街に比べ、黴臭いだのお堅いだのと言われたりもするが、家の者はそれもストランジらしさだと誇っている。
アマリリスにとって唯一の不満は、西に接するインスピア領から距離があること。たまに地理関係がぐるっとひっくり返らないかと詮ない妄想をしたりする。
「いらっしゃい、キティ! 遠路はるばるありがとう」
「リィリ、こっちこそお招きありがと~! リィリの家に来るの久々だね!」
しばらくぶりに会う親友は少し陽に焼けた顔をきらきら輝かせた。王都で三つの展示会を見に行き、それ以外は主に街角や広場で道行く人のスケッチをしていたという。互いの夏休みのことを話しながら歩けば、エントランスから自室まではすぐだ。
普段なら胸が弾むひととき。しかし今日に限っては、この後の計画に対する心の準備がままならなくて、アマリリスは静かに焦っていた。ノアの手が恭しく扉を開いていく。
足を踏み入れて三歩。親友の笑みがたちまち怪訝な顔に取って変わる。
視線の先はお茶会の準備が整ったテーブルではなく、椅子の上でつやつやしている精霊だった。
「あの。やっぱり驚くわよねぇ? 今日はこのことで相談があって、」
「おっきいわらびもち……」
「もち?」
キャスリンは小さく呟き、物怖じせず彼を間近で観察し始めた。警戒されないだけ幸先が良い――のだろうか。
「その、なんとかもちというのは魔物じゃないだろうな」
「わらびもちが喋った!」
「オレは精霊だ」
「わらびもちの精霊!?」
フロウはフロウで噛み合わないまま平然と話を続けるものだから、親友は猫のように目を丸くした。
普通でない精霊を学園に伴うにあたり、本人と両親を交えて色々話し合ったのだ。能力や特性の確認、人前でどちらの姿でいるべきか、誰に何をどこまで明かすか、などを。
そして別荘でノアがいてくれたように、事情を話せる相手が絶対に必要だと結論した。
学園に使用人を連れていくことはできない。ならば、どの教師よりもキャスリンを頼ろうと考えたのは自然な流れだった。家族ぐるみの付き合いなので両親の信頼も篤い。
「キティ。お土産、食べちゃうわよぅ……?」
「お願い先食べてて! あ、紙で包んでバキバキするといいよ~」
なのでフロウのことをある程度伝えたのだが――。最後に見せた人間姿が琴線にがっつり触れたようで、お茶を放り出してスケッチし始めてしまった。
宝飾デザインの道を志すキャスリン曰く、美しいものに目が無いのだとか。
「もう。お茶が冷めちゃうわ」
キャスリンが王都の商会の物産展で買ってきてくれた煎餅を、皿に敷かれたナプキンごと掴んでばきりと割る。
東の海の果て、絶国からの舶来品はどれも高価だ。独特のしょっぱい匂いが漂ってきて口の中に涎が湧いた。レシピは伝来しているため醤油やそれを使った煎餅などは国内でも細々と作られているが、やはり本場ものは一味違う。
ここでは誰に気を使うこともない。コインぐらいの欠片を口に入れ、ばりぼり音を立てて噛み砕く。ティーカップには同じくお土産の緑茶が注がれていて、乾いた食感に生々しい苦みがよく合った。
一方キャスリンはいつの間にか拡大鏡を取り出し、フロウの手の甲を観察していた。
「うわわわ、ちゃんと男の人の骨格だし色白って訳でもないのに、箱入りのご令嬢みたいな
「なあ」
「きめ細かあ~」
「なあ。動いて良いか? オレも緑の茶を飲みたい」
「あっどうぞ! ごめんなさい!」
ぱっとフロウを解放したキャスリンは、テーブルに戻るかと思えば再び画帳を構えた。もう満足するまで放っておくしかなさそうだ。
「……気は済んだ?」
「ばっちり! 暴走しちゃってごめんね、スケッチ一枚あげるから許してっ」
「許したわぁ」
テーブルにはお煎餅と、カザヤで買った木の実のクッキー、それにイチジクの小さなタルトなどなど。先に食べていたためもうお腹いっぱいである。
元気にぱくついているキャスリンに、アマリリスはスケッチを吟味しながらふと訊いた。それが契約精霊との生活にどれだけ影響するかなんて、この時は思いもせずに。
「ねぇ。最初に言ってたもちって何の話?」
「わらびもち?」
「そう、それよ」
「絶国のデザートだよ! 透明で、丸っこくて、冷たくて、もっちもちなの。物産展のカフェで食べたんだ~」
人間態のフロウと、思わず顔を見合わせた。透明で、丸っこくて、冷たくて。確かに、もっちもち以外は水の姿の彼と一致する。
「もち、もちか……」
興味を惹かれたのか、フロウはとぷんと姿を変え、何か考え込んでいる。しばらくして身体の一部がキャスリンの方にするする伸びた。
「これでどうだろう」
「えっあたし? 触って良いの?」
「良い」
握手するように、キャスリンが透明な腕先を掴んだ。
「わ、もっちもち!」
「このぐらいの固さか?」
「もうちょっと弾力あるかも……あ、こんな感じ。お~、すご……おお~…………」
「えっ、キティ? そんなにそんな?」
返事のような吐息のような声を漏らして、友は無心にもちもちしている。
アマリリスは置いてけぼりを食らった気分になり、椅子の上に鎮座するフロウをぎゅむっと押した。
――もち、むにににに。むにぅ。
いつものふにゃりとした感触ではなく、適度な抵抗が手のひらを押し返す。それでいて指の間からはみ出す柔らかさがあった。控えめな冷たさも沁みるようで好ましい。
つまり総合的にすこぶる心地よい。
「おぉ…………」
心地よさの遥か彼方で、脳が儚い警鐘を鳴らしている。
ダメだ。これは人をダメにする魔性のもちもちだ。
◆
我に返るまでだいぶ掛かった。
「そんなに良いなら、この姿の時はもちもちでいようか……?」
慕う相手をふしだらにも撫で回し、揉み倒した事実が歴然と残ってしまったが、所詮は過ぎた話である。
フロウの提案に滲む困惑も些細なことである。
――今夜は羞恥心で眠れないだろう。
「ぜひ……じゃなくて、あの、でも、疲れるんじゃぁないの? 身体の弾力を変えるなんて」
「いや、丈夫な泡を作って表面を覆っているだけだ。人間のときの服と同じで、疲れるようなものじゃない」
だとすると困ったことに遠慮する口実がない。
元々フロウの身体は、人の姿でも水の姿でも
更に魅惑のもちもちまで加わったらアマリリスは耐えられるのか。あらゆる自由時間を、彼をもちることに費やしてしまわないだろうか。ただでさえ成績が危ういのに。
「リィリが要らないなら止めるが」
「要るわぁ」
理性が負けた。
「泡の温度を上げれば、冬は温かくもできると思う」
ぽよ、と揺れながらフロウが追い討ちをかけてくる。この精霊、ちっぽけな契約者をどれだけダメにする気なのだ。
ずっと静かだと思ったら、キャスリンはとうの昔に気を取り直し、再びスケッチを始めていた。あの手触りのイメージを描き残したかったらしい。
覗き込んだ紙の上ではアマリリスが遠慮なく彼の透明な身体に両手を
◆
◆
◆
【絶国】
大陸から東の海に出、航海の果てに行き着く国、絶国。
その所在は別の大陸とも孤島とも巨大な艦上とも言われます。正確な国名も不明で、絶国というのは仮称です。
全容が定かでないのは、交易品と共に戻った船員は入国前後の記憶を失っているためです。絶国の情報を持ち帰る作戦はどれも失敗しています。