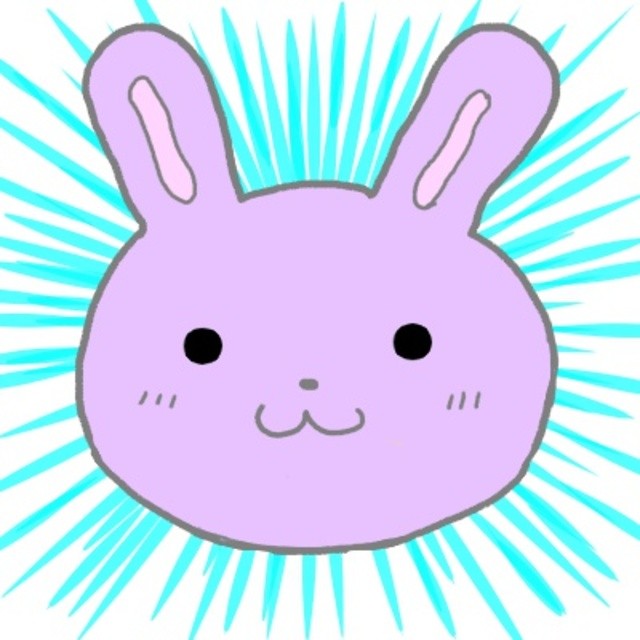第4話
文字数 3,037文字
中学校に進学してから四ケ月目。
電車通学にも慣れてきた。学校生活もそこそこ楽しい。男だらけというのも悪くない。けれど時折り、学校にいるときの自分に違和感を覚えることがある。
心ではムカついてるのに、顔では笑っていたりする。故意に、ではなく無意識に。
自分では全然気づいていなくて、クラスメートに「人間ができてる」なんて言われて初めて気づいたのだ。
自分がいつのまにか、感情通りの表情をしなくなっていることに。
――なんなんだ、これ。思春期特有のものだったりすんのかな……
腹の中ではムカムカしていても、顔はニコニコしているのだから、誰にも迷惑をかけていない。むしろ、周囲の人間は俺が穏やかな性格だと思っている。ただ、表に吐きだされないムカムカは、日々自分の中に蓄積 されていく。
それらを腹の中で上手く飼いならせるようになったときが「大人になった」ということなのだろうか。
俺は、部活に所属していない。
クラスでは九十パーセント、中等部全体では八十パーセントの生徒が、何らかの部活に所属している。運動系、文化系など種類は様々で、中高合同だったり別だったりする。
入学したての頃は、どこかに入るつもりで一通 り回って見学した。けど、他の学校と比べても種類は豊富なはずなのに、魅力を感じるものは一つもなかった。
星が好きだから天文学同好会へも足を向けたが、中等部の部員はゼロな上、のぞいた部室は薄暗く、オタクっぽい人たちばかりでゾッとした。
部活動は強制じゃないから、未 だに俺は帰宅部というわけである。
電車に乗って自宅の最寄駅に着くと、駅直結の市立図書館へ向かった。頭痛は鈍痛をキープしていた。
このままフェードアウトしてくれたら、薬に頼らずにすむんだけど。俺は、制服の内ポケットを探り、常用薬を指先で確かめた。
新設の座り心地のよい椅子は常に満席だが、学生服を着ていれば譲 ってもらえる。
俺はいつものように、星座に関する本や図鑑を手に取った。一応勉強中を装って、ノートや筆記用具もテーブルの上に出しておく。
幼いころから星空を見上げるのが好きだった。
小学校の低学年ごろまでは、親にねだってプラネタリウムへ連れて行ってもらった。もう親と一緒に出かけることはないけれど、星が好きなのは成長した今でも変わらない。
誌上に広がる星たちを見てると、不思議と気持ちが落ち着く。紙に印刷された写真に過ぎないのに、いつのまにか、俺の視覚や思考は銀河系に入り込み、自分の体がその中の一部になるような一体感に浸 れる。
限りなく、どこまでも広い宇宙。それに比べてたら、地球上の人類なんてちっぽけな存在なんだと実感できて、安心する。
将来の夢が何も思い描けなくて、早く歳をとって大人になればいいのに、とか。平気なふりをしていても、本当は帰宅部に罪悪感があったりとか。
常に俺の胸の中を占領していて、日々、自分の中に溜め込まれている得体の知れない灰色のかたまりだとか。
それらすべてが、どうでもいいことに思えるから。
だから俺は、星や宇宙が好きなのかもしれない。
「歩夢 ?」
ふいに名前を呼ばれ、俺は意識を地上に降ろした。
「よう、海斗 、今帰りか」
元小学校の同級生海斗 は、頷 きながら隣に座った。俺と同じような本を、両手に抱えている。
焦げ茶色の髪はサラサラで少し長め。華奢 で色白で、一見女子に見間違われそうな外見だけど、さすがに詰襟 の制服を着ていれば、男子に見える。
「ねえ、夏の大三角もうさがせた?」
「まだだな。最近夜は曇ってるから見えにくいよな」
「僕も。うちのベランダってさ、周囲にやたら明るい看板があるから、小さいと全然だよ」
「俺んちも方角がダメなんだよな」
「見られたら教えてよ」
「ああ、おまえもな」
「うん」
海斗 は神話の解説をしている本を開いた。俺も、星をテーマにしたイラスト集を開く。
俺たちにとって、会話は特に重要じゃない。いつも海斗と二人でいるときは大抵こんな感じで、個々に自分の世界に没頭している。海斗は俺にとって、好きな時間を共有できる貴重な存在だった。
もしここにいるのが学校のクラスメイトだったなら、こんな風に会話もせずに、ゆったりした心地の自然体でいられないだろう。相手によってどんな会話を振れば正解なのかとか、常に忙 しなく、思考を酷使 しなければならないからだ。
学校以外の場所で、そんなことに気を遣うなんて、まっぴらごめんだった。
真横にある多目的スペースの、仕切り版のガラスを横目で盗み見て、そこに映った自分の顔を確認する。
大丈夫だ。
海斗と一緒にいる時の俺は、心と表情、同じバランスを保っている。
中学受験に挑 む小学生が増加しているとはいえ、それは主に都内に集中しており、俺たちが住んでるような都下の学校ではまだまだ少数だった。
六年生は二クラス。それぞれのクラスで中学受験を控えているのは、俺と海斗の二人だけだった。クラスが別でも六年生の数が少ないから、一組と二組合同で行う授業が多く、みんなまとめてクラスメートのような感覚だった。海斗は同じ進学塾に通っていたから、すぐに仲良くなれた。
塾のクラスは別でも、バスで一緒に通った。互いに星が好きという共通点もあったから、理科の星座のテストは楽しく競 った。志望校目指して切磋琢磨 していた。
そして小学校を卒業して別々の中学校へ進学してからも、俺と海斗はこうして二人で過ごす時間を作っていた。ごく自然な流れだったと思う。
互いの学校生活の話題などに、触れたことはあまりない。
会う場所がいつも図書館だというのもあるけれど、俺と海斗は必要以上に会話せず、こうして静かな時間を一緒に過ごしている。
同じ空間を大勢の人間が共有しているのに、誰もが沈黙を貫き、しかもリラックスできる空間。図書館のこんな雰囲気が、俺はとても好きだ。一人で来るものいいけれど、海斗と一緒なのが心地いい。
海斗がパタリと本を閉じて顔を上げた。ふと横を見ると、正面をぼんやり見つめている。
「どうした、海斗」
俺が声を落として話しかけると、聞こえているのかいないのか、反応がない。きっと寝不足なんだろうと思い、読みかけの本に視線を戻した。
すると、海斗は「ぼく……」とつぶやいた。再び顔を上げた俺の目に映った横顔は、うつろな眼差しだった。
「引っ越すことになったんだ」
「えっ、マジか。学校の近くとか?」
「ううん、北海道だって」
「…………は?」
思わずでかい声が出て、周囲の咎 めるような視線を一斉に感じる。俺は意味がわからず、海斗の横顔を凝視した。
「今、北海道って言ったか。あの北の、でっかい、北海道?」
海斗 は表情も変えずに答えた。
「うん」
「嘘だろ、そんな冗談……」
「冗談ならどんなにいいかって、僕も思うよ」
海斗はすっと立ち上がると、俺の腕を引っ張った。
電車通学にも慣れてきた。学校生活もそこそこ楽しい。男だらけというのも悪くない。けれど時折り、学校にいるときの自分に違和感を覚えることがある。
心ではムカついてるのに、顔では笑っていたりする。故意に、ではなく無意識に。
自分では全然気づいていなくて、クラスメートに「人間ができてる」なんて言われて初めて気づいたのだ。
自分がいつのまにか、感情通りの表情をしなくなっていることに。
――なんなんだ、これ。思春期特有のものだったりすんのかな……
腹の中ではムカムカしていても、顔はニコニコしているのだから、誰にも迷惑をかけていない。むしろ、周囲の人間は俺が穏やかな性格だと思っている。ただ、表に吐きだされないムカムカは、日々自分の中に
それらを腹の中で上手く飼いならせるようになったときが「大人になった」ということなのだろうか。
俺は、部活に所属していない。
クラスでは九十パーセント、中等部全体では八十パーセントの生徒が、何らかの部活に所属している。運動系、文化系など種類は様々で、中高合同だったり別だったりする。
入学したての頃は、どこかに入るつもりで
星が好きだから天文学同好会へも足を向けたが、中等部の部員はゼロな上、のぞいた部室は薄暗く、オタクっぽい人たちばかりでゾッとした。
部活動は強制じゃないから、
電車に乗って自宅の最寄駅に着くと、駅直結の市立図書館へ向かった。頭痛は鈍痛をキープしていた。
このままフェードアウトしてくれたら、薬に頼らずにすむんだけど。俺は、制服の内ポケットを探り、常用薬を指先で確かめた。
新設の座り心地のよい椅子は常に満席だが、学生服を着ていれば
俺はいつものように、星座に関する本や図鑑を手に取った。一応勉強中を装って、ノートや筆記用具もテーブルの上に出しておく。
幼いころから星空を見上げるのが好きだった。
小学校の低学年ごろまでは、親にねだってプラネタリウムへ連れて行ってもらった。もう親と一緒に出かけることはないけれど、星が好きなのは成長した今でも変わらない。
誌上に広がる星たちを見てると、不思議と気持ちが落ち着く。紙に印刷された写真に過ぎないのに、いつのまにか、俺の視覚や思考は銀河系に入り込み、自分の体がその中の一部になるような一体感に
限りなく、どこまでも広い宇宙。それに比べてたら、地球上の人類なんてちっぽけな存在なんだと実感できて、安心する。
将来の夢が何も思い描けなくて、早く歳をとって大人になればいいのに、とか。平気なふりをしていても、本当は帰宅部に罪悪感があったりとか。
常に俺の胸の中を占領していて、日々、自分の中に溜め込まれている得体の知れない灰色のかたまりだとか。
それらすべてが、どうでもいいことに思えるから。
だから俺は、星や宇宙が好きなのかもしれない。
「
ふいに名前を呼ばれ、俺は意識を地上に降ろした。
「よう、
元小学校の同級生
焦げ茶色の髪はサラサラで少し長め。
「ねえ、夏の大三角もうさがせた?」
「まだだな。最近夜は曇ってるから見えにくいよな」
「僕も。うちのベランダってさ、周囲にやたら明るい看板があるから、小さいと全然だよ」
「俺んちも方角がダメなんだよな」
「見られたら教えてよ」
「ああ、おまえもな」
「うん」
俺たちにとって、会話は特に重要じゃない。いつも海斗と二人でいるときは大抵こんな感じで、個々に自分の世界に没頭している。海斗は俺にとって、好きな時間を共有できる貴重な存在だった。
もしここにいるのが学校のクラスメイトだったなら、こんな風に会話もせずに、ゆったりした心地の自然体でいられないだろう。相手によってどんな会話を振れば正解なのかとか、常に
学校以外の場所で、そんなことに気を遣うなんて、まっぴらごめんだった。
真横にある多目的スペースの、仕切り版のガラスを横目で盗み見て、そこに映った自分の顔を確認する。
大丈夫だ。
海斗と一緒にいる時の俺は、心と表情、同じバランスを保っている。
中学受験に
六年生は二クラス。それぞれのクラスで中学受験を控えているのは、俺と海斗の二人だけだった。クラスが別でも六年生の数が少ないから、一組と二組合同で行う授業が多く、みんなまとめてクラスメートのような感覚だった。海斗は同じ進学塾に通っていたから、すぐに仲良くなれた。
塾のクラスは別でも、バスで一緒に通った。互いに星が好きという共通点もあったから、理科の星座のテストは楽しく
そして小学校を卒業して別々の中学校へ進学してからも、俺と海斗はこうして二人で過ごす時間を作っていた。ごく自然な流れだったと思う。
互いの学校生活の話題などに、触れたことはあまりない。
会う場所がいつも図書館だというのもあるけれど、俺と海斗は必要以上に会話せず、こうして静かな時間を一緒に過ごしている。
同じ空間を大勢の人間が共有しているのに、誰もが沈黙を貫き、しかもリラックスできる空間。図書館のこんな雰囲気が、俺はとても好きだ。一人で来るものいいけれど、海斗と一緒なのが心地いい。
海斗がパタリと本を閉じて顔を上げた。ふと横を見ると、正面をぼんやり見つめている。
「どうした、海斗」
俺が声を落として話しかけると、聞こえているのかいないのか、反応がない。きっと寝不足なんだろうと思い、読みかけの本に視線を戻した。
すると、海斗は「ぼく……」とつぶやいた。再び顔を上げた俺の目に映った横顔は、うつろな眼差しだった。
「引っ越すことになったんだ」
「えっ、マジか。学校の近くとか?」
「ううん、北海道だって」
「…………は?」
思わずでかい声が出て、周囲の
「今、北海道って言ったか。あの北の、でっかい、北海道?」
「うん」
「嘘だろ、そんな冗談……」
「冗談ならどんなにいいかって、僕も思うよ」
海斗はすっと立ち上がると、俺の腕を引っ張った。