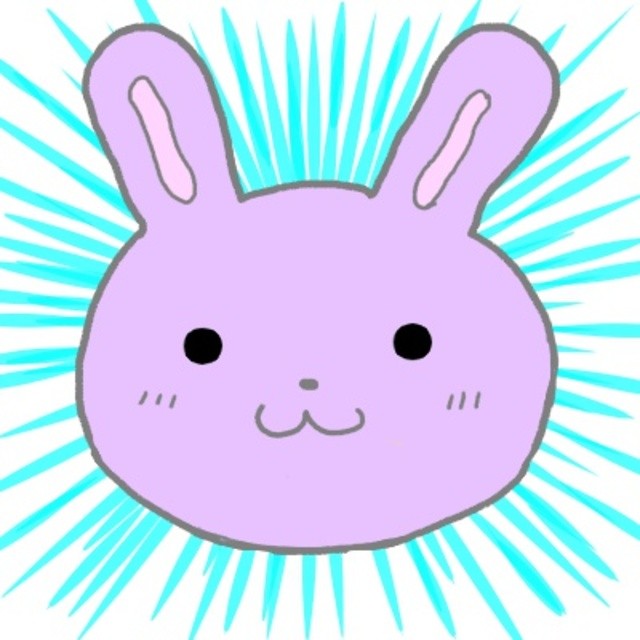第7話
文字数 2,830文字
「今日は早いな」
図書館には、先に海斗が来ていた。椅子の横には星座の写真集が二冊置いてある。
元々、この図書館は規模のわりに宇宙や星座に関する書物が少なかった。だから、海斗と相談しながら色々リクエストをしているうち、徐々に増えていったのだ。
「歩夢 ……」
海斗は、昨日よりも覇気 のない表情で俺を見上げた。その目は伏し目がちで、俺の姿がちゃんと映っているのか心配になる。
「あのさ、これからうちに来ないか。ゆっくり話したいし」
海斗は救いを求める子犬のような目で、こっくり頷いた。俺は心臓をギュッと掴まれたように痛んだけれど、それを顔に出さないよう頑張った。
海斗の自転車に俺がまたがり、後ろに海斗を乗せる。二人分の体重を乗せた自転車はギイギイ音を立てる。 途中、海斗の家を通り過ぎた。
幼い頃に見たSF映画のように、地上を離れどこまでも、海斗と一緒に遠くへ行きたい。俺たちはまだまだ子供で、親の庇護下 でないと生きられないけれど、それでも思わずにはいられなかった。
海斗のために何もできない非力な自分が虚 しかった。
俺の自宅へ到着し、海斗の自転車を棟の横へ停める。上り始めた階段が暗く感じて見上げると、蛍光灯の一か所が切れていた。四階の俺の部屋まで上がり、鍵を開ける。
海斗に先に部屋へ行ってもらい、俺はキッチンへ入った。気の利いた飲み物がないか探してみる。食器棚の下の扉奥に、缶のジュースが箱ごと眠っていた。お歳暮かなんかで貰ったものだろう。きれいなコップがないから、同じく扉奥で見つけた紙コップに、二人分のオレンジジュースを注ぐ。
部屋へ入ると、海斗は本棚の星図鑑を見ていた。ジュースを乗せたトレイを床に置き、俺はその隣に座った。
「引っ越しまで、少しは時間があるんだろ?」
「うん、八月中旬くらいになると思う。……新学期に間に合うように」
打ち明けたことで気が抜けたのか、海斗はぼんやりしている。俺はその顔をのぞき込んだ。
「なあ海斗、去年の夏によく話したよな。受験終わったら、星が綺麗に見える場所へ一緒に行こうって。北海道なら、こっちより全然見えるだろうけど、俺はおまえと一緒に見たい。どうだ?」
うつろだった海斗の瞳に、かすかに光が差した。
「星を、二人で?……」
不安気 な表情がやわらぎ、口元がわずかに嬉しそうに緩 んでくる。
「いいな、行きたい! でも、どこへ? そんなに遠くへは行けないよね」
「わかってる、まあ聞いてくれ。俺に考えがあるんだ」
昨夜から今日一日かけて、俺はずっと考えていた。そして、意外にも近くにベストスポットがあるのを思い出したのだ。
それは、小学校の裏山だった。
俺たちが六年間通った小学校は高台に位置しており、その上が小さな山みたいになっている。
夜になればその周辺は闇に包まれ、誰も寄り付かない場所になる。俺たちが低学年の頃「暗くなると変質者が出没する」なんて噂が立ったけれど、実際見たやつがいたという話は聞いたことがなかった。
俺の話を聞きながら、海斗の表情はみるみる生き生きとしていく。一年前に二人で語った、あの日と同じような瞳で。
「行きたい! 見に行きたいよ僕! 歩夢と二人で!」
「うん、行こうぜ! 必ず実現させよう」
互いの気持ちは確認できた。後は、それを実現させるために考えて行動するだけだ。
それから、決行日はいつにするか、何時頃がいいのか、当日の服装や持ち物など、俺たちは夢中になって話した。
「すっかり遅くなっちゃったな。ああ腹減った、何も用意してなくて悪かったな。次はちゃんと用意しておくからさ」
「ううん、僕も今度は何か持ってくるよ。気が回らなくてごめん」
そうは言っても、数時間前の海斗の顔を見れば、そんな余裕がないのはわかっていた。
外へ出ると、すっかり夜だった。空気はいくらかひんやりして、向かいに見える棟のたくさんの窓から灯りがもれている。
海斗は来たときよりも少しは軽い足取りで、建物の横に停めていた自分の自転車へ近づく。そして不思議そうに巨大なコンクリートの塊 を見上げた。
「歩夢のお母さん、今日は帰りが遅いの?」
「ん? ……ああ、最近パート行っててさ、帰りが遅いんだ」
「――そっか」
海斗は、小学校の頃は比較的頻繁 に、俺の部屋に遊びに来ていた。その頃は、きれい好きな母さんが必ず在宅だったし、掃除は行き届いていた。
シンクに食器は山積みになっていなかったし、ゴミもあちこちに散乱していなかった。収集日に出し忘れたゴミの袋が玄関に積んである、なんてことも当然なかった。
海斗は自転車のライトのスイッチをオンにすると、自転車にまたがる。
「すごく楽しみだよ。実現させたいね」
「ああ、きっと大丈夫だ。夏休みに入ったら、毎日連絡取り合おうぜ」
「うん。……あのさ、歩夢」
「ん?」
海斗は間を置いてから、困ったような顔をした。なんというか、照れたような表情だ。
「歩夢って……頼れるヤツだったんだなって。――ちょっとびっくりした」
「え? なんだよ、変なこと言うなよ」
そんなことをいきなり言われたら、こっちだって困る。
「褒 めてるんだよ! ……なんかそういうとこ、僕は知らなかった気がして」
「そ、そうかな」
「うん。そう」
なんだかひどくいたたまれなくて、俺は頭の後ろをボリボリかいた。確かに海斗の前では、ずっと自分を抑 えてきたかもしれなかったからだ。
俺が中学受験の勉強を始めたのは五年生の三学期で、海斗より二年以上遅れてのスタートだった。
塾内でのクラス編成は成績順でA、B、Cの三つに分けられ、海斗はAクラスで俺は一番下のCクラスだった。学校ではクラスメートのような存在だけど、互いの位置関係を知ってから仲良くなった。
受験で戦うための手持ちの武器や知識は、海斗に劣 っていたし、実際成績で現実を突きつけられていた。常に俺は、海斗の背中を追っていた。海斗には勝てないという思いはあった。
実力が違うのだから、当然俺と海斗の志望校のレベルは違う。
レベルを競うわけではないのだから、俺は自分の志望校に受かればいいのであって、実力の差とか、勝ち負けとか、そんなことは気にしなければいい。
けれど、自覚のないまま「海斗の方が上だ」という考えが、自然と態度に出ていたのかもしれない。
「気を付けて帰れよ。また、続き話そうぜ」
「うん。じゃあね」
自転車をこぐ海斗の後ろ姿を、俺は見えなくなるまで見送った。
図書館には、先に海斗が来ていた。椅子の横には星座の写真集が二冊置いてある。
元々、この図書館は規模のわりに宇宙や星座に関する書物が少なかった。だから、海斗と相談しながら色々リクエストをしているうち、徐々に増えていったのだ。
「
海斗は、昨日よりも
「あのさ、これからうちに来ないか。ゆっくり話したいし」
海斗は救いを求める子犬のような目で、こっくり頷いた。俺は心臓をギュッと掴まれたように痛んだけれど、それを顔に出さないよう頑張った。
海斗の自転車に俺がまたがり、後ろに海斗を乗せる。二人分の体重を乗せた自転車はギイギイ音を立てる。 途中、海斗の家を通り過ぎた。
幼い頃に見たSF映画のように、地上を離れどこまでも、海斗と一緒に遠くへ行きたい。俺たちはまだまだ子供で、親の
海斗のために何もできない非力な自分が
俺の自宅へ到着し、海斗の自転車を棟の横へ停める。上り始めた階段が暗く感じて見上げると、蛍光灯の一か所が切れていた。四階の俺の部屋まで上がり、鍵を開ける。
海斗に先に部屋へ行ってもらい、俺はキッチンへ入った。気の利いた飲み物がないか探してみる。食器棚の下の扉奥に、缶のジュースが箱ごと眠っていた。お歳暮かなんかで貰ったものだろう。きれいなコップがないから、同じく扉奥で見つけた紙コップに、二人分のオレンジジュースを注ぐ。
部屋へ入ると、海斗は本棚の星図鑑を見ていた。ジュースを乗せたトレイを床に置き、俺はその隣に座った。
「引っ越しまで、少しは時間があるんだろ?」
「うん、八月中旬くらいになると思う。……新学期に間に合うように」
打ち明けたことで気が抜けたのか、海斗はぼんやりしている。俺はその顔をのぞき込んだ。
「なあ海斗、去年の夏によく話したよな。受験終わったら、星が綺麗に見える場所へ一緒に行こうって。北海道なら、こっちより全然見えるだろうけど、俺はおまえと一緒に見たい。どうだ?」
うつろだった海斗の瞳に、かすかに光が差した。
「星を、二人で?……」
「いいな、行きたい! でも、どこへ? そんなに遠くへは行けないよね」
「わかってる、まあ聞いてくれ。俺に考えがあるんだ」
昨夜から今日一日かけて、俺はずっと考えていた。そして、意外にも近くにベストスポットがあるのを思い出したのだ。
それは、小学校の裏山だった。
俺たちが六年間通った小学校は高台に位置しており、その上が小さな山みたいになっている。
夜になればその周辺は闇に包まれ、誰も寄り付かない場所になる。俺たちが低学年の頃「暗くなると変質者が出没する」なんて噂が立ったけれど、実際見たやつがいたという話は聞いたことがなかった。
俺の話を聞きながら、海斗の表情はみるみる生き生きとしていく。一年前に二人で語った、あの日と同じような瞳で。
「行きたい! 見に行きたいよ僕! 歩夢と二人で!」
「うん、行こうぜ! 必ず実現させよう」
互いの気持ちは確認できた。後は、それを実現させるために考えて行動するだけだ。
それから、決行日はいつにするか、何時頃がいいのか、当日の服装や持ち物など、俺たちは夢中になって話した。
「すっかり遅くなっちゃったな。ああ腹減った、何も用意してなくて悪かったな。次はちゃんと用意しておくからさ」
「ううん、僕も今度は何か持ってくるよ。気が回らなくてごめん」
そうは言っても、数時間前の海斗の顔を見れば、そんな余裕がないのはわかっていた。
外へ出ると、すっかり夜だった。空気はいくらかひんやりして、向かいに見える棟のたくさんの窓から灯りがもれている。
海斗は来たときよりも少しは軽い足取りで、建物の横に停めていた自分の自転車へ近づく。そして不思議そうに巨大なコンクリートの
「歩夢のお母さん、今日は帰りが遅いの?」
「ん? ……ああ、最近パート行っててさ、帰りが遅いんだ」
「――そっか」
海斗は、小学校の頃は比較的
シンクに食器は山積みになっていなかったし、ゴミもあちこちに散乱していなかった。収集日に出し忘れたゴミの袋が玄関に積んである、なんてことも当然なかった。
海斗は自転車のライトのスイッチをオンにすると、自転車にまたがる。
「すごく楽しみだよ。実現させたいね」
「ああ、きっと大丈夫だ。夏休みに入ったら、毎日連絡取り合おうぜ」
「うん。……あのさ、歩夢」
「ん?」
海斗は間を置いてから、困ったような顔をした。なんというか、照れたような表情だ。
「歩夢って……頼れるヤツだったんだなって。――ちょっとびっくりした」
「え? なんだよ、変なこと言うなよ」
そんなことをいきなり言われたら、こっちだって困る。
「
「そ、そうかな」
「うん。そう」
なんだかひどくいたたまれなくて、俺は頭の後ろをボリボリかいた。確かに海斗の前では、ずっと自分を
俺が中学受験の勉強を始めたのは五年生の三学期で、海斗より二年以上遅れてのスタートだった。
塾内でのクラス編成は成績順でA、B、Cの三つに分けられ、海斗はAクラスで俺は一番下のCクラスだった。学校ではクラスメートのような存在だけど、互いの位置関係を知ってから仲良くなった。
受験で戦うための手持ちの武器や知識は、海斗に
実力が違うのだから、当然俺と海斗の志望校のレベルは違う。
レベルを競うわけではないのだから、俺は自分の志望校に受かればいいのであって、実力の差とか、勝ち負けとか、そんなことは気にしなければいい。
けれど、自覚のないまま「海斗の方が上だ」という考えが、自然と態度に出ていたのかもしれない。
「気を付けて帰れよ。また、続き話そうぜ」
「うん。じゃあね」
自転車をこぐ海斗の後ろ姿を、俺は見えなくなるまで見送った。