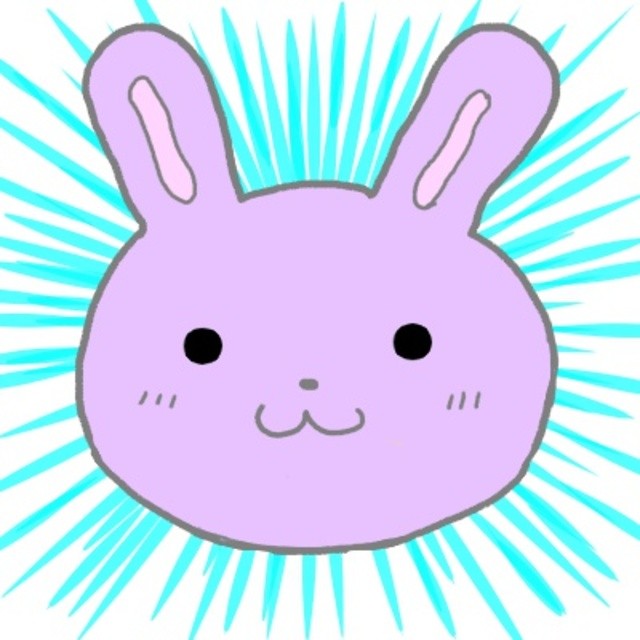第20話 エピローグ
文字数 1,710文字
今朝は可燃ゴミの収集日だった。
忘れずちゃんと捨てられたから、狭い玄関はすっきりしている。
けれど、掃除をマメにしていないから、部屋の四隅に埃 のかたまりが、一見可愛らしい妖精みたいにふわふわ浮いている。
紙くずや生ゴミはちゃんとゴミ箱に入れるけど、リビングは取り込んだ洗濯物が山積みになっている。
洗濯して干すまではなんとかできても、畳んで箪笥 にしまうのは至難 の業 なのだ。
「どうぞ、上がってください」
先輩は玄関でぼんやりしていたけれど、われに返ったように「あ、うん。おじゃまします」と言い、几帳面に脱いだスニーカーを揃 えた。
「先輩、シャワー使いますか」
言いながら、洗濯物の山の中に手を突っ込む。洗濯済みのタオルがあるはずだ。
返事がないので振り向くと、先輩はリビングに視線を止めたまま、立ち尽くしていた。
「家の人は……いつから、いないんだ」
「え?」
そう言われて、俺は改めて自分の住居をながめた。
「そんなに長くないと思いますけど……」
埃 があちこち浮いている室内は、家具が少ないから広く見える。
けれど殺風景で、家族で住むには、あらゆる物が足りていない。
「お前の親とか、家族は、どこにいるんだよ。もしかして……田神一人で住んでるのか」
「そういうことになりますね」
「なんで」
草本先輩の表情が強張 った。
「なんでだろ……」
なぜ、どうして、こんなことになったのか。それは、俺が一番知りたいことだった。
「高一ならまだしも、お前まだ中一だろ」
「そうですよね。俺もあと三年、待ってほしかったんですけど」
俺が五年生の二月、父さんの海外赴任が決まった。
俺はちょうどそのタイミングで、進学塾内の新六年生に進級していた。
俺が中学受験を一年後に控えていなかったら、母さんと二人でついていったと思う。
けれど両親は、俺の進路の事を優先させた。父さんが一人で行くことになり、母さんと俺が日本に残った。
後で聞いた話だが、ずいぶん前から、海外赴任の話は職場で持ち上がっていたらしい。父さんはまだ子供が小さいからと、断っていたようだ。
当時、俺たち家族は二階建ての一軒家に住んでいた。俺がまだ母さんの腹の中にいるころに、数十世帯ほど売り出していた建売住宅だ。
建売住宅なのだが、壁や床や、ある程度自分たちで決められる点と、小さな庭があるのが気に入ったらしかった。
俺に弟か妹ができる未来も想定して、四LDKの間取りに決めた。
俺は、あの家が好きだった。
好きだなんて言葉にしたことはなかったし、親にも伝えたことはないけれど、物心ついたときから、幸せで、ふわふわの真綿に包まれているような毎日だった。ずっとそんな日々が続くと、信じて疑わなかった。
けれど、事態は暗転していく。
当初父さんは、二年ほどで赴任先から戻れるだろうと話していたのに、期間はさらに二年延びた。いつ日本に戻れるのか、わからなくなった。
四LDKの住まいは、俺と母さんの二人暮らしには広すぎた。想い出の沢山詰まった家を売りに出し、俺と母さんは、同じ市内の団地へ引っ越したのだ。
母さん自身、父さんと住んでいた家に住み続けるのが、淋しかったようだ。
母さんは俺の塾通いや勉強に協力してくれたけど、毎日父さんに会えなくて淋しそうだった。とにかくウザいくらい仲のいい夫婦なのだ。年に二~三回、帰国した父さんに会う程度じゃ、却 って淋しさが募 るらしかった。
それは父さんも同じだったようで、毎日スカイプを利用し、三人で会話した。それだけでは到底足りず、二人きりでも長い時間話していたに違いない。
それでも多分、精神的にギリギリだったんだと思う。
無事俺の進学先が決まって、小学校を卒業し、春になって中学に通い始めて半月経った頃。
確か水曜日だった。いつものように登校して帰宅したら、母さんが消えていた。
忘れずちゃんと捨てられたから、狭い玄関はすっきりしている。
けれど、掃除をマメにしていないから、部屋の四隅に
紙くずや生ゴミはちゃんとゴミ箱に入れるけど、リビングは取り込んだ洗濯物が山積みになっている。
洗濯して干すまではなんとかできても、畳んで
「どうぞ、上がってください」
先輩は玄関でぼんやりしていたけれど、われに返ったように「あ、うん。おじゃまします」と言い、几帳面に脱いだスニーカーを
「先輩、シャワー使いますか」
言いながら、洗濯物の山の中に手を突っ込む。洗濯済みのタオルがあるはずだ。
返事がないので振り向くと、先輩はリビングに視線を止めたまま、立ち尽くしていた。
「家の人は……いつから、いないんだ」
「え?」
そう言われて、俺は改めて自分の住居をながめた。
「そんなに長くないと思いますけど……」
けれど殺風景で、家族で住むには、あらゆる物が足りていない。
「お前の親とか、家族は、どこにいるんだよ。もしかして……田神一人で住んでるのか」
「そういうことになりますね」
「なんで」
草本先輩の表情が
「なんでだろ……」
なぜ、どうして、こんなことになったのか。それは、俺が一番知りたいことだった。
「高一ならまだしも、お前まだ中一だろ」
「そうですよね。俺もあと三年、待ってほしかったんですけど」
俺が五年生の二月、父さんの海外赴任が決まった。
俺はちょうどそのタイミングで、進学塾内の新六年生に進級していた。
俺が中学受験を一年後に控えていなかったら、母さんと二人でついていったと思う。
けれど両親は、俺の進路の事を優先させた。父さんが一人で行くことになり、母さんと俺が日本に残った。
後で聞いた話だが、ずいぶん前から、海外赴任の話は職場で持ち上がっていたらしい。父さんはまだ子供が小さいからと、断っていたようだ。
当時、俺たち家族は二階建ての一軒家に住んでいた。俺がまだ母さんの腹の中にいるころに、数十世帯ほど売り出していた建売住宅だ。
建売住宅なのだが、壁や床や、ある程度自分たちで決められる点と、小さな庭があるのが気に入ったらしかった。
俺に弟か妹ができる未来も想定して、四LDKの間取りに決めた。
俺は、あの家が好きだった。
好きだなんて言葉にしたことはなかったし、親にも伝えたことはないけれど、物心ついたときから、幸せで、ふわふわの真綿に包まれているような毎日だった。ずっとそんな日々が続くと、信じて疑わなかった。
けれど、事態は暗転していく。
当初父さんは、二年ほどで赴任先から戻れるだろうと話していたのに、期間はさらに二年延びた。いつ日本に戻れるのか、わからなくなった。
四LDKの住まいは、俺と母さんの二人暮らしには広すぎた。想い出の沢山詰まった家を売りに出し、俺と母さんは、同じ市内の団地へ引っ越したのだ。
母さん自身、父さんと住んでいた家に住み続けるのが、淋しかったようだ。
母さんは俺の塾通いや勉強に協力してくれたけど、毎日父さんに会えなくて淋しそうだった。とにかくウザいくらい仲のいい夫婦なのだ。年に二~三回、帰国した父さんに会う程度じゃ、
それは父さんも同じだったようで、毎日スカイプを利用し、三人で会話した。それだけでは到底足りず、二人きりでも長い時間話していたに違いない。
それでも多分、精神的にギリギリだったんだと思う。
無事俺の進学先が決まって、小学校を卒業し、春になって中学に通い始めて半月経った頃。
確か水曜日だった。いつものように登校して帰宅したら、母さんが消えていた。