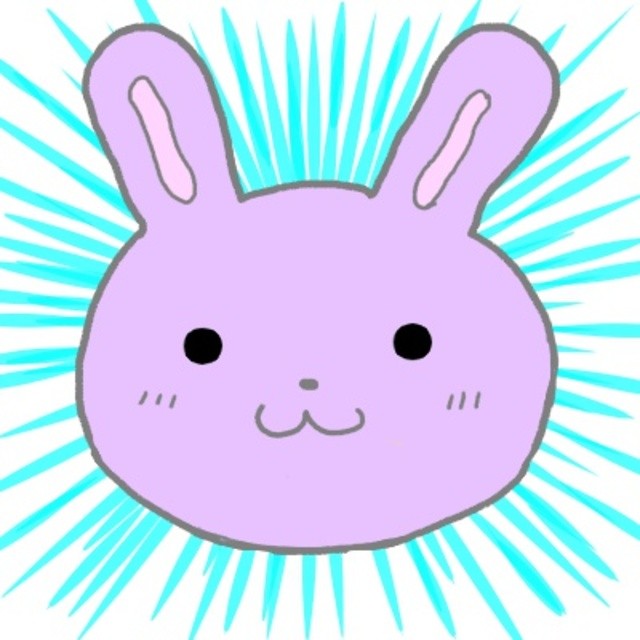第13話
文字数 4,555文字
夏休みに入って数日が過ぎ、いよいよ、待ちに待った当日となった。
一番心配だった天気は快晴。絶好の星空観察日和と言えるだろう。
俺は念入りに、リュックの中身の最終チェックをした。レジャーシート、防寒具、懐中電灯、虫よけスプレーなど、必需品にもれはない。準備万端だ。
結局、両親にも叔父さんにも今夜のことは伝えなかった。心待ちにしていた大切な日だからこそ、邪魔 が入るのは避けたいからだ。
夜になったら、俺が海斗の家まで迎えに行き、そこから自転車二台で、一緒に学校の裏山まで行くことになっている。
夕方、早めにシャワーを浴びて、買ってきた夕食の弁当をテーブルに置く。テレビをつけて適当な番組をながめながら、箸 を動かしモソモソと咀嚼 した。
父さんの提案で、わが家は食事のときにテレビをつけない決まりだった。だから決まって父さんが、職場の話(ほとんどくだらない内容だけど)をしたり、寒いオヤジギャグを言ったり、母さんが近所で仕入れた世間話をしたり、俺が学校の話を少しする。
他人から見たら、いかにも『わきあいあい』な家族団欒 を地でやっていた。
「ほんっと……いつもくっだらないギャグばっかだったよな……」
思わず思い出し笑いをしながら独り言ちて、ペットボトルの麦茶に口をつける。
ふと、海斗のことを考えた。
海斗の家で、笑い声は聞こえるのだろうか。海斗は、おじさんが家に帰って来ないと言っていたが、それなら、おばさんと海斗の間に笑顔はあるのか、そして笑い声は……。
今までの様子だと、それは期待できそうにないなと思った。先日の、海斗の悲しそうな顔が頭に浮かんで、胸の中がささくれていくような気がした。
♢
今夜だけは、予想外のアクシデントが起きてほしくない。誰にも邪魔されたくない。
だから俺は、もしものときの保険代わりに、置き手紙を残すことにした。俺達は、自分の意思で部屋を抜け出したこと、日数をかけて準備を重ねていたこと。それらを丁寧に書いて、テーブルの上に置いた。
万が一、この手紙を誰かに見られたとしても、大丈夫だという自信が俺にはあった。心配なのは、海斗のお母さんだった。
おばさんがぐっすり眠ったのを確認してから、海斗は自分の部屋を出る。おばさんの眠る部屋と、海斗の部屋は隣り合わせだから、慎重に行動しないと気づかれてしまう恐れがある。
極力物音を立てず、静かに行動するよう海斗には伝えたし、二人で何度もシミュレーションを繰り返した。
シミュレーションといっても、俺がおばさんの役で海斗は本人役。最初は真面目に始めるんだけどついつい笑ってしまい、完成度の低い出来損ないのコントみたいなのをただ繰り返しただけだ。
あの時は楽しかったけど、実践でその効果は……期待できそうもない。
今さらだけど、大丈夫だろうか。
Tシャツに長めのジーンズ、腰に防寒用の長袖シャツを巻いて、リュックを背負って帽子をかぶった。
音を立てないように玄関ドアの鍵をかけて、そっと階段を降りた。あらかじめ、自転車置き場の手前に移動しておいた自転車のライトをつけ、またがると海斗の家へ向かった。
普段はバス通学だから、しばらくほったらかしにしていたせいで、自転車はところどころ錆 びついているようだった。キイキイと嫌な音を出し、ひっそり静まり返った住宅街にやけに響いた。
街灯の少ない薄暗い通りを、自転車のライトを頼りに進む。畑や木々の多い道は特に真っ暗で、地上と空の継ぎ目がわからないほどだった。周囲も空もまっ黒で、けれど、空には星が瞬 いて、いる。
――すっげえ、キラキラしてる
期待と緊張で胸は痛いほどドキドキしてるのに、周囲の景色が綺麗で、一刻も早く、海斗と分かち合いたいと思った。
目的地より少し手前で、自転車を静かに停めた。
海斗の家は、屋根も外壁も白い板が何枚も折り重なったような造りで、建売の住宅とは違ういかにもオシャレな洋風の家だ。周りのどの家よりも白く浮かび上がって見えるから、すぐにわかった。
海斗はまだ外に出ていなかった。俺は玄関の正面を避けて、自転車を家の脇道に移動させた。
しばらく待っていると、玄関のドアがゆっくり開き、人影が出てきた。
――海斗?
海斗だった。
ホッとして見守っていると、なんだか様子が変だった。やけに軽装だし、リュックも背負 っていない。
「歩夢……歩夢……いるの?」
暗くて表情はわからないが、その声は震えていて、なにかしらのアクシデントを予感させた。俺の背中がぴしりと強貼 る。
「こっちだ、海斗。どうした? もしかして、おばさんに見つかったのか」
「歩夢っ」
すぐそばまで行くと、海斗はひどく困ったような顔をしていた。
「お母さん、いつもこの時間なら自分の部屋に入って朝まで出てこないんだけど、今夜に限ってリビングに居座って、ずっと誰かと電話してるんだ」
「まじかよ……」
「とりあえずトイレに起きたふりして出てきたんだけど、このまま出発したとしてもお母さんに怪しまれるし、リュックなんて背負 ってたら絶対にバレちゃうよ」
海斗の家は、二階へ上がる階段が廊下ではなくリビングの奥にある。だから、海斗の部屋から玄関へ移動するには、リビングにいるおばさんの横を通らないと行けない。
そういえば小学校低学年のころ、何度か母さんと一緒に海斗の家へ遊びに行ったことがあった。そのとき、家の間取りを母さんがしきりに感心してたのを思い出した。
ほとんどの家は、階段は廊下の近くか、玄関側にあったりするらしい。けれど、海斗の家はリビングの奥に二階へ上がる階段がある。
思春期を迎えた子供は、帰宅すると親の顔も見ずに真っ直ぐ自室へひっこんでしまいがちになるが、この家のようにリビングを通らないと自室へ行けない造りなら、たとえ会話がなくても頻繁 に子供と顔を合わせることになる。だからその点で、この家は子育てをする上で理想的だと、母さんは羨 ましげに話していた。
そういえば、以前俺が住んでいた一戸建ては、やっぱり玄関入ってすぐ階段だったと思い出す。
でもうちの両親は、子供に気を遣うようなたまじゃない。
帰宅したら必ず「ただいま」を言わされたし、「行ってきます」を忘れたりしたりしたら大変だった。
母さんと父さんに、代わる代わるしつこくハグされるし、俺が意地を張ったりしたら、母さんの顔中キス攻撃が待っていた。
「ここは日本だ」とか「思春期の子供なんてそんなもんだ」などという一般的な見解は、うちの両親には一切通じない。
だが海斗の家の、子育てに理想的な造りが、今回の計画には仇 となってしまっている。
――どうする? ……落ち着け。どうすればいい?
こんなときほど焦 らず、冷静に判断して決断しなければならない。俺は、とにかく冷静になれるよう、自分に言い聞かせた。
「どうしよう、歩夢……。僕、今夜見に行きたいのに。すごくすごく、楽しみにしてたのに」
「海斗……」
海斗の顔は、今にも泣きだしそうに歪 んでいる。
こんな悲しそうな顔のまま、北海道に行かせたくなかった。二人の心に深く残る想い出を作りたい。別れのときは晴れやかな笑顔で送り出したい。
俺の中に、ふつふつと何か熱いものが湧 き上がるのを感じた。今年の二月、寒さが一番堪 える時期の記憶がよみがえった。
入試本番を迎えるまで、俺たちは互いに励 まし合い、決してあきらめなかった。頑張ろう頑張ろうと、いつも声をかけ合っていた。
あの頃の俺はもっと熱い人間だったはずだ。こんなに冷めたヤツじゃなかった。明るい未来を信じて、がむしゃらに頑張っていた。
あの頃の気持ちを忘れてしまっていた。振り返らず前だけを見つめて、ひたすら勉強していたころの自分を。
月明かりに照らされた海斗の顔は、白く浮かんで見える。その瞳に映る俺の顔は、きっと情けない表情に違いない。
第一志望校の合格発表の日、パソコンの画面上に自分の受験番号を見つけられなかったあの日。
一緒に頑張ってきたのに、俺だけが志望校に受からなかったのだと知ったあの日。
「海斗に負けた」と確かに思った。置いて行かれたと思った。 北海道へ行ってしまう海斗のために、頑張りたいだなんて口先だけで、未 だ常にどこか、諦 めや絶望に囚 われている。
あの瞬間から今の今まで、俺はずっと立ち止まったままだったのだろう。その事実を突きつけられ、愕然 とした。
――自分なりにあきらめて、現実を受け入れたつもりだったのにな……。
あきらめて、無理矢理現実を見ようとした。
頑張っても報われないことがあることを知った。見せられた。忘れようとしていた。
いくら子供は親の都合で行く先を決められることになっても、思いだけは自分のものなのに。
なら、もっと肩の力を抜いて普通に生きていけばいいじゃないかと、俺はそう思った。その方が断然楽だったからだ。
十二歳で、残酷な現実を突き付けられた俺は、そう思うしかなかったんだ。
だがそれでも、俺はまだラッキーな方だった。併願で受験した今の学校に入れたんだから。塾仲間の中には、どこにも受からずに結局、学区内の公立中学校へ進学したヤツもいた。
四年生から進学塾に通い、放課後の遊びをずっと断わり続けた人間が、中学に上がって同じ教室にいたら、そりゃ周囲は驚くだろう。けれど、そんなヤツらはゴロゴロいた。どんなに屈辱 を受けても、三年間は耐えなければならないのだ。
――そうだ、俺はあいつらに比べたら、マシだった。
気持ちの上では、そう折り合いをつけて納得したつもりだった。けれど、俺にとっての厳しい現実はそれだけじゃなかったから……。
底抜けに明るい両親の顔が浮かぶ。俺が思春期だろうがなんだろうが何処 吹く風で、まさにおしどり夫婦な俺の父さんと母さん。俺の中の二人は、常に笑顔で温かい空気を漂わせていて……。
俺は首を振って、二人の顔を頭から消した。
「嫌だな、ほんと……。こんな自分にはうんざりだ」
「歩夢?」
じっと俺を見つめる海斗の手を引き寄せ、ぐっと強く握りしめた。
「俺が、おばさんと話すよ。頼んでみる」
その手を引っ張り二人で玄関の正面に立つと、息を深く吸った。冷たい海斗の手のひらから、とくんとくんと脈の鼓動 が伝わる。
「おばさんを呼んできてくれないか」
海斗は不安そうに、大きな目をさらに大きくした。
「大丈夫だよ、おれにまかせろ」
俺は強く握っていた手をそっと離した。それを合図に、海斗はドアの向こうへ消えた。
一番心配だった天気は快晴。絶好の星空観察日和と言えるだろう。
俺は念入りに、リュックの中身の最終チェックをした。レジャーシート、防寒具、懐中電灯、虫よけスプレーなど、必需品にもれはない。準備万端だ。
結局、両親にも叔父さんにも今夜のことは伝えなかった。心待ちにしていた大切な日だからこそ、
夜になったら、俺が海斗の家まで迎えに行き、そこから自転車二台で、一緒に学校の裏山まで行くことになっている。
夕方、早めにシャワーを浴びて、買ってきた夕食の弁当をテーブルに置く。テレビをつけて適当な番組をながめながら、
父さんの提案で、わが家は食事のときにテレビをつけない決まりだった。だから決まって父さんが、職場の話(ほとんどくだらない内容だけど)をしたり、寒いオヤジギャグを言ったり、母さんが近所で仕入れた世間話をしたり、俺が学校の話を少しする。
他人から見たら、いかにも『わきあいあい』な家族
「ほんっと……いつもくっだらないギャグばっかだったよな……」
思わず思い出し笑いをしながら独り言ちて、ペットボトルの麦茶に口をつける。
ふと、海斗のことを考えた。
海斗の家で、笑い声は聞こえるのだろうか。海斗は、おじさんが家に帰って来ないと言っていたが、それなら、おばさんと海斗の間に笑顔はあるのか、そして笑い声は……。
今までの様子だと、それは期待できそうにないなと思った。先日の、海斗の悲しそうな顔が頭に浮かんで、胸の中がささくれていくような気がした。
♢
今夜だけは、予想外のアクシデントが起きてほしくない。誰にも邪魔されたくない。
だから俺は、もしものときの保険代わりに、置き手紙を残すことにした。俺達は、自分の意思で部屋を抜け出したこと、日数をかけて準備を重ねていたこと。それらを丁寧に書いて、テーブルの上に置いた。
万が一、この手紙を誰かに見られたとしても、大丈夫だという自信が俺にはあった。心配なのは、海斗のお母さんだった。
おばさんがぐっすり眠ったのを確認してから、海斗は自分の部屋を出る。おばさんの眠る部屋と、海斗の部屋は隣り合わせだから、慎重に行動しないと気づかれてしまう恐れがある。
極力物音を立てず、静かに行動するよう海斗には伝えたし、二人で何度もシミュレーションを繰り返した。
シミュレーションといっても、俺がおばさんの役で海斗は本人役。最初は真面目に始めるんだけどついつい笑ってしまい、完成度の低い出来損ないのコントみたいなのをただ繰り返しただけだ。
あの時は楽しかったけど、実践でその効果は……期待できそうもない。
今さらだけど、大丈夫だろうか。
Tシャツに長めのジーンズ、腰に防寒用の長袖シャツを巻いて、リュックを背負って帽子をかぶった。
音を立てないように玄関ドアの鍵をかけて、そっと階段を降りた。あらかじめ、自転車置き場の手前に移動しておいた自転車のライトをつけ、またがると海斗の家へ向かった。
普段はバス通学だから、しばらくほったらかしにしていたせいで、自転車はところどころ
街灯の少ない薄暗い通りを、自転車のライトを頼りに進む。畑や木々の多い道は特に真っ暗で、地上と空の継ぎ目がわからないほどだった。周囲も空もまっ黒で、けれど、空には星が
――すっげえ、キラキラしてる
期待と緊張で胸は痛いほどドキドキしてるのに、周囲の景色が綺麗で、一刻も早く、海斗と分かち合いたいと思った。
目的地より少し手前で、自転車を静かに停めた。
海斗の家は、屋根も外壁も白い板が何枚も折り重なったような造りで、建売の住宅とは違ういかにもオシャレな洋風の家だ。周りのどの家よりも白く浮かび上がって見えるから、すぐにわかった。
海斗はまだ外に出ていなかった。俺は玄関の正面を避けて、自転車を家の脇道に移動させた。
しばらく待っていると、玄関のドアがゆっくり開き、人影が出てきた。
――海斗?
海斗だった。
ホッとして見守っていると、なんだか様子が変だった。やけに軽装だし、リュックも
「歩夢……歩夢……いるの?」
暗くて表情はわからないが、その声は震えていて、なにかしらのアクシデントを予感させた。俺の背中がぴしりと
「こっちだ、海斗。どうした? もしかして、おばさんに見つかったのか」
「歩夢っ」
すぐそばまで行くと、海斗はひどく困ったような顔をしていた。
「お母さん、いつもこの時間なら自分の部屋に入って朝まで出てこないんだけど、今夜に限ってリビングに居座って、ずっと誰かと電話してるんだ」
「まじかよ……」
「とりあえずトイレに起きたふりして出てきたんだけど、このまま出発したとしてもお母さんに怪しまれるし、リュックなんて
海斗の家は、二階へ上がる階段が廊下ではなくリビングの奥にある。だから、海斗の部屋から玄関へ移動するには、リビングにいるおばさんの横を通らないと行けない。
そういえば小学校低学年のころ、何度か母さんと一緒に海斗の家へ遊びに行ったことがあった。そのとき、家の間取りを母さんがしきりに感心してたのを思い出した。
ほとんどの家は、階段は廊下の近くか、玄関側にあったりするらしい。けれど、海斗の家はリビングの奥に二階へ上がる階段がある。
思春期を迎えた子供は、帰宅すると親の顔も見ずに真っ直ぐ自室へひっこんでしまいがちになるが、この家のようにリビングを通らないと自室へ行けない造りなら、たとえ会話がなくても
そういえば、以前俺が住んでいた一戸建ては、やっぱり玄関入ってすぐ階段だったと思い出す。
でもうちの両親は、子供に気を遣うようなたまじゃない。
帰宅したら必ず「ただいま」を言わされたし、「行ってきます」を忘れたりしたりしたら大変だった。
母さんと父さんに、代わる代わるしつこくハグされるし、俺が意地を張ったりしたら、母さんの顔中キス攻撃が待っていた。
「ここは日本だ」とか「思春期の子供なんてそんなもんだ」などという一般的な見解は、うちの両親には一切通じない。
だが海斗の家の、子育てに理想的な造りが、今回の計画には
――どうする? ……落ち着け。どうすればいい?
こんなときほど
「どうしよう、歩夢……。僕、今夜見に行きたいのに。すごくすごく、楽しみにしてたのに」
「海斗……」
海斗の顔は、今にも泣きだしそうに
こんな悲しそうな顔のまま、北海道に行かせたくなかった。二人の心に深く残る想い出を作りたい。別れのときは晴れやかな笑顔で送り出したい。
俺の中に、ふつふつと何か熱いものが
入試本番を迎えるまで、俺たちは互いに
あの頃の俺はもっと熱い人間だったはずだ。こんなに冷めたヤツじゃなかった。明るい未来を信じて、がむしゃらに頑張っていた。
あの頃の気持ちを忘れてしまっていた。振り返らず前だけを見つめて、ひたすら勉強していたころの自分を。
月明かりに照らされた海斗の顔は、白く浮かんで見える。その瞳に映る俺の顔は、きっと情けない表情に違いない。
第一志望校の合格発表の日、パソコンの画面上に自分の受験番号を見つけられなかったあの日。
一緒に頑張ってきたのに、俺だけが志望校に受からなかったのだと知ったあの日。
「海斗に負けた」と確かに思った。置いて行かれたと思った。 北海道へ行ってしまう海斗のために、頑張りたいだなんて口先だけで、
あの瞬間から今の今まで、俺はずっと立ち止まったままだったのだろう。その事実を突きつけられ、
――自分なりにあきらめて、現実を受け入れたつもりだったのにな……。
あきらめて、無理矢理現実を見ようとした。
頑張っても報われないことがあることを知った。見せられた。忘れようとしていた。
いくら子供は親の都合で行く先を決められることになっても、思いだけは自分のものなのに。
なら、もっと肩の力を抜いて普通に生きていけばいいじゃないかと、俺はそう思った。その方が断然楽だったからだ。
十二歳で、残酷な現実を突き付けられた俺は、そう思うしかなかったんだ。
だがそれでも、俺はまだラッキーな方だった。併願で受験した今の学校に入れたんだから。塾仲間の中には、どこにも受からずに結局、学区内の公立中学校へ進学したヤツもいた。
四年生から進学塾に通い、放課後の遊びをずっと断わり続けた人間が、中学に上がって同じ教室にいたら、そりゃ周囲は驚くだろう。けれど、そんなヤツらはゴロゴロいた。どんなに
――そうだ、俺はあいつらに比べたら、マシだった。
気持ちの上では、そう折り合いをつけて納得したつもりだった。けれど、俺にとっての厳しい現実はそれだけじゃなかったから……。
底抜けに明るい両親の顔が浮かぶ。俺が思春期だろうがなんだろうが
俺は首を振って、二人の顔を頭から消した。
「嫌だな、ほんと……。こんな自分にはうんざりだ」
「歩夢?」
じっと俺を見つめる海斗の手を引き寄せ、ぐっと強く握りしめた。
「俺が、おばさんと話すよ。頼んでみる」
その手を引っ張り二人で玄関の正面に立つと、息を深く吸った。冷たい海斗の手のひらから、とくんとくんと脈の
「おばさんを呼んできてくれないか」
海斗は不安そうに、大きな目をさらに大きくした。
「大丈夫だよ、おれにまかせろ」
俺は強く握っていた手をそっと離した。それを合図に、海斗はドアの向こうへ消えた。