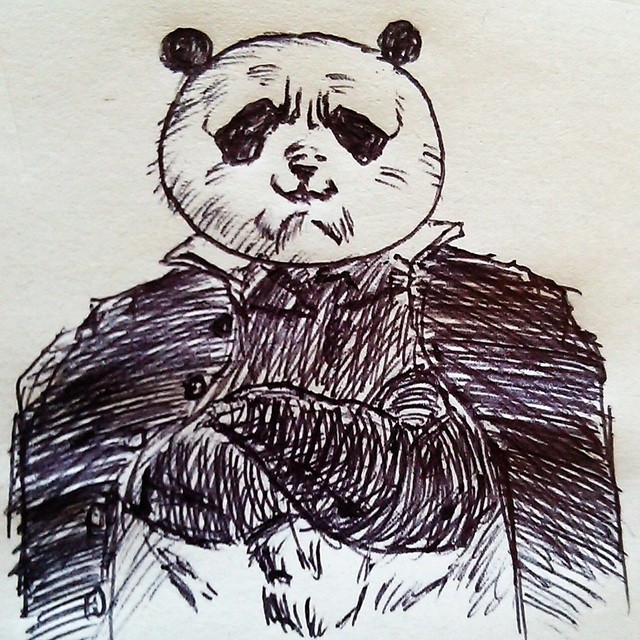お題【私の代わりに……】
文字数 7,738文字
柳小路華子を俺はよく知っている。
彼女はいいところのお屋敷の子で、良くいえば上品、悪くいえばトロかった。ただ彼女の家はここいらでは昔からの大地主だったし、容姿も可愛かったので、彼女についての感想を求められた大抵の人は、言葉を選び、決して蔑む者など居なかった。
俺は、小学校の一年と二年で、彼女と同じクラスだった。
小学校で最初の運動会、ダンスで開始時点のペアが彼女だった。手を握った時の気恥ずかしさと、彼女のはにかんだ笑顔とが印象的で、それからは意識して彼女の横顔を追うようになった。
夏休みが始まる前、広島に送る千羽鶴を皆で折ることになった。
彼女は、折るのはとても遅いけれど、仕上がりはクラスで一番キレイだった。その折り方も丁寧で、俺は彼女の指に見とれていた。いつからかは分からないけれど、柳小路華子は確実に、俺の初恋だったのだ。
うちの小学校は、奇数年次にクラス替えがあった。三年生の時、彼女と同じクラスになれなかった俺は、別の子を好きになったりもした。でも、五年のクラス替えの時、柳小路華子熱が再び高まり、同じクラスになることを熱望した。
あの日の事はよく覚えている。
五年生の最初の登校日。
学校に着いてからクラス替えの結果がわかる。
俺は、配られた名簿の中、いち早く柳小路華子の名前を探す。そして見つけた……同じクラスだ! これは運命的な再会だと俺は感じた。喜び勇んでクラスへと入り……他の人には気付かれないよう視界の隅ギリギリで柳小路華子の姿を探す……居る! ……でも。
柳小路華子は座り込んでいた。
教室の床に。下腹部を抱きしめるようにうずくまっている。
「お腹、痛いんでしょ? トイレ行ったら?」
「そうね、それがいいわ。私たち手伝ってあげる」
彼女を取り囲んでいた四人の女子たちは、柳小路華子を無理やり立たせると、一緒に教室を出ていった。数分後、四人だけで戻ってきた。俺は能天気なことに、柳小路華子は保健室にでもいるのだと勝手に思っていた。
後で知ったことだが、柳小路華子を囲んで嗤っていた連中は、三、四年で彼女と同じクラスだったヤツラで、『トイレの花子さん』という都市伝説をモチーフに、彼女をトイレに連れて行って閉じ込めるという『遊び』をもう半年以上続けているということだった。
いじめ主犯格の女子の好きだった男子が、柳小路華子を可愛いと言ったとか言わないとかいう、くだらない理由で。
当時の担任だった若い男性教師は、いじめに気付いて注意した。
しかしその直後、主犯格女子に、セクハラの濡れ衣を着せられて学校を去り、それ以降、いじめは黙殺されるようになっていたのだという。
いじめ女子連中は、朝一に彼女をトイレに閉じ込めて出られないようにし、放課後まで放置して、帰宅前にトイレのドアを開けるという、その一連の行為を『遊び』とのたまい、毎日のように繰り返した。
俺は、それを黙って見ていた。教師ですら手を出せないそいつらに、歯向かう勇気も知恵も力も、俺には何もなかったから。
彼女を見殺しにしている自分の罪悪感を、俺はよりによって「あんだけやられてそれでも毎日学校に来るのは、彼女自身たいしたことはないと思っていて、きっと勉強サボれてラッキーくらいに思っているかも」などという最低の思い込みで、散らして、ごまかして、見て見ぬふりを続けた。
そんな日々が数週間ほど経ったある放課後に、悲鳴が響いた。俺は掃除当番の途中だったが、悲鳴の聞こえた方向へすぐさま走った。いやな予感がしたからだ。
俺たちの教室から十五メートルほどしか離れていない女子トイレの前に、連中がいた。
いつもは柳小路華子を転ばせて見下ろしながら嗤っている連中が、怯えた表情で、女子トイレの前の廊下にみっともなくしゃがみ込んでいた。
連中全員の視線が向かっている先を、女子トイレの中を、俺は覗き込めないでいた。それは女子トイレの中だからではなくて……そうなっている可能性を、考えたくもなかったから。
やがて、教師が来て、救急車と、警察とが来て。
そして柳小路華子は二度と登校してこなかった。
担任は……大人は皆、彼女について一切何も触れなかった。
柳小路華子という禁忌は、やがて、彼女をいじめていた連中が一人ずつ登校拒否になるという、どう考えても呪いとしか思えないことが四回も続いたことで更にタブー感を増してゆく。
中学生になると、違う小学校出身の何人かが、安易な気持ちで「トイレのハナコさん」の話題を振ってきた。
彼女と同じ小学校出身の俺たちは、思い出したくもないトラウマに触れられた時の表情で睨み返す。
そういうやり取りを何回か経て、柳小路華子の話をする者はどこにも居なくなった。
去る者は日日に疎し。
俺は中学を卒業し、高校も出て、東京の大学に入り、大学の近くでそのまま就職した。
結婚もして一人息子も生まれ、順風満帆だった。ここ二十年近く彼女の名前を聞くこともなく、すっかり忘れていた。
たった今までは。
「安井君、君のことは孫の華子からよく聞いているよ」
俺の目の前に座っている老人は、穏やかな表情でそう言った。
ここは、大地主である柳小路さんのお屋敷。そう、思い出した。柳小路華子の実家だ。
「……はい」
俺は混乱していた。
柳小路華子は勝手に死んだと思っていたが、そうではなかったのか。
というより、俺の話をしていた?
柳小路華子が?
俺は、自分が彼女を見殺しにしていた辛い記憶を飛び越えて、純粋に彼女を想っていた初恋の記憶を、手繰り寄せようとした……が、そう都合よく完結出来るわけもない。
思い出したくないことも芋づる式に溢れてくる。
なんだか動悸が早くなる。
落ち着け俺。
よく聞いているとは言ったが、どんな内容かまでは聞いていないんだ。
よく見ろ、柳小路さんの表情。決して笑顔ではない。
かといって刺すような非難の目でもない。
どっちなんだ……わからない。
ああ、居心地が悪い。
なんでこんな居心地の悪いところに、俺は座っているんだろう。
こんな事態になった発端は去年、お袋が亡くなったあたりだろう。
俺の親父は昔の人間で、お袋に世話になりっぱなしで、自分では生活のことを何一つできない。
俺は、親父が一人で生きていけないんじゃないかと心配だった。
そんな俺を見かねた妻が、家族三人で実家へと戻り、同居することを承諾してくれた。
仕事も地元で再就職先を探すことになった。いろんなツテを頼り、職種を変えずにようやくこちらの工務店に勤めることができた。
その社長が、この現場に俺を指名したのだ。
「安井君。是非とも君にお願いしたい案件があるんだがね。先方が君をご指名なんだよ」
「自分を、ですか?」
こちらには最近、戻ってきたばかり。
かつての同窓の友人達にさえもまだ、戻ってきたことを伝えてはいないのに。
「ああ、是非にと」
とにかく俺をご指名だと言うのなら、行くしかないだろう……そうやって連れて行かれた先が柳小路家だったのだ。
柳小路さんは、現在、この広いお屋敷に一人暮らしと言う。
娘一家は現在海外に住んでおり、この広さを持て余しているらしい。
「私も歳でね。そろそろ体の自由もきかなくなってきた。施設に入ろうと思っているのだよ」
「柳小路さん、まだまだお若いじゃないですか」
「世辞はいらんよ。でな、死ぬ前に、この屋敷をどうにかしようと考えているんだ。娘はこの屋敷の相続はしたくないと言っている。もういっそ売ってしまおうか、と……」
これだけの敷地、十分にマンションが建つし、戸建てにしてもかなり戸数取れるんじゃないか。
社長がやけに頑張れを連呼していたのはこのせいか。
「その売却を、弊社にお任せくださるということでしょうか」
「ああそうだ。ただし、条件付きだがな」
「条件、ですか?」
「ああ、私の代わりに……華子を頼む」
俺は一瞬、返答に詰まった。
頼むというのは、そういうことだろうか。
俺には妻子がいる。
いくら柳小路華子が初恋の人とはいえ……妻と息子を捨てる選択肢はありえない。
それにさっきは娘一家という表現を使ってた……ということは、華子さんにだって家族が居るってことだろう。
つまりは、そういうことじゃないってことだよな……初恋というソースは人の恋心を容易に空腹にする。危険危険……じゃなくて。
では、いったい頼むというのはどういうことなのだろうか。
早とちりで安易な返事は出来ない。せっかくの大きなチャンスなのだし。
返答の前にまずは詳細を聞いてからだ。
「……あの……頼む、というのは」
「こちらに来たまえ」
柳小路さんは、立ち上がり、廊下へ出た。
屋敷の奥の方へ向かって歩き始める。
「どうしたんだね。ついてきなさい」
「は、はいっ」
俺は慌てて柳小路さんのあとをついてゆく。
そして一つのドアの前にたどり着く。
「入りたまえ」
「はい」
なんだか嫌な予感はしたが、俺は言われた通りそのドアを開けて中へ入ろうとした。
すぐに脛を便器にぶつけそうになった。
そこは異様に奥行きのないトイレ。
しかも入ってすぐ、寒気がした。
「閉めるぞ」
柳小路さんの声と同時に、俺の背中ギリギリにトイレのドアが閉められた。
俺は便座のフタを閉じ、仕方なくその上に座ることにした。
ここでいったい何を……。
その思考はすぐに中断される。女の子の笑い声が聞こえたからだ。
その声に俺は聞き覚えがあった。柳小路華子の声なのだ。
声のする方向を探し見ると、トイレ上方の壁に穴が空いている。
笑い声はその向こうから聞こえて来ているようだ。
あ、笑い声が、止まった。
「安井君、久しぶりだね」
あれ、海外に居るのでは……ひょっとして、一時的に帰国しているとか?
妙にソワソワする……待て待て。俺も向こうも家族持ちなんだ。
あ、早く返事しなきゃ。
「そうだね……覚えていてくれたんだ」
「安井君の方こそ、私の事、忘れていたんじゃない?」
「そ、そんなことないってば」
また、彼女の笑い声。
柳小路華子の笑い声。
向こうは笑っているというのに、俺は涙がにじむ。またこうやって一緒に話せる日が来るだなんて。
他愛もない挨拶から始まり、出会ったばかりの低学年の頃のエピソードだけをチョイスしての思い出話。
俺は、しばし初恋の人との会話を楽しんだ。
しばらくすると、華子ちゃんが黙った。
俺は何度か声をかけてみたが、返事はない。
数秒待ち、数分待ち、どんどん膨らんでゆく不安に後押しされるように、俺はあの小さな穴を覗いてみた。
「華子ちゃん……居ないの?」
穴の向こうも、トイレだった。
面積的なことを考えると、最初にあったトイレに壁を無理やり作り、手前にトイレを新設した感じ……でも、どうしてそんな工事を?
さらに気付いたこともある。
向こう側のトイレには、出入り口になりそうな扉の類がまるでないのだ。俺は不安にかられ、一度、トイレを出ようとした。
ガチャ、ガチャ。
鍵がかけられている。おかしいだろ。普通、鍵って内側からかけるもんじゃないのか。
「安井君、聞こえたかね?」
「柳小路さん、どういうことですか? それに……この壁の向こうに華子さんが」
「ああ、聞こえたのか。一安心だ」
カチャリ。
トイレの外付けの鍵があっさりと開錠される。
ドアノブを回すと、今度はなんなくドアが開く。
おいおい。これって、華子ちゃんと会話できなかったら閉じ込めらるとかそんなオチだったのか?
「華子は恥ずかしがり屋なんだ」
柳小路さんは表情の読めない顔で言う。
「はぁ……あの、華子さんは、今、どこに」
「もう、君と一緒に居るよ」
柳小路さんのその言葉がどういうことを指すのか、その時点では俺はまったく理解していなかった。
「これでようやく、この屋敷も取り壊すことが出来る」
柳小路さんが、その後に続けた言葉に少しひっかかったものの、善は急げで契約の説明をしているうちに些細なことは全て飛んでしまう。
すぐに駆けつけてきた社長も俺同様、大きな契約を前にして興奮し、「余計な口は挟まない」ルールが出来上がってしまっていたし。
きっと、分割した家の一つが華子ちゃんの家になるんだろう……俺は勝手にそう考えていた。
帰社し、社長に褒められ、祝の酒宴に連れて行かれた先のとある小料理屋のトイレに入るまで、全て忘れていた。
ギィ……ギィ……。
用を足している俺の後ろで、何かが揺れている音がする。
俺は酔いがちょっと回っていたから、鍵を閉め忘れてたかな、とまず思った。
それからジッパーを上げて、振り向こうとしたら、トイレの電気が消えた。
「わっ」
思わず声が出る。
「ごめんね」
え、今の……。
「まさか……華子ちゃん?」
なんでこのタイミングでそう聞いたのかはわからない。でも、声が華子ちゃんだったから。
「そう」
華子ちゃんの声が返ってきた。
「私、見られたくないの。だから暗くないと、イヤなの」
「そっか……じゃあ、暗いままでいいよ」
「わぁ。嬉しいなぁ。安井君、やっぱり優しい」
華子ちゃんと言葉を交わしながら、俺はやっとわかったのだ。「もう、君と一緒に居る」ということがどういうことなのかを。
不思議と恐怖は少なかった。
それよりも、今度こそは逃げたくないという気持ちの方が強かった。
俺はあの頃、毎日トイレに連れて行かれる華子ちゃんをずっと見て見ぬふりをしていたんだ。もしかしたら、助けられたかもしれないのに。
だから、今度は。
その日から、俺はトイレに入る度に、華子ちゃんとしゃべるようになった。
楽しかった頃の話を。
華子ちゃんは、トイレでしか声を出すことが出来なくて、しかも灯りを極端に嫌う。
俺は電気を消してから用を足すのが上手になった。
「おい、お前。いつの間にトイレで独り言なんてクセついたんだ?」
親父にそんなことを言われ、うまくごまかしはしたものの、このままではいけないなと考えるようになる。
そのタイミングで、柳小路さんから嬉しい申し出があった。
柳小路さんの広大なお屋敷は取り壊され、現在は戸建て八戸の分譲住宅が建てられている真っ最中。柳小路さんは、そのうちの一戸を格安で購入する権利を俺にくれるという。
これを断る理由はない。幸い、この新居と実家とは、ラーメンは伸びるけれどスープは冷めない距離だし。
理由はあともう一つ。
何もできないと思っていた親父がけっこう家事ができるようになっていたのだ。
お袋は親父より先に逝くことが分かっていたのか、家事ノートを作り、生きているうちから親父にいろいろ仕込んでいたのだ。
「俺はな、こうして家事をしていると、母さんと一緒に生きている、そう感じるんだ」
そんなことを言う親父を見て、俺はやっぱりこの人の子どもなんだなと感じる。
俺だって、華子ちゃんと一緒に居る時間には、甘酸っぱい幸せをいつも感じているから。
俺と妻子は新居へと移り、これからは何もかも上手くいく。
そう信じていた。
だが、新居には不穏な空気が漂い始めていた。
俺と華子ちゃんとの会話を、実家で親父がたまたま聞いたということは、俺の妻や息子がたまたま聞く可能性もあるということだ。
聞かれていたんだ。
俺がトイレで「ハナコチャン」という名前を連呼していることを、息子に。
とある夜、息子はトイレで「ハナコチャン」と口に出してみた。
なんの気なしに。
すると、華子ちゃんはそれに反応して、現れて……電気が点いていたから、息子は、華子ちゃんの姿を見てしまったんだ。
華子ちゃんをいじめていた連中があの日見た、華子ちゃんの最期の姿をそのまま。
息子はそれ以来、自分の部屋から出て来なくなってしまった。
妻は「寝ぼけてオバケの夢でも見たんじゃない?」とか言っていたが、俺にはわかったんだ。
息子が断片的に訴えた、恐怖の瞬間の報告から、彼が華子ちゃんを見てしまったのだということが。
俺はさっそく業者を手配し、自宅のトイレを改装した。柳小路さんの家で見たあのトイレと同じように、華子ちゃん専用の真っ暗なトイレを確保して、俺たちが用を足す日常用のトイレを新設した。
でも、遅かったんだ。
「安井君、キライ。私のこと見て酷いこと言った」
「ごめんよ。あれは俺じゃなくって俺の息子なんだ」
「だって安井君だったよ」
華子ちゃんの言う通り、俺の息子は、若い頃の俺に顔がよく似ている。
「もう、ここのトイレは使いたくない。イヤなトイレになっちゃったもん」
「華子ちゃんのために、せっかくトイレを改装したんだよ?」
「うちにはあと七つもトイレあるじゃない。他のトイレを使おうよ」
どうやら華子ちゃんは、もと柳小路家の敷地にある建物のトイレは全部「うちのトイレ」という感覚でいるようだった。
実際、トイレで変な声を聞いたとか、幽霊を見たとか、息子の一件以降、他の七軒の分譲住宅でもちらほら騒ぎ立てる人が出てくるようになった。
俺は慌てて、そういった住人の方のトイレを、柳小路さん式のトイレへと次々改装していった。
少なくとも、華子ちゃんがとても嫌がっている「姿を見られる」事件は減らせるだろうから。
「華子ちゃん……」
華子ちゃんはすぐに返事をしてくれないことが増えてきた。他の家のトイレに行っているのかな。
「……華子ちゃん」
「なぁに」
「ああ、良かった。ようやく来てくれた」
「安井君? 私、ここのトイレ、もう好きくないって言ったよ。どうして他のトイレを使ってくれないの」
「それは……」
柳小路さんの家が解体され、新しく八つの家が建てられたことを、俺がそのうちの一つのトイレにしか入れないことを、どうやって彼女に説明しようか悩んでいたら、華子ちゃんはとんでもないことを言いだした。
「いいもん。私、見つけたんだ。安井君よりカッコイイ子がいたんだよ。あの子、どこのトイレを使っている子だったっけかな……」
初恋は実らないって言うけれど、本当だな……いや、違う。
華子ちゃんの「うちのトイレ」に、その「カッコイイ子」とやらが二度と入らなければ……また俺の所に戻ってきてくれるはず。
確か妻が、お向かいの子がプリントをよく持ってきてくれるとか言っていた。そいつなのか……そいつさえ居なくなれば。
<終>
彼女はいいところのお屋敷の子で、良くいえば上品、悪くいえばトロかった。ただ彼女の家はここいらでは昔からの大地主だったし、容姿も可愛かったので、彼女についての感想を求められた大抵の人は、言葉を選び、決して蔑む者など居なかった。
俺は、小学校の一年と二年で、彼女と同じクラスだった。
小学校で最初の運動会、ダンスで開始時点のペアが彼女だった。手を握った時の気恥ずかしさと、彼女のはにかんだ笑顔とが印象的で、それからは意識して彼女の横顔を追うようになった。
夏休みが始まる前、広島に送る千羽鶴を皆で折ることになった。
彼女は、折るのはとても遅いけれど、仕上がりはクラスで一番キレイだった。その折り方も丁寧で、俺は彼女の指に見とれていた。いつからかは分からないけれど、柳小路華子は確実に、俺の初恋だったのだ。
うちの小学校は、奇数年次にクラス替えがあった。三年生の時、彼女と同じクラスになれなかった俺は、別の子を好きになったりもした。でも、五年のクラス替えの時、柳小路華子熱が再び高まり、同じクラスになることを熱望した。
あの日の事はよく覚えている。
五年生の最初の登校日。
学校に着いてからクラス替えの結果がわかる。
俺は、配られた名簿の中、いち早く柳小路華子の名前を探す。そして見つけた……同じクラスだ! これは運命的な再会だと俺は感じた。喜び勇んでクラスへと入り……他の人には気付かれないよう視界の隅ギリギリで柳小路華子の姿を探す……居る! ……でも。
柳小路華子は座り込んでいた。
教室の床に。下腹部を抱きしめるようにうずくまっている。
「お腹、痛いんでしょ? トイレ行ったら?」
「そうね、それがいいわ。私たち手伝ってあげる」
彼女を取り囲んでいた四人の女子たちは、柳小路華子を無理やり立たせると、一緒に教室を出ていった。数分後、四人だけで戻ってきた。俺は能天気なことに、柳小路華子は保健室にでもいるのだと勝手に思っていた。
後で知ったことだが、柳小路華子を囲んで嗤っていた連中は、三、四年で彼女と同じクラスだったヤツラで、『トイレの花子さん』という都市伝説をモチーフに、彼女をトイレに連れて行って閉じ込めるという『遊び』をもう半年以上続けているということだった。
いじめ主犯格の女子の好きだった男子が、柳小路華子を可愛いと言ったとか言わないとかいう、くだらない理由で。
当時の担任だった若い男性教師は、いじめに気付いて注意した。
しかしその直後、主犯格女子に、セクハラの濡れ衣を着せられて学校を去り、それ以降、いじめは黙殺されるようになっていたのだという。
いじめ女子連中は、朝一に彼女をトイレに閉じ込めて出られないようにし、放課後まで放置して、帰宅前にトイレのドアを開けるという、その一連の行為を『遊び』とのたまい、毎日のように繰り返した。
俺は、それを黙って見ていた。教師ですら手を出せないそいつらに、歯向かう勇気も知恵も力も、俺には何もなかったから。
彼女を見殺しにしている自分の罪悪感を、俺はよりによって「あんだけやられてそれでも毎日学校に来るのは、彼女自身たいしたことはないと思っていて、きっと勉強サボれてラッキーくらいに思っているかも」などという最低の思い込みで、散らして、ごまかして、見て見ぬふりを続けた。
そんな日々が数週間ほど経ったある放課後に、悲鳴が響いた。俺は掃除当番の途中だったが、悲鳴の聞こえた方向へすぐさま走った。いやな予感がしたからだ。
俺たちの教室から十五メートルほどしか離れていない女子トイレの前に、連中がいた。
いつもは柳小路華子を転ばせて見下ろしながら嗤っている連中が、怯えた表情で、女子トイレの前の廊下にみっともなくしゃがみ込んでいた。
連中全員の視線が向かっている先を、女子トイレの中を、俺は覗き込めないでいた。それは女子トイレの中だからではなくて……そうなっている可能性を、考えたくもなかったから。
やがて、教師が来て、救急車と、警察とが来て。
そして柳小路華子は二度と登校してこなかった。
担任は……大人は皆、彼女について一切何も触れなかった。
柳小路華子という禁忌は、やがて、彼女をいじめていた連中が一人ずつ登校拒否になるという、どう考えても呪いとしか思えないことが四回も続いたことで更にタブー感を増してゆく。
中学生になると、違う小学校出身の何人かが、安易な気持ちで「トイレのハナコさん」の話題を振ってきた。
彼女と同じ小学校出身の俺たちは、思い出したくもないトラウマに触れられた時の表情で睨み返す。
そういうやり取りを何回か経て、柳小路華子の話をする者はどこにも居なくなった。
去る者は日日に疎し。
俺は中学を卒業し、高校も出て、東京の大学に入り、大学の近くでそのまま就職した。
結婚もして一人息子も生まれ、順風満帆だった。ここ二十年近く彼女の名前を聞くこともなく、すっかり忘れていた。
たった今までは。
「安井君、君のことは孫の華子からよく聞いているよ」
俺の目の前に座っている老人は、穏やかな表情でそう言った。
ここは、大地主である柳小路さんのお屋敷。そう、思い出した。柳小路華子の実家だ。
「……はい」
俺は混乱していた。
柳小路華子は勝手に死んだと思っていたが、そうではなかったのか。
というより、俺の話をしていた?
柳小路華子が?
俺は、自分が彼女を見殺しにしていた辛い記憶を飛び越えて、純粋に彼女を想っていた初恋の記憶を、手繰り寄せようとした……が、そう都合よく完結出来るわけもない。
思い出したくないことも芋づる式に溢れてくる。
なんだか動悸が早くなる。
落ち着け俺。
よく聞いているとは言ったが、どんな内容かまでは聞いていないんだ。
よく見ろ、柳小路さんの表情。決して笑顔ではない。
かといって刺すような非難の目でもない。
どっちなんだ……わからない。
ああ、居心地が悪い。
なんでこんな居心地の悪いところに、俺は座っているんだろう。
こんな事態になった発端は去年、お袋が亡くなったあたりだろう。
俺の親父は昔の人間で、お袋に世話になりっぱなしで、自分では生活のことを何一つできない。
俺は、親父が一人で生きていけないんじゃないかと心配だった。
そんな俺を見かねた妻が、家族三人で実家へと戻り、同居することを承諾してくれた。
仕事も地元で再就職先を探すことになった。いろんなツテを頼り、職種を変えずにようやくこちらの工務店に勤めることができた。
その社長が、この現場に俺を指名したのだ。
「安井君。是非とも君にお願いしたい案件があるんだがね。先方が君をご指名なんだよ」
「自分を、ですか?」
こちらには最近、戻ってきたばかり。
かつての同窓の友人達にさえもまだ、戻ってきたことを伝えてはいないのに。
「ああ、是非にと」
とにかく俺をご指名だと言うのなら、行くしかないだろう……そうやって連れて行かれた先が柳小路家だったのだ。
柳小路さんは、現在、この広いお屋敷に一人暮らしと言う。
娘一家は現在海外に住んでおり、この広さを持て余しているらしい。
「私も歳でね。そろそろ体の自由もきかなくなってきた。施設に入ろうと思っているのだよ」
「柳小路さん、まだまだお若いじゃないですか」
「世辞はいらんよ。でな、死ぬ前に、この屋敷をどうにかしようと考えているんだ。娘はこの屋敷の相続はしたくないと言っている。もういっそ売ってしまおうか、と……」
これだけの敷地、十分にマンションが建つし、戸建てにしてもかなり戸数取れるんじゃないか。
社長がやけに頑張れを連呼していたのはこのせいか。
「その売却を、弊社にお任せくださるということでしょうか」
「ああそうだ。ただし、条件付きだがな」
「条件、ですか?」
「ああ、私の代わりに……華子を頼む」
俺は一瞬、返答に詰まった。
頼むというのは、そういうことだろうか。
俺には妻子がいる。
いくら柳小路華子が初恋の人とはいえ……妻と息子を捨てる選択肢はありえない。
それにさっきは娘一家という表現を使ってた……ということは、華子さんにだって家族が居るってことだろう。
つまりは、そういうことじゃないってことだよな……初恋というソースは人の恋心を容易に空腹にする。危険危険……じゃなくて。
では、いったい頼むというのはどういうことなのだろうか。
早とちりで安易な返事は出来ない。せっかくの大きなチャンスなのだし。
返答の前にまずは詳細を聞いてからだ。
「……あの……頼む、というのは」
「こちらに来たまえ」
柳小路さんは、立ち上がり、廊下へ出た。
屋敷の奥の方へ向かって歩き始める。
「どうしたんだね。ついてきなさい」
「は、はいっ」
俺は慌てて柳小路さんのあとをついてゆく。
そして一つのドアの前にたどり着く。
「入りたまえ」
「はい」
なんだか嫌な予感はしたが、俺は言われた通りそのドアを開けて中へ入ろうとした。
すぐに脛を便器にぶつけそうになった。
そこは異様に奥行きのないトイレ。
しかも入ってすぐ、寒気がした。
「閉めるぞ」
柳小路さんの声と同時に、俺の背中ギリギリにトイレのドアが閉められた。
俺は便座のフタを閉じ、仕方なくその上に座ることにした。
ここでいったい何を……。
その思考はすぐに中断される。女の子の笑い声が聞こえたからだ。
その声に俺は聞き覚えがあった。柳小路華子の声なのだ。
声のする方向を探し見ると、トイレ上方の壁に穴が空いている。
笑い声はその向こうから聞こえて来ているようだ。
あ、笑い声が、止まった。
「安井君、久しぶりだね」
あれ、海外に居るのでは……ひょっとして、一時的に帰国しているとか?
妙にソワソワする……待て待て。俺も向こうも家族持ちなんだ。
あ、早く返事しなきゃ。
「そうだね……覚えていてくれたんだ」
「安井君の方こそ、私の事、忘れていたんじゃない?」
「そ、そんなことないってば」
また、彼女の笑い声。
柳小路華子の笑い声。
向こうは笑っているというのに、俺は涙がにじむ。またこうやって一緒に話せる日が来るだなんて。
他愛もない挨拶から始まり、出会ったばかりの低学年の頃のエピソードだけをチョイスしての思い出話。
俺は、しばし初恋の人との会話を楽しんだ。
しばらくすると、華子ちゃんが黙った。
俺は何度か声をかけてみたが、返事はない。
数秒待ち、数分待ち、どんどん膨らんでゆく不安に後押しされるように、俺はあの小さな穴を覗いてみた。
「華子ちゃん……居ないの?」
穴の向こうも、トイレだった。
面積的なことを考えると、最初にあったトイレに壁を無理やり作り、手前にトイレを新設した感じ……でも、どうしてそんな工事を?
さらに気付いたこともある。
向こう側のトイレには、出入り口になりそうな扉の類がまるでないのだ。俺は不安にかられ、一度、トイレを出ようとした。
ガチャ、ガチャ。
鍵がかけられている。おかしいだろ。普通、鍵って内側からかけるもんじゃないのか。
「安井君、聞こえたかね?」
「柳小路さん、どういうことですか? それに……この壁の向こうに華子さんが」
「ああ、聞こえたのか。一安心だ」
カチャリ。
トイレの外付けの鍵があっさりと開錠される。
ドアノブを回すと、今度はなんなくドアが開く。
おいおい。これって、華子ちゃんと会話できなかったら閉じ込めらるとかそんなオチだったのか?
「華子は恥ずかしがり屋なんだ」
柳小路さんは表情の読めない顔で言う。
「はぁ……あの、華子さんは、今、どこに」
「もう、君と一緒に居るよ」
柳小路さんのその言葉がどういうことを指すのか、その時点では俺はまったく理解していなかった。
「これでようやく、この屋敷も取り壊すことが出来る」
柳小路さんが、その後に続けた言葉に少しひっかかったものの、善は急げで契約の説明をしているうちに些細なことは全て飛んでしまう。
すぐに駆けつけてきた社長も俺同様、大きな契約を前にして興奮し、「余計な口は挟まない」ルールが出来上がってしまっていたし。
きっと、分割した家の一つが華子ちゃんの家になるんだろう……俺は勝手にそう考えていた。
帰社し、社長に褒められ、祝の酒宴に連れて行かれた先のとある小料理屋のトイレに入るまで、全て忘れていた。
ギィ……ギィ……。
用を足している俺の後ろで、何かが揺れている音がする。
俺は酔いがちょっと回っていたから、鍵を閉め忘れてたかな、とまず思った。
それからジッパーを上げて、振り向こうとしたら、トイレの電気が消えた。
「わっ」
思わず声が出る。
「ごめんね」
え、今の……。
「まさか……華子ちゃん?」
なんでこのタイミングでそう聞いたのかはわからない。でも、声が華子ちゃんだったから。
「そう」
華子ちゃんの声が返ってきた。
「私、見られたくないの。だから暗くないと、イヤなの」
「そっか……じゃあ、暗いままでいいよ」
「わぁ。嬉しいなぁ。安井君、やっぱり優しい」
華子ちゃんと言葉を交わしながら、俺はやっとわかったのだ。「もう、君と一緒に居る」ということがどういうことなのかを。
不思議と恐怖は少なかった。
それよりも、今度こそは逃げたくないという気持ちの方が強かった。
俺はあの頃、毎日トイレに連れて行かれる華子ちゃんをずっと見て見ぬふりをしていたんだ。もしかしたら、助けられたかもしれないのに。
だから、今度は。
その日から、俺はトイレに入る度に、華子ちゃんとしゃべるようになった。
楽しかった頃の話を。
華子ちゃんは、トイレでしか声を出すことが出来なくて、しかも灯りを極端に嫌う。
俺は電気を消してから用を足すのが上手になった。
「おい、お前。いつの間にトイレで独り言なんてクセついたんだ?」
親父にそんなことを言われ、うまくごまかしはしたものの、このままではいけないなと考えるようになる。
そのタイミングで、柳小路さんから嬉しい申し出があった。
柳小路さんの広大なお屋敷は取り壊され、現在は戸建て八戸の分譲住宅が建てられている真っ最中。柳小路さんは、そのうちの一戸を格安で購入する権利を俺にくれるという。
これを断る理由はない。幸い、この新居と実家とは、ラーメンは伸びるけれどスープは冷めない距離だし。
理由はあともう一つ。
何もできないと思っていた親父がけっこう家事ができるようになっていたのだ。
お袋は親父より先に逝くことが分かっていたのか、家事ノートを作り、生きているうちから親父にいろいろ仕込んでいたのだ。
「俺はな、こうして家事をしていると、母さんと一緒に生きている、そう感じるんだ」
そんなことを言う親父を見て、俺はやっぱりこの人の子どもなんだなと感じる。
俺だって、華子ちゃんと一緒に居る時間には、甘酸っぱい幸せをいつも感じているから。
俺と妻子は新居へと移り、これからは何もかも上手くいく。
そう信じていた。
だが、新居には不穏な空気が漂い始めていた。
俺と華子ちゃんとの会話を、実家で親父がたまたま聞いたということは、俺の妻や息子がたまたま聞く可能性もあるということだ。
聞かれていたんだ。
俺がトイレで「ハナコチャン」という名前を連呼していることを、息子に。
とある夜、息子はトイレで「ハナコチャン」と口に出してみた。
なんの気なしに。
すると、華子ちゃんはそれに反応して、現れて……電気が点いていたから、息子は、華子ちゃんの姿を見てしまったんだ。
華子ちゃんをいじめていた連中があの日見た、華子ちゃんの最期の姿をそのまま。
息子はそれ以来、自分の部屋から出て来なくなってしまった。
妻は「寝ぼけてオバケの夢でも見たんじゃない?」とか言っていたが、俺にはわかったんだ。
息子が断片的に訴えた、恐怖の瞬間の報告から、彼が華子ちゃんを見てしまったのだということが。
俺はさっそく業者を手配し、自宅のトイレを改装した。柳小路さんの家で見たあのトイレと同じように、華子ちゃん専用の真っ暗なトイレを確保して、俺たちが用を足す日常用のトイレを新設した。
でも、遅かったんだ。
「安井君、キライ。私のこと見て酷いこと言った」
「ごめんよ。あれは俺じゃなくって俺の息子なんだ」
「だって安井君だったよ」
華子ちゃんの言う通り、俺の息子は、若い頃の俺に顔がよく似ている。
「もう、ここのトイレは使いたくない。イヤなトイレになっちゃったもん」
「華子ちゃんのために、せっかくトイレを改装したんだよ?」
「うちにはあと七つもトイレあるじゃない。他のトイレを使おうよ」
どうやら華子ちゃんは、もと柳小路家の敷地にある建物のトイレは全部「うちのトイレ」という感覚でいるようだった。
実際、トイレで変な声を聞いたとか、幽霊を見たとか、息子の一件以降、他の七軒の分譲住宅でもちらほら騒ぎ立てる人が出てくるようになった。
俺は慌てて、そういった住人の方のトイレを、柳小路さん式のトイレへと次々改装していった。
少なくとも、華子ちゃんがとても嫌がっている「姿を見られる」事件は減らせるだろうから。
「華子ちゃん……」
華子ちゃんはすぐに返事をしてくれないことが増えてきた。他の家のトイレに行っているのかな。
「……華子ちゃん」
「なぁに」
「ああ、良かった。ようやく来てくれた」
「安井君? 私、ここのトイレ、もう好きくないって言ったよ。どうして他のトイレを使ってくれないの」
「それは……」
柳小路さんの家が解体され、新しく八つの家が建てられたことを、俺がそのうちの一つのトイレにしか入れないことを、どうやって彼女に説明しようか悩んでいたら、華子ちゃんはとんでもないことを言いだした。
「いいもん。私、見つけたんだ。安井君よりカッコイイ子がいたんだよ。あの子、どこのトイレを使っている子だったっけかな……」
初恋は実らないって言うけれど、本当だな……いや、違う。
華子ちゃんの「うちのトイレ」に、その「カッコイイ子」とやらが二度と入らなければ……また俺の所に戻ってきてくれるはず。
確か妻が、お向かいの子がプリントをよく持ってきてくれるとか言っていた。そいつなのか……そいつさえ居なくなれば。
<終>