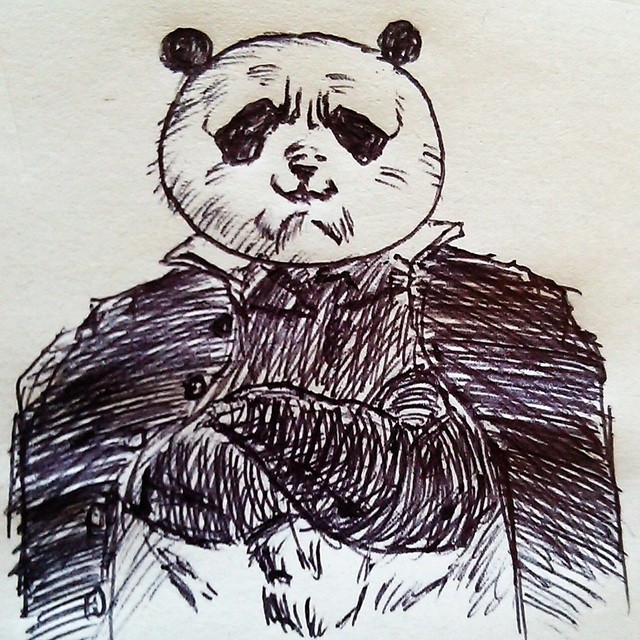お題【これは、天が私に授けてくれたに違いない】
文字数 2,461文字
いつ頃からだろうか。他人の死期が見えるようになったのは。
始めはそういう力だとは分からなかった。人の周囲にぼんやりと光が見えるだけだったから。
だが時折、そのまとう光が弱くなっている人を見かけるようになり、そういう人たちは時間を経ずして必ず死んでいくことに気付いたとき、私は力の意味を理解した。
そして私はいつしか光が薄くなった人を常に探すようになっていた。死に近づきつつある人を、少なからず助けたいと考えたからだ。
このような力がどうして私に備わったのかは分からない。
力を持った者の常として理由を考えたり使い道に悩んだりもした。
しかしどうしても力を私利私欲のために使う気にはなれず、いつしか私はこの力を世の中のために役立てたいと、いや、人を救うために天が私に授けてくれた力なのだと思うようになっていた。
親しい仲間たちはこぞって「そんなことやめておけ」と私へ忠告したが、私は聞かなかった。
私は、死期が近づいた人へと近づき、それを知らせようとしたのだ。
どんなに健康そうに見える人でも周囲にまとっている光が急に弱くなればその人の死は近い。病床の老人ならばともかく自分が死ぬだなんて夢にも思っていない儚き運命の人たちへ、私がそれを知らせることで、死を迎えるための準備が出来たならば、もしくは死そのものを回避できることだってあるかもしれないと、そう考えたのだ。
私は奔走した。
人を助けたくて。その力になりたくて。
私が授かったこの力を無駄にすることなく、死期の迫った人々へ伝え続けようとした……しかし私の想いは、結局のところ誰一人として歓迎してもらえはしなかった。
それどころか本来は死へ向かうべきであろう恐怖や怒りを私に向ける者さえ少なくなかったのだ。
私の存在とはいったいなんなのだ。
天はどうしてこの力を私なんぞに授けたのだろうか。
苦悩に呑まれそうになる私の足は気がつけばある場所へ向かっていた。
とあるコンビニへ……ああ、居た。
レジの向こう。彼女の笑顔を見ているだけで心がふわりと軽くなる。そう、私は彼女に恋をしている。
人の死ばかり追いかけてきた私にとって彼女の笑顔は、いままで私が看取った「消え行く光」の全てをあわせたよりも眩しいものだった。
彼女を眺めている、それだけで、私にしみついた死の臭いがすべて消えてしまうような幸福感に包まれる。
ああ、もっと近くで彼女を眺めたい……けれど、そんな勇気が私には湧いてこなかった。
人々が私を見るときの恐怖や怒りに満ちたあの負の表情を、彼女にもさせてしまうのではないだろうか、あの笑顔を曇らせてしまうのではないだろうか……それが怖くて。
私が物陰から彼女を眺めるようになり、どれくらいの時間が経っただろうか。
私は自分の力も使命感も全て忘れ、彼女の笑顔に癒される日々を送っていた。
そういう距離で十分だった。眺めているだけで幸せだった。だが、天からの授かりものを放棄していた私にバチでも当たったというのだろうか、私は気付いてしまった。彼女を包む光が、弱まっていることに。
何もしなければ、彼女の笑顔だけじゃなく彼女自身という光そのものが消えてしまう。それがわかっているのに、私は彼女の前に出てそれを伝えることが出来ないでいた。
私を見た彼女の表情からはきっと笑顔が消えてしまう……葛藤の中、彼女を包む光は日々弱くなってゆく。
ダメだ。
このまま何もしなければきっと私は後悔する。
それに何よりも彼女は私にとってもはやこの世の中で唯一の光なのだ。
私は決意した。
物陰に隠れるのをやめ、彼女の前へと姿を現す。
ふと自分の手を見ると、強い光に満ち満ちている。
私の意志の光。
どうしてそう思ったのかは分からない。でも、私はこの光を彼女へ贈ろうと考えていた。
私の命の光を、彼女へ。
その時は、やったこともないその行為を全く疑いもしなかった。命を贈るだなんて。ただただ夢中だった。彼女を救いたい一心で。
私は彼女に近づいてゆく。
彼女は商品の並べ替えに夢中になっていて、まだ私に気付いていない。
いいんだ。それでいい。
彼女の笑顔が曇らないならその方がいい。私は彼女の隣に立ち、飛んで、そして彼女の手へと触れた。
私の光が彼女の中に流れてゆくのを感じる。
嗚呼、これでいい。
私の意識が薄れゆくなか、彼女の悲鳴が聞こえた。そして、倒れる音……。
あたしの目が覚めたとき、近くにママが居た。
ママに声をかけようと思ったのだけれど声が出ない。
体のあちこちが痛いし重い。
それでも一生懸命体を動かそうとしていたら、ママはあたしに気付いてくれた。ママは泣きながら喜んで「看護士さん!」と叫ぶ……ここ、病院?
すぐに白衣の人たちがやってくる。看護士さんにお医者さん、かな? 皆、あたしのことを見つめながら興奮気味に叫んでいる。どういうこと? あたしが生きていることがそんなにすごいことなの?
「君は悲鳴をあげながらコンビニから飛び出したところで大型トラックにはねられたんだ。だが、脅威の生命力で……その……普通の人なら死んでいるような怪我なのに生きているんだっ! 普通の人間なら即死のところを」
はねられた? 大型トラックに? ……コンビニってあたしがバイトしていた? えっと……あ、そうだ確かいきなりアレが飛んできてあたしの手にとまったのよね。それで慌てて逃げ出して……ズキッとお腹のあたりが痛くなる。ああ、そう、ものすごい痛みがお腹の上を通り抜けたような……あたしはその時気付いてしまった。ベッドに横たえられている自分の体の下半分がないことに。その時、頭の奥の方で声が聞こえた。
その声はあたしに『だいじょうぶだよ』と告げてから、語りはじめた。
『いつ頃からだろうか。他人の死期が見えるようになったのは……』
<終>
始めはそういう力だとは分からなかった。人の周囲にぼんやりと光が見えるだけだったから。
だが時折、そのまとう光が弱くなっている人を見かけるようになり、そういう人たちは時間を経ずして必ず死んでいくことに気付いたとき、私は力の意味を理解した。
そして私はいつしか光が薄くなった人を常に探すようになっていた。死に近づきつつある人を、少なからず助けたいと考えたからだ。
このような力がどうして私に備わったのかは分からない。
力を持った者の常として理由を考えたり使い道に悩んだりもした。
しかしどうしても力を私利私欲のために使う気にはなれず、いつしか私はこの力を世の中のために役立てたいと、いや、人を救うために天が私に授けてくれた力なのだと思うようになっていた。
親しい仲間たちはこぞって「そんなことやめておけ」と私へ忠告したが、私は聞かなかった。
私は、死期が近づいた人へと近づき、それを知らせようとしたのだ。
どんなに健康そうに見える人でも周囲にまとっている光が急に弱くなればその人の死は近い。病床の老人ならばともかく自分が死ぬだなんて夢にも思っていない儚き運命の人たちへ、私がそれを知らせることで、死を迎えるための準備が出来たならば、もしくは死そのものを回避できることだってあるかもしれないと、そう考えたのだ。
私は奔走した。
人を助けたくて。その力になりたくて。
私が授かったこの力を無駄にすることなく、死期の迫った人々へ伝え続けようとした……しかし私の想いは、結局のところ誰一人として歓迎してもらえはしなかった。
それどころか本来は死へ向かうべきであろう恐怖や怒りを私に向ける者さえ少なくなかったのだ。
私の存在とはいったいなんなのだ。
天はどうしてこの力を私なんぞに授けたのだろうか。
苦悩に呑まれそうになる私の足は気がつけばある場所へ向かっていた。
とあるコンビニへ……ああ、居た。
レジの向こう。彼女の笑顔を見ているだけで心がふわりと軽くなる。そう、私は彼女に恋をしている。
人の死ばかり追いかけてきた私にとって彼女の笑顔は、いままで私が看取った「消え行く光」の全てをあわせたよりも眩しいものだった。
彼女を眺めている、それだけで、私にしみついた死の臭いがすべて消えてしまうような幸福感に包まれる。
ああ、もっと近くで彼女を眺めたい……けれど、そんな勇気が私には湧いてこなかった。
人々が私を見るときの恐怖や怒りに満ちたあの負の表情を、彼女にもさせてしまうのではないだろうか、あの笑顔を曇らせてしまうのではないだろうか……それが怖くて。
私が物陰から彼女を眺めるようになり、どれくらいの時間が経っただろうか。
私は自分の力も使命感も全て忘れ、彼女の笑顔に癒される日々を送っていた。
そういう距離で十分だった。眺めているだけで幸せだった。だが、天からの授かりものを放棄していた私にバチでも当たったというのだろうか、私は気付いてしまった。彼女を包む光が、弱まっていることに。
何もしなければ、彼女の笑顔だけじゃなく彼女自身という光そのものが消えてしまう。それがわかっているのに、私は彼女の前に出てそれを伝えることが出来ないでいた。
私を見た彼女の表情からはきっと笑顔が消えてしまう……葛藤の中、彼女を包む光は日々弱くなってゆく。
ダメだ。
このまま何もしなければきっと私は後悔する。
それに何よりも彼女は私にとってもはやこの世の中で唯一の光なのだ。
私は決意した。
物陰に隠れるのをやめ、彼女の前へと姿を現す。
ふと自分の手を見ると、強い光に満ち満ちている。
私の意志の光。
どうしてそう思ったのかは分からない。でも、私はこの光を彼女へ贈ろうと考えていた。
私の命の光を、彼女へ。
その時は、やったこともないその行為を全く疑いもしなかった。命を贈るだなんて。ただただ夢中だった。彼女を救いたい一心で。
私は彼女に近づいてゆく。
彼女は商品の並べ替えに夢中になっていて、まだ私に気付いていない。
いいんだ。それでいい。
彼女の笑顔が曇らないならその方がいい。私は彼女の隣に立ち、飛んで、そして彼女の手へと触れた。
私の光が彼女の中に流れてゆくのを感じる。
嗚呼、これでいい。
私の意識が薄れゆくなか、彼女の悲鳴が聞こえた。そして、倒れる音……。
あたしの目が覚めたとき、近くにママが居た。
ママに声をかけようと思ったのだけれど声が出ない。
体のあちこちが痛いし重い。
それでも一生懸命体を動かそうとしていたら、ママはあたしに気付いてくれた。ママは泣きながら喜んで「看護士さん!」と叫ぶ……ここ、病院?
すぐに白衣の人たちがやってくる。看護士さんにお医者さん、かな? 皆、あたしのことを見つめながら興奮気味に叫んでいる。どういうこと? あたしが生きていることがそんなにすごいことなの?
「君は悲鳴をあげながらコンビニから飛び出したところで大型トラックにはねられたんだ。だが、脅威の生命力で……その……普通の人なら死んでいるような怪我なのに生きているんだっ! 普通の人間なら即死のところを」
はねられた? 大型トラックに? ……コンビニってあたしがバイトしていた? えっと……あ、そうだ確かいきなりアレが飛んできてあたしの手にとまったのよね。それで慌てて逃げ出して……ズキッとお腹のあたりが痛くなる。ああ、そう、ものすごい痛みがお腹の上を通り抜けたような……あたしはその時気付いてしまった。ベッドに横たえられている自分の体の下半分がないことに。その時、頭の奥の方で声が聞こえた。
その声はあたしに『だいじょうぶだよ』と告げてから、語りはじめた。
『いつ頃からだろうか。他人の死期が見えるようになったのは……』
<終>