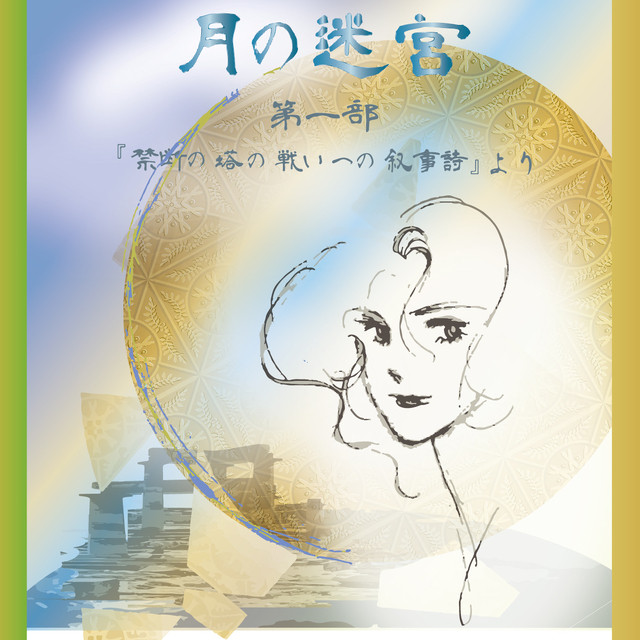第29話 外伝 その六 『精霊の病』②
文字数 2,082文字
リデンは今、精霊の女王として試されていた。全ての治療を拒絶して、唯一『精霊の森』から移植した樹から抽出された樹液の香を焚きしめて寝所の紗幕の中に籠っていた。
その間のすべてはフィーナが取り仕切り、侍女達は中に入るのも彼女の許可が要り、シュラさえ拒まれた。
それでも、あらゆる治療法を求めて国内外の有能な医師や薬草の専門家を当たる王にフィーナはリデンの言葉を告げた。
「陛下にお出来になることは唯一つ・・いえ、それこそがリデン様の病をお救い出来る唯一の治療法なのですが、今すぐ、戦争をお止め下さいまし」
しかし、今のシュラにはそれは簡単には出来ない。何故なら、初めに主要な地域を抑えたシュメリアは開戦以来、その国力を増大させていた。
占領した各地からの物資、特に貴重な鉱物資源のおかげで各種の産業が盛んになり、シュメリアの伝統とも言える高い工芸技術によって武器から装飾品に至るあらゆるものが量産されていた。そして、そういった高品質の製品が海を隔てた国々で飛ぶように売れていた。
周辺諸国の半包囲網の中にあるシュメリアにとって、今や海は命綱とも言え、以前にも増して海洋貿易が盛んになっていた。その堅牢な要塞に守られた幾つかの港からは、夫々一本の真っ直ぐな道が王都メリスへと続き、異国の珍しい物資が大量に運ばれて来た。
更には王都の拡張も進み、今ではそれまでの都の二倍近い規模になっている。その新市街地には、日々を生き延びようとする民のあらゆる営みが生まれ、それが更に至るところから人々を呼び寄せ渦巻くような活気に満ちている。
砂漠化を免れた土地の開墾も進み、そんな多くの民を養えるようにもなっていた。
そして、元々軍事国家ではないシュメリア軍の大半はその莫大な資金で雇った傭兵部隊で、戦に駆り出される国民の犠牲は最小限に抑えられていた。そのためか、民間の厭戦気分も然程高くはない。
しかも傭兵達は入隊して暫くすると、どんな無法者でも易々と厳しい軍律に従うようになる。それには曾ての『月の神殿』での神官養成の方法が使われていた。
そんな事から今やシュラは、国に膨大な富みをもたらす偉大な王として絶大な人気と支持を得ていた。
シュラ王といえば曾ては〝狂王〟とさえ揶揄され、幾つもの無用な城の建設で国家財政を破綻の淵にまで追いやった張本人だ。その狂王が、今や信じられないほどの国家運営の才を見せているのだ。
一時期の脆弱とも思えた気質も強い陽射しの下に消え失せたようで、国中の民が挙って称賛するのも無理はない。
しかしその高騰する景気も、占領地の資源があってこそのものなのだ。
当然、その地の奪還を狙う勢力の抵抗は激しく、更に、団結した周辺諸国をねじ伏せるのは容易ではない。
・・が、連日燃え盛る炎が美しい森を呑み込み、その中に取り残される夢に魘されたシュラは、森の精霊の病が何に起因するものなのか・・漠然と理解した。
それで渋々、リデンが回復するまでは休戦とする事を受け入れた。
リデンが病に倒れてから月が何度も満ち、既に半年以上も過ぎたその満月の夜の夜半過ぎ、リデンのテラスの幕屋に寝そべり、半分微睡みながら・・シュラは、ふと思った。
(・・仮病か?)
その半年の間、ずっとリデンの昏睡状態は続いているという。しかし、寝所に詰めるフィーナは病に差し障ると言って、シュラの入室を頑として拒んでいた。
最近の紛争地からの偵察の報告では、休戦を良いことに敵方の補給活動が活発で、闘の再開の暁にはかなり手こずる事になりそうだ。
(つまり・・回復を遅らせることで、我が軍に不利に働くように仕向け、更なる戦争の拡大を回避・・いや、むしろ終結させようとしているのではないのか・・それも、我が軍の敗北という形で・・)
そんなことを思っていたシュラの耳に、垂れ幕で覆われたリデンの寝所の方から予期せぬ・・泣き声が聞こえて来た。
(え・・まさか!)
思わず跳び起きたシュラは、急いで閨に向かった。
「あ、陛下・・!」
「・・陛下、おめでとうございます!」
呆然としながら寝所に入ったシュラが目にしたのは、その腕に柔らかな布地に包まった小さな二つの命を抱いているリデンの姿だった。
「こ、これは・・精霊の病と言うのは・・こういうことだったのか」
久し振りに目にした病み上がりのリデンは得もいわれず美しく、驚いたことにあの素晴らしい純白の髪が、これまた魅惑的な褐色に変わっていた。
「し、しかしこれは・・誰の子だ・・」
まだ半分合点がいかないように、シュラが言った。
「まあ、陛下・・」
それまでずっと一人で取り仕切って来たフィーナがやや呆れて、憤慨したような口調で言った。
・・精霊の女王の出産など、精霊の系譜に於いても極めて稀なことなのだ。そのためリデンさまが一体、何を失わなければならなかったかと言うことは、その髪が物語っている・・。
しかし当のリデンは、赤子達の父親のそんな言動などまったく意に介した様子もなく、新しい命を見つめる慈しみの眼差しのまま、その視線を向けただけだった・・。
その間のすべてはフィーナが取り仕切り、侍女達は中に入るのも彼女の許可が要り、シュラさえ拒まれた。
それでも、あらゆる治療法を求めて国内外の有能な医師や薬草の専門家を当たる王にフィーナはリデンの言葉を告げた。
「陛下にお出来になることは唯一つ・・いえ、それこそがリデン様の病をお救い出来る唯一の治療法なのですが、今すぐ、戦争をお止め下さいまし」
しかし、今のシュラにはそれは簡単には出来ない。何故なら、初めに主要な地域を抑えたシュメリアは開戦以来、その国力を増大させていた。
占領した各地からの物資、特に貴重な鉱物資源のおかげで各種の産業が盛んになり、シュメリアの伝統とも言える高い工芸技術によって武器から装飾品に至るあらゆるものが量産されていた。そして、そういった高品質の製品が海を隔てた国々で飛ぶように売れていた。
周辺諸国の半包囲網の中にあるシュメリアにとって、今や海は命綱とも言え、以前にも増して海洋貿易が盛んになっていた。その堅牢な要塞に守られた幾つかの港からは、夫々一本の真っ直ぐな道が王都メリスへと続き、異国の珍しい物資が大量に運ばれて来た。
更には王都の拡張も進み、今ではそれまでの都の二倍近い規模になっている。その新市街地には、日々を生き延びようとする民のあらゆる営みが生まれ、それが更に至るところから人々を呼び寄せ渦巻くような活気に満ちている。
砂漠化を免れた土地の開墾も進み、そんな多くの民を養えるようにもなっていた。
そして、元々軍事国家ではないシュメリア軍の大半はその莫大な資金で雇った傭兵部隊で、戦に駆り出される国民の犠牲は最小限に抑えられていた。そのためか、民間の厭戦気分も然程高くはない。
しかも傭兵達は入隊して暫くすると、どんな無法者でも易々と厳しい軍律に従うようになる。それには曾ての『月の神殿』での神官養成の方法が使われていた。
そんな事から今やシュラは、国に膨大な富みをもたらす偉大な王として絶大な人気と支持を得ていた。
シュラ王といえば曾ては〝狂王〟とさえ揶揄され、幾つもの無用な城の建設で国家財政を破綻の淵にまで追いやった張本人だ。その狂王が、今や信じられないほどの国家運営の才を見せているのだ。
一時期の脆弱とも思えた気質も強い陽射しの下に消え失せたようで、国中の民が挙って称賛するのも無理はない。
しかしその高騰する景気も、占領地の資源があってこそのものなのだ。
当然、その地の奪還を狙う勢力の抵抗は激しく、更に、団結した周辺諸国をねじ伏せるのは容易ではない。
・・が、連日燃え盛る炎が美しい森を呑み込み、その中に取り残される夢に魘されたシュラは、森の精霊の病が何に起因するものなのか・・漠然と理解した。
それで渋々、リデンが回復するまでは休戦とする事を受け入れた。
リデンが病に倒れてから月が何度も満ち、既に半年以上も過ぎたその満月の夜の夜半過ぎ、リデンのテラスの幕屋に寝そべり、半分微睡みながら・・シュラは、ふと思った。
(・・仮病か?)
その半年の間、ずっとリデンの昏睡状態は続いているという。しかし、寝所に詰めるフィーナは病に差し障ると言って、シュラの入室を頑として拒んでいた。
最近の紛争地からの偵察の報告では、休戦を良いことに敵方の補給活動が活発で、闘の再開の暁にはかなり手こずる事になりそうだ。
(つまり・・回復を遅らせることで、我が軍に不利に働くように仕向け、更なる戦争の拡大を回避・・いや、むしろ終結させようとしているのではないのか・・それも、我が軍の敗北という形で・・)
そんなことを思っていたシュラの耳に、垂れ幕で覆われたリデンの寝所の方から予期せぬ・・泣き声が聞こえて来た。
(え・・まさか!)
思わず跳び起きたシュラは、急いで閨に向かった。
「あ、陛下・・!」
「・・陛下、おめでとうございます!」
呆然としながら寝所に入ったシュラが目にしたのは、その腕に柔らかな布地に包まった小さな二つの命を抱いているリデンの姿だった。
「こ、これは・・精霊の病と言うのは・・こういうことだったのか」
久し振りに目にした病み上がりのリデンは得もいわれず美しく、驚いたことにあの素晴らしい純白の髪が、これまた魅惑的な褐色に変わっていた。
「し、しかしこれは・・誰の子だ・・」
まだ半分合点がいかないように、シュラが言った。
「まあ、陛下・・」
それまでずっと一人で取り仕切って来たフィーナがやや呆れて、憤慨したような口調で言った。
・・精霊の女王の出産など、精霊の系譜に於いても極めて稀なことなのだ。そのためリデンさまが一体、何を失わなければならなかったかと言うことは、その髪が物語っている・・。
しかし当のリデンは、赤子達の父親のそんな言動などまったく意に介した様子もなく、新しい命を見つめる慈しみの眼差しのまま、その視線を向けただけだった・・。