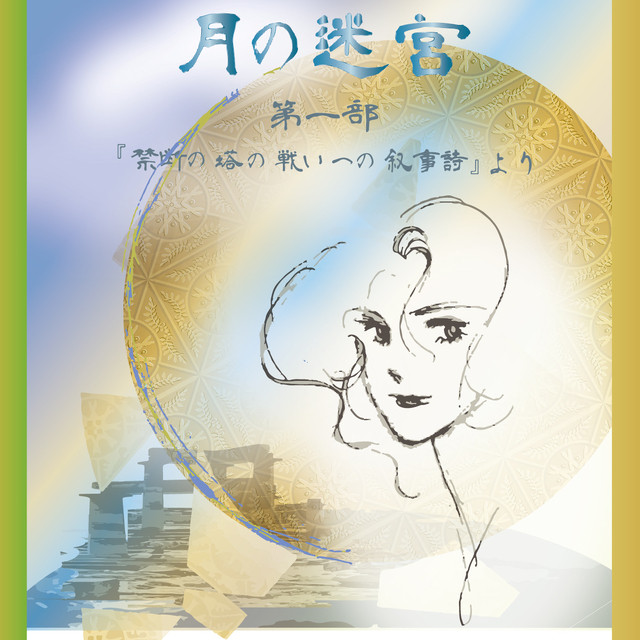第27話 外伝 その五 『精霊の樹』②
文字数 1,583文字
そしてその実が食べ頃になった頃、部族の者達は皆で神々の賜物を味わうことにした。
最初にまず、長老の一人が食べてみることにした。長老は艶々としてズッシリとして見るからに美味しそうな果実を手に取り、一斉に注がれる視線の中やや勿体ぶって一口齧って見せた。
「うう~ん・・」
そう言って、目を細めて美味しそうに味わっていたが・・。
「・・こ、これは・・!」
突然、そう言って、急いで吐き出した。
「こ、これは、食べてはいかん!」
「毒か・・?!」
「不味いのか?」
「い、いや。美味い。し、信じられぬくらい・・」
「じゃあ・・何でだ・・」
「そんなこと言って、後で自分だけ、こっそり食べるつもりか」
「なら、自分で食べてみろ・・わしの言う意味がわかる・・」
その言葉に皆、一斉に果実を手に取り一齧りした。暫く口の中で味わっていたが・・皆、慌てて吐き出した。
「こ・・これは・・」
「確かに、長老の言いなさる通りだ。これは・・」
「・・ホントに・・聖なる果実だ」
「ああ・・神様の喰いもんだ」
「・・天から・・この地のために贈られたもんだな・・」
果たして信心深き古の民が何ゆえ、そう断じたのかは不明ながら・・以来、『精霊の森』より流れ着いたその樹の赤い果実は決して食べられることはなく、天と地に捧げられた。
そしてその熟して落ちた果実の与える滋養のゆえか、この地は深く耕す必要もなく、毎年豊かな収穫を与える豊穣なる大地へと変わっていった。
そしてこの高台の地を愛でたように『聖なる樹』は更なる株を増やし、やがてその実を食べた鳥達が毎年、遥か『精霊の森』へと飛来し、運んで来た果実の種を落とした。
その種が芽を出し、若木に育ち、やがて赤い実を付け・・再び蘇った精霊の大樹が全ての森を養い、精霊達もその本来の活力と長い生命を保つようになった。
その『精霊の樹』は、今でも歴代のリデン達が集う『太古の森』にあると謂われている・・。
『精霊の森』の至宝、その失われた赤い果実の樹を育み、長きに渡って守り続けた古のシュメリア・・この地の民。それ故、リデンと森の精霊達も今まで長らえる事が出来たのだ。
リデンがここシュメリアに赴いた、もう一つの理由がそれだった。その地とその民が苦しんでいる今、『精霊の森』の女王が正にいるべき場所こそ・・。
リデンは以後、連日、その場に通い続け、怪我や病気で臥す者等に『精霊の森』から移植した植物から抽出した香薬を与え自らの手で癒した。
最初は皆、リデンをシュラ王の妃と間違えて平伏した。しかしその内、その名で呼んでは慕うようになった。
「突然、作物・・だけじゃねえ、周り中の草木が枯れはじめてな、何も食えねえで、大勢死んだんだよ・・」
「皆、町に流れて・・でも、そのうちどこ行っても門を閉められちまって」
「だからまだ歩けるもんは次の町へ・・でも皆、どんどん倒れていってな・・」
「そのうち、都の開墾地の噂を聞いてよ・・」
「でも、ここのもんが占領してな、俺達には割り当ててもらえねエんだ」
「それもしょうがねエけどよ・・ここのもんも、周りがこんな状態じゃあな」
「何とか、端っこの方を耕してる連中もいるけどよ・・その辺りだと砂が混じっててな、何にも出来ねえっていうんだ」
「出来れば、戻りてェけどよ・・」
「・・もう・・戻れねえよな・・」
ある日の夕刻、リデンはその手に一本の苗木を携え、テラスから見える砂丘にひとり上った。
美しい夕陽が、何処までも続く波打つ砂の稜線を赤く染め上げている。
暫しの間、その光景に目をやっていたリデンは、それからその苗木を乾いた砂土に植えた・・新たな計画の証として。
目の前に、その一本の木が育ち、株を増やし・・やがて、滴るような緑の森と大地が何処までも続く幻景が浮かび上がった。
見上げると、黄昏の中、東の空に美しい月が昇ろうとしていた・・。
最初にまず、長老の一人が食べてみることにした。長老は艶々としてズッシリとして見るからに美味しそうな果実を手に取り、一斉に注がれる視線の中やや勿体ぶって一口齧って見せた。
「うう~ん・・」
そう言って、目を細めて美味しそうに味わっていたが・・。
「・・こ、これは・・!」
突然、そう言って、急いで吐き出した。
「こ、これは、食べてはいかん!」
「毒か・・?!」
「不味いのか?」
「い、いや。美味い。し、信じられぬくらい・・」
「じゃあ・・何でだ・・」
「そんなこと言って、後で自分だけ、こっそり食べるつもりか」
「なら、自分で食べてみろ・・わしの言う意味がわかる・・」
その言葉に皆、一斉に果実を手に取り一齧りした。暫く口の中で味わっていたが・・皆、慌てて吐き出した。
「こ・・これは・・」
「確かに、長老の言いなさる通りだ。これは・・」
「・・ホントに・・聖なる果実だ」
「ああ・・神様の喰いもんだ」
「・・天から・・この地のために贈られたもんだな・・」
果たして信心深き古の民が何ゆえ、そう断じたのかは不明ながら・・以来、『精霊の森』より流れ着いたその樹の赤い果実は決して食べられることはなく、天と地に捧げられた。
そしてその熟して落ちた果実の与える滋養のゆえか、この地は深く耕す必要もなく、毎年豊かな収穫を与える豊穣なる大地へと変わっていった。
そしてこの高台の地を愛でたように『聖なる樹』は更なる株を増やし、やがてその実を食べた鳥達が毎年、遥か『精霊の森』へと飛来し、運んで来た果実の種を落とした。
その種が芽を出し、若木に育ち、やがて赤い実を付け・・再び蘇った精霊の大樹が全ての森を養い、精霊達もその本来の活力と長い生命を保つようになった。
その『精霊の樹』は、今でも歴代のリデン達が集う『太古の森』にあると謂われている・・。
『精霊の森』の至宝、その失われた赤い果実の樹を育み、長きに渡って守り続けた古のシュメリア・・この地の民。それ故、リデンと森の精霊達も今まで長らえる事が出来たのだ。
リデンがここシュメリアに赴いた、もう一つの理由がそれだった。その地とその民が苦しんでいる今、『精霊の森』の女王が正にいるべき場所こそ・・。
リデンは以後、連日、その場に通い続け、怪我や病気で臥す者等に『精霊の森』から移植した植物から抽出した香薬を与え自らの手で癒した。
最初は皆、リデンをシュラ王の妃と間違えて平伏した。しかしその内、その名で呼んでは慕うようになった。
「突然、作物・・だけじゃねえ、周り中の草木が枯れはじめてな、何も食えねえで、大勢死んだんだよ・・」
「皆、町に流れて・・でも、そのうちどこ行っても門を閉められちまって」
「だからまだ歩けるもんは次の町へ・・でも皆、どんどん倒れていってな・・」
「そのうち、都の開墾地の噂を聞いてよ・・」
「でも、ここのもんが占領してな、俺達には割り当ててもらえねエんだ」
「それもしょうがねエけどよ・・ここのもんも、周りがこんな状態じゃあな」
「何とか、端っこの方を耕してる連中もいるけどよ・・その辺りだと砂が混じっててな、何にも出来ねえっていうんだ」
「出来れば、戻りてェけどよ・・」
「・・もう・・戻れねえよな・・」
ある日の夕刻、リデンはその手に一本の苗木を携え、テラスから見える砂丘にひとり上った。
美しい夕陽が、何処までも続く波打つ砂の稜線を赤く染め上げている。
暫しの間、その光景に目をやっていたリデンは、それからその苗木を乾いた砂土に植えた・・新たな計画の証として。
目の前に、その一本の木が育ち、株を増やし・・やがて、滴るような緑の森と大地が何処までも続く幻景が浮かび上がった。
見上げると、黄昏の中、東の空に美しい月が昇ろうとしていた・・。