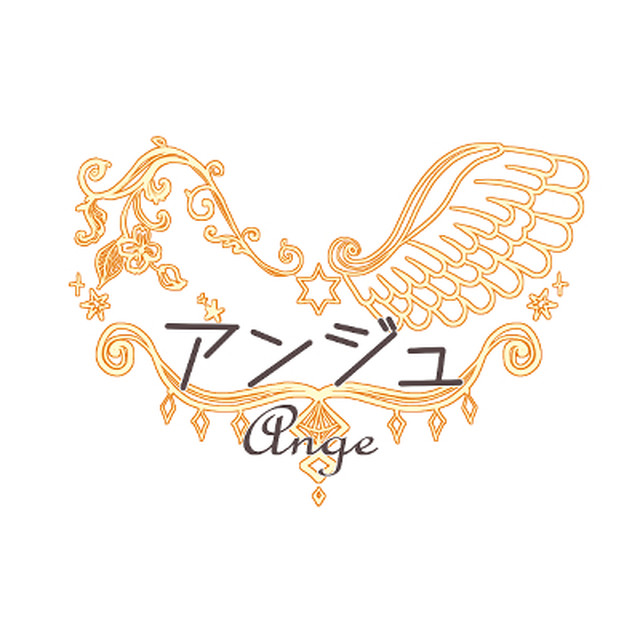【瞳さんと博巳】
文字数 5,317文字
東京都西部、八王子市郊外。
昭和五十八年七月二十一日。午前十一時十五分。
茜坂「総合」病院。
がんを抱える人々の最後の砦。
大戦前からある、打ちっぱなしコンクリート造の、古い病院。
戦争の機銃掃射の弾痕までその外壁に纏った、本当に古い病院。
増改築に増改築を重ねた山の中にあるその建物は、まるで迷路だ。
その病棟は、ツタに覆われて、廃墟みたいにも見える。
でも、その病室はとても清潔で綺麗だ。
古い建物なのにネズミ一匹見かけたことは無い。
窓もカーテンもいつも綺麗でぴかぴか。
患者さんを大事にしてくれる意思が伝わる、そんな病院だ。
その手前二百メートル坂の下。
茜坂病院前バス停にて。
十四歳の倉敷博巳は待つ。
一つ年上の、瞳さんを。
約束まで十五分あるが、今日は調子が良くて、頭痛もそんなに酷くない。
母さんに市内で買ってきて貰ったTシャツにジーンズ。
かっこいい青のスニーカー。
あんなに嫌だった医療用帽子でさえ、今日は僕の一張羅だ。
蝉がみんみん。
お日様さんさん。
夏だ。……夏だ! 青春だ。
(僕にも青春が来たんだ!)
初恋の人と、病院の皆には内緒の秘密の逃避行。
心が……踊った。
……
博巳が脳腫瘍だと疑われたのは、十二歳の時。
それまではやんちゃで、どこにでも居るような普通の小学六年生だった。
ところがある日。
急に言葉が上手く喋れなくなった。
まっすぐ歩けなくなって、転んだ。
転んだ拍子に額を切った。
ちょうど親の前で、大した傷じゃないのに、母さんは泡を食ってお医者さんに駆け込んだ。
そのお医者さんが、博巳が斜視になっているのを見て、また泡を食った。
そして、茜坂総合病院への紹介状を書いて……
気がついたら闘病生活は二年目に突入していた。
抗がん剤治療で、髪の毛が無くなって久しい。
初めは自転車で三十分以上かけて会いに来てくれた友達も、年月を重ねる度、一人、また一人と来なくなり、今では立派なひとりぼっちだ。
薬は飲む度、頭もぼんやりするし体もあちこち痛い。
気圧が下がるとそれだけで割れるように頭が痛かった。
(痛い。痛い。苦しい。もう嫌だ)
入院してからいい事なんてこれっぽっちもなかった。
(もう、死ぬのかな)
ある四月の曇りの日。
酷い頭痛の中、そう思った。
痛み止めが効かなくて。
目の奥が釘を刺されてるかのように痛くて。
頭を抱えて、整えられた清潔なベッドの上で悶絶していて。
生きることを諦めそうになっていた。
……そんな時。
「かくまって。お願い」
午前十一時十五分。
唐突に同い年位の女子が、病室に駆け込んできた。
切れ長の目。
赤いノースリーブのワンピース。
白いリボンの麦わら帽子。
背中の真ん中まである真っ黒のロングヘア。
ふんわりと香るユリの匂い。
何から何まで、凡そ、この病院に居る人間らしくない格好だ。
「へ? な、何を……」
「しー」
博巳の唇に人差し指を当てたその子は、博巳のベッドの下に潜り込んだ。
「逢沢さん? 逢沢さーん」
看護婦さん達がばたばたと廊下を早歩きしている。
「居た?」
「ううん」
「信じられない、もうそんなに歩き回れるような……」
会話は最後まで聞こえなかった。
「ありがと、ボク」
そう言って、「逢沢さん」はベッドの下から這い出て、窓を開けた。
「待ってよ、逢沢さん」
「ありゃ、なんであたしの名前知ってるの」
つるつるで綺麗な窓から身を乗り出した逢沢さんが聞く。
「いや、だって看護婦さん達言ってたし」
「あちゃあ、バレちゃったかー。……逢沢瞳だよ、よろしくね、ボク?」
そう言って手を差し出した。
「ボク、じゃないです。倉敷博巳です。こう見えても十四なんですよ」
そう言いながら差し出された手を握り返した。
逢沢さんの手は、とても──まるで生きてないみたいに──ひんやりしていた。
「ふふ、やっぱりボクだよ。あたし十五なの」
そう言って、にひひと笑った。
博巳の病室は一階だった。
それも窓はそのまま、隅々まで綺麗に整備された中庭に面している。
逢沢さんはひょいと簡単に外に出た。
「逢沢……さんは、どこに行くんです?」
「瞳、でいいよ。ボク」
またしても博巳の事をボクと呼びながら、小さな花のチャームが付いた白いお洒落なサンダルを履いた。
「瞳さん。どこへ行くんですか?」
「ちょっとそこまで、よん」
そう言うと、平然と歩き出した。
「あ、まっ、待ってください」
博巳も慌てて病院のスリッパで後を追う。
「ありゃ、ボクまで着いてくる必要はないんだけど?」
「だ、だって瞳さん、ここの患者さんなんでしょ、なら大人しくしてないと……」
「にひひ」
にやり。
瞳さんが意地悪く笑う。
「ワガハイの辞書に不可能は無いのだー!」
信じられない事に急に走り出した。
「バイちゃ! きーん!」
そして、病院のテレビでみたアニメの女の子みたいに、両手を広げた。
「あっはははははは!」
「ふ、ふふ、あはははっ」
なんだかそのハチャメチャ具合が楽しくて、博巳も一緒に走り出していた。
「ふー、ふー、さすがに無理があったわね」
二人とも、二百メートルしか走ってない。
「はあ、はあ、もう、戻らないと、はあ、はあ」
「ううん」
瞳さんが急に真顔になった。
「もう、目的地に到着、だよん」
「ええ?」
息を整えて、顔を上げると、そこはバス停だった。
(こんな所にバス停、あったっけ)
とても古くて、初めてここに来た時は存在すら気づかなかった。
サビだらけ。
字も日に焼かてしまって読み取りづらい。
微かに、「茜坂病院前」と書かれているのが見える。
「バス停が目的地って……その先はどうするんです」
「どうもしないよ。……待ってるんだ」
「待つって、何を?」
「……」
瞳さんは何も答えずに、バス停の傍に置いてあった、古ぼけた旅行カバンを手に持ち、白いシンプルレースの日傘を差した。
そのまま、何もせず何も言わず立ち止まっていしまった。
ぽかぽか。
四月だから、曇りでももうだいぶ暖かい。
気持ちいい気候ですね。
そんな気の効いたことを言えたらなあ、と少し後悔した。
静かに、十五分くらいが過ぎた。
ぶろろろろ。
バスがディーゼルの音を響かせて重そうにやって来た。
朱色とベージュの、西東京バスだ。
八王子駅北口、という行先を掲げている。
(ああ、あのバスを待っていたのか)
そう思っていたら、バスはバス停も、瞳さんもまるでそこに居ないみたいに通り過ぎた。
「え?」
博巳は立ち上がった。
「バス、なんで素通りしちゃったんですか? 瞳さん待ってたのに」
「……いいのよん。これで、いいの」
そう言うと、傘を閉じて、旅行カバンと一緒にバス停の横に置いた。
「さ、帰ろっか、ボク」
「だから、僕には博巳という名前が」
「にひひ! 似てるね!」
「何がです?」
「『ひろみ』に『ひとみ』。何かの縁かしら?」
「……縁なんですかね?」
「バイちゃ! きーん!」
「あ、待って!」
アニメのロボットの女の子になって駆け出した瞳さんを、博巳は引き摺られるように追いかけて、病室に戻った。
……
それから瞳さんは毎日、博巳のいる脳腫瘍患者用の病室を「経由して」あのバス停に向かった。
博巳は毎日、馬鹿正直に付いて行った。
そして、毎回決まって、赤のワンピース、白いリボンの麦わら帽子、白いレースの日傘、古ぼけた旅行カバンという姿になって、バスを待った。
決して停ることの無い、バスを。
ユリのやさしい匂いを纏って。
そしてバスが通過すると、日傘と旅行カバンを置き、帰っていく。
毎回毎回、何をしているのかと思うのだが……
「にひひ。女は秘密を纏って美しくなるのよ、ボク」
などと何処かの映画で聞いたことのあるような無いような台詞を言ってはぐらかされてしまい、教えてくれる気配は無い。
帰りはいつもこのセリフだ。
「バイちゃ! きーん!」
楽しかった。
瞳さんと走る、二百メートルが。
静かに立つ瞳さんとバスを待つ、十五分が。
バスが通過して、戻るまでの二百メートルが。
好きだった。
「きーん」と言って両手を広げて走る、瞳さんが。
博巳のことを「ボク」と言って、からかう、瞳さんが。
赤のノースリーブのワンピース、白いリボンの麦わら帽子、白いシンプルレースの日傘、古ぼけた旅行カバンという姿で、バス停横で凛として立つ、瞳さんが。
日常が変わった。
辛い闘病生活が、色鮮やかになった。
毎日痛くて、本当に痛くて。
ただただ辛いだけだったベッドの上での時間が、瞳さんを待つ素敵でうきうきする時間に変わった。
(瞳さんが好きだ)
倉敷博巳がそう思うまで、さして時間はかからなかった。
……
昭和五十八年七月二十日。午前十一時三十分。
いつも通り、重い躯を精一杯の力で坂を登るバスは凛として立つ瞳さんを通り過ぎた。
この後は、「バイちゃ! きーん!」だ。
また瞳さんを追いかけよう。
……その、はずだった。
「ごほっ」
瞳さんがむせはじめた。
いつも「にひひ」と笑う瞳さんだ。
どうせ唾でも喉に引っかかったんだろう。
そうとしか思ってなかった。
だから。
「ごほっ、ごぼっ、ごぼぼっ」
血を吐いて、苦しそうにしてそして……
倒れるなんて、思ってもみなかった。
「瞳さんっ?」
何度呼びかけても、こんな細い身体のどこから……と思うような鮮血を、口から噴水のように流すだけだった。
「瞳さんっ、瞳さんっ」
博巳は泣きそうになりながら、身体を揺すった。
二分程して、吐血は収まった。
ひび割れだらけで隙間から雑草が生えたアスファルトの上で、瞳さんは力無く呟いた。
「……あーあ。もう……時間みたい……」
「時間って、なんです? 明日もまた、ここに来ますよね?」
「……ううん、ひろみくん。……もう、いいの。楽しかったんだよ。あたし……だから、もう……」
(なんで、なんでそんなこと言うんだよ、瞳さん。そこは、ひろみくん、じゃなくて、ボク、でしょ。楽しかったんじゃない。楽しいんだ。今も……)
いつもみたいに「にひひ」って笑ってよ。
いつもみたいに「きーん!」って言って走ってよ。
いつもみたいに……
ぽた。ぽたた。
涙が、零れた。
(いつもみたいに……? そうか!)
「ねえ、瞳さん」
そう言って、瞳さんをおんぶした。
信じられないくらい、軽かった。
ふわり。
ユリの匂いがする。
「明日、一緒にバスに乗ろう。瞳さんが乗りたがってたバス、僕が止めるから。一緒に乗って、瞳さんが行きたがってた所に、僕が連れて行ってあげる。だから、来て。明日も。このバス停に」
「……胸が当たってるじゃん。えっちだなあ、ボクちゃんったら……」
「ち、違いますっ! 瞳さんが辛そうだったから……」
「にひひ……うん、いいよ。また、明日……また明日ね……」
病院に戻ると、看護婦さんが何人かで真っ青な顔をして駆け寄ってきた。
瞳さんをストレッチャーに乗せると、バタバタと去っていった。
そして、残った一番年上っぽい看護婦さんにえらく怒られた。
「逢沢さんがなんの病気なのか、わかって外に出たの、あなたは!」
知らないと答えると、更に怒られた。
「白血病なのよ! それももう末期の! 外なんかに出たら、なんの病気にかかるか分からないじゃないの! それなのにあなたと来たら……」
(白血病……? 末期……?)
違うよ。
だって瞳さんは、毎日外に出ていた。
毎日きーんといって走ってた。
毎日、僕を「ボク」と呼んでからかってた……
「入院してから、誰も迎えに来ない、家族すらお見舞いにも来ない。可哀想だから、色々大目に見てたけど、逆効果だったわね」
そう言うと、不機嫌な看護婦さんは博巳の元から去っていった。
(そうか。瞳さんは帰りたかったんだ。バスに乗って、お家に。帰りたかったんだ……)
(明日は、絶対に連れていこう。瞳さんを、お家に。絶対に)
……
昭和五十八年七月二十一日。午前十一時二十分。
今日も八王子は暑い。
このまま一時間も居たら熱中症になってしまうだろう。
でも、そんなのは今の博巳には関係ない。
(そろそろだ)
瞳さんが、きーん、といって、白いコンクリートの坂道を降りてくる時間だ。
いつも嬉しそうに走る、両手を広げたあの後ろ姿が目に浮かぶ。
(瞳さん。昨日。背中に当たるあなたの胸に賭けて誓ったんです。今日は貴方をお家まで連れてってあげますって。ここから二人で、出ようって。バスなら、僕が飛び出してでも、止めて見せますから……)
一分。
二分。
五分。
八分。
(あれ、瞳さんが来ない。そんな訳無い。いいよ、また明日ね。確かにそう言ったんだ。確かにそう……)
ごおおっ。
西東京バスが、倉敷博巳の前を通り過ぎた。
いつも瞳さんなんて始めからそこにいないかのように通り過ぎるのと、同じように。
ふと、バス停が気になって、見てみた。
……停らない訳だ。
「茜坂病院前」と微かに読めるそのバス停は、ほとんど朽ちて、行先もバスの系統も時刻表も読めない。
使われてない、バス停だった。
……
その日、逢沢瞳が倉敷博巳の前にいつもの笑顔で現れることは、最後までなかった。
昭和五十八年七月二十一日。午前十一時十五分。
茜坂「総合」病院。
がんを抱える人々の最後の砦。
大戦前からある、打ちっぱなしコンクリート造の、古い病院。
戦争の機銃掃射の弾痕までその外壁に纏った、本当に古い病院。
増改築に増改築を重ねた山の中にあるその建物は、まるで迷路だ。
その病棟は、ツタに覆われて、廃墟みたいにも見える。
でも、その病室はとても清潔で綺麗だ。
古い建物なのにネズミ一匹見かけたことは無い。
窓もカーテンもいつも綺麗でぴかぴか。
患者さんを大事にしてくれる意思が伝わる、そんな病院だ。
その手前二百メートル坂の下。
茜坂病院前バス停にて。
十四歳の倉敷博巳は待つ。
一つ年上の、瞳さんを。
約束まで十五分あるが、今日は調子が良くて、頭痛もそんなに酷くない。
母さんに市内で買ってきて貰ったTシャツにジーンズ。
かっこいい青のスニーカー。
あんなに嫌だった医療用帽子でさえ、今日は僕の一張羅だ。
蝉がみんみん。
お日様さんさん。
夏だ。……夏だ! 青春だ。
(僕にも青春が来たんだ!)
初恋の人と、病院の皆には内緒の秘密の逃避行。
心が……踊った。
……
博巳が脳腫瘍だと疑われたのは、十二歳の時。
それまではやんちゃで、どこにでも居るような普通の小学六年生だった。
ところがある日。
急に言葉が上手く喋れなくなった。
まっすぐ歩けなくなって、転んだ。
転んだ拍子に額を切った。
ちょうど親の前で、大した傷じゃないのに、母さんは泡を食ってお医者さんに駆け込んだ。
そのお医者さんが、博巳が斜視になっているのを見て、また泡を食った。
そして、茜坂総合病院への紹介状を書いて……
気がついたら闘病生活は二年目に突入していた。
抗がん剤治療で、髪の毛が無くなって久しい。
初めは自転車で三十分以上かけて会いに来てくれた友達も、年月を重ねる度、一人、また一人と来なくなり、今では立派なひとりぼっちだ。
薬は飲む度、頭もぼんやりするし体もあちこち痛い。
気圧が下がるとそれだけで割れるように頭が痛かった。
(痛い。痛い。苦しい。もう嫌だ)
入院してからいい事なんてこれっぽっちもなかった。
(もう、死ぬのかな)
ある四月の曇りの日。
酷い頭痛の中、そう思った。
痛み止めが効かなくて。
目の奥が釘を刺されてるかのように痛くて。
頭を抱えて、整えられた清潔なベッドの上で悶絶していて。
生きることを諦めそうになっていた。
……そんな時。
「かくまって。お願い」
午前十一時十五分。
唐突に同い年位の女子が、病室に駆け込んできた。
切れ長の目。
赤いノースリーブのワンピース。
白いリボンの麦わら帽子。
背中の真ん中まである真っ黒のロングヘア。
ふんわりと香るユリの匂い。
何から何まで、凡そ、この病院に居る人間らしくない格好だ。
「へ? な、何を……」
「しー」
博巳の唇に人差し指を当てたその子は、博巳のベッドの下に潜り込んだ。
「逢沢さん? 逢沢さーん」
看護婦さん達がばたばたと廊下を早歩きしている。
「居た?」
「ううん」
「信じられない、もうそんなに歩き回れるような……」
会話は最後まで聞こえなかった。
「ありがと、ボク」
そう言って、「逢沢さん」はベッドの下から這い出て、窓を開けた。
「待ってよ、逢沢さん」
「ありゃ、なんであたしの名前知ってるの」
つるつるで綺麗な窓から身を乗り出した逢沢さんが聞く。
「いや、だって看護婦さん達言ってたし」
「あちゃあ、バレちゃったかー。……逢沢瞳だよ、よろしくね、ボク?」
そう言って手を差し出した。
「ボク、じゃないです。倉敷博巳です。こう見えても十四なんですよ」
そう言いながら差し出された手を握り返した。
逢沢さんの手は、とても──まるで生きてないみたいに──ひんやりしていた。
「ふふ、やっぱりボクだよ。あたし十五なの」
そう言って、にひひと笑った。
博巳の病室は一階だった。
それも窓はそのまま、隅々まで綺麗に整備された中庭に面している。
逢沢さんはひょいと簡単に外に出た。
「逢沢……さんは、どこに行くんです?」
「瞳、でいいよ。ボク」
またしても博巳の事をボクと呼びながら、小さな花のチャームが付いた白いお洒落なサンダルを履いた。
「瞳さん。どこへ行くんですか?」
「ちょっとそこまで、よん」
そう言うと、平然と歩き出した。
「あ、まっ、待ってください」
博巳も慌てて病院のスリッパで後を追う。
「ありゃ、ボクまで着いてくる必要はないんだけど?」
「だ、だって瞳さん、ここの患者さんなんでしょ、なら大人しくしてないと……」
「にひひ」
にやり。
瞳さんが意地悪く笑う。
「ワガハイの辞書に不可能は無いのだー!」
信じられない事に急に走り出した。
「バイちゃ! きーん!」
そして、病院のテレビでみたアニメの女の子みたいに、両手を広げた。
「あっはははははは!」
「ふ、ふふ、あはははっ」
なんだかそのハチャメチャ具合が楽しくて、博巳も一緒に走り出していた。
「ふー、ふー、さすがに無理があったわね」
二人とも、二百メートルしか走ってない。
「はあ、はあ、もう、戻らないと、はあ、はあ」
「ううん」
瞳さんが急に真顔になった。
「もう、目的地に到着、だよん」
「ええ?」
息を整えて、顔を上げると、そこはバス停だった。
(こんな所にバス停、あったっけ)
とても古くて、初めてここに来た時は存在すら気づかなかった。
サビだらけ。
字も日に焼かてしまって読み取りづらい。
微かに、「茜坂病院前」と書かれているのが見える。
「バス停が目的地って……その先はどうするんです」
「どうもしないよ。……待ってるんだ」
「待つって、何を?」
「……」
瞳さんは何も答えずに、バス停の傍に置いてあった、古ぼけた旅行カバンを手に持ち、白いシンプルレースの日傘を差した。
そのまま、何もせず何も言わず立ち止まっていしまった。
ぽかぽか。
四月だから、曇りでももうだいぶ暖かい。
気持ちいい気候ですね。
そんな気の効いたことを言えたらなあ、と少し後悔した。
静かに、十五分くらいが過ぎた。
ぶろろろろ。
バスがディーゼルの音を響かせて重そうにやって来た。
朱色とベージュの、西東京バスだ。
八王子駅北口、という行先を掲げている。
(ああ、あのバスを待っていたのか)
そう思っていたら、バスはバス停も、瞳さんもまるでそこに居ないみたいに通り過ぎた。
「え?」
博巳は立ち上がった。
「バス、なんで素通りしちゃったんですか? 瞳さん待ってたのに」
「……いいのよん。これで、いいの」
そう言うと、傘を閉じて、旅行カバンと一緒にバス停の横に置いた。
「さ、帰ろっか、ボク」
「だから、僕には博巳という名前が」
「にひひ! 似てるね!」
「何がです?」
「『ひろみ』に『ひとみ』。何かの縁かしら?」
「……縁なんですかね?」
「バイちゃ! きーん!」
「あ、待って!」
アニメのロボットの女の子になって駆け出した瞳さんを、博巳は引き摺られるように追いかけて、病室に戻った。
……
それから瞳さんは毎日、博巳のいる脳腫瘍患者用の病室を「経由して」あのバス停に向かった。
博巳は毎日、馬鹿正直に付いて行った。
そして、毎回決まって、赤のワンピース、白いリボンの麦わら帽子、白いレースの日傘、古ぼけた旅行カバンという姿になって、バスを待った。
決して停ることの無い、バスを。
ユリのやさしい匂いを纏って。
そしてバスが通過すると、日傘と旅行カバンを置き、帰っていく。
毎回毎回、何をしているのかと思うのだが……
「にひひ。女は秘密を纏って美しくなるのよ、ボク」
などと何処かの映画で聞いたことのあるような無いような台詞を言ってはぐらかされてしまい、教えてくれる気配は無い。
帰りはいつもこのセリフだ。
「バイちゃ! きーん!」
楽しかった。
瞳さんと走る、二百メートルが。
静かに立つ瞳さんとバスを待つ、十五分が。
バスが通過して、戻るまでの二百メートルが。
好きだった。
「きーん」と言って両手を広げて走る、瞳さんが。
博巳のことを「ボク」と言って、からかう、瞳さんが。
赤のノースリーブのワンピース、白いリボンの麦わら帽子、白いシンプルレースの日傘、古ぼけた旅行カバンという姿で、バス停横で凛として立つ、瞳さんが。
日常が変わった。
辛い闘病生活が、色鮮やかになった。
毎日痛くて、本当に痛くて。
ただただ辛いだけだったベッドの上での時間が、瞳さんを待つ素敵でうきうきする時間に変わった。
(瞳さんが好きだ)
倉敷博巳がそう思うまで、さして時間はかからなかった。
……
昭和五十八年七月二十日。午前十一時三十分。
いつも通り、重い躯を精一杯の力で坂を登るバスは凛として立つ瞳さんを通り過ぎた。
この後は、「バイちゃ! きーん!」だ。
また瞳さんを追いかけよう。
……その、はずだった。
「ごほっ」
瞳さんがむせはじめた。
いつも「にひひ」と笑う瞳さんだ。
どうせ唾でも喉に引っかかったんだろう。
そうとしか思ってなかった。
だから。
「ごほっ、ごぼっ、ごぼぼっ」
血を吐いて、苦しそうにしてそして……
倒れるなんて、思ってもみなかった。
「瞳さんっ?」
何度呼びかけても、こんな細い身体のどこから……と思うような鮮血を、口から噴水のように流すだけだった。
「瞳さんっ、瞳さんっ」
博巳は泣きそうになりながら、身体を揺すった。
二分程して、吐血は収まった。
ひび割れだらけで隙間から雑草が生えたアスファルトの上で、瞳さんは力無く呟いた。
「……あーあ。もう……時間みたい……」
「時間って、なんです? 明日もまた、ここに来ますよね?」
「……ううん、ひろみくん。……もう、いいの。楽しかったんだよ。あたし……だから、もう……」
(なんで、なんでそんなこと言うんだよ、瞳さん。そこは、ひろみくん、じゃなくて、ボク、でしょ。楽しかったんじゃない。楽しいんだ。今も……)
いつもみたいに「にひひ」って笑ってよ。
いつもみたいに「きーん!」って言って走ってよ。
いつもみたいに……
ぽた。ぽたた。
涙が、零れた。
(いつもみたいに……? そうか!)
「ねえ、瞳さん」
そう言って、瞳さんをおんぶした。
信じられないくらい、軽かった。
ふわり。
ユリの匂いがする。
「明日、一緒にバスに乗ろう。瞳さんが乗りたがってたバス、僕が止めるから。一緒に乗って、瞳さんが行きたがってた所に、僕が連れて行ってあげる。だから、来て。明日も。このバス停に」
「……胸が当たってるじゃん。えっちだなあ、ボクちゃんったら……」
「ち、違いますっ! 瞳さんが辛そうだったから……」
「にひひ……うん、いいよ。また、明日……また明日ね……」
病院に戻ると、看護婦さんが何人かで真っ青な顔をして駆け寄ってきた。
瞳さんをストレッチャーに乗せると、バタバタと去っていった。
そして、残った一番年上っぽい看護婦さんにえらく怒られた。
「逢沢さんがなんの病気なのか、わかって外に出たの、あなたは!」
知らないと答えると、更に怒られた。
「白血病なのよ! それももう末期の! 外なんかに出たら、なんの病気にかかるか分からないじゃないの! それなのにあなたと来たら……」
(白血病……? 末期……?)
違うよ。
だって瞳さんは、毎日外に出ていた。
毎日きーんといって走ってた。
毎日、僕を「ボク」と呼んでからかってた……
「入院してから、誰も迎えに来ない、家族すらお見舞いにも来ない。可哀想だから、色々大目に見てたけど、逆効果だったわね」
そう言うと、不機嫌な看護婦さんは博巳の元から去っていった。
(そうか。瞳さんは帰りたかったんだ。バスに乗って、お家に。帰りたかったんだ……)
(明日は、絶対に連れていこう。瞳さんを、お家に。絶対に)
……
昭和五十八年七月二十一日。午前十一時二十分。
今日も八王子は暑い。
このまま一時間も居たら熱中症になってしまうだろう。
でも、そんなのは今の博巳には関係ない。
(そろそろだ)
瞳さんが、きーん、といって、白いコンクリートの坂道を降りてくる時間だ。
いつも嬉しそうに走る、両手を広げたあの後ろ姿が目に浮かぶ。
(瞳さん。昨日。背中に当たるあなたの胸に賭けて誓ったんです。今日は貴方をお家まで連れてってあげますって。ここから二人で、出ようって。バスなら、僕が飛び出してでも、止めて見せますから……)
一分。
二分。
五分。
八分。
(あれ、瞳さんが来ない。そんな訳無い。いいよ、また明日ね。確かにそう言ったんだ。確かにそう……)
ごおおっ。
西東京バスが、倉敷博巳の前を通り過ぎた。
いつも瞳さんなんて始めからそこにいないかのように通り過ぎるのと、同じように。
ふと、バス停が気になって、見てみた。
……停らない訳だ。
「茜坂病院前」と微かに読めるそのバス停は、ほとんど朽ちて、行先もバスの系統も時刻表も読めない。
使われてない、バス停だった。
……
その日、逢沢瞳が倉敷博巳の前にいつもの笑顔で現れることは、最後までなかった。