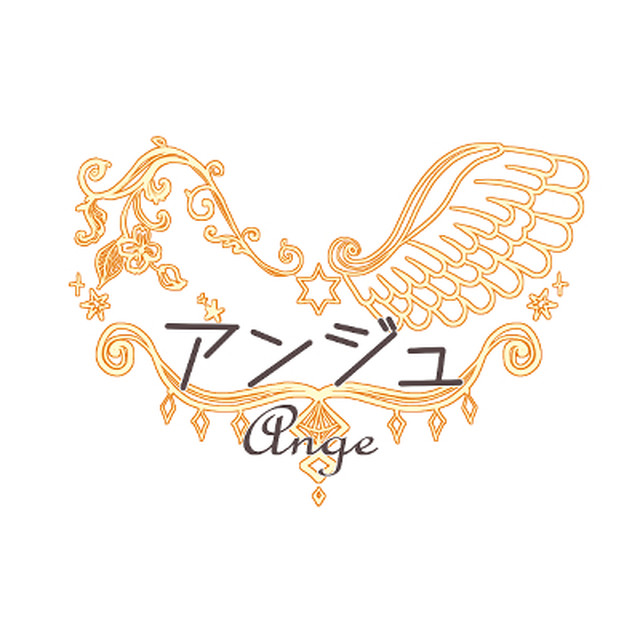【或る少年と或る呼び声】
文字数 2,540文字
少年は、独りだった。
「それ」よりも前から独りだったが、「そのこと」があってから、前よりもずっとずっと独りになった。
……
二ヶ月後にあった手術は、成功した。
命は、助かった。
そしてその手術を以て、病院は廃院となった。
入院当初は綺麗だった病院も、退院する頃には荒れて、汚くなっていた。
それでも、最後の患者として、ユリの花束まで貰った。
ユリの花束。ユリ。ユリの匂い。
想い人が待ち合わせに来なかった翌日。
植え込みに隠してあった白いサンダルを見ていたあの日。
煙を見た。空に高く登る煙を。
そして、想い人にそっくりなおかっぱ頭の女の子が喪服みたいな服を着て、白い壺みたいなのを持って歩いているのを見た。
後ろには、花束を持った、その子の保護者らしい女の人。
その花束は、とてもいい匂いがした。
想い人がこれまで彼の前に現れた時いつもさせていたものと、同じ、ユリの匂い。
だから。
もうその人は、この世に居ないとわかった。
……
それから手術に成功しても、学校に復帰出来ても、独りぼっちな気がして、何をしても寂しさが頭から離れなかった。
(皮肉だなあ)
もう摘出は不可能だと言われた。
命は無いと言われた。
そんな少年に、奇跡が起きた。
命をそのままに、癌は頭から取り除くことが出来た。
でも。
この頭の中で響いて止まない孤独感は、取り除けなかった。
……
学校では、馴染めなかった。
いや、馴染まなかった。
医者になろうと決めたから。
子供を治す、医者に。
勉強を沢山しなければならない。
自分と同じ悲しみが頭の中で響く人を一人でも減らしたかった。
高校も、医学部のある大学への進学率の基準だけで選んだ。
高校入学後は、部活も恋愛もせず、ひたすら医学部に入る為に勉強に勉強を重ねた。
そうしてがむしゃらに頑張っている間は、頭の中で響く寂しさと悲しみが、薄らいだから。
誰も、傍に近寄らせるつもりはなかった。
(あの人以外、誰も傍に置いちゃダメなんだ)
誰に言われた訳でもないが、そう決めていた。
……
がむしゃらにがむしゃらを重ねて。
気がついたら、大学生になっていた。
そして医者になるための勉強が、いざ始まろうとしたその矢先。
構内の廊下で声をかけられた。
「さっきの講義、よければ教えてくれる?」
そう言って、隣に座った。
おかっぱ頭で、背が高くて、切れ長の目をしていて。
いつも黒のワンピースに白のカーディガンを着ていた。
……どことなく、雰囲気が似ていた。
自分が子供の頃に大好きだった、その人に。
「料理作るよ」
「洗濯物洗っとくね」
「お部屋、片付けとくよ」
その人は、いつの間にか少年の傍に居るようになった。
大学近くの自分の家に、いつの間にか居座るようになった。
嫌ではなかった。
むしろ、心地よかった。
ずっとずっと冷えていた心に、灯りがほんのりと灯ってくれたかのような暖かさだった。
……
ある時、その人が姉から教わった、と言って、カセットコンロと鉄板を出てきた。
小さい頃死んだお父さんから受け継いだ味だ、と言って少年の目の前で作ってくれた。
それは……お好み焼きだった。
頭に唐突にあの日のあの人の言葉が蘇った。
『特にお好み焼きが大好き! 死んだお父さんが、よく作ってくれたんだー』
『オジサンが今度作ってあげよっか? ボク』
『あたぼーよー! あたし、六歳の頃から英才教育受けてきたからね、お好み焼きの!』
「ねえ」
少年は思わず聞いた。
「そのお姉さんの名前って、瞳じゃ……」
「そうだけど? あれ、言ってたっけ……でももう何年も……」
……
「やあ、お久しぶり、ボク!」
ふわり、ユリのいい匂い。
振り返ると、その想い人が、立っていた。
「あたし、今も待ってるんだ。あの病院で。あのバス停で」
(ああ。ずっと。ずっと会いたかった)
「瞳さん。僕もそっちへ行っていいですか」
想い人は笑って、答えない。
でも少年は決めた。
(もう二度と手放さなすもんか)
「バイちゃ! きーん!」
想い人は走り出した。
(ああ、待って。僕も行きます。今、行きます)
走った。
自分の部屋の扉を開けて。
ぐんぐん走った。
二十三区にあるはずの家なのに、外は山だ。
夜ご飯の時間だったはずなのに、外は昼だ。
(この山、この坂道、僕は知っている。この坂道を下った先に、バス停があるんだ。そこに居るんだ。大好きな……瞳さんが)
茜坂病院前。
バス停に着いた。
でも、想い人……瞳さんがいない。
少年は、その場に座った。
待つことにした。
ずっと瞳さんが、そうしていたように。
みーんみんみん。
蝉が大合唱だ。
七月の太陽が、木漏れ日が眩しい。
夏の山の匂いが新鮮だ。
懐かしい。
全てが懐かしさで溢れている。
(早く会いたい。瞳さんに、早く会いたい)
『倉敷くん、倉敷くん!』
ふと、誰かが読んでいる声がした。
『いつからです?』
『さっき、晩ご飯を食べようとしたら……』
『何か思い当たることは? 本人から何か聞いてますか?』
『わかりません……あ、子供の頃脳腫瘍があったって……そう言っていました』
『あなた、お名前は? この人との関係は?』
『愛です。……岩崎愛です……この人の……』
(岩崎……愛……? 誰だっけ……何かとても大切な……大切な人だった気がする)
「あら、ボク」
後ろから声がした。
(瞳さんだ!)
振り返る。
手でぱたぱたと扇いで見せながら、瞳さんが笑っている。
「こんな暑い日に、こんな所でなにやってるの?」
「会いた……かったです……ずっと」
「およー、どしたん? どして泣いてるの? なんか悲しいことあったん? あ、そだ、オジサンが今度お好み焼き作ってあげるからさ……だから泣くなよう、ボクー」
泣いている小さい子を見つけた時のように、瞳さんがしゃがみ込んで困った顔をしている。
(それでも、構わない。ずっと、何年も、何年も会いたかったんだ)
少年は泣き続けた。
『倉敷くん、目を覚ましてよ……倉敷くん……』
『倉敷くん……あのね、わたしね……倉敷くんのこと……』
倉敷博巳は、決めた。
僕には瞳さんがいる、他には何も要らない、と。
ずっと呼びかける声には、聞こえないフリをしよう、と。
そう、決めてしまった。
「それ」よりも前から独りだったが、「そのこと」があってから、前よりもずっとずっと独りになった。
……
二ヶ月後にあった手術は、成功した。
命は、助かった。
そしてその手術を以て、病院は廃院となった。
入院当初は綺麗だった病院も、退院する頃には荒れて、汚くなっていた。
それでも、最後の患者として、ユリの花束まで貰った。
ユリの花束。ユリ。ユリの匂い。
想い人が待ち合わせに来なかった翌日。
植え込みに隠してあった白いサンダルを見ていたあの日。
煙を見た。空に高く登る煙を。
そして、想い人にそっくりなおかっぱ頭の女の子が喪服みたいな服を着て、白い壺みたいなのを持って歩いているのを見た。
後ろには、花束を持った、その子の保護者らしい女の人。
その花束は、とてもいい匂いがした。
想い人がこれまで彼の前に現れた時いつもさせていたものと、同じ、ユリの匂い。
だから。
もうその人は、この世に居ないとわかった。
……
それから手術に成功しても、学校に復帰出来ても、独りぼっちな気がして、何をしても寂しさが頭から離れなかった。
(皮肉だなあ)
もう摘出は不可能だと言われた。
命は無いと言われた。
そんな少年に、奇跡が起きた。
命をそのままに、癌は頭から取り除くことが出来た。
でも。
この頭の中で響いて止まない孤独感は、取り除けなかった。
……
学校では、馴染めなかった。
いや、馴染まなかった。
医者になろうと決めたから。
子供を治す、医者に。
勉強を沢山しなければならない。
自分と同じ悲しみが頭の中で響く人を一人でも減らしたかった。
高校も、医学部のある大学への進学率の基準だけで選んだ。
高校入学後は、部活も恋愛もせず、ひたすら医学部に入る為に勉強に勉強を重ねた。
そうしてがむしゃらに頑張っている間は、頭の中で響く寂しさと悲しみが、薄らいだから。
誰も、傍に近寄らせるつもりはなかった。
(あの人以外、誰も傍に置いちゃダメなんだ)
誰に言われた訳でもないが、そう決めていた。
……
がむしゃらにがむしゃらを重ねて。
気がついたら、大学生になっていた。
そして医者になるための勉強が、いざ始まろうとしたその矢先。
構内の廊下で声をかけられた。
「さっきの講義、よければ教えてくれる?」
そう言って、隣に座った。
おかっぱ頭で、背が高くて、切れ長の目をしていて。
いつも黒のワンピースに白のカーディガンを着ていた。
……どことなく、雰囲気が似ていた。
自分が子供の頃に大好きだった、その人に。
「料理作るよ」
「洗濯物洗っとくね」
「お部屋、片付けとくよ」
その人は、いつの間にか少年の傍に居るようになった。
大学近くの自分の家に、いつの間にか居座るようになった。
嫌ではなかった。
むしろ、心地よかった。
ずっとずっと冷えていた心に、灯りがほんのりと灯ってくれたかのような暖かさだった。
……
ある時、その人が姉から教わった、と言って、カセットコンロと鉄板を出てきた。
小さい頃死んだお父さんから受け継いだ味だ、と言って少年の目の前で作ってくれた。
それは……お好み焼きだった。
頭に唐突にあの日のあの人の言葉が蘇った。
『特にお好み焼きが大好き! 死んだお父さんが、よく作ってくれたんだー』
『オジサンが今度作ってあげよっか? ボク』
『あたぼーよー! あたし、六歳の頃から英才教育受けてきたからね、お好み焼きの!』
「ねえ」
少年は思わず聞いた。
「そのお姉さんの名前って、瞳じゃ……」
「そうだけど? あれ、言ってたっけ……でももう何年も……」
……
「やあ、お久しぶり、ボク!」
ふわり、ユリのいい匂い。
振り返ると、その想い人が、立っていた。
「あたし、今も待ってるんだ。あの病院で。あのバス停で」
(ああ。ずっと。ずっと会いたかった)
「瞳さん。僕もそっちへ行っていいですか」
想い人は笑って、答えない。
でも少年は決めた。
(もう二度と手放さなすもんか)
「バイちゃ! きーん!」
想い人は走り出した。
(ああ、待って。僕も行きます。今、行きます)
走った。
自分の部屋の扉を開けて。
ぐんぐん走った。
二十三区にあるはずの家なのに、外は山だ。
夜ご飯の時間だったはずなのに、外は昼だ。
(この山、この坂道、僕は知っている。この坂道を下った先に、バス停があるんだ。そこに居るんだ。大好きな……瞳さんが)
茜坂病院前。
バス停に着いた。
でも、想い人……瞳さんがいない。
少年は、その場に座った。
待つことにした。
ずっと瞳さんが、そうしていたように。
みーんみんみん。
蝉が大合唱だ。
七月の太陽が、木漏れ日が眩しい。
夏の山の匂いが新鮮だ。
懐かしい。
全てが懐かしさで溢れている。
(早く会いたい。瞳さんに、早く会いたい)
『倉敷くん、倉敷くん!』
ふと、誰かが読んでいる声がした。
『いつからです?』
『さっき、晩ご飯を食べようとしたら……』
『何か思い当たることは? 本人から何か聞いてますか?』
『わかりません……あ、子供の頃脳腫瘍があったって……そう言っていました』
『あなた、お名前は? この人との関係は?』
『愛です。……岩崎愛です……この人の……』
(岩崎……愛……? 誰だっけ……何かとても大切な……大切な人だった気がする)
「あら、ボク」
後ろから声がした。
(瞳さんだ!)
振り返る。
手でぱたぱたと扇いで見せながら、瞳さんが笑っている。
「こんな暑い日に、こんな所でなにやってるの?」
「会いた……かったです……ずっと」
「およー、どしたん? どして泣いてるの? なんか悲しいことあったん? あ、そだ、オジサンが今度お好み焼き作ってあげるからさ……だから泣くなよう、ボクー」
泣いている小さい子を見つけた時のように、瞳さんがしゃがみ込んで困った顔をしている。
(それでも、構わない。ずっと、何年も、何年も会いたかったんだ)
少年は泣き続けた。
『倉敷くん、目を覚ましてよ……倉敷くん……』
『倉敷くん……あのね、わたしね……倉敷くんのこと……』
倉敷博巳は、決めた。
僕には瞳さんがいる、他には何も要らない、と。
ずっと呼びかける声には、聞こえないフリをしよう、と。
そう、決めてしまった。