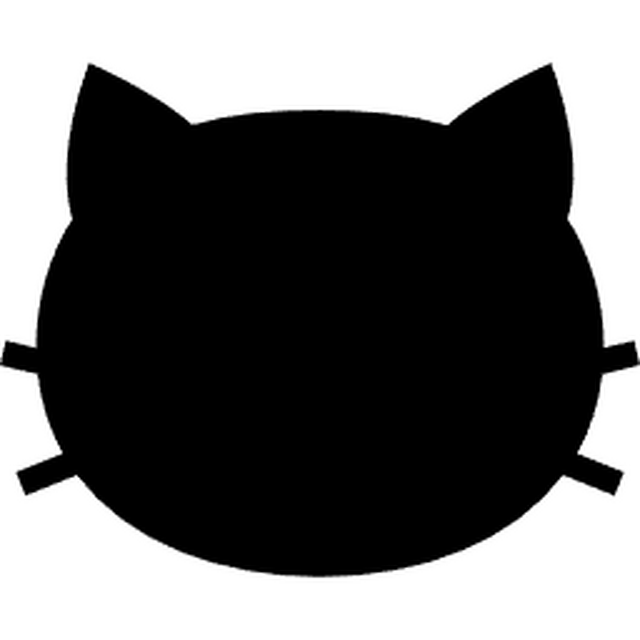#45 - 俊傑
文字数 4,252文字
*
オレは本当はギタリストになりたかった。
バンドでは花形だし、歌いながら弾けたらなおかっこいい。
中学に進学の祝いで何が欲しいか両親に聞かれた時、ギターと答えたがもちろん却下された。
ロック好きな4歳年上の姉はベースを持っていた。好きなバンドのベーシストのモデルだというそのベースをお年玉を溜めて買ったのだが、少しでも触ろうとすると烈火 のごとく怒られる。
ケチくさい両親と姉だと思い、オレはその時から反抗期を始めた。
「俊 ちゃん、ギター障りに来いよ。帰りウチ寄って」
中学1年のある日、親友の清人 に言われた。
「は?ギターどうしたん?」
「いいから、一緒帰ろうぜ」
清人 は理由を答えずただオレを誘った。どうせ良からぬ事をして手に入れたのだろうが、言われるがまま放課後彼の家に行った。
小学校に入った時から仲良くて何でも話せる親友だったが、家に招待されたのは初めてだった。
木造で2階建ての古いアパートの1階の隅が、彼と母親が住む家だった。
キッチンに畳の部屋が2つ、洗濯物は干したまま、布団は端に畳んで置いてあるだけで、決して片付いているとは言えない雑然としたその部屋に似つかわしくなく、エレキギターが置いてあった。
「順番に練習しようぜ」
そう言ってオレらは代わる代わるそのギターを手にした。
練習と言ってもまだコードもわからない、あっても読めないだろうが譜面もない、ただ憧れのギターを触ってそれらしいことをしていただけだった。
日も暮れて夕飯時になると「メシ食う?」と、言ってキッチンに行き清人 は片手鍋でお湯を沸かし、キッチンの隅に無造作に置かれている白いビニール袋から袋入りのインスタント麺を2つ取り出した。
「料理できんの?」
オレが聞くと
「コレは料理とは言わないだろ。これくらい毎日やってればできるよ」
と、清人 は笑いながら手際よく調理してオレに差し出してくれた。出来立てのその熱い麺をオレらは無言ですすった。
何も言わずに遅く帰ったので家に着くなり母親に怒られた。
「ご飯あるのに、どうするの?」
「食べればいんだろ」
反抗期のオレはボソっとつぶやいて母親の作った、煮物や焼き魚やみそ汁を食べた。
どこにでもあるような住宅街の家で、父はこの家のローンと家族のために働き、母はパートをしながら家事もして夕飯を作りオレらの帰りを待っている。夕食を済ませて猫と遊んでいた姉はしらけた顔で怒られているオレを見ている。どこにでもいるような4人家族。
ギターは買ってもらえないが、オレは恵まれている環境にいることに気がついた。それに対して感謝の気持ちが湧いてきたが、反抗期中のオレはそれを悟られないように不機嫌なまま食事を続けた。
「どこにいたの?」
と、まだ怒っている母は食事中だというのに聞く。
「清人 んち」
不愛想に答えると
「ウチに連れて来て一緒にご飯食べればよかったのに。気が利かない子ねぇ」
と、母は言った。
母はきっと清人 の家の事情を知っていた。ウチから歩いて10分くらいだから知っていても不思議はない。地元のボランティアなどに積極的に参加しているような世話好きで活動的な母は、いつも清人 を気にしていた。
小学1年生の時、清人 がお弁当を忘れたり菓子パン1つなど質素なものを持ってくるとからかわれていた。彼はイジメにも近いそれを笑顔で交わしていたが、オレはついに我慢できなくなってイジメていた奴の弁当を奪ってオレが一気に食べ、オレの弁当を清人 に食べさせた。
これが問題になり母が学校に呼び出された。まだ素直だったオレは思ったことを母に話すと母はオレを叱らずに、それ以降『清人 をウチに連れて来なさい』と言うようになり、連れてくると必ず夕飯を食べさせて、帰りに何かしら持たせていた。
そしてウチに遊びに来るたびに「俊 ちゃんの家はいいな」と、清人 は言っていた。
何故かは知らないが、清人 は母親と2人暮らしで母は仕事を掛け持ちしていてほとんど家にいない。うるさく行動を詮索してくる母親がいつもいなくていいじゃないかと思っていたが、この日オレは母に小言を言われながらも母の作った料理をウマイと思いながら食べていた。
それからオレは小遣いでギターの教則本と中古の小さなアンプを買って、ギターを持ってウチに来いと清人 を誘った。ひとしきり練習すると、母親の作った夕飯を一緒に食べた。
毎日のように一緒に練習した。けれど清人 の方が格段に上手かった。家に帰ってからも練習しているからだろうか。
それに何といってもギターを弾いている姿がサマになっていた。彼は病的なほど細身で神経質な雰囲気の端正な外見で、指使いは繊細で正確だった。
大人になった清人 がギターを奏でて、声援を浴びている姿が想像できるほどギターが似合っていた。それにこの上達ぶりからするとギタリストとして食べていけるかもしれないとまで思った。
一方オレは、リズム感は悪くないと思うし手先は器用な方だったが、彼のように鮮やかに弾くことはできなかった。練習の差なのか、持って生まれた資質なのか。
清人 がギターに愛されているようでうらやましかった。
「1日100円で貸してあげるよ」
姉が突然ベースに触る事を許してくれた。1本のギターを代わる代わる演奏しているオレ達を気の毒に思ったのか。それ以前にきっと好きなバンドが変わってそのベースに思い入れがなくなったのだろう。実際、レンタル料は取られなかったがオレはベースに集中した。ギターはどんなに頑張っても清人 にかなう気がしなかったらだ。
オレはベース、清人 はギター、2人だけのバンドを組んで毎日練習した。
中学3年生頃には学校の同級生のヴォーカルとドラムが加わり、ドラムは他のバンドとの掛け持ちだったがバンドらしい形になって、文化祭でカバー曲を演奏したこともあった。
高校生になってオレと清人 は地元のライブハウスに出入りするようになった。
そこで杏 という女の子と出逢う。オレらのバンドのドラムが掛け持ちしているもう1つのバンドでヴォーカルをやっていた。そのバンドはベースが抜けてしまって今は活動できないでいた。
彼女もロックが好きで同じ年だったのでオレ達はバンドぐるみで仲良くなった。彼女達はベーシストがなかなか見つからず、オレはたまに彼女たちの練習に付き合った。
「俊 ちゃんは背高いから、ベース似合うね」
杏はオレに言った。この時ベースをやっていてよかったと初めて思った。
ライブハウスに出られるほど上手くもないし、オリジナル曲もないがオレ達は漠然とした将来の夢を語り合ったりしていた。
杏は明るくて溌溂 としていて威勢 よく歌う。誰にでも愛想がいいタイプではないが、仲良くなると屈託 のない笑顔を向けてくれる。ロックやパンクからの影響か社会的な発言もよくしていてかっこいい一面もあった。
オレはいつの間にか彼女に惹かれていた。
だけど恥ずかしがりで奥手のオレは、そんな気持ちを打ち明けることもできずにただ彼女を思っているだけだった。
オレたちのバンドはカバーばかりで趣味の域を脱し得なかった。それに高校がバラバラになったことで集まりも悪くなっていた。
オレはともかく清人 はちゃんとしたバンドに入るべきだと思っていた。
そんなタイミングでライブハウスで何度か顔を合わせていた本格志向の人達に声をかけられた。彼らはギターとドラムとボーカルの3人でベースを探していた。
「親友のギタリスト、うまいから、一緒ならいいよ」
と、オレが持ち掛けると1度みんなで合わせてみようということになり貸スタジオに集まった。
Queen の“Keep Yourself Alive ”を演奏した。
何とも言えない快感があった。息が合ったというか、魂が呼応したというか、今まで味わったことのない一体感があった。
「イケる気がする」
誰かが言った。オレもそう思った。
ステージに立つことやデビューを目標として、DOOMSMOON というバンドを結成した。
その後すぐにヴォーカルが抜けて一時停滞するが、すぐに新しく圧倒的な歌唱力と魅力的な歌声を持つヴォーカリストが加わったことで本格的な活動がスタートした。
高校3年のとある日、みんなでライブハウスに行こうと駅で待ち合わせしていた。
1番最後に現れたのは杏 と清人 だった。
その頃の杏 はオレ達より1歩先に進んでいて、年上の女性達と新しくバンドを結成してガールズパンクバンドをやっていて、地元のライブハウスに出演するようになっていた。オレの彼女への憧れは増していた。
そして清人 がオレ達に向かって言った。
「オレ達付き合う事になったんだぁ。よろしく」
清人 の腕に杏 は腕を絡ませてにこやかな2人だった。
オレは人知れず失恋した。杏 への密かな思いは伝える事さえないまま終った。
杏 に愛されている清人 がうらやましかった。
しばらくオレはただベースに打ち込むことで杏 への気持ちに区切りをつけた。
何度かステージで前座をさせてもらえるようになって、何人かオレを好きだという女の子がいて、その中から1番仲良かった子と付き合った。
けれど数ヶ月後、わざわざ海に呼び出されてフラれた。彼女から言い寄ってきたのにだ。オレは彼女の理想とは違ったようだ。
それで結局オレにはベースしかなくてまた黙々と練習し、曲作りに専念していた。
度々新曲を作ろうとメンバーで集まった。
オレはデモの段階ではあまり深く考えず初期衝動をぶつけていたので毎回粗雑 なデモを何曲も持っていったが、清人 は寡作 であまりデモを持ってこなかった。
そんな彼がめずらしく1曲用意していた日があった。
息を飲むほど綺麗な旋律のバラードで
「清人 、どうやって思いついた?」
オレが思わず聞くと
「ん……何となく?」
彼はあっけらかんと返事した。
一同感動に震え、早速これを完成させようと作業に取り掛かった。デモの持っている繊細な雰囲気を壊さないように、オレとドラムでリズムを付け、ギター2人で起伏を付けてドラマチックな演出を作り出した。
そして最後に清人 が何となく書いた詞に作詞には才能があったヴォーカルがアドバイスをして練っていた。
出来上がった詞は壮大なラブソングで、多分、杏 のことを思って書いたのだろう。
デモがあまりにもよかったのであっという間に完成したその曲をみんなで聴いた時、オレは涙がでそうなくらい感動した。多分オレだけじゃない。
きっとこの曲を聴いた誰もがこの曲に惚れ、涙すると思った。
これだけの才能のある清人 がうらやましかった。
そしてここまで清人 に愛される杏 のこともうらやましかった。
オレは本当はギタリストになりたかった。
バンドでは花形だし、歌いながら弾けたらなおかっこいい。
中学に進学の祝いで何が欲しいか両親に聞かれた時、ギターと答えたがもちろん却下された。
ロック好きな4歳年上の姉はベースを持っていた。好きなバンドのベーシストのモデルだというそのベースをお年玉を溜めて買ったのだが、少しでも触ろうとすると
ケチくさい両親と姉だと思い、オレはその時から反抗期を始めた。
「
中学1年のある日、親友の
「は?ギターどうしたん?」
「いいから、一緒帰ろうぜ」
小学校に入った時から仲良くて何でも話せる親友だったが、家に招待されたのは初めてだった。
木造で2階建ての古いアパートの1階の隅が、彼と母親が住む家だった。
キッチンに畳の部屋が2つ、洗濯物は干したまま、布団は端に畳んで置いてあるだけで、決して片付いているとは言えない雑然としたその部屋に似つかわしくなく、エレキギターが置いてあった。
「順番に練習しようぜ」
そう言ってオレらは代わる代わるそのギターを手にした。
練習と言ってもまだコードもわからない、あっても読めないだろうが譜面もない、ただ憧れのギターを触ってそれらしいことをしていただけだった。
日も暮れて夕飯時になると「メシ食う?」と、言ってキッチンに行き
「料理できんの?」
オレが聞くと
「コレは料理とは言わないだろ。これくらい毎日やってればできるよ」
と、
何も言わずに遅く帰ったので家に着くなり母親に怒られた。
「ご飯あるのに、どうするの?」
「食べればいんだろ」
反抗期のオレはボソっとつぶやいて母親の作った、煮物や焼き魚やみそ汁を食べた。
どこにでもあるような住宅街の家で、父はこの家のローンと家族のために働き、母はパートをしながら家事もして夕飯を作りオレらの帰りを待っている。夕食を済ませて猫と遊んでいた姉はしらけた顔で怒られているオレを見ている。どこにでもいるような4人家族。
ギターは買ってもらえないが、オレは恵まれている環境にいることに気がついた。それに対して感謝の気持ちが湧いてきたが、反抗期中のオレはそれを悟られないように不機嫌なまま食事を続けた。
「どこにいたの?」
と、まだ怒っている母は食事中だというのに聞く。
「
不愛想に答えると
「ウチに連れて来て一緒にご飯食べればよかったのに。気が利かない子ねぇ」
と、母は言った。
母はきっと
小学1年生の時、
これが問題になり母が学校に呼び出された。まだ素直だったオレは思ったことを母に話すと母はオレを叱らずに、それ以降『
そしてウチに遊びに来るたびに「
何故かは知らないが、
それからオレは小遣いでギターの教則本と中古の小さなアンプを買って、ギターを持ってウチに来いと
毎日のように一緒に練習した。けれど
それに何といってもギターを弾いている姿がサマになっていた。彼は病的なほど細身で神経質な雰囲気の端正な外見で、指使いは繊細で正確だった。
大人になった
一方オレは、リズム感は悪くないと思うし手先は器用な方だったが、彼のように鮮やかに弾くことはできなかった。練習の差なのか、持って生まれた資質なのか。
「1日100円で貸してあげるよ」
姉が突然ベースに触る事を許してくれた。1本のギターを代わる代わる演奏しているオレ達を気の毒に思ったのか。それ以前にきっと好きなバンドが変わってそのベースに思い入れがなくなったのだろう。実際、レンタル料は取られなかったがオレはベースに集中した。ギターはどんなに頑張っても
オレはベース、
中学3年生頃には学校の同級生のヴォーカルとドラムが加わり、ドラムは他のバンドとの掛け持ちだったがバンドらしい形になって、文化祭でカバー曲を演奏したこともあった。
高校生になってオレと
そこで
彼女もロックが好きで同じ年だったのでオレ達はバンドぐるみで仲良くなった。彼女達はベーシストがなかなか見つからず、オレはたまに彼女たちの練習に付き合った。
「
杏はオレに言った。この時ベースをやっていてよかったと初めて思った。
ライブハウスに出られるほど上手くもないし、オリジナル曲もないがオレ達は漠然とした将来の夢を語り合ったりしていた。
杏は明るくて
オレはいつの間にか彼女に惹かれていた。
だけど恥ずかしがりで奥手のオレは、そんな気持ちを打ち明けることもできずにただ彼女を思っているだけだった。
オレたちのバンドはカバーばかりで趣味の域を脱し得なかった。それに高校がバラバラになったことで集まりも悪くなっていた。
オレはともかく
そんなタイミングでライブハウスで何度か顔を合わせていた本格志向の人達に声をかけられた。彼らはギターとドラムとボーカルの3人でベースを探していた。
「親友のギタリスト、うまいから、一緒ならいいよ」
と、オレが持ち掛けると1度みんなで合わせてみようということになり貸スタジオに集まった。
何とも言えない快感があった。息が合ったというか、魂が呼応したというか、今まで味わったことのない一体感があった。
「イケる気がする」
誰かが言った。オレもそう思った。
ステージに立つことやデビューを目標として、
その後すぐにヴォーカルが抜けて一時停滞するが、すぐに新しく圧倒的な歌唱力と魅力的な歌声を持つヴォーカリストが加わったことで本格的な活動がスタートした。
高校3年のとある日、みんなでライブハウスに行こうと駅で待ち合わせしていた。
1番最後に現れたのは
その頃の
そして
「オレ達付き合う事になったんだぁ。よろしく」
オレは人知れず失恋した。
しばらくオレはただベースに打ち込むことで
何度かステージで前座をさせてもらえるようになって、何人かオレを好きだという女の子がいて、その中から1番仲良かった子と付き合った。
けれど数ヶ月後、わざわざ海に呼び出されてフラれた。彼女から言い寄ってきたのにだ。オレは彼女の理想とは違ったようだ。
それで結局オレにはベースしかなくてまた黙々と練習し、曲作りに専念していた。
度々新曲を作ろうとメンバーで集まった。
オレはデモの段階ではあまり深く考えず初期衝動をぶつけていたので毎回
そんな彼がめずらしく1曲用意していた日があった。
息を飲むほど綺麗な旋律のバラードで
「
オレが思わず聞くと
「ん……何となく?」
彼はあっけらかんと返事した。
一同感動に震え、早速これを完成させようと作業に取り掛かった。デモの持っている繊細な雰囲気を壊さないように、オレとドラムでリズムを付け、ギター2人で起伏を付けてドラマチックな演出を作り出した。
そして最後に
出来上がった詞は壮大なラブソングで、多分、
デモがあまりにもよかったのであっという間に完成したその曲をみんなで聴いた時、オレは涙がでそうなくらい感動した。多分オレだけじゃない。
きっとこの曲を聴いた誰もがこの曲に惚れ、涙すると思った。
これだけの才能のある
そしてここまで