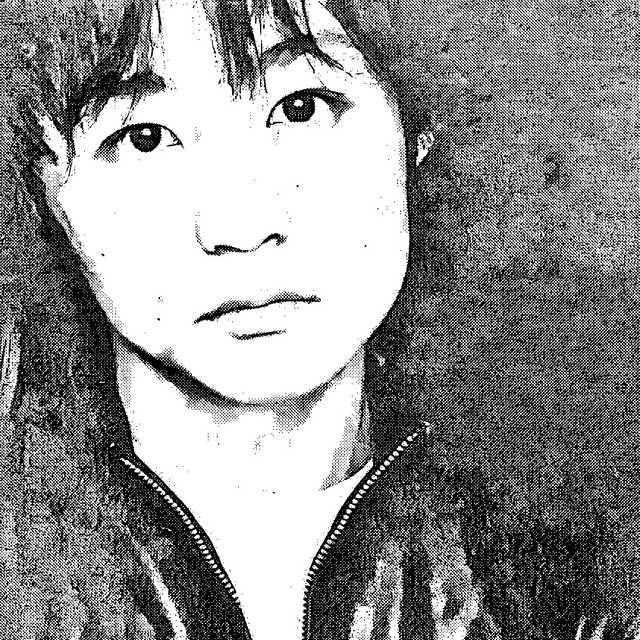第3章 (1) はじめての告白
文字数 3,038文字
セットしておいた腕時計のアラームで目を覚ました。午前五時三十五分。大きく伸びをして起き上がる。イテテ、予想通り全身筋肉痛になっている。今日一日しんどい旅になりそうだが、とりあえず俺がおっさんじゃないことは証明された。
「おはよう」俺のベッドの二階からモトが顔を出した。
「うん、おはよ。ハユはまだ寝てる?」
モトが隣のベッドの二階に目を向ける。
「大口開けてよだれ垂らして寝てるよ。あのアラーム結構うるさいのにね」
ハユのイメージ通りの寝起きの悪さに少し可笑しくなった。
「朝飯六時からだから、それまでに支度しようよ」
「この自由人はどうする?」
「一応起こしてみよう」
自分のベッドから立ち上がり、梯子を三段登ってハユのベッドを覗きこんだ。
「ハユ、もう朝だよ。五時四十分。六時から飯だからそれまでに支度して行こうよ」
ハユの肩を揺すると、ハユは一瞬だけ片目を開けて俺の顔を見て、「頼む、朝飯まで寝かせて。ごめん」と言ってまた目を閉じてしまった。既に寝息を立てている。あまりしつこくして機嫌を損ねるのも面倒なので、とりあえず俺とモトだけ身支度をすることにした。
荷物を整理して、洗面所に行って顔を洗って髪をセットしているとあっという間に六時二分前になっていた。慌てて部屋に戻った。ハユはまだ寝ている。
「河原田、もう時間だから俺だけとりあえず先に行っとくよ。俺が起こすと多分怒るから本橋起こして連れてきて」
モトはそう言うと一人で先に食堂に向かった。モトも結構気を使ってるんだな。ハユはそういうの気が付いてないだろうけど……
「ハユ、目ヤニがすごいから顔を洗ってきなよ」
愚図るハユを何とか説得して起こして、顔を洗うように言った。
「俺の風呂で使った小さいタオル濡らして持ってきて」
俺が言ったことは無視をして、ハユはまた横になってしまった。人使いの荒いヤツだと思いながらも、ハンガーにかけてあったハユのタオルを手に取り、渋々洗面所に向かった。後ろからハユが更にリクエストをしてきた。
「お湯でしぼれよ」
どこまで王様気質なんだコイツは。
「あー気持ちいい! おお河原田おはよう。腹が減ったな。早く食堂行こうぜ」
ハユは、俺が持って来た濡れタオルで顔を拭くと、途端に元気になってそう言った。
俺たちが食堂に行くと、驚くべきことに、モトが女子高生三人組と同じテーブルで食事をしていた。
「おう、こっちこっち」モトがドヤ顔で俺たちを呼んでいる。えっ、なんでこんなことに?モト、すごいよ!あまりの急展開に胸の鼓動が高鳴ってきたが、ばれないように極力自然に「おはようございまーす」と挨拶をしながら席に着いた。
「挨拶したら、一緒にいた人たちはって聞かれて、まだ寝てるって言ったらじゃあ一緒に食べませんかって誘ってくれたんだ」モトがこうなった成り行きを説明した。
「かわいー。超寝癖ついてるー」
ハユの寝癖を見て女の子たちが母性本能をくすぐられているようだ。わざわざ早起きして髪をセットした俺は何なんだ。こんなやつ起こさずに置いてくればよかったと思っていると、俺のお気に入りのマダイさん(仮名)が「キミ、女の子みたいな顔してるね~」と話しかけてきた。これまでもたくさんの人に女の子みたいな顔だと言われてきた。言った人たちは褒めているつもりなのだが、男らしくなりたいと思っている俺にとっては全然嬉しくない。マダイさん(仮名)も俺のことを男として見ていないようだ。一瞬、『実は、昨日あなたのおっぱいを見て勃起したんですよ』とでも言えば男だと認めてもらえるかと思ったが、そんなことを言えるはずもなく、「いやあ、それほどでも」とよくわからない返答をしてしまった。テストなら零点だ。
それにしても、モトが一人で女の子たちと一緒にご飯を食べられる度胸があったことに驚いた。高校生のお姉さんがいるから免疫があったのだろうか。俺には二つ下の妹がいるが、妹が連れてきた友達とおやつを一緒に食べるのさえ躊躇してしまう。
「ああ名古屋の子なんだー、俺名古屋に親戚がいて時々行くよー」
ハユがイラッとするくらい親し気に話している。どうやら女の子たちは名古屋市内の高校に通っているらしい。今回は友達三人で旅行に行きたくて親に言ったら、名古屋から比較的近くて周りに繁華街の無いこのユースホステルに行くなら良いと言われここに二泊することになったそうだ。でも実際に来てみたら本当に何もないので海で泳ぐくらいしかないということだった。俺は密かに彼女たちのご両親に感謝した。娘を危険に晒したくない一心でここでの宿泊を提案したであろうに、親御さんの愛情のおかげで俺たちはおっぱいを見ることができたのだ。
俺たちが浜松から自転車で来て、今日は岡崎市のキャンプ場まで移動することをモトが説明した。
「ざんねんーっ、今日もいるなら一緒に海に行ったりしたかったのになあ」クロダイさん(仮名)が言った。
「マジで! じゃあもう一泊しようかなあ」ハユが悩みだした。あの表情は話を合わせているだけじゃなく本気だろう。俺もオクテな自分を棚に上げて、マダイさん(仮名)とのアバンチュールを脳内に描き、なんならそれもありだと思いかけた時、モトが苛立った口調で言った。
「本橋、一度立てた計画を変えるのはダメだ。キャンプ場の人とか色んな人に迷惑がかかる」
モトの断固とした態度に、あり得ない奇跡に期待しようとしていた自分が急に恥ずかしくなった。「そうだよハユ、今日は予定通りにキャンプ場に行こう」
その後も、モトとハユは女の子たちとの会話を楽しみながら、俺はそれを眺めつつ時々会話を振られてドギマギしながらも六人でゆっくりと朝食を食べた。
朝食後、俺たちは予定を大幅に遅れて、七時半にユースホステルを出発した。ユースホステルの入り口まで女の子たちが見送りに来てくれた。
「いってらっしゃーい」
なんかいい感じだ。結婚して奥さんに毎朝見送られるのはこんな気分なんだろうか。かわいい奥さんが毎朝チュッとキスしてくれて「いってきます」と言って家を出る俺。マダイさん(仮名)みたいな奥さんがいいなあ……と妄想していると、モトがマゴチさん(仮名)の前に一歩足を踏み出した。
「もしまたどこかで会えたらデートしてください!」
ど、どうしたんだモト! お前は俺と同類のオクテじゃなかったのか? モトの突然の告白に皆の視線がマゴチさん(仮名)に集中した。
「うん、いいよ」
照れ笑いのマゴチさん(仮名)とモトの間にいい感じの空気が漂っている。
「ありがとう。じゃあまた!」照れ臭かったのか、突然モトが自転車に飛び乗って走り出した。えっ? そんな別れ方?!
「おい本山! ちょっと待てよ! ……チッ、仕方ねえな。じゃあまたね。バイバーイ」ハユも慌てて女子たちに別れを告げてモトの後ろを追った。
「あの、それじゃあ俺も」
我ながらきまりの悪い旅立ちに呆れながら、モトたちを追いかけた。
モトは猛スピードで走り続け、一キロ程進んだ自動販売機の前で止まった。そしてリュックから財布を取り出し、自販機で俺が大好きなレモンティーを三本買って、俺とハユに配った。
「どうせもう会うこともないと思って頑張って言ってみた。初めて女をデートに誘った。俺の奢りだ。まあ飲んでくれ」モトは清々しい笑顔でそう言った。俺たちはレモンティーで乾杯をした。大好きなレモンティーが普段より酸っぱく感じたのは、俺がモトに先を越された気がしたからだろう。
「おはよう」俺のベッドの二階からモトが顔を出した。
「うん、おはよ。ハユはまだ寝てる?」
モトが隣のベッドの二階に目を向ける。
「大口開けてよだれ垂らして寝てるよ。あのアラーム結構うるさいのにね」
ハユのイメージ通りの寝起きの悪さに少し可笑しくなった。
「朝飯六時からだから、それまでに支度しようよ」
「この自由人はどうする?」
「一応起こしてみよう」
自分のベッドから立ち上がり、梯子を三段登ってハユのベッドを覗きこんだ。
「ハユ、もう朝だよ。五時四十分。六時から飯だからそれまでに支度して行こうよ」
ハユの肩を揺すると、ハユは一瞬だけ片目を開けて俺の顔を見て、「頼む、朝飯まで寝かせて。ごめん」と言ってまた目を閉じてしまった。既に寝息を立てている。あまりしつこくして機嫌を損ねるのも面倒なので、とりあえず俺とモトだけ身支度をすることにした。
荷物を整理して、洗面所に行って顔を洗って髪をセットしているとあっという間に六時二分前になっていた。慌てて部屋に戻った。ハユはまだ寝ている。
「河原田、もう時間だから俺だけとりあえず先に行っとくよ。俺が起こすと多分怒るから本橋起こして連れてきて」
モトはそう言うと一人で先に食堂に向かった。モトも結構気を使ってるんだな。ハユはそういうの気が付いてないだろうけど……
「ハユ、目ヤニがすごいから顔を洗ってきなよ」
愚図るハユを何とか説得して起こして、顔を洗うように言った。
「俺の風呂で使った小さいタオル濡らして持ってきて」
俺が言ったことは無視をして、ハユはまた横になってしまった。人使いの荒いヤツだと思いながらも、ハンガーにかけてあったハユのタオルを手に取り、渋々洗面所に向かった。後ろからハユが更にリクエストをしてきた。
「お湯でしぼれよ」
どこまで王様気質なんだコイツは。
「あー気持ちいい! おお河原田おはよう。腹が減ったな。早く食堂行こうぜ」
ハユは、俺が持って来た濡れタオルで顔を拭くと、途端に元気になってそう言った。
俺たちが食堂に行くと、驚くべきことに、モトが女子高生三人組と同じテーブルで食事をしていた。
「おう、こっちこっち」モトがドヤ顔で俺たちを呼んでいる。えっ、なんでこんなことに?モト、すごいよ!あまりの急展開に胸の鼓動が高鳴ってきたが、ばれないように極力自然に「おはようございまーす」と挨拶をしながら席に着いた。
「挨拶したら、一緒にいた人たちはって聞かれて、まだ寝てるって言ったらじゃあ一緒に食べませんかって誘ってくれたんだ」モトがこうなった成り行きを説明した。
「かわいー。超寝癖ついてるー」
ハユの寝癖を見て女の子たちが母性本能をくすぐられているようだ。わざわざ早起きして髪をセットした俺は何なんだ。こんなやつ起こさずに置いてくればよかったと思っていると、俺のお気に入りのマダイさん(仮名)が「キミ、女の子みたいな顔してるね~」と話しかけてきた。これまでもたくさんの人に女の子みたいな顔だと言われてきた。言った人たちは褒めているつもりなのだが、男らしくなりたいと思っている俺にとっては全然嬉しくない。マダイさん(仮名)も俺のことを男として見ていないようだ。一瞬、『実は、昨日あなたのおっぱいを見て勃起したんですよ』とでも言えば男だと認めてもらえるかと思ったが、そんなことを言えるはずもなく、「いやあ、それほどでも」とよくわからない返答をしてしまった。テストなら零点だ。
それにしても、モトが一人で女の子たちと一緒にご飯を食べられる度胸があったことに驚いた。高校生のお姉さんがいるから免疫があったのだろうか。俺には二つ下の妹がいるが、妹が連れてきた友達とおやつを一緒に食べるのさえ躊躇してしまう。
「ああ名古屋の子なんだー、俺名古屋に親戚がいて時々行くよー」
ハユがイラッとするくらい親し気に話している。どうやら女の子たちは名古屋市内の高校に通っているらしい。今回は友達三人で旅行に行きたくて親に言ったら、名古屋から比較的近くて周りに繁華街の無いこのユースホステルに行くなら良いと言われここに二泊することになったそうだ。でも実際に来てみたら本当に何もないので海で泳ぐくらいしかないということだった。俺は密かに彼女たちのご両親に感謝した。娘を危険に晒したくない一心でここでの宿泊を提案したであろうに、親御さんの愛情のおかげで俺たちはおっぱいを見ることができたのだ。
俺たちが浜松から自転車で来て、今日は岡崎市のキャンプ場まで移動することをモトが説明した。
「ざんねんーっ、今日もいるなら一緒に海に行ったりしたかったのになあ」クロダイさん(仮名)が言った。
「マジで! じゃあもう一泊しようかなあ」ハユが悩みだした。あの表情は話を合わせているだけじゃなく本気だろう。俺もオクテな自分を棚に上げて、マダイさん(仮名)とのアバンチュールを脳内に描き、なんならそれもありだと思いかけた時、モトが苛立った口調で言った。
「本橋、一度立てた計画を変えるのはダメだ。キャンプ場の人とか色んな人に迷惑がかかる」
モトの断固とした態度に、あり得ない奇跡に期待しようとしていた自分が急に恥ずかしくなった。「そうだよハユ、今日は予定通りにキャンプ場に行こう」
その後も、モトとハユは女の子たちとの会話を楽しみながら、俺はそれを眺めつつ時々会話を振られてドギマギしながらも六人でゆっくりと朝食を食べた。
朝食後、俺たちは予定を大幅に遅れて、七時半にユースホステルを出発した。ユースホステルの入り口まで女の子たちが見送りに来てくれた。
「いってらっしゃーい」
なんかいい感じだ。結婚して奥さんに毎朝見送られるのはこんな気分なんだろうか。かわいい奥さんが毎朝チュッとキスしてくれて「いってきます」と言って家を出る俺。マダイさん(仮名)みたいな奥さんがいいなあ……と妄想していると、モトがマゴチさん(仮名)の前に一歩足を踏み出した。
「もしまたどこかで会えたらデートしてください!」
ど、どうしたんだモト! お前は俺と同類のオクテじゃなかったのか? モトの突然の告白に皆の視線がマゴチさん(仮名)に集中した。
「うん、いいよ」
照れ笑いのマゴチさん(仮名)とモトの間にいい感じの空気が漂っている。
「ありがとう。じゃあまた!」照れ臭かったのか、突然モトが自転車に飛び乗って走り出した。えっ? そんな別れ方?!
「おい本山! ちょっと待てよ! ……チッ、仕方ねえな。じゃあまたね。バイバーイ」ハユも慌てて女子たちに別れを告げてモトの後ろを追った。
「あの、それじゃあ俺も」
我ながらきまりの悪い旅立ちに呆れながら、モトたちを追いかけた。
モトは猛スピードで走り続け、一キロ程進んだ自動販売機の前で止まった。そしてリュックから財布を取り出し、自販機で俺が大好きなレモンティーを三本買って、俺とハユに配った。
「どうせもう会うこともないと思って頑張って言ってみた。初めて女をデートに誘った。俺の奢りだ。まあ飲んでくれ」モトは清々しい笑顔でそう言った。俺たちはレモンティーで乾杯をした。大好きなレモンティーが普段より酸っぱく感じたのは、俺がモトに先を越された気がしたからだろう。