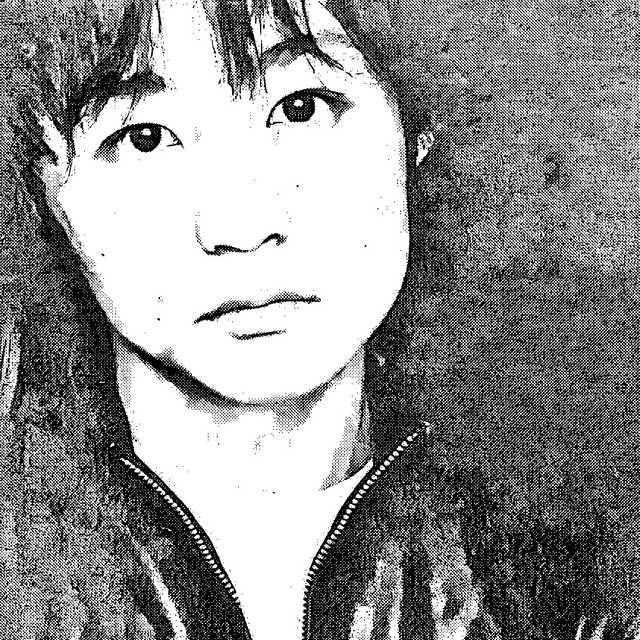終章 (3) 蘇った記憶
文字数 3,430文字
一人自転車で浜松に向かいながら、色々なことを考えた。なぜ、俺はかつて自らおもちゃを壊し、今日また楽しい時間を壊してしまったのか。物心ついた頃から、親父に怯えながら生きてきた。平和な時間は親父が突然キレることで何度も壊された。いつ静かな時間が破壊されるのかに怯えて生きていた。そして、俺自身が壊す側の人間になってしまった。
確かに俺の家庭環境は普通ではない。だからと言って、俺がこれから幸せになっていけない理由はない。道徳の授業で習った足の無いアメリカ人の少年のことを思い出した。彼は上半身だけしかない身体でスケボーに乗って楽しそうに生きていた。俺は自分の境遇が可哀想だから、今日のような態度を取ってしまうのだろうか。それは甘えなんじゃないか。殺したいくらい嫌いな親父の家に自ら帰る俺。この現状を何とかしたいと思いつつも、そのままにしているのは俺自身の意思が弱いからなんじゃないだろうか。そんなことを考えていたら、ハンドルを握る手にポツリ、ポツリと雨が降ってきた。やっぱ降ってきたか。そう思った瞬間、ザーッと土砂降りが始まった。あまりにも突然雨量が増えたので、雨宿りする間もなくずぶ濡れになった。今の気分には丁度いいか。いっそこのまま雨が降り続けて洪水になって流されて死ぬのも悪くない。このままペダルを漕ぎ続けることにした。
雨に打たれながら自転車に乗っていると、頭の中で何かがよぎった。なんだっけこの感じ、前にも経験したことがある。ムシムシした気候、雨の匂い、背中を覆う大きな影、もっと小さい頃……そうだ、今みたいな土砂降りの中、俺は自転車のサドルに座ってハンドルを握り、後ろの荷台に座った誰かが俺を包み込むようにハンドルを握ってペダルを漕いでいた。そうか、あれは近所の兄ちゃんだってヒロシに話したよな。でも、近所の兄ちゃんに乗せてもらった時にはいつも俺が後ろの荷台に座って、兄ちゃんの背中にしがみついていた。じゃああれは誰だ?
「悠紀彦、しっかりハンドル握っておけよ」
俺の脳裏にその時の声が甦った。
――― あれは親父だったんだ ―――
仮面ライダースーパー1のヘルメットを買ってもらった俺が親父に自転車に乗せてくれとねだったんだ。
「ヤッホー! Vジェットだー」
スーパー1のバイクに乗っている気分ではしゃいでいる俺を乗せて親父は近所を走ってくれた。そして雨が降った。親父は家に戻ろうと言った。
「やだ、もっと乗る。雨でもいい」
俺は駄々を捏ねた。
「よおし、じゃあとことん行くぞ!」
親父は俺のわがままを受け入れて、雨に濡れながら自転車を漕いでくれた。滅多に遊んでくれない親父が一緒に遊んでくれて嬉しかった気持ちが甦った。
一度記憶の扉を開けてしまったら、次から次へと記憶が溢れ出てきた。親父は母さんが俺を身ごもって、産んだら死んでしまうかもしれないというリスクを背負っても俺を産もうと決意して以来、大好きだった酒を止めて、毎日神社にお百度参りをしたのだと母さんが話してくれたこと。俺を寝かしつける時にこの話をよくしてくれて、
「お父さんは悠紀彦のことを世界で一番大切にしてくれてるの。お酒も大好きだったのに、それからずっと飲んでないのよ。毎日お仕事で朝が早いから悠紀彦とあんまり遊べないけど、お仕事をしないとお金がなくなって悠紀彦がご飯食べたり、洋服を買ったり、おもちゃを買ったりできなくなっちゃうでしょ。だからお父さんは悠紀彦と遊びたいのを我慢してお仕事をしているのよ。かっこいいお父さんだね」
そう嬉しそうに笑っていた。俺はこの話を聞きながら寝るのが大好きだった。当時はまだ親父の暴力も始まっていなかった。俺は何歳くらいだったのだろう……
土砂降りの中、親父と自転車に乗った後はどうしたんだっけ……家に帰ってきたあと親父と一緒に風呂に入ってから、二人でリビングでテレビを観たんだ。確か野球中継だった。そこに母さんが「これふやけちゃってるよ」と仮面ライダーのヘルメットを持って来たんだ。仮面ライダーの目の部分がステッカーで、長い間雨に打たれて、その後放置しておいたので、ふやけてボロボロになってしまったのだ。俺が雨に濡れても良いと言ったのに、まだ四歳だった俺は泣いて親父をなじった。
「お父さんのせいでスーパー1のヘルメットが壊れた。お父さんとはもう遊ばない。お父さんなんか大っ嫌い!」
親父に殴られたのはおそらくあの時が最初だった。そして、その日を境に親父はやめていた酒を飲むようになり、暴れるようになったのだ。そうだ、あの日から悪夢のような生活が始まったんだ。
親父は、俺がきっかけでまた酒を飲み始め、俺たち家族はメチャクチャになった。でも、親父は本当に家庭を壊そうとしていたのだろうか。記憶を巡っていくと、俺の態度が親父をあんな風にしてしまったのではないかと思えてくることが、次々と脳裏に甦った。
幼稚園の頃、親父が突然かくれんぼをしようと言ってきた。俺は親父のことが既に嫌いだったので「いいよ」と言って、親父に十数えさせて、自分の部屋に行ってあおり止めの鍵をかけて本を読み始めた。やがて親父は俺が鍵をかけて部屋にいることに気が付いた。
「鍵をかけるのは反則だぞー。十秒以内に出てこないと怒るからなあ」
部屋の前で、そう笑いながら言って十数えた。俺は親父が笑っていたので本気ではないと高を括っていたのだが、十数え終わった親父はドアを思いっきり引っ張って力づくで開けた。あおり止めが剥がれてドアが壊れるのを見た瞬間俺は恐怖に震え、そして薄ら笑いで近づいてくる親父に殴られた。もしかすると、親父は俺と仲直りがしたくて、頑張っていたのかもしれない。そして俺を喜ばせようとかくれんぼをしたのに、俺はすぐに鍵をかけて無視をした。
小学生になって友達の誕生会に何度も呼ばれていたので、四月生まれで一年生の時には入学したてでできなかった俺の誕生会を二年生の四月にうちで開いた。親父が料理を作ってくれて、来てくれた友達にお土産として、木製の電車キットも人数分、器用な親父が木を削って作ってくれた。
「すげえなお前のお父さん!」
友達は皆喜んでそう言ってくれた。けど、俺は親父が聞いているのを知っていてわざとこう答えた。
「全然すごくないよ。ご飯だってお母さんが作ったやつの方が美味しいし」
十歳のころ、親父が始めた小さなレストランで、生け簀の中でひっくり返って死にかけたアジがもう売り物にはできないからと、親父にアジのさばき方を教わった。
「初めてでこれだけできれば大したもんだ」
親父は目を細めていた。その日、親父がその話を常連さんにした。
「悠紀彦君、俺にもアジの叩きつくってよ」
俺は常連さんのリクエストに応えて、今度は活きの良いアジをさばいた。常連さんにも褒められて良い気分だったのを覚えている。それなのに、別の日に親父にまた違う常連さんにアジをさばいてくれと頼まれたのに「嫌だ」と言って断った。
「気分が乗らない時もあるよねえ」
常連さんは俺を庇ってくれたが、俺はあの時、親父が困れば良いと思ってわざとそんな態度を取ったのを覚えている。その夜、酔っぱらって帰ってきた親父に俺は殴られた。俺は家族が完全に壊れてしまう前に自分で壊したかったのだろうか。
俺は親父に愛されていないとずっと思ってた。今になって母さんが言っていた「お父さんを嫌いにならないでね」という意味がわかった気がした。
富士山の五合目で、親父が見本の絵を売店の店員に描き直させたあのジャガベーコン、「あのベーコンおっきくて美味そう」と俺が言ったから注文してくれたことを思い出した。
中学1年の時、親父がパチンコで取ったと言って、金のネックレスをくれたことがあった。すぐにリサイクルショップに売りに行って金に換えた。
今年の誕生日に親父にポロシャツをもらったが、一度も着ることなく後輩にあげた。
親父は確かに非常識だ。子供相手にマジでキレて大人気ないのかもしれない。愛情表現が上手くなかったのかもしれない。でも、俺のことを親父が愛しているのは確かだった。そして俺もそれに気が付いていた。でも、それを冷たく拒絶していたんだ。
何でそんなことをしてしまったのだろう。どこかで俺が親父の気持ちを受け入れていたら、俺の家族はこんな風にならなかったのかもしれない。歯車は狂ってしまった。俺は泣きながら自転車で走り続けた。
確かに俺の家庭環境は普通ではない。だからと言って、俺がこれから幸せになっていけない理由はない。道徳の授業で習った足の無いアメリカ人の少年のことを思い出した。彼は上半身だけしかない身体でスケボーに乗って楽しそうに生きていた。俺は自分の境遇が可哀想だから、今日のような態度を取ってしまうのだろうか。それは甘えなんじゃないか。殺したいくらい嫌いな親父の家に自ら帰る俺。この現状を何とかしたいと思いつつも、そのままにしているのは俺自身の意思が弱いからなんじゃないだろうか。そんなことを考えていたら、ハンドルを握る手にポツリ、ポツリと雨が降ってきた。やっぱ降ってきたか。そう思った瞬間、ザーッと土砂降りが始まった。あまりにも突然雨量が増えたので、雨宿りする間もなくずぶ濡れになった。今の気分には丁度いいか。いっそこのまま雨が降り続けて洪水になって流されて死ぬのも悪くない。このままペダルを漕ぎ続けることにした。
雨に打たれながら自転車に乗っていると、頭の中で何かがよぎった。なんだっけこの感じ、前にも経験したことがある。ムシムシした気候、雨の匂い、背中を覆う大きな影、もっと小さい頃……そうだ、今みたいな土砂降りの中、俺は自転車のサドルに座ってハンドルを握り、後ろの荷台に座った誰かが俺を包み込むようにハンドルを握ってペダルを漕いでいた。そうか、あれは近所の兄ちゃんだってヒロシに話したよな。でも、近所の兄ちゃんに乗せてもらった時にはいつも俺が後ろの荷台に座って、兄ちゃんの背中にしがみついていた。じゃああれは誰だ?
「悠紀彦、しっかりハンドル握っておけよ」
俺の脳裏にその時の声が甦った。
――― あれは親父だったんだ ―――
仮面ライダースーパー1のヘルメットを買ってもらった俺が親父に自転車に乗せてくれとねだったんだ。
「ヤッホー! Vジェットだー」
スーパー1のバイクに乗っている気分ではしゃいでいる俺を乗せて親父は近所を走ってくれた。そして雨が降った。親父は家に戻ろうと言った。
「やだ、もっと乗る。雨でもいい」
俺は駄々を捏ねた。
「よおし、じゃあとことん行くぞ!」
親父は俺のわがままを受け入れて、雨に濡れながら自転車を漕いでくれた。滅多に遊んでくれない親父が一緒に遊んでくれて嬉しかった気持ちが甦った。
一度記憶の扉を開けてしまったら、次から次へと記憶が溢れ出てきた。親父は母さんが俺を身ごもって、産んだら死んでしまうかもしれないというリスクを背負っても俺を産もうと決意して以来、大好きだった酒を止めて、毎日神社にお百度参りをしたのだと母さんが話してくれたこと。俺を寝かしつける時にこの話をよくしてくれて、
「お父さんは悠紀彦のことを世界で一番大切にしてくれてるの。お酒も大好きだったのに、それからずっと飲んでないのよ。毎日お仕事で朝が早いから悠紀彦とあんまり遊べないけど、お仕事をしないとお金がなくなって悠紀彦がご飯食べたり、洋服を買ったり、おもちゃを買ったりできなくなっちゃうでしょ。だからお父さんは悠紀彦と遊びたいのを我慢してお仕事をしているのよ。かっこいいお父さんだね」
そう嬉しそうに笑っていた。俺はこの話を聞きながら寝るのが大好きだった。当時はまだ親父の暴力も始まっていなかった。俺は何歳くらいだったのだろう……
土砂降りの中、親父と自転車に乗った後はどうしたんだっけ……家に帰ってきたあと親父と一緒に風呂に入ってから、二人でリビングでテレビを観たんだ。確か野球中継だった。そこに母さんが「これふやけちゃってるよ」と仮面ライダーのヘルメットを持って来たんだ。仮面ライダーの目の部分がステッカーで、長い間雨に打たれて、その後放置しておいたので、ふやけてボロボロになってしまったのだ。俺が雨に濡れても良いと言ったのに、まだ四歳だった俺は泣いて親父をなじった。
「お父さんのせいでスーパー1のヘルメットが壊れた。お父さんとはもう遊ばない。お父さんなんか大っ嫌い!」
親父に殴られたのはおそらくあの時が最初だった。そして、その日を境に親父はやめていた酒を飲むようになり、暴れるようになったのだ。そうだ、あの日から悪夢のような生活が始まったんだ。
親父は、俺がきっかけでまた酒を飲み始め、俺たち家族はメチャクチャになった。でも、親父は本当に家庭を壊そうとしていたのだろうか。記憶を巡っていくと、俺の態度が親父をあんな風にしてしまったのではないかと思えてくることが、次々と脳裏に甦った。
幼稚園の頃、親父が突然かくれんぼをしようと言ってきた。俺は親父のことが既に嫌いだったので「いいよ」と言って、親父に十数えさせて、自分の部屋に行ってあおり止めの鍵をかけて本を読み始めた。やがて親父は俺が鍵をかけて部屋にいることに気が付いた。
「鍵をかけるのは反則だぞー。十秒以内に出てこないと怒るからなあ」
部屋の前で、そう笑いながら言って十数えた。俺は親父が笑っていたので本気ではないと高を括っていたのだが、十数え終わった親父はドアを思いっきり引っ張って力づくで開けた。あおり止めが剥がれてドアが壊れるのを見た瞬間俺は恐怖に震え、そして薄ら笑いで近づいてくる親父に殴られた。もしかすると、親父は俺と仲直りがしたくて、頑張っていたのかもしれない。そして俺を喜ばせようとかくれんぼをしたのに、俺はすぐに鍵をかけて無視をした。
小学生になって友達の誕生会に何度も呼ばれていたので、四月生まれで一年生の時には入学したてでできなかった俺の誕生会を二年生の四月にうちで開いた。親父が料理を作ってくれて、来てくれた友達にお土産として、木製の電車キットも人数分、器用な親父が木を削って作ってくれた。
「すげえなお前のお父さん!」
友達は皆喜んでそう言ってくれた。けど、俺は親父が聞いているのを知っていてわざとこう答えた。
「全然すごくないよ。ご飯だってお母さんが作ったやつの方が美味しいし」
十歳のころ、親父が始めた小さなレストランで、生け簀の中でひっくり返って死にかけたアジがもう売り物にはできないからと、親父にアジのさばき方を教わった。
「初めてでこれだけできれば大したもんだ」
親父は目を細めていた。その日、親父がその話を常連さんにした。
「悠紀彦君、俺にもアジの叩きつくってよ」
俺は常連さんのリクエストに応えて、今度は活きの良いアジをさばいた。常連さんにも褒められて良い気分だったのを覚えている。それなのに、別の日に親父にまた違う常連さんにアジをさばいてくれと頼まれたのに「嫌だ」と言って断った。
「気分が乗らない時もあるよねえ」
常連さんは俺を庇ってくれたが、俺はあの時、親父が困れば良いと思ってわざとそんな態度を取ったのを覚えている。その夜、酔っぱらって帰ってきた親父に俺は殴られた。俺は家族が完全に壊れてしまう前に自分で壊したかったのだろうか。
俺は親父に愛されていないとずっと思ってた。今になって母さんが言っていた「お父さんを嫌いにならないでね」という意味がわかった気がした。
富士山の五合目で、親父が見本の絵を売店の店員に描き直させたあのジャガベーコン、「あのベーコンおっきくて美味そう」と俺が言ったから注文してくれたことを思い出した。
中学1年の時、親父がパチンコで取ったと言って、金のネックレスをくれたことがあった。すぐにリサイクルショップに売りに行って金に換えた。
今年の誕生日に親父にポロシャツをもらったが、一度も着ることなく後輩にあげた。
親父は確かに非常識だ。子供相手にマジでキレて大人気ないのかもしれない。愛情表現が上手くなかったのかもしれない。でも、俺のことを親父が愛しているのは確かだった。そして俺もそれに気が付いていた。でも、それを冷たく拒絶していたんだ。
何でそんなことをしてしまったのだろう。どこかで俺が親父の気持ちを受け入れていたら、俺の家族はこんな風にならなかったのかもしれない。歯車は狂ってしまった。俺は泣きながら自転車で走り続けた。