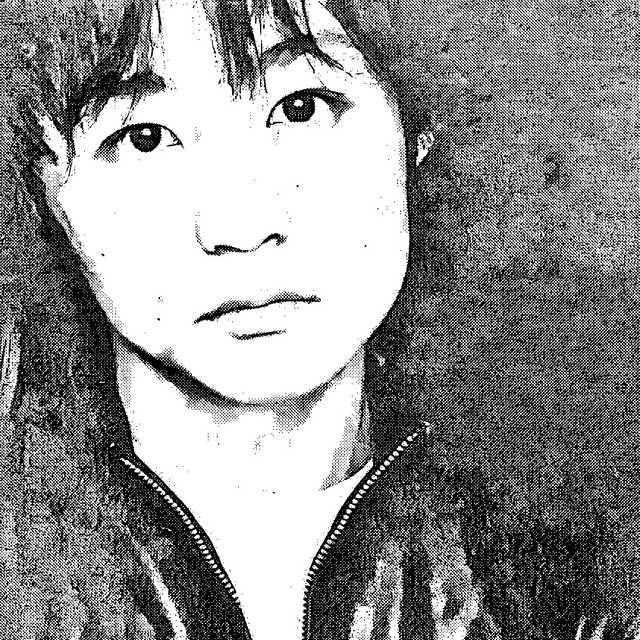第2章 (3) 14の夏
文字数 6,960文字
あさひやを出た俺たちは、舘山寺街道沿いを走り続けた。この旅行の練習を兼ねて、このメンバーで本橋の家から浜名湖に行って釣りをしたり、浜名湖一周約五十キロを五時間かけてサイクリングしてみたりしたので、まだまだこの辺りでは旅に出ている感覚は全くなく、リラックスした状態でペダルを漕ぐことができた。
浜名湖に釣りに行った時には全然釣果が上がらなくて、俺は小さな真鯛を一匹のみ、河原田はボウズ、本橋は50センチくらいのマダコを釣ったというか偶然引っ掛けた。そう言えばあのマダコ、本橋はどうしたんだろうか。俺のすぐ前を走っている本橋に向かって叫んだ。
「本橋、そういや前に浜名湖で釣ったマダコどうしたのー?」
「あー、あれは家に帰ったら珍しく親父が帰ってきていて、親父がさばいて刺身で食ったよー」本橋も叫び返す。自転車に乗りながら話すには普段より大きな声じゃないと聞こえづらい。
「お前の真鯛はどうしたー?」本橋が聞き返す。
「猫のエサになったー」人間が食べるにはあまりに小さいので飼っている猫のエサにしたのだ。本橋が再び声を張り上げる。
「小っちゃかったもんなあ。ところで河原田は何釣ったんだっけー?」
「うるさーい!」最後列を走る河原田が怒鳴ったので、皆で笑った。
遊園地パルパルに到着したのは午前七時二十一分。予定より二十一分遅れているが、あさひやで朝食を取っていた時間がそのまま遅れているだけなので、ここまでは計画通りと言えるだろう。パルパルにはこれまでに何度も来たことがあるが中学生になってからはそう言えば一度も来ていない。営業時間外のパルパルを見たのは初めてで、普段は家族連れやカップルで賑わっている場所に誰もいないのは不気味だった。
「さて、ここからは県道323号線を国道1号線に当たるまでずっと一本道だよ。距離的には十四キロ弱だから快調に飛ばせば八時ちょいくらいに着けると思う」河原田が的確な説明をしてくれた。
「お前すげえな。なんで距離とかわかるの?」本橋が驚いた顔をして尋ねた。
「地図見て測ればいいだけだよ」
「お前が自分で測ったの?」
「うん、その方がどんなスピードでどんだけ進めば良いかわかって安心でしょ」
どうやら河原田にとっては当たり前のことらしい。俺はそこまでマメにはできないな。河原田の冷静な分析力は自分にはないもので、出会ってからいつも驚かされている。
遊園地パルパルからしばらくは、左側に林があり右手の奥の方には浜名湖が見えて、その周辺には民家が並んでいるような道が続いた。その後浜名湖は見えなくなり、代わりに畑が多く見られるようになった。ビニールハウスもある。昔小学校でトマトのビニールハウス見学に行ったことを思い出した。大きなトマトを作るには、生えてきた脇芽を小さいうちに摘んで、太い幹をより太く育てると良いらしく、その脇芽をヤゴと言うのだと農家のおばさんが教えてくれた。その時にトンボの幼虫もヤゴじゃないかと思ったことも思い出したが、それが何年生の頃だったのかは思い出せない。
そこを抜けると今度は、左右に竹藪がある区域に突入した。竹藪のあとはまた左右に木々が茂った区域になって、そこを抜けると左手に同じ木がずらっと並んだエリアになった。多分桜の木だ。五百メートルくらいはありそうだ。花見のシーズンは絶景だろう。中学の入学式の日、正門から続く桜並木を母さんと並んで歩いたことがフラッシュバックした。思えば中学生活ももう半分近くが過ぎ去ったのだ。
自転車をこぎながら、ふと道路脇の県道標識を見た。いつの間にか県道319号線になっている。慌ててブレーキをかけた。
「ねえ、ここ県道319号線になってるんだけど」
「モト、大丈夫だよ。このまま行けばまた323号線になるんだ。ここは県道323号線であって319号線でもあるんだよ。こういう場所結構あるよ」河原田が教えてくれた。
道が重なっている部分があるなんて初めて知った。まだ旅が始まって一時間ちょっとしか経っていないのに、既に色々な発見がある。俺はこの三日間で起こるであろうたくさんの出来事にワクワクしながら再びペダルをこぎ出した。
やがて右側がすぐ浜名湖の湖岸沿いの道になった。遊歩道があるので、安全にサイクリングを楽しめるコースになっている。しばらくすると左側にも湖が見えるようになった。浜名湖大橋だ。全長二キロ以上ある長い橋で有料道路になっているが自転車は無料で通過できる。
「やべぇ、ちょっと怖い。俺真ん中になっていい?」本橋が立ち止った。俺はむしろ気持ち良いと感じていたので意外だった。
「何が怖いの? 気持ち良いじゃん」河原田も同感なようだ。
「だって、右も左も海ってことはさ、この道浮いてるみたいじゃん。俺は高い所が嫌いなんだよ」
「ヘヘ、鬼の目にも涙ってやつだな」ここぞとばかりに攻撃したのだが、本当に怖いらしく本橋は「頼むよ」と懇願している。
「それを言うなら弁慶の泣き所」河原田がツッコミを入れてきた。えっ鬼の目にも涙って、鬼のような人間でも泣く事はあるって意味じゃないの?
「なんでもいいから、早く俺を真ん中にしてくれ!」本橋が叫んだ。
前後で「ヤッホーイ!」と叫ぶ俺と河原田の間で「あー怖ぇぇぇ!」と叫ぶ本橋という構図で、俺たちは浜名湖大橋を渡り切った。
浜名湖大橋を渡ったあとも、引き続き県道323号線を突き進み、新幹線の線路の下をくぐるとようやく国道1号線に突き当たった。到着時間八時七分。河原田の読み通りだ。
「河原田先生、次はどう行くんすか?」本橋はすっかり河原田に頼りっきりで地図さえ見ようとしない。
「次は国道1号線を約六キロ進んで、海沿いを走る国道42号線に流れる。まあ二十分あれば着くでしょ」
国道1号線になると車の量が増えてきた。最初は歩道があったのでそこを走ったのだが、すぐに海の上を走る橋に入った。今度は歩道がないので車道を走ることになる。本橋はさぞかし怯えているだろうと思ったのだが怖くないようだ。後ろを振り返った俺の意図を察して「橋が低いから怖くねえよ」と笑った。
橋を抜けてすぐに、国道301号線との分かれ道に来たが、ここはそのまま国道1号線を進んだ。辺りは住宅が多くなり、俺たちが住んでいる地域と同じような雰囲気のエリアになった。そこをひたすら進むと、今度はまたビニールハウスがたくさん見えてきた。時計を見るともう午前九時前だった。もうだいぶ走った筈だが……少し不安になった。
「だいぶ走ったけど、まだ国道42号線につかないのかな?」
「もうとっくに42号線になってるよ」河原田が答えた。
「だいぶ前に分かれ道があって、俺たちは真っ直ぐ来たんだけど、曲がっているほうが1号線で、こっちが42号線だからわからなかったのかもね」
「てことは、ここから先はどんな感じ?」またもや本橋は地図も開かずに河原田を頼っている。
「もうここからは伊良湖岬までこの道一本。ひたすら続くよ。五十キロくらいなはず。目標到着時刻が13時だから、時々休憩しながら気楽に流す感じで良いと思う」
「了解!」
国道42号線は河原田の言ったようにひたすら続いた。のどかで車の通りも少ないので、最初のうちは二人が並走して一人がその後ろについて、うちの中学の同学年でナース服が一番似合う女は誰かとか、乳首がピンクそうなのは誰かとか、オナニーをしてそうな女を挙げろとか、三人でくだらない話をしながら進んだ。俺はナース服と乳首に関しては太田さと美のことを想像したが言わなかった。本橋も河原田も太田さんのことは口にしなかった。
午前十時を過ぎたころには流石にエロ話にも疲れて皆無口になっていた。景色ももうずっと代わり映えが無く、一人で走っていたら居眠り運転してしまいそうなレベルだ。前方に自販機が二台並んでいるのが見えた。
「ちょっとあそこの自販機の所で休憩しようよ」河原田が提案して、俺たちは休憩をすることになった。「なんか疲れてきたから甘酸っぱいものが飲みたくなって」
俺たちは自分の水筒にそれぞれ、俺は麦茶、本橋は緑茶、河原田は水を入れてきていたのだが、確かにちょっと甘酸っぱいものが欲しい気がする。
「よっしゃ、じゃあ俺はちみつレモン!」本橋が速攻ではちみつレモンを買って飲み始めた。
「うわっ、思ったより甘過ぎる。飲んでみ」
「確かに甘ったるい」
「残念だなあ。こういう甘さを求めてないんだよねー。はちみつレモンはやっぱサントリーだよな。この自販機どこのだよ?」本橋は恨み節を並べている。
「これはJTの自販機だね」河原田がそう言いながら自販機のボタンを押した。ガタンゴトンと音がしてジュースが落ちてきた。河原田が取り出したのを見たら真っ黄色の缶のレモンティーだった。
「甘さひかえめって書いてあるからこれなら大丈夫でしょ」そう言うと河原田はレモンティーを飲み始めた。ゴクゴクゴク、河原田の喉仏が上下している。女子に間違えられそうなくらい綺麗な顔立ちの河原田の男性的な部分が見えて、まだあそこの毛も生えてきていない俺はなんか悔しくなった。俺の第二次成長期はいつ来るんだ?
「どんぴしゃ! これ超美味いよ!」俺の悩みを知る由もない河原田が珍しくハイテンションで喜んでいる。
「俺にもちょうだい」気持ちを切り替えて一口もらった。本橋のはちみつレモンと比べると文字通り甘さひかえめでレモンの酸味がちょうどいい。サッカー部の試合のハーフタイムでよく出してもらうレモンのはちみつ漬けに近い。
「俺にも飲ませてよ」本橋が俺から缶を奪って一口飲んだあと大きなため息をついた。「河原田、俺の尊い犠牲があるからこそ、お前は美味いレモンティーを飲めることになったんだからな」
数秒間唖然とした河原田だったが、呆れたように鼻で笑って頭に巻いているバンダナを取って本橋に差し出した。
「ハユわかったよ。お礼に俺のバンダナあげるよ。まだ予備も持ってきてるし」
「大丈夫。ダサいからいらないよ」本橋は苦笑いで返品している。ハッキリ言って本橋のヘアバンドも十分ダサい。俺はどっちもいらない。
「お前が着てるレーのTシャツならもらってやるよ」
「それは無理だよ。ていうかこれリーだし」
本橋は英語が全くできない。中学に入学してから最初の英語の授業で小城原先生と揉めて、それ以来授業は全部寝たふりで実質ボイコットしている。中一の時、俺は本橋と同じクラスだったのでよく覚えている。
中学校最初の英語の授業はいきなりBe動詞から始まった。俺たちの中学はほとんどの生徒が塾に通っていて、通っていないのは周りでは俺と本橋ぐらいだった。他の生徒は普通に授業を受けている中、俺は何をやっているのかさっぱりわからなかった。授業の最後に先生が何か質問はないかと聞いた。
「ずっと一生懸命聞いていたんですけど、全然わかりませんでした。僕は何かを聞き逃したんですか? Be動詞って何すか?」本橋が手を挙げて質問した。
「キミは授業が終わったら先生の所に来なさい」そう言って小城原先生は授業を閉めた。
直後、本橋が先生の所に話を聞きに行った。俺も同じように訳が分からなかったので、黒板を消すふりをして聞く耳を立てた。
「君は塾に行っていないのかな?」
「行っていません」
「君以外のほとんどの子が塾で予め予習をしている。君だけの為に最初から教えるのは非効率なんだよ。君も皆を君だけの為に待たせるのは嫌だろう。君も塾に行くなりして追いつきなさい」小城原先生は諭すようにそう言った。
「嫌ですよ。ていうかうちにそんな金無いし。中学校は義務教育ですよね。だったら、一生懸命授業を聞いていればわかるように教えないとダメなんじゃないですか。こんなやり方じゃどんなに一生懸命授業を聞いてもわかりません」本橋も淡々と言い返す。
「だから、わからないなら塾に行けと言っている」小城原先生は本橋の話に聞く耳を持たないようだ。
「オッケーオッケー、英語の授業は二度と真剣に聞かねえよ。あんた言ってることがおかしいよ」本橋がすぐさま応戦した。キレそうな気持ちを抑えているのか早口になっている。本橋は今にも先生を殴りそうな雰囲気だ。
「ご自由に。君の成績が悪くなるだけです」そう捨て台詞を残して、小城原先生は逃げるように教室を後にした。
それ以来、本橋は英語の授業の時は、机に伏せて寝たふりをしている。噂じゃテストも名前しか書かずに出しているらしい。俺は最初の授業のあと、親にBe動詞について教えてもらって、なんとか英語の授業にはついていけるようになった。ただ、あの時のことを思い出すと今でもモヤモヤする。かと言って、本橋と同じように授業をボイコットしようとは思わないけれど……
休憩のあと、再び走り始める際に本橋が先頭をローテーションして走ろうと提案をしてきた。少し向かい風になっているので、風の抵抗を一番受ける先頭が一番疲れる。逆に言えば前に人がいれば風の抵抗が少なく、休みながら自転車がこげるらしい。
「競輪用語でスリップストリームって言うんだよ。オートレースでも使われるテクニックだけどな」
こいつなんでそんなこと知ってるんだ?
「ハユってなんでそんなこと知ってるの?」河原田が代わりに聞いてくれた。
「ああ、俺、親父に連れられて三歳くらいから、競輪、競艇、オートレース、パチンコ、雀荘に行ってたから、そっち方面のことはだいたい知ってるんだよ」本橋は少し悲しそうな笑みを浮かべてそう答えた。
本橋の提案通り、先頭をローテーションすることになった。最初は本橋が先頭を走った。本当にそんなので風の抵抗が変わるのかなと思ったが、意識して真後ろにポジションを取ると、思ったよりも風の抵抗を受けずに楽に進める気がした。
俺たちは三十分交代で先頭に立った。景色は相変わらず退屈だったが、逆に走ることに集中できて、途中から走ることが苦ではなくなった。これがランナーズハイというものなんだろうか。顔に当たる風が心地よい。頭の中では尾崎豊の【15の夜】が繰り返し流れている。バイクじゃなくて自転車で、盗んでなくて親に買ってもらったんだけど、疾走感と自由になれた気がしていることだけは同じだった。
あっという間に九十分が過ぎ、俺たちは伊良湖岬のかなり近くまで来ることができた。時刻は午前十一時五十五分。予定より少し速いペースで走ったようだ。
少し余裕ができたので、景色が良い海沿いのサイクリングロードを使って伊良湖岬まで行くことにした。死ぬほど退屈な国道42号線をようやく脱出できた。思いの外綺麗な、エメラルドブルーと言えなくもない海、さんさんと降り注ぐ太陽、額から頬に流れる汗。夏を感じながら、今俺は仲間と旅をしているのだという喜びが込み上げてきた。
やがて俺たちは左手に広がる白い砂浜と出会った。
「ここは恋路が浜、その昔、高貴な身分の男女が許されぬ恋がゆえに都を追放されこの地に暮らした事にちなむと言う」河原田が芝居がかった声で説明を入れた。
「ずいぶんロマンチックな名前じゃねえか。観光地にしたくて無理矢理頑張ってる感は否めないけどな」と本橋。
「恋人たちが想いを込めて鳴らす鐘があそこにあります。そしてあちらの土産物屋で購入できる【願いが叶う鍵】をこの恋路が浜の柵にかけるとその愛は永遠のものになると言う」河原田はまだナレーションを続けている。確かに柵の方を見るとほとんどがカップルだ。
「お前は恋の宣教師か!」本橋がツッコむ。
「いやあ、なんかたまには俺もこういう小芝居してもいいかなあと思って」恥ずかしくなったのか、河原田は30メートルほど先の駐車場の端にあるJTの自販機を見つけて「またあのレモンティー買おう」と行ってしまった。
「俺も行く」麦茶以外のものが飲みたくなった。
「俺は便所行ってくるわ。ウンコしてくるから終わったらどこに行けばいい?」本橋が顔をしかめながら聞いてきた。
「じゃあ自販機の隣のベンチに座って飲んどくよ」俺がそう答えると、本橋は自販機とは逆方向にあるトイレに小股で走っていった。
缶コーヒーを買った俺は、今頃になってトイレに行きたくなったので、缶を開けずに先にトイレに行くことにした。さっき本橋と一緒に行けばよかったな。朝食を二度食べたせいか、大の方をしたくなった。トイレの向こうに恋人たちが鳴らす鐘と、鍵をかける柵がある。今もたくさんのカップルが鐘の前で順番待ちをしたり、愛の柵に【願いが叶う鍵】をかけて手を合わせている。俺もいつかあんな風に誰かとカップルになるのかな。
ん? あれは!
そこで俺は見てしまった。柵に鍵をかけている本橋の姿を。
本橋が真剣な表情で手を合わせ目を閉じて祈っている。多分太田さんとのことを祈っているのだろう。
あまりに真剣な本橋の姿にひやかす気にもならなかったので、トイレに行って用を足した。手を洗って外に出ると、本橋は既に河原田と合流していた。
「ここからフェリーターミナルまであと十分くらいだって。腹減ったから早く行こうぜ」本橋が急かしてくる。
「オッケー行こうぜ!」
【願いが叶う鍵】をかけて祈っていた本橋の事を話題にしないことで、少し大人になれた気がした14の夏だった。
浜名湖に釣りに行った時には全然釣果が上がらなくて、俺は小さな真鯛を一匹のみ、河原田はボウズ、本橋は50センチくらいのマダコを釣ったというか偶然引っ掛けた。そう言えばあのマダコ、本橋はどうしたんだろうか。俺のすぐ前を走っている本橋に向かって叫んだ。
「本橋、そういや前に浜名湖で釣ったマダコどうしたのー?」
「あー、あれは家に帰ったら珍しく親父が帰ってきていて、親父がさばいて刺身で食ったよー」本橋も叫び返す。自転車に乗りながら話すには普段より大きな声じゃないと聞こえづらい。
「お前の真鯛はどうしたー?」本橋が聞き返す。
「猫のエサになったー」人間が食べるにはあまりに小さいので飼っている猫のエサにしたのだ。本橋が再び声を張り上げる。
「小っちゃかったもんなあ。ところで河原田は何釣ったんだっけー?」
「うるさーい!」最後列を走る河原田が怒鳴ったので、皆で笑った。
遊園地パルパルに到着したのは午前七時二十一分。予定より二十一分遅れているが、あさひやで朝食を取っていた時間がそのまま遅れているだけなので、ここまでは計画通りと言えるだろう。パルパルにはこれまでに何度も来たことがあるが中学生になってからはそう言えば一度も来ていない。営業時間外のパルパルを見たのは初めてで、普段は家族連れやカップルで賑わっている場所に誰もいないのは不気味だった。
「さて、ここからは県道323号線を国道1号線に当たるまでずっと一本道だよ。距離的には十四キロ弱だから快調に飛ばせば八時ちょいくらいに着けると思う」河原田が的確な説明をしてくれた。
「お前すげえな。なんで距離とかわかるの?」本橋が驚いた顔をして尋ねた。
「地図見て測ればいいだけだよ」
「お前が自分で測ったの?」
「うん、その方がどんなスピードでどんだけ進めば良いかわかって安心でしょ」
どうやら河原田にとっては当たり前のことらしい。俺はそこまでマメにはできないな。河原田の冷静な分析力は自分にはないもので、出会ってからいつも驚かされている。
遊園地パルパルからしばらくは、左側に林があり右手の奥の方には浜名湖が見えて、その周辺には民家が並んでいるような道が続いた。その後浜名湖は見えなくなり、代わりに畑が多く見られるようになった。ビニールハウスもある。昔小学校でトマトのビニールハウス見学に行ったことを思い出した。大きなトマトを作るには、生えてきた脇芽を小さいうちに摘んで、太い幹をより太く育てると良いらしく、その脇芽をヤゴと言うのだと農家のおばさんが教えてくれた。その時にトンボの幼虫もヤゴじゃないかと思ったことも思い出したが、それが何年生の頃だったのかは思い出せない。
そこを抜けると今度は、左右に竹藪がある区域に突入した。竹藪のあとはまた左右に木々が茂った区域になって、そこを抜けると左手に同じ木がずらっと並んだエリアになった。多分桜の木だ。五百メートルくらいはありそうだ。花見のシーズンは絶景だろう。中学の入学式の日、正門から続く桜並木を母さんと並んで歩いたことがフラッシュバックした。思えば中学生活ももう半分近くが過ぎ去ったのだ。
自転車をこぎながら、ふと道路脇の県道標識を見た。いつの間にか県道319号線になっている。慌ててブレーキをかけた。
「ねえ、ここ県道319号線になってるんだけど」
「モト、大丈夫だよ。このまま行けばまた323号線になるんだ。ここは県道323号線であって319号線でもあるんだよ。こういう場所結構あるよ」河原田が教えてくれた。
道が重なっている部分があるなんて初めて知った。まだ旅が始まって一時間ちょっとしか経っていないのに、既に色々な発見がある。俺はこの三日間で起こるであろうたくさんの出来事にワクワクしながら再びペダルをこぎ出した。
やがて右側がすぐ浜名湖の湖岸沿いの道になった。遊歩道があるので、安全にサイクリングを楽しめるコースになっている。しばらくすると左側にも湖が見えるようになった。浜名湖大橋だ。全長二キロ以上ある長い橋で有料道路になっているが自転車は無料で通過できる。
「やべぇ、ちょっと怖い。俺真ん中になっていい?」本橋が立ち止った。俺はむしろ気持ち良いと感じていたので意外だった。
「何が怖いの? 気持ち良いじゃん」河原田も同感なようだ。
「だって、右も左も海ってことはさ、この道浮いてるみたいじゃん。俺は高い所が嫌いなんだよ」
「ヘヘ、鬼の目にも涙ってやつだな」ここぞとばかりに攻撃したのだが、本当に怖いらしく本橋は「頼むよ」と懇願している。
「それを言うなら弁慶の泣き所」河原田がツッコミを入れてきた。えっ鬼の目にも涙って、鬼のような人間でも泣く事はあるって意味じゃないの?
「なんでもいいから、早く俺を真ん中にしてくれ!」本橋が叫んだ。
前後で「ヤッホーイ!」と叫ぶ俺と河原田の間で「あー怖ぇぇぇ!」と叫ぶ本橋という構図で、俺たちは浜名湖大橋を渡り切った。
浜名湖大橋を渡ったあとも、引き続き県道323号線を突き進み、新幹線の線路の下をくぐるとようやく国道1号線に突き当たった。到着時間八時七分。河原田の読み通りだ。
「河原田先生、次はどう行くんすか?」本橋はすっかり河原田に頼りっきりで地図さえ見ようとしない。
「次は国道1号線を約六キロ進んで、海沿いを走る国道42号線に流れる。まあ二十分あれば着くでしょ」
国道1号線になると車の量が増えてきた。最初は歩道があったのでそこを走ったのだが、すぐに海の上を走る橋に入った。今度は歩道がないので車道を走ることになる。本橋はさぞかし怯えているだろうと思ったのだが怖くないようだ。後ろを振り返った俺の意図を察して「橋が低いから怖くねえよ」と笑った。
橋を抜けてすぐに、国道301号線との分かれ道に来たが、ここはそのまま国道1号線を進んだ。辺りは住宅が多くなり、俺たちが住んでいる地域と同じような雰囲気のエリアになった。そこをひたすら進むと、今度はまたビニールハウスがたくさん見えてきた。時計を見るともう午前九時前だった。もうだいぶ走った筈だが……少し不安になった。
「だいぶ走ったけど、まだ国道42号線につかないのかな?」
「もうとっくに42号線になってるよ」河原田が答えた。
「だいぶ前に分かれ道があって、俺たちは真っ直ぐ来たんだけど、曲がっているほうが1号線で、こっちが42号線だからわからなかったのかもね」
「てことは、ここから先はどんな感じ?」またもや本橋は地図も開かずに河原田を頼っている。
「もうここからは伊良湖岬までこの道一本。ひたすら続くよ。五十キロくらいなはず。目標到着時刻が13時だから、時々休憩しながら気楽に流す感じで良いと思う」
「了解!」
国道42号線は河原田の言ったようにひたすら続いた。のどかで車の通りも少ないので、最初のうちは二人が並走して一人がその後ろについて、うちの中学の同学年でナース服が一番似合う女は誰かとか、乳首がピンクそうなのは誰かとか、オナニーをしてそうな女を挙げろとか、三人でくだらない話をしながら進んだ。俺はナース服と乳首に関しては太田さと美のことを想像したが言わなかった。本橋も河原田も太田さんのことは口にしなかった。
午前十時を過ぎたころには流石にエロ話にも疲れて皆無口になっていた。景色ももうずっと代わり映えが無く、一人で走っていたら居眠り運転してしまいそうなレベルだ。前方に自販機が二台並んでいるのが見えた。
「ちょっとあそこの自販機の所で休憩しようよ」河原田が提案して、俺たちは休憩をすることになった。「なんか疲れてきたから甘酸っぱいものが飲みたくなって」
俺たちは自分の水筒にそれぞれ、俺は麦茶、本橋は緑茶、河原田は水を入れてきていたのだが、確かにちょっと甘酸っぱいものが欲しい気がする。
「よっしゃ、じゃあ俺はちみつレモン!」本橋が速攻ではちみつレモンを買って飲み始めた。
「うわっ、思ったより甘過ぎる。飲んでみ」
「確かに甘ったるい」
「残念だなあ。こういう甘さを求めてないんだよねー。はちみつレモンはやっぱサントリーだよな。この自販機どこのだよ?」本橋は恨み節を並べている。
「これはJTの自販機だね」河原田がそう言いながら自販機のボタンを押した。ガタンゴトンと音がしてジュースが落ちてきた。河原田が取り出したのを見たら真っ黄色の缶のレモンティーだった。
「甘さひかえめって書いてあるからこれなら大丈夫でしょ」そう言うと河原田はレモンティーを飲み始めた。ゴクゴクゴク、河原田の喉仏が上下している。女子に間違えられそうなくらい綺麗な顔立ちの河原田の男性的な部分が見えて、まだあそこの毛も生えてきていない俺はなんか悔しくなった。俺の第二次成長期はいつ来るんだ?
「どんぴしゃ! これ超美味いよ!」俺の悩みを知る由もない河原田が珍しくハイテンションで喜んでいる。
「俺にもちょうだい」気持ちを切り替えて一口もらった。本橋のはちみつレモンと比べると文字通り甘さひかえめでレモンの酸味がちょうどいい。サッカー部の試合のハーフタイムでよく出してもらうレモンのはちみつ漬けに近い。
「俺にも飲ませてよ」本橋が俺から缶を奪って一口飲んだあと大きなため息をついた。「河原田、俺の尊い犠牲があるからこそ、お前は美味いレモンティーを飲めることになったんだからな」
数秒間唖然とした河原田だったが、呆れたように鼻で笑って頭に巻いているバンダナを取って本橋に差し出した。
「ハユわかったよ。お礼に俺のバンダナあげるよ。まだ予備も持ってきてるし」
「大丈夫。ダサいからいらないよ」本橋は苦笑いで返品している。ハッキリ言って本橋のヘアバンドも十分ダサい。俺はどっちもいらない。
「お前が着てるレーのTシャツならもらってやるよ」
「それは無理だよ。ていうかこれリーだし」
本橋は英語が全くできない。中学に入学してから最初の英語の授業で小城原先生と揉めて、それ以来授業は全部寝たふりで実質ボイコットしている。中一の時、俺は本橋と同じクラスだったのでよく覚えている。
中学校最初の英語の授業はいきなりBe動詞から始まった。俺たちの中学はほとんどの生徒が塾に通っていて、通っていないのは周りでは俺と本橋ぐらいだった。他の生徒は普通に授業を受けている中、俺は何をやっているのかさっぱりわからなかった。授業の最後に先生が何か質問はないかと聞いた。
「ずっと一生懸命聞いていたんですけど、全然わかりませんでした。僕は何かを聞き逃したんですか? Be動詞って何すか?」本橋が手を挙げて質問した。
「キミは授業が終わったら先生の所に来なさい」そう言って小城原先生は授業を閉めた。
直後、本橋が先生の所に話を聞きに行った。俺も同じように訳が分からなかったので、黒板を消すふりをして聞く耳を立てた。
「君は塾に行っていないのかな?」
「行っていません」
「君以外のほとんどの子が塾で予め予習をしている。君だけの為に最初から教えるのは非効率なんだよ。君も皆を君だけの為に待たせるのは嫌だろう。君も塾に行くなりして追いつきなさい」小城原先生は諭すようにそう言った。
「嫌ですよ。ていうかうちにそんな金無いし。中学校は義務教育ですよね。だったら、一生懸命授業を聞いていればわかるように教えないとダメなんじゃないですか。こんなやり方じゃどんなに一生懸命授業を聞いてもわかりません」本橋も淡々と言い返す。
「だから、わからないなら塾に行けと言っている」小城原先生は本橋の話に聞く耳を持たないようだ。
「オッケーオッケー、英語の授業は二度と真剣に聞かねえよ。あんた言ってることがおかしいよ」本橋がすぐさま応戦した。キレそうな気持ちを抑えているのか早口になっている。本橋は今にも先生を殴りそうな雰囲気だ。
「ご自由に。君の成績が悪くなるだけです」そう捨て台詞を残して、小城原先生は逃げるように教室を後にした。
それ以来、本橋は英語の授業の時は、机に伏せて寝たふりをしている。噂じゃテストも名前しか書かずに出しているらしい。俺は最初の授業のあと、親にBe動詞について教えてもらって、なんとか英語の授業にはついていけるようになった。ただ、あの時のことを思い出すと今でもモヤモヤする。かと言って、本橋と同じように授業をボイコットしようとは思わないけれど……
休憩のあと、再び走り始める際に本橋が先頭をローテーションして走ろうと提案をしてきた。少し向かい風になっているので、風の抵抗を一番受ける先頭が一番疲れる。逆に言えば前に人がいれば風の抵抗が少なく、休みながら自転車がこげるらしい。
「競輪用語でスリップストリームって言うんだよ。オートレースでも使われるテクニックだけどな」
こいつなんでそんなこと知ってるんだ?
「ハユってなんでそんなこと知ってるの?」河原田が代わりに聞いてくれた。
「ああ、俺、親父に連れられて三歳くらいから、競輪、競艇、オートレース、パチンコ、雀荘に行ってたから、そっち方面のことはだいたい知ってるんだよ」本橋は少し悲しそうな笑みを浮かべてそう答えた。
本橋の提案通り、先頭をローテーションすることになった。最初は本橋が先頭を走った。本当にそんなので風の抵抗が変わるのかなと思ったが、意識して真後ろにポジションを取ると、思ったよりも風の抵抗を受けずに楽に進める気がした。
俺たちは三十分交代で先頭に立った。景色は相変わらず退屈だったが、逆に走ることに集中できて、途中から走ることが苦ではなくなった。これがランナーズハイというものなんだろうか。顔に当たる風が心地よい。頭の中では尾崎豊の【15の夜】が繰り返し流れている。バイクじゃなくて自転車で、盗んでなくて親に買ってもらったんだけど、疾走感と自由になれた気がしていることだけは同じだった。
あっという間に九十分が過ぎ、俺たちは伊良湖岬のかなり近くまで来ることができた。時刻は午前十一時五十五分。予定より少し速いペースで走ったようだ。
少し余裕ができたので、景色が良い海沿いのサイクリングロードを使って伊良湖岬まで行くことにした。死ぬほど退屈な国道42号線をようやく脱出できた。思いの外綺麗な、エメラルドブルーと言えなくもない海、さんさんと降り注ぐ太陽、額から頬に流れる汗。夏を感じながら、今俺は仲間と旅をしているのだという喜びが込み上げてきた。
やがて俺たちは左手に広がる白い砂浜と出会った。
「ここは恋路が浜、その昔、高貴な身分の男女が許されぬ恋がゆえに都を追放されこの地に暮らした事にちなむと言う」河原田が芝居がかった声で説明を入れた。
「ずいぶんロマンチックな名前じゃねえか。観光地にしたくて無理矢理頑張ってる感は否めないけどな」と本橋。
「恋人たちが想いを込めて鳴らす鐘があそこにあります。そしてあちらの土産物屋で購入できる【願いが叶う鍵】をこの恋路が浜の柵にかけるとその愛は永遠のものになると言う」河原田はまだナレーションを続けている。確かに柵の方を見るとほとんどがカップルだ。
「お前は恋の宣教師か!」本橋がツッコむ。
「いやあ、なんかたまには俺もこういう小芝居してもいいかなあと思って」恥ずかしくなったのか、河原田は30メートルほど先の駐車場の端にあるJTの自販機を見つけて「またあのレモンティー買おう」と行ってしまった。
「俺も行く」麦茶以外のものが飲みたくなった。
「俺は便所行ってくるわ。ウンコしてくるから終わったらどこに行けばいい?」本橋が顔をしかめながら聞いてきた。
「じゃあ自販機の隣のベンチに座って飲んどくよ」俺がそう答えると、本橋は自販機とは逆方向にあるトイレに小股で走っていった。
缶コーヒーを買った俺は、今頃になってトイレに行きたくなったので、缶を開けずに先にトイレに行くことにした。さっき本橋と一緒に行けばよかったな。朝食を二度食べたせいか、大の方をしたくなった。トイレの向こうに恋人たちが鳴らす鐘と、鍵をかける柵がある。今もたくさんのカップルが鐘の前で順番待ちをしたり、愛の柵に【願いが叶う鍵】をかけて手を合わせている。俺もいつかあんな風に誰かとカップルになるのかな。
ん? あれは!
そこで俺は見てしまった。柵に鍵をかけている本橋の姿を。
本橋が真剣な表情で手を合わせ目を閉じて祈っている。多分太田さんとのことを祈っているのだろう。
あまりに真剣な本橋の姿にひやかす気にもならなかったので、トイレに行って用を足した。手を洗って外に出ると、本橋は既に河原田と合流していた。
「ここからフェリーターミナルまであと十分くらいだって。腹減ったから早く行こうぜ」本橋が急かしてくる。
「オッケー行こうぜ!」
【願いが叶う鍵】をかけて祈っていた本橋の事を話題にしないことで、少し大人になれた気がした14の夏だった。