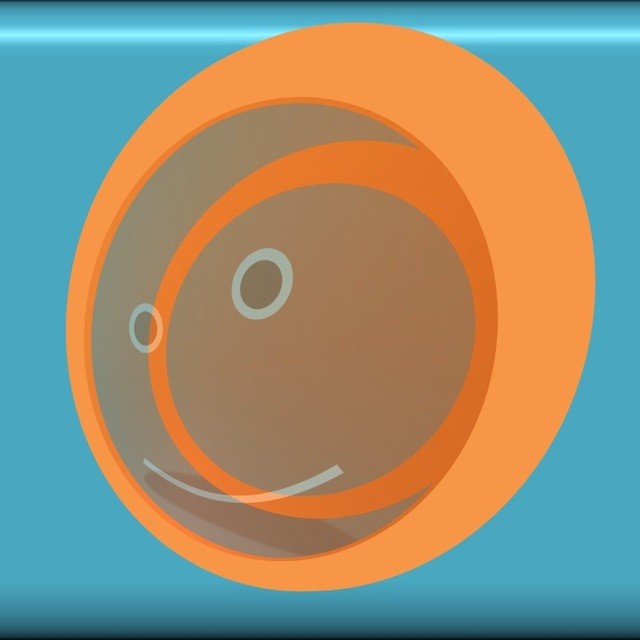第5話:魔女のあれこれ。
文字数 4,899文字
「――いや、出さんでいい。この件に関しては、師匠に委ねる。未知の属性だけでも厄介なのに、その上、八属性共存となると最早私たちの手に負える案件ではない」
と言うのが、ミザリイの決断。それに対しアリアは何度か頷いていたので、概ね同意と言う事なのだろう。
「じゃあ、コリンの家で鑑定を進めると言う話は――」
「当然、師匠の判断を仰いでからになる。コリンにはアリアから伝えておいてくれるか?私は午後マグナラタンへと赴き、師匠に事の経緯を説明してくるゆえ」
そう言いミザリイは席に着き、再び茶を飲み始める……。アリアも別段慌てふためく様子は無い。
のんびりとしているのだ。恐らく、すごく重大な案件を抱えこんでしまった筈なのに。
今すぐ何か手を打つとか、詳細説明のためにコリンを呼びつけるとか、状況が変わったのだから今後の展望を打ち合わせるとか、何か出来ることがあるだろう……と考えるのは、おれが魔女では無いからか、この世界の人間ではないからか。
それと、ひとつ感じるのは、魔女とは偉大な存在だとは思うが何か抜けているところがあると言う事。
ミザリイやアリアは優等生の様に見えるが、リスクマネジメントがぬる過ぎる。この世界にはまだ危機管理やリスクアセスメント的な考え方が無いのかもしれない。コリンに関しては言うまでも無い。カーリーにしても似た様なものだと思う。
いや、リスクに対する考え方に関しては元いた世界でも国や地域に寄りけりで、おれの世界でも全ての人間がリスクに対して感度が高いワケでは無いけれど。
日本を含む幾つかの先進諸国と第三世界の人々を比べて、リスクや仕事の取組み方に関して同等の感性や認識を有しているか?と問われると、それは全く以てNOです、と断言するしか無いのが実情だから。
そう、だから、おれの感性や価値観で物事を進めてゆくと、生き急いでいると感じ取られてしまうのだろう。南国の島国とか長閑な農村で余暇を過ごすくらいの気持ちで事に臨んだ方が、彼女たちとの足並みが揃うということか……。
それを踏まえて、おれものんびりと茶を楽しむ。ここでおれ一人が慌ててどうにかなる問題はひとつも無いのだから。
「――あれ?結局、アリアはおれの診察とか治療はしないんだっけ?」
ふと、思い出しそう問い掛けた。
「診察はしてますよ?会話中に、貴方の魔力の流れを診ました。表面上の傷や怪我は時期綺麗に治りますから心配は無用です」
「それってさ、アリアはそういう能力に長けているって言う事?治癒が得意なんだよね?」
おれがそういうと、彼女は右手を差し出した。薬指にきらきらと光り輝く指輪をしている。
「この指輪が、極めて高い治癒効力を有する魔導具なのです。肉体の欠損を治したり、死者を甦らせたり不治の病を劇的に回復させることは出来ませんが、人間が有する自然治癒力で治せる傷や怪我の治癒をかなり促進させます」
「へえ、凄いね。そう言うのって、何処かで売ってるのかい?」
「いいえ。ここまで強力な魔導具を商店や商人から購入するのは難しいでしょうね。アンヌヴンの塔の街にある、まじない小路でならもしかしたら入手できるかもしれませんが。これに関しては、コリンが製作しました」
不思議な光方をする宝石が填めてある。見る角度により色が変わって見えるのだ。
いやそれより、この魔導具をコリンが作ったと言うのだから、おれは目を見開き驚きの声を上げてしまった。
「え!?コリンが?あの人、こんな凄い魔導具を作れちゃうんだ?」
アリアはおれの反応を見てクスクスと笑みを零した。
「はい、コリンは、魔女としては全く駄目ですけれど、魔導具に関しては超一流ですからね。あの子が装着してる魔導具も全て自作の筈です。例の不可視化する魔導具の効力でどの様な魔導具を装着してるのか分かりませんけれど」
と、言う事はその不可視化する魔導具もコリン製作になるのか。
逆に言うとそれほど魔導具に特化してるからこそ、支配域をアリアへと委ね自分のやりたいことだけに集中できる……まさに魔導具職人といったところだ。
一度どの様に製作しているのか見てみたいと思った。企業秘密、と突っ撥ねられる……ことは恐らく無いと思うが、今度会った時に申し入れてみよう。
「――さて、では、私はそろそろ次の患者のところへと参りますね、ごきげんよう」
そういうとアリアはすうっと立ち上がり、棚から黄色いローブと魔女の帽子を取り出し、手早く身支度を整えると特に別れの挨拶を語ること無く出て行ってしまった。
文字通りあっと言う間の出来事。見送りに立ち上がることも出来ない程の速さだった。
おれは扉へと向けた視線をミザリイへと戻した。
「次の患者ってことは、アリアって魔女同盟内の集落とかを回って怪我や病気の人を治してるってこと?」
「うむ。昔はそれ程集落の人間に興味を示すことは無かったが、例の治癒の魔導具を手に入れてからは人が変わってしまってな。今では、魔女のくせに聖女様と持て囃されて、本人もその気になっておる、ということだ」
なるほど、そういう感じか。怪我人を治癒して感謝されて、それが気持ち良くなっちゃったんだろう。
「じゃあ、治癒の魔導具を手に入れる前は、ミザリイみたいな感じだったってこと?」
「あ、いや……私と言うよりかは、カーリーの様な感じだった。他の魔女同盟と争いがあらば、真っ先に飛び出してカーリーと戦功を競い合う様な……。今となっては、あの頃の面影は無いに等しい。言葉遣いも随分と違うな」
「アリアが、カーリーみたいな感じ?そ、そうなんだ……魔導具ひとつで変わるものだね人って」
いかにも清楚で、荒々しさなど微塵も感じなかったけれど、人は見かけに寄らないとはこのことだ。しかし、そうと聞いてもアリアが戦場で荒ぶる姿を想像するのは難しい。要するにキャラ変が上手くいったという事か。
集落に住む人々に取っても、戦闘狂よりも聖女様でいてくれた方が有難いだろうし。
「それで、午後から師匠のところに行くってことは、図書館から職員がミザリイの支配域へやって来るってこと?」
これまでを振り返ってみても、ミザリイが誰かと連絡を取っている光景は思い出すことが出来なかった。
何か魔女的な連絡手段があるのなら一度見てみたいと思っていたのだ。
「私と師匠は魔紋で直接繋がっておるからな。遠話で語り合う事が出来るのだ。その声は貴様には届いておらん。魔力や思念の指向性の問題だ。特定個人と魔力疎通や遠話をするのに全方向に対し魔力を送る必要はない」
「と、言う事は、もう師匠に遠話済みってこと?」
「そういう事だ。私から師匠に、師匠から職員共に。そして職員共が私の支配域へと入って来たら、私は支配域を出てマグナラタンへと向かう。アリアやカーリーは支配域で有能な人間を使役しているから、比較的自由に外出出来るが、私の場合そうはいかん」
ミザリイが使役してるのは魔獣や幻獣ばかりらしい。人間はおれが初めてだと聞いている。
「あのさ?ミザリイは、なぜ今まで人間を使役してこなかったんだい?話を聞いていると、有能な人間を使役した方が、魔女の本分ってヤツにも良いことが多いと思うけど……」
その問い掛けに対して、彼女は一旦口を閉ざした。
気分を害してしまったのかな?と少し思ったが、彼女は継続して会話をすると今の様に間を設けることが多々あるので、おれは茶を飲み待つしか無かった。
そして、彼女は口を開く。
「――面倒臭いと、思っておった。私は、魔女の中でも魔獣や幻獣と意志の疎通を図るのが得意でな。魔女になってからは、それが面白くてそれ以外のことに興味が向かなくなったのだ。二十年か三十年くらい普通の人間とまともに会話をせんかった時期がある。それを経て、他の魔女たちが使役している人間たちとあれやこれやとやり取りしてるのを見て、人間は繊細で面倒くさく使役するには手間が掛かると思い、であれば私は魔獣や幻獣を使役するだけで良い……と思ったのだ、おそらく。もう彼是百年以上前の話ゆえ、多分そうだったとしか言いようが無い」
何ともミザリイらしい理由だった。
使役してる人間とのコミュニケーションが時間の無駄だと感じてしまったのだろう。要するに多分この人、若干コミュ障なんだと思う。
「それで、実際、人間のおれを使役してみて、今はどんな気分なんだい?」
恐らく、こういうやり取りが面倒くさいのだろうと分かりつつも、おれはそう訊ねてみた。
するとミザリイは、苦い笑みを零し「想像していた百倍は面倒くさい。ただ、思っていたほど嫌な気はせん」と言う。そして、また少し間を設けて続けた。「――しかし、貴様の他にだれか人間を使役しようとは考えてはおらん。基本的に人間の子供……それも幼少期に魔紋を刻んで、私の手で育てなければならんからな。それを考えるとやはり面倒くさいと、思う。十年も育てれば使い走りくらいは出来る様になるのかもしれんが」
初めの一人か二人目までは魔女自身の手で育てて、以降は育成を使役してる者たちへと委ねていくものなのだろう。
しかし、彼女の場合、初めの一人すらも面倒くさいと感じてしまうのだから、その性質を今更変えるのは難しいと思う。それこそ、人間の子供を慈しみたくなる魔導具みたいなものがあれば、人が変わった様になるのかもしれないが。
「じゃあ、魔女の弟子ってのはさ、どういう風に見つけるの?使役した者の中から、素養の高い者を魔女にする?」
これも前から聞いておきたい事だった。今現在、彼女に弟子はいないみたいだから、使役した者の中から選ぶというのは強ち間違いでは無い様な気がする。
「いや、そうでは無く、ある日突然巡り逢うらしい。師匠や他の魔女に聞いた感じでは、直視出来ん程に眩く光り輝いて見える様だ。これがまた不思議なことに、他の魔女が見てもそうは見えんのだ。当然、私はまだ弟子になるべき人物に巡り逢ったことは無い」
「それって純粋に、魔力の高さとか属性の問題なのかな?」
「うむ。私も、初めはそうだろうと思っておったのだが、どうやらそれだけではないらしい。私の場合は、赤子の時に図書館の前に捨てられていて、それを偶然通り掛かった師匠が拾い抱えた瞬間に、眩く光輝いたと言っていたから、この現象に関しては人それぞれということになるな」
何ともファンタジーテイスト溢れる現象だと思った。勿論、科学的な検証を行えば、その原因は解明されてしまうのだろうけれど。
この手の現象は、分かってしまうと味気なく感じてしまうから、いつまでもロマンチックのベールに包んでおいて欲しいと思ってしまう。
「そっか。じゃあ、ミザリイは赤ちゃんの頃に師匠の弟子になったってこと?」
「いや、一旦、使役して私を拾ってから十年後に弟子にしたと言っていた。師匠的には、その光輝きがいつまでも続くものなのか試してみたかったらしい。で、十年経っても光が収まらんし、成長した私が図書館の中を歩き回り眩しくて目障りだから弟子にしたみたいだ」
それを聞き思ったのは、ミザリイの師匠は現代最高の魔女なのかもしれないけれど、恐らく他の魔女と同じで何処か抜けてるところがあるんだろうなあ、ということ。
まあ、少し天然入ってくれていた方が、おれ的には気が楽になるから構わないけれど。
――それから暫く他愛もない歓談が続き、図書館の職員がミザリイの支配域に入って来たみたいで、彼女は茶を飲み干して静かに立ち上がった。
「もう出発する?」と、おれも立ち上がる。
ミザリイは「ああ、そろそろ出るか。貴様は、その作業服に着替えておけ」といい、自身は流れる様な動きでローブを纏い鍔の広い帽子を被った。
何故出掛ける間際にそれを言うかな?と思いつつも、おれは新品同様となった作業服に着替えることにした。
第4章
魔女について。
END
と言うのが、ミザリイの決断。それに対しアリアは何度か頷いていたので、概ね同意と言う事なのだろう。
「じゃあ、コリンの家で鑑定を進めると言う話は――」
「当然、師匠の判断を仰いでからになる。コリンにはアリアから伝えておいてくれるか?私は午後マグナラタンへと赴き、師匠に事の経緯を説明してくるゆえ」
そう言いミザリイは席に着き、再び茶を飲み始める……。アリアも別段慌てふためく様子は無い。
のんびりとしているのだ。恐らく、すごく重大な案件を抱えこんでしまった筈なのに。
今すぐ何か手を打つとか、詳細説明のためにコリンを呼びつけるとか、状況が変わったのだから今後の展望を打ち合わせるとか、何か出来ることがあるだろう……と考えるのは、おれが魔女では無いからか、この世界の人間ではないからか。
それと、ひとつ感じるのは、魔女とは偉大な存在だとは思うが何か抜けているところがあると言う事。
ミザリイやアリアは優等生の様に見えるが、リスクマネジメントがぬる過ぎる。この世界にはまだ危機管理やリスクアセスメント的な考え方が無いのかもしれない。コリンに関しては言うまでも無い。カーリーにしても似た様なものだと思う。
いや、リスクに対する考え方に関しては元いた世界でも国や地域に寄りけりで、おれの世界でも全ての人間がリスクに対して感度が高いワケでは無いけれど。
日本を含む幾つかの先進諸国と第三世界の人々を比べて、リスクや仕事の取組み方に関して同等の感性や認識を有しているか?と問われると、それは全く以てNOです、と断言するしか無いのが実情だから。
そう、だから、おれの感性や価値観で物事を進めてゆくと、生き急いでいると感じ取られてしまうのだろう。南国の島国とか長閑な農村で余暇を過ごすくらいの気持ちで事に臨んだ方が、彼女たちとの足並みが揃うということか……。
それを踏まえて、おれものんびりと茶を楽しむ。ここでおれ一人が慌ててどうにかなる問題はひとつも無いのだから。
「――あれ?結局、アリアはおれの診察とか治療はしないんだっけ?」
ふと、思い出しそう問い掛けた。
「診察はしてますよ?会話中に、貴方の魔力の流れを診ました。表面上の傷や怪我は時期綺麗に治りますから心配は無用です」
「それってさ、アリアはそういう能力に長けているって言う事?治癒が得意なんだよね?」
おれがそういうと、彼女は右手を差し出した。薬指にきらきらと光り輝く指輪をしている。
「この指輪が、極めて高い治癒効力を有する魔導具なのです。肉体の欠損を治したり、死者を甦らせたり不治の病を劇的に回復させることは出来ませんが、人間が有する自然治癒力で治せる傷や怪我の治癒をかなり促進させます」
「へえ、凄いね。そう言うのって、何処かで売ってるのかい?」
「いいえ。ここまで強力な魔導具を商店や商人から購入するのは難しいでしょうね。アンヌヴンの塔の街にある、まじない小路でならもしかしたら入手できるかもしれませんが。これに関しては、コリンが製作しました」
不思議な光方をする宝石が填めてある。見る角度により色が変わって見えるのだ。
いやそれより、この魔導具をコリンが作ったと言うのだから、おれは目を見開き驚きの声を上げてしまった。
「え!?コリンが?あの人、こんな凄い魔導具を作れちゃうんだ?」
アリアはおれの反応を見てクスクスと笑みを零した。
「はい、コリンは、魔女としては全く駄目ですけれど、魔導具に関しては超一流ですからね。あの子が装着してる魔導具も全て自作の筈です。例の不可視化する魔導具の効力でどの様な魔導具を装着してるのか分かりませんけれど」
と、言う事はその不可視化する魔導具もコリン製作になるのか。
逆に言うとそれほど魔導具に特化してるからこそ、支配域をアリアへと委ね自分のやりたいことだけに集中できる……まさに魔導具職人といったところだ。
一度どの様に製作しているのか見てみたいと思った。企業秘密、と突っ撥ねられる……ことは恐らく無いと思うが、今度会った時に申し入れてみよう。
「――さて、では、私はそろそろ次の患者のところへと参りますね、ごきげんよう」
そういうとアリアはすうっと立ち上がり、棚から黄色いローブと魔女の帽子を取り出し、手早く身支度を整えると特に別れの挨拶を語ること無く出て行ってしまった。
文字通りあっと言う間の出来事。見送りに立ち上がることも出来ない程の速さだった。
おれは扉へと向けた視線をミザリイへと戻した。
「次の患者ってことは、アリアって魔女同盟内の集落とかを回って怪我や病気の人を治してるってこと?」
「うむ。昔はそれ程集落の人間に興味を示すことは無かったが、例の治癒の魔導具を手に入れてからは人が変わってしまってな。今では、魔女のくせに聖女様と持て囃されて、本人もその気になっておる、ということだ」
なるほど、そういう感じか。怪我人を治癒して感謝されて、それが気持ち良くなっちゃったんだろう。
「じゃあ、治癒の魔導具を手に入れる前は、ミザリイみたいな感じだったってこと?」
「あ、いや……私と言うよりかは、カーリーの様な感じだった。他の魔女同盟と争いがあらば、真っ先に飛び出してカーリーと戦功を競い合う様な……。今となっては、あの頃の面影は無いに等しい。言葉遣いも随分と違うな」
「アリアが、カーリーみたいな感じ?そ、そうなんだ……魔導具ひとつで変わるものだね人って」
いかにも清楚で、荒々しさなど微塵も感じなかったけれど、人は見かけに寄らないとはこのことだ。しかし、そうと聞いてもアリアが戦場で荒ぶる姿を想像するのは難しい。要するにキャラ変が上手くいったという事か。
集落に住む人々に取っても、戦闘狂よりも聖女様でいてくれた方が有難いだろうし。
「それで、午後から師匠のところに行くってことは、図書館から職員がミザリイの支配域へやって来るってこと?」
これまでを振り返ってみても、ミザリイが誰かと連絡を取っている光景は思い出すことが出来なかった。
何か魔女的な連絡手段があるのなら一度見てみたいと思っていたのだ。
「私と師匠は魔紋で直接繋がっておるからな。遠話で語り合う事が出来るのだ。その声は貴様には届いておらん。魔力や思念の指向性の問題だ。特定個人と魔力疎通や遠話をするのに全方向に対し魔力を送る必要はない」
「と、言う事は、もう師匠に遠話済みってこと?」
「そういう事だ。私から師匠に、師匠から職員共に。そして職員共が私の支配域へと入って来たら、私は支配域を出てマグナラタンへと向かう。アリアやカーリーは支配域で有能な人間を使役しているから、比較的自由に外出出来るが、私の場合そうはいかん」
ミザリイが使役してるのは魔獣や幻獣ばかりらしい。人間はおれが初めてだと聞いている。
「あのさ?ミザリイは、なぜ今まで人間を使役してこなかったんだい?話を聞いていると、有能な人間を使役した方が、魔女の本分ってヤツにも良いことが多いと思うけど……」
その問い掛けに対して、彼女は一旦口を閉ざした。
気分を害してしまったのかな?と少し思ったが、彼女は継続して会話をすると今の様に間を設けることが多々あるので、おれは茶を飲み待つしか無かった。
そして、彼女は口を開く。
「――面倒臭いと、思っておった。私は、魔女の中でも魔獣や幻獣と意志の疎通を図るのが得意でな。魔女になってからは、それが面白くてそれ以外のことに興味が向かなくなったのだ。二十年か三十年くらい普通の人間とまともに会話をせんかった時期がある。それを経て、他の魔女たちが使役している人間たちとあれやこれやとやり取りしてるのを見て、人間は繊細で面倒くさく使役するには手間が掛かると思い、であれば私は魔獣や幻獣を使役するだけで良い……と思ったのだ、おそらく。もう彼是百年以上前の話ゆえ、多分そうだったとしか言いようが無い」
何ともミザリイらしい理由だった。
使役してる人間とのコミュニケーションが時間の無駄だと感じてしまったのだろう。要するに多分この人、若干コミュ障なんだと思う。
「それで、実際、人間のおれを使役してみて、今はどんな気分なんだい?」
恐らく、こういうやり取りが面倒くさいのだろうと分かりつつも、おれはそう訊ねてみた。
するとミザリイは、苦い笑みを零し「想像していた百倍は面倒くさい。ただ、思っていたほど嫌な気はせん」と言う。そして、また少し間を設けて続けた。「――しかし、貴様の他にだれか人間を使役しようとは考えてはおらん。基本的に人間の子供……それも幼少期に魔紋を刻んで、私の手で育てなければならんからな。それを考えるとやはり面倒くさいと、思う。十年も育てれば使い走りくらいは出来る様になるのかもしれんが」
初めの一人か二人目までは魔女自身の手で育てて、以降は育成を使役してる者たちへと委ねていくものなのだろう。
しかし、彼女の場合、初めの一人すらも面倒くさいと感じてしまうのだから、その性質を今更変えるのは難しいと思う。それこそ、人間の子供を慈しみたくなる魔導具みたいなものがあれば、人が変わった様になるのかもしれないが。
「じゃあ、魔女の弟子ってのはさ、どういう風に見つけるの?使役した者の中から、素養の高い者を魔女にする?」
これも前から聞いておきたい事だった。今現在、彼女に弟子はいないみたいだから、使役した者の中から選ぶというのは強ち間違いでは無い様な気がする。
「いや、そうでは無く、ある日突然巡り逢うらしい。師匠や他の魔女に聞いた感じでは、直視出来ん程に眩く光り輝いて見える様だ。これがまた不思議なことに、他の魔女が見てもそうは見えんのだ。当然、私はまだ弟子になるべき人物に巡り逢ったことは無い」
「それって純粋に、魔力の高さとか属性の問題なのかな?」
「うむ。私も、初めはそうだろうと思っておったのだが、どうやらそれだけではないらしい。私の場合は、赤子の時に図書館の前に捨てられていて、それを偶然通り掛かった師匠が拾い抱えた瞬間に、眩く光輝いたと言っていたから、この現象に関しては人それぞれということになるな」
何ともファンタジーテイスト溢れる現象だと思った。勿論、科学的な検証を行えば、その原因は解明されてしまうのだろうけれど。
この手の現象は、分かってしまうと味気なく感じてしまうから、いつまでもロマンチックのベールに包んでおいて欲しいと思ってしまう。
「そっか。じゃあ、ミザリイは赤ちゃんの頃に師匠の弟子になったってこと?」
「いや、一旦、使役して私を拾ってから十年後に弟子にしたと言っていた。師匠的には、その光輝きがいつまでも続くものなのか試してみたかったらしい。で、十年経っても光が収まらんし、成長した私が図書館の中を歩き回り眩しくて目障りだから弟子にしたみたいだ」
それを聞き思ったのは、ミザリイの師匠は現代最高の魔女なのかもしれないけれど、恐らく他の魔女と同じで何処か抜けてるところがあるんだろうなあ、ということ。
まあ、少し天然入ってくれていた方が、おれ的には気が楽になるから構わないけれど。
――それから暫く他愛もない歓談が続き、図書館の職員がミザリイの支配域に入って来たみたいで、彼女は茶を飲み干して静かに立ち上がった。
「もう出発する?」と、おれも立ち上がる。
ミザリイは「ああ、そろそろ出るか。貴様は、その作業服に着替えておけ」といい、自身は流れる様な動きでローブを纏い鍔の広い帽子を被った。
何故出掛ける間際にそれを言うかな?と思いつつも、おれは新品同様となった作業服に着替えることにした。
第4章
魔女について。
END